「昭和24(1949)年1月26日、午前6時57分法隆寺駅着の汽車で出勤してきた法隆寺五重塔工事主任の竹原技師は、南大門をはいったとき、金堂から煙があがっているのを見ておどろき、直ちに工事事務所に通報した。
当時法隆寺は、金堂・五重塔の解体工事の最中で、工事事務所には、常時かなりの人数が泊まっていた。通報をきいた事務所員が、金堂の西南および東南隅にホースをとりつけ消火にあたった。法隆寺の防火水道は、寺内から1キロほど離れたところに特別の貯水池をつくり、3人がかりでなければホースが持てないほど圧力の強いものであった。これが金堂の火災に際し、建物の消火には役立ったが、壁画にとっては不幸になった。
大工が金堂南面の扉をあけ、堂内の直接消火が行われたとき、工事関係者は壁画に水をかけるなと叫んだが、気が転倒しているのとホースの圧力が強く自由がきかなかったのとで、壁画に直接多量の水がかかり、彩色が全くおちてしまっただけではなく、阿弥陀浄土を描いた6号壁などは大穴があいてしまった。
法隆寺の金堂が焼けたというニュースは、その日の午前中に全国につたわった。」
(久野健「文化財の受難」-『写真記録昭和の歴史④』(1984年、小学館)所収-)
9.白鳳文化
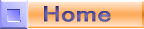
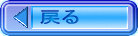


7世紀後半の文化を白鳳文化(はくほうぶんか)といいます。白鳳は『扶桑略記(ふそうりゃくき)』『藤氏家伝(とうしかでん)』等に見られる元号ですが、天武天皇の時代に白雉(はくち。650~654)という元号はあっても、白鳳という元号はありません。政府が公式に制定した元号ではない一種の私年号か、白雉を白鳳と美称したものかと思われます。

① 律令建設期の文化
白鳳時代は、大化の改新(645)から平城京遷都(710)にかけての頃に相当します。つまりは、孝徳天皇の諸改革からはじまって、天智・天武・持統朝を通じて、律令国家体制を建設・整備していった時期にあたります。そのため、律令国家体制の完成を目指して坂をかけあがろうとするような、生き生きとした意気込みが感じられます。若々しくはつらつとした青年期のような文化といってもよいかと思います。色彩でいえば白や青、言葉でいえば「清(すが)し」が似合う清新な文化だといえましょう。

② 初唐文化の影響
律令体制のお手本にしていた唐も618年の建国以来、最盛期に向かって上り調子にありました。白鳳文化は、新羅から伝えられた初唐文化の影響を受けています。

③ 国家仏教への方向づけ
飛鳥期には建てられた寺院は、各豪族の氏寺(うじでら)が中心でした。壮麗な寺院建築は豪族たちの権力誇示の手段となり、そこでは各氏族の繁栄が祈られました。
白鳳期になると、国家によって官立の寺院が建立されました。これを官寺(かんじ)・官大寺(かんだいじ)・大寺(おおでら)などといいました。伽藍(がらん)の造営や維持・管理の費用を国家から受ける寺です。大官大寺(たいかんたいじ。もとの百済大寺。後に大安寺となります)、薬師寺、法興寺(ほうこうじ。のちの元興寺)、弘福寺(ぐふくじ。川原寺(かわらでら)ともいいます)などがあります。奈良時代にも聖武天皇による東「大寺」や、聖武の娘称徳天皇による西「大寺」などが建てられました。官寺は地方にも建立されました。常陸国(ひたちのくに。茨城県)の新治廃寺(にいはりはいじ)、豊後国(ぶんごのくに。大分県)の法鏡寺(ほうきょうじ)などがあります。
国家の保護を受ける官寺だけでなく、この時期には、地方寺院の建立数も増加しました。飛鳥時代には50ほどしかなかった寺院が、白鳳時代になると500以上に急増しています。692年の調査によると、545の寺院があったといいます。仏教伝来直後には飛鳥という狭い地域に展開していた仏教文化が、次第に地方へと浸透していったことがわかります。
さて、公の寺院においては、国家の安泰を祈る経典(仁王経(にんのうきょう)・金光明経(こんこうみょうぎょう)・法華経(ほけきょう)の三つを「護国三部経(ごこくさんぶきょう)」といいます)がよまれました。仏教は、個人の魂の救済や現世利益(げんぜりやく)を祈るものではなく、鎮護国家(ちんごこっか)の役割を担うことが方向づけられたのです。仏教は国家の保護を受けて発展するとともに、国家の統制下に置かれました。寺院に在住する僧尼たちも、僧尼令(そうにりょう)によって厳しく管理されるようになったのです。

④ 伊勢神宮の尊崇
壬申の乱に際し、大海人皇子が伊勢神宮を遙拝(ようはい。現地から遠く離れた地から礼拝すること)したといいます。
伊勢神宮は天皇家の祖先神天照大神(あまてらすおおみかみ)を祀る神社です。祖先神の加護によって勝利したというので、伊勢神宮に対する信仰が高まりました。天皇を中心とした律令国家を建設する過程で、天皇家の祖先神への尊崇を高める狙いがあったのでしょう。

白鳳建築の現存する唯一の遺構が薬師寺東塔(とうとう)です。高さ34.1mの三重塔ですが、各層についている裳階(もこし。建物の外側にさしかけた庇(ひさし)とその下の空間のこと)によって、六重塔のように見えます。アメリカ人の東洋美術研究家フェノロサ(1853~1908)は、その律動美を「凍(こお)れる音楽」と賞賛しました。
ゆく秋の大和の国の薬師寺の塔の上なる一ひらの雲
佐佐木信綱(ささきのぶつな。1872~1963)
なお、1982(昭和57)年、山田寺(やまだでら)の発掘調査で、横倒しになった東回廊が白鳳時代の姿そのままで発見されました。建築物の遺構としてはわが国最古のものです。

飛鳥彫刻はクスノキの木像が中心でしたが、この時代には金銅像が多く造られました。金銅像というのは銅または青銅(銅と錫の合金)で造った仏像に金メッキをしたものです。ほとんどの仏像は金が剥落(らくはく)してなくなっています。
白鳳彫刻を前代の彫刻と比べると、左右対称ではなくなった、アルカイックスマイルが消えた、肉付きがよくなり量感あふれるプロポーションになった等の新たな特色が見られます。
代表的な作品に、薬師寺金堂薬師三尊像、薬師寺東院堂聖観音像、興福寺(旧山田寺)仏頭、法隆寺阿弥陀三尊像、法隆寺夢違観音像などがあります。すべて金銅像です。

① 薬師寺金堂薬師三尊像
本尊の薬師如来像(高さ254.7cm)を中心に、向かって右側に日光菩薩像(高さ317.3cm)、左側に月光(がっこう)菩薩像(高さ315.3cm)を配置しています。両菩薩はやや体をひねるなど、やわらかく変化ある肢体には動きが感じられます。
中尊(ちゅうそん。中央に座す仏像)の薬師如来像をのせる台座(高さが150.7cm)には葡萄唐草文(ぶどうからくさもん)、邪鬼(じゃき)、四神(しじん)などが浮き彫りにされています。西アジアや中国の影響が見てとれます。
◆月光菩薩の首切り事件
薬師寺金堂薬師三尊像の脇侍である月光菩薩像には、首の部分に亀裂が走っていました。この亀裂が生じた理由は不明ですが、時を経るにしたがって次第に大きくなり、1952(昭和27)年7月17日に起こった吉野地震によって、ぐらつくまでに悪化してしまいました。
薬師寺からの依頼で調査に赴いた文化財保護委員会(文化庁の前身)の技官たちは、「このままでは首が不安定であぶない、急ぎ頭部をおろした方がよい」と判断しました。そこで、なかごの鉄心を切って、頭部をおろしたのです。これを聞いて、世間では「月光菩薩の首が切られた」と大騒ぎになりました。
正確にいえば、月光菩薩の体内を通っていたなかごの鉄心を切断したのであって、首を切ったのではありませんでした。しかし、あまりにも性急な処置だったことは否めません。いずれ頭部を下ろす必要があったにせよ、とりあえずは頭部が落下しないように、応急処置を施すべきでした。その上で、修理方法をじっくり慎重に検討してから処置したのであったなら、これほど大騒ぎになることはなかったでしょう。
文化財保護委員会には専門家をはじめ、人びとの批判が相継ぎました。そこで、国は専門家を集めて鳩首協議させ、内枠固定法と金属接着剤とを併用するという方針をたて、月光菩薩の修理を行うことに決めました。国庫からは約600万円の修理予算が計上され、2年間にわたり補修がされました。月光菩薩像は、こうして現在の姿に蘇ったのです。
【参考】
・『芸術新潮・国宝』1990年1月号、40ページ
・参議院会議録情報 第016回国会 文部委員会 第8号(昭和28年7月16日木曜日)
「http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/016/0804/01607160804008c.html」(2012年9月28日参照) |

② 薬師寺東院堂聖観音像(しょうかんのんぞう)
顔が十一面あったり、、手が千本あったりと、観音像には変化(へんげ)観音が多いのですが、変化しない、人と同じ姿の観音像を聖観音像といいます。「正観音像」と書くこともありますが、これは「本来の観音像」という意味です。
正面観(しょうめんかん。礼拝者が真正面から見ること)を念頭に造られているため、衣文(えもん)は左右対称になっています。これは古い様式を示しています。肉付きが豊かな仏像で、密着する衣によって脚の形を表現しています。身にまとっている天衣(てんね)が肩や腕を巻いて、全身をリズミカルにめぐっています。高さが188.9cmあります。

③ 興福寺(旧山田寺)仏頭
もともとは山田寺の本尊でした。山田寺に安置されていた薬師三尊像の中尊の頭部(高さ98.3cm)です。頭部しか残っていないものの、白鳳彫刻の特色をよくそなえた、青年のような表情をたたえた作品です。
興福寺に仏頭が伝わったのには、次のような経緯があります。
1180(治承4)年、平氏の南都焼打ちによって東大寺や興福寺が焼亡しました。その後東金堂が復興しましたが、安置する本尊がありません。そこで1187(文治3)年、東金堂の本尊とするため、興福寺の僧兵たちが山田寺の本尊を奪い取ってきたのです。しかし1411(応永18)年、火災によって像は焼け落ち、頭部のみが残りました。この頭部は長らく所在が不明でしたが、1937(昭和12)年、興福寺東金堂の台座の内から発見されました。

④ 法隆寺阿弥陀三尊像(伝橘夫人念持仏)
光明皇后の母橘三千代(たちばなのみちよ)の念持仏(ねんじぶつ)と伝えられていますが、その根拠は不明です。木製の厨子(ずし)に入れられた阿弥陀三尊像で、中尊の高さは34.0cmです。丸顔で、柔和な表情をしています。

⑤ 法隆寺夢違(ゆめちがい)観音像
左手に小さな水瓶(すいびょう)を持った聖観音の立像です。悪夢を見た際、この仏像に祈ると吉夢にかえてくれるという信仰があるため、このように呼ばれます。夢違はかつて「ゆめたがえ」とも読まれました。
造像当初からの消息は長らく不明でしたが、その後、18世紀初めには東院絵殿におさめられていたことが判明しました。現在は法隆寺西院北東の大宝蔵に安置されています。高さ86.9cm。

① 法隆寺金堂壁画
法隆寺金堂壁画とは、金堂外陣(げじん)の柱間に12面あった仏教絵画をいいます。釈迦(しゃか)・阿弥陀(あみだ)・弥勒(みろく)・薬師(やくし)各如来の4浄土を描いた大壁4面が有名です。なかでも、西6号壁の阿弥陀浄土図が優品で、日本史の教科書・図説資料集でよく紹介されていることもあって、法隆寺金堂壁画といえば、これを想起するほど有名なものです。鉄線描(てっせんびょう)という弾力性のある線描や、繧繝彩色(うんげんさいしき)という段層的なぼかしなど、特徴な技法が使われています。また、インドのアジャンターや中国の敦煌(とんこう)の石窟寺院の壁画との類似性が指摘されており、世界史的に見ても貴重な絵画作品です。
しかし1949(昭和24)年、火災による焼損という衝撃的な事件が起こりました。壁画の模写作業で使用した暖房器具の電源の切り忘れ、または漏電が失火の原因といわれています。この事件を契機に、翌1950(昭和25)年に文化財保護法が制定され、のち文化庁が発足しました。火災のあった1月26日は、この事件を記憶にとどめるために、文化財保護デーに定められました。

② 高松塚古墳壁画
高松塚古墳は、奈良県高市郡明日香村にある終末期の円墳です。1972年、その玄室の壁に、彩色壁画(さいしきへきが)のあることがわかりました。彩色壁画は九州や関東に見られますが、この古墳のように、リアルに描かれた彩色壁画が見つかったのは初めてのことでした。
壁画には中国や朝鮮半島の強い影響が見られます。おそらくは高句麗系の画師が描いたのではないか、と推測されています。天井には星宿図、北面に玄武、東面に青竜と人物群、西面に白虎と人物群が描かれています。南面にも四神の一つ朱雀が描かれていたと推測されますが、剥落したのか現在は見られません。壁面がカビやダニによって痛んだため、古墳を解体して、修復・保存が行われました。
高松塚古墳の南方約1kmにあるキトラ古墳(また亀虎古墳とも)も同じ時期の円墳です。玄室内の四面に、四神が揃って描かれています。また、複数描かれている獣頭人身像は、おそらくは十二支であろうと思われます。消えかかっていますが、四面に3体ずつ計12体描かれていたと考えられています。
太陽・月とともに天井には金箔で約350の星が表現され、赤い線によって北斗七星などの星座が描かれています。壁画の痛みが激しく、壁画の剥(は)ぎ取りが行われ、石室の外で修復作業が進められました。

③ 薬師寺東塔の水煙(すいえん)
薬師寺東塔の相輪の最上部にとりつけられているのが水煙です。炎をかたどった青銅製の飾りですが、建物に炎は火事を連想させて不吉であるため、水煙と称しています。東塔の水煙の中には、飛雲の中で舞い踊る飛天(ひてん)の姿が透(す)かし彫りにされています。

�
① 漢 詩
中国文化の吸収・模倣が中心で、独創的なものは少ないといわれています。大津皇子・大友皇子らが代表的な詩人です。彼らの漢詩は、奈良時代の『懐風藻(かいふうそう)』に収録されました。
◆大津皇子の辞世
白鳳時代の代表的な漢詩の代表的な作品に、次のようなものがあります。686年、大津皇子が謀叛の嫌疑をかけられて処刑されるときの辞世の詩です。
原文・書き下し文・現代語訳とも、小島憲之編『王朝漢詩選』(1987年、岩波文庫、P.26~27)によるものです。
臨終(りんじゅう) 大津皇子
金烏西舎臨 金烏(きんう)、西舎(せいしゃ)に臨み、
鼓聲催短命 鼓声(こせい)、短命(たんめい)を催(うなが)す。
泉路無賓主 泉路(せんろ)、賓主(ひんしゅ)無し、
此夕誰家向 此(こ)の夕(ゆふへ)誰(た)が家(いへ)にか向(む)かはん。
(現代語訳)
月は西のやかたに傾き、時刻(とき)を告げる太鼓の音はわが短い命をせきたてる。迎えてくれる主人(あるじ)もない黄泉路(よみじ)のひとり旅、今夕(こよい)このわれいずこに
宿るやら。 |

② 和 歌
天智・天武・持統天皇、額田王(ぬかたのおおきみ)、柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)らが活躍しました。彼らの作品は、のちに奈良時代の『万葉集』に収録されました。
�


