62.立憲政友会の成立
「明治33(1900)年に ( 中略 ) 自由党というものが消滅してしまったのである。 ( 中略 )
主義に依り、国民の意思に依り、輿論(よろん)に依って成り立つところの政党というものが、その時によほど性質を一変したのである。この日本の憲法史、日本の政党史に大なる関係を持つところの年は33年である。その時に自由党は自滅して、高名なる大政治家の伊藤(博文)侯(爵)の下に、自由党、国民協会の一部、官吏の一部、その他中立、実業家というものが集(つど)って、政友会(立憲政友会)というものが生まれたのである。その時には伊藤侯の声望と、且(か)つ伊藤侯の政治的才略に依ってほとんど天下響きの如く応じた。
その時に我が党(憲政本党のこと)はどういう有様であったかというと、ご承知の通りに、我が党の最も有力な数人は、不幸にも我が党を脱して伊藤侯の下に馳せ加わり、このがために進歩党(正しくは憲政本党)は非常に動揺したのである。もし放擲(ほうてき。何もしないでうち捨てておくと)すれば、ほとんど進歩党は瓦解(がかい)し尽し、自由党の如く政友会の下に加わらなければならぬという運命に出遇(であ)ったのである。
(「大隈重信、憲政本党総理退任の辞」1907年-早稲田大学編『大隈重信演説談話集』2016年、岩波文庫、P.219~220-。理解しやすいよう適宜注を入れ、改行した。)
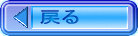

① 政府と政党の接近
政府は超然主義を標榜(ひょうぼう)し、主権線・利益線の確保のため軍事拡張予算の成立(すなわち増税=地租の増徴)を主張し続けていました。
これに対抗する政党勢力は、地租を納める農村地主層を支持基盤としていたため、「節約して予算支出を減らし、国民を休ませよ(政費節減、民力休養)」(=減税)と主張し続けていました。
こうして初期議会(第1議会~第6議会)の両者の主張は、常に平行線をたどっていたのです。
しかし、日清戦争前後から、両者の間に歩み寄りが見られるようになりました。政府にとって軍拡を進めるためには何よりも予算案を成立させることが必要でしたが、そのためには帝国議会の賛同を必要としました。しかし、議会を構成する衆貴両議院のうち衆議院は、軍拡(=増税)に反対する民党勢力が議席の過半数を占めていました。民党勢力と妥協しなければ、軍拡予算を成立させることは、まずは不可能でした。
一方、民党勢力も政府との妥協の道を探るようになりました。自分たちの理想とする政治を実現するためには、ある程度の妥協によって政府に恩を売り、その見返りに自分たちの主張を少しでも国政に反映させることが必要だと考えたのです。
こうして第2次伊藤博文内閣(1892~1896)と自由党は妥協し、内務大臣に板垣退助を迎えました。
ついで第2次松方正義内閣(1896~1897)は進歩党に接近し、大隈重信を外務大臣として政権内に取り込みました。政府・進歩党両者の妥協によって成立したこの内閣を「松隈内閣(しょうわいないかく)」といいます。こうして「松隈内閣」は、第10議会(1897)で軍事予算を通過させることに成功したのです。

② 憲政党の結成
しかし、有権者(地主層)の強い希望は減税でした。それは1898(明治31)年に実施された第5回衆議院議員総選挙の結果に表れています。この選挙で自由党は98議席、進歩党は91議席をとり、両党のみで衆議院300議席中189議席の圧倒的多数を制したのです。
第3次伊藤博文内閣(1898)が地租増徴案(増税)を提出すると、自由党・進歩党両党は一致してこれに反対し、地租増徴案は否決されました。政府は衆議院の解散でこれに応えましたが、自由党・進歩党両党は総選挙に備えてそれぞれ解党して合同し、新たな政党、憲政党を結成しました。政府との対決姿勢を旗幟鮮明(きしせんめい)にしたのです。

③ 第1次大隈重信内閣(隈板内閣)-わが国初の政党内閣-
こうした情勢を見て取った伊藤は、これ以上の政権運営は無理だと判断し、天皇に辞表を提出しました。代わって、憲政党の大隈重信と板垣退助に組閣の大命が下りました。
大隈が総理大臣と外務大臣を兼任し、板垣が内務大臣に就任したこの内閣を、第1次大隈重信内閣(1898)、別名「隈板内閣(わいはんないかく)」といいます。「隈板内閣」は、陸軍大臣(桂太郎)・海軍大臣(西郷従道)を除く全ての閣僚が憲政党員から成る、わが国初の政党内閣でした。
しかし、この「わが国初の政党内閣」という輝かしい意義を語り継がれるはずの内閣は、党内対立や藩閥勢力の圧力によって、わずか4カ月で崩壊してしまいました。そればかりか「政党が衰退する転機となった」という汚名を残すことになったのです。
第1次大隈内閣が与党とする憲政党は、旧進歩党系・旧自由党系の寄り合い所帯であり、当初から両グループ間には反目がありました。
共和演説事件(1898)によって尾崎行雄が文部大臣を辞職すると、その後任をめぐって内部対立が表面化してしまいました。旧自由党系の星亨(ほしとおる)は駐米公使だったにもかかわらず、急遽(きゅうきょ)帰国してきました。しかし、文部大臣には進歩党系の犬養毅が就任し、星が要求する外務大臣ポストも大隈によって拒否されると、星は旧自由党員を率いて憲政党から飛び出してしました。そして、新たに結成した政党を、同名の憲政党と命名したのです。
同時に、旧自由党系の板垣退助内相・松田正久蔵相・林有三逓相(ていしょう)らが辞表を提出し、旧進歩党系の閣僚も閣内不一致を理由に辞表を提出しました。こうして「わが国初の政党内閣」はわずか4カ月で崩壊してしまったのです。
なお、残された進歩党系グループは憲政本党(けんせいほんとう)と名乗りました。こうして憲政党は、旧自由党系の憲政党と、急進歩党系の憲政本党に分裂してしまったのです。
◆共和演説事件(1898)
1898(明治31)年8月、全国の教員を集めた帝国教育会夏期講習会において、尾崎行雄文相が演説をしました。そこで「もし、日本が共和制だったとすれば、三井・三菱は大統領候補となるだろう」と、日清戦争後の拝金主義の風潮を批判したのです。ところが枢密院・貴族院はこの発言を取り上げて「仮定であるにせよ、文相が日本に共和政治が実現するなどと発言するのは不敬である」と尾崎を非難・攻撃しました。
この尻馬に乗ったのが、政党に敵意を持つ藩閥政治家や、旧進歩党系の尾崎を追い落として勢力拡張を狙う旧自由党系議員たちでした。尾崎の発言は政争の具とされ、ついに尾崎は文相辞任に追い込まれてしまったのでした。
|

① 第2次山県有朋内閣(1898~1900)
「隈板内閣」の崩壊後成立した第2次山県有朋内閣は、薩長閥に山県系官僚を加えた純然たる軍閥・官僚閥の内閣でした。
この内閣は、衆議院議員選挙法の改正、文官任用令の改正、治安警察法の制定、軍部大臣現役武官制の制定などの諸政策を行いました。
《 衆議院議員選挙法の改正(1900) 》
山県内閣は、憲政党(旧自由党系)の閣外協力を得て懸案の地租増徴案を成立させ、日清戦後経営のための安定した財源確保に成功しました。そして、地租増徴への協力の見返りとして、衆議院議員選挙法を改正して有権者の納税資格を引き下げました。
有権者資格は、従来は直接国税15円以上納入する25歳以上の男子となっていましたが、このうち納税資格を直接国税10円以上に引き下げて、都市民の政治参加への道を拡大しました。
《 文官任用令の改正 》
文官任用令を改正して、親任官(しんにんかん。大臣・知事・公使など)以外の勅任官(ちょくにんかん。高級官吏)への登用には、文官高等試験に合格することが必要と改めました。この改正により、政党員の勅任官への就任を阻止しようとしたのです。
《 治安警察法の制定(1900) 》
社会主義運動や労働運動を取り締まるため、治安警察法を制定しました。
日清戦争をきっかけに労働組合運動が発足し、労働争議が多発するようになりました。そこで、集会・結社・言論の自由を制限し、第17条で労働者のストライキと農民の小作争議を禁止することにしたのです。第17条の違反者は1カ月以上6カ月以下の重禁錮(じゅうきんこ。刑務所に留置するが労働は強制しない刑罰)に処せられた上、3円以上の罰金を科せられました。
この法案は、屋内集会の事前禁止条項を削除したのみで、ほとんど審議されずに、衆議院を通過しました。当時の政党は有産階級で組織されていたので、労働者や農民(小作人)の権利を考える発想がなかったのです。
なお、本法第5条で女子の政談集会への参加を禁止しましたが、1922(大正11)年に本条項は撤廃されました。
《 軍部大臣現役武官制の制定(1900) 》
山県内閣は、政党の軍部への影響力の浸透を防ぐため、改正陸軍省・海軍省官制を交付し、陸軍・海軍大臣及び総務長官(事務次官に相当)の任用資格を現役将官に限定しました。これを、軍部大臣現役武官制といいます。
この規定は、制定当時はさほど重要視されませんでした。しかし、その後の政治運営にあたり、重要な役割を果たすことになりました。「陸軍大臣・海軍大臣を現役将官に限る」というのは、とりもなおさず「軍部が大臣候補者を出さなければ組閣ができない」ということを意味するからです。
軍部大臣現役武官制は1913(大正2)年、第1次山本権兵衛内閣によっていったん廃止されました(ただし、現実には現役将官の大臣就任が継続しました)が、陸軍統制派の影響のもとで成立した広田弘毅(ひろたこうき)内閣により、1936(昭和11)年、復活しました。
この制度によって宇垣一成(うがきかずしげ)内閣が流産し、米内光政(よないみつまさ)内閣が瓦解させられました。軍部大臣現役武官制は、軍部の政治的発言力を強めるとともに、内閣の死命を制する大きな武器として利用されたのです。

② 立憲政友会の成立
藩閥勢力への接近を強めていた憲政党(旧自由党系)は、山県内閣への党員入閣を拒否されると山県との提携断絶を宣言しました。そして次には、山県と官僚閥を二分する伊藤博文への接近をはかったのです。
憲政党幹部は、伊藤に同党党首への就任を要請しました。すると伊藤は、政策運営には党利党略にとらわれない国家的見地が必要であると説き、官僚・実業家・政党等を含めた新党結成の考えがあることを彼らに披瀝(ひれき)しました。そこで、憲政党は自ら解党して、伊藤の新党運動に合流することを決定したのです。
藩閥政治家には政党嫌いが多かったため、新党は伊藤の強い要望で「党」の字を避け、
立憲政友会と命名されました。総裁には伊藤が就任しました。立憲政友会は議院内閣制(政党内閣)を否定して輔弼内閣制(ほひつないかくせい)を承認し、天皇政治の補佐を目指す政治集団であることを宣言したのです。
立憲政友会の発会式は1900(明治33)年9月15日、帝国ホテルにおいて、山県有朋首相はじめ貴族院議員や衆議院議員らの列席のもと、盛大に行われました。このあと、立憲政友会を基盤に第4次伊藤博文内閣が成立することになります。
ところで、伊藤といえば藩閥勢力の巨頭の一人です。保安条例発布時には首相で、自由民権運動を弾圧した張本人が伊藤でした。つまり、自由党の系譜に連なる憲政党員らは、政権獲得を急ぐあまりに、往年の仇敵(きゅうてき)と手を結んだことになります。もはや彼らは増税にも反対せず、軍拡をも容認することになったのです。
こうした裏切り行為に対し、幸徳秋水は「自由党を祭る文」を発表しました(『万朝報(よろずちょうほう)』1900年8月30日)。秋水は、弔辞(ちょうじ。死者をとむらうための文)の形式をとる文章において、自由党(当時の名称は憲政党)が自由民権運動の光栄ある歴史に背を向け、藩閥勢力の権力基盤に成り下がったことを痛烈に批判しました。
こうして成立した立憲政友会でしたが、衆議院においては多数政党の地位を占め続け、後年、ついにわが国初の本格的政党内閣(原敬内閣)を成立させることになるのです。

�
① 官僚とは
明治維新以来、日本では、政府の指導によって上からの近代化が推し進められました。これに大きな役割を果たしたのが官僚でした。官僚は、官吏(役人)のなかでも国の政策決定に力をもつ、特に上・中級官吏を指す言葉です。
官僚の出身をみると、明治時代のなかごろまでは薩摩・長州・幕臣出身者がその地位を独占していました。役職別でみると、高級官僚は薩摩・長州出身者、下級官吏は幕臣出身者という具合でした。つまり、上司が薩長閥、部下が幕臣出身者というわけです。
しかし、こうした出身や身分という縁故・情実による登用法自体、本来、好ましいものではありません。官僚にはその職を全うするだけの専門知識や能力が必要ですし、また採用する際には、誰しもがその選抜方法に納得する透明性・公平性が必要です。
そこで政府は、文官任用令・文官懲戒令・文官分限令などの諸法令を整備して官僚制の整備を進め、また文官高等試験をおこなって優秀な人材を選抜・採用することにしました。つまり、選抜試験に合格さえすれば、行政上の専門知識・能力をもつ者と認められて、身分や出身地等に関係なく、官僚に採用されることになったのです。
ただし、選抜試験は難関でした。そのため、高級官僚はほぼ帝国大学卒業生たちによって独占されました。この結果、それまでの藩閥官僚に代わって学閥官僚が登場することになりました。これは学歴社会の始まりでもありました。

② 元老とは
またこのころ、明治維新以来の功労者で有力な長老政治家が、天皇の相談役として後継首相の推薦や国家の重要事項の決定等に参画しました。彼らは元老とよばれ、政治の第一線を退いたのちも政界に大きな影響力をもちました。ただし、「元老」という地位が、法律上に規定されていたわけではありません。あくまでも非公式のものでした。
元老といえば、具体的には薩摩藩出身の黒田清隆(くろだきよたか)・松方正義(まつかたまさよし)・大山巌(おおやまいわお)・西郷従道(さいごうつぐみち)、長州藩出身の伊藤博文(いとうひろぶみ)・井上馨(いのうえかおる)・山県有朋(やまがたありとも)の7人を指しました。明治時代末期になると、長州藩出身で山県系の桂太郎(かつらたろう)と、公家出身の西園寺公望(さいおんじきんもち)がこれに加わりました。
�

