60.条約改正
「抑々(そもそも)条約改正の大業は維新以来国家の宿望(しゅくぼう)に係り、之(これ)を完成せざる間は維新の鴻業(こうぎょう)も尚ほ一半を剰すに均(ひと)しとは、久しく我国(わがくに)朝野(ちょうや)帰一の意見たり。
因(より)て明治十三年当時の外務大臣井上伯爵(はくしゃく)が始(はじめ)て一の条約改正案を作り、締盟各国と談判の緒(ちょ)を開き、長日月の間、百方計画する所ありしも、不幸にして其(その)業半途に失敗し、其後歴任の当局者は孰(いず)れも、所謂(いわゆる)井上案に対し其時相当の修正を加へたる約案を以(もっ)て各国政府の代表者と会商し、就中(なかんずく)大隈伯爵の如きは、権変縦横(けんぺんじゅうおう)の才を奮(ふる)ひ、当時世論の逆潮(ぎゃくちょう)に抵抗し、其志望を達せむとしたるも其局尚ほ失敗に了(おわ)り、条約改正の歴史は殆(ほとん)ど失敗の歴史たるに至りぬ。」
(陸奥宗光『蹇蹇録(けんけんろく)』1978年第26刷(1933年初刷)、岩波文庫、P.95。 なお、読みやすくするために漢字は現行のものに改め、適宜句読点・よみがなを付した。)
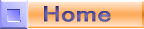
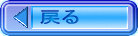

① 欧化政策とは
岩倉具視・寺島宗則のあとをうけて、条約改正交渉の中心となったのが、井上馨でした。
条約改正交渉がなぜ失敗するのか? それは、諸外国が日本を相変わらず未開の遅れた国と認識しているからに他なりません。それなら、日本の近代化がここまできているということを諸外国にアピールして、条約改正を促進すべきだ。
このように考えた井上は、あらゆる方面で西欧化を推進しました。こうした一連の政策を「欧化政策」といいます。

② 鹿鳴館時代(1883~1886)
欧化政策の象徴とされる鹿鳴館(ろくめいかん)は、1883(明治16)年11月、東京日比谷に開館した官営国際社交場です。
設計は工部大学校造家学科(東京大学工学部建築学科の前身)の教官ジョサイア=コンドル(1852~1920。コンドルはオランダ風の読み方。英語の発音はコンダーの方が近い)。明治政府が招聘(しょうへい)した「御雇い外国人」の一人で、1877(明治10)年、24歳の新進建築家としてイギリスから来日しました。
鹿鳴館はルネッサンス風の2階建て煉瓦造りの建物。建坪410坪(約1、353㎡)に総工費18万円を費やしました。屋根は中央部にフランス瓦、他は桟瓦(さんがわら)で葺(ふ)き、ベランダにはイスラム風のとっくり状の柱を並べました。内部には大小十数の部屋があり、社交ダンスが行われた有名な舞踏室は2階にありました。建物の造りが悪いためか、ダンスの際には舞踏室の板張りの床がゆらゆら揺れました。「床が抜けるのではないか」と冷や冷やしていた外国人賓客もいたといいます。
鹿鳴館では連日のように舞踏会、慈善会(バザー)などが催されました。しかし、鹿鳴館が社交場として利用されたのは、1883(明治16)年から1886(明治19)年までのわずか3年間にすぎません(鹿鳴館時代)。井上が失脚してしまったからです。
◆鹿鳴館の「淑女」たち
鹿鳴館に諸外国の貴顕・淑女を招いて、社交ダンスを催すことになりました。しかし、ダンスをやった経験者がほとんどいません。たまたまヤンソン(獣医学)というドイツ人がダンスを知っているというので、彼を指導者として毎週月曜日に練習会を実施することにしました。
「紳士」の方はともかくも、ダンスを踊る「淑女」の数が足りませんでした。そこで、さまざまな身分の女性をかき集めて洋装させ、やっと人数を揃えました。芸妓などが多かったそうです。フランス人画家のビゴーは、ダンス練習の休憩時にタバコをふかす、お行儀があまりよくない女性たちのスケッチを残しています。
ですから、こんなこともありました。鹿鳴館で開催されたあるパーティでの出来事。背後がぱっくり開いたイヴニングドレスを着た婦人の背中に、点々と二列縦隊になっているマークがありました。それを見つけた外国人が、好奇心をおさえきれず、次のような質問をしたといいます。
「背中のマークは、日本の貴婦人のしるしでしょうか?」
二列縦隊のマークとは? それは、お灸(きゅう)をすえた痕(あと)だったということです。 |

③ 極端な西欧化推進運動
ついで、衣食住など各分野にわたる改良運動が展開しました。中には「国字を廃止してローマ字にせよ」、「欧米人と結婚して人種改良せよ」などといった極端な提案も堂々と主張されました。
このような欧米の風俗・習慣等の表面だけの導入は、外国人の目から見れば滑稽な「猿真似」、日本人の目から見れば軽佻浮薄な伝統破壊と映りました。
内田魯庵(うちだろあん。1868~1929)はこの時代を回顧して、次のように書いています。
「一時は世を挙(あ)げて欧化の魔術にヒプノタイズ(注:hypnotize(英語)。催眠術をかける、の意)されてしまった。が、暫(しばら)くして踊り草臥(くたび)れて漸(ようや)く目が覚めると、苦々しくもなり馬鹿々々しくもなった。この猿芝居は畢竟(ひっきょう)するに条約改正のための外人に対する機嫌取(きげんとり)であるのが誰にも看取されたので、かくの如きは国家を辱(はず)かしめ国威を傷つける自卑自屈であるという猛烈なる保守的反動を生じた」(内田魯庵『四十年前-新文学の曙光-』1925年-青空文庫による。底本は内田魯庵『新編 思い出す人々』1994年、岩波文庫-)
時代は、松方デフレーションの嵐の中にありました。民衆が疲弊の中に喘ぎ、活計困難を理由とした自殺者が相次ぎ、自由党による過激事件が各地で頻発していた頃です。こうした社会情勢をよそに、また一般民衆の生活から遊離した欧化政策は、各方面からの激しい批判にさらされました。

④ 井上案の概要
井上案の重点目標は、治外法権の撤廃にありました。そこで、税権は税率の引き上げ程度にとどめることにしました。しかし、諸外国がやすやすと、日本の改正案を認めてくれるはずはありません。見返りを要求されることは必至でした。
本会議前に諸外国との予備会議を催した井上は、取引き条件として、
・外国人の内地雑居(外国人に日本内地を開放する)
・裁判所への外国人判事任用(外国人が関係する刑事事件の予審に外国人判事をあてる)
・法典の予約(重要法典の公布前に外国の承認を得る)
などを約束することにしました。
しかしこの間、ノルマントン号事件(1886)が起こり、国民の対英感情が極度に悪化していました。
交渉は秘密裏に進められましたが、フランス人の法律顧問ボアソナード(1825~1910)は、日本側が提示した取引き条件があまりにも屈辱的であるとして、井上案に猛反対しました。政府内部からも反対の声があがりました。農商務大臣の谷干城(たにたてき。1837~1911)は、井上案反対の意見書を提出して辞職してしまいました。両者の意見書は秘密出版で民間に流布し、反対運動は全国に燃え広がりました。そのため、ついに井上は辞職に追い込まれてしまったのです。
しかし、世論はそれでもおさまりませんでした。外交失策の挽回(井上案を外交失策として糾弾)等を求める三大事件建白運動がおこりました。そのため、政府は保安条例(1887)を公布し、高揚した運動の鎮静につとめねばならなかったのです。
◆ノルマントン号事件
ノルマントン号は、イギリス系商社アダムソン=ベル商会所有の1533トンの貨物船。もともと客船としての免許状を持っていませんでしたが、1886(明治19)年10月、日本人乗客25名を乗せて、横浜を出発して神戸に向かっていました。
事故は10月24日の夜に起きました。和歌山県潮岬(しおのみさき)沖で風雨にあい、航路を誤った船は座礁してやがて沈没。船には日本人乗客以外に、イギリス人船長以下39名の乗組員(清国人3名、インド人15名を含む)が乗っていました。しかし、船長以下乗組員29名はわれ先にとボートに乗って脱出。翌25日朝、串本などに漂着した26名が救助されました(残り3名は凍死)。
こうして、見捨てられた日本人乗客25名全員と、ボートに乗れなかった乗組員10名(インド人9名を含む)が犠牲になりました。つまり、おもな犠牲者は有色人種だったのです。逃げ出したイギリス人たちに、人種差別の意識はなかったのでしょうか。また船長や乗組員には、乗客救助に当たる義務はなかったのでしょうか。
事件について、神戸イギリス領事館庁で海事審判が開かれました。ところが驚いたことに、判事長ツループは「ボートに乗り移るよう勧めたが、日本人は英語を解さなかった」というウィリアム=ドレーク船長の陳述を認め、日本人乗客らを見捨てた船長たちの措置に過失はなかったと結論づけたのです。
「英語がわからない乗客は見殺しにしてもいい」という屁理屈がまかり通ったことに、船長の厳罰を期待して事態の推移を見守っていた世論は沸騰しました。世論に圧された政府は、兵庫県知事内海忠勝に船長を殺人罪で告訴させました。そこで、横浜領事庁の裁判長ジョン=ハーネンは12月8日、船長を職務怠慢の理由をもって禁錮3ヵ月に処する判決を下しましたが、犠牲者には1銭の賠償金も支払われませんでした。
翌年になっても国民感情の高ぶりはおさまらず、船長らの非人道的行為を非難する「ノルマントン号沈没の歌」(最初36節、事件解決後23節を追加したものという)が作られ、広く国民に流行しました。この事件を契機に、治外法権撤廃を目指す条約改正要求の動きが一段と加速したのでした。 |

① 大隈案の概要
大隈案も井上案とほとんど内容は変わりません。まずは法権回復に重点をおきました。見返りに、外国人の内地雑居、外国人判事の任用、近代的な法典編纂の外国への約束などを認めた改正案を用意しました。井上案と異なるのは、外国人判事の任用を大審院に限定したこと、法典に外国の承認を必要としないことなどでした。
大隈は、井上の交渉失敗の原因が国際会議方式にあると考えました。会議場に外国一同を集めるやり方では、諸外国に結束する機会を与えてしまいます。それを避けるためには、国別に交渉を進める方が得策ではないか。そう判断した大隈は、秘密裏にアメリカ・ドイツ・ロシアと次々に交渉して、条約を締結していきました。

② 大隈の遭難
改正交渉は順調に進んでいるかに見えました。しかし、イギリスとの交渉中、その内容が『ロンドン・タイムズ』紙上に暴露されてしまいました。それを見ると、日本国民があれほど反対した井上案と大差がないではありませんか。
さらにこの頃には、大日本帝国憲法がすでに発布されていたため、違憲論議まで起こりました。
憲法第19条には、
「日本臣民ハ法律命令ニ定ムル所ノ資格ニ応ジ、均(ひと)シク文武官ニ任ゼラレ、其(そ)ノ他ノ公職ニ就(つ)クコトヲ得(う)」(日本臣民はだれでも文官・武官、その他の公職に就く権利がある)
と書いてあります。裏返せば「公職に就けるのは日本臣民のみであって、外国人を大審院の判事に任命することは許されない」ということになります。こうして国内各地に、大隈案に対する猛烈な反対運動がおこりました。
こうした中、大隈案に不満をもつ国家主義者が、大隈めがけて爆弾を投げつけるという事件が起こりました(1889年10月19日)。大隈は片足を失いましたが、一命はとりとめました。黒田清隆内閣は条約改正中止を決し、総辞職しました(10月24日)。またもや条約改正交渉は挫折してしまったのでした。
◆「隻脚侯(せききゃくこう)」大隈重信
1889(明治22)年10月19日午後4時頃、閣議を終えた大隈を乗せた馬車が外務省正門近くにさしかかった時、一人の男が車上の大隈めがけて爆弾を投げつけました。男の名は来島恒喜(くるしまつねき)。右翼団体玄洋社(げんようしゃ)の社員で、大隈の条約改正案に憤慨しての犯行でした。来島はその場で自殺。一方、大隈は、右脚に重傷を負ったため、大腿部下部3分の1の部位から切断せざるを得ませんでした。
政府は条約改正交渉の中止を決定すると、療養中の大隈を除いて総辞職しました。外相の任を解かれた大隈は、「(右脚を)失脚して失脚した」といわれました。
この時51歳の大隈は、しかし意気軒昂(いきけんこう)でした。「脚1本なくなっても、その分、からだのほかのところに栄養が回るからいい」と豪語し、その後2度目の内閣総理大臣を務め、85年の天寿を全うしました。
大隈は自身の右脚をアルコール漬けにして、自宅で保管していました。しかし、定期的にアルコールを取り替えるのがめんどうな上、費用もかかりました。持てあましたのち、赤十字中央病院(看護大学の前身)に寄付しました。病院では右脚を円筒形のガラス容器に入れ、ホルマリン漬けにして保存することにしました。
1998(平成10)年、右脚はいったん大隈ゆかりの早稲田大学(大隈が創設した東京専門学校の後身)に返還されました。現在は、佐賀県にある大隈の菩提寺竜泰寺(りゅうたいじ)に納められているということです。 |

① 青木案の概要
青木周蔵(あおきしゅうぞう。1844~1911)外相は、治外法権の撤廃・関税自主権回復、見返りは外国人への内地開放(ただし不動産所有権を外国人に与えない)のみという対等条約案を作成しました。
青木は、まず条約改正案を政府内で種々検討し、ついで枢密院に内示して了解を得ました。それまでの改正交渉では、交渉が始まったあとで閣僚や枢密顧問官から反対論が出たました。そうした失敗にかんがみ、同じ轍を踏まないように、最初に政府内部の意志統一をはかった上で、関係官庁に根回しをしたのです。
交渉は国別に行うこととし、最初に最難関のイギリスから交渉することに決めました。イギリスとの交渉がうまくいかなければ、他の国とどのような妥結をみても、結局は無駄になってしまうからでした。

② イギリスの思惑
それまでイギリスは、条約改正には消極的でした。しかし、ロシアがシベリア鉄道の建設に着手し、極東進出に積極的な姿勢を示すと、その態度を一変させます。貿易上、たいした利益でなくなりつつあった領事裁判権に固執するよりも、治外法権撤廃要求に応じて日本に恩を売った方が、イギリスの国益にとってはるかに賢明な選択と判断したからです。
当時、朝鮮半島の支配権をめぐり、日清両国が対立していました。もし、朝鮮半島に日本か清国のどちらかを置くことができれば、ロシアの南進を防ぐ盾(たて)とすることができます。そうすれば、イギリスは自ら労することなく、清国における権益を守ることができる。そのためには、日本を利用できる条約改正というカードを切るのは今だ、と考えたのです。
イギリスが柔軟な姿勢を示したこともあり、交渉は順調に進んでいるかに見えました。しかし、大津事件(1891)が起こったため、青木は引責辞職を余儀なくされ、またもや交渉は中断されてしまったのでした。
◆大津事件
1891(明治24)年、ウラジオストクでのシベリア鉄道起工式に出席する途中、ロシア皇太子ニコライ(のちのニコライ2世)が軍艦7隻を率い日本に来遊しました。ところが、大津町(現、滋賀県大津市)で警衛中の巡査津田三蔵(つださんぞう)は、皇太子の来日を日本侵略の下見と疑い、剣を抜いて皇太子に斬りかかったのです。津田はすぐさま2人の人力車夫に取り押さえられました。皇太子は頭に2カ所の創傷を負ったものの、生命に別状はありませんでした。
事件に日本国中が震撼しました。何せ、相手は大国ロシアの皇太子です。日露戦争にでもなれば、とても日本に生き延びる術(すべ)はありません。明治天皇は、皇太子を見舞うために京都に向かいました。ロシアの報復を恐れた国民はパニックに陥りました。皇太子への謝罪と称して、自殺する国民まで出たほどです。皇太子への国民の見舞状は1万通を越えました。大津事件が発生した滋賀県では、知事や警部長が懲戒免職となりました。
日露関係の悪化を恐れた政府・元老らは、犯人を極刑に処することで事態の収拾をはかろうとしました。そこで、大審院長児島惟謙(こじまこれかた、こじまいけん。1837~1908)に大逆罪(刑法116条)の適用を求め、また担当判事たちに圧力を加えました。
大逆罪というのは「天皇・大皇太后・皇太后・皇后・皇太子・皇太孫に対して危害を加えたり、加えようとした者を死刑に処する」という罪科です。つまり、大逆罪の対象は日本の皇室のみであって、外国の皇太子に対しては適用されないのです。
大津地方裁判所で開かれた大審院特別法廷は、津田に刑法112条・同292条の通常謀殺未遂罪を適用し、無期徒刑(むきとけい)を言い渡しました。政府の圧力を退け、「司法権の独立」を守ったのです。
この判決に政府は頭を抱えこみましたが、諸外国は妥当な判決としておおむね好意的に評価しました。司法のぶれない態度が、日本の近代国家への成長ぶりを諸国に印象づける結果となったのです。 |

① 苦境に立つ政府
初期議会(第1議会~第6議会)は混乱を極め、政府は苦境に立たされていました。専制政治を批判する反政府熱は議会にとどまらず、全国民的になっていました。1894(明治27)年3月27日付け、青木周蔵駐英公使あての陸奥宗光(むつむねみつ。1884~1897)外相の手紙は悲痛に満ちていました。
「内国(ないこく)ノ形勢ハ日又一日(ひまたいちにち)ト切迫シ、政府ハ到底何カ人目ヲ驚(おどろ)カシ候(そうろう)程(ほど)ノ事業ヲ、成敗(せいはい。成功と失敗)ニ拘(かかわ)ラズナシツツアルコトヲ明言スルニアラザレバ、此(この)騒擾(そうじょう)ノ人心ヲ挽回(ばんかい)スベカラズ」 (井上清『条約改正』1955年、岩波新書、P.216)
さりとて、人目を驚かす事業というのは何でしょうか。理由もなく戦争を起こすわけにも行きません。ですから「唯一ノ目的ハ条約改正ノ一事ナリ」と、条約改正に全力を注ぐことになるのです。しかし、実際には、「人目を驚かす事業」が二つセットになって到来するのです。それが、条約改正(日英通商航海条約調印による治外法権撤廃)と日清戦争の開始でした。

② 治外法権の撤廃に成功
日英通商航海条約は、陸奥宗光外相の交渉により、日本が治外法権の撤廃に成功した最初の改正条約。税権の部分的回復も盛り込まれていました。1894(明治27)年7月16日に駐英公使青木周蔵・イギリス外相キンバリー間で調印、同年8月27日公布、1899(明治32)年7月17日より実施されました。イギリスを皮切りに、同内容の条約を他の国々とも次々調印しました。
日本の条約改正の求めにイギリスが応じたのは、前述したように、朝鮮半島をめぐって清国と対立を深めつつある日本を利用して、ロシアの極東進出を牽制する意図があったからです。
条約調印後、キンバリーは青木公使と日本政府に対し、次のような祝辞を述べました。
「此条約ノ性質タル、日本ニ取リテハ清国ノ大兵ヲ敗走セシメタルヨリモ寧(むし)ロ遥(はるか)ニ優(すぐ)レルモノアリ」
キンバリーがいみじくも語ったように、同条約が日本の国際的地位の向上に果たした役割は大きいものでした。イギリスの好意的支持を取り付けた日本は、朝鮮半島の指導権をめぐって対立していた清国に、7月24日を期限とする最後通牒(さいごつうちょう)を送りました。まだ宣戦布告がなされていないにもかかわらず、翌25日には豊島沖(ほうとうおき)で清国艦隊を奇襲し、これを撃破しました。この時、清国に雇われていたイギリス商船も一緒に撃沈させられました。しかし、この被害をとやかく言い立てて、日本を困らせるようなことをイギリスはしなかったのです。
8月1日に、やっと宣戦布告がなされました。かくして日清戦争(1894~1895)は開始されたのです。
◆陸奥宗光-外務省構内で唯一銅像になった外務大臣-
外務省構内で歴代外相中ただ一人、銅像になっているのが陸奥宗光です。銅像が建立された経緯について、外務省のHPには次のように書いてあります。
「日清戦争や条約改正といった難局に、外相として立ち向かった陸奥宗光の業績を讃え、各界の基金により1907年(明治40年)、外務省内に銅像が建立されました。しかし1943年(昭和18年)、戦時金属回収により供出されました。その後、同外相の没後70周年に当たる1966年(昭和41年)に再建されました。」
(外務省HP「http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/qa/sonota_02.html」)
陸奥の実父は、『大勢三転考(たいせいさんてんこう)』の著作で知られる伊達千広(だてちひろ。1802~1877)。和歌山藩の要職(勘定奉行兼寺社奉行)にありましたが政争で失脚し、約10年間、田辺に幽閉されました。そのため、一家は辛酸をなめ、陸奥も江戸に出て苦学しました。
陸奥はその後脱藩して尊王攘夷運動に身を投じ、坂本龍馬の海援隊に入隊。維新後は明治政府に仕官するも、1877年に明治政府転覆計画に関与したかどで免官・投獄されました。1883年に出獄してヨーロッパに遊学、帰国後外務省に入りました。第1回衆議院議員総選挙で和歌山県から立候補して当選。第1次山県有朋内閣、第1次松方正義内閣の農商務相になります。「藩閥政府」の中で、閣僚中唯一の衆議院議員でした。
第2次伊藤博文内閣では外相として、日英通商航海条約の調印に成功。15カ国と同様の条約を調印して、政府・国民の悲願だった治外法権撤廃に成功しました。また、日清戦争の難局に当たり、講和条約を成立させました。世人は陸奥を「カミソリ大臣」、その対外政策を「陸奥外交」とよびました。
陸奥が口述・著作した『蹇蹇録(けんけんろく)』は、「陸奥外交」の内実を知る上での重要史料です。書名は「蹇蹇匪躬(けんけんひきゅう)」に由来。臣下が君主に身を苦しめて仕える、の意です。その書名のごとく、激務から肺結核を悪化させて外相を辞任。その1年後、53歳で他界してしまったのでした。 |

① 関税自主権の回復に成功
日英通商航海条約(1896年までに各国とも同様の条約を調印)では関税の部分的引き上げはなされましたが、関税自主権そのものは回復されませんでした。そこで小村寿太郎(こむらじゅたろう。1855~1911)は、条約の有効期限の切れるのを待って、1911(明治44)年、改定の条約(日米通商航海条約。以後各国とも同様の条約を調印)で関税自主権を回復したのです。
ここにおいて、日本国民の悲願だった条約改正がようやく達成されたのでした(ただし、旧居留地の永代借地権は1942年まで回収できませんでした)。
なお、小村は条約改正以外にも、日英同盟の推進、ポーツマス条約の締結・調印など、明治末期における一連の困難な外交課題に果敢に取り組みました。その激務は小村の命を縮める結果になりました。条約改正が成就したその年、小村は56歳で他界してしまいました。

② 小村寿太郎と陸奥宗光
小村寿太郎は19歳の時、第1回文部省留学生の一人としてアメリカに渡り、ハーバード大学で法学を学んだという経歴をもちます。当時の旅券の写しが外務省記録に残っており、旅券発給記録に小村の身体的特徴が記述されています。それによると、小村は「鼻高き方、口小さき方、面長き方、色白き方」で、身長は「五尺一寸五分(約156センチメートル)」だったといいます。その風貌から「ネズミ」とあだ名されました。
小村はのち外務官僚になりました。身長が高く体格のよい欧米外交官の中に混じると、小柄な小村はさぞや貧相に見えたことでしょう。
しかし、彼には外交官としての並々ならぬ才能がありました。そうした小村の才能を見出したのは陸奥だった、といわれます。たとえば、小村は抜群の記憶力を有していました。いつも原稿を見ることなく、長い演説をこなしました。あとで速記録と原稿を比較すると、一言一句異なるところがなかったというのです。
陸奥といい小村といい、己の命を削ってまで自らの役割を全うしようとした明治の人びとの使命感には強烈なものがありました。彼らによって条約改正が達成されたころ、明治という時代はその幕をゆっくりとおろしつつありました。
【参考】
・外務省HP「http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/qa/sonota_02.html」
・日本外交文書デジタルアーカイブ
「http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/index.html」

