6.飛鳥の朝廷
「(608年の遣隋使は)前の使節の小野妹子で間にあわせた。ただし妹子の履歴に箔をつけるためか、彼は当時朝廷の実力者大臣である蘇我馬子の姓をとって、蘇我妹子と称して使いしたらしい。だから隋の歴史には、蘇因高(そがいもこ)と記している。相手が稀代の暴君煬帝であるから、こちらからできるだけの礼節は尽すが、その代わり、先方でも礼儀をもって待遇しろと、言うだけのことを言っているから面白い。そして国書を書くにはずいぶん強硬な態度を示し、いわば硬軟両様の使いわけをして、はなはだ弾力がある。当時の日本の国力としてはまず上出来な外交であったということができよう。」
(宮崎市定『隋の煬帝』1987年、中公文庫、P.141~142)
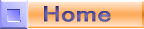
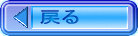


① 外交の失敗
朝鮮半島には、北に高句麗(こうくり)が大きく領域を占めていました。そして、その南の東側に新羅(しらぎ、しんら)、西側に百済(くだら、ひゃくさい)が、それぞれ国を構えていました。朝鮮半島の南端に加耶(かや)諸国が、新羅・百済に囲まれるように位置していました。
6世紀になると、高句麗南下の圧力を受けた新羅・百済が南に押し出され、加耶諸国に迫りました。加耶諸国は次々に新羅や百済の支配下にはいり、562年までに半島からその姿をすっかり消してしまうことになりました。
ヤマト政権は、加耶地域から大量の鉄資源や大陸の新技術を導入していたので、その滅亡は大きな打撃でした。こうして、朝鮮半島におけるでのヤマト政権の勢力は後退したのでした。
6世紀初め、政治を主導したのは、大伴金村(おおとものかなむら)でした。大伴氏は、加耶西部の地域に対する百済の支配権が確立したことが失政とされ、失脚しました。真偽は不明ですが、百済から賄賂を受け取り、加耶西部(かつては「任那四県(みまなよんけん)」と称しました)を百済に渡してしまったというのです。
大伴氏が失脚すると、6世紀中ごろには、物部(もののべ)氏と蘇我(そが)氏が対立するようになりました。

② 豪族間の対立
物部氏は、大連(おおむらじ)の姓(かばね)をもつ伝統的な勢力です。磐井(いわい)の乱を鎮圧したことに示されるように、軍事を職掌とする一族です。日本古来の神祇信仰を守っていこうという立場をとり、外来宗教である仏教に需要に関しては否定的でした。
一方、蘇我氏は大臣(おおおみ)の姓をもつ新興勢力です。斎蔵(いみくら。神庫)・内蔵(うちつくら。大王の財産)・大蔵(おおくら。政権の財産)の三蔵(みつくら)を管理する経済官僚で、現在でいうなら財務大臣に相当しましょう。当時、文字を書いたり計算ができる人材は、渡来人以外、多くはいませんでした。渡来人と結んで朝廷の財政権を握った蘇我氏は、渡来人が信仰する仏教の受容を積極的に推進しました。
両者の対立は587年に、物部守屋(もののべのもりや。?~587)の滅亡、蘇我馬子(そがのうまこ。?~626)の勝利という形で決着をみました。この時、若い厩戸王(うまやとおう。のち「聖徳太子」と呼ばれる)は四天王(してんのう。仏法の守護神)に「仏敵物部氏」の滅亡を祈願し、蘇我氏と一緒に戦いに臨みました。祈願成就の礼として建立したのが、四天王寺だといわれます。
なお、テラツツキ(キツツキ)という鳥が、今でも寺院をつついて柱や板壁に穴をあけているのは、排仏派の守屋の生まれ変わりだからだという俗信があります。

① 隋による中国統一
さて、後漢滅亡後、長らく分裂状態だった魏晋南北朝時代に終止符を打ったのが隋(ずい)の楊堅(ようけん。文帝)でした。589年に南朝の陳(ちん)を滅ぼし、およそ400年ぶりに中国を統一しました。隋は律令制を整備するとともに、周辺地域に進出を開始しました。高句麗に対しては、数次にわたって大軍を派遣しました。東アジアは、隋の登場によって、新たな激動の時代を迎えることになりました。倭国では、この隋の圧力に対処するため、権力の集中を迫られました。

② 国内の動向
蘇我氏は一族の娘を天皇の后(きさき)とし、多くの皇子・皇女の外戚になることで権力を強化しました。そして、用明天皇(ようめいてんのう。在位585~587)、崇峻天皇(すしゅんてんのう。在位587~592)と、蘇我氏の娘が生んだ皇子を次々即位させ、権力の集中をはかりました。しかし、物部氏滅亡後、蘇我馬子は、蘇我氏の権勢を嫌った崇峻天皇を暗殺してしまいます(592年)。
亡くなった天皇に代わって、敏達天皇(びたつてんのう)の后で馬子の姪(めい)でもある推古天皇(すいこてんのう。在位592~628)が即位します。わが国最初の女帝の誕生です。翌593年、推古天皇を補佐したのが、天皇の甥(おい)の厩戸王でした。この時代、推古天皇・厩戸王・蘇我馬子三者による共同統治により、権力の集中がはかられます。
◆厩戸王(うまやとおう)
以前の日本史教科書には「593年、聖徳太子は推古天皇の摂政になり、政治を補佐した」というようなことが書いてありました。しかし、近年の教科書には「厩戸王(聖徳太子)」と記載され、「聖徳太子」の名が後方に押しやられている上、太子の業績についても記述があっさりしています。これはなぜでしょう。
聖徳太子といえば、憲法十七条を定め、対等外交を目指して遣隋使を派遣し、法隆寺・四天王寺などを創建した偉人とされてきました。「1度に10人の訴えを聴き分けた」などという超人的な逸話が数多く残されています。しかし、後世の潤色が多く、どこまでが事実かわかないのです。そもそも「聖徳太子」が登場するのは、奈良時代に編纂された『日本書紀』なのですから、その死後すでに100年が経過しています。この時点で、すでに太子は伝説化していました。
まずは名前ですが、「聖徳太子」というのは本名ではありません。聖徳とは仏教に通じて仏に備わるすぐれた徳をもつという意、太子は皇太子の意。おそらく、当時伝えられていた太子伝が『日本書紀』を編纂する際に取り入れられたのでしょう。皇太子の制も、飛鳥時代当時にはまだ成立していませんでした。こうした粉飾を取り除くと、実在の人物の名はどうも「厩戸」らしい。「皇子」は天武朝以降の称で、このころの王族は「王」と呼ばれていたはずですから、近年の教科書では「厩戸王」と記すようになったのです。
『日本書紀』には、太子は「推古天皇の皇太子となり、摂政として政治全般を委任された」とあります。しかし実質的には蘇我馬子との共同統治であり、それも10年間ほどのことでした。とても「政治全般を委任された」とは考えられません。その一方で、信仰対象としての太子のイメージは大きくふくらみ、偶像化された太子像がひとり歩きしていきました。
最近、学問の厳しい目が太子に向けられるようになりました。従来太子の事績とされてきたものが否定されたり、太子の存在自体にまで疑いの目が向けられるようになったのです。
【参考】
・五味文彦・野呂肖生著『ちょっとまじめな日本史Q&A(上 原始古代・中世)』2006年、山川出版社、 P.62~63を参照 |

③ 推古朝の政治
推古朝の政策の中で重要なものは603年に制定された冠位十二階の制、604年に制定された憲法十七条です。ともに、官僚制的な中央集権国家を目指したものですが、両者の政策は新羅遠征計画と密接に関わっています。当時の倭国は、新羅を牽制するために、隋との交際が必要でした。しかし、隋と交際するためには、最低限の条件として政治や儀礼が備わっていなければなりませんでした。こうした倭国を取り巻く国際情勢の中で、冠位十二階の制と憲法十七条が制定されたのでした。
《 冠位十二階の制 》
冠位十二階の制は、氏族単位の王権組織を再編成し、人材登用を狙ったものです。それまでの氏姓制度のもとでは、姓は世襲で入れ替わりがないため、社会が固定化してしまいます。そこで、個人の能力や業績などによって官吏が昇進できるシステムを作りました。冠位はその官人一代限りのものでした。
儒教徳目の徳・仁・礼・信・義・智をそれぞれ大小に分け、上から順番に大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼・大信・小信・大義・小義・大智・小智としました。それぞれの地位は外見で判別できるように、視覚化されています。徳・仁・礼・信・義・智にそれぞれに紫・青・赤・黄・白・黒の各色を順番に割り当て、冠と冠の飾りをそれぞれの色で作ったというのです。たとえば、大徳には濃い紫、小徳には薄い紫を割り当てるというように。それなら、大義の濃い白、小義の薄い白というのは実際どんな色なんでしょうか?
なお、この冠位十二階の制が適用されたのは、中央豪族のうち、大夫(まえつきみ)層以下の人びとだけでした。王族や蘇我氏、地方豪族などは、対象外でした。
《 憲法十七条 》
次に、憲法十七条ですが、ここでいう憲法とは、現在われわれが「日本国憲法」という意味で使用する憲法とは意味が異なります。憲法十七条は、「官吏としての心得」を17条にわたって書いたものです。
具体的内容は、豪族の融和(第1条)、政治理念として仏教重視(第2条)、天皇権威の絶対化(第3条)などです。王権のもとに中央・地方の行政機構を編成しようとする意図が見られます。しかし、天皇の権威をあまりにも強く打ち出していること(第3条)、当時存在しなかった「国司」などの言葉が見られること(第12条)等から「憲法十七条は後世の偽作だ」という意見もあります。憲法十七条は、100年以上も後の720年に成立した『日本書紀』に載っている史料ですから、多分に後世の潤色はあるでしょうが、大綱においては存在したと理解されています。
憲法十七条の17という数字は、中国の陰陽思想にもとづくものです。陰の最大数8と陽の最大数9を足したものだといわれます。「法令のはじまりは憲法十七条」という思想が生まれ、後世に影響を及ぼしました。おもだった法令は、17という数字を意識して作成されました。たとえば、次のようなものがあります。
御成敗式目 51ヵ条(=17×3)
建武式目 17ヵ条
朝倉孝景条々 17ヵ条
塵芥集 171ヵ条(=17×10+1)
禁中並公家諸法度 17ヵ条
《 その他 》
このほか、官僚制的中央集権国家にかかわる政策として、603年の小墾田宮(おわりだのみや)造営と、620年の国史編纂があげられます。
前者は従前の宮にくらべて格段に規模が大きいもので、天皇が政務に臨み、官僚が執務する場所としての機能をもつものです。
後者は、天皇を中心とした官僚制的中央集権国家の形成過程を示すために、企てられた事業でしょう。『天皇記(てんのうき、すめらみことのふみ)』、『国記(こっき、くにのふみ)』、『臣連伴造国造百八十部并公民等本記(おみむらじとものみやつこくにのみやつこももあまりやそとものおあわせておおみたからどものもとつふみ)』を作成したと伝えられていますが、乙巳(いっし)の変(645)の蘇我氏滅亡の折りに失われたといいます。

�
① 遣隋使の派遣
東アジアの新動向に対応して、中国との外交を再開しました。これを遣隋使といいます。『隋書』や『日本書紀』によると、600年、607年、608年(2度)、610年、614年の計6回の派遣記事があります。しかし、これらすべてが実際に派遣されたのかどうかは議論が分かれます。
この中で、派遣されたことが確実で、もっとも重要な意味を持つのは607年に派遣された遣隋使です。

② 607年の遣隋使
607年、倭国は大礼(だいらい)小野臣妹子(おののおみいもこ)を隋に派遣しました。大礼は冠位十二階中の第5位でしたね。この時、使節は次のような文面の国書を持参したと言います。
「日出(い)づる処(ところ)の天子、書を日没する処の天子に致(いた)す。恙(つつが)無きや、云々(うんぬん)」(『隋書』倭国伝)
「日出づる処の天子」、「日没する処の天子」という言葉から、隋と対等の姿勢で外交を展開しようとしたことがうかがえます。天子(皇帝)という称号を使用し、隋の皇帝と同じ立場に立てば、朝鮮諸国の王たちより上位に立つことができます。「倭の五王」時代とは大きく異なる外交姿勢です。
しかし隋から見れば、倭国は蛮夷の一つに過ぎません。それが「天子」を僭称(せんしょう)して、煬帝(ようだい)と同等の立場に立とうとしているのです。そもそも天子(皇帝)というのは、この世の中で中国皇帝一人だけではありませんか。当然のことながら、倭国の国書は煬帝を激怒させます。煬帝は鴻臚卿(こうろけい、外交事務を担当する役人)に向かい、「今後、蛮夷の国書に無礼なものがあったら、二度と奏上するな」と命じました。
しかし、高句麗出兵を計画していた煬帝は、倭国との関係悪化を避けるため、倭国をむげに拒絶することができませんでした。倭国が高句麗と連携でもしようものなら大変です。何しろ、高句麗というのは、煬帝の父文帝(楊堅)がかつて大軍を動員して遠征を試みたものの、ついに降すことができなかった強国でした(煬帝も三度高句麗遠征を試み、ことごとく失敗します。この失敗が隋滅亡の原因のひとつになります)。倭国が高句麗に味方でもすれば、面倒なことになってしまいます。倭国の方でも、そうした国際情勢を見越して、わざわざこの時期に、かような国書を送ってきたのでしょう。
翌年、煬帝は答礼使に文林郎(ぶんりんろう。文史を撰録する秘書省の属官)裴世清(はいせいせい)を任命し、倭国に派遣します。ただし、裴世清の官位は日本の令制の少初位上(しょうそいのじょう)、すなわち30階中の29位に相当するものでした。「蛮夷相手の役人はこの程度の者で十分だ」という、隋の大国意識が見て取れます。
◆煬帝不快の真の原因は
607年の遣隋使の国書の評価に関しては、近年、検討が迫られています。
本文中には「隋と対等な姿勢で外交を展開しようとした」という現在の通説を書きました。しかし、「日出づる処」・「日没する処」という言葉には、倭国と隋の上下関係・対等関係の意味はない、というのです。これらは、単に東・西を示す言葉に過ぎないということが、奈良大学教授の東野治之(とうのはるゆき)氏の研究によって明らかになりました。出典は鳩摩羅什(くまらじゅう)訳『大智度論』であり、607年の遣使の目的も、使者の言葉によれば、仏教を興隆させた「菩薩天子(煬帝)」を拝し、僧侶らを派遣して仏法を学ばせることにありました。
煬帝不快の原因も、通説は、「中華思想上において一人しか存在しない『天子』を倭王が僭称した」ことにあると考えられてきました。しかし、607年の国書が仏教経典を下敷きにした仏教用語にちりばめられ、その内容も僧侶の仏教留学を目的としていたとするなら、この場合の「天子」も仏教用語としての「天子(仏法によって国を統治する王)」と理解する方が自然です。もしそうならば、複数の「天子」が存在することも可能でしょう。
このように見てくると、煬帝が倭の国書に不快を示したのは、中華思想の「天子」を倭王が僭称して対等外交を求めてきたからでなく、仏教の後進国たる倭の王が、仏教先進国の隋の皇帝と同じく「天子」を名乗ったことに原因があったと考えられるのです。つまり、「文化レベルの低い蛮夷の王が、俺と同じく『天子』を名乗るなんてとんでもない」と。
【参考】
・河上麻由子「遣隋使」(『週間 新発見!日本の歴史03(飛鳥時代7)』2013年7月14日号、朝日新聞社、P.19参照)
|

③ 608年の遣隋使
608年、裴世清を帰国させるため、小野妹子(中国では「蘇因高」とよばれました)を大使として、再度隋に派遣しました。『日本書紀』によるとこの時、8人の学生・学問僧を一緒に派遣しています。学生は倭漢直福因(やまとのあやのあたいふくいん)・奈羅訳語恵明(ならのおさのえみょう)・高向漢人玄理(たかむこのあやひとのくろまろ)・新漢人大國(いまきのあやひとだいこく)、学問僧は新漢人日文(いまきのあやひとにちもん。後の記事には旻(みん)と記してあります)・南淵漢人請安(みなみぶちのあやひとしょうあん)・志賀漢人慧隠(しがのあやひとえおん)・新漢人広済(いまきのあやひとこうさい)でした。「漢人(あやひと)」・「今漢人(いまきのあやひと。「今」は「新来」の意)」とありますから渡来人系の人びとが選抜されたことがわかります。「訳語(おさ)」は通訳ですね。ですから、おそらく彼らは、言葉には不自由しなかったはずです。
この時派遣された学生や学問僧は、隋の滅亡後も中国にとどまって勉強を続け、大化の改新前後に相次いで帰国します。彼らのもたらした新知識が大化の改新の指導原理となりました。高向玄理・僧旻は改新政府で国博士として活躍します。南淵請安は改新政府で内臣(うちつおみ)となる中臣鎌足の学問の師です。


