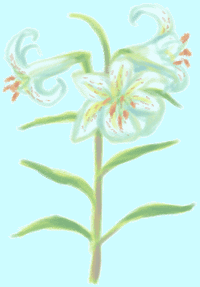
●古墳の出現とヤマト政権● |
| ◆「ヤマト政権」の表記 かつては「大和朝廷」と呼ばれました。なぜ、表記が「ヤマト政権」にかわったのでしょうか。それは、4~5世紀の政治勢力を示す歴史用語として、「大和」と「朝廷」の二つの表記がともに不適切だという意見が強くなったからです。 古墳時代の政治勢力の根拠は奈良県東南部であって、その後の大和国全体ではありません。そもその「大和」の文字が使用されるのが8世紀後半以降であり、それ以前には「倭」「大倭」が用いられました。 一方、「朝廷」というのは、大王のもとに官僚集団が形成され、全国的に支配を及ぼす体制ができてからの呼称です。4~5世紀頃の政治連合を示す語としては不適切といえます。 そのようなわけで、「大和」ではなくて「ヤマト」、「朝廷」でなくて「政権」とするのが適切だというので、「ヤマト政権」という表記にかわったのです。 【参考】 ・五味文彦・野呂肖生編著『ちょっとまじめな日本史Q&A 上 原始古代・中世』2006年、山川出版社 |
●前・中期の古墳● |
| ◆前方後円墳とは 朝鮮半島でも発見例がありますが、わが国独特の古墳の形状と考えられています。 この特異な古墳の形を初めて「前方後円」と呼んだのは、江戸時代の尊王思想家、蒲生君平(がもうくんぺい)でした。彼は、墳丘を宮車に見立て、前方部を轅(ながえ)、後円部を座席の上をおおう蓋(かさ)、造り出し部分を車輪と見たのでした(『山陵志』)。 前方後円墳の成立については諸説あります。最近では、弥生時代の墳丘墓を母体として成立したとする説が有力です。周溝をもつ墳丘墓には、周溝の外部から中央の墳丘にいたる通路として陸橋部分がありました。この陸橋部分が変化してできた突出部をもつ墳丘墓が、弥生時代後期には多く出現します。つまり、この突出部をもつ円形の墳丘墓が、前方後円墳に発達していったというのです。 【参考】 ・五味文彦・野呂肖生編著『ちょっとまじめな日本史Q&A 上 原始古代・中世』2006年、山川出版社 |
●東アジア諸国との交渉● |
| ◆好太王碑文 鴨緑江(おうりょくこう)の中流北岸、高句麗の古都国内城(丸都城(がんとじょう)、現在の中国吉林省集安市)に近い場所に、414年、長寿王が父好太王(広開土王)の事績を顕彰するために建立した自然石の角柱碑です。高さ6.34m、幅ほぼ1.6mに1775文字が刻まれています。 1880(明治13)年に発見され、1883(明治16)年、参謀本部の軍人の酒匂景信(さこうかげのぶ)がその拓本を日本に持ち帰りました。中国側から「碑文に石灰を塗り込んで、日本軍部が文字を改竄(かいざん)したのではないか」という疑惑が出されましたが、現在その考えは否定されています。 碑文には倭関係の記事が9カ所見られ、特に391年の朝鮮半島進出の記事が有名です。 |
| ◆朝貢(ちょうこう)と冊封(さくほう) 朝貢は、中国皇帝に貢ぎ物を持参して挨拶に行くことをいいます。往々にして中国皇帝から回賜(かいし。お返しに物品を賜ること)が行われます。 冊封は、中国皇帝が周辺地域の支配者に対し、その支配を認め称号を与えることをいいます。冊封をうけた場合、中国皇帝に服属する形式をとります。 |
| ◆朝鮮半島の鉄 古墳時代、日本は朝鮮半島南部と緊密な関係にありました。それは朝鮮半島に当時貴重品だった鉄資源があったからでした。古墳の中から見つかる鉄てい(「てい」はあらがねの意で、金へんに廷)と呼ばれる短冊形の鉄板は、朝鮮半島南部にあった加耶諸国から搬入されたと考えられています。鉄ていは、鉄製品の素材としてばかりでなく、貨幣的な役割をもっていた可能性が指摘されています。 |
●大陸文化の受容● |
●古墳文化の変化-後期の古墳文化-● |
●古墳時代の人びとの生活● |
●ヤマト政権と政治制度● |