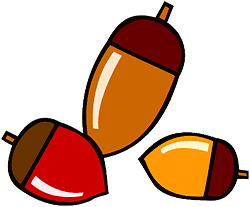●縄文文化の成立● |
① 気候が暖かくなって、木の実や中小動物が増えた
今から約1万年余り前、寒冷だった更新世(氷河時代)がようやく終わり、現在にまで続く完新世に移行しました。地球の気候も温暖になり、地表の氷河が解けた水が海に流れ込んだり、海水が膨張するなどして、海面が上昇しました。その結果、日本列島もユーラシア大陸と切り離されて、現在に近い自然環境となりました。
植物も亜寒帯性の針葉樹林に代わり、東日本にはブナやナラ・クリなどの落葉広葉樹林が、西日本にはカシやシイなどの照葉樹林(しょうようじゅりん。常葉広葉樹林)が広がりました。こうした森林相の変化は、豊かな実りを人びとにもたらし、植物性食物の利用機会を増大させました。新環境に適応できない大型動物は姿を消しましたが、森には下草が繁茂し、ニホンシカやイノシシなどの生息に適した環境になりました。
こうした自然環境の変化に対応して、人びとの生活も大きく変わり、縄文文化(じょうもんぶんか)が成立します。この文化は約1万2000年前から、水稲農耕を特色とする弥生時代がはじまる紀元前4世紀までの期間にわたりました。
② 縄文文化の成立-弓矢・土器・磨製石器の出現-
縄文文化を特徴づけるのは、殺傷力が強化された磨製石器(ませいせっき。新石器)、植物性食物を煮るための土器、動きの速い中小動物や鳥類を射とめる弓矢などの出現です。
磨製石器を使用する時代を新石器時代といいます。西アジアや中国などでは、新石器時代になると農耕・牧畜が行われる食料生産の段階(生産経済)に入るのに対し、日本の縄文文化は基本的には食料採取段階(獲得経済)の文化です。
| 考古学の時代区分 | 日本史の文化区分 | ||
| 旧石器時代 | 獲得経済 | 旧石器文化(旧石器時代) | 獲得経済 |
| 新石器時代 | 生産経済 | 縄文文化(新石器時代) | |
| 青銅器時代 | (日本には青銅器時代なし) | 生産経済 | |
| 鉄器時代 | 弥生文化(鉄器時代) | ||
③ 縄文土器の発明と生活の変化
縄文時代には盛りつけ用の浅鉢(あさばち)や保存用の壺(つぼ)はあまり発達しませんでした。この時代の土器の主流が深鉢型(ふかばちがた)なのは、土器使用の主目的が、煮ることにあったことを物語っています。事実、各地で発見された深鉢型の土器の表面には煤(すす)が付着しています。これは火をおこし、その中に土器を置いて使用した証拠です。
土器の発明は、縄文人の食べ物の幅を広げました。煮ることによって、それまで生では食べることのできなかった植物性食料が、利用できるようになりました。
たとえば、植物の種類によっては煮ることによって、アクを抜いて渋みや苦みをとったり、毒を無害にしたりすることができるようになりました。アラカシ・トチ・クヌギなどはアクが強くて、そのままでは食用に耐えません。しかし、これを砕いて土器に入れ、水で晒(さら)したり(注)、灰を入れて加熱したりするとアク抜きができるのです。
(注)水晒しには大量の水を必要とします。水が豊富な場所で発見される「水場遺跡」はこうした水晒しの作業のために作られた遺跡だと考えられています。
また、生のままでは、食べても人間のエネルギー源にならない食料がありました。たとえば、植物が生産するデンプンは、生のままではベータ型といった結晶状態にあり、人間の消化酵素では分解しにくいものでした。しかし、煮ることによって、結晶状態が解かれたアルファ型に変化し、消化吸収できるようになるのです。煮るという技術が、デンプンをエネルギー源として利用することを可能にしたわけです。
こうして土器の発明・普及によって、われわれの祖先は、各地の森林がもたらす植物性食料を積極的に利用する道を開いたのです。
なお、貝類なども海水とともに土器に入れておけば、短期保存さえできるようになりました。
この時代に用いられた土器は、表面を平らにするために撚糸(よりいと)などをころがしてつけた「縄文」とよばれる文様を持つものが多いので、縄文土器といいます。縄文土器の最初の名付け親は、大森貝塚(東京都)を発見したアメリカ人の動物学者エドワード=シルベスター=モースです。彼はこの特徴的な土器を、”Cord marked pottery”と呼びました。それが「索紋土器」、「縄紋土器」「縄文式土器」などの訳語を経て、現在の「縄文土器」の名称に落ち着いたのです(E・S・モース著、近藤義郎・佐原真編訳『大森貝塚』1983年、岩波文庫、P.205、その他)。
| ◆「縄文原体」の発見 従来の定説では、縄文土器の表面にある縄目のような文様は、織物や編み物を器面におしつけて作られたと考えられていました。この定説は、山内清男(やまのうちすがお)さんの何気ない行動と一瞬のひらめきによって、いとも簡単にくつがえされました。 1931(昭和6)年、東北帝国大学に勤めていた山内さんは、ある時綿棒の軸を何気なくゴム粘土の上で転がしていたそうです。その際、軸の端にあった刻みが、粘土上に不思議な文様を作ることに気づきました。何かがひらめいた山内さんは、近くにぶら下がっていたカーテンの房を使い、同じように粘土の上に転がしてみたそうです。すると、なんと縄文土器にそっくりな文様が現れたではありませんか。そこで山内さんは、いろいろと紐(ひも)の撚(よ)り方を変えてみて、同じ作業を何度も粘土上で試みたのでした。そして、縄文土器の文様が、器面に撚紐(よりひも)やそれを巻いた軸を回転させて作られたものであることを証明したのです。 山内さんはこの撚紐を「縄文(山内さん自身は「縄紋」と表記)原体」と呼びました。 【参考】 ・笠原一男他編『日本史こぼれ話(古代・中世)』1993年、山川出版社 |
④ 縄文土器の特徴と時代区分
縄文土器は低温で焼かれ、厚手(あつで)で黒褐色(こっかっしょく)のものが多いという特徴があります。また、この縄文土器の形の変化から縄文文化の時代は、草創期・早期・前期・中期・後期・晩期の6期に区分されます。それぞれの土器は次のような形態の特徴を持っています。
| 14C年代 | 時期区分 | 土器の特徴 |
| 1万3,000年前 ~ 1万年前 | 草創期 | 方形の平底か円形の丸底の深鉢形土器が多い。貝殻などで爪形(つめがた)の文様を連ねた爪形文や、粘土の紐を貼りつけた隆起線文(りゅうきせんもん)が多い。 |
| 1万年前 ~6,000年前 |
早期 | 炉のそばの土にさして使用する尖底土器(せんていどき)が中心。 |
| 6,000年前 ~5,000年前 |
前期 | 平底の深鉢が普及。 |
| 5,000年前 ~ 4,000年前 |
中期 | 装飾が立体的な火焔型土器(かえんがたどき)が出現。 |
| 4,000年前 ~3,000年前 |
後期 | 多様な器形。急須のような注口(ちゅうこう)土器(酒などを注ぐ)が普及。 |
| 3,000年前 ~ |
晩期 | 東日本で精巧な亀ヶ岡式土器(かめがおかしきどき)が出現。 |
このうち草創期の土器は、現在のところ世界でもっとも古い土器とされています。このことについては、「縄文土器は世界最古の土器として、日本列島で独自に生まれた」(縄文土器自生論)と考えるか、「一番古い土器は西アジアで生まれたというのが定説だ。だから、縄文土器が世界で一番古いはずはない。年代測定法の信頼性が問題だ」と考えるか、さまざまな意見があるでしょう。また、今後、アジア大陸などでこれと同じような古い土器が発見される可能性は十分にあります。しかし、たとえそうであっても、日本列島に住んだ人びとが更新世から完新世への自然環境の変化に対応する新しい文化を、はやい段階に生み出していたことは確かでしょう。
| ◆ 放射性炭素14C年代測定法(Radiocarbon dating) 放射性炭素14C年代測定法によると、縄文時代の開始期は約1万2,000年前とされてきました。大気や大気中に生存する生物には14Cが含まれていますが、生物が死ぬと14Cが一定割合で減少します。この原理を応用して生物遺体中の14Cの残存量を測定し、死後経過した年代を算出するのです。 ところが、過去から現代にいたる大気中の14Cの濃度は常に一定とは限らないので、この測定法ではどうしても誤差が生じてしまいます。最近では1979年に提案されたAMS法(Accelerater Mas Spectrometry、加速器質量分析法)の採用で高精度化した14C年代を、さらに年輪年代測定法などの確実な方法によって補正する研究が進んでいます。こうした方法によると、縄文時代の開始期は約1万6,500年前に遡るといいます。しかし、従来の定説からかけはなれ た古い年代なので、この補正年代を認めない研究者もいます。 なお、○○年前というのは、1950年を起点としてB.P.(Before Present)という記号を用いて示しています。 |
●縄文人の生活と信仰● |
① 縄文時代はまだ獲得経済が中心
縄文時代の人びとは、新しい環境に対応しました。とくに植物性食料は重要です。前期以降にはクリ・クルミ・トチ・ドングリなどの木の実やヤマイモなどを採取するばかりでなく、クリ林の管理・増殖(クリはアク抜きの必要がなく美味の上、建築材や薪としても利用されました。青森県の三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき)ではクリのDNAを研究することによって、クリ林を大規模に管理していたことがわかりました)、ヤマイモなどの半栽培、さらにマメ類・エゴマ・ヒョウタンなどの栽培もおこなわれていたようです。また一部に、コメ・ムギ・アワ・ヒエなどの栽培もはじまっていた可能性が指摘されています。土掘り用の打製の石鍬(いしくわ)、木の実をすりつぶす石皿(いしざら)やすり石なども数多く出土していますが、本格的な農耕の段階には達していませんでした。
狩猟には弓矢が使用され、落し穴やわななどもさかんに利用されました。これらは、環境の温暖化にともなって登場した足のはやい中小動物を捕獲するために、工夫されたものです。狩猟のおもな対象はニホンシカやイノシシなどでした。
また海面が上昇する海進の結果、日本列島は入江の多い島国になりました。その結果、漁労が発達しました。今も各地に縄文時代の貝塚(かいづか)が数多く残っています。
貝塚からは、釣針(つりばり)・銛(もり)・やすなどといった骨角器(こっかくき。シカなどの骨や角で作られた道具)とともに、石製や土製の錘(おもり)が出土します。これらは漁網につけて使用されました(また、編み物をする際の錘としても使用されました)。石錘(せきすい)・土錘(どすい)の存在は、網を使用した漁法がさかんにおこなわれていたことを示しています。
また、丸木舟(まるきぶね)も各地で発見されており、伊豆大島や伊豆諸島の南端に位置する八丈島にまで縄文時代の遺跡がみられます。これは、縄文人が丸木舟を用い、外洋にまで乗り出していたことを物語っています。
② 住居の中はせまかった
食料の獲得法が多様化したことによって、人びとの生活は安定し、定住的な生活がはじまりました。
彼らは地面を掘りくぼめ、その上に屋根をかけた竪穴住居(たてあなじゅうきょ)を営みました。住居の中央には炉(ろ)が設けられており、炊事をともにし、同じ屋根の下に住む一世帯の住まいであったことを示しています。
炉の役割は炊事以外にもいろいろありました。寒冷な時期、火で暖をとることはもちろん、梅雨の頃は湿った地面を乾かす役割もあったでしょうし、夏場は煙でいぶすことにより蚊などを除去したことでしょう。竪穴住居に煙突はついていませんでしたが、屋内の煙は屋根のカヤの隙間を通って屋外に出て行きました。サンタクロース以外、困る人はいなかったようです。
屋内は案外狭いものでした。姥山貝塚(うばやまかいづか。千葉県)は、今から約4500年前の縄文中期の遺跡ですが、ここから縄文時代の一世帯家族がタイムカプセルとなって発見されています。6畳ほどの広さの竪穴住居跡から、三世代5体(老女1、成人男2、成人女1、未成年1)の人骨が発見されました。フグの骨が出土するので、おそらくはフグ毒による一家全滅と推測されます。その死の原因がわからない周辺住民から気味悪がれたため、埋葬されずにそのまま放置されたのでしょう。この遺跡を見てみると、炉の面積を差し引いて、一人あたり畳一枚ほどの面積が割り振られていたようです。狭くとも支障がなかったのは、昼間や狩猟・採集・土器作りなど屋外作業が主で、屋内は雨の日や夜をともに過ごすためだったからでしょう。
現在のところ、最古とされる竪穴住居は、はさみ山遺跡(大阪府藤井寺市)で確認されています。この遺跡は縄文時代より古い、旧石器時代後期のものです。その後も長く、竪穴住居は人々の住居として使用されました。東日本では、10世紀まで使用が続きました。
③ 集落は小規模
集落は日当りがよく、飲料水の確保にも便利な水辺に近い台地上に営まれました。それは広場を囲んで数軒の竪穴住居が環状に並ぶものが多く、住居だけではなく、食料を保存するための貯蔵穴群や墓地などがありました。さらには三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき。青森県)のように大型の竪穴住居がともなう場合もありました。大型竪穴住居は、集合住宅か集会場だったのかも知れません。
これらのことから、縄文時代の社会を構成する基本的な単位は、4~6軒程度の世帯からなる20~30人ほどの集団であったと考えられます。
④ 集団間の交流は広範囲
こうした集団は近隣の集団と通婚し、さまざまな情報を交換しあったことでしょう。また黒曜石(こくようせき)やサヌカイトなど石器の材料や、ひすい(硬玉)などの装身具の材料の分布から、かなり遠方の集団との交易もおこなわれていたことが知られています。
「黒く光り輝く石」という意味の名をもつ黒曜石は、二酸化珪素(にさんかけいそ)を多く含む火山岩質マグマが急冷されることによってできた、いわば天然のガラスです。うち欠くと非常に鋭利な切り口を示し、石器の原材料として使用されました。産出地が限られており、北海道の白滝や十勝岳(「十勝石(とかちいし)」)、長野県の和田峠、大分県の姫島、熊本県の阿蘇山など、特定の地域でしか産出しません。
これら産地の中では、長野県の和田峠が最も有名です。和田峠は国内最大級の黒曜石産地であり、ここを中心に半径200キロメートル以上もの広範囲に、和田峠産の黒曜石製石器が分布しているのです。活発な交易のあったことが想像できますね。
余談ですが、江戸時代に書かれた『採薬使記(さいやくしき)』という本は、和田峠で産する黒曜石を「星石」と記述しています。和田峠の黒曜石産出地には、星ヶ塔(ほしがとう)・星ヶ台(ほしがだい)・星糞峠(ほしくそとうげ)などの「星」がつく地名が多く見られます。昔の人のネーミング・センスには、何となくロマンチックなものを感じますね。
| ◆ 星 石 『採薬使記(さいやくしき)』は享保頃(1716~1736年)の内容を記載したものとされます。阿部照任(あべてるとう)と松井重康(まついしげやす)という二人の人物が、幕命を拝して諸国の薬効ある動植鉱物等の探索にあたりました。彼らを採薬使といいました。彼らからの聞き書きを、地方別に配列したものが本書です。 本書には、和田峠で産する「星石(=黒曜石)」についての記載があります。 「○信州之部 照任曰(いわく)、信州和田峠ト云(い)フ所ニ、星石ト云フ物アリ、其(その)色黒ク シテ、水晶ノ 如(ごと)ク、透(す)キ、其中ニ白キ星ノ形アリ 光生(こうせい。後藤光生)按(あん)スルニ是レ西国ニテ、黒水晶ト云フ石アリ、 此(この)類ナルヘシ」 本書によると、「星石」の名称は、その中に「星ノ形」が透けて見えるからだといいます。おそらく、鉱物の結晶などの、内包物のことをいっているのでしょうね。 なお、和田峠の黒曜石は、建築用・園芸用のパーライトに加工されて、現在でも利用されています。 【参考】 ・早稲田大学収蔵本『採薬使記』による。次のHPを参照してください。 〔http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ni01/ni01_00790/ni01_00790.pdf〕 |
サヌカイト(讃岐石(さぬきいし))は、讃岐国(現在の香川県の旧国名)で多く見つかることからのネーミングです。ガラス質の安山岩で、たたき合わせるとカーンカーンという金属音がするので、カンカン石の別名があります。大阪府と奈良県の境にある二上山(にじょうさん。『万葉集』では「ふたかみやま」)が主産地として知られています。サヌカイトは石器の材料として使用され、近畿地方から瀬戸内地方にかけて分布しています。
ひすいは緑色をした石で、軟玉(なんぎょく。ネフライト)と硬玉(こうぎょく)があります。現在でも宝石として珍重されているのは、後者の硬玉です。硬玉は、新潟県姫川(ひめかわ)流域でしか産出しないのですが、遠く青森県の三内丸山遺跡からも、姫川産の硬玉製装身具が出土しています。
人びとは集団で力をあわせて働き、彼らの生活を守りました。男性は狩猟や石器づくり、女性は木の実とりや土器づくりにはげみ、集団には統率者はいても、身分の上下関係や貧富の差はなかったと考えられています。それは、一般の竪穴住居間には大きさの差があまり見られず、共同墓地に葬られた人々にほとんど副葬品を伴わないことからも、推測されましょう。
⑤ 信 仰
《 アニミズム 》
縄文時代は獲得経済の段階にあったため、自然の恵みに依存する受動的な生活を縄文人たちに強制しました。そのため彼らは、自然界の霊威を意識せざるを得ませんでした。あらゆる自然物や自然現象に精霊の存在を信じたのです。これをアニミズム(精霊崇拝)といいます。
アニミズムはラテン語のanima(息、魂、の意)が語源で、英語のanimalやanimationもこれに由来します。animalは「息をするもの」から、動物の意味となりました。一方、動詞のanimate(生命を吹き込む)の名詞形がanimation。「あたかも生き物のように動く絵=動画」という意味ですね。
《 石棒(せきぼう)・土偶(どぐう) 》
縄文時代の遺物には、彼らが呪術によって災いをさけ、豊かな収穫を祈ったと思われる証拠が数多く見られます。たとえば、こうした呪術的風習を示す遺物に、男性生殖器を表現したと推測される石棒や、女性を形どった土偶などがあります。
特に土偶は、顔がハート型、ミミズク型、遮光器型(しゃこうきがた。イヌイットなどが紫外線から目を守るためにかけるサングラスのようなもの)と、バラエティーに富んでいて、見ているだけであきることがありません。
これらの土偶は、乳房や臀部(でんぶ)、妊娠した腹部など女性的特徴を誇張したものが多いので、女性の生殖力を神秘と感じた縄文人たちが、収穫の恵みを祈って作った女神像ではないかと考えられています。
また、土偶の多くはわざとこわされています。これは、悪い部位の治癒(ちゆ)を祈って、このようにしたのだといわれています。
土偶は、縄文後期・晩期に東日本を中心にたくさん作られましたが、次の弥生時代になると急速に姿を消していってしまいました。
《 抜歯(ばっし) 》
現在は見られない風習に、抜歯があります。抜歯は縄文時代の中ごろからさかんに行われました。これは、通過儀礼(イニシエーション)の一種と見られます。成人式の際などにおこなわれたものでしょう。
また、同じく歯を加工したものに、縄文晩期に特有の叉状研歯(さじょうけんし)があります。東海から近畿地方に分布しており、集団中の一部の人々にしか見られません。おそらくは、呪術師か種族の有力者、もしくは集団の代表者・指導者などに施された標識だったのでしょう。
《 屈葬(くっそう) 》
死者の多くは、共同墓地に、屈葬という形で埋葬されています。屈葬というのは、死者の手足を折りたたんだ状態で埋葬するものです。その中には、石を抱かせたり(抱石葬(ほうせきそう、だきいしそう)といいます)、甕(かめ)をかぶせたり(被甕葬(ひようそう)といいます)するなど、変わった葬り方をするものも見られます。
しかし、なぜ屈葬にしたのか、その理由はよくはわかっていません。コンパクトに人体を折りたたむことによって、埋葬の際の土を掘る労力を節約したのでしょうか。胎児と同じ姿をさせることによって、大いなる自然にかえす呪術だったのでしょうか。それとも、死者の霊が生者に災いを及ぼすことのないように、死者の復活を妨げるのが目的だったのでしょうか。時に、その上に石が置かれることがありますが、それは、死者の霊が悪さをしないようにするための封印だったのかもしれません。
| ◆貝 塚 貝塚は人びとが食べた貝の貝殻などの捨てたものがたい積して、層をなしている遺跡です。土器・石器・骨角器などが出土するほか、貝殻にふくまれるカルシウム分によって保護された人骨や獣・魚などの骨が出土し、その時代の人びとの生活や自然環境を知るうえで重要な資料となっています。 なお、日本の近代科学としての考古学は1877(明治10)年にアメリカ人動物学者エドワード=シルベスター=モースが、東京 にある大森貝塚を発掘調査したことにはじまりました。 【参考】 ・E・S・モース著、近藤義郎・佐原真編訳『大森貝塚』1983年・岩波文庫 |