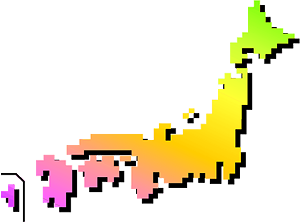●旧石器時代人の生活● |
① 人類の文化は道具で分ける
-「旧石器→新石器→青銅器→鉄器時代」-
人類の特徴は4つあります。第1に直立歩行(ちょくりつほこう)、第2に火の使用、第3に言語の使用、そして第4に道具の製作です。人間の骨は溶けやすいので、古い人骨が現在にまで残るとは限りません。骨が見つからなくては、直立歩行をしたのか、言語を使用できるほど脳が発達していたのかは、わかりませんね。
フランクリンは「人間は道具を作る動物である」といみじくも言いました。ある地層を発掘した場合、たとえ人骨が見つからなくても、石器(=人間が作った道具)が出土すれば、その時代に人類がいた証拠になります。
ですから遺物や遺跡などから人間の歴史を研究する考古学では、道具を研究することはたいへん重要です。使用された道具(利器)の材質で、人類の文化を「石器時代→青銅器時代→鉄器時代」と区分しますし、石器時代はさらに製作技法の違いによって、打ち欠いただけの打製石器のみを使用した旧石器時代(主に更新世)と、石器を磨いて仕上げた磨製石器が出現する新石器時代(主に完新世)とに時代分けがされています。
日本列島の場合は、縄文時代までが石器時代です。しかし、それに続く弥生時代には青銅器とともにすでに鉄器があるので鉄器時代であり、青銅器時代がありません。つまり、日本列島の場合は「旧石器時代→新石器時代(縄文時代)→鉄器時代(弥生時代)」となるのです。
②「岩宿(いわじゅく)」の発見
―更新世の地層から打製石器(旧石器)が出土―
さて、かつて日本列島には旧石器時代の遺跡は存在しないと考えられていました。ところが、この考古学界の常識は、戦後まもない頃、相沢忠洋(あいざわただひろ。1926~89)という一青年によってくつがえされました。彼は、群馬県新田郡笠懸村(ぐんまけんにったぐんかさがけむら。現、みどり市)の岩宿(いわじゅく)という場所で、関東ローム層(更新世に降り積もった火山灰土で、関東地方では俗に「赤土(あかつち)」と呼ばれています)の中から、黒曜石(こくようせき)製の打製石器を発見したのです。人類が存在しないはずの更新世の地層から、人類がつくった打製石器(旧石器)を発見した感動は、相沢さんの著書『「岩宿」の発見』の中に生き生きと描かれています。
そして1949(昭和24)年、明治大学による岩宿遺跡の学術調査がおこなわれ、更新世地層から打製石器が出土することが確かめられました。「更新世の日本列島に人類が存在した」ことが、紛れもない事実であると確認されたのです。これ以後、日本各地で更新世の地層からの石器発見があいつぎ、「日本にも旧石器時代の文化が存在した」ことが明らかになりました。
| ◆旧石器時代遺跡ねつ造事件 2000(平成12)年11月、旧石器時代前期とされていた上高森遺跡(宮城県)のねつ造が発覚しました。発掘調査担当者の一人で東北旧石器文化研究所の副理事長が、自ら持参した石器をひそかに更新世の地層に埋めている姿が『毎日新聞』の記者にスクープされたのです。その後の調査・検証によって、上高森遺跡をはじめ、彼が発掘に関わった旧石器時代前期・中期とされる遺跡のすべてがねつ造として否定されました。旧石器時代前期・中期の遺跡名を載せた教科書や歴史書は、訂正や回収されるという騒ぎになりました。 この結果、旧石器時代の確かな遺跡は、今のところ、約3万5,000年前以降の後期旧石器時代のものだけとなっているのです。 【参考】 ・河合信和『旧石器遺跡捏造』2003年、文藝春秋(文春文庫) |
③ 旧石器時代の人びとは狩猟と採取の生活が主
この時代の人びとは、狩猟と植物性食料採取の生活をおくっていました。こうした生活の仕方を「獲得経済」といいます(農耕牧畜が開始されると「生産経済」といいます)。 狩猟にはナイフ形石器や尖頭器(せんとうき)などの石器を棒の先端につけた石槍(いしやり。せきそう)を用い、ナウマンゾウ・オオツノジカ・ヘラジカなどの大型動物を捕えました。
石器の発達は、技術の進歩を示します。簡単な石器から精巧な石器へと発達し、動物を捕獲する際の殺傷力が強化されていきました。
次に、旧石器の種類と用途について見ておきましょう。
④ さまざまな旧石器
《 石斧(せきふ) 》
直接手に持ったり、短い棒の先にくくりつけて使用しました。木材の伐採や加工、土掘りなど、多目的に使用されました。その形状から楕円形(だえんけい)石器、敲(たた)いたり打ったりする石器なので敲打器(こうだき)、直接手に持ったり柄(え)をつけて使用する槌(つち)や斧(おの)なので握り槌(にぎりつち)・握り斧(にぎりおの)などとも呼ばれています。英語のハンド=アックスの訳語です。
《 ナイフ型石器 》
直接手に持つか、柄をつけてナイフのように使用しました。主な用途は切断です。別名を石刃(せきじん)といい、英語のブレイドの訳語です。
《 尖頭器(せんとうき) 》
木の葉のような形をしていますが、長い棒の先にくくりつけて、槍や投げ槍として使用しました。つまり、主な用途は刺突(しとつ)です。「先が尖(とが)っている石器」という意味の尖頭器(せんとうき)の別名があります。英語のポイントの訳語です。
また旧石器時代の終りごろには、細石器(さいせっき。マイクロリス)とよばれる小型の石器が出現しています。細石器とは、長さ3~4センチの小石器(細石刃)を、木や骨などでつくった軸の側縁の溝に何本か並べて埋めこんで用いる、組み合わせ式の石器です。
この細石器文化は、中国東北部からシベリアにかけて著しく発達したもので、北方から日本列島におよんだものです。なお、旧石器時代から新石器両時代へと移行する時期に細石器が登場しますが 、この時代を「中石器時代(ちゅうせっきじだい)」とよぶ人もいます。
| ◆先土器文化(せんどきぶんか) 更新世の地層から打製石器は出土するものの、土器が見つかりませんでした。そこで、土器の発見に先立つ文化というので「先土器文化」、土器がないというので「無土器文化」、縄文時代より以前の文化なので「先縄文文化」などと呼んでいました。現在は「旧石器文化」という呼び方に統一されています。 ただし、「旧石器文化」の次を「新石器文化」でなく、「縄文文化」と呼ぶのでは名称のつけ方に一貫性がない、という意見があります。そこで「岩宿文化」の名称を提唱する人もいます。 |
⑤ 移動生活と住居
旧石器時代の人びとが調理した跡と見られる礫群(れきぐん。集石)などは発見されますが、生活の痕跡を示す遺跡の発見は,たいへん少ない状況です。それは、一カ所での定住期間が短く、食料を求めて、小集団で絶えず移動を繰り返していたからだと考えられます。このため、住居も簡単なテント式の小屋だったり、一時的に洞穴を利用したりすることもありました。