28.戦国大名の登場
永禄8年(1565)この多聞山城を訪問したイルマンのルイス=フロイス=デ=アルメイダは、つぎのように述べている。
「この城(多聞山城)は、日本においてもっとも美麗なるものの一つにして、ダションドン(松永弾正久秀)という人の城である。この人は、今七カ国を領するに過ぎないが、日本全国においてもっとも尊敬され、また全権を持っている三好長慶(みよしながよし)と将軍義輝の臣下である。しかし久秀は、才智あり、長慶や義輝に服従するがごとくでありながら、まるで長慶や義輝を臣下のごとくにあつかい、自分の思うままに長慶や義輝を動かしているほどである」
かれが主家の打倒を企てはじめていたのがいつのころかは断定しがたい。しかし永禄6年(1563)には長慶の子義興(よしおき)を毒殺し、同7年には長慶の弟安宅冬康を讒(ざん)してこれを殺させた。しかもついで長慶が死ぬと将軍義輝をも殺している。
久秀のこの急速な進出に対しては、三好三人衆とよばれた三好長縁(ながやす)・同政康・岩成友通(いわなりともみち)らが反撃した。それとからんで、久秀に従っていた大和の国人筒井順慶(つついじゅんけい)も離反した。そんなことから、かれは三人衆の陣した東大寺大仏殿に火を放ち、焼き払う暴挙にでた。東大寺を焼き払ったのは平家の一門重衡(しげひら)以来のことである。世に久秀の三悪事というのは、三好家への反攻、大仏の焼却、将軍の謀殺をいうのである。
しかし、久秀はその悪名にもかかわらず、やはり長慶の方式を踏襲した旧型の人物であり、戦国大名らしい領国経営も示さないまま、やがて織田信長に圧倒されてゆく。 ( 中略 )
中央の政局の混迷は、けっきょく信長の進出をまたねば解決されなかったのである。
(杉山博『日本の歴史11・戦国大名』1974年、中公文庫、P.279~281)
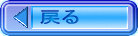


① 群雄割拠の時代の幕開け
応仁の乱によって幕が開いた戦国時代(通常は1467年から、織田信長が上洛した1568年までの間を指します)に、自らの力で分国をつくりあげ、独自の支配をおこなう新たな地方権力者が登場しました。彼らを、戦国大名といいます。
戦国大名の出自はさまざまです。守護(武田・今川・佐竹・大内・大友・島津など)、守護代(上杉・織田・朝倉など)、国人(伊達・徳川・浅井・小早川・毛利・竜造寺・長宗我部など)、その他、にほぼ大別できます。
東北地方では国人や土豪たちが割拠していました。中でも最上(もがみ)・伊達(だて)・蘆名(あしな)の各氏が有力になっていきました。
関東地方では、享徳の乱(きょうとくのらん。1454~82)(注)を機に、鎌倉公方が分裂しました。足利持氏の子成氏(しげうじ。1434?~97)を古河公方(こがくぼう)、将軍義政の異母兄政知(まさとも。1435~91)を堀越公方(ほりごえくぼう)といいます。また、関東管領の上杉家も、山内(やまのうち)・扇谷(おうぎがやつ)の両上杉家に分かれて争っていました。
(注)足利成氏は、自殺した足利持氏(永享の乱で幕府によって討滅)の末子で、鎌倉公方を継ぎました。しかし、上杉氏と不和になった成氏は、関東管領上杉憲忠を暗殺してしまったため、幕府軍の追討を受けることになります(享徳の乱)。幕府は足利政知を鎌倉公方として派遣し、下総国古河(現茨城県古河市)に逃れた成氏 (古河公方)に対抗させようとしました。しかし、政知は関東諸将の支持を得られず、伊豆の堀越にとどまったまま鎌倉に入ることができませんでした(堀越公方)。
この混乱に乗じて、15世紀末に堀越公方を滅ぼして伊豆を奪い、ついで相模に進出して小田原を本拠としたのが、伊勢宗瑞(いせそうずい。伊勢新九郎。1432~1519)です。この系譜の戦国大名は、宗瑞の子氏綱(うじつな)の時代から北条氏を称しました。そこで初代の伊勢宗瑞は出家して早雲庵宗瑞(そううんあんそうずい)と号したので、後世の人々は彼を北条早雲(ほうじょうそううん)とよぶことになります。鎌倉時代の北条氏と区別するために、戦国時代に小田原を根拠にした早雲・氏綱(うじつな。1487~1541)・氏康(うじやす。1515~71)・氏政・氏直5代にわたる北条氏を「後北条氏(ごほうじょうし)」と称します。早雲の子氏綱・孫氏康の時に、北条氏は関東の大半を支配する大大名になりました。
北陸地方では、越後の上杉謙信(うえすぎけんしん。長尾景虎(ながおかげとら)。1530~78)、甲斐の武田信玄(たけだしんげん。武田晴信(たけだはるのぶ)。1521~73)が有力でした。両者は5回にわたって信濃国の川中島(かわなかじま。千曲川(ちくまがわ)と犀川(さいかわ)に挟まれた地域)で争いましたが(川中島の戦い。1553~64)、とうとう勝敗は決しませんでした。
中国地方では、大内義隆(おおうちよしたか。1507~51)が家臣の陶晴賢(すえはるかた。1521~55)に国を奪われ、さらに厳島の戦い(いつくしまのたたかい。1555)で毛利元就(もうりもとなり。1497~1571)がこれに代わりました。中国地方を制覇した毛利氏は、一族の小早川(こばやかわ)氏・吉川(きっかわ)氏と連携した毛利両川(もうりりょうせん)体制を築きました。
四国地方では、土佐の豪族長宗我部元親(ちょうそかべもとちか。1538~99)が有力でした。のち四国全土を支配する戦国大名に成長しました。
九州地方北部では豊後の大友氏、肥前の竜造寺(りゅうぞうじ)氏の台頭が著しく、九州地方南部では薩摩の島津氏が勢力を拡大していました。

② 戦国大名の分国支配
《 寄親(よりおや)・寄子(よりこ)制 》
戦国大名は、国人や地侍を家臣団に組み入れていきました。その際、国人層は知行地を与えられて給人(きゅうにん)と呼ばれる上級家臣団を構成し、地侍は加地子(かじし。年貢の中間得分)取得権を保障されて、足軽(あしがる)などの下級家臣団を構成しました。
戦国大名は家臣団を、擬制的(ぎせいてき。なぞらえること)な親子関係の仕組みを使って管理しました。上級家臣を寄親、下級家臣を寄子として、寄親に複数の寄子を預ける形をとったのです。これを寄親・寄子制といいます。こうしたを形をとることによって、鉄砲隊や長槍隊などの新兵器を使う集団戦も可能になりました。
上級家臣(国人層) 下級家臣(地侍層)
(平時)戦国大名 - 寄親(一族衆・譜代衆・国衆などと呼ばれる給人) - 寄子(足軽)
↓ ↓ ↓
(戦時)戦国大名 - 軍奉行(いくさぶぎょう)- 組頭 - 組(鉄砲隊・長槍隊など軍奉行の統率のもと戦闘)
《 分国法(ぶんこくほう) 》
戦国大名は家臣団統制や領国支配のために、分国法(戦国家法)を制定しました。分国法は御成敗式目をはじめとする幕府法を継承した法とともに、さまざまな法を吸収したいわば中世法の集大成という性格を持っていました。しかし、なかには、新たな権力者としての戦国大名の性格を示す特徴的な法も多く見られます。
たとえば、武田氏の分国法『甲州法度之次第(こうしゅうはっとのしだい。別名信玄家法)』などには、喧嘩両成敗(けんかりょうせいばい)の規定があります。
喧嘩の事、是非に及ばず成敗を加ふべし。但し、取り懸ると雖(いえど)も、堪忍(かんにん)せしむるの輩(やから)に於(おい)ては、罪科に処すべからず。(『甲州法度之次第』)
これは、喧嘩(決闘・私闘)をした者はその理由のいかんを問わず、双方を死罪に処するというものです。従来は、紛争解決手段の一つとして喧嘩は慣習的に認められていました。喧嘩両成敗法は、そうした私闘による個人間の紛争解決手段を全面否定し、すべての紛争解決を大名の裁判に一本化することを宣言したものです。この姿勢は、後の豊臣秀吉の惣無事令(そうぶじれい。豊臣平和令)にも継承されていきます。
集団戦が戦闘の主流になってくると、城下町に家臣団を常住させておく必要に迫られました。分国法ではありませんが、越前朝倉氏の『朝倉孝景条々(あさくらたかかげじょうじょう)』は、朝倉氏の城下町一乗谷(いちじょうだに)への家臣団集住を令したものとして有名です。
朝倉が館之外(あさくらがたちのほか)、国内□(にカ)城郭(じょうかく)を為構(かまえさせる)まじく候。惣別(そうべつ。全て)分限(ぶげん。身分・経済力のこと)あらん者、一乗谷へ引越(ひっこし)、郷村(ごうそん)には代官計(ばかり)可被置事(おかるべきこと)。(『朝倉孝景条々』)
こうして家臣たちは、普段は農民、戦時は戦闘員という二足の草鞋を履くことが許されなくなっていきました。そこで、城下町に常住する武士という消費者集団と、彼らを養う食料生産者である農民身分を分離する必要が出てきました(兵農分離)。こうした事態が、近世の身分制へとつながっていきます。
また、駿河(するが)・遠江(とおとうみ)の戦国大名今川氏の分国法『今川仮名目録(いまがわかなもくろく)』では、私婚を禁止しています。婚姻関係を結ぶことが、家同士の同盟の意味を持っていたからです。
駿・遠両国(すん・えんりょうごく。駿河・遠江の両国)の輩、或(あるい)はわたくしとして他国より嫁をとり、或は婿(むこ)にとり、娘をつかはす事、自今(じこん)已後(いご)停止(ちょうじ)し畢(おわん)ぬ。(『今川仮名目録』)
その他、領民の逃散・一揆の禁止、嫡子単独相続の奨励、共犯者を処罰する連坐制、個人の罪を一族にも及ばせて処罰する縁坐制など、特徴的な条文が分国法には多く見られます。
《 指出(さしだし)検地と貫高制 》
戦国大名は、土地・農民を直接支配しようとしました。検地によって収入を把握し、家臣に与えた土地の収入額に応じて軍役を負担させようとしました。
ただし戦国大名の検地は、後の太閤検地と異なって、統一基準によって領内を測量したものではありませんでした。家臣団・寺社などに自己申告させたのです。自己申告書を提出させる形式(指出(さしだし))による検地だったので、これを指出検地(さしだしけんち)といいます。
家臣たちの所領は、それぞれの所領からの年貢・公事・夫役などの得分を銭に換算した形で表示されました。これを貫高(かんだか)といいます。戦国大名は、貫高という基準によって家臣たちに、それぞれの貫高に見合った軍役を負担させました。この仕組みを貫高制といいます。なお、貫は銭を数える時の単位です(銭は1枚1文、1,000文を1貫文といいます)。
《 富国強兵策 》
戦国大名は、周囲の戦国大名たちに侵略から分国を守り、あわよくば勢力拡大を狙って、富国強兵に努めました。
城下町を建設して家臣団・商工業者を集住させ、その繁栄をはかりました。たとえば、城下町の商業を振興するために、楽市令(らくいちれい)や撰銭令(えりぜにれい)を出し、関所を撤廃しました。
楽市令は座の特権を否定したもので、自由な商取引を保証したものです。撰銭令は良銭・悪銭の交換比率を定め、また悪銭の受取忌避を禁止して、スムーズな貨幣流通を促した法令です。また、この時代の関所は通行税(関銭)徴収が主目的でした。関所を撤廃することによって、物資流通が阻害されなくなりました。
治水事業に努めた大名もいます。甲斐の武田氏は土木技術にすぐれ、釜無川(かまなしがわ)と御勅使川(みだいがわ)に築いた堤防は「信玄堤(しんげんづつみ)」と呼ばれています。
また、鉱山開発にも努めました。有名な鉱山に佐渡金山(上杉氏)、甲斐金山(武田氏)、石見銀山(いわみぎんざん。大内氏、尼子氏、毛利氏)などがあります。
この中で特に重要な鉱山は、石見銀山です。16世紀初頭に、博多商人の神谷寿禎(かみやじゅてい)が明の製錬技術である灰吹法(はいふきほう)をわが国にもたらすと石見銀山の産額が一挙に増加しました。近世初期には、世界に流通した銀の3分の1が日本産であり、そのほとんどが石見銀山のものだったと言われています(注)。
(注)島根県ホームページ http://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/ginzan/outline/(2015年2月19日参照)

① 都市の発展
室町時代には、城下町・門前町・寺内町・港町・宿場町など、各種の都市が発展しました。
《 城下町 》
戦国時代に特に発展した都市は、城下町です。大名たちは、最初は攻めるに難く守るに容易な山上に城郭を築きました。山城(やまじろ)です。
しかし、武士団・商工業者の城下町集住を促し、産業・経済・流通等を振興するなど領国経営上の利便性・必要性から、山城は次第に平野に移行していき、平山城(ひらやまじろ)・平城(ひらじろ)を取り囲むように城下町が発達していきました。
北条氏の小田原、今川氏の駿府(現静岡市)、上杉氏の春日山(かすがやま。現上越市)、大友氏の豊後府内(現大分市)、島津氏の鹿児島などがあります。
《 門前町と寺内町 》
寺社の門前に発達した文化的・経済的都市を門前町(もんぜんまち)といいます。門前町には、寺社の隷属民や寺社経済を支える職人・商人が集住しました。また、中世の経済発展にともなって、寺社参詣者が増加すると、門前町の発展が加速されました。
おもな都市に、伊勢神宮内宮(ないくう)・外宮(げくう)の門前に発達した宇治・山田、興福寺等多くの諸寺社をかかえる奈良、「牛に牽(ひ)かれて善光寺参り」の諺で有名な善光寺の門前町長野などがあります。
これに対し、政治的・軍事的都市ともいうべきものが、寺内町(じないまち、じないちょう)です。寺内町は、おもに一向宗の道場・寺院を中心に形成された都市で、門徒の商工業者などが集住しました。周囲には城下町のような濠・土塁などの防御施設が施され、領主から諸役免除の特権を得るなど、自由都市的な性格も強かったと考えられています。
山科(やましな)・石山(本願寺)、今井(称名寺)、富田林(とんだばやし。興正寺)などがあります。
《 港町と宿場町 》
商品経済の発展による遠隔地間の取引きの増大、地域内の流通の活発化にともなって、港町・宿場町が発達しました。
港町は年貢米や商品の積み卸し、陸上交通との結節点に発達しました。坊津(ぼうのつ)、博多、尾道(おのみち)、堺、小浜(おばま)、大津、桑名などがあります。
宿場町は東海道や山陽道など陸上交通上、地域の商品流通の結節点に発達しました。なかには、北条氏など戦国大名が伝馬制度の整備とともに宿場町を設定する場合もありました。

② さまざま自由都市
この時代、自治的町政が運営された自由都市が各所で見られました。有名な自由都市として博多、堺、京都などがあります。
《 博 多 》
博多は、日明・日朝・南海各貿易港として繁栄しました。大内・大友両氏の二元的な支配が行われていましたが、大内氏の滅亡後は大友氏の支配下にありました。博多では、12人の年行司(ねんぎょうじ)とよばれる代表者によって、町政が運営されていました。
《 堺 》
堺は京都・奈良の外港でして、また貿易港として繁栄しました。戦国時代には町を取り囲む環濠を開削し、軍事的な機能を備えた環濠集落でした。町政は、富裕な商人層から選ばれた36人の会合衆(かいごうしゅう、えごうしゅう)によって運営されており、治安もよく守られていました。また、堺の町は一種のアジール(避難所)としての機能も有していたらしく、この町の中にいる限りは、世俗上の敵対関係も問題にされなかったといわれています。
そうした堺の自由な空気を、宣教師のガスパル=ヴィレラは次のように描写しています(『耶蘇会士日本通信』)。
堺の町は甚(はなは)だ広大にして、大なる商人多数あり。此(こ)の町はベニス市の如(ごと)く執政官(しっせいかん)に依(よ)りて治めらる。(1561(永禄4)年8月17日書簡)
日本全国当堺の町より安全なる所なく、他の諸国に於(おい)て動乱あるも、此(この)町には嘗(かつ)て無く、敗者も勝者も、此町に来住すれば皆平和に生活し、諸人相和し、他人に害を加うる者なし。市街に於ては嘗(かつ)て紛擾(ふんじょう)起ることなく、敵味方の差別なく皆大なる愛情と礼儀を以て応対せり。市街には悉(ことごと)く門ありて番人を付し、紛擾あれば直(ただち)に之(これ)を閉づることも一(ひとつ)の理由なるべし。紛擾を起す時は犯人其他(そのた)悉く捕えて処罰す。 (中 略) 町は甚だ堅固にして、西方は海を以(もっ)て、又他の側は深き堀を以て囲まれ、常に水充満せり。(1562(永禄5)年書簡)
《 京 都 》
京都では応仁の乱後、二条通りを境界にして、北にはおもに公家・武士の町である上京(かみぎょう)が、南にはおもに商工業者の町である下京(しもぎょう)が、それぞれ形成されました。
上京・下京それぞれの周囲には、堀や土塀の防御施設がぐるりと取り巻いています。これを構(かまえ)といいます。二つの町は、室町通りという南北にのびる一本の道路によってのみつながっていました。
下京では自治的組織が発展し、町掟を定めました。自治的組織を町(ちょう)といいます。町は、道路を挟んで向かい合う両側の家々(町屋(まちや))で構成される一区画(両側町(りょうがわちょう))をさし、数町で町組(ちょうぐみ)という共同体を構成しました。
町の構成員を町衆(ちょうしゅう)といいます。町衆は酒屋・土倉ら自営の商工業者が中心でした。町衆の中から月行事(がちぎょうじ。がつぎょうじ)が選出されて、行事を運営しました。応仁の乱で中断していた祇園祭(ぎおんまつり)が町衆によって再開され、町ごとに趣向を凝らし贅(ぜい)を尽くした山鉾(やまぼこ)が市中を巡行しました。
その他、中小都市で自治が行われた所としては平野(摂津)、桑名・大湊(おおみなと。伊勢)、堅田(かただ。近江)などが有名です。


