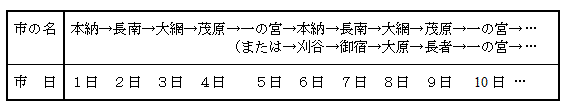27.幕府の衰退と庶民の台頭
「応仁丁亥ノ歳(ていがいのとし。1467年)天下大(おおい)ニ動乱シ、ソレヨリ永ク五畿七道悉(ことごと)ク乱ル。其起(そのおこり)ヲ尋(たずぬ)ルニ、尊氏将軍ノ七代目ノ将軍義政公ノ天下ノ成敗(せいばい)ヲ有道(うどう)ノ管領(かんれい)ニ任セズ、タダ御台所(みだいどころ。日野富子)或(あるい)ハ香樹院(きょうじゅいん)或ハ春日局(かすがのつぼね)ナド云(いう)、理非ヲモ弁(わきま)ヘズ、公事(くじ。裁判)政道ヲモ知リ給(たま)ハザル青女房(あおにょうぼう。若い未熟な女性)、比丘尼達(びくにたち)計(はから)ヒトシテ酒宴淫楽(しゅえんいんらく)ノ紛(まぎ)レニ申(もうし)沙汰(さた)セラレ ( 中略 )
若(も)シコノ時忠臣アラバ、ナドカ之(これ)ヲ諫(いさ)メ奉(たてまつ)ラザランヤ。然(しか)レドモタダ天下ハ破レバ破レヨ。世間ハ滅バゞ滅ビヨ。人ハトモアレ我身サヘ富貴ナラバ他ヨリ一段瑩羹様(かがやかんよう。栄えるよう)ニ振舞(ふるまわ)ント成行(なりゆき)ケリ。 (中 略)
サレバ大乱ノ起ルベキヲ天予(あらかじ)メ示サレケルカ、寛正六年(1465年)九月十三日夜亥ノ刻(いのこく)ニ、坤方(ひつじさるのかた。南西)ヨリ艮方(うしとらのかた。東北)ヘ光ル物飛渡(とびわた)リケル。 ( 中略 )
不計(はからざりき)万歳期セシ花ノ都、今何ンゾ狐狼(ころう)ノ伏土(ふしど。寝床)トナラントハ、適(たまたま)残ル東寺・北野サヘ灰土(かいど)トナルヲ。古(いにしえ)ニモ治乱(ちらん)興亡(こうぼう)ノナラヒアリトイエドモ、応仁ノ一変ハ仏法・王法トモニ破滅シ、諸宗皆悉(ことごと)ク絶(たえ)ハテヌルヲ、感歎ニ堪(た)ヘズ、飯尾彦六左衛門尉(いいお(いのお)ひころくざえもんのじょう)、一首ノ歌ヲ詠(えい)ジケル。
汝(なれ)ヤシル都ハ野辺(のべ)ノ夕雲雀(ゆうひばり)アガルヲ見テモ落(おつ)ルナミダハ 」 (『応仁記』)
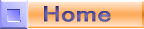
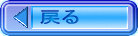


① 将軍権力の弱体化
義満の後継者4代将軍足利義持(あしかがよしもち。1386~1428)の時代は、比較的安定していました。1416(応永23)年に、鎌倉府の内紛に乗じて前関東管領の上杉禅秀(うえすぎぜんしゅう。氏憲(うじのり))が反乱を起こすという大事件が起こりますが、翌年には鎮圧されます(上杉禅秀の乱)。ただ、義持の頃には守護大名独立の気運が次第に高まり、幕政は管領の細川氏・畠山氏らに左右されるようになっていきました。こうした中で、将軍の後継者問題が持ち上がったのです。
義持が将軍職を退いたあと、義量(よしかず)が5代将軍となりましたが、早世してしまいます。後継者がいなかったため、将軍空位の時期が数年間続きました。そして、義持もまもなく他界してしまいます。
義持は将軍後継者を指名しないまま亡くなってしまいました。仮に後継者を指名したとしても、守護大名たちが「将軍として器量ある人物だ」と認めなければ、誰も新将軍に衷心から服属しないでしょう。そうした時代になっていたことを、義持は悟っていたのかも知れません。
義持には出家した4人の弟たちがいました。守護大名たちは、彼らの中から次期将軍を選ぶことにしました。この時、神前でのくじ引きという手段を選択します。神意に丸投げすることによって、お互いの腹の内の探り合いを避けようとしたのでしょう。
当たりくじは青蓮院義円(しょうれんいんぎえん)が引きました。還俗(げんぞく。僧侶から俗人にもどること)して義宣(よしのぶ)と名乗ります。しかし、音が「世忍ぶ」に通じて縁起が悪いというので、改名しました。これが6代将軍義教(よしのり。1394~1441)です。
義教は将軍権力の強化をはかって、専制的な政治を行いました。ただ、それが余りに露骨で容赦ないものだったため、ある人は「万人恐怖」とその日記に記すほどでした。
当時、鎌倉公方足利持氏(あしかがもちうじ。1398~1439)と関東管領上杉憲実(うえすぎのりざね。1410~1466)が対立していました。義教は、1438(永享10)年、関東に討伐軍を派遣し、翌39年、幕府に反抗的な足利持氏を滅ぼしました。これを、永享の乱といいます。義教はその後も有力守護を弾圧し続けます。
こうした中、「次は自分が将軍に討たれるに違いない」と疑心暗鬼になった播磨の守護大名赤松満祐(あかまつみつすけ。1373~1441)によって、1441(嘉吉元)年、義教は謀殺されてしまいます。
赤松満祐は、どうせ滅ぼされるのなら、将軍を道連れにしようと考えました。結城合戦(ゆうきがっせん。足利持氏の遺児を擁した結城氏朝軍との戦闘。1440~1441)の勝利を祝う宴会を催すとの名目で、将軍や有力守護大名を自宅に招き入れました。宴会の途中、突然障子を開けて飛び込んできた数人の武士に、あっけなく将軍は討たれてしまったのです。居並ぶ守護大名達は、よもや赤松一人でこんな大それたことをしでかしたのではあるまい、とこれまたお互い疑心暗鬼になり、赤松邸からほうほうの体で逃げ出しました。将軍暗殺後、てっきり一戦に及ぶと思っていた赤松満祐は、その場で諸大名に斬り殺されることもなく、ゆうゆうと播磨国に落ち延びていったのです(その後赤松は播磨にこもりますが、諸将に攻められて敗死しました)。
この将軍暗殺事件を嘉吉の変(1441)といい、その後赤松が幕府軍に滅ぼされるまでの一連の戦闘を嘉吉の乱といいます。伏見宮貞成(さだふさ)親王の『看聞日記(かんもんにっき)』は、将軍義教の死を評して、
将軍此(かく)の如(ごと)き犬死、古来その例を聞かざる事なり
(先例を聞いたことがない犬死である)
と冷たくつき放しています。また当時の落書(らくしゅ)。
田舎(いなか。鎌倉のこと)にも京にも御所(ごしょ)の絶え果てて
公方にことを欠きつ元年
(鎌倉公方足利持氏も京都の公方(将軍)足利義教もともに殺されて、公方に事欠く嘉吉元年で
あることよ、の意)
この嘉吉の乱以降、将軍の権威は大きく揺らいでいきました。
嘉吉の乱による政治的空白を狙い、足利義勝(あしかがよしかつ)の7代将軍就任に当たっての「代始めの徳政」を要求して、近江・大和・山城を中心に土一揆が起こりました。地侍が指導した数万人に及ぶ一揆の前に幕府は屈服し、初めて徳政令(嘉吉の徳政令)を発令します。
これ以後、徳政令や、債権の十分の一または五分の一の金額(分一銭(ぶいつせん))を幕府に納入すれば徳政令は適用されないとする分一徳政令(ぶいつとくせいれい)が頻発され、社会はますます混迷の度を深めていきます。

② 応仁・文明の乱(1467~1477)
応仁の乱は、将軍家や諸大名の相続争いに、細川・山名両氏の権力争いのからんだことが、そもそもの原因でした。
義教暗殺後、7代将軍となった義勝はわずか10歳で早世してしまいます。ついで、義勝の弟足利義政(あしかがよしまさ。1436~1490)が8代将軍に就任するものの、これまた14歳の若い将軍でした。
新将軍を後見する宿老たちには幕府主導の力がなく、母親や乳母(めのと)の政治介入を招きました。成人後も妻日野富子(ひのとみこ。1440~1496)の兄日野勝光(ひのかつみつ)、政所執事の伊勢貞親(いせさだちか)、僧侶などの政治介入を許してしまいます。
義政には、父親が守護大名に暗殺されたというトラウマがあったのでしょうか、隠遁生活にあこがれて政務を放棄し、趣味の世界に没入してしまいます。のちには、妻の富子に幕政の実権を握られてしまいます。
将軍権力の弱体化にともなって、有力守護大名や将軍家にあいついで内紛が起こりました。嫡子単独相続がはじまったこの時代、嫡子は庶子にくらべて絶対的に優位な立場となったため、嫡子の地位をめぐって争いが多くなりました。しかも、大名の家督の決定は、父親の意志だけで決定できなくなってきます。将軍の意向や、家臣たちの支持が家督決定に少なからぬ影響を持つようになってきたのです。
当時の嫡子単独相続では、「器量」ある人物が家督を相続すべきだという考えが支配的で、必ずしも長子が相続するとは限りませんでした。4代将軍義持が後継者を指名せずに亡くなったのも、自分が指名した人物を「器量」ある者だと守護大名達が認めなければ、彼らが素直に臣従しないだろうことを察していたからでしょう。そのため、家督争いはますます複雑化・熾烈化していきました。
家督争いは、まず管領家である畠山政長(はたけやままさなが。1442~1493)・義就(よしひろ(よしなり)。1437~1490)、斯波義廉(しばよしかど。1446?~?)・義敏(よしとし。1435?~1508)それぞれの間でおこりました。ついで将軍家でも、義政の弟義視(よしみ。1439~1491)と、義政の妻で子の義尚(よしひさ。1465~1489)をおす日野富子の間で家督争いがおこりました。これら有力諸家の家督争いに、当時幕府の実権を握ろうと対立していた細川勝元(ほそかわかつもと)と山名持豊(やまなもちとよ。また山名宗全(そうぜん)とも。「赤入道」とよばれました。1404~1473)が介入したため、争いは激化しました。ついに、1467(応仁元)年、戦国時代の幕開けとなる応仁・文明の乱が始まりました。
守護大名たちは、それぞれ東軍(細川方)と西軍(山名方)に分かれて戦いました。乱はおおよそ次のような対立関係でしたが、その時々の利害に応じて敵・味方が入れかわるという、節操のない戦闘でした。
| |
将軍家 |
畠山氏 |
斯波氏 |
支援者 |
| 東 軍 |
義 尚 |
政 長 |
義 敏 |
細川勝元 |
| 西 軍 |
義 視 |
義 就 |
義 廉 |
山名持豊(宗全) |
この間、政治担当者でもない女性たち(日野富子ら)が政治に口出しし、責任ある地位にある人々は政務を放棄して犬追物や笠懸などの遊興に明け暮れ、将軍は大酒を飲んでいるという有様。戦乱中であるにもかかわらず、「まるで天下泰平の時のようだ」だと、興福寺別当尋尊(じんそん)は皮肉っています。
天下公事(くじ)修り、女中御計(おんはからい)、公方(くぼう)は大御酒(おおごしゅ)、諸大名は犬笠懸、天下泰平の時の如(ごと)くなり。
将軍権威の失墜は誰の目にも明らかで、「日本国は悉(ことごと)く以(もっ)て御下知(ごけち)に応ぜざるなり(将軍の命令に誰も従わなくなった)」(『大乗院寺社雑事記(だいじょういんじしゃぞうじき)』)という状態に陥っていました。
11年間にも及んだ戦闘のため、主戦場となった京都は荒廃しきってしまいました。『応仁記』には飯尾彦六左衛門尉(いいお(いのお)ひころくざえもんのじょう)の作として
汝(なれ)や知る都は野辺(のべ)の夕雲雀(ゆうひばり)
揚がるを見ても落つる涙は
という悲嘆の一首が記載されています。
1477(文明9)年、戦いに倦んだ両軍の間で和議が結ばれ、応仁・文明の乱はやっと終戦を迎えることになりました。守護大名たちの多くは領国に下りました。しかし、争乱はその後も地域的な争いとして続けられ、全国的に広がっていきました。京都で守護大名たちが戦っていた留守中に、力をもった守護代や有力国人に領国の支配が移っているところもありました。この争乱により、有力守護が在京して幕政に参加する幕府の体制は崩壊しました。それと同時に荘園制の解体も進んだのです。

③ 下剋上の風潮(山城の国一揆、加賀の一向一揆)
守護大名が京都で戦いを繰り広げていたころ、守護大名の領国では、留守を預かっていた守護代や有力な国人が力をたくわえ、領国支配の実権を守護大名から奪い取っていきました。このように、実力によって下位の者がのし上がっていく現象を下剋上(げこくじょう)といいます。下剋上の風潮は、この時代、広く見られた現象でした。
たとえば、畠山政長・義就の両軍が戦闘を繰り広げていた山城地方では、1485(文明17)年、国人たちが中心になって、両畠山軍国外に退去させるという山城の国一揆がおこりました。15・6歳から60歳までの国人たちが集会し、両軍の撤退を要求したのです。さらに国人たちは、山城国を運営するための掟を決め、約8年間にわたる自治的支配を実現しました。中心となったのは、三十六人衆と呼ばれた南山城の国人たちでした。
また1488(長享2)年には、加賀の一向一揆が起こっています。そもそも北陸地方は、本願寺の蓮如(兼寿)の布教によって、浄土真宗が広まっていた地方のひとつでした。守護富樫政親(とがしまさちか1455~1488)の教団弾圧に反対して20万人もの浄土真宗門徒が蜂起し、政親がこもる高尾城を囲んで、自殺に追い込みました。その後門徒たちは、政親の代わりに名目のみの守護富樫泰高(とがしやすたか)をたて、約100年間、国人・坊主・農民の寄合によって加賀国を実質支配しました。その有様は、まるで「百姓の持ちたる国のやう」だと評されました。
こうした一揆の高揚を、当時の人々は「下剋上の至り」ととらえたのでした。

① 惣村の形成
鎌倉後期に、経済の先進地域である近畿およびその周辺部では、荘園や公領の内部でいくつかの村が自然発生的に生まれ、南北朝期の動乱期にしだいに各地に広がっていきました。これらの自治的な村を、惣(そう)または惣村(そうそん)といいます。村の鎮守社の祭礼(宮座という農民たちの祭祀集団が祭礼をとりしきりました)や農業の共同作業や戦乱に対する自衛などを通じて、村民たちの結合は強くなっていったのです。
惣は、村役人と一般農民からなります。村役人は古くからの有力農民であった名主層たちで、おとな(長・乙名)・沙汰人(さたにん)・刀禰(とね)・肝煎(きもいり)・年寄(としより)などと呼ばれました。惣を構成する一般農民を惣百姓(そうびゃくしょう)といいます。
彼らは、村の会議である寄合(よりあい)で惣掟(そうおきて。村法)を定めたり、地下検断(じげけんだん。自検断)といって村内の秩序維持のため村民自身が警察権を行使したり、入会地(いりあいち。共同利用地)や灌漑用水の管理を行ったりしました。また、年貢納入を惣村が請け負う地下請(じげうけ。百姓請・村請)も次第に広がっていきました。
強い連帯意識で結ばれた村民たちは、災害時における年貢の減免や不法を働く荘官の免職を求めて、一揆を結びました。全員が耕作を放棄して山林に逃げ込んだり(逃散(ちょうさん))、荘園領主のもとに大挙して押しかけたり(強訴(ごうそ))、しばしば実力行使をおこないました。さらに、惣村の有力者の中には守護などと主従関係を結んで侍身分を獲得して地侍になる者も多く出現したため、荘園領主や地頭らが荘園・郷を領主支配していくことはますます困難になっていきました。

② 正長の徳政一揆(1428)
これらの惣村は、時には荘園・郷の枠組みを越えて、広範囲に連合することがありました。こうした農民の連合勢力が大きな力となって、中央政界に衝撃を走らせたのが、1428(正長元)年の正長の徳政一揆(正長の土一揆)でした。
前年の1427年、近江の坂本で、徳政を求めておこった馬借一揆が発端でした。坂本は比叡山延暦寺の門前町としてにぎわい、また琵琶湖の湖上交通と、関西への陸上交通の結節点として、馬借ら交通業者が多く集まる地です。彼らは早くから貨幣経済に取り込まれていたため、借金の棒引きを求めて蜂起し、その機動力の素早さから周辺に飛び火したのです。坂本ばかりでなく、このころの農村には土倉などの高利貸資本が深く浸透していたため、ひとたびきっかけがあると、徳政一揆はたちまち近畿地方やその周辺に拡大しました。
彼らは、京都の酒屋・土倉などの金融業者や寺院(堂塔補修を名目とする祠堂銭(しどうせん)を高利で貸し出していた)などを襲い、質物や借用証文を奪いました。また各地でも、債務の破棄や売却地の取り戻しを求める私徳政が行われました。『大乗院寺社雑事記(だいじょういんじしゃぞうじき)』は
日本開白(かいびゃく。開闢)以来、土民蜂起是(これ)初めなり
(日本はじまって以来、土民の蜂起はこの正長の徳政一揆が初めてである)
と正長の徳政一揆の衝撃を記録しています。

① 農業の集約化・多角化が進む
室町時代には、土地の生産性を向上させる集約化・多角化が進められました。川の流れを利用した水車や中国から導入された竜骨車(りゅうこっしゃ)などによって、灌漑・排水設備が整備・改善され、畿内では従来の二毛作に加え、三毛作もおこなわれるようになりました。1420(応永27)年に朝鮮から来日した宋希璟(そうきけい。号は老松堂)は、畿内での先進的な農業経営に目を見張り、尼崎(兵庫県)で米・麦・ソバの三毛作が行れていたことを記録しています(『老松堂日本行録』)(注)。
(注)1419(応永26)年、倭寇を恐れた朝鮮が、その根拠地の一つと見なした対馬に、軍船200隻で突如来襲するという事件がありました(応永の外寇)。幕府は朝鮮の意図を探るため使節を派遣し、翌年回礼使として来日したのが宋希璟でした。
また、稲の品種改良も進み、成長速度の異なる早稲(わせ)・中稲(なかて)・晩稲(おくて)の各品種が、各地の自然条件に応じて作付けされるようになりました。また、味は白米に劣るものの、干魃や冷害に強くて収穫量の多い早稲種の大唐米(たいとうまい。赤米)が大陸から伝来し、西日本を中心に庶民の食用米として普及しました(注)。
(注)大唐米は農民にとっては救いの作物でした。しかし、白米より食味が劣るということは、領主側からすれば、年貢米としては価値の低いものだったということになります。したがって、年貢米として大唐米をどの程度含めるかに関して、領主・農民間でさまざまな駆け引きがおこなわれていただろうことが推測されます。

② 入会地や用水の利用が農民の団結を強めた
二毛作・三毛作が広まってくると、一つの土地を年に二回・三回と耕作するようになりますし、用水も二倍・三倍必要になってきます。そのため水争いが起こってきます。
また、地力を回復して収穫を安定化させるためには、従来にまして肥料が必要です。刈敷・草木灰などに加え、下肥(しもごえ。人糞尿)や厩肥(きゅうひ。牛馬の糞尿)が広く使われるようになりました。
ただ、刈敷・草木灰を作るためには、刈草が大量に必要になります。施肥回数が増えてくると刈草の需要が高まり、入会地の利用をめぐって紛争が多発するようになってきます。諸紛争を回避するためには、用水の分配や入会地の利用について惣村内でルール作り(惣掟)が必要となってきます。こうした諸活動を通じて、惣村内での人びとの結束はますます固くなっていきました。
また、手工業の原料として、苧(お。からむし。繊維として利用)・桑(くわ。生糸をとる蚕の餌)・楮(こうぞ。和紙の原料)・漆(うるし)・藍(あい。藍染めの原料)・茶などの栽培も盛んになり、これらは加工されて商品として流通するようになりました。
このような生産性の向上は農民の生活を豊かにし、物資の需要を高め、商品の生産・流通を盛んにしました。こうして、自給自足だった農村にも、次第に商品経済が浸透していきました。

① 特産品の生産
この時代には、農民の需要にも支えられて、地方の産業の盛んになり、各地の特色を活かした様々な特産品が生産されるようになりました。京都・加賀・丹後の絹織物、美濃の美濃紙、播磨の杉原(すいばら)紙、美濃・尾張の陶器、備前の刀剣、能登・筑前の釜、河内の鍋、京都・河内・大和・摂津の酒などが有名です。
製塩は、塩田で作られました。自然浜(揚浜)のほか、堤防で囲った砂浜に潮の干満を利用して海水を導入する古式入浜(のちの入浜塩田)も作られるようになりました。晴天の多い瀬戸内海沿岸地方が、塩の生産地として有名です。

② 六斎市(ろくさいいち)と行商人の活躍
農業や手工業の発達により、扱う商品の数・量が増えていきました。そこで、地方の市場もその数と市の開催日の回数が増していきました。それまでは月に3回開く三斎市でしたが、応仁の乱後は、月6回開催する六斎市が一般化しました。
近年の千葉県の定期市の例ですが、六斎市とはどのようなものなのか、下の図で確認しましょう。

二つの円が「一の宮」によってつながっています。地名の下に記してある数字は市日です。たとえば、本納と刈谷は、1・6の日が、市の立つ日です。1・6の市なら1日・6日・11日・16日・21日・26日の月6回、その場所で市が開催される六斎市です。その日の商売を終えた商人は、2・7の市が立つ場所(本納→長南、刈谷→御宿)へ移動します。翌日には新たな市で商売をするわけです。これを順に繰り返していきます。たとえば、ある商人が本納からまわり始めるとすると、下のような流れになるでしょう。
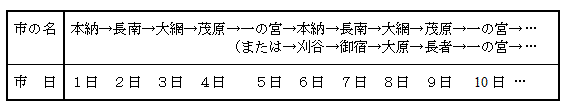
このように、各地の市場をまわって商品を売り歩いていたのは、固定された店舗を構えない商人たちでした。こうした商人を行商人(ぎょうしょうにん)といいます。連雀(れんじゃく)と呼ばれる紐(ひも)をつけた背負子(しょいこ)に荷物をくくりつけて行商した連雀商人や、荷物をぶら下げた天秤棒(てんびんぼう)をかついで売り歩いた振売(ふりうり)、炭・薪を売り歩いた大原女(おはらめ)、鵜飼集団の女性で鮎を売り歩いた桂女(かつらめ)など、多くの行商人が行き交いました。女性の行商人の活躍が目立つのも、この時代の特色の一つです。
一方、京都などの大都会では見世棚(みせだな)と呼ばれた常設小売店が一般化し、京都の米場(こめば)・淀の魚市などのように、特定の商品だけを扱う市場も生まれました。

③ 座の発展
手工業や商人たちの組合である座も、種類や数が増えていきました。大寺社と結びついた商人には神人(じにん)、天皇家と結びついた商人には供御人(くごにん)という称号を与えられ、彼らは朝廷や大寺社を本所とし、一定の座役(製品や営業税など)を納めることによって、独占的な販売権や原料仕入権、関銭の免除などを認められました。この中には、全国的に活動した座もありました。
たとえば、大山崎の油神人(油座)は、石清水八幡宮を本所とし、畿内・美濃・尾張・阿波など約10カ国以上油の販売と、その原料である荏胡麻購入の独占権を持っていました。
しかし、15世紀以降になると、座に加わらない「新儀(しんぎ)の商人」(新興商人)が増え、旧来の座商人との間に売買の権利をめぐって対立が起こるようになりました。また地方には、特定の本所を持たない、新しい性格の座も出現し、その中から戦国時代の御用商人につながる有力商人たちが成長していきました。

④ 貨幣の流通
商品経済が盛んになると、貨幣の流通量が著しく増大し、社会の隅々に貨幣の使用が浸透していきます。農民も年貢・公事・夫役という現物納や労役を、貨幣で代納するようになりました。これを代銭納(だいせんのう)といいます。
ただ、遠隔地取引が拡大してくると、貨幣や米などは重くて運搬に不便なため、為替(かわし)が盛んに利用されるようになりました。銭の為替は替銭(かえせん)、米の為替は替米(かえまい)といいます。
為替とは、たとえば「十貫文」と書かれた為替手形(割符(さいふ))をこちらの業者(為替屋(かわしや))に作ってもらって遠方に送付し、そちらの業者に持ち込んで手形と交換で十貫文の銭を受け取るというシステムです。十貫文の銭の重さは37.5kgにもなります。それを紙片1枚で持ち運ぶことができるのですから、格段に便利な仕組みですね。為替は、商人たちの間ばかりでなく、荘園現地から京都の荘園領主に年貢を送付する際にも利用されました。
貨幣は、従来の宋銭とともに、日明貿易で新たに流入した永楽通宝(えいらくつうほう)・洪武通宝(こうぶつうほう)・宣徳通宝(せんとくつうほう)などの明銭が使用されました。需要の増大にともなって粗悪な私鋳銭(鐚銭(びたせん))も流通するようになり、取引きにあたって悪銭の受け取りを拒否し、良質の貨幣を選ぶ撰銭(えりぜに、せんせん)がおこなわれて、円滑な流通が阻害されるようになりました。そのため、幕府や戦国大名たちは悪銭と良銭の混入比率を定めたり、一定の悪銭の流通を禁止する代わりに、それ以外の貨幣の流通を強制する撰銭令(えりぜにれい、せんせんれい)をしばしば発布しました。
貨幣経済の発達は、金融の活発化を促しました。酒屋などの富裕な商工業者は、土倉(どそう。どくら)と呼ばれた高利貸業を兼ねるものが多く、幕府はこれらの酒屋や土倉を保護・統制するとともに、酒屋役(酒壺の数に応じて賦課)・土倉役(倉の数に応じて賦課)と呼ばれる営業税を徴収しました。15世紀には土倉・酒屋の数は京都だけでも350軒あったといいます。
中世末から近世初期にかけて活躍した豪商には、土倉・酒屋から発達した者が少なくありません。角倉了以(すみのくらりょうい。1551~1614)もその一人です。
◆土倉と角倉了以(すみのくらりょうい。1554~1614)
土倉は担保をとって融資する高利貸業者。現在の質屋に近いイメージでしょうか。担保物件を保管するため、火災や盗難に強い堅牢な土壁の倉庫を建てました。これが土倉の名称の由来です。
彼らは大地主でもあり、収穫した米で酒を造り、ほとんどが酒屋を兼任していました。当時の土倉は荘園領主にも貸し付けし、年貢の取り立ても代行しました。返済不能になれば、担保の土地を兼併しました。もともと大地主だった土倉は、ますます膨張していったのです。
土倉が納める土倉役は、室町幕府の重要な財源の一つでした。幕府は土倉の有力者を納銭方に任命するようになります。納銭方になった土倉は、国家財政を切り盛りして権勢をふるいました。
質屋といっても、現代感覚の庶民相手の質屋のイメージではありませんね。
近世初期の朱印船貿易家であった角倉了以は、京都嵯峨で土倉を営んだ角倉氏の一族です。千光寺大非閣にある角倉了以の木像は僧形ですが、室町時代以来、京都の土倉はきまって頭を丸めていました。それは、京都の土倉が比叡山延暦寺を本所としていたからです。世間は土倉を「土倉法師(どくらほうし)」とよんでいました。応仁の乱後、延暦寺の統制力が弱まって俗体の土倉も現れるようになりましたが、角倉了以は昔ながらに僧形のままでした。
【参考】
・陳舜臣『人物・日本史記』、文春文庫、1987年の「角倉了以」の項 |

⑤ 交通の発達
地方の産業が盛んになると、遠隔地取引も活発になりました。海・川・陸の交通路が発達し、廻船(かいせん。港から港へ移動する輸送船)の往来も頻繁になり、交通の要地には問屋(といや)がおかれました。
一方、幕府・寺社・公家などが、関銭(せきせん。通行税)・津料(つりょう。入港税)徴収を目当てに、水陸交通の要地に次々と関所を設けるようになりました。これは、交通の大きな障害となったので、戦国大名や織豊政権は関所の撤廃を命じました。
物資は海上交通によって全国各地から京都などの消費地に運ばれ、ついで河川交通・湖沼交通を利用して内陸に搬送されました。
しかし、舟運が利用できない区間は、陸上輸送するしかありません。
たとえば、日本海側から若狭湾を経て琵琶湖に運び込まれた荷物は、大津や坂本など琵琶湖沿岸の港で荷揚げされました。しかし、ここから京都までの輸送は、陸上輸送に頼るほかはありません。ですから、水上交通と陸上交通の結節点である大津や坂本などには、馬借(ばしゃく。馬によって荷物を輸送)や車借(しゃしゃく。牛馬に引かせた車で米・木材などの重量物を輸送)などの運送業者が多く集まりました。かれらは広汎な情報を収集し、またその機動力からしばしば一揆の中心になりました。正長の徳政一揆が、坂本の馬借一揆に端を発していることは、よく知られています。

① 倭寇の活動
14世紀後半から15世紀にかけて、東アジアの情勢は大きく変化しました。この頃、倭寇と呼ばれる海賊集団が朝鮮半島や中国大陸の沿岸を襲いました。
倭寇は胡蝶軍(こちょうぐん)、八幡船(ばばんせん)、三島(さんとう)倭寇などと呼ばれました。胡蝶軍というのは神出鬼没な行動を胡蝶にたとえたもの、八幡船というのは「八幡大菩薩の旗を掲げて海賊行為をしたから」とよく説明されますが、そもそも海賊行為を「ばはん」といって、それに宛て字をしたのかも知れません。三島倭寇というのは、倭寇の根拠地を冠してこう呼んだもの。壱岐、対馬と、島ではありませんが肥前の松浦(まつら。まつうら)を三島と称しました。
倭寇(日本人の海賊の意)とはいっても、必ずしも日本人に限りませんでした。日明貿易を挟んだ前後で、前期倭寇と後期倭寇に二分しますが、後期倭寇のほとんどは中国人だったといわれます。
倭寇に悩まされた高麗は、日本に倭寇の禁圧を求めました。しかし、日本が南北朝の動乱の中にあったので、成功しませんでした。

② 明との交易
中国では1368年に明(みん)が成立しました。元の支配を排して成立した漢民族国家の明は、伝統的な国際秩序の回復に努めました。これを知った足利義満は、1401(応永8)年、明に僧の祖阿(そあ)、博多商人の肥富(こいつみ)を派遣し、国交を開きました。僧侶を派遣したのは、漢文の読み書きができるので実際の交渉や通訳にあてるためだったのでしょう。また、博多商人を同行させたのは、大陸に最も近い商業港博多を貿易の拠点の一つとする腹づもりだったからでしょう。
実際の貿易は1404年から始まりますが、これは朝貢貿易(ちょうこうぼうえき)の形式をとらなければなりませんでした。朝貢貿易というのは、宗主国である明の皇帝に、属国の国王が貢ぎ物を持参してご機嫌をうかがい、その返礼として明の皇帝から恩賜の品物を拝領するという形式で行われる貿易です。そこで、日明間の国交を開くにあたり、明の皇帝は義満に「日本国王源道義(足利氏は源氏。道義(どうぎ)は義満の法号)」宛ての返書と暦(大統暦)をおくりました。義満は公式文書に「日本国王臣源(にほんこくおうしんげん)」と署名し、明国皇帝に臣従する形をとりました。
また、遣明船は、倭寇と区別するために勘合(かんごう)と呼ばれる証書を持参するよう明から義務づけられました。よって日明貿易を勘合貿易ともいいます。昔の日本史教科書はこの証書を「勘合符」と書いていましたが、これは江戸時代に始まる誤用であること、「符」とすると木札と誤解されかねないことなどから、現在の教科書では「勘合」と訂正されています(注)。
(注)勘合は実物が残っていないので、その実際の形や大きさ、記載内容などといった基本的なことすら判明していません。近年、北海道大学大学院准教授で日本中世史・東アジア海域史を専門とする橋本雄(はしもとゆう)氏が、勘合の復元に取り組んでいます。氏によると、勘合の大きさは縦81cm×横108cm程度の大きさだったらしいとのことです(2012年現在)。もし、この推定が正しいとするなら、勘合は、教室に掲示されている時間割の模造紙くらいの大きさがあったことになります。
【参考】http://www.let.hokudai.ac.jp/history-area/japanese/staff-list-040.php
朝貢形式の貿易は、利益が非常に大きいものでした。何しろ運搬費用や滞在費用は明国の負担だった上、莫大な返礼品が返ってきましたから。こうしてわが国には、大量の銅銭のほか、生糸や絹織物、陶磁器、書籍、書画などがもたらされました。これらは唐物(からもの)と呼ばれて珍重されました。
ちなみに、日本からの輸出品は刀剣・鎗(やり)・鎧(よろい)などの武器・武具類、扇・屏風などの工芸品、銅(日本の銅には不純物として銀などが多く含まれていました)・硫黄(日本は火山国なので硫黄が多量に産出します。硫黄は黒色火薬の材料になりました)などの鉱産物でした。
利益が大きい半面、朝貢形式は屈辱的なものでした。建前上は明国皇帝の臣下であるので、皇帝が派遣した使者を「日本国王」が平伏して迎え、中国の暦を受取る(これを「正朔(せいさく)を奉じる」といいます)ことになっていました。
4代将軍義持は朝貢形式を嫌い、貿易は一時中断しました。しかし、貿易の利益が大きかったので、6代将軍義教は日明貿易を再開することにしました。
15世紀後半になると、貿易の実権は次第に博多商人と結んだ大内氏と、堺商人と結んだ細川氏に移っていきました。大内氏・細川氏の両者は激しく争い、1523(大永3)年に中国の寧波(ニンポー)で衝突を起こしました。この事件を寧波の乱といいます。この争いに勝利した大内氏は日明貿易を独占しました。
しかし、16世紀半ばの大内義隆(おおうちよしたか)の時、家臣の陶晴賢(すえはるかた)の下剋上によって滅亡させられてしまうと日明貿易は断絶し、再び倭寇の活動が活発になりました。豊臣秀吉が1588年に海賊取締令(かいぞくとりしまりれい)を出してその禁圧に乗り出すまで、倭寇の跳梁(ちょうりょう)は続きました。

③ 朝鮮との交易
日本で南北朝の合体がおこなわれた1392年、朝鮮半島では李成桂(りせいけい)が高麗を倒し、朝鮮(李朝)を建国しました。朝鮮も日本に倭寇の禁圧を求め、義満もこれに応じたので両国間に国交が開かれました。
日朝貿易は日明貿易と異なり、幕府ばかりでなく、守護大名や商人らも参加しておこなわれました。そこで朝鮮は、対馬の宗氏(そうし)を通じて、貿易を統制しようとしました。1443(嘉吉3)年、朝鮮と宗氏との間に結ばれた癸亥約条(きがいやくじょう。嘉吉条約)では、宗氏の交易船も年間50隻に制限されました。
その後、対馬の当主が交代し倭寇の活動が活発になったので、1419年、李従茂の指揮する朝鮮軍が、倭寇の本拠地と見なしていた対馬を200隻の軍船と1万7千の兵力で襲うという事件が起こりました。これを応永の外寇(おうえいのがいこう)といいます。日朝貿易は応永の外寇で一時中断しますが、16世紀まで活発におこなわれていました。
朝鮮は、半島の南端に位置する釜山浦(ふざんぽ)・乃而浦(ないじほ)・塩浦(えんぽ)の3港(これを三浦(さんぽ)といいます)を開き、これら三浦と首都の漢城(漢陽)に使節の接待と貿易のための倭館(わかん)を置きました。当初、三浦に住む日本人たち(これを朝鮮は恒居倭(こうきょわ)と呼びました)にはさまざまな特権が与えられていましたが、次第にそれらの特権は縮小されていきました。そのことに不満を持つ恒居倭たちが、1510(永正7)年、暴動を起こして鎮圧されました。これを三浦の乱(さんぽのらん)といいます。この三浦の乱後、日朝貿易は次第に衰退していきました。
日朝貿易の日本からのおもな輸出品は、銅・硫黄などの鉱産物や工芸品、琉球貿易で入手した蘇木(そぼく。染料)・香木(香料)などでした。一方、朝鮮からの輸入品は、木綿をはじめとする織物類や大蔵経(だいぞうきょう)などでした。
とくに木綿は、麻を日常衣料としていた当時の人びとの生活に、大きな影響を及ぼしました(柳田国男『木綿以前のこと』)。衣料としては、防寒にすぐれ、染色が自由にでき、洗ってもさほど縮まず、着心地もよいという特長があったからです。衣料ばかりでなく、鉄砲の火縄、船の帆(風をよくはらんで船足を早めました)などにも利用されました。

① 琉球王国の成立
沖縄では、北山・中山・南山の三地方勢力が争っていましたが、 1429(永享元)年、中山王の尚巴志(しょうはし)が三山を統一し、琉球王国が成立しました。
琉球王国は都を首里(しゅり)におきました。尚氏が住む首里城には、琉球文化を基調にしつつも中国・日本それぞれの建築様式を見ることができます。
首里の外港である那覇(なは)は、国際港として繁栄しました。琉球王国は多国間の中継貿易を盛んにおこない、その貿易船は、明や日本ばかりか、遠くジャワ島・スマトラ島・インドシナ半島にまで行動範囲を広げました。
首里城の正殿には「万国津梁之鐘(ばんこくしんりょうのかね)」が掛けられていました。その銘文には当時の琉球王国の繁栄とともに、
舟楫(しゅうしゅう)をもって万国の津梁(しんりょう)となす(琉球船が世界の架け橋となる)
という言葉が記されています。何とスケールの大きな言葉ではないでしょうか。

② 蝦夷ヶ島(えぞがしま)
一方、津軽半島の西側に位置する十三湊(とさみなと)は、畿内と結ぶ日本海貿易の拠点として繁栄していました。当時の海上交易のメインストリートは太平洋側ではなく、日本海側でした。
日本海を行き交う北前船などを通じて、サケ・ニシン・コンブなど北海の産物が、畿内にもたらされていました。京都の名物にコンブで出汁(だし)をとったニシンソバがあります。コンブもニシンも北海道の産品ですね。北海道から遠く離れた西日本で、料理の出汁(だし)を取る際コンブ出汁を用いることが多いのは、この時代が端緒になっています(ちなみに東日本ではカツオ出汁が主流)。
やがて、本州の人びとは、蝦夷ヶ島(北海道)の南岸に進出しました。古くから蝦夷ヶ島に住み、狩猟・漁労や交易を生業としていたアイヌは、彼らを和人(わじん)と呼びました。
和人たちは、渡島(おしま)半島の沿岸各地に港や館を築いて定住し、津軽の豪族安藤(安東)氏の支配に属して勢力を広げました。館を建てた小豪族は館主(たてぬし)と呼ばれ、彼らの居住区はのちに道南十二館(どうなんじゅうにたて)と総称されます。そのうちの一つ、現在の函館市にあった志苔館(しのりだて)の跡地からは、約37万枚もの中国銭が出土しています。この地域が経済的に繁栄していたを偲ばせます。
和人はアイヌと交易を行っていましたが、次第にアイヌの生活を圧迫するようになりました。アイヌ青年が和人に殺害されるという事件をきっかけに、長年の不満を爆発させたアイヌ諸部族は1457(長禄元)年、大首長コシャマインに率いられて蜂起しました。一時は茂別館(もべつだて)・花沢館(はなざわだて)以外の道南十二館を陥落させるほどの勢いでしたが、まもなく上之国(かみのくに)花沢館主の蠣崎氏(かきざきし。下北半島蠣崎から15世紀に渡島半島に渡ってきた一族)の客将武田信広(たけだのぶひろ。1431~94)によってコシャマインが射殺されて、鎮圧されました。これをコシャマインの乱といいます。
武田信広はコシャマインの蜂起鎮圧により蠣崎氏をつぎ、その後、一族は道南地域の支配者となりました。さらに江戸時代になると、松前氏(まつまえし)と改名して、蝦夷地を支配する大名となりました。