25.鎌倉文化
「運慶は仏像を生けるがままに具象化しようとした。玉眼(ぎょくがん)に水晶を嵌(は)め込む技法は、その現実感を一層効果的にする。抽象には何かがあるかも知れないが、それを感じ取るまでには時間と忍耐を要する。写実は瞬時の躊躇(ちゅうちょ)なく直截(ちょくせつ)に訴える。それが見事な出来であればあるほど、素朴な感嘆を与える。作家の精神が、民衆の距離のない感動に融け合うのだ。もともと信仰の本質は感動ではないか。 ( 中略 )
建仁三年には、竣工した東大寺南門に入れる金剛力士像を運慶は快慶と一体ずつ受けもって仕事をすることになった。二丈八尺の巨大な寄木造りである。
これは「阿・吽(あ・うん)」の一対の形像であるから、対照に統一がなければならない。運慶は吽形(うんぎょう)像をうけもつことにし、阿形像(あぎょうぞう)を造る快慶に作風の歩調を合わせるよう打ち合せた。打合せというよりも、彼の態度は云い渡したというに近かった。康慶はすでに亡くなり、運慶が一門の統率者として支配の地位に立っていた。年齢も、もう六十近いのである。 ( 中略 )
だが、快慶の阿形像を見て、運慶は驚嘆した。よくもこれだけおれに合せたと思った。それから彼の才能にも今さらながら愕(おどろ)いた。そこには快慶が今まで未練気に持ちつづけてきた迷うような静寂はどこにもない。歪形(わいぎょう)に近い写実の誇張は運慶にも逼っていた。運慶はこの異常な職人に圧迫さえ感じた。
南大門の金剛力士の二像は、果して喝采をうけた。それは運慶が期待した通りなのだ。作品は最も期待した対象を得て、一番の精細を放つ。殊(こと)に写実の世界ではそうなのだ。」
(松本清張「運慶」-『小説日本芸譚』1957年,新潮文庫,P.21~26による-。なお、運慶・快慶は吽形像・阿形像を分担・制作したのではない。ともに吽形像の制作にあたったことが、金剛力士像の昭和大修理の際に判明している)
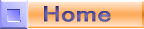
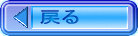


鎌倉時代には、武家・庶民を新たな担い手とする新しい文化が成長しました。素朴・質実な武家社会の気風や、庶民性が文学や美術等に影響を与えるようになりました。それは、従来の貴族文化のような深い教養や学力等を必要とせず、直截(ちょくせつ)に我々の心に迫ってきます。
この時代の文化の特徴は、「平易で躍動的」という言葉で置き換えることができるかも知れません。平易な教えを説くいわゆる「鎌倉新仏教」、文字が読めなくとも聞いただけで理解できる語り物文学、見た瞬間に実在として迫ってくる写実的な彫刻群など。
もう一つ、南宋や元の文化の影響も見逃せません。日宋間に正式な国交はありませんでしたが、両国間を往来した僧侶や商人らによって、また南宋滅亡でわが国に亡命してきた中国僧らによって、朱子学・禅宗などの大陸文化がわが国に伝えられたのでした。

当時の人々は、末法思想の浸透を背景とした社会不安にさいなまれていました。保元・平治の乱以降うち続く武士の争乱。貴族から武士へ、平氏から源氏へと目まぐるしくかわる支配者。養和の飢饉をはじめ、うち続く災害。
しかし、人々が心の拠(よ)り所として頼るべき大寺院は、旧来の権益を守るために武装して朝廷や院に強訴を繰り返すばかり。また、仏教の教義そのものが祈祷(きとう)や学問中心である上、厳しい修行を要請しました。とても、庶民の心を平安に導くものではありません。
こうした状況のもと、庶民や武士など幅広い階層に門戸を開く、新しい仏教がおこってきました。鎌倉仏教の開祖たちのほとんどが開宗以前に比叡山で修行し、「仏の前に一切衆生(いっさいしゅじょう)は平等である」とする天台教学を学んでいたことも、一つの要因だったでしょう。
また開祖たちは、奇(く)しくも源平の争乱(法然、栄西)、承久の乱(親鸞、道元)、蒙古襲来(日蓮、一遍)といった危機的状況のもとで登場しました。それは、激動する社会や武家・庶民の勃興する新たな時代相が、彼らの教えを必要としていたからかも知れません。
開祖たちの言葉に耳を傾けた人々は、念仏・題目・禅の中から一つの教えを「選択(せんちゃく、せんじゃく)」します。それは、たとえば「南無阿弥陀仏」と唱えるだけでよい、というような誰にでもできる「易行(いぎょう。やさしい修行方法)」でした。あとはそれに「専修(せんじゅ。専念)」すればよいのです。
「選択」・「易行」・「専修」を特色とする新たな仏教は、時代の担い手となる幅広い社会的階層の人々を対象としていました。

① 浄土教系の開祖たち(法然、親鸞、一遍)とその教え
《 法然の浄土宗 》
最初にあらわれたのは法然(ほうねん。源空(げんくう)。1133~1212)でした。天台教学を学んだ法然は、念仏(南無阿弥陀仏)をとなえれば、死後は平等に極楽浄土に往生できるという専修念仏(せんじゅねんぶつ。他の行をかえりみずに、ひたすら念仏のみをとなえること)の教えを説いて、のちに浄土宗の開祖とあおがれました。
法然によれば、極楽往生するには、二つの道があるといいます。一つを聖道門(しょうどうもん)、もう一つを浄土門(じょうどもん)といいます。聖道門は旧来の道で、いわば自力難行道(じりきなんぎょうどう)というべきものです。経典を買う財力、それを読み解く学力、目的を達成しようとする強い意志と困難な修行が必要とされます。それに対し、浄土門は、阿弥陀仏の力にすがって極楽往生を目指す、誰にでも実行可能な、いわば「他力易行道(たりきいぎょうどう)」です。法然は「選んで浄土門に入れ」と勧めます。
浄土門に入るためには、正行(しょうぎょう)と雑行(ぞうぎょう)という二つの修行方法があり、法然は「選んで正行に帰すべし」といいます。さらに正行を修するにも、正定(しょうじょう)の業と助業という二つの手段があります。法然は「選んで正定を専(もっぱ)らにすべし」といいます。それでは正定の業とは、具体的には何なのでしょうか。
正定の業は、読誦(どくじゅ)・観察(かんざつ)・礼拝(らいはい)・称名(しょうみょう)・讃歎供養(さんだんくよう)の五つを言います(五種正業)。経典を読んだり、仏像を見たり、礼拝したり、念仏したり、仏の徳を讃えたり、といったことをするわけです。このなかから法然は、特に「称名(阿弥陀仏の名を称える)」すなわち念仏を選択しました。阿弥陀仏は48の誓願をたて、その第18願で「私に帰依する衆生(しゅじょう)のすべて救おう」と誓われました。ですから、阿弥陀仏のこの言葉(これを本願といいます)を信じて、ひたすら念仏しなさい、と言ったのです。
選択を繰り返した結果、最終的に念仏が選択されました。
念仏「南無阿弥陀仏」=正定の業→正行→浄土門→極楽往生
「阿弥陀仏の本願(衆生を救おうという言葉)を信じて念仏を選択した」ので、法然の著書を『選択本願念仏集(せんちゃくほんがんねんぶつしゅう)』といいます。『選択本願念仏集』は、九条兼実の求めに応じて書かれた浄土宗の教義を説いた書です。法然の教えは貴族や、武士・庶民にまで広まっていきました。
念仏という易行によって信者を獲得し、急速に宗勢を拡大する法然らに対して、旧仏教側から非難の声が高まりました。
たとえば華厳宗の明恵(みょうえ。高弁(こうべん))は、次のように法然を痛烈に批判しました。
ここに近代、上人(しょうにん。法然のこと)あり。一巻の書を作る。名づけて選択本願念仏集と曰ふ。経論に迷惑して諸人を欺誑(ぎきょう)せり。往生の行(ぎょう)を以て宗とすと雖(いえど)も、反(かえ)つて往生の行を妨礙(ぼうげ)せり。 (『摧邪輪(さいじゃりん)』)
(法然は『選択本願念仏集』を書いた。誤った経典解釈をし、念仏をすれば極楽に往生できるなどと唱えて人々をだましている。極楽浄土へ往生できる行ということで浄土宗をはじめたが、むしろ極楽往生の行を妨げているものだ)
また、法相宗の貞慶(じょうけい)は『興福寺奏状(こうふくじそうじょう)』を書いて、法然一派を弾劾(だんがい)しました。その結果、1207(承元元)年、法然は土佐(実際には讃岐)に流されてしまいます。これを「承元(じょうげん)の法難」と言います。
浄土宗の総本山は、京都の知恩院(ちおんいん)です。
《 親鸞の浄土真宗(一向宗) 》
親鸞(しんらん。1173~1262)も、法然に連座して越後(新潟県)に流されました。強制的に還俗(げんぞく。僧の身分を奪い俗人に戻すこと)させられたのち妻帯(恵信尼(えしんに)という女性を妻としました)し、自らを「愚禿(ぐとく。戒律を守れない愚か者の僧の意)親鸞」と称しました。肉食妻帯は仏教の戒律に違反した行為(破戒)でしたが、このことが親鸞に戒律を守れない人々(悪人)こそが救われるべきだという信念を持たせることになります。
赦免(しゃめん)後は常陸国稲田(いなだ)の西念寺(さいねんじ。現、茨城県笠間市)を拠点に東国地方に布教し、さらには東北・北陸地方へも布教を進めました。代表的著作『教行信証(きょうぎょうしんしょう)』は、西念寺で書かれました。
法然の念仏には、他力本願という立場に立ちながら、念仏を一遍唱えるよりも十遍、十遍よりは百遍…というように、「極楽往生するには念仏は数多く称(とな)えた方がよい」という考え方が潜んでいます。阿弥陀仏という「他力」に帰依すると言っておきながら、念仏の回数という「自力」を重視しているのです。法然の教えにあった自力本願的要素を徹底的に排除したのが親鸞でした。
念仏は回数が問題なのではありません。我が身が戒律を守れない救いようのない凡夫(ぼんぷ)であり、それゆえ阿弥陀仏しか頼るものがない。そうした自覚をもって、我が身のすべてを阿弥陀仏の前に投げ出す強い信心こそが、もっとも重要だと親鸞は考えました。ですから、そうした自覚を強烈にもつ煩悩(ぼんのう)深い人間(悪人)こそが、阿弥陀仏の最も救済されるべき対象であると親鸞は説いたのです。この考え方を、悪人正機説(あくにんしょうきせつ。悪人正因説)といいます。
「善人なをもちて往生をとぐ、いはんや悪人をや(善人が往生できるのだから、悪人が往生できないわけがない)。しかるを、世のひとつねにいはく、『悪人なを往生す、いかにいはんや善人をや』と。この条、一旦(いったん)そのいはれあるににたれども、本願他力の意趣(いしゅ)にそむけり。そのゆへは、自力作善(じりきさぜん)の人は、ひとへに他力をたのむこゝろか(欠)けたるあひだ、弥陀(みだ)の本願にあらず。 (中 略) 煩悩具足(ぼんのうぐそく)のわれらは、いづれの行(ぎょう)にても生死(しょうじ)をはなるゝことあるべからざるを哀(あわれみ)たまひて、願ををこしたまふ本意(ほい)、悪人成仏のためなれば、他力をたのみたてまつる悪人、もとも(もっとも)往生の正因(しょういん)なり。よりて善人だにこそ往生すれ、まして悪人は」と仰(おおせ)さふらひき。(『歎異抄(たんにしょう)』)
親鸞の教えは農民や地方武士のあいだに広がり、やがて浄土真宗(一向宗。一向専修(いっこうせんじゅ)に由来します)とよばれる教団を形成していきました。
浄土真宗は京都の本願寺(ほんがんじ)を根拠としましたが、江戸時代初期に東本願寺と西本願寺に分裂しました。
《 一遍の時宗 》
同じ浄土教系でも一遍(いっぺん。智真(ちしん)。1239~1289)になると、念仏の回数はおろか、善人・悪人の区別や信心の有無さえ関係なく、すべての人々が救済されると説きました。
極楽往生は、理屈や信心によりません。名号(南無阿弥陀仏)によるのです。「極楽往生なんかしまい」と心に思っても、ひとたび「南無阿弥陀仏」と念仏をとなえれば、極楽往生はその瞬間に決定している、というのです。
往生はまたく義によらず、名号(みょうごう。南無阿弥陀仏のこと)によるなり。法師が勧(すすむ)る名号を信じたるは往生せじと心にはおもふとも、念仏だに申さば往生すべし。いかなるゑせ義(誤った理屈)を口にいふとも、心におもふとも、名号は義によらず、心によらざる法なれば、称すればかならず往生するぞと信じたるなり。(『一遍上人絵伝』)
一遍は、「南無阿弥陀仏、六十万人決定(けつじょう)往生」と書かれたお札を民衆に配って、人々に念仏を勧めました。この行為を賦算(ふさん)といいます。信心・不信心にかかわらず、お札を手にした人々は極楽往生が確約されている、というのです。60万人という救済目標の数字は、六字名号(南無阿弥陀仏)に十方世界を乗じて算出したといわれます。
一遍とその信者たち(時衆)は、踊念仏(おどりねんぶつ)によって多くの民衆に教えを広めながら各地を布教して歩きました。諸国を巡り歩いて教えを説くことを「遊行(ゆぎょう)」といったので、一遍は「遊行上人(ゆぎょうしょうにん)」とよばれました。また、「日常のどのような時も臨終と心得て念仏せよ(臨命終時宗)」というその教えから、一遍の教えは時宗とよばれました。
一遍は死に臨み、一切の著作物を火中に投じさせました。そのため、一遍自身による著作は伝わっていません。ただ一遍の活動は、弟子たちが一遍の法語・和歌・消息などを編集して江戸時代に刊行した『一遍上人語録』や、一遍の布教の有様を描いた『一遍上人絵伝』(法眼円伊(ほうげんえんい)によって描かれました)などによって知ることができます。
一遍の教えは、地方の武士や農民の間に広く受け入れられていきました。
時宗の総本山は、神奈川県にある清浄光寺(しょうじょうこうじ。遊行寺(ゆぎょうじ)とも呼ばれます)です。

② 天台系-日蓮の法華宗-
日蓮(1222~1282)もまた比叡山に登り、天台宗を学びました。やがて法華経こそが釈迦の正しい教えであるという確信をいだき、題目(だいもく。南無妙法蓮華経(なむにょうほうれんげきょう))をとなえる(唱題(しょうだい))ことで救われると説きました。
日蓮は、法華経こそが真の教えであるとして、「念仏無間(むげん)、禅天魔(てんま)、真言亡国、律国賊(念仏を称える輩は無間地獄に堕ちる。禅宗は天魔の所為である。真言宗は国を滅ぼす。律宗を信じる者は国賊である)」(四箇格言(しかかくげん))と他宗を激しく攻撃しながら、鎌倉の市中で民衆に布教を進めました(辻説法(つじせっぽう))。
1260(文応元)年、日蓮は前執権北条時頼に『立正安国論(りっしょうあんこくろん)』を提出します。その内容は、天変地異が続発するのは法華経の正法に背くからである、このまま法華経を尊信しないなら『薬師経』に書かれた七難の内、自界叛逆難(じかいほんぎゃくなん。国内の反乱)と他国侵逼難(たこくしんぴつなん。外国の侵略。すなわちこれが蒙古襲来の予言だというのです)という二つの国難が起こるであろう、というものでした。かえって日蓮は処罰され、伊豆・佐渡に流されました。
日蓮は赦免(しゃめん)後も布教活動続け、日蓮宗(法華宗)は関東の武士層や都市の商工業者を中心に広まっていきました。
日蓮宗の総本山は、山梨県の身延山(みのぶさん)久遠寺(くおんじ)です。

③ 禅宗系(栄西、道元)の教え
《 栄西の臨済宗(りんざいしゅう) 》
難行苦行によっても悟りを開けなかったゴータマ=シッダールタが、悟りを開き仏陀(目覚めた者の意。覚者)となったのは、坐禅の力によってでした。坐禅によって自らを鍛練し、仏陀の境地に近づくことを主張する禅宗の自力本願的要素が、実力によって武家政権を確立した鎌倉武士の気性に合致していたのでしょう。禅宗は当時、関東武士の間に、急速に受容されて行きました。
12世紀末ごろ、宋から日本に禅宗(9世紀の唐僧臨済が開いた禅宗の一派である臨済宗)を伝えたのは、2度の入宋経験をもつ栄西(えいさい、ようさい。1141~1215)でした。栄西は密教の祈祷にもすぐれ、公家や幕府有力者の帰依を受けて、のちに臨済宗の開祖とあおがれました。
栄西の禅は、坐禅のみならず、公案(こうあん)といういわば小テストを解き続ける(これを「公案問答(こうあんもんどう)」と言います)ことによって、一歩一歩階段を昇るように、修行者を悟りの高みへと導くものです。公案は、たとえば「両手を叩くと音がするが、片手ではどんな音がするか」(江戸時代の臨済僧白隠が作成した「隻手音声(せきしゅおんじょう)」の公案)というように、一般人にとっては難解なものでした。後世、こうした禅問答を落語の題材として取りあげて、質問者と応答者のやりとりのとんちんかんさを笑ったものに「蒟蒻問答(こんにゃくもんどう)」があります。
さて、栄西は宋から禅宗とともに、茶(茶種や苗木)を持ち帰りました(遣唐使派遣の時代に最澄や空海等が茶を持ち帰りました。しかし、その使途は解熱・強壮・眠気覚まし等の薬用中心であり、また高級品として一般には出回りませんでした)。
茶(当時は抹茶)は、禅宗と縁の深い飲み物です。カフェインによって睡魔を払い、心身の疲労を回復する効果があるとされた茶は、宋の禅僧にとって、長時間の瞑想(めいそう)に耐えるために必要不可欠な飲料でした。栄西のもたらした茶種は、その後栂尾(とがのお)高山寺(こうさんじ)の明恵(みょうえ。高弁(こうべん))の手に渡りました。そして、京都の宇治で栽培されるようになって、全国へ広まっていったのです。
また栄西には、茶の功徳(くどく)や栽培法を論じた『喫茶養生記(きっさようじょうき)』という著作もあります。本書は、二日酔いに悩んだ3代将軍源実朝に、良薬として茶を献じた際、一緒に献上されたといいます(『吾妻鏡』建保2年(1214)2月4日の条。ただし「茶の徳を誉むる書」とあるだけで、『喫茶養生記』という書名はあがっていません)。
栄西の死後、南宋から蘭溪道隆(らんけいどうりゅう。1213~1278)・無学祖元(むがくそげん。1226~1286)・一山一寧(いっさんいちねい。1247~1317)ら多くの禅僧が来日しました。幕府は臨済宗を重んじて、鎌倉に大きな寺院をつぎつぎと建立していきました。たとえば、北条時頼の帰依を受けた蘭溪道隆が開いたのが建長寺(けんちょうじ)、北条時宗の帰依を受けた無学祖元が開いたのが円覚寺(えんがくじ)です。
臨済宗の総本山は京都の建仁寺 (けんにんじ)です。
◆栄西の慈悲
栄西がまだ建仁寺にいた頃の話。一人の男が寺にやってきて言うことに、「私の家は貧しくて、夫婦子ども2、3人が餓死しようとしています。お慈悲をもって、お救いください」と。しかしその時、建仁寺の僧坊中には、まったく衣食財物等がありませんでした。ただ、薬師如来像を造立しようと、後背の材料にする打ちのばした銅が少々ありました。栄西は、この銅を自ら打ち折って束ねて丸めると、「これを食物と代えて飢えをふさぎなさい」と言って、男にやってしまいました。
弟子たちは、次のように言って、栄西の行動を非難しました。
「あの銅は仏像の光背を造るためのものです。それを俗人に与えてしまうのは、仏のために使用するものを勝手に使用した罪になると思いますが、いかがですか」
それに対しての栄西の言葉。
誠に然(しか)り。但(ただ)し佛意(ぶっち)を思ふに佛(ほとけ)は身肉手足(しんにくしゅそく)を割(さ)きて衆生(しゅじょう)に施こせり。現に餓死すべき衆生には設(たと)ひ佛の全體(ぜんたい)を以(もっ)て與(あた)ふるとも佛意に合(かな)ふべし。
(誠にその通りである。ただ仏の意志を思うと、仏は身肉手足を切って施しをされたのであり、現に餓死に瀕する人びとがいれば、たとい仏の全体をもってその人たちに与えても、仏意にかなうことになろう。)
また、次のようにも言われました。
我れは此(こ)の罪に依(より)て悪趣(あくしゅ。地獄、餓鬼、畜生、修羅の悪道)に墮(だ)すべくとも、只(ただ)衆生の飢へを救ふべし。
(自分は仏の物を私用に使った罪で悪趣に堕ちても、ただ人の飢えを救うであろう。)
【参考】
・古田紹欽(ふるたしょうきん)訳註『正法眼蔵随聞記』1960年、角川文庫、P.74~75
|
《 道元の曹洞宗 》
幕府との結びつきを強めた禅宗なかで、権力との癒着を嫌い、坐禅に徹することを説き、曹洞宗(そうとうしゅう。9世紀に唐で始まった禅宗の一派。宗名は派祖と弟子の名から一字ずつ取ったものといわれています)をひらいたのが道元(1200~1253)でした。
道元は栄西の弟子に学び、さらに南宋にわたって禅を学びました。道元の禅宗は公案を用いず、坐禅そのものを重視しました。ひたすら坐禅すること(只管打坐(しかんたざ))によって悟りの境地の体得を目指しました。
道元の弟子の懐奘(えじょう)が師の言行を筆録した『正法眼蔵随聞記(しょうぼうげんぞうずいもんき)』の中で、道元は次のように言っています。
学道の最要は坐禅これ第一なり。大宋(だいそう)の人多く得道(とくどう)することみな坐禅のちからなり。一問不通(いちもんふつう)にて無才愚癡(むさいぐち)の人も、坐禅をもはら(専ら)すればその禅定(ぜんじょう)の功によりて多年の久学聡明(きゅうがくそうめい)の人にも勝るるなり。しかあれば、学人は祗管打坐(しかんたざ)して他を管することなかれ。(『正法眼蔵随聞記』)
道元は、京から越前(福井県)に下って永平寺を開き、厳格な宗風をつくりあげていきました。道元の代表的著作が『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』です。

④ 旧仏教の革新
新仏教の活動は、旧仏教側に法然らに対する反発とともに、旧態依然とした自らを反省させるきっかけとなりました。
法相宗の貞慶(じょうけい)や華厳宗の明恵(みょうえ)は戒律を重視して、南都仏教の復興に力をそそぎました。律宗の叡尊(えいぞん)・忍性(にんしょう)・俊芿(しゅんじょう)らは、戒律を尊重するとともに、社会事業にも力を尽くしました。
《 貞慶(じょうけい。解脱(げだつ)) 》
貞慶(1155~1213)は法相宗を中興しました。笠置寺(かさぎでら)・海住山寺(かいじゅうせんじ)で、戒律の復興に努めました。法然の浄土宗を批判した『興福寺奏状(こうふくじそうじょう)』を書き、法然らが京都から追放された「承元(じょうげん)の法難」のきっかけを作りました。
《 明恵(みょうえ。高弁(こうべん)) 》
明恵(1173~1232)は、華厳宗を基礎としながらも、華厳宗と真言密教を融合した厳密(ごんみつ)という独自の宗教観を打ち立てました。後鳥羽上皇から京都栂尾(とがのお)の地を賜り、高山寺(こうさんじ)を開きました。『摧邪輪(さいじゃりん)』を著して、法然の浄土宗を激しく批判したことは前述したとおりです。また、栄西から茶の種子を譲られ、栂尾に茶園を開きました。栂尾から伝わったのが宇治茶です。
なお、高弁の自在な境地を伝えるものとして、月の明るさを詠んだ次の和歌が有名です。
あかあかやあかあかあかやあかあかやあかあかあかやあかあかや月
《 叡尊(えいぞん。思円(しえん)) 》
叡尊(1201~1290)は大和(奈良)西大寺を中心に戒律の復興に努め、真言律宗を開きました。貧者や病人の救済事業や土木社会事業を行い、興正菩薩(こうしょうぼさつ)と呼ばれました。
《 忍性(にんしょう。良観(りょうかん)) 》
忍性(1217~1303)は叡尊の弟子です。鎌倉極楽寺(ごくらくじ)を再興し、戒律復興に努めました。奈良にハンセン氏病の救済施設北山十八間戸(きたやまじゅうはちけんこ。間取りが18ある棟割長屋なので、こう呼ばれました)を建て、施療や慈善に尽くしたことは特筆されます。
《 俊芿(しゅんじょう。我禅(がぜん)) 》
南宋から帰国した俊芿(しゅんじょう。1166~1227)は、戒律の復興に努めました。京都の泉涌寺(せんにゅうじ)を再興して天台・真言・禅・律の四宗兼学道場としました。泉涌寺は1242(仁治3)年に四条天皇が寺内に埋葬されたところから皇室の菩提寺となり、「御寺(みてら)」と呼ばれるようになった皇室ゆかりの寺院です。

⑤ 伊勢神道
鎌倉仏教の影響を受けた独自の神道理論が、伊勢神宮外宮(げくう)の神官度会家行(わたらいいえゆき。?~?)によって形成された伊勢神道(度会神道)です。度会家行は『類聚神祇本源(るいじゅうぎんじほんげん)』を著し、従来の本地垂迹説と反対の立場に立って、神を主として仏を従とする神本仏迹説(しんぽんぶつじゃくせつ)をとなえました。

① 有職故実(ゆうそくこじつ)と古典研究
武士に実権を奪われ政治から疎外されつつあった貴族たちでしたが、文化の面では依然として伝統的権威を背景にして大きな力を保持していました。
ただし、それは懐古趣味とも、王朝憧憬(おうちょうしょうけい)とも呼ぶべき性格のものでした。兼好法師が「何事も、古き世のみぞしたはしき(何ごとにつけても、昔の世の中ばかりが慕わしく思われる)」(『徒然草』第22段)と漏らしたように、過ぎ去りしよき時代を懐かしみ、貴族文化華やかだった時代の作品群を尊重する念にあふれていました。
こうした文化的雰囲気の中で隆盛したのが、朝廷の儀式や先例を研究する有職故実(ゆうそくこじつ)の学問や、『万葉集』や『源氏物語』などの注釈を中心とした古典研究の学問でした。
《 有職故実 》
有職故実の書としては、後鳥羽上皇の『世俗浅深秘抄(せぞくせんしんひしょう)』(2巻)と、その子順徳天皇の『禁秘抄(きんぴしょう)』(3巻)があります。
『世俗浅深秘抄』は皇室・摂関家の古記録を引用して朝廷の儀礼等を記しています。ただし著者を後鳥羽上皇ではなく、一条兼良(いちじょうかねら(かねよし))とする説、藤原基房(ふじわらのもとふさ)とする説もあります。
『禁秘抄』(『禁中抄(きんちゅうしょう)』、『建暦御記(けんりゃくぎょき)』とも)は宮中の故実作法の全般を記しています。後世の準則となりました。
《 古典研究 》
源光行(みつゆき。1163~1244)・親行(ちかゆき。?~?)父子が源氏物語の注釈書『水原抄(すいげんしょう)』(54巻)を著しました。『水原抄』は、『源氏物語』の「源」の字を「水(さんずい)」と「原」に分解して書名にしたといわれています。ただし、散逸してしまい現存しません。本書を引用する他の古注釈書によって、その内容を推測するだけです。
また、光行の子素寂(そじゃく。?~?)も『源氏物語』の注釈書『紫明抄(しめいしょう)』(10巻)を著しました。
卜部兼方(うらべのかねかた。?~?)は『日本書紀』の注釈書『釈日本紀(しゃくにほんぎ)』(28巻)を著しました。『釈日本紀』は、現存最古の『日本書紀』の注釈書で、散逸してしまって今日目にすることができない古典を数多く引用していることで知られます。
僧仙覚(せんがく。1213~?)は『万葉集註釈(まんようしゅうちゅうしゃく。『万葉集抄』、『仙覚抄』とも)』(10巻)を著しました。東国出身の学問僧(天台宗)だった仙覚は、13歳から『万葉集』の研究を志した、と伝えられています。摂家将軍九条頼経の命で『万葉集』諸本の校合を行うなどした後、『万葉集』の体系的な注釈作業に取りかかり、本書を完成させました。

② 宋学(そうがく)と金沢文庫(かねさわ(かなざわ)ぶんこ)
《 宋 学 》
儒学は、中国の春秋・戦国時代に登場した思想家孔子や孟子らの打ち立てた学問です。しかし、何百年もたつうちに、同じ中国人でもその解釈に意見の相違が生じてきました。宋代、朱熹(しゅき。朱子(しゅし))が孔孟の教えを独自に解釈した儒学の一派を、宋学(そうがく。朱子学)といいます。
宋学は鎌倉時代末期、わが国に伝えられました。その特色は、君主は君主らしく、家臣は家臣らしくして、上下の秩序関係を保たねばならない、とする大義名分論(たいぎめいぶんろん)にあります。大義名分論が与えた影響は大きく、後醍醐天皇らの討幕運動の理論的根拠となりました。
《 金沢文庫 》
歴史書・法律書等を編纂したり政務を執ったりする上での必要性や、公家との文化交流等を通じて、武士の中にも学問に興味・関心をもち、精励する者が生まれてきました。北条実時(ほうじょうさねとき。金沢実時。1224~1276)は、そうした好学の武士の一人として知られます。
鎌倉の外港としてさかえた六浦(むつら)の金沢(かねさわ。現横浜市)に実時の別邸があり、実時はそこで自分が収集した蔵書を公開しました。実時が開設した私設図書館を金沢文庫(当時は「かねさわぶんこ」。現在は「かなざわぶんこ」と発音)といいます。文庫はその後も実時の子顕時(あきとき)、孫貞顕(さだあき)らに継承されて内容を充実させていきました。鎌倉幕府の滅亡によっていったん散逸してしまったものの、のち再興されて現在に至ります。同所には、金沢氏の菩提寺である称名寺(しょうみょうじ)が建立されました。

③ 歴史と軍記物
《 愚管抄(ぐかんしょう) 》
慈円(じえん。1155~1225)は、幕府開創期に頼朝と親しかった九条兼実(くじょうかねざね)の弟で、天台座主(てんだいざす)の要職を4度もつとめました。承久の乱を前にして、後鳥羽上皇を中心とした討幕計画を諫めるねらいもあって、乱直前の1220(承久2)年に『愚管抄』を著したといわれています。
本書は、末法思想を根底にして、「道理」(歴史をつらぬく原理)による歴史の解釈をこころみた最初の歴史哲学書です。北畠親房の『神皇正統記』(南北朝時代)、新井白石の『読史余論』(江戸時代)と合わせて「三大史論」と称されます。
《 吾妻鏡(あずまかがみ) 》
『吾妻鏡』は幕府の公式記録書です。1180(治承4)年~1226(文永3)年までの87年間、初代将軍の源頼朝から第6代の皇族将軍宗尊親王までの幕府の事績を日記体で記述しています。
幕府による編纂物であるため、たとえば幕府に不都合な事柄については記述の脱落や曲筆が疑われる箇所が見られますし、北条氏の権勢を正当化する脚色があることでも知られています。したがって、鎌倉幕府を理解する上での基本史料であるものの、その取り扱いには十分な注意が必要です。
《 水鏡(みずかがみ)と今鏡(いまかがみ) 》
歴史物語としては『水鏡』(中山忠親(なかやまただちか)カ)と『今鏡』(藤原為経(ふじわらのためつね)カ)が作られました。前者は『大鏡』以前神武天皇から850年までの歴史を扱い、後者は『大鏡』以後1025年から1170年までの歴史を扱っています。ともに四鏡(しきょう)の一つに数えられます。
《 元亨釈書(げんこうしゃくしょ) 》
『元亨釈書』(30巻)は、虎関師錬(こかんしれん)によるわが国最初の日本仏教史です。
《 平家物語 》
『平家物語』は、室町時代の『太平記』とともに「軍記物の双璧」と評価されます。平氏の興亡を題材に、「無常観」をテーマにした軍記物語の最高傑作です。
『徒然草』には「後鳥羽院の時代に、信濃前司行長(しなののぜんじゆきなが)なる人物が『平家物語』を作り、生仏(しょうぶつ)という琵琶法師にこれを語らせた」とあります。しかし、『平家物語』は特定個人の創作物ではなく、その成立には複数の人々の介在があったものと考えられています。
和漢混淆文(わかんこんこうぶん)の勇壮でリズミカルな文体は、武士の活躍する姿を生き生きと表現しています。『平家物語』は琵琶法師によって平曲(へいきょく)として語られ、文字を読めない人びとにも「耳で聞く文学」として広く親しまれました。
『平家物語』以外にも、『源平盛衰記(げんぺいせいすいき)』、『保元物語』、『平治物語』などの軍記物語が作られました。

④ 和 歌
《 新古今和歌集 》
和歌の分野では、後鳥羽上皇が院中に和歌所を設置し、藤原定家・藤原家隆らに命じて『新古今和歌集』を編纂させました。おもな歌人に後鳥羽上皇、藤原良経、慈円、西行らがいます。その洗練された技巧的な歌風は新古今調とよばれます。代表的な作品として、秋の夕暮れを詠んだ「三夕(さんせき)の和歌」を挙げておきましょう(すべて三句切れ・体言止め)。
寂しさはその色としもなかりけりまき立つ山の秋の夕暮れ 寂蓮(じやくれん)
心なき身にもあはれは知られけり鴫(しぎ)立つ沢の秋の夕暮れ 西行
見渡せば花も紅葉(もみぢ)もなかりけり浦の苫屋(とまや)の秋の夕暮れ 藤原定家
しかし、鎌倉時代中期以降になると、それまで盛んだった歌壇も次第に衰えていきました。歌道の師範として朝廷に仕えた定家の子孫も、二条・京極(きょうごく)・冷泉(れいぜい)の3家に分裂して互いに争い、作品自体には見るべきものはなくなっていきました。
《 金槐和歌集(きんかいわかしゅう) 》
3代将軍源実朝は、京都の公家文化に強い憧れがありました。幕府の実権は北条氏らに握られており、将軍としての実権がなかった実朝は、和歌をはじめとする公家文化に耽溺することで、自らの無力感を紛らわせていたのかもしれません。
それを象徴的に示すできごとがありました。足利義兼(あしかがよしかね。北条政子の妹を娶り、北条氏との関係が深い人物です。1154?~1199)の娘との縁談を破棄して、京都から坊門信清(ぼうもんのぶきよ。1159~1216)の娘を迎えたという事実です。
坊門信清は後鳥羽上皇の叔父に当たります。この縁組を通じて実朝も後鳥羽上皇に接近し、上皇を取り巻く華やかな和歌の世界に身を置くことになりました。実朝は『新古今和歌集』の撰者である藤原定家を師と仰ぎました。定家は実朝の求めに応じ、作歌指導のため、歌論書『近代秀歌』(1巻)を実朝に送っています。
ただ、武家の棟梁が、公家文化の中に自ら取り込まれるような行動をとることは、北条氏をはじめ鎌倉御家人たちの目には苦々しいものと映ったことでしょう。
定家を師としながらも実朝は万葉調の歌をよみ、『金槐和歌集(きんかいわかしゅう)』を残しました。書名は「鎌倉(金は鎌の偏をとりました)槐門(大臣の唐名。実朝は右大臣でした)の和歌集」の意です。
箱根の山をうち出(いで)て見れば浪のよる小島あり、供の者に此(この)うらの名は知るやと
尋ねしかば、伊豆のうみとなむ申(まうす)と答侍(こたへはべり)しをききて
箱根路をわが越えくれば伊豆の海や 沖の小島に波のよるみゆ
あら磯に浪のよるを見てよめる
大海の磯もとどろに寄する波 われてくだけてさけて散るかも
なお、明治の俳人であり歌人であった正岡子規(1867~1902)は、「実朝は和歌に於て不朽の業を為すを得たり。政治家として如何(いか)に実朝を貶(へん)するとも、歌人として萬葉以後只一人たるの名誉は終(つい)に之(これ)を没するべからず」(『病牀譫言(びょうしょうせんげん)』)と実朝を高く評価し、次のような和歌を詠んでいます(斎藤茂吉校注『金槐和歌集』1929年(1963年改版)、岩波文庫、P.266~267)。
人丸ののちの歌よみは誰かあらむ 征夷大将軍みなもとの実朝
(歌聖柿本人麻呂以後の歌人には誰がいるだろうか。征夷大将軍の源実朝のみである)
はたちあまり八つの齢(よわい)を過ぎざりし君を思へば愧(は)ぢ死ぬわれは
(28歳という若さで没しながらこれだけのすばらしい作品を残した実朝を思うと、恥ずかしくて死にたくなる)
◆槐門棘路(かいもんきょくろ)
鎌倉幕府の3代将軍源実朝の和歌集を『金槐和歌集(きんかいわかしゅう)』といいます。よく間違えて「金槐」を「金塊」と書いてしまいますが、「金塊」では金のカタマリです。
『金槐和歌集』の「金」は鎌倉のこと。「鎌」という字の金偏をとったものです。また、「槐」はえんじゅの木のこと。中国周代、太師(たいし)・太傅(たいふ)・太保(たいほ)が臣下の最高位で、これを三公(さんこう)といいました。三公の座を定めるのに、朝廷に3本のえんじゅを植えたところから、三公の家柄を「槐門(かいもん)」と呼んだのです。わが国では、三公に太政大臣・左大臣・右大臣をあて、「槐門」をその唐名(とうめい)としました。
実朝は右大臣でした。そこで「鎌倉の槐門の和歌集」すなわち『金槐和歌集』と名づけたのです。
ちなみに周では、公卿(こうけい)の座を棘(いばら)を植えて定めました。公卿は九卿あったので、これを九棘(きゅうきょく)または棘路(きょくろ)といいます。「槐門棘路(かいもんきょくろ)」といえば三公・公卿の異称であり、政界での最高幹部のたとえとなっています。 |
《 山家集(さんかしゅう) 》
西行(さいぎょう。1118~1190)は俗名を佐藤義清(さとうのりきよ)といいました。北面の武士で、和歌の才能にあふれ、文武両道に秀でた人物でした。それが23歳の時、妻子を捨てて突如出家してしまいました。出家の動機は不明です。親友の死が原因とも、高貴な女性との失恋がきっかけともいわれています。
出家後は各地を漂泊(ひょうはく)しつつ、数多くのすがすがしい秀歌をよみました。巧緻(こうち)を極め技巧の限りを尽くした歌風をよしとする当時の風潮の中で、西行は心の琴線(きんせん)に触れた恋のせつなさや雪月花の美しさを、自然恬淡(しぜんてんたん)の歌風で清らかに歌い上げました。藤原定家は歌人としての西行を高く評価し、「慈鎮(じちん)・西行などは歌よみ、その外の人は歌作りなり(真の歌人というのは慈円や西行らを言うのであって、その他の連中は歌作りに過ぎない)」とまで言い切っています(佐佐木信綱校訂『山家集』1928年、岩波文庫、P.7)。
『新古今和歌集』に入撰した歌数94首は、同集入撰者中で最多です。西行の残した和歌集を『山家集(さんかしゅう)』といいます。
ねがはくは花の下(した、もと)にて春死なん そのきさらぎのもち月の頃
(もしも願いが叶うならば、桜の花の下で死にたいものだ。春の2月15日ごろに)
その言葉通り、釈迦涅槃(しゃかねはん。仏陀の命日。2月15日)の翌日に73歳の生涯を終えました。見事というほかありません。

⑤ 随 筆
《 方丈記(ほうじょうき) 》
鴨長明(かものちょうめい。1155?~1216)は、下鴨社(賀茂御祖神社(かものみおやじんじゃ))の神職の子として生まれました。しかし妨害にあって神職の地位にはつけず、不遇のなか出家して京都郊外の日野山に閑居しました。
『方丈記』の書名は、隠棲した草庵(方1丈(ほぼ3m四方)の広さ)に由来します。長明が20代に体験した1180年前後の五大災厄(安元の大火・治承の竜巻・養和の飢饉・元暦の地震という4つの自然災害と、福原遷都による混乱という人災)を回想し、人生の無常を嘆いています。
「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」という無常観を漂わせた冒頭文や、それに続く五大災厄を描いた場面の中でも、養和の飢饉の惨状や福原遷都による平安京の荒廃・人心の移り変わり等を描写した部分が有名です。
《 徒然草(つれづれぐさ) 》
兼好法師(けんこうほうし。1283?~1352?)は俗名を卜部兼好(うらべのかねよし)といい、吉田神社の神職の子として生まれました。朝廷に出仕し、和歌の道にも才能を発揮しましたが、のち出家しました。
『徒然草』は、鎌倉時代末期に兼好の著した随筆集です。冒頭の「つれづれなるままに、日ぐらしすずりにむかひて、心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」が書名の由来となっています。社会や人間を鋭い観察眼と深い洞察力でとらえ、自由で簡潔な文体で記しました。全部で243段から成ります。
内容は、必ずしも思想的に首尾一貫しているわけではありません。先の段で述べたことと矛盾した意見を、後の段で述べていることもあります。しかし、そうした不整合や矛盾はあるにしても、現在の我々でも共感できる意見や感想が多々見られます。それは、時代を超えても変わらない人生の真理を、兼好がとらえているからなのでしょう。
昔より、賢き人の富めるはまれなり。(第18段)
(昔から賢い人で富貴な人は稀だ)
なんぞただ今の一念において、直ちにすることの甚(はなは)だかたき。 (第92段)
(目前の一瞬間において、直ちに実行することは、どうしてこんなにもむずかしいのだろう)
友とするにわろき者七つあり。一つには高くやんごとなき人、二つには若き人、三つには病なく身つよき人、四つには酒を好む人、五つには武(たけ)く勇める兵(つわもの)、六つには虚言(そらごと)する人、七つには欲深き人。よき友三つあり。一つには物くるる友、二つにはくすし(注、医者)、三つには知恵ある友。(第117段)
なお、『方丈記』・『徒然草』に『枕草子』を合わせて、「三大随筆」と称します。

⑥ 説 話
説話文学では『十訓抄(じっきんしょう)』(作者未詳)、『宇治拾遺物語(うじしゅういものがたり)』(作者未詳)、『古今著聞集(ここんちょもんじゅう)』(橘成季(たちばなのなりすえ))、『沙石集(しゃせきしゅう)』(無住)、『発心集(ほっしんしゅう)』(鴨長明)など、多くの作品が生まれました。

⑦ 日記・紀行
京都・鎌倉間を結ぶ東海道の交通が盛んになり、『十六夜日記(いざよいにっき)』(阿仏尼)、『東関紀行(とうかんきこう)』(作者未詳)、『海道記(かいどうき)』(作者未詳)などの作品が生まれました。
《 十六夜日記(いざよいにっき) 》
『十六夜日記』は、藤原為家(ふじわらのためいえ。定家の子。1198~1275)の妻阿仏尼(あぶつに。?~1283)が鎌倉に下った時の旅行記です。実子為相(ためすけ)の荘園(播磨国細川荘)が先妻の子為氏(ためうじ)に奪われたので、訴訟のため鎌倉に旅立ったのです。もともと作者は日記に名前をつけていませんでしたが、日記が10月16日に始まっているので、後世の人が「十六夜」を書名としました。
《 海道記(かいどうき) 》
『海道記』は作者未詳です。作者は、政治の中心として繁栄する鎌倉を一目見たいという希望と、旅によって俗念を一洗したいという念願から旅に出ることを思い立ちました。貞応2(1223)年4月に京都を出立して、2週間後に鎌倉に着き、鎌倉には十数日間滞在しました。しかし、京に残した老母が気になって、早々に帰郷の途についています。
文章は漢文直訳的に訓読しており、かなり生硬で読みにくい文章です。ただ内容は、至る所で農民・漁師・商人などの人々に対し同情する感想を漏らしたり、旅において人生を味わったりと、主観的な思いが書き連ねてあって共感できる点が少なくありません。
《 東関紀行(とうかんきこう) 》
『東関紀行』も作者未詳です。はっきりとは書かれていないので、鎌倉に旅行した目的はわかりません。仁治3(1242)年8月に京都を出立してから10日余りで鎌倉に着き、3カ月ばかり滞在したのち、10月下旬に帰郷するまでを記録した紀行文です。
『東関紀行』の文章は、『海道記』に比べるとよほどの名文です。和文体のよくこなれた文章で、長く後世の普通文の模範となりました。この点において、「東関紀行は我が国の文章史上に重きをなす作品」(玉井幸助校訂『東関紀行・海道記』1935年、岩波文庫、P.144)だと評されます。しかし、内容的には『海道記』ほどの深みはないようです。

源平争乱によって焼失した奈良の諸寺の復興がきっかけとなって、建築・彫刻・絵画等の分野に新傾向が見られるようになりました。
① 建 築
《 大仏様(だいぶつよう) 》
宋に三度渡ったと言われる重源(ちょうげん。俊乗坊(しゅんじょうぼう)。1121~1206)は、復興資金を獲得するために勧進上人(かんじんしょうにん)となって、各地を寄付を募ってまわりました。そして、宋人陳和卿(ちんなけい)の協力を得て、東大寺の再建にあたりました。この時重源が採用したのが大仏様(だいぶつよう)の建築様式です。
この様式は、かつては天竺様(てんじくよう)と称しましたが、「インド様式」と誤解されるというので現在は用いません。大仏様は、使用する部材の種類が少なく、巨大な建造物を建てるのに適した建築様式です。大陸的な雄大さ、豪壮な力強さ・簡潔さが特色です。遺構例としては東大寺南大門(大和、奈良県)、浄土寺浄土堂(播磨、兵庫県)などがあります。ただ、日本人の気風に合わなかったためか、作例はそれほど多くはありません。
《 禅宗様(ぜんしゅうよう) 》
鎌倉中期になると、大陸から禅宗様(ぜんしゅうよう)が伝えられました。この様式は、かつては唐様(からよう)と称しましたが、「中国唐代の様式」と誤解されるというので現在は用いません。禅宗様では細かな部材を組み合わせて、整然とした美しさを表現しました。急勾配の屋根や白木柱・花頭窓(かとうまど)・桟唐戸(さんからど)などを備えているのが特徴です。円覚寺舎利殿(えんがくじしゃりでん。神奈川県)などの禅宗寺院建築に用いられた様式です。禅宗様は、日本人に感受性に合ったためか、受容されて各地に広がっていきました。
《 和様(わよう)・折衷様(せっちゅうよう) 》
伝統様式の和様建築も盛んに造られました。その代表例は、蓮華王院本堂(れんげおういんほんどう。通称「三十三間堂」。長さ125mは宗教建築としては世界最長。京都)や石山寺多宝塔(近江、滋賀県)などです。
また、大陸から伝えられた新様式と和様が融合した建築も生まれました。これを折衷様(せっちゅうよう)といいます。観心寺金堂(河内、大阪府)がその代表例です。

② 彫 刻
奈良の諸寺の復興とともに、そこに安置する大量の仏像の需要がおこりました。そこで活躍したのが、奈良仏師の運慶(うんけい。?~1223)・湛慶(たんけい。1173~1256)父子や快慶(かいけい。?~?)らです。彼らの名前には「慶」の字が共通しているので、この奈良仏師集団を「慶派(けいは)」と称します。彼らが生み出す仏像や肖像彫刻は、躍動的・写実的・個性的・豊かな人間味、という特徴をもっています。
おもな作品に東大寺南大門金剛力士像(運慶・快慶ら)、同僧形八幡神像(快慶)、興福寺無著像・世親像(むじゃくぞう・せしんぞう。運慶)、同天燈鬼・竜燈鬼(てんとうき・りゅうとうき。康弁(こうべん))、蓮華王院千一体千手観音像(湛慶(たんけい))などがあります。
また、肖像彫刻として、六波羅蜜寺空也上人像(康勝(こうしょう))、東大寺重源上人(ちょうげんしょうにん)像、明月院上杉重房(うえすぎしげふさ)像などがあります。
《 東大寺南大門金剛力士像 》
東大寺南大門金剛力士像は、2体とも8メートルを超す巨像ながら、運慶・快慶らを中心とする仏師集団の共同作業により、わずか69日という短期間で完成しました。口を開いているのが阿形像(あぎょうぞう)、口元を結んでいるのが吽形像(うんぎょうぞう)です。ともに寄木造の技法で制作され、それぞれが約3,000にも及ぶ部材によって構成されています。
運慶らは、力士像をいったん完成させたあとも、乳頭やへその位置を下にずらすなど、最終段階までさまざま修正を加えました。力士像を見上げる参拝者に圧倒的な威圧感を与えるよう、最後まで工夫を重ねたのです。

③ 絵 画
絵画では、平安時代末期にはじまった絵巻物が全盛期を迎えました。物語絵や、武士の活躍を描いた合戦絵、民衆に教えを広めるために制作されるようになった縁起物、伝記物などがあります。また似絵(にせえ)、頂相(ちんぞう)などの肖像画も多く描かれるようになりました。
《 絵巻物 》
この時代の絵巻物には、次のようなものがあります。
・物語絵:『紫式部日記絵巻』
『伊勢物語絵巻』
・合戦絵:『蒙古襲来絵巻(竹崎季長絵詞)』
『平治物語絵巻』
『後三年合戦絵巻』
・縁起物:『北野天神縁起絵巻』
『春日権現験記絵(かすがごんげんげんきえ)』(高階隆兼(たかしなたかかね))
『石山寺縁起絵巻』(高階隆兼)
・伝記物:『法然上人絵伝』
『一遍上人絵伝』(円伊(えんい))
『西行物語絵巻』
『鑑真和上東征伝』
・その他:『男衾三郎(おぶすまさぶろう)絵巻』
『地獄草紙』
『餓鬼草紙』
『病草紙(やまいのそうし)』
上記の絵巻物類のうち、蒙古襲来を視覚的にとらえうる当時の史料として『蒙古襲来絵巻(竹崎季長絵詞(たけさきすえながえことば))』(2巻)が特に重要です。この絵巻物は、肥後国(熊本県)の御家人竹崎季長(たけさきすえなが)が、一番駆けの功名と鎌倉への恩賞請求訴訟の経緯を絵師に命じて描かせたものです。
最初は鎮守甲佐(こうさ)大明神に寄進されましたが、のち所有者を転々と代え、明治時代になって皇室に献上されました。「海中に落ちて大魚の腹から出てきた」という伝承があるくらい損傷が激しく、江戸時代にはすでにばらばらになっていました。それらを復元する際に、絵・詞書の前後関係が狂ってしまいました。絵は21枚、詞書は16枚あり、全体に大きさが不統一なので、現在は補紙をあてがって約40cm幅に仕立て直してあります。
日本史の教科書には、竹崎季長が元軍に立ち向かって「てつはう」が破裂している有名な場面の写真が載っていますが、近年「継ぎ目に描かれたモンゴル兵などは後世の補筆ではないか?」という疑問が出されています。
《 肖像画 》
平安時代まで天皇や僧侶の肖像画は描かれることはあっても、その他の個人の肖像を写実的に描くことはほとんどありませんでした。一説に、公家などは呪詛(じゅそ)の手段に使われることを恐れたからともいわれます。
個人の写実的な肖像画を似絵(にせえ)といいます。この分野には、藤原隆信(たかのぶ。1142~1205)・信実(のぶざね。1176~1266)父子の名手が現れました。『法然上人絵伝』には、モデルの法然を前にして見たままを写しとっている(これを対看写照(たいかんしゃしょう)といいます)藤原隆信の姿が描かれています。似絵の作品には、『伝源頼朝像』(伝藤原隆信)、『後鳥羽上皇像』(藤原信実)などがあります。
また、禅宗僧侶の肖像画を頂相(ちんぞう)といいます。「頂(頭部)の相貌(そうぼう)」を写した絵、という意味で、中国宋代に流行しました。わが国には鎌倉時代にもたらされ、頂相彫刻とともに室町時代に全盛期を迎えました。頂相は、外見的特徴を単に写しとっているばかりでなく、モデルである僧侶の高い精神性までもが表現されています(これを伝神写照(でんしんしゃしょう)といいます)。
弟子が一人前になると、師が「自」分の肖像「画」(頂相)に、「自」ら漢文で教訓的・宗教的な「賛」(詩文)を添えて弟子に贈りました。「自画自賛」という言葉は、これに由来します。頂相は直弟子の証明であるとともに、崇拝の対象でした。弟子は頂相によって師の面影を偲(しの)び、師から受けた教えを反芻(はんすう)したのでした。
◆伝源頼朝像
従来、源頼朝像とされてきた神護寺蔵の肖像画が、近年「伝源頼朝像」と呼ばれるようになりました。「別人の肖像画ではないか?」という疑問が呈せられたからです。
別人説によると、「伝源頼朝像は、実際は足利直義(あしかがただよし)像だ」というのです。伝源頼朝像を含むいわゆる「神護寺三像」の残り二人のモデルも、伝平重盛像は足利尊氏、伝藤原光能(ふじわらのみつよし)像は足利義詮(あしかがよしあきら)だと主張されています。そのおもな根拠は3点あります。
第一は、足利直義願文(1345年)に「尊氏・直義の影像を神護寺に納めた」とあることです。同寺の伝平重盛像・伝源頼朝像がそれだ、というのです。
第二は、これら肖像画の描写法に、室町時代に行われた表現技法が多く見られるので、室町時代の誰かを描いた作品だ、というのです。目に瞳を描く、眉や髭を一本一本細かく描く等は室町時代でなければ描けない作品であり、モデルの精神性までを写しとろうとする制作態度(伝神写照)も、室町時代の肖像画の特徴だというのです。
第三に、等持院(とうじいん)にある歴代足利将軍の特徴を写したとされる木造の尊氏像・義詮像に、伝平重盛像・伝藤原光能像が酷似しているという事実です。ですから伝平重盛像は足利直義願文にある「尊氏の影像」に間違いない、というのです。もしもこれが真実なら、伝源頼朝像は「直義の影像」か、または足利氏関係者の誰かの肖像画ということになります。
一方、この肖像画を源頼朝本人とする説も、根強く支持されています。この肖像画は絹地に彩色され、縦143cm、横112.8cmと巨大です。このように、俗人を巨大な絵画に描くことは鎌倉前期までしか見られません。また、絹地の裏から彩色を施す裏彩色(うらざいしき)という平安時代の伝統的技法が用いられているので、鎌倉初期の作品であることに間違いはなく、寺伝通り「源頼朝像」だ、というのです。
|

④ 書 道
書道では、伏見天皇の皇子尊円入道親王(そんえんにゅうどうしんのう。1298~1356)が、従来の書風に宋の書風をとり入れて青蓮院流(しょうれんいんりゅう)を創始しました。入道親王は親王宣下をうけたのち仏門に入った皇子の呼称であり、青蓮院は親王が住した門跡寺院です。青蓮院が京都粟田口(あわたぐち)にあったところから、青蓮院流は粟田口流とも呼ばれました。代表的な作品が『鷹巣帖(たかのすじょう)』です。尊円入道親王が、後光厳天皇(ごこうごんてんのう。兄後伏見天皇の孫)のために書いた習字の手本です。
青蓮院流は、すっきりとしていて読みやすい流麗(りゅうれい)な書法でした。江戸時代になると御家流(おいえりゅう)と呼ばれ隆盛しました。自己流の癖字(くせじ)では読みにくいため、誰にでも読みやすい字体が求められたからです。ワープロのなかった江戸時代には、朝廷・幕府・諸藩の公文書は御家流で書くことを求められ、庶民もまた御家流を学習しました。

⑤ 工 芸
武士の成長とともに、鎧(よろい)・甲冑(かっちゅう)・刀剣など、武具の製作が盛んになりました。
甲冑では明珍派(みょうちんは。粟田口派)、刀剣では長船長光(おさふねながみつ。備前)・粟田口吉光(あわたぐちよしみつ。京都)・岡崎正宗(おかざきまさむね。鎌倉)・郷義弘(ごうのよしひろ。越中)ら名工があらわれ、幾多の名作を残しました。
また、宋・元の強い影響を受けて、各地で陶器生産が発展をとげました。なかでも尾張の瀬戸焼(せとやき)が有名です。今日でも、「瀬戸物(せともの)」が陶器の代名詞となっているほどです。釉(うわぐすり)を用いる瀬戸焼には、道元とともに入宋した加藤景正(かとうかげまさ。加藤四郎左衛門景正から「藤四郎(とうしろう)」と呼ばれました)が創始したとする伝承がありますが、確証はありません。ただ、瀬戸焼に、宋や元の陶器の強い影響が認められることは間違いありません。


