22.鎌倉幕府の成立
「頼朝は武蔵を経て鎌倉に向かった。石橋山の敗戦で安房に没落してからわずか一月余りで、事情はまったく一変した。さきに敵側にあった畠山重忠を先陣とし、千葉常胤(ちばつねたね)を後詰(ごづ)めとし、『凡(およ)そ扈従(こじゅう)の軍兵幾千万(いくせんまん)なるかをしらず』という大軍を率いた頼朝は、十月六日、父義朝の居館趾(きょかんし)もある鎌倉にはいった。
そして同時に、ここを本拠地とするための建設事業を開始した。かつて頼義(よりよし)が前九年の役の戦勝祈願のため、石清水(いわしみず)を勧請(かんじょう)して由比郷に建立した八幡宮を小林郷北山に移して守護神とし、これを中心に頼朝居館以下の施設がととのえられていった。
また数日を経て、十月十一日には政子が伊豆山から迎えられた。訣別(けつべつ)以来『日夜魂を消す』思をつづけた彼女は、はればれしい建設の槌音(つちおと)のひびくあたらしい本拠地に、感激の再会をはたしたのである。」
(永原慶二『源頼朝』1958年、岩波新書、P. 76~77。読みやすくするため、適宜改行した。)
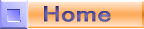
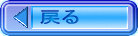


① 反平氏勢力の蜂起
平清盛は後白河法皇を幽閉すると、1180(治承4)年、高倉天皇(たかくらてんのう。1161~1181)と娘の徳子(建礼門院。1155~1213)との間に生まれた外孫、言仁親王(ときひとしんのう。1178~1185)を皇位につけて権力を独占しました。安徳天皇(あんとくてんのう。在位1180~1185)です。この時、天皇はわずか3歳の幼子(おさなご)でした。こうした平氏の専制政治に対して、中央の貴族や大寺院、地方武士団の中には反発が大きくなっていきました。
以上の経緯を見れば、平氏が貴族社会の中で孤立していった理由が、容易に推測できます。
平氏が政権を獲得した方法は、貴族社会で見られた婚姻によって天皇と外戚政策を築くことにあり、その権力の強化には一族による高位高官の独占、知行国・荘園の独占という、新味のない従来の政治手法によりました。しかも、平氏は藤原氏などの伝統的な貴族とは違って、急速に勢力を伸ばした言わば「成り上がり者」でしたから、武力を背景にした強引さが目立ちました。そのため、平氏の急速な進出は、院や貴族、大寺院など旧来の支配勢力との間に軋轢(あつれき)を生む結果となったのです。
この情勢を見て平氏打倒ののろしを最初にあげたのが、以仁王(もちひとおう。1151~80)と源頼政(みなもとのよりまさ。1104~80)でした。
後白河法皇の第三皇子であった以仁王は、平氏打倒の令旨(りょうじ。王の命令)を発して、全国の武士に蜂起をよびかけました。その大意は、「清盛ら平氏一門の暴虐の徒によって国家は滅び、官民は心を悩まし、五畿七道は略奪された。源氏や藤原氏をはじめ、我こそはという勇士は、平氏追討に助力せよ。協力しない者は、平氏一族の同類と見なし、死罪等の罪科に処す」というものでした。参考までに、史料の一部を次に挙げておきます。
清盛法師(注:清盛は出家して浄海(じょうかい)と称しました)並びに宗盛等(むねもりら)、威勢を以(もっ)て凶徒を起し、国家を亡(ほろ)ぼし、百官万民を悩乱し、五畿七道を虜掠(りょりゃく)す。 ( 中略 ) 源家の人、藤氏の人、兼ねては三道諸国の間、勇士に堪(た)ふる者は、同じく与力(よりき)追討せしめよ。若(も)し同心せざるに於(おい)ては、清盛法師の従類(じゅうるい。一族と家来のこと)に准(じゅん)じて、死流追禁の罪過(ざいか)に行ふべし。(『吾妻鏡』1180年4月9日、原漢文)
鵺(ぬえ)退治の伝承(実際にはおどろおどろしい化け物ではなく、トラツグミという小鳥を退治したようですが)でも有名な源頼政は、平等院において、平氏との戦いで戦死してしまいました。以仁王自身も、南都の寺院勢力の協力を得るために移動中、平氏の追討軍のために戦死してしまいます。かくして、以仁王の平氏打倒計画は失敗に終わったのです。
しかし、この呼びかけが端緒となって、打倒平氏の声は燎原(りょうげん)の火のごとく全国に広がっていきました。園城寺(おんじょうじ。三井寺)・興福寺等の僧兵や、平治の乱に敗れて伊豆蛭ヶ小島(ひるがこじま)に流されていた源頼朝(1147~1199)や信濃の源義仲(木曽義仲。1154~84)ら各地に雌伏していた源氏や、平氏に反感を持つ地方武士団が次々と挙兵していきました。
この内乱は全国に広がり、争乱は5年におよびました。これを「治承・寿永の乱(じしょう・じゅえいのらん)」(注)といいます。
(注)源平の争乱があったこの時代は、二つの元号が並び立った時代でした。「治承」は源氏の勢力範囲で使用された元号です。1184年、後白河院政の下で後鳥羽天皇が即位すると「元暦(げんりゃく)」、翌年さらに「文治(ぶんち)」と改元しました。一方、平氏の勢力範囲では安徳天皇政権下で、1181年に「治承」を「養和(ようわ)」、ついで翌年「寿永」と改元しました。平氏は壇ノ浦で滅亡する1185年まで、この「寿永」の元号を使い続けました。

② 福原遷都(1180年6月~11月)
反平氏勢力の動きに対抗するため、平氏は都を一時期、摂津国福原京(ふくはらきょう。現在の神戸市)へと移しました。この地は、平氏が修築した良港大輪田泊(おおわだのとまり。現在の神戸港)があり、日宋貿易の拠点であるとともに、瀬戸内海支配のための平氏の拠点でした。
にわかに持ち上がった遷都発表に右往左往する人々の有様を、鴨長明(かものちょうめい)は『方丈記(ほうじょうき)』に次のように記載しています。
帝(みかど)より始め奉(たてまつ)りて、大臣(だいじん)・公卿(くぎょう)みな悉(ことごと)く移ろひ給(たま)ひぬ。 ( 中略 ) 軒(のき)を争ひし人のすまひ、日を経(へ)つつ荒れゆく。家はこぼたれて淀河(よどがわ)に浮(うか)び、地は目のまへに畠となる。人の心みな改まりて、ただ馬・鞍(くら)をのみ重くす。牛・車を用する人なし。西南海の領所を願ひて、東北の庄園を好まず。 (中略) 古京はすでに荒れて、新都はいまだ成らず。ありとしある人は皆浮雲(ふうん)の思ひをなせり。
(安徳天皇をはじめとして大臣・公卿のすべてが福原京へお移りになった。 ( 中略 ) 軒を並べて建っていた住宅は、日ごとに荒れていった。移築のために家は取り壊されて、その材木は筏(いかだ)に組まれて淀川に浮かび、その跡地はみるみるうちに畠となってしまう。人の気持ちもみな変わってしまい、武家風の馬や鞍ばかりが重視されている。公家風の牛・車を用いる人はいない。平氏の勢力下にある西海道(九州)や南海道(四国)方面の領地を得ることを希望し、源氏の勢力下にある東海道・東山道・北陸道方面の荘園を好まない。 ( 中略 ) 古京(平安京)はすでに荒廃して、新都(福原京)はいまだ完成していない。ある限りの人々は、浮き雲のように落ち着かない気持ちであった。)
しかし、遷都には大寺院(特に延暦寺は、平安京の王城鎮護の役割を担ってきたことにより権威づけられていましたから、遷都には激しく反対しました)や貴族たちの反対が強く、結局半年もたたないうちに都を平安京に戻すことになりました。
なお、還都を行った同年末、清盛は平重衡(たいらのしげひら)に命じ、反平氏派の東大寺・興福寺を焼き討ちにしました。平氏による南都焼き討ちは、かけがえのない多くの文化財を消失させた不幸なできごとでしたが、その一方で、焼亡した堂塔伽藍や仏像の復興・再建に、重源(ちょうげん)や陳和卿(ちんなけい)といった人々や運慶・快慶ら慶派仏師らの活躍する場を提供し、新たな文化を生み出すきっかけの一つになりました(「鎌倉文化」で後述)。

③ 養和の大飢饉と清盛の死
平氏が福原遷都を行った1180年の夏、西日本は大干魃(だいかんばつ)で凶作になりました。そして、その後2~3年間、畿内・西国では飢饉が続きました。これを養和の大飢饉といいます。養和元(1181)年を中心に起こった飢饉という意味です。西日本を勢力基盤としていた平氏は、養和の大飢饉によって大打撃を受けたのでした。
さらには、平氏の中心的存在だった清盛までが、1181年に熱病で亡くなってしまいます。その体熱を冷ますために、石の水槽の中に裸の清盛を入れ、これに冷水を注いだもののすぐさま蒸発して黒煙があがったと、『平家物語』は清盛の熱病のすさまじさを誇張的に伝えています。こうして一代で位(くらい)人臣を極めた平清盛は、「自分の墓には頼朝の首を供えよ」との言葉を遺して病死しました。63歳でした。
◆清盛の熱病
清盛が熱病に罹りました。高熱に苦しむ有様を、『平家物語』は次のように伝えています。
身の内のあつき事、火をたくが如(ごと)し。ふしたまへる所(ところ)四五間(し・ごけん)が内(うち)へ入(いる)ものは、あつさたへがたし。ただのたまふ事とては、「あた、あた」とばかり也。すこしもたゞ事とは見えざりけり。比叡山(ひえいざん)より千手井(せんじゅい)の水をくみくだし、石の舟にたたへて、それにおりてひえたまへば、水おびたゝしくわきあがッて、程(ほど)なく湯にぞなりにける。もしやたすかりたまふと、筧(かけひ)の水をまかせたれば、石やくろがねなンどのやけたるやうに水ほとばしッて、よりつかず。おのづからあたる水は、ほむらとなッてもえければ、くろけぶり殿中(でんちゅう)にみちみちて、炎うづまいてあがりけり。(梶原政昭・山下宏明校注『平家物語(二)』1999年、岩波文庫、P.288)
(からだの中の熱いことは、まるで火を焚いているかのよう。清盛が寝ている側に近づく者は、その熱さに耐えきれぬほど。清盛もただ「熱い、熱い」と言うばかり。これは尋常な病気には見えない(おそらく神仏の祟りではあるまいか)。そこで、比叡山の千手井という井戸から汲み出した水を、石造りの水槽に湛え、そこに清盛を沈めて冷やそうとした。ところが、あまりの熱さのために水はものすごく沸き立って、ほどなく湯になってしまうという有様。清盛の苦痛を少しでも和らげようと、筧(かけい)を使って水をかければ、焼けた石や鉄にかけたかのように水がほとばしって、全く寄せつけない。たまたま清盛に当たった水は、炎となって燃えあがる始末。部屋の中は黒煙で充満し、炎がうずまいて燃え上がる。)
冷水が沸騰して湯になり、はては発火してしまうほどのすさまじい高熱。江戸時代の川柳子は、
清盛の医者ははだかで脈をとり
と、悪のりしすぎた『平家物語』の表現を茶化しています。 |

④ 平氏滅亡(1185年)
清盛の死後、平氏は急速にその勢力を失っていきました。
1183(寿永2)年、北陸から上京する源義仲軍を迎え撃つため、平維盛(これもり)率いる平氏軍が京を出発しました。両軍は加賀・越中の国境にある砺波山(となみやま。倶利伽羅峠(くりからとうげ))で激突し、義仲軍が勝利しました。義仲軍は、両角(りょうつの)に松明(たいまつ)を結びつけた牛の大群を用意し、平氏軍めがけて放つという奇策(火牛(かぎゅう)の計略)によって勝利を得た、とされています。これを「砺波の戦い(倶利伽羅峠の戦い)」といいます。
余勢を駆った義仲軍が入京する前に、平氏の人びとは安徳天皇とともに都を捨てて、勢力基盤である西国目指して落ちていきました(平氏都落ち)。
都落ちした平氏に追い打ちをかけたのが、源頼朝の命令をうけた源範頼(みなもとののりより。?~?)・義経(よしつね。1159~1189)らの軍でした。源氏の兵たちに攻めたてられ、一の谷の戦い(摂津)、屋島の合戦(讃岐)と、平氏は西へ西へと追い詰められていきました。そしてついに1185(文治元)年、壇の浦(長門。現下関市)において滅亡させられてしまったのです。
◆馬を背負った畠山重忠
一の谷合戦の時の話。源義経率いる源氏軍は、崖下にいる平家軍の背後をつこうと、騎馬のままで谷を駈け下りることを決断します。しかし、大事な馬がケガでもしたら一大事。そう考えた畠山重忠は、ヒョイと馬をおんぶして、そのまま岩場を下っていきました。このエピソードをもとに、埼玉県深谷市畠山には、愛馬「三日月」を背負った畠山重忠の銅像まで建っています(「畠山重忠公史跡公園」で検索すると、銅像の写真を見ることができます)。
『源平盛衰記』では、重忠が愛馬を背負って谷を下る場面を、次のように描いています。
手綱(たづな)腹帯(はらおび)より合せて、七寸(しちすん)に余(あまり)て大(おおき)に太(ふと)き馬を十文字に引からげて、鎧(よろい)の上に掻負(かきおい)て、椎(しい)の木のすたち一本ねぢ切(きり)杖(つえ)につき、岩の迫(さこ)しづしづとこそ下けれ。
しかし、いくら大力で知られた畠山重忠であっても、馬を背負って谷を下りる、なんてことができたのでしょうか?
『源平盛衰記』に、重忠の馬は「七寸に余」る馬だったと記されています。中世、馬の体高を表す場合、基準を4尺(約121cm。これを「小馬(こうま)」といいました)とし、これを超える場合には1寸とか2寸とか表記しました。つまり、「七寸に余」る馬というのは、4尺に7寸(約21cm)余を足して、4尺7寸(約142cm)余の馬ということなります。
当時5尺(約152cm)の馬を「大馬(おおうま)」と言いました。重忠の愛馬は、大馬に拳(こぶし)1つ分ほど足りないくらいの大きさだったのです。これは現在のポニーと、ほぼ同じ大きさでしょうか。
ポニーと同じなら、その体重は300kg前後はあります。20kgほどの鎧(よろい)・甲冑(かっちゅう)を着て、300kgの馬を背負い、足下の不安定な谷を下りていくという芸当が、いくら剛力自慢の畠山重忠だったとしても、到底できたとは思えません。見てきたような嘘をつく、軍記物語のなせる「ハナシ」でしょう。
同じ軍記物語の『平家物語』には、重忠が馬を背負う「ハナシ」は出てきません。また当時、畠山重忠が所属していたのは、源範頼の軍勢だったといいます。そもそも義経の別働隊の中に、重忠はいなかったのです。
【参考】
・村田重幸「中世の馬について」1957年(2014年9月12日、インターネットで検索)
・『源平盛衰記』の引用は「http://www.j-texts.com/sheet/seisuik.html」を参照。 |

⑤ 地方武士団の動き
この治承・寿永の内乱の結末に大きな影響をおよぼしたのが、地方武士団の動きでした。
彼らは、自分たちを長らく「侍(さむらい)」として扱ってきた王朝貴族に、卑屈な従属心がありました。しかしその一方、実力によって地方領主の地位を獲得したという、自負心と独立心をも有していたのです。彼らは、国司や荘園領主に対抗して、先祖伝来の所領支配の安定をはかるとともに、常に所領拡大の機会をうかがっていました。
ただし彼らは、容易に一個の集団としてまとまることができず、統一した意識・行動をとることができませんでした。ですから彼らは、自分たちを超越する存在に、所領支配の保障を求めたのでした。たとえばそれは、天皇、上皇、摂関家、清和源氏、桓武平氏などといった貴種や伝統的権威、名声をもつ人々だったわけです。
しかし、同じ武士仲間だったはずの桓武平氏は、圧倒的な権力・権威を手中にしながらも、地方武士たちのそうした所領保障の期待に、十分には応えてくれませんでした。平氏自身、貴族たちが作りあげた旧来の体制の中でその勢力を伸ばしていったわけですから、平氏の没落は、地方武士団が平氏を見限った結果であると言えなくもありません。
地方武士団の期待に応えた人物は、太政大臣の平清盛ではなく、征夷大将軍の源頼朝だったのです。

① 鎌倉の特徴
平治の乱で敗れた源義朝の子頼朝は、流人として伊豆の蛭ヶ小島(ひるがこじま)で北条時政(1138~1215)の監視下にありました。しかし、反平氏の諸勢力の一つ、東国の諸武士団は、清和源氏の棟梁である頼朝のもとに結集し、もっとも有力な勢力に成長しました。
頼朝は挙兵後まもなく、鎌倉(相模)を根拠地に定めました。鎌倉は、源氏にとって祖先の源頼義以来、源氏にゆかりのある土地でした。
鎌倉は三方を山に囲まれ、南方は相模湾に口を開いた地形をしています。海岸は遠浅で船の着岸ができないため、海上から鎌倉へ攻め入ることは困難です。また、陸地から鎌倉に侵入する場合には、七つの「切り通し」と呼ばれる狭い通路を通るよりほかはありません。このように鎌倉は、攻めるに難く、守るに容易な要害の地でした。

② 鎌倉幕府の成立(1185年)
鎌倉に腰を据えた頼朝は「鎌倉殿(かまくらどの)」と呼ばれました。そして、地方武士団と広く主従関係を確立することにつとめました。頼朝と主従関係を結んだ武士を「御家人(ごけにん)」と言います。頼朝は、関東地方の荘園・公領を支配して、御家人たちの所領支配を保障し、彼らとの絆を強めていきました。
1183(寿永2)年に入り、頼朝は京都の後白河法皇と交渉して、荘園・公領の年貢を頼朝が保障する(戦乱等で徴収できなくなっていた年貢等を京都の荘園領主らに送り届ける)ことを交換条件にして、東海・東山両道の東国支配権の承認を、朝廷から得ることに成功します。これを「寿永二年十月宣旨(じゅえいにねんじゅうがつせんじ)」といいます。なお、北陸道は当時源義仲の支配下にあり、西国は平氏の支配下にありました。
さて、平氏が滅亡した1185年、頼朝の勢力の強大化を恐れた後白河法皇は、弟の義経に頼朝追討を命じました。これを好機ととらえた頼朝は、軍勢を京都におくって法皇にせまり、義経を謀反人として追討する命令を出させました。そして、謀反人追討を口実に諸国には守護を、荘園・公領には地頭を任命する権利を獲得したのです。地頭には1段当り5升の兵粮米(ひょうろうまい。軍事行動費)を荘園・公領を問わず徴収することができるとし、さらには諸国の国衙を実質的に運営している在庁官人の支配権まで獲得しました。
守護・地頭の設置については、武家と公家ではまったく正反対の評価を下しています。守護・地頭の設置を提案した大江広元(おおえのひろもと)の意見に、頼朝は「殊に甘心(かんしん)し、此儀を以て治定す。本末の相応、忠言の然らしむる所なり」(『吾妻鏡』)とべた褒めでしたが、九条兼実(くじょうかねざね)は「凡(およ)そ言語の及ぶ所に非ず(言語道断である)」(『玉葉』)と守護・地頭の設置に激しく反発したのでした。
こうして東国を中心にした頼朝の支配権は、西国にもおよぶこととなり、武家政権としての鎌倉幕府が実質的に確立したのです。
◆幕府とは何か
中国の戦国時代、王に代わって軍の指揮を取った将軍が、戦場で周囲に幕を張って陣営としました。それを「幕府」と呼びました。「府」は役所の意です。
日本では、近衛府や近衛大将の居館、征夷大将軍の居館の中国風のよび方として用いられ、転じて武家政権をさす語となりました。
なお、征夷大将軍は本来は蝦夷を討つための臨時の将軍を意味する令外官の一つでした。源頼朝の就任以後、しだいに武士の統率者の地位を示す官職となっていきました。 |

③ 頼朝、征夷大将軍に就任(1192年)
さて、兄頼朝と対立した義経は、奥州藤原氏を頼って東北に逃れました。藤原秀衡(ふじわらのひでひら)の死後、子の泰衡(やすひら)は頼朝の要求に屈服し、義経を殺してその首級を頼朝のもとに送りました。しかし、頼朝は泰衡を許さず、1189(文治5)年、奥州に軍勢を進めました。そして、奥州藤原氏を滅ぼして、陸奥・出羽2国を支配下におきました。金や名馬の産出を背景に、東北地方に一大勢力を張る奥州藤原氏の存在を、頼朝は許さなかったのです。
1190(建久元)年、頼朝は上洛して右近衛大将(うこのえたいしょう)に就任します。しかし、これはわずか1週間ほどで辞任しました。右近衛大将(右大将)は身分的に高い地位だったとはいえ、単なる親衛隊の隊長に過ぎません。頼朝の目指したのは、全国の武士に動員命令をかけることができる征夷大将軍への就任でした。後白河法皇に籠絡(ろうらく)されることを嫌って辞任したものの、「右大将(右近衛大将)」は頼朝の呼称の一つとして、その後も長く使用され続けます。
そしてついに「法皇御万歳(後白河法皇の死)」の時を迎えます。頼朝の征夷大将軍への就任を阻んでいた法皇が亡くなることにより、1192(建久3)年、頼朝は念願の征夷大将軍の称号を手に入れました。
この後、1333年に滅亡するまでを「鎌倉時代」とよびます。
◆鎌倉幕府の成立はいつか
鎌倉幕府は、武家政権としての体裁・機構を一挙に整えたわけではありません。そのため、鎌倉幕府の成立時期については、下記のように諸説あります。しかし、かつて「イイクニ(1192年)つくろう鎌倉幕府(頼朝が征夷大将軍に就任)」という語呂合わせで覚えた1192年説は、現在では少数派です。
1.1180(治承4)年説…侍所設置(南関東に私的な武家政権が成立した)
2.1183(寿永2)年説…寿永二年十月宣旨(頼朝の東山道・東海道の支配権を朝廷が事実上承認した)
3.1184(元暦元)年説…公文所・問注所設置(幕府の主要機関が設置され、機構・体制が整備された)
4.1185(文治元)年説…守護・地頭設置(幕府支配が諸国に及び、敵対する軍事的勢力が一掃された)
5.1190(建久元)年説…頼朝、右近衛大将に就任(幕府は近衛大将や征夷大将軍の居館のこと)
6.1192(建久3)年説…頼朝、征夷大将軍に就任(幕府は近衛大将や征夷大将軍の居館のこと)
|

④ 幕府の支配機構
幕府の支配機構は、簡素で実務的なものでした。重要なのは中央機関として置かれた侍所(さむらいどころ)、公文所(くもんじょ)、問注所(もんちゅうじょ)の三つです。
侍所は御家人を組織し統制する機関で、別当(長官)には東国御家人の和田義盛(わだよしもり)が任じられました。東国における軍事政権の樹立を特徴づけるものとして、重要な機関です。
公文所(のち政所(まんどころ))は一般政務や財政事務をつかさどる機関で、別当には貴族の大江広元(おおえのひろもと)が任命されました。
問注所は、裁判事務を担当する機関で、執事(長官)には貴族の三善康信(みよしのやすのぶ)が任命されました。
武家政権である鎌倉幕府で、なぜ、京都の貴族出身者が政務・裁判の仕事を任されたのでしょうか。それは鎌倉武士の教養の低さに起因します。何しろ当時の武士たちは実務には素人で、自分の名前すら書けない者たちもいたのですから。実務官僚としての能力を、頼朝は大江広元や三善康信に期待したのです。
◆実務官僚、大江広元
東国に武家政権を打ち立てた源頼朝は、多くの実務官僚を必要としました。その一人が大江広元(1148~1225)です。「成人後は泣いたことがない」といわれる広元には、冷徹な人物というイメージがあります。しかし、際立った政治的センスをもつ有能な人材だったことは間違いありません。
広元は中原氏の養子になり、長く中原広元を名乗り、のち大江氏に姓を戻しました。大江氏・中原氏ともに朝廷の実務官僚を務める家柄で、広元自身朝廷の外記(げき。太政官の文筆官僚)職を務めたのち、義兄が頼朝の知り合いだった縁から関東に下向し、頼朝の右筆(ゆうひつ。手紙の代筆者)になりました。
広元は頼朝と御家人をつなくパイプ役となり、頼朝・朝廷間の交渉にも深く関わりました。守護・地頭の設置の立案や、朝廷との折衝(せっしょう)にあたったのも広元でした。公文所の初代別当、政所の初代別当に任ぜられ、「関東の爪牙耳目(そうがじもく。武家政権の手足となって働く者)」として行政実務の中心的役割を果たしました。
【参考】
・上杉和彦氏による-『週間 新発見!日本の歴史06・鎌倉時代1』2013年8月4日号、朝日新聞出版、P.7- |

⑤ 守護と地頭
諸国には守護が、荘園には地頭がおかれました。
《 守 護 》
守護は当初、惣追捕使(そうついぶし)や国地頭(くにじとう)などともよばれました。
守護は原則として各国に一人ずつ、主として東国出身の有力御家人が任命されました。守護としての得分(給与)はありません。主な職務内容は軍事と警察です。平時には国内の御家人を指揮して治安維持と警察権の行使にあたり、戦時には武士の統率にあたりました。
平時の守護の職務で最も重要なものは、大犯三カ条(だいぼんさんかじょう)です。大犯三カ条は、京都大番役(きょうとおおばんやく)の催促、謀叛人の逮捕、殺害人の逮捕の三つをいいます。
京都大番役は、天皇の居所である内裏や院御所にある諸門を警固する御家人の奉公の一つです。有力御家人は幕府から直接命令を受け、一般御家人は守護から催促を受けて(これが大番催促です)上京しました。京都では京都守護(のちに六波羅探題(ろくはらたんだい))の統括のもと、守護が御家人を指揮して、6カ月間(あるいは3か月間)、警固の任務に当たりました。務めが終わると、御家人には覆勘状(ふっかんじょう)という終了証明書が交付されました。
京都大番役にならって整えられたのが、鎌倉番役です。鎌倉番役は、東国御家人が1~2カ月交代で、将軍の御所や諸門の警固に当たりました。
なお、守護は在庁官人を支配し、とくに東国では国衙(こくが)の行政事務を引き継いで、地方行政官としての役割も果たしました。
《 地 頭 》
そもそも地頭は、1185年に源義経ら謀反人・凶徒等の追討を口実に「荘公を論ぜず(荘園・国衙領の別を問わず)」設置されたものです。
しかし、荘園領主は地頭の設置に激しく反発しました。武士というよそ者の荘園進入を許し、さらには「兵粮米(ひょうろうまいい)徴収」という名目で、荘園領主の収入の一部までもが奪われてしまうからです。結局、地頭の設置範囲は、平家没官領(へいけもっかんりょう。平氏から没収した荘園)や謀反人・凶徒等から没収した所領に限定せざるを得ませんでした。
平家没官領はのちに関東御領(かんとうごりょう)と呼ばれる頼朝の荘園になります。関東御領や、関東御領以外の所領で頼朝が地頭補任権を有する関東進止所領(かんとうしんししょりょう)等にも地頭が置かれました。
地頭の職務は、荘園の下地(したじ。土地)管理、荘園内の治安維持、年貢等の徴収等で、徴収した年貢等は荘園領主のもとへ送付しました。地頭の得分(給与)は、1185年時点では1段につき5升の兵粮米でしたが、承久の乱後に設置された新補地頭では、新補率法という得分規定によって収入が決められました(後述)。
それまでの在地管理に当たっていた荘官の多くは、頼朝から新たに任命を受けた地頭となりました。よほどの失態がない限り、地頭職(じとうしき)とそれにともなう収入が保障されたのでした。これを所職安堵(しょしきあんど)といいます。
のちに地頭は荘園侵略を進め、しばしば荘園領主と紛争を起こすようになります。なお、「泣く子と地頭には勝てぬ」という諺は、地頭の横暴さから生まれたものとよくいわれますが、ここでいう「地頭」は江戸時代の旗本・代官などのことで、鎌倉時代の地頭の実態を示すものではありません。
◆執念深い頼朝
軍事政権を打ち立て、「鎌倉殿」として専制的権力を強めていった源頼朝。しかし、頼朝には頭痛の種がありました。それは、京都の公家政権から位階官職をもらい、それを誇るという鎌倉武士たちの権威主義。
御家人が官職に就く場合には、頼朝が該当者を推薦し、しかるのちに京都方が任命するというルールがありました。ところが、頼朝の推薦を受けずに多くの関東武士が直接、朝廷の官職に就任したのです。これでは、ほかの御家人たちにしめしがつきません。勝手に任官した御家人らに対する頼朝の怒りには、すさまじいものがありました。
1185(文治元)年4月、頼朝は彼らの本国帰還を禁止しました。そして、尾張国の墨俣川(すのまたがわ)以東に足を踏み入れた者は、本領を没収した上斬罪(ざんざい)に処すと宣告したのです。さらには、該当者のリストには一々、悪口までが書き添えられています。
たとえば、「兵衛尉(ひょうえのじょう)義廉(よしかど)」のところには、次のような書き込みがあります。
「鎌倉殿(頼朝)はひどい主人だ。それにひきかえ、木曽殿(義仲)はよい主人だから、仲間ともども木曽殿のもとへ馳せ参じよう」「鎌倉殿に仕えても、どうせ最後は落人(おちうど)になるのが関の山」などと、憎まれ口を叩いていた義廉。そんなことも忘れたのか。この「悪」兵衛尉め!
ほかの御家人に対しても、「目ハ鼠眼(ねずみまなこ)」だとか、「色ハ白ラカニシテ、顔ハ不覚気ナルモノ」だとか、「顔ハフハフハ」だ、などという悪口がずらずら。
九条兼実が「其ノ性強烈」(『玉葉)』)と評した頼朝ですが、その徹底した執念深さには恐怖さえ感じます。
【参考】
・永原慶二『源頼朝』1958年、岩波新書、P.131~132
・龍粛訳註『吾妻鏡(一)』1939年、岩波文庫、P.183~185 |

① 封建制度
幕府支配の根本となった仕組みを封建制度(ほうけんせいど)といいます。封建制度とは、土地をなかだちにした将軍と御家人との主従関係をいいます。鎌倉幕府は、封建制度にもとづいて成立したわが国最初の政権です。
当時はまだ農業社会でしたから、作物を生産したり、薪炭や材木を採取したりする土地が生活の基盤でした。生活のために先祖伝来の所領を死守することに、武士たちは全精力を注ぎました。こうした土地を「一所懸命の地」といいます。文字通り「一つの所に命を懸けた」のです。頼朝は御家人に対し、おもに地頭に任命することによって、こうした先祖伝来の所領の支配を保障しました。これを本領安堵(ほんりょうあんど)といいます。
また大きな功績をあげた場合には、新領を与えることもありました。これを新恩給与(しんおんきゅうよ)といいます。
本領安堵や新恩給与、また所職安堵などのさまざまな御恩(ごおん)に対して、御家人は奉公(ほうこう)の義務を負いました。戦時には軍役を、平時には京都大番役(内裏や院の警固)や鎌倉番役(幕府の警固)、異国警固番役(蒙古襲来によって設定された北九州警固の番役)、関東御公事(かんとうみくうじ。内裏・幕府・寺社などの修造役)などの奉公をつとめたのです。

② 公武の二元支配
鎌倉幕府が成立して、東国に武家の支配権を打ち立てたものの、この時代には京都の朝廷や貴族・大寺社を中心とする荘園領主の力がまだ強く残っていました。
そのため、政治・経済両面において、公武の二元的な支配という特徴が見られます。
たとえば、国についてみると、鎌倉幕府が任命した守護が一国の軍事・警察権を掌握していましたが、行政権は朝廷が任命した国司が握っていました。
荘園についてみると、幕府の補任した地頭が荘園の現地管理を行っていましたが、貴族・大寺社は荘園領主として、土地からの収益の多くをにぎっており、その配下には鎌倉幕府に属さない非御家人の武士たちも多くいたのです。

③ 支配者としての共通性
将軍である頼朝自身も多くの知行国(関東知行国。最大9カ国ありました)や大量の荘園(関東御領。平家没官領 500余カ所以上から成ります)を所有していました。幕府の経済的基盤を見ると、貴族・大寺社など旧来の勢力と変わるところはなかったのです。
共通点は経済面ばかりでなく、政治面においても見られます。幕府と朝廷は支配者としての共通点を有していました。
幕府と朝廷の関係も、新制(しんせい)とよばれる朝廷の法令や宣旨で定められていました。新制というのは、10世紀以後、律令格式編纂後に朝廷が出した特別法のことです。こうした新制は鎌倉時代にも出され、幕府もこれにならって新制とよばれる法を出すようになりました。
幕府は守護・地頭を通じて全国の治安維持にあたり、また年貢を対捍(たいかん。手元に留め置いて納入しない)・押領(おうりょう。力ずくで奪うこと)して荘園領主のもとに送付しない地頭を罰するなど、一面では朝廷の支配や荘園・公領の維持を助けることにもなりました。
しかしその一方で、幕府は東国以外の地方でも支配権を伸長しようとしたために、幕府の派遣する守護・地頭と、朝廷の派遣する国司や荘園領主とのあいだで、次第に軋轢が生じるようになっていきました。やがて、各地で荘園領主の支配下にあった現地の荘官が、鎌倉幕府と主従関係を結び地頭へとかわっていきました。こうして、鎌倉幕府による現地支配力が次第に強まっていくと、公武の対立もそれに伴って深まっていったのでした。
◆大田文(おおたぶみ)
一国内の荘園・公領ごとの田地面積や領有関係などを記した文書を大田文といいます。大田文は、田数帳(でんすうちょう)・図田帳(ずでんちょう)・作田惣勘文(さくでんそうかんもん)などさまざまな名称で呼ばれましたが、本来国衙の土地台帳としてつくられたものです。
しかし、鎌倉時代の大田文には、国司が命じて作成させたものと、幕府が命じて各国守護に作成させたものとの二種類があります。ただし、いずれも場合も、大田文の実際の作成者は国衙の在庁官人でした。この事実は、国衙に対する幕府の支配力の浸透を物語っています。 |


