21.院政期の文化
「そのかみ十余歳の時より今に至る迄(まで)、今様(いまよう。流行歌のこと)を好みて怠る事なし。( 中略 )
昼はひねもす(終日)うたひ暮し、夜はよもすがら唄ひ明さぬ夜はなかりき。夜は明れど戸(と)蔀(しとみ)をあげずして、日出るを忘れ日高くなるをしらず、其(その)声をやまず。大方夜昼をわかず、日を過し月を送りき。( 中略 )
声をわる事三ヶ度なり。二度は法の如(ごと)くうたひかはして、声の出るまで歌ひ出したりき。あまりせめしかば、喉(のど)はれて、湯水通ひしもすぢなかりしかど、かまへてうたひ出しき。或(あるい)は七八五十日、もしは百日の歌など始めて後、千日の歌も歌ひ通してき。昼はうたはぬ時もありしかど、よるは歌を歌ひ明さぬ夜はなかりき。( 中略 )
かくのごとく好みて六十の春秋を過しにき。」
(『梁塵秘抄口伝集』-佐佐木信綱校訂『新訂 梁塵秘抄』1933年、岩波文庫、P. 95~96-による。後白河法皇が今様修行の半生を述懐した部分。旧字体は新字体に改めた。(
)はホームページ作成者が付した注。)
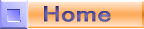
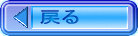


平安末期(11世紀後半~12世紀)に入ると、中央で栄えた国風文化が、地方に普及していきました。その背景には、地方豪族や地方武士の中央進出、貴族の没落等の事情がありました。
また、貴族たちも、庶民や武士たちの間で流行した芸能をおもしろがり、また歌謡や説話の中に武士や庶民の姿を活写するなど、庶民文化や地方文化を積極的にとり込むようになりました。
こうして、院政期には、それまでにない新鮮で豊かな文化が生み出されました。

平安末の文学が、地方の動きや武士・庶民の姿に関心を持っていたことを示す好例として、説話文学と軍記物語があげられます。また、古代から中世への転換点となったこの時代には、歴史への関心が高まり、歴史物語が書かれました。
① 説話文学-庶民が多く登場するようになった-
説話文学というのは、おもに平安末期から室町時代に行われた、神話や伝説等を素材にした文学をいいます。芸術性の高いものではありませんが、当時の庶民の考え方や信仰、生活の有様などを知ることができ、たいへん興味深いものです。
説話文学の代表例が『今昔物語集(こんじゃくものがたりしゅう)』です。『今昔物語集』は、インド・中国・日本から1000余りの説話を集めた全31巻(現存28巻)にものぼる大説話集です。仏教史観に貫かれた説話が多く、それぞれの説話の中に武士や庶民の生活が生き生きと描かれています。

② 軍記物語-新時代の担い手を主人公にした物語-
武士を主人公にした戦争文学が軍記物語です。『将門記(しょうもんき・まさかどき)』と『陸奥話記(むつわき)』が代表的で、ともに作者未詳です。
《 将門記 》
『将門記』(1巻)は、関東で起こった平将門の乱(939~940)の顛末を記したもので、軍記物語の嚆矢(こうし)される作品です。一説に、乱直後の940年、東国でこの乱を実見した人物によって書かれたのではないか、と推測されています。公的文書も多数引用されており、平将門の乱に関する最重要史料です。
ただし、文体が純粋な漢文ではなく、和臭漢文体(わしゅうかんぶんたい)なので、読み下すのは容易ではありません。
《 陸奥話記 》
『陸奥話記』(1巻)は、東北で起こった前九年合戦(1051~62)を題材にした軍記物語です。陸奧の豪族安倍頼時(よりとき)・貞任(さだとう)親子の反乱から筆を起こし、安倍氏征討にあたった源頼義(みなもとのよりよし)・義家(よしいえ)と出羽の豪族清原武則(きよはらのたけのり)らの軍によって鎮圧されるまでを叙述しています。『陸奥話記』も漢文体で書かれています。

③ 歴史物語
平安末には、10世紀に途絶してしまった六国史のあとを書き継ごうとする動きが見られました。たとえば、藤原通憲(ふじわらのみちのり。信西)も、その中の一人でした。鳥羽法皇の内命を受け、通憲が編纂し始めた漢文体の歴史書を、『本朝世紀(ほんちょうせいき)』といいます。しかし、平治の乱によって通憲が死去してしまい、未完成に終わってしまいました。
実際に六国史のバトンを引き継いだのは、従来のような漢文体の歴史書ではなく、和文体の歴史物語でした。『栄花(華)物語(えいがものがたり)』と『大鏡(おおかがみ)』がそれです。
《 栄花(華)物語 》
『栄花(華)物語』(40巻)の作者は赤染右門(あかぞめえもん)が有力視されていますが、確証はありません。和文の編年体で、宇多天皇から堀河天皇に至る前後15代、約200年間のできごとを叙述しています。題名の「栄花(華)」は、藤原道長の栄華を描くことに主題があることを意味します。
《 大鏡と四鏡 》
『大鏡』(3巻本・6巻本・8巻本があります。別名『世継物語』)の作者は不明です。和文の紀伝体で、文徳天皇から後一条天皇に至る14代176年間のできごとを描いています。
雲林院(うりんいん。現在の京都市北区紫野にあった天台宗の寺)の菩提講(ぼだいこう。悟りを求めるために法華経を講説する法会)で、大宅世継(おおやけのよつぎ)と夏山繁樹(なつやまのしげき)いう2老人が昔時を語り、青侍(あおざむらい。年が若く身分の低い侍)がこれにコメントするという趣向です。老人たちが実見した歴史を語るという辻褄合わせのために、彼らの年齢は世継が190歳、繁樹が180歳という、おそろしく長寿に設定されています。
中心になるのは、道長の栄華の叙述です。ただ、同じ道長の栄華を語るにしても、『栄花物語』とは異なり、『大鏡』には藤原氏に対する批判がそこかしこに見られるところに特徴があります。
『大鏡』以降、『今鏡(いまかがみ)』・『水鏡(みずかがみ)』・『増鏡(ますかがみ)』など、「鏡」を名に付す歴史物語が次々と作られました。多くは老人の昔語りという形式をとるこれらの歴史物語群は「鏡物(かがみもの)」と総称されます。上記の『大鏡』以下4つの作品群は、「四鏡(しきょう)」とも呼ばれます。

① 建 築
特定の寺院に所属しない民間の布教者は、「聖(ひじり)」とか「上人(しょうにん)」などとよばれました。諸国を遍歴する彼らによって、浄土教思想は全国に広がっていきました。
浄土教の地方普及を背景に、地方豪族のつくった阿弥陀堂建築や浄土教美術の優品が各地に残されています。
平泉(岩手県)には奥州藤原氏の初代藤原清衡(ふじわらのきよひら)が建てた中尊寺金色堂(ちゅうそんじこんじきどう)が残されています。当時奥州では黄金が豊富に産出しました。そうした経済力を背景に造られた豪華な建造物が、中尊寺金色堂です。内側・外側とも黒漆を塗った上に金箔が押されています。内陣(ないじん)にはきらびやかな装飾が施され、その須弥壇(しゅみだん)の下には、清衡・基衡・秀衡三代のミイラが安置されていました。近年、世界遺産に指定されました。
2代基衡が建立した毛越寺(もうつうじ)や3代秀衡の建てた無量光院(むりょうこういん)は、残念ながら現存してはいません。
陸奥(福島県)の白水阿弥陀堂(しらみずあみだどう)は、藤原秀衡の妹で徳尼(とくに)という女性が、亡夫岩城則通(いわきのりみち)の冥福を祈って建立したものです。奥州藤原氏ゆかりの女性が建立したものなので、「白水」は「平泉」にちなんだもの(「泉」の文字を上下に分解すると「白水」になる)といわれています。
豊後(大分県)に残る富貴寺大堂(ふきじおおどう)は、九州最古の阿弥陀堂建築です。浄土教の地方伝播の典型例の一つです。

② 彫 刻
京都の蓮華王院(れんげおういん。本堂は「三十三間堂」の名で知られています)千手観音像、豊後(大分県)臼杵(うすき)の磨崖仏(まがいぶつ。凝灰岩に大日如来・菩薩などの石仏を彫りだした。全部で62体あり、大部分が平安後期に造られた)などがあります。

③ 絵 画
絵画では大和絵の手法を用いて、絵と詞書(ことばがき)をおりまぜて時間の進行を表現する絵巻物が作られました。この時代に描かれた『源氏物語絵巻』、『伴大納言絵巻(ばんだいなごんえまき)』、『信貴山縁起絵巻(しぎさんえんぎえまき)』、『鳥獣人物戯画(ちょうじゅうじんぶつぎが)』の四つの絵巻を、特に「四大絵巻」といいます。
《 源氏物語絵巻 》
『源氏物語絵巻』は、『源氏物語』を絵巻にしたものです(原形はおそらく10巻程度だったろうとされます)。おそらく、貴族の求めによって描かれたものでしょう。「引目鉤鼻(ひきめかぎばな)・吹抜屋台(ふきぬけやたい)」というを描き方に特徴があります。「引目」というのは直線を引いてそこに瞳をわずかに点ずる目の描き方、「鉤鼻」は平がなの「く」の字形のような鼻の描き方をいいます。物語の舞台が屋内であることが多いため、屋根を取り払って室内を斜め上から俯瞰(ふかん)して描く表現方法の工夫が「吹抜屋台」です。
《 伴大納言絵巻 》
『伴大納言絵巻』(3巻)は、常磐光長(ときわみつなが)の筆になるといわれます。応天門の変(866)に取材した絵巻で、応天門の放火事件の顛末を描いたもの。すさまじい迫力で炎上する応天門や、火事場に集まった多様な身分の野次馬たちの姿を描いた場面、事件の真相解明のきっかけになる子どもの喧嘩を描いた場面などが有名です。子どもの喧嘩の場面には、一つの画面に時間が異なる複数のシーンを描く異時同図法(いじどうずほう)という技法が使われています。
《 信貴山縁起絵巻 》
『信貴山縁起絵巻』(3巻)は、信貴山の中興の祖とされる僧命蓮(みょうれん)にまつわる説話を描いたものです。命蓮が法力によって、強欲な長者の米倉を空中に運び去ってしまう「飛倉(とびくら)」の場面が有名です。浮かび上がった米倉を見て、あわてふためく人々の姿が、生き生きとしかも巧みに描写されています。
《 鳥獣人物戯画 》
『鳥獣人物戯画』は、時期も制作者も異なる甲・乙・丙・丁4巻の絵巻が、『鳥獣人物戯画』の名のもと、一つに集成されたものです。これら4巻の中では、ウサギとカエルの相撲の場面などを描いた甲巻が一番有名です。動物を擬人化して生き生きと描いており、現在でも人気がある作品です。「人間社会を風刺したものだ」とよく言われますが、詞書がないので、実際のところはよくわかりません。絵画に巧みだった鳥羽僧正(とばそうじょう)覚猷(かくゆう)が作者に擬せられていますが、複数にわたる制作者の中に鳥羽僧正がいたという確証はありません。ただ、鳥羽僧正を作者に仮託する伝承から、後世、この種のアニメチックな絵を「鳥羽絵(とばえ)」と称するようになりました。
《 その他 》
地方社会や庶民の生活ぶりを描いているのは、こうした絵巻物ばかりではありません。『扇面古写経(せんめんこしゃきょう)』の下絵にも、庶民の女性や子どもたちの姿などが生き生きと描かれています。
なお、航海の守護神として、平氏の信仰篤かった安芸(あき。広島県)の厳島神社(いつくしまじんじゃ)には、贅(ぜい)をこらした平家納経(へいけのうきょう)が残されています。平氏の栄華と貴族性がしのばれる作品です。

当時流行した民間歌謡を、今様(いまよう)といいます。今様は「当世風」の意です。
後白河法皇は十代の頃から死ぬまで、今様(いまよう)に熱中しました。夜も昼も歌い暮らし、時には歌いすぎて、喉(のど)をつぶすこともありました。今様の名人がいると聞けば、身分の差もかまわずその者の元を訪れ、教えを請うほどの力の入れよう。ついには好きが高じて、今様や催馬楽(さいばら。古代歌謡)などの歌謡を、みずから集大成しようと思い立ちました。これを『梁塵秘抄(りょうじんひしょう)』といいます。最高権力者自らが民間芸能の集成に乗り出すという行為に、この時代の貴族と庶民文化との深い関わりが、象徴的に示されています。
『梁塵秘抄』の中から有名な今様を一つ、次に掲げます。
「仏は常にいませども、現(うつつ)ならぬぞあはれなる、人の音せぬ暁(あかつき)に、ほのかに夢に見え給(たま)ふ。」 (佐佐木信綱校訂『新訂 梁塵秘抄』1933年、岩波文庫.p. 16)
また、本来は田植え時の神事芸能だった田楽(でんがく)や、滑稽を主とした雑芸や歌曲である猿楽(さるがく)などの芸能も、庶民ばかりでなく、貴族のあいだにも流行しました。
◆梁塵(りょうじん)を動かす
後白河法皇が撰んだ『梁塵秘抄』。『梁塵秘抄』の書名は中国の故事に由来します。
中国漢代、魯(ろ)国に虞公(ぐこう)という美声の持ち主がいました。ひとたび歌えば、その響きで梁(はり。柱の上に渡す横木)の上の塵まで動いたといいます。
この故事から、歌声が優れていることや音楽に優れていることを、「梁塵を動かす」とたとえるようになりました。 |


