20.院政と平氏の台頭
「これ皆源氏の勢(せい)なれば、白旗二十余流(ながれ)うたてたり。大宮面(おおみやおもて)には、平家の赤旗三十余ながれさしあげて、勇みすすめる三千余騎、一度に鬨(とき)をどっと作りければ、大内(おおうち)もひびきわたておびただし。鬨の声におどろきて、只今までゆゆしく見えられつる信頼卿(のぶよりきょう)、顔色かわて草の葉のごとくにて、南階(なんかい)をおりられけるが、膝ふるひており兼(かね)たり。…」
(岸谷誠一校注『平治物語』1934年、岩波文庫、P55~56。一部表記を改めた。藤原信頼が武士達の鬨の声に恐怖する場面。このあと信頼は馬から転げ落ちて鼻血を流し、その臆病ぶりに源義朝は信頼を見限ることになる)
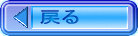


① 新しい中世像-中世のはじまりは院政期から-
昔の日本史教科書は、中世の開始を12世紀末ととらえ、鎌倉時代から記述を始めるのが普通でした(終期は戦国時代の終わり)。ですから、「イイ国(1192年)つくろう鎌倉幕府」という語呂合わせから、授業が始まったのです(最近は、鎌倉幕府の成立は「イイ箱(1185年)つくろう鎌倉幕府」になっていますが)。それは、中世という時代の特徴を、軍事政権の確立(=鎌倉幕府の成立)と、土地をなかだちとした御恩と奉公による封建制度にあると捉えていたからです。
しかし、近年の日本史教科書は、中世の開始期を11世紀中頃からとしています。中世の冒頭は、鎌倉幕府の成立ではなく、院政期であると考えるようになりました。それは、この頃すでに、中世的な諸特徴が明確になってきた、と考える専門家の意見によるものです。

② 中世的な諸特徴とは何か
院政期を中世の始まりと見なす理由は、以下のような中世的な諸特徴が、この時期に出現しているからだといいます。
(1) 政治権力の分散化が見られた。
政治の実権が複数の権力体によって分有され、それぞれが支配権を行使していました。
(2) 武士団が社会に優越しはじめていた。
軍事を専門職掌とする武士団が力を持ち、武家政権の獲得を決定づけ、社会に優越しはじめていました。
(3) 主従制が発達した。
武士団の中には主従制が存在していました。御恩と奉公の関係が成立して、封建制(土地をなかだちとした御恩と奉公の主従関係が成立した社会)の原型がみられました。
(4) 一つの土地に複数の権利が重層的に存在していた。
院政期には荘園公領制(しょうえんこうりょうせい。後述)が確立し、荘園・公領の中に多くの権利が重なって存在する状態が一般的になりました。荘園領主(本家・領家)は下位の者に、土地に対する権利を御恩として与えていました。

① 後三条天皇(ごさんじょうてんのう)の登場
後冷泉(ごれいぜい)天皇には、藤原頼通(ふじわらのよりみち)の娘寛子(かんし)が入内(じゅだい)していましたが、皇子が生まれませんでした。そこで、後冷泉の弟である尊仁(たかひと)親王が皇太子になりました。尊仁親王の父は後朱雀(ごすざく)天皇で、母は三条天皇の娘禎子(ていし)内親王(陽明門院)です。尊仁親王は、藤原氏を外戚としない皇太子でした。
頼通は、藤原氏腹(ふじわらしばら)の皇子が生まれれば、すぐさま尊仁親王を廃太子して、外孫を立太子するつもりだったのでしょう。皇太子の証(あかし)である「壺切の太刀(つぼきりのたち)」を、長年にわたって尊仁親王に渡すのを拒んでいたといわれます。しかし、頼通の望みは絶たれます。藤原氏の娘から、とうとう皇子が生まれなかったのです。
1068年に後冷泉天皇が崩御(ほうぎょ)して、尊仁親王が天皇として即位しました。後三条天皇(1034~73。在位1068~72)です。即位までの間、24年間も皇太子にとどめおかれていたことになります。
藤原氏と外戚関係のない天皇の出現は、宇多天皇以来171年ぶりとなります。天皇の外祖父となることに失敗した頼通は落胆し、関白職を弟の教通(のりみち)に譲って宇治に隠退してしまいました。
36歳という壮年で即位した後三条天皇は、深い学識を有する人物であるとともに、強い意志の持ち主でもありました。
ある時、天皇のブレーンのひとりであった大江匡房(おおえのまさふさ。1041~1111)が、後三条天皇の学識のレベルを人からたずねられました。それに対し、匡房は「大江佐国(おおえのすけくに)と同等でしょう」と答えたといいます。大江佐国は、当代一流の学者のひとりでした。
また、天皇の意志の強さは、いつ皇太子を廃されるかわからない不安な状況の下、長年にわたって学問に励みつつ、藤原氏の圧力に耐え抜いたことからも推測できます。よほど剛直な人物だったと推測されます。
天皇は源師房(みなもとのもろふさ。村上源氏)や大江匡房ら、学識にすぐれた人材を登用し、国政の改革を強力に推進していきました。

② 後三条天皇の施策
《 延久の宣旨枡(せんじます) 》
後三条天皇は斗升法(としょうほう)を制定し、宣旨枡を定めました。その大きさは口が4寸8分平方、深さが2寸4分で、容量は現行の約6合に相当します。
それまでは、枡の大きさが地域によってバラバラで、物資のスムーズな流通を妨げていました。また、大きな枡で米を受け取り、米を支払う時は小さな枡を使用するなどといった不正も行われていました。基準枡を定めることにより、流通の効率化と不正防止がはかられたのです。
宣旨枡は、豊臣秀吉が京枡(きょうます)を制定する16世紀後半まで使用されました。
天皇はまた、市での公定価格を設定して、物価の安定をはかりました。これを估価法(こかほう。1072)といいます。
《 延久の荘園整理令 》
後三条天皇の施策の中で、もっとも重要なものは荘園整理です。当時は荘園が増加して公領(国衙領)を圧迫し、国司の仕事に支障が出ていました。
902(延喜2)年の延喜の荘園整理令が出されて以来、荘園整理令は幾度か発令されていました。しかし、それまでの荘園整理令は、あまり実効がありませんでした。それも当然のこと。荘園整理令を発した中央政府の責任者が藤原氏であり、整理すべき荘園の最大所有者も同じ藤原氏だったのですから。
摂関家領をはじめとする荘園の増大は、国司の仕事を妨げました。太政官符・民部省符という証拠文書がなくても、権力者の威光を笠に着て納税を免れようとしたり、国司が派遣する検田使等の立ち入りを拒否しようとしたりする荘園が跡を絶たなかったからです。
鎌倉時代に藤原氏出身の慈円(じえん)が著した『愚管抄(ぐかんしょう)』には、
「宇治殿(うじどの。藤原頼通のこと)ノ時、一ノ所(いちのところ。摂関家のこと)ノ御領、御領トノミ云(いい)テ、庄園(しょうえん)諸国ニミチテ受領ノツトメタヘガタシ(頼通殿の時、摂関家の所領と称する荘園が諸国に満ちあふれて、受領の務めに支障が出ている)」
と書かれています。
そこで、後三条天皇は、1069(延久元)年に延久の荘園整理令を出して、不正な荘園や成立根拠の不明な荘園の整理を強力に推進しました。具体的には、中央に記録荘園券契所(きろくしょうえんけんけいじょ。「記録所」と略称)を設けて、荘園の所有者からの券契(証拠書類)と国司の報告とをあわせて審査し、1045(寛徳2)年以降に成立した新しい荘園や、それ以前の荘園であっても券契が不分明なものや国務の妨げになるものなど、基準にあわない荘園を停止したのです。荘園として認可されなかった土地は、公領に編入されて課税されました。
たとえば、石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)は34カ所の荘園を所有していましたが、そのうち認められたのは21カ所のみで、残り13カ所の荘園は停止されました。
摂関家が所有する荘園も、例外ではありませんでした。「天皇は頼通の権勢をはばかって、摂関家の荘園を整理令の対象外にした」と言われることがありますが、実際には摂関家の荘園も整理令の対象になりました。藤原氏と姻戚関係のなかった後三条天皇には、藤原氏に対して遠慮する理由はなかったのです。後三条天皇は
「関白摂政ノオモクオソロシキコトハ、帝(みかど)ノ外祖(がいそ。外祖父)ナドナルコソアレ、朕(ちん。天皇の自称)ハナントモ思ハムゾ」(『続古事談』)
と言ったと伝えられています。
当時の最大の荘園領主は藤原氏でした。諸国の国司たちは、その役目柄、藤原氏に対して反感をもっていました。それというのも、藤原摂関家の権威を笠に着て、租税を免れたり、検田使等の立ち入りを拒否したりする荘園と常に対峙(たいじ)していたのは、彼ら受領たちだったからです。彼らは大いに溜飲(りゅういん)をさげるとともに、天皇への信頼を高めていきました。

① 荘園化する公領
荘園整理の結果、荘園と公領(国衙領)とが明確になり、両者の境目には榜示杭(ぼうじぐい)が打たれました。こうして、一国は荘園と公領で構成されていきました。
国司は公領を、郡(ぐん)・郷(ごう)・保(ほ)などの新たな所領単位に再編成しました。それぞれの単位には郡司・郷司(ごうじ)・保司(ほし。ほうし)を任命して徴税を請け負わせました。郡司・郷司・保司には、地方で成長してきた開発領主や地方豪族をあてました。
また国衙では、田所(たどころ)・税所(さいしょ)・調所(ずしょ)などの所(ところ)と呼ばれる行政機構を整備しました。そこでは、目代(もくだい。国司の派遣した代官)が政務を指揮しました。実務には、開発領主や地方豪族を在庁官人(ざいちょうかんじん)に採用して、それぞれの仕事を担当させました。
律令制度のもとでは、一国の内部は「国-郡-里(郷)」の上下関係で構成されていました。しかし、在庁官人らが、公領を私有地のように管理したり、荘園領主に寄進したりしたため、公領は本質的には荘園と何ら変わらないものとなっていきました。

② 荘園公領制の成立
こうして11世紀中ごろには一国の編成は、荘・郡・郷などから成る荘園と、郡・郷・保から成る公領で構成される体制に変化していきました。荘園・公領には多くの権利が重層的に存在し、本家・領家など上位の者が下位の者に権利を御恩として与えるという構図ができあがっていきました。こうした仕組みを、荘園公領制といいます。

③ 荘園・公領の内部構造
荘園や公領の内部では、耕地を名(みょう)という単位に分け、その経営と租税納入を田堵(たと)など有力農民に割り当てました。1年契約が主であった田堵は、しだいに土地に対する権利を強化して名主(みょうしゅ)とよばれるようになりました。
名主は、請け負った名の一部を下人(げにん。隷属農民)に耕作させたり、作人(さくにん。農民)などに耕作させたりしながら、請け負った税を年貢(ねんぐ)・公事(くじ)・夫役(ぶやく)などの形で領主に納入しました。
年貢は米・絹布など、公事は手工業製品や特産物などです。夫役は労役による奉仕です。これは、かつて国司が、田堵に課していた官物(かんもつ)と臨時雑役(りんじぞうやく)の系統を引くものでした。

① 白河上皇の登場
白河天皇(しらかわてんのう。1053~1129。位1072~1086)は、父の後三条天皇にならって親政をおこないました。しかし1086(応徳3)年、突然8歳の善仁(たるひと)親王に譲位したのです。これが堀河天皇(ほりかわてんのう。1079~1107。位1086~1107)です。
譲位した天皇は、太上天皇(だいじょうてんのう。「上皇」と略称)と呼ばれます。その居所は院(または院御所(いんのごしょ))と呼ばれ、転じて上皇その人を指す言葉となりました。
白河は上皇(院)として院庁(いんのちょう)という役所をひらき、天皇を後見しながら政治の実権をにぎる院政の道をひらきました。
当時の人びとは、上皇を「治天(ちてん)の君(きみ)」、天皇を「在位(ざいい)の君」と呼びました。政治の実権は上皇が握っていましたから、天皇は名ばかりの存在でした。当時の人々は、天皇のことを「東宮のごとし(皇太子のように実権がない)」と称したのは、この実態を伝えたものです。
なぜ、白河上皇は、院政をはじめたのでしょうか。白河上皇がこのような挙に出たのは、亡くなった中宮賢子(けんし。28歳で病死)との間に生まれたわが子に皇位を継承させたいという、私的な動機に由来するといわれています。白河には異母弟で、後三条天皇が皇太子に指名した実仁(さねひと)親王がいました。しかし、実仁親王は、やがて疱瘡(ほうそう)で病死してしまいます。その死後、白河は堀河に譲位し、院政を開始したのです。
しかし、白河上皇はまだ安心できませんでした。有力な皇位継承者としてもうひとりの弟、輔仁(すけひと)親王がいたからです。輔仁親王側へ皇位が移る可能性を断つため、白河上皇は堀河天皇を自分の同母妹(篤子(とくし)皇后)と結婚させ、さらにその子に皇位を継承させようと画策しました。
ところが、当時堀河天皇は13歳で皇后は32歳。当然のことながら、この企ては成功しませんでした。
のち、藤原実季(さねすえ)の娘茨子(しし)を堀河の女御(にょうご)に迎え、鳥羽(とば)天皇が誕生します。直系の孫の誕生を、白河は涙を流して喜んだと伝えられています。間もなく堀河天皇が病死すると、鳥羽天皇はわずか5歳で即位し、これまた白河が上皇として後見したのです。
こうして天皇の母方尊属(外戚)を中心とする政治(摂関政治)から、父方尊属(上皇)を中心とする政治体制(院政)へと移ることになりました。
白河上皇の
「政(まつりごと)は叡慮(えいりょ)より出(い)で、全く相門(そうもん。摂関家のこと)によらず」(『中右記』)
という有様でしたから、摂関家の勢力の衰退は明らかでした。院政は白河上皇ののちも、鳥羽上皇・後白河上皇と100年余りも続きました。
◆雨水の獄(うすいのごく)
院政は、白河上皇が自分の子孫に皇位を継承させようと私的動機からはじまったものです。白河上皇は、「意に任せ、法に拘(かか)わらず」(中御門宗忠『中右記』)専制的に政治の実権を行使しました。そうした白河上皇のワンマン振りを象徴的に示すエピソードが「雨水の獄」です。
ある時、一切経の供養を法勝寺(ほっしょうじ)で行おうとしたところ、あいにくの雨。そうした雨天順延の繰り返しに怒った上皇は、容器に雨を集めさせました。そして、それを牢獄に閉じこめてしまったというのです(源顕兼『古事談』(鎌倉期)による)。 |

② 院政期の時期区分
院政を行った上皇は何人もいますが、ここでは平安末から鎌倉初期にかけての白河・鳥羽・後白河・後鳥羽上皇の時代を「院政期」ととらえることにします。
4人の上皇の名前を見ると、保元の乱(1156)を画期として、白河・鳥羽の時期と、彼らの名前に「後」を付けた後白河・後鳥羽の時期に二分できます。
保元の乱については後述しますが、中央政界の権力の帰趨(きすう)を決定づける要素が武力であることを見せつけた事件でした。保元の乱を機に、藤原摂関家から権力を奪って院政を開始した上皇らの警戒の目が、平氏や源氏などの武士へと向かっていきました。後白河は平氏と源氏を争わせてその勢力を削(そ)ぐことに努め、後鳥羽は西面の武士を設置して院の武力を増強し、北条義時追討を掲げて承久の乱(1221)を起こしました。
したがって、「院政期」は、次のようにまとめることができるでしょう。
前期(対摂関家)
白河院政1086~1129 3代43年(堀河・鳥羽・崇徳天皇)
鳥羽院政1129~1156 3代27年(崇徳・近衛・後白河天皇)
〈 保元の乱(1156) 〉
後期(対武士)
後白河院政1158~79、81~92 5代34年(二条・九条・高倉・安徳・後鳥羽天皇)
後鳥羽院政1129~1156 3代23年(土御門・順徳・仲恭天皇)

③ 院政のしくみ
院の家政機関は、院庁(いんのちょう)と呼ばれました。院庁は、院近臣(いんのきんしん)や職員である院司(いんし。別当(べっとう)・年預(ねんよ)・判官代(はんがんだい)など)で組織されました。
院近臣というのは上皇の側近です。その出身は后妃や乳母(めのと)の近親者、受領層・武士層などでした。乳母(めのと)というのは、上皇が幼い頃、その養育にあたった女性のことです。白河上皇は、こうした気心が知れた個人的な知り合いや、荘園整理の断行を歓迎する受領国司たち、藤原氏の官職独占に反感をもつ他氏(村上源氏など)、新興勢力の武士などを支持勢力にとり込んだのです。
上皇の命令は院宣(いんぜん)で行われ、院庁は院庁下文(いんのちょうくだしぶみ)を発給することにより、院知行国や院領荘園の運営にあたりました。
また白河上皇は、僧兵たちの強訴等に対処するため、院に武装集団を組織しました。これを「北面の武士(ほくめんのぶし)」といいます。

④ 法皇たちの仏教帰依-信仰を物量で表現した時代-
白河・鳥羽・後白河の3上皇は仏教をあつく信仰し、出家して法皇(太政法皇)となりました。彼らの仏教への入れ込みようには、すさまじいものがありました。
《 六勝寺(ろくしょうじ)の建立 》
まず、天皇家の御願寺(ごがんじ。祈願を行う寺院)として、「勝」のつく6寺を建てました。これを六勝寺といいます。白河の法勝寺(ほっしょうじ)、堀河の尊勝寺、鳥羽の最勝寺、近衛の延勝寺(えんしょうじ)、待賢門院(たいけんもんいん。藤原璋子)の円勝寺、崇徳の成勝寺(じょうしょうじ)です。
すべて現在の京都市左京区岡崎付近(鴨川東岸)にあり、仁和寺(にんなじ)を総検校(そうけんぎょう。寺の総務を監督する役)としました。
なかでも、法勝寺は「国王ノ氏寺」(『愚管抄』)と呼ばれ、その八角九重の塔は81mの高さに及び、院政期の京を象徴する建築物として威容を誇ったといいます。
《 白河の物量主義 》
六勝寺ばかりではありません。三法皇は多くの大寺院や堂塔・仏像をつくり、盛大な法会をいくどもおこないました。それは、物量主義ともいうべき数量の多さでした。
たとえば、ある人が語った「白河院の御善根(白河法皇が仏教のために寄進・寄付したもの)」として、『中右記』の筆者(中御門右大臣(なかみかどうだいじん)藤原宗忠(ふじわらのむねただ))が書きとめた内容の一部は、次のようなものでした。
絵像5,470余体
生丈仏5体
丈六仏(4.8mの仏像)127体
半丈六仏(2.4mの仏像)6体
等身仏3,150体
三尺以下仏(90cm以下の仏像)2,930余体
堂宇21基
小塔446,630余基
金泥一切経書写 等
これらの数字にどこまで信憑性があるかわかりませんが、すさまじいまでの物量には圧倒されてしまいます。
鳥羽が平忠盛に造営させた得長寿院(とくちょうじゅいん)には千一体の観音像が安置されていましたし、後白河が平清盛に造営させた蓮華王院(れんげおういん。俗称「三十三間堂」)にも千一体の観音像が安置されていました。他の法皇も桁違い(けたちがい)の物量主義であったことには、変わりがありませんでした(村井康彦『日本の文化』2002年、岩波ジュニア新書、P.121~2)。
《 頻繁におこなわれた熊野詣・高野詣 》
また、上皇たちは紀伊(和歌山県)にある熊野三山や高野山(こうやさん)等への参詣=熊野詣(くまのもうで)や高野詣(こうやもうで)などをくり返しました。たとえば、各上皇が行った熊野詣について見てみましょう。
熊野信仰は平安中期頃から盛んになりました。末法思想の流行を背景に、熊野は浄土につながる場所として人々の信仰を集めました。徒歩で、熊野三山(くまのさんざん。本宮本社・新宮速玉(はやたま)大社・那智(なち)大社)を目指して険しい山道をたどることは、篤い信仰心の表れであり、その分御利益も多いと考えられました。
院政期の上皇・法皇たちは頭陀行(ずだぎょう)として、京からの参詣地に至る道中に設けられた王子(熊野信仰の若王子(にゃくおうじ)を勧請して祀ってある土地のこと)をたどりながら、熊野三山(本宮大社・新宮速玉(はやたま)大社・那智(なち)大社)を目指しました。頭陀行というのは行く先々で食を乞い、露宿するなどする清貧な仏道修行のことです。ただし、上皇一行の道中は、お伴(とも)だけでも数千人に及んだといいます。上皇の権威の強大さを民衆に見せつける意味もあったのでしょうが、参詣にかかる費用は莫大でした。
さらに、参詣回数も頻繁でした。白河が9回、鳥羽が21回、後白河が34回、後鳥羽が28回、それぞれ熊野詣を行っています。
◆蟻(あり)の熊野詣
紀州の熊野は、古くから神聖視された土地でした。記紀によれば、八咫烏(やたがらす)に導かれた神武天皇が上陸した地だというのです。
そもそも熊野詣とは、熊野三山(本宮本社・新宮速玉(はやたま)大社・那智(なち)大社)に参詣することをいいます。
平安時代後期以降、浄土教が広く普及する中で、熊野は浄土の地と見なされるようになりました。三山に祀られる神々の本地(本体)はそれぞれ阿弥陀如来(極楽浄土の教主)、薬師如来(浄瑠璃浄土の教主)、千手観音(補陀落(ふだらく)浄土の教主)であると考えられました。僧侶の中には、熊野を補陀落浄土に向かう「補陀落渡海」の出発地と考えて、ウツボ舟(周囲を板で打ち付けた舟)に乗って海に乗り出し、その多くが命を落としたのでした。
また、熊野三山全体を母胎に見立てて、胎内巡りをすることによって穢れが浄化され、魂が再生するとも信じられました。上皇たちにとって、熊野は極楽往生を願う霊場であると同時に、王権の再生をはかる場でもあったのです。
院政期の上皇たちの頻繁な「熊野御幸(くまのごこう)」は、民衆に熊野詣の存在を知らしめる一つのきっかけになりました。中世以降は各地から大勢の参詣者が当地に集まるようになり、その賑わい振りは「蟻の熊野詣(蟻が列をなして巣穴と餌との間を往復する様に見立てたもの)」の諺を生むほどでした。
なお、2013年には紀伊山地(和歌山県・奈良県・三重県)に点在する熊野三山、吉野・大峯(おおみね)、高野山の3つの霊場と、それらを結ぶ参詣道が世界遺産に登録されました(紀伊山地の霊場と参詣道)。 |
《 売位・売官の風潮が強まる 》
造寺・造像・起塔・法会等、仏教関連以外の事業のほか、京都郊外に白河殿(しらかわどの)や鳥羽殿(とばどの)などの離宮を造営するなど、上皇・法皇たちはお金を湯水のように使いました。
こうした莫大な費用を捻出するために、成功・重任などの売位・売官が盛んに行われました。これは、中・下級の貴族にとっては、成功・重任によって財産を殖やす絶好の機会でした。おもに受領層であった彼らは、すすんで上皇に奉仕したのです。
こうして、政治の乱れはますます激しくなりました。

① 院の経済的基盤
先述しましたが、上皇のまわりに集まった人びとは、院近臣(いんのきんしん)と呼ばれました。
院近臣は、后妃や乳母(めのと)の一族など上皇の私的な関係者であったり、身分は低いながらも裕福な受領層や新興の武士団であったりしました。
彼らは、上皇の力添えによって温国(豊かな国)の国司に任命されるなどし、任期中に蓄えた財力によって院に奉仕しました。
院政を支える経済的基盤になったのは、こうした受領層の経済的奉仕のほかに、知行国の制度や寄進地系荘園などでした。また、院や知行国主・国司の私領のようになった公領なども、院の経済的基盤の一つとなりました。
《 知行国の制度 》
知行国というのは、上級貴族に知行国主として一国の支配権をあたえ、その国からの収益を取得させる制度です。知行国主は子弟や近親者を国守に任じますが、彼らは任国には赴任せず、都に住み続けます。現地には代理人である目代を派遣し、任国の支配をおこなわせるのです。これは貴族の俸禄支給が有名無実化したため、貴族の収入を確保するために考え出されたものだといわれています。
院を知行国主とする知行国を、院分国といいます。
《 院に寄進された荘園群-八条院領と長講堂領- 》
院政を支えた財源の一つが大量の寄進地系荘園でした。とくに鳥羽上皇の時代には、院に荘園の寄進が集中しました。上皇はそうした荘園を、近親の女性に譲ったり、寺院に寄付したりしました。
たとえば、鳥羽上皇は美福門院との間に生まれた暲子(しょうし。1137~1211)に、院と同等の待遇を与えました。こうした待遇を得、院号を与えられた三后や内親王たちの女性を女院(にょいん)といいます。八条東洞院(はちじょうひがしのとういん)を居所とした暲子は八条院と称し、両親から大量の荘園を譲渡されました。これらの荘園群は八条院領とよばれ、平安時代末には約 100カ所にのぼり、最終的には220カ所を超えたといわれます。八条院領は、鎌倉末期に、亀山天皇の系譜である大覚寺統に伝領されました。
一方、後白河法皇は大量の荘園を、長講堂に寄進しました。長講堂は、院御所の六条殿内に建立した持仏堂です。寄進された荘園群を長講堂領といい、鎌倉時代初めに約90カ所ありました。長講堂領は、鎌倉末期に後深草天皇の系譜である持明院統に伝えられ、その財政基盤となりました。
荘園の寄進先は「治天の君」たる上皇ばかりか、有力貴族や大寺院に向けられました。こうした中、租税を納入しない不輸の権や、検田使等の立ち入りを拒否する不入の権を持つ荘園が一般化しました。不入の権の中身も、警察権の排除にまで拡大されて、荘園の独立性がますます強まっていきました。

② 中世社会の幕開け
《 世俗化する大寺院と僧兵(そうへい)の横暴 》
大量の荘園を所有した大寺院は、「堂徒(どうと)」とか「大衆(たいしゅう)」などと称した下級僧侶を僧兵として組織しました。僧兵という武装集団を擁した大寺院は、荘園整理を進めようとする国司と争ったり、神木や神輿を先頭に立てて朝廷や院に強訴(ごうそ)して、自らの要求を押し通そうとしました。要求を拒否すれば、仏罰や神罰があたるというアピールです。
興福寺の僧兵は「奈良法師(ならほうし)」とよばれ、春日神社の神木である榊(さかき)を掲げて強訴しました。興福寺は藤原氏の氏寺であり、春日神社は藤原氏の氏神でした。彼らは藤原摂関家の権威を笠に着て、無理な要求を繰り返しました。氏寺・氏神の権威を背景に要求しましたから、藤原氏にとっても彼らの要求を退けることはなかなか困難でした。
興福寺はかつて山階寺(やましなでら)と呼ばれました。藤原氏の権勢を笠に着て、訴訟を起こせばどんな無理難題なことであっても、勝訴することが当たり前でした。そこで、理不尽な事柄を押し通すことを「山階道理(やましなどうり)」というようになりました。『大鏡』にも、「いみじき非道の事も、山階寺にかかりぬれば又ともかくも人もの言はず、山階道理とつけておきつ」と書かれています。
「南都北嶺(なんとほくれい)」といって、興福寺と並び称されたのが延暦寺の僧兵です。「南都」というのは、平安京から見て古都平城京(奈良)が南に位置するので、奈良にある興福寺を指す言葉です。また、「北嶺」というのは、平安京の艮(うしとら)の方角、すなわち東北に位置する比叡山のこと。延暦寺の別称です。延暦寺の僧兵は「山法師(やまほうし)」とよばれ、「奈良法師」同様、乱暴な僧兵として知られました。山法師たちは強訴のたびに、延暦寺の守り神である日吉(ひえ)神社の神輿(みこし)をかつぎ出し、大挙しては京都になだれこむ行為を繰り返しました。
興福寺や延暦寺以外にも、園城寺(おんじょうじ。三井寺)の僧兵団(寺法師(てらほうし)とよばれました)や東大寺の僧兵団などがよく知られています。
こうした僧兵の武力や神仏の威を借りて強訴を繰り返す大寺院に対抗するため、院や貴族たちが登用したのが武士でした。武士たちは、御所や貴族の身辺警護にあたったり、強訴の鎮圧にあたったりしました。こうして、桓武平氏や清和源氏などの有力な武士団が、中央に活躍の場を獲得していくことになるのです。
《 奥州藤原氏の繁栄 》
一方、地方では各地の武士が館をきずいて、一族や地域の結びつきを強めるようになりました。なかでも繁栄したのは、陸奥の平泉を根拠地とした奥州藤原氏でした。
奥州藤原氏は、金・馬などの産物や北方の地との交易で富を築き、繁栄を誇りました。彼らは京都文化の移入に積極的に努め、中尊寺(ちゅうそんじ)・毛越寺(もうつじ)・無量光院(むりょうこういん)などの大寺院を次々に建立し、あたかも阿弥陀如来の仏国土のような世界をつくりあげていきました。
こうして奥州藤原氏は、清衡(きよひら)・基衡(もとひら)・秀衡(ひでひら)の3代 100年にわたって繁栄を誇りましたが、その富強を恐れた源頼朝によって4代泰衡(やすひら)の時に滅ぼされてしまいました(1189年)。
このように院政期には、私的な土地所有が展開して、院や大寺社、武士ら複数の権力体がそれぞれ独自の支配権を行使して、広く権力が分化していくことになりました。軍事専門集団である武士団が力を持ち、実力によって社会を動かそうとする風潮が強まってきました。
政治権力の分散化、武士団の優越、主従制の発達、荘園・公領内における権利の重層性などの特徴をもつ中世社会は、ここにはじまりを告げたのです。

�
① 源平の進出
武家の棟梁として有力なものに清和源氏と桓武平氏がありました。
《 清和源氏 》
源氏は、平忠常の乱、前九年合戦、後三年合戦の緒戦を通じて東国にその勢力を広げ、地方の武士と主従関係を強化していきました。
その結果、東国武士団のなかには、保護を求めて源義家に土地を寄進する者が急増したため、驚いた朝廷は特に源義家を名指しして、義家への土地寄進を禁止したほどでした。さまざまな武勇をうたわれた義家は、ついには院への昇殿を許され、貴族と同じ場に立つほどの威勢を誇りました。
しかしその後、内紛によって、清和源氏はその勢力をやや後退させました。
《 桓武平氏 》
かわって台頭してきたのが、桓武平氏でした。中でも、伊勢・伊賀地方を根拠地とした伊勢平氏は、院と結んで勢力を急速に伸ばしていきました。
その一人、平正盛(たいらのまさもり)は、出雲で反乱をおこして出雲目代を殺害した源義親(みなもとのよしちか)を討ち、武名を挙げました。義親は源義家の子です。
正盛の子の忠盛(ただもり)は、瀬戸内海の海賊平定などで勲功を挙げ、上皇の篤い信任を得ました。忠盛は武士として、また院近臣として、白河上皇や鳥羽上皇に重く用いられました。諸国の受領を歴任し、また日宋貿易に関与して、富勢を誇りました。しかし、人となりは恭謙で、その死に際しては多くの人々がその死を惜しんだと伝えられています。
忠盛の子の平清盛(たいらのきよもり)は、こうした平氏の勢力を「飛躍的」と形容するほどに伸長させました。

② 保元の乱(1156)-「武士の時代」の幕開けとなった事件-
鳥羽法皇には崇徳(すとく)、近衛(このえ)、後白河(ごしらかわ)の男子がいました。天皇となった長子の崇徳は、鳥羽の命によって、在位わずかで近衛(3歳で即位)への譲位を余儀なくされました。鳥羽院政が継続していたため、崇徳は上皇となっても、政治的実権はありませんでした。ほどなく近衛は17歳で病没しますが、鳥羽は次の天皇に後白河を指名しました。崇徳は実子の重仁(しげひと)親王を皇太子に立てたいと願っていましたが、皇太子には後白河の子守仁(もりひと)親王(のちの二条天皇)が立てられたため、崇徳の願いは砕かれてしまったのです。鳥羽法皇の崇徳に対する度重なるむごい仕打ちは、崇徳が後鳥羽の実子ではなく実父を白河(後鳥羽の祖父)とする噂があったため、これを疎んじた結果だったともいわれます。
この皇統の継承問題に、摂関家の内部争いが絡みました。藤原忠実(ふじわらのただざね)には、忠通(ただみち)・頼長(よりなが)の男子がいました。才気に富む弟の頼長を愛した忠実は、兄の忠通に対し、関白職を弟の頼長に譲るよう命じました。これを忠通が拒否したことから、怒った忠実は、忠通から内覧の地位と氏長者の地位を奪って頼長に与えてしまいました。忠実らの仕打ちに対し、忠通は鳥羽法皇の後ろ盾を取り付けて対抗しました。後白河天皇の即位もあって、頼長の関白就任の道は閉ざされました。忠通が鳥羽法皇・後白河天皇と手を結んだため、対抗上、頼長は崇徳上皇と連携することになりました。
1156(保元元)年、鳥羽法皇が死去すると、後白河天皇・藤原忠通と崇徳上皇・藤原頼長と対立は、源・平の武士たちを巻き込んだ争乱に発展しました。
鳥羽法皇の立場を引き継いでいた後白河天皇は、近臣の藤原通憲(ふじわらのみちのり。出家した後は信西(しんぜい)と名乗りました)や忠通の進言によって、平清盛・源義朝らの武士たちを動員しました。義朝の提案を採用して上皇方を夜襲して、これを破りました。
敗れた崇徳上皇は讃岐に流され、上皇に味方した源為義(みなもとのためよし。義朝の父)・平忠正(たいらのただまさ。清盛の叔父)らは処刑されました。死刑の復活は、810年の薬子の変以来346年ぶりのことでした。この戦闘を、保元の乱といいます。
《 乱の影響と意義 》
保元の乱や、後述する平治の乱は、これら以後の戦乱にくらべると短期間で、動員された兵力もわずかな小規模の戦闘でした。しかし、長らく平穏だった平安京の中で戦闘が行われ、放火や殺戮(さつりく)等を目の当たりにした人々の受けたショックは、相当大きなものでした。ために朝廷は、元号選定にあたって、二字の上の文字に「保」と「平」に使用することを忌避することとなりました。この点、現在の「平成」という元号は異例です(尾藤正英『日本文化の歴史』2000年、岩波新書、P.112)。
保元の乱は、貴族内部の争いを武士の実力によって、決着をはかった事件でした。このことは「武者(むさ)ノ世」(『愚管抄』)の幕開けを、人々に強く印象づけることとなりました。

③ 平治の乱(1159)-平氏の政権獲得への道を開いた事件-
保元の乱が終わると、乱の勝者間で不協和音が生じ始めました。院政をはじめた後白河上皇の近臣間における権力闘争と、恩賞の不公平が主な原因でした。
戦後処理に当たった近臣の信西(藤原通憲)は平清盛と姻戚関係を築き、自己の権力強化をはかりました。しかし信西の人事は恣意的だったため、周囲の人々の反感を買うことになりました。
たとえば、近臣で信西のライバルだった藤原信頼(のぶより)は、近衛大将への就任を信西によって拒絶され、信西と激しく対立しました。また、平清盛は播磨守・大宰大弐に就官して要地の国司に昇りましたが、戦功著しかった源義朝は左馬頭(さまのかみ)にとどまりました。
宮中には馬の飼育・調教等を司る馬寮(めりょう)という役所があり、左馬寮(さまりょう)と右馬寮(うまりょう)の二つに分かれていました。左馬頭というのは、左馬寮(さまりょう)の長官のことです。「大した働きもしていない連中が莫大な恩賞に預かり、功績抜群の俺はたかだか馬の飼育係か…」。信西のこうした不公平な人事に、義朝が信西を深く恨んだことは想像に難くありません。
不満を持つ者同士、信頼と義朝はともに手を結び、信西・清盛への反撃の機会をうかがいました。二人は1159年、清盛が熊野詣で京を留守にした隙を狙って挙兵。後白河上皇と二条天皇を幽閉し、信西を殺害したのです。しかし、すぐさま上皇・天皇は奪取され、清盛の反撃にあった信頼・義朝らは敗北を喫しました。信頼は捕縛されたのち六条河原で処刑。義朝も東国に逃れようとした途中、尾張国で殺され、その子頼朝(よりとも)は伊豆に流されました。この一連の事件を、平治の乱といいます。
この乱の勝利によって平氏の地位と権力は急速に高まり、政権獲得へさらに一歩近づくことになりました。

�
① 平氏の政権獲得
平清盛が、京の六波羅(ろくはら)に邸宅を構えたので、平氏政権を別名「六波羅政権」ともいいます。
平治の乱後、清盛は後白河上皇のもとで急速な昇進をとげ、1167(仁安2)年には武士として初めて太政大臣となりました。その子平重盛をはじめ、一族もみな高位高官にのぼり、その権勢は並ぶものがないほどでした。その絶頂の有様を伝えるのが、
「此一門(このいちもん。平氏一門)にあらざらむ人は皆人非人(にんぴにん)なるべし」
という、平時忠(清盛の妻時子の弟)の言葉(『平家物語』)です。何と驕(おご)りたかぶった言葉ではないでしょうか。
平氏が繁栄したのには理由がありました。この時代には、あちらこちらで地方武士団の成長が見られました。西日本を中心に勢力基盤を築いてきた平氏は、地方の武士たちを荘園や公領の地頭に任命しました。地頭とは、現地の実質的な支配者でした。こうして平氏は、畿内から九州にかけての武士たちを家人とし、これを支配下に置くことに成功したのです。
武家の棟梁として西国一帯の武士たちに君臨した平氏でしたが、新興の武士勢力としての顔を持ちながらも、貴族的な性格も色濃く有していました。たとえば、清盛は娘徳子(建礼門院)を高倉天皇に中宮として入内させ、後白河上皇と姻戚関係を結びました。徳子が生んだ男子が即位する(安徳天皇)と、外戚として権力を振るいました。これは、かつての摂関家の外戚政策と同じです。
平氏を経済的に支えたのも、従来の貴族たちの経済基盤と同じ知行国や寄進地系の荘園などでした。『平家物語』には
「日本秋津嶋(あきつしま)は纔(わずか)に六十六箇国、平家知行の国卅(さんじゅう)余箇国、既(すで)に半国にこえたり。其外(そのほか)庄園・田畠いくらといふ数を知ず」
と書かれていますが、平氏全盛期には、日本全国の約半分が平氏の知行国であり、500カ所余りにのぼる荘園が平氏のもとに集中していたといいます。

② 日宋貿易の発展
このほか、平氏の経済的基盤として見逃せないのが、日宋貿易の利益です。平氏は忠盛以来、日宋貿易にも力を入れてきました。
11世紀後半以降、日本と高麗・宋とのあいだで商船の往来が活発となりました。12世紀になると、中国の北方に女真人が金を建て、宋を圧迫するようになりました。南に移って南宋となって以降、日本と南宋間で盛んに通商が行われるようになりました。
これに対応して清盛は、従来北九州までにとどまった宋船を、瀬戸内海を経て、平安京近くまで引き込もうと考えました。そこで、摂津の大輪田泊(おおわだのとまり。現在の神戸港)を修築するとともに、瀬戸内海航路の安全をはかるため、交通の難所であった音戸の瀬戸(おんどのせと)を開削したのです。こうして清盛は、積極的に宋商人の畿内への来航を促し、日宋貿易の発展をはかったのでした。
日宋貿易では、日本からの輸出品は、金・水銀・硫黄・木材・米・刀剣・漆器・扇などでした。宋からの輸入品は、宋銭や陶磁器(青磁・白磁)・香料・薬品・書籍(太平御覧(たいへいぎょらん)など)などでした。このうちの香料・薬品類は、もともとは東南アジア産のものです。
輸入品の中では、我が国の経済に大きな影響を及ぼした宋銭が、特に重要です。

③ 平氏に対する反発
平氏は高位高官を独占してその権力の強化・拡大をはかったために、そこからこぼれ落ちた旧勢力は平氏に対して強い反感を持ちました。とくに後白河法皇を取り巻く近臣たちとの対立は深く、ついに鹿ヶ谷(ししがたに)の陰謀事件が起こりました。
1177(治承元)年、京都郊外の鹿ヶ谷にあった僧の俊寛の別荘に、藤原成親(なりちか)ら近臣たちが集まり平氏打倒の密謀を練ったというのです。どのような計画だったのかわかりませんが、もしかすると気の置けない仲間内の酒席に気がゆるんで、声高に平氏打倒を叫んだだけなのかも知れません。
しかし、事件は密告によって平氏の耳に入るところになり、関係者は処罰されてしまいました。なお、この時、鹿ヶ谷には後白河法皇も出席していました。清盛と後白河法皇との対立も、次第に溝を深めていきました。
1179(治承3)年、ついに清盛は、後白河法皇を鳥羽殿に幽閉するとともに、関白をはじめとする多くの貴族から官職を剥奪し、これらを処罰するという強圧的手段に打って出ました。
こうして清盛は、政界の主導権をにぎることに成功しました。しかし、こうした乱暴な手段による権力独占は、かえって院や貴族、寺社、源氏などの反対勢力の結集をうながしました。その結果、平氏の没落をはやめることとなったのです。


