14.平安朝廷の形成
「遊猟を好む桓武は、このころ長岡京周辺の山野にしばしば狩猟に出かけ、新京の候補地を探していたが、793年(延暦12)、山背国葛野郡宇太の地への遷都の方針を発表すると、ただちに建設を開始し、翌794年には自らもそこに移り、「山背国」を「山城国」に改め、新都は「平安京」と名づけられた。 ( 中略 )
795年(延暦14)正月の踏歌節会(ふみうたせちえ)に、貴族たちは「新京楽、平安楽土、万年春」と歌い、新しい都の行く末を祝福し、それが永遠に平安であることを祈ったのである。」
(網野善彦『日本社会の歴史(上)』1997年、 岩波新書、P.173~174)
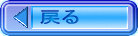


① 桓武天皇と「王朝交替」
光仁天皇(こうにんてんのう。在位770~781)は、行財政の簡素化や公民の負担軽減などにつとめ、律令制の再建を目指しました。
はじめ光仁天皇には、天武天皇の血統をつぐ皇后井上(いのうえ)内親王(717~775)とその子で皇太子他戸(おさべ)親王(761~775)がいましたが、天皇を呪詛(じゅそ)したという疑いによって、排除されました。代わって、光仁天皇と渡来系氏族出身の高野新笠(たかののにいがさ。?~789)との間に生まれた山部(やまべ)親王(737~806)が即位し、桓武天皇(かんむてんのう。在位781~806)となりました。
桓武天皇の即位によって、壬申の乱以来、政権を握ってきた天武天皇の血統が、天智天皇の血統に入れかわったことになります。桓武天皇は、この「王朝交替」の事実を演出し、積極的に政権強化のために利用しました。
(天武系)
天武─草壁皇子─文武─聖武─孝謙(称徳)
(天智系) 天智─施基(しき)皇子─ 光仁 ─桓武
785(延暦4)年、桓武天皇は河内国交野(かたの)(注)で、昊天(こうてん)祭祀の儀式を行いました。昊天祭祀というのは、中国皇帝が都城の南の円丘で、天帝と自分が属する王朝の初代皇帝を祭る儀式です。桓武天皇は「天神(あまつかみ)」とともに父の光仁天皇を祭りました。つまり、父を初代とする新王朝がスタートしたということを、人びとに印象づけようとしたわけです。
また、中国には辛酉(しんゆう)年には大きな変革(革命)が、甲子(かっし)の年には小さな変革(革令)があるという讖緯説(しんいせつ)があり、日本に伝わっていました。王朝交替をアピールする桓武天皇は、辛酉年(781)に即位し、甲子年(784)に長岡京に遷都しました。ちなみに、794年の「平安遷都の詔(みことのり)」は辛酉の日(10月28日)に下しています。
(注)交野(かたの)は現在の大阪府枚方市(ひらかたし)。桓武天皇の母高野新笠の出身母体である百済王氏(くだらのこにきし)の本拠地が交野でした。

② 長岡京遷都(784)
渡来人系で身分が低い母親所生の桓武天皇に対しては、反対者も多かったようです。桓武天皇が即位した翌年(782、延暦1)には、天武系皇親の氷上川継(ひかみのかわつぐ。?~?)という人物が謀叛未遂事件を起こしています。
桓武天皇は、新王朝の基盤を固め、前時代の仏教政治の弊害を断つ(桓武天皇は平城京から新都への寺院移転や建立を禁止しました)意味もあって、平城京からの遷都を決意します。
784(延暦3)年、平城京から山背国乙訓郡(おとくにぐん)長岡村に遷都しました。これを長岡京といいます。
では、なぜ長岡の地が選定されたのでしょうか。その理由を、『続日本紀』(787年10月条)は
「水陸の便あるを以(もっ)て、都を茲(こ)の邑(ゆう)に遷(うつ)す」
と伝えています。長岡は桂川に面し、宇治川・木津川の合流地点に近接していました。また、山陽道・山陰道も通っており、水陸交通の要衝だったのです。
また、渡来人との関係も重要です。桓武天皇の母は百済系渡来人で、その本拠地河内国交野(かたの)は、長岡京のすぐ近くにありました。また、山背国には土木技術に長けた新羅系渡来人の秦(はた)氏が居住していました。彼ら渡来人を造都に利用することを、桓武天皇は念頭に置いていたのでしょう。

③ 造長岡宮使(ぞうながおかぐうし)藤原種継の暗殺(785)
しかし、桓武天皇の権力基盤はまだ不安定で、遷都に反対する根強い抵抗勢力がありました。ついには、天皇の腹心の部下で、長岡京造営の責任者だった藤原種継(ふじわらのたねつぐ。737~785。式家。母が山背国の秦氏出身)が暗殺されるという事件に発展します。
785年のある夜、新都建設の陣頭指揮にあたっていた種継を、いずこからか飛んできた矢が貫きました。犯人として、大伴継人(つぐひと)らが捕らえられました。尋問の結果、種継暗殺事件直前に死去した大伴家持(おおとものやかもち。718?~785)が大伴氏・佐伯氏(さえきし)らとはかり、事に及んだと証言しました。陰謀は種継暗殺にとどまらず、桓武天皇を倒して早良(さわら)親王(750~785。桓武天皇の弟で皇太子)の天皇擁立をはかり、しかも親王自身がこの陰謀に加担していたとする驚くべき内容のものでした。関係者は斬首や配流になるなど、厳しく処罰されました。すでに亡くなっていた大伴家持も官籍から除名処分されました。
早良(さわら)親王は、京内の乙訓寺(おとくにでら)に幽閉されて皇太子の地位を剥奪され、淡路島に護送されました。その途上、親王は絶食して憤死します。無実をアピールする抗議行動だったのかもしれません。しかし、遺体はそのまま淡路島に送られ、彼の地に埋葬されました。
皇太子には、実弟の早良親王に代わり、桓武天皇の嫡子安殿親王(あてしんのう。のちの平城(へいぜい)天皇)が立てられました。

④ 完成しない長岡京
その後、飢饉や疫病が流行し、桓武天皇の周辺では母親(789年死去)や皇后(790年死去)ら親しい人びとがあいついで死去するなど、不幸な出来事が度重なりました。人びとは、早良親王の怨霊によるものと噂し合いました(注)。
こうした中、長岡京の建設工事は、遅々として進みませんでした。
長岡京は土地構造上に欠陥がありました。宮城は丘陵上にあって周囲が傾斜し、京域は低地にありました。丘陵を雛段状に造り替えて、そうした欠陥を少しでも是正しようとした形跡がありますが、当時の土木技術では限界があったようです。いったん雨でも降ろうものなら、雨水が低い建物の中に流れ込んできました。
また、水上交通の便のよさは、水害と隣り合わせでした。事実、長岡京は、しばしば洪水の被害に見舞われました。
さらには、皇太子の安殿親王までが病いに倒れるという事態が起こりました。桓武天皇はついに、長岡京から離れる決心を固めたのです。
(注)792(延暦11)年、早良親王が葬られた淡路島に使者が派遣されてその霊に謝し、墓守が置かれました。桓武天皇が亡くなる際の言葉は「崇道天皇(すどうてんのう。早良親王の霊をなぐさめるためにおくられた名)の奉為(おんため)に、永く件(くだん)の経(金剛般若経)を読ましむ」(『類聚三代格』延暦25年3月17日官符)でした。死の間際まで天皇の心には、亡き弟の怨霊に対する謝罪と恐れが去来していたのです。

④ 平安京遷都(794)
長岡京からの遷都を建議したのは、和気清麻呂(わけのきよまろ)でした。桓武天皇は、清麻呂の意見に従い、794(延暦13)年、山背国葛野(かどの)郡宇太(うだ)村の地に新しい都を造営することにしました。
遷都の詔(『日本紀略』794年10月28日)によると、
「葛野(かどの)の大宮(おおみや)の地は、山川(さんせん)も麗(うるわ)しく、四方(よも)の国の百姓(ひゃくせい)の参出(まい)で来(く)ることも便(たよ)りにして…」
とあります。自然の美しさと交通の便の良さを、遷都の理由にあげています。
それまでの都は、地名を冠して、「難波長柄豊碕宮(なにわながらのとよさきのみや)」とか「近江大津宮(おうみおおつのみや)」とか呼ばれました。しかし、新都が「宇太京(うだきょう)」と呼ばれることはついにありませんでした。「平安京」という命名は、「平安楽土」の現出、すなわち平穏な生活を望む桓武天皇の思いを反映したものでしょう。
遷都とともに、国名の表記も変更されました。「山背国(やましろのくに)」という命名は、長らく都が置かれてきた大和の背後にあったこと由来します。当地に新都が造営されたところから、「山城国」と改められました。山河が新都をとり囲み、自然の要害(城。き)を形づくっているという理由からでした。
これ以後、源頼朝が鎌倉に武家政権をひらくまでの約 400年間を平安時代といいます。

① 奈良時代の東北経営 - 光仁天皇の時代 -
《 城柵を拠点とした東北経営 》
中央政府は、北上川や日本海沿いを北上して、次々と城柵(じょうさく)を設置していきました。城柵は、東北地方の蝦夷(えみし。中央政府に従わない東北の人びと)の動静を監視するとともに、彼らに軍事的圧力を加えるための施設です。城柵には政庁や倉庫などが配置され、平時には行政的な役所として機能しました。その周辺には、関東地方などから農民を移住させ、開拓を進めました。移民は、柵戸(さくこ)とよばれました。こうして、城柵を拠点に、蝦夷の住んでいる地域へ、政府の支配が浸透していったのです。
一方、服属した東北の人びとは俘囚(ふしゅう)と呼ばれました。政府は、彼らを関東以西の各地域に移住させました。
《 伊治呰麻呂(これはりのあざまろ)の乱(780) 》
しかし、帰順したのにもかかわらず、差別されることに対し、俘囚の人びとは強く反発しました。
780(宝亀11)年には、陸奥国伊治郡(これはり(る)ぐん)の郡司だった俘囚の伊治呰麻呂(これはり(る)のあざまろ。?~?)が反乱をおこしました。常日頃から陸奥国牡鹿郡(おしかぐん)の郡司から侮辱されていたことが、反乱に踏み切った理由といわれます。鬱積していた怒りが爆発したのでしょう。呰麻呂は陸奥守紀広純(きのひろずみ)を殺害して多賀城を焼き、反乱は大規模化しました。
以後30数年にわたって、東北地方では、律令政府と蝦夷との戦争が繰り返されました。

② 平安時代初期の東北経営 - 桓武天皇の時代 -
《 阿弖流為(あてるい)の活躍 》
789(延暦8)年、律令政府は紀古佐美(きのこさみ。733~797)を征東大使に任じて大軍を発し、北上川中流、胆沢(いさわ)地方に居住する蝦夷の制圧をはかりました。しかし、蝦夷の族長阿弖流為(あてるい。?~802)の巧妙な戦術により、政府軍は翻弄されます。
阿弖流為の戦い方は次のようなものでした。300人ほどの蝦夷相手に、政府軍が優勢に戦いを進めます。蝦夷の住む村々を放火しながら前進していくと、突然、目の前に新手の蝦夷軍があらわれました。ひるんだ政府軍の背後に、さらに新手の蝦夷たちがあらわれ、挟み撃ちにします。その結果政府軍は大混乱となり、死者25人、溺死者1000人余、矢傷を負った者240人余、裸で泳ぎ帰った者1200人余という大敗北を喫したのでした。政府軍は戦意を喪失したといいます(川尻秋生『平安京遷都 シリーズ日本古代史⑤』2011年、岩波新書、P.36~37)。
こうした手痛い敗北の記憶が、悪路王(あくろおう)伝説(注)を生んだのでしょう。
(注)鎌倉幕府の歴史書『吾妻鏡』には、奥州平泉を本拠にしていたとする「悪路王」に関する記事があります。悪路王は、坂上田村麻呂に成敗されたという伝説上の鬼ですが、阿弖流為が悪路王に転訛(てんか)したのかもしれません。茨城県鹿嶋市の鹿島神宮や同東茨城郡城里町の鹿嶋神宮には、悪路王の木造首級像が奉納されています。
《 坂上田村麻呂の活躍(東北の拠点が「多賀城→胆沢城→志波城」と北進) 》
その後、坂上田村麻呂が征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)となりました。田村麻呂の祖先は、朝鮮半島から渡来したとする阿知使主(あちのおみ)の子孫東漢氏(やまとのあやうじ)だといわれます。田村麻呂の容貌は、赤ら顔で黄色いあごひげを生やし、分厚い胸板をもった武人だったと伝えられています。
田村麻呂は 802(延暦21)年に胆沢城(いさわじょう。岩手県奥州市)を築き、鎮守府を多賀城からここに移しました。
また、阿弖流為ら500余人を降伏させた田村麻呂は、阿弖流為を連れて上京します。田村麻呂は阿弖流為の助命を嘆願しましたが、貴族たちの反対にあい、阿弖流為は処刑されてしまいました。
胆沢城を築いた翌803(延暦22)年、田村麻呂は北上川をさらに上流にさかのぼり、志波城(しわじょう。岩手県盛岡市)を築造しました。志波城は、東北経営の最北端の拠点として機能しました。
日本海側でも、米代(よねしろ)川流域まで、律令政府の支配がおよぶことになりました。
のち嵯峨天皇は、811(弘仁2)年に征夷将軍として文室綿麻呂(ふんやのわたまろ。765~823)を東北に派遣しました。綿麻呂は、徳丹城(岩手県矢巾(やはば)町)を築きました。以後、蝦夷の内民化が進みました。

③ 徳政相論(とくせいそうろん) - 軍事と造作の停止 -
しかし、蝦夷征討と平安京造営という二大政策は、国家財政や民衆にとって大きな負担となっていました。
805(延暦24)年、桓武天皇は「徳政(徳のある政治)とは何か」を重臣たちに下問しました。そこで、参議の藤原緒嗣(ふじわらのおつぐ。774~843)が「今、天下の民が苦しんでいるのは、軍事(蝦夷征討)と造作(平安京造営)である。この二つの事業を停廃すれば、人びとは安んずるだろう」という意見を述べました。同じく参議の菅野真道(すがののまみち。741~814)はこれに反対し、二大政策の継続を主張しました。
桓武天皇は緒嗣の意見を採用し、ついに二大事業の打ち切りを決定します。この議論を「徳政相論」といいます。

① 桓武天皇(在位781~806)の改革
桓武天皇は、貴族をおさえながら積極的に政治改革を進めました。律令制を再建するために「官を省き、民を息(やす)む」方針を示しました。すなわち冗官(じょうかん)の整理と民衆負担の軽減です。桓武天皇の改革は、平城天皇・嵯峨天皇にも引き継がれました。
《 冗官の整理と令外官(りょうげのかん) 》
冗官の整理では、ふえていた定員外の国司や郡司を廃止しました。
その一方、国司交替に際しての事務引継ぎをきびしく監督させるため、勘解由使(かげゆし)を新設しました。
勘解由使は、国司在任中の租税徴収等に不正がない時に、新任国司から前任国司に対して交付される解由状(げゆじょう)授受の審査にあたりました。勘解由使というのは「解由状(役人交代の証明書)を勘判(審査)する役人」という意味です。
勘解由使のように、令に定められていない新設の官職を令外官(りょうげのかん)といいます。
《 健児(こんでい)制の採用 》
民衆の負担で最も重いものは兵役でした。それは「一人点ぜらればその戸が亡ぶ(一人徴兵されると、その家は滅んでしまう)」とまでいわれたほどでした。班田農民による兵士の質が次第に低下したため、792(延暦11)年、陸奥・出羽・佐渡・西海道諸国の等の辺境の要地を除いて、軍団兵士制は廃止されました。
代わって、郡司の子弟や地方有力農民の志願による少数精鋭の騎兵に切り替えました。これを健児(こんでい)といいます。健児は、国の大小・軍事的必要性に応じ、国ごとに20~ 200人の人数を定めてました。そして、60日交替で要地警備・儀仗(ぎじょう)・護衛などにあたりました。

② 嵯峨天皇(在位809~823)の改革》
《 蔵人頭と検非違使の設置 》
嵯峨天皇(在位809~823)は、即位ののち 810(弘仁1)年に、平城京に遷都しようとする兄の平城太上天皇(774~824)と対立し、天皇と太上天皇の双方から命令が出る「二所(にしょ)朝廷」とよばれる政治的混乱におちいりました。
結局、嵯峨天皇側が迅速に兵を出して勝利することによって、この政治的混乱は解消されました。太上天皇は出家し、その寵愛を受けた藤原薬子(?~810。式家)は服毒自殺し、薬子の兄藤原仲成(764~810。式家)は射殺されました。
ちなみに、仲成の処刑後、1185(保元元)年の保元の乱まで、律令政府は死刑を執行しませんでした。政治的不遇のうちに亡くなった人びとは怨霊となって、災いをもたらすと考えられたからです。
従来、仲成・薬子兄妹が、嵯峨天皇を廃して平城太上天皇の重祚を企てた張本人とされ、この事件を「薬子の変」と呼んできました。しかし実際、平城太上天皇の命令がなければ兵の動員などできるものではありません。平城太上天皇の意志によって事件が起こったことは明白です。おそらくは、平城太上天皇に罪が及ばないようにするため、薬子・仲成の二人にすべての罪を帰したのでしょう。現在ではこの事件を「平城太上天皇の変」と呼ぶようになりました。
この事件に際し、秘密が太上天皇側に漏れるのを防ぎ、天皇の命令を迅速に太政官へ伝達するため、新たに秘書官を設けました。この秘書官を蔵人(くろうど)といい、その長官を蔵人頭(くろうどのとう)、役所を蔵人所(くろうどどころ)といいます。初代の蔵人頭には、藤原冬嗣(775~826。北家)と武人の巨勢野足(こせののたり)が任命されました。
蔵人頭になった冬嗣は、これを契機に嵯峨天皇との関係を深め、藤原北家台頭の基礎を築きました。
嵯峨天皇は、また検非違使(けびいし)を設けました。検非違使とは「非違(=違法)を検察・糾弾する役人」という意味で、平安京内の警察に相当します。検非違使はのちには裁判も担当するようになり、京の統治をになう重要な職となっていきました。
《 三代格式 》
嵯峨天皇のもとで、法制も整備されていきました。律令制定後、社会の変化に応じて出された法令が、次第に増加・蓄積されていきました。これらの法令の整理が行われたのです。法令は大きく格(きゃく)と式(しき)の二つに分けられます。
格は律令の規定を補足・修正する法令です。たとえば、723(養老7)年に出された三世一身法は「養老七年の格」と呼ばれました。一方式は、律・令・格をどのように実施するのかを記した施行細則のことです。
嵯峨天皇の時代、格と式とを分類・編集し、弘仁格式が編纂されました。この後さらに、貞観格式(清和天皇時)、延喜格式(醍醐天皇時)がそれぞれ編纂されました。これらをあわせて三代格式といいます。
格は三代の格を集めた『類聚三代格(るいじゅうさんだいきゃく)』が、式は『延喜式(えんぎしき)』が現在に伝わっています。そのほか、国司交替についての規定である交替式が、延暦・貞観・延喜の三代にわたってつくられました。
《 令の注釈書 - 『令義解』と『令集解』 - 》
淳和天皇(在位823~833)の833(天長10)年には、令の解釈を公式に統一した官撰注釈書『令義解(りょうのぎげ)』10巻が清原夏野(きよはらのなつの。782~837)らによって編まれました。これ以後『令義解』は、養老令と同等の法的効果を持ちました。
また、清和天皇(在位858~876)の貞観年間には、惟宗直本(?~?。これむねのなおもと)によって諸家の注釈を広く集めた私撰注釈書『令集解(りょうのしゅうげ)』が編まれました。『令集解』が載せる『古記(こき)』 は唯一の大宝令の注釈書で、現在は失われた大宝令を一部引用しており、たいへん重要です。『令集解』は35巻が現存しています。

① 変わる地方
《 不課口の増加 》
8世紀後半以降、農民たちはさまざまな手段を使って、課役や兵役の重い負担から免れようとしました。たとえば、課役負担する男子を、実際よりも少なく申告する不正がふえていきました。こうした虚偽の記載をした戸籍を、偽籍(ぎせき)といいます。偽籍では、性別ばかりでなく年齢をごまかしたり、逃亡や死亡を隠したりする不正も行われました。課役負担を少なく、そして口分田の班給を多くするように操作したのです。
その結果、不課口(課役負担をしない人)の多い戸籍が増えていきました。
戸籍は、班田収授法を実施する上での基本台帳でしたが、浮浪・逃亡・偽籍等のために、実態とあわなくなっていきました。また、手続きの煩雑さもあって、班田収授そのものの実施も困難になっていきました。
《 桓武天皇の改革 》
このような現状に対し、桓武天皇は、何とか班田収授を励行させようと考えました。そこで、801(延暦20)年、班田期間を従来の6年1班から12年(一紀)1班に改めて、国司の負担軽減をはかりました。また、公出挙の利息を利率5割から3割に減らしたり、雑徭の期間を年間60日から30日に半減するなどして、農民の負担軽減とその維持をはかったのです
しかし、その効果は見られず、9世紀には班田収授が実施されない地域が、次第に増えていきました。

② 土地を占有する有力者たち
不課口の増加は、とりもなおさず、国庫収入の減少に直結します。政府は国家財政の維持が困難になると、国司・郡司たちの租税徴収にかかわる不正・怠慢を取り締まるとともに、財源を確保するために土地を占有してその直接経営に乗り出します。
823(弘仁14)年には大宰府管内で、公営田(くえいでん)を設けます。これは、農民に手当と食料を給付して耕作させ、収穫した稲をすべて官が収公するという方式で、財政を確保したのです。
公営田にならい、中央政府は879(元慶3)年、畿内5カ国に4000町歩に及ぶ官田(正式には「元慶官田(がんぎょうかんでん)」といいます)を設けました。一部は請作、一部は直営方式で、その収益を財政にあてました。
また、中央の諸官司それぞれも、墾田を集めて財源を確保するようになりました。諸官司が所有する土地を諸司田といいます。
このような動きは、皇族や貴族にも及びました。天皇は勅旨田(ちょくしでん)と称する土地を持ち、皇族も天皇から与えられた賜田(しでん)を確保しました。
天皇と親しい少数の皇族・貴族たち(院・宮家・皇親5世以下の王・臣下の諸家)は、私的に多くの土地を集積して勢力をふるうようになり、院宮王臣家(いんぐうおうしんけ)とよばれました。下級官人たちや「富豪の輩(ふごうのやから)」と呼ばれた在地の有力者たちは、その保護を求めて自ら院宮王臣家の勢力下に入っていきました。


