12.平城京の時代
「(天平勝宝4年、752年)4月9日、太上天皇、太后、天皇以下諸王・百官人・僧1万の出席のもとに、宮廷儀礼の諸形式をもとりいれた開眼会が執り行われた。雅楽寮および諸寺の種々の音楽がことごとくもち来らされて、次々に演奏され、また王臣らによって、五節の田舞、久米舞、楯伏、踏歌、袍袴等の内外の歌舞がくりひろげられた。
「仏法東帰より、斎会の儀、未だかつてかくのごとく盛んなるはあらず」(続日本紀巻18)
とまでいわれ、絢爛荘重をきわめた催しであった。国の富、古今東西の技術の粋、そして幾百万の民の力がすべてここに惜しみなく投入され、8年の星霜をへるあいだに、行基たおれ、聖武もついに退位し、幾変遷をみたとはいえ、大仏造顕こそは、天平期におけるわが古代国家の全力量を、まさに、その専制支配の危機克服のために、発現させたものであった。」
(北山茂夫『萬葉の時代』1976年改版(1954年初版)、 岩波新書、P.168)
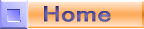
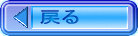


① 遷都の理由
710(和銅3)年、元明天皇(げんめいてんのう。661~721。在位707~715)は藤原京から平城京(へいぜいきょう、へいじょうきょう)へと遷都しました。この後、山背国の長岡京・平安京に遷都するまでを奈良時代(710~784)といいます。
奈良盆地北端の地を選定したのには理由があります。元明天皇は708(和銅元)年2月15日に、次のような遷都の詔(みことのり)を発しました。
「方今(ほうこん)、平城(へいぜい)の地は四禽(しきん)図に叶(かな)ひ…」
四禽とは、中国人が考えた東西南北それぞれ守護する神々のこと。すなわち、この地は「四神(しじん)相応の地」であり、青龍(せいりゅう。東に川)・朱雀(すざく。南に開けており窪地)・白虎(びゃっこ。西に道)・玄武(げんぶ。北に丘陵)の四神に相当する地形が、それぞれの方位に位置するめでたい地相だというのです。
もっとも奈良盆地は、もともと古代の重要な陸路(上つ道・中つ道・下つ道)・水路(木津川~淀川)が交わる交通の要衝であったのですが。
しかしながら、造営からわずか16年しか経っていないのに、藤原京を捨てて新都に遷ったのはどうしてなのでしょうか。
これには、都市プランの誤りを正すということが、その理由の一つにあったと考えられます。
藤原京は、遣唐使の派遣がちょうど中断されていた時期に、『周礼』など中国文献のみを参照して造られました。長安の都城制を実見せずに造られた都だったのです。そのため、702(大宝2)年に派遣された遣唐使たちは、藤原京と長安との決定的な相違に気づかされたはずです。たとえば、藤原京の宮城は京域中央にありましたが、長安では北端に位置していました。
ですから、当時の為政者たちは、律令体制の完成にやっとこぎつけたのにこれではまずい、と思ったのでしょう。そこで、律令体制の充実ぶりを内外に誇示するため、長安にならった本格的な都城制を造ろうと考えたのかも知れません。
なお、遷都の直前には「慶雲の飢疫(きえき)」と呼ばれる飢饉がありました。遷都には、攘災招福(じょうさいしょうふく)、すなわち災いをうち払って福を呼び込もう、という意味合いもあったとされます。遷都によって、人心の一新をはかろうとしたのです。
また708(和銅元)年、武蔵野国で自然銅が発見されたことも、遷都にはずみをつけることになったでしょう。鋳造された和同開珎(わどうかいちん)は、造都事業の財源の一つになりました。

② 平城京の街並み
《 条坊制 》
平城京は長安の都城制にならって造られました。条坊制(じょうぼうせい)といいます。どのような計画都市だったのか、順を追って見ていきましょう。
京域は、碁盤目状に東西・南北に直交する道路で区画され、東西の道路は北から南に向かって一条大路(一条北大路・一条南大路)、二条大路、三条大路…九条大路、南北の道路は中央にある朱雀大路(すざくおおじ)から外側に向かってそれぞれ一坊大路、二坊大路、三坊大路・四坊大路というように命名されました。一条北大路(北)・九条大路(南)・四条大路(東・西)は京域の一番端なので「京極(きょうごく。京の極みの意)」といいます。
条坊制によると、長屋王の邸宅の位置は「左京三条二坊」、唐招提寺の位置は「右京五条二坊」と表示できます。田地の土地割り制度である条里制に似て、位置の把握にはたいそう便利な仕組みです。
ところで、平城京は長安をお手本にして造られたわけですが、長安とは決定的な差異がありました。それは、長安城が城壁に囲まれていたのに対し、平城京には城壁がなかったことです(朱雀大路の南端には羅城門(らじょうもん)がありますが城壁はありません。羅城門とは、城壁で囲まれている(=羅城)市域内への出入り口(=門)のことです)。その理由として、日本には外敵とすべき異民族がいないこと、内部からの反乱には城壁は役立たないこと、平城京が政治的都市であったこと、などが考えられます。
政治的都市というのは、平城京の街並みが基本的には宮殿・官庁・官僚住宅等から成り、そこに住む人びとが生産に直接携わらない消費者集団であったということを意味します。そもそも市(いち)がなければ彼らの生活は成り立たなかったわけですから、城壁によって周辺の農村と分断してしまうというのは自殺行為にも等しいことでした。
《 都の中枢は北端に集中 》
都の北部中央には平城宮が位置しました。平城宮には天皇の生活の場である内裏(だいり。雛人形の「お内裏さま」は天皇をモデルにしています)、政務・儀礼の場である大極殿(だいごくでん)や朝堂院(ちょうどういん)、そして二官・八省などの役所がおかれていました。
中央北端に内裏をはじめ重要施設が集中しているのは、「天子南面」という考えによるものです。全宇宙を司る天帝は、宇宙の中心である北極星のもと、紫微垣(しびえん)いう場所にいると考えられました。ですから天子(天皇)も北に座し、南に向かって政治を行うのです。
《 街並みのようす 》
京域は、中央を南北に走る朱雀大路で、東西に二分されます。東側を左京(さきょう)、西側を右京(うきょう)と呼ぶのは、北に座す天皇からみてそれぞれが左手側、右手側に相当するからです。なお、左京から東に張り出した街区は「外京(げきょう)」といい、やや標高の高いこの場所には藤原氏の氏寺である興福寺が建てられました。また、右京の北への張り出し部分は「右京北辺(うきょうきたべ)」または「右京北辺坊(うきょうほくへんぼう)」といいます。
京内には貴族・官人や庶民の住宅が建ち並び、大安寺・薬師寺・元興寺・興福寺、のちには東大寺・西大寺などの大寺院が建てられました。
官人の住宅地域は、上級官人と下級官人で分けられていたようです。宮城近くの五条大路以北には貴族の大邸宅が並び、それより遠い南の地域には下級官人たちの小規模住宅が並んでいました。
なお、平城京の人口は、約10万人あったと考えられています。
《 市と貨幣の流通 》
左京には東市(ひがしのいち)、右京には西市(にしのいち)という官営の市がそれぞれ設けられ、市司(いちのつかさ)がこれを監督しました。市では、地方から運ばれた産物、官吏たちに現物給与として支給された布や糸などが交換されました。
なお、地方の市としては、大和国(現奈良県)の海石榴市(つばきいち、つばのいち)・軽市(かるのいち)、河内国(現大阪府)の餌香市(えかのいち)が有名です。
708(和銅元)年、武蔵国(むさしのくに)から和銅(自然銅)が献上されると、政府は年号を和銅と改め、唐の開元通宝を手本にして、和同開珎(わどうかいちん)を鋳造しました。政府は当初、銀銭・銅銭の二種類を発行しましたが、銀銭はすぐに発行を停止し、銅銭のみを鋳造しました。この後も銅銭鋳造が続き、10世紀半ばの乾元大宝(けんげんたいほう)まで12回にわたって銭貨が鋳造されました。これらを本朝十二銭(または皇朝十二銭)と称します。
銭貨は、官人や宮都造営に雇われた人びとの給与や工賃として支払われ、東西の市での買い物や土地・家屋の売買などに使われるようになりました。政府はさらにその流通促進をめざし、多額の銭貨を蓄えた者に位階を授与する蓄銭叙位令(711年)や、税の銭納制度(調銭)を設けるなどの政策を行いました。
しかし、京・畿内およびその周辺地域の外では、相変わらず、稲や布などを用いた物々交換が広くおこなわれていたのです。
なお、銭貨鋳造は、令外官(りょうげのかん。令の規定にはない新設された官)である鋳銭司(ちゅうせんし、じゅせんのつかさ)がつかさどりました。現在に残る鋳銭司(すぜんじ。山口県山口市)・銭司(ぜず。京都府相楽郡加茂町)などの地名は、その名残りです。

③ 中央と地方
全国的な交通制度としては、都から七道の諸地域へのびる官道(駅路)が整備され、ほぼ16kmごとに駅家(うまや)が設けられました(駅制)。駅路は幅広い直線的な道路で、役人が公用で利用しました。一方、地方では、郡家(ぐうけ)などを結ぶ伝路が網目のように張りめぐされていました。
現在の都道府県庁所在地に相当するのが国府です。国府には、政務や儀礼をおこなう国衙(こくが)が置かれ、国府の近くには国分寺も建立されました。国府は、地方の政治・経済・文化の中心だったのです。また、各郡には郡家が設けられ、郡内における支配の拠点となりました。
政府は、鉄製農具や進んだ灌漑技術を用いて耕地の拡大につとめました。武蔵(むさし)・周防(すおう)では銅、陸奥では金、伊勢では水銀などの鉱物資源が採掘され、貨幣や大仏造立の材料として使用されました。また、納税のための特産品も各地に生まれました。

④ 支配領域の拡大
国力が充実してくると、中央政府は、東北・南西の周辺に向かって支配領域の拡大をはかりました。
《 東北方面-蝦夷(えみし)- 》
政府は東北地方に住む、いまだまつろわぬ人びとを「蝦夷」という蔑称でよびました。
7世紀半ば、蝦夷に対する最前線基地として、日本海側に二つの柵が設けられました。渟足柵(ぬたりのさく。647年設置。現新潟県中央区沼垂(ぬったり))・磐舟柵(いわふねのさく。648年設置。現新潟県村上市)です。
斉明天皇の時代には、阿倍比羅夫(あべのひらふ。?~?)が派遣され、さらに北方に領域を広げました。
8世紀になると、政府に帰順する蝦夷は優遇し、反抗する蝦夷は武力制圧するという二面的な政策により、日本海側に出羽国(712年設置。現在の秋田県・山形県)をおいて秋田城(733年設置)を築きました。
一方、太平洋側には多賀城(724年設置。現宮城県多賀城市)を築きました。多賀城は陸奥国府と鎮守府を兼ねて、東北地方の政治・軍事の拠点となりました。
《 南西方面-隼人(はやと)- 》
南九州には隼人とよばれた人びとがいましたが、大伴旅人(おおとものたびと。665~731)の活躍によって大方が帰服しました。
この地には701年に薩摩国(さつまのくに)、713年に大隅国(おおすみのくに)がおかれ、また種子島・屋久島をはじめとする島々とも交渉をもつようになりました。沖縄との交渉はまだありませんでした。

8世紀初めは、中央政界における諸氏間の勢力バランスが比較的安定していましたが、やがて藤原氏が政界に進出してくると、皇族・他氏との間でせめぎ合いがおこってくるようになりました。

① 藤原不比等(ふじわらのふひと)
藤原不比等(ふじわらのふひと。659~720)の娘宮子(みやこ。?~754。母は賀茂比売(かもひめ)の娘)は文武天皇(もんむてんのう)に嫁して夫人(ぶにん)となり、701(大宝元)年に首皇子(おびとのみこ)を生みました。のちの聖武天皇(701~756。在位724~749)です。
夫人というのは、一夫多妻制の時代における、天皇の配偶者の名称の一つです。それにはランクがあり、律令(後宮職員令)によると、上から順に「后(こう)・妃(ひ)・夫人(ぶにん)・嬪(ひん)」の4段階がありました。夫人は、上から3番目です。
不比等は外孫(がいそん)の首皇子にも娘の光明子(こうみょうし。701~760。母は県犬養三千代(あがたいぬかいのみちよ))を夫人として嫁がせ、外戚として天皇家と密接な関係をきずいていきました。
不比等は律令貴族として大宝律令の作成に参加し、718年には養老律令を撰修して、720年に死去します。死後、正一位・太政大臣を贈られ、淡海公(たんかいこう)に封じられました。太政大臣は極官です。天皇の臣下としてはこれより上の官職はありません。
◆中臣氏と藤原氏の分離
天智天皇は危篤の床にあった中臣鎌足を訪ね、長年の貢献を称えて鎌足に「藤原」姓を賜与しました。もともとこれは、鎌足個人に与えられたものでしたが、中臣氏一族は、状況によって中臣・藤原両姓を使い分けていました。中臣姓を用いる場合は神祇の仕事に、藤原姓を用いる場合は一般行政の仕事に、それぞれ関わっている時でした。
これを踏まえて698(文武天皇2)年、文武天皇はこれ以後一族を二分して、意美麻呂(おみまろ)の子孫を中臣氏(神祇担当)、不比等の子孫を藤原氏(行政担当)とするよう詔(みことのり)しました。文武天皇の詔は、古い氏族制度の下で祖業の神祇を担当していた中臣氏が、これ以降神祇の中臣氏と政治の藤原氏とに分離することで、新しい律令体制に対応したことを意味します。
不比等は、自らが中心になって制定した大宝律令によって、太政官・神祇官を二大頂点とする官僚体制(二官八省一台五衛府)を構築しました。何のことはない、二つの頂点である神祇官を占めたのが中臣氏であり、太政官を占めたのが藤原氏だったのです。こうして藤原氏は、以後千年にわたって政治の世界を牛耳ることになるのです。
【参考】
・村井康彦『日本の文化』2002年、岩波ジュニア新書、P.52~54参照 |

② 長屋王と藤原四子
不比等に代わって、皇族で左大臣(常置の最高職)だった長屋王(ながやおう。?~729)が政権の座につきました。長屋王は壬申の乱で活躍した高市皇子(たけちのみこ。654?~696)の子で、天武天皇の孫にあたります。このあと、儒教にもとづく理想主義な政治を展開します。
《 長屋王の変(729) 》
728(神亀5)年、聖武天皇と光明子との間に生まれた藤原氏待望の男子(皇太子)が、わずか1歳で亡くなってしまいます(この亡くなった基(もとい)親王のためにつくられた金鐘寺(こんしゅじ)が、のちに東大寺になります)。そして同じ年、聖武天皇と県犬養広刀自(あがたいぬかいのひろとじ)との間に、安積親王(あさかしんのう)が生まれます。このままでは、皇位は他氏の生んだ安積親王の方に行ってしまうかも知れません。
聖武天皇後の皇位継承に不安を感じた不比等の子、武智麻呂(むちまろ。680~737。南家の祖)・房前(ふささき。681~737。北家の祖)・宇合(うまかい。694~737。式家の祖)・麻呂(まろ。695~737。京家の祖)の4兄弟は、聖武天皇の夫人だった妹の光明子を、皇后に立てようと画策します。皇后なら、聖武天皇に不測の事態があった場合にその政務を代行したり(称制)、場合によっては臨時に天皇として立つことも可能でした。また、政界に大きな発言力も維持できるでしょう。
しかし、ここに一つ、問題がありました。后・妃になるには四品以上の内親王(すなわち皇族)でなければならないという条件です。皇族の娘でない光明子を強引に立后しようとすれば、長屋王をはじめとする皇親勢力や守旧派貴族の反発を招くことは必至です。
そこで、藤原四子は729(神亀6)年、長屋王に謀叛の罪を着せて、一族ともども自殺させてしまいました。皇太子が亡くなったのも、長屋王が「私(ひそ)かに左道(さどう。呪術のこと)を学びて国家を傾けんと」呪詛(じゅそ)した結果だというのです。
2月10日に長屋王謀反の密告があり、同日夜、藤原宇合らが六衛府(令制の五衛府と中衛府)の兵を率いて、長屋王邸を囲みました。11日に長屋王の罪状糾問が行われ、翌12日には早々に長屋王とその妻吉備内親王(きびないしんのう)、およびその間に生まれた男子たちが自殺させられたのです。そして13日には、長屋王夫妻の遺体を生駒山に埋葬するという、電光石火の早業でした。
この事件を、長屋王の変といいます。
《 天平改元と光明子立后 》
同年、左京職(長官は藤原麻呂)が、河内国古市郡の人が献上したという一匹の亀を朝廷にもたらしました。その甲羅に「天王(てんのう)貴(たっと)く平(たい)らかにして、百年(ももとせ)を知らさむ」という瑞祥の文字があったというのです。これにより、「天平」と改元されました。
かくして藤原氏は、天平改元のセレモニーによって人心の一新をはかった直後、光明子立后(りゅうごう)を実現させたのです。これは、皇族以外の者が皇后になった(人臣皇后)初例です。
かくして順風満帆に見えた藤原氏の勢力は、思わぬ事態によって、一時衰退を余儀なくされました。737(天平9)年、九州から広がった天然痘(てんねんとう)が都でも猖獗(しょうけつ)をきわめ、次々と4兄弟の命を奪ってしまったのです。

③ 橘諸兄と藤原広嗣の乱
勢力を後退させた藤原氏にかわって政権をにぎったのは、橘諸兄(たちばなのもろえ。684~757)でした。諸兄は美努王(みのおう)と県犬養三千代(あがたいぬかいのみちよ。?~733)との間に生まれた皇族で、最初葛城王(かずらきおう)といいましたが、臣籍降下(しんせきこうか)して橘氏を名乗ったのです。母の三千代は藤原不比等と再婚して光明子を生みましたから、諸兄と光明子は異父兄妹の関係にあります。
《 吉備真備と僧玄昉 》
諸兄は、唐から新知識を学んで帰国した吉備真備(きびのまきび。693?~775)や僧の玄昉(げんぼう。717~735)を、自らの知嚢(ちのう)として活用しました。吉備真備は皇太子(のちの孝謙天皇)の教育係として、玄昉は長年鬱状態にあった宮子(聖武の母)の病状回復に力があったとして、それぞれ聖武天皇から絶大な信頼を得ました。特に吉備真備は、のちに菅原道真と並称されるほどの学識をもち、説話絵巻(『吉備大臣入唐絵巻(きびのおとどにっとうえまき)』)の主人公になるほどの学者でした。
しかし、以前から政府に仕えている貴族たちにすれば、自分たちをさしおいて、どこの馬の骨かわからない地方出身の学者や得体の知れない僧侶が、突然政治の中枢に参画して権力をふるい始めたのです。面白かろうはずがありません。
《 藤原広嗣の乱(740) 》
740(天平12)年、藤原宇合の子という名門の出でありながら、大宰少弐(だざいのしょうに)として辺境に追いやられていた藤原広嗣(ふじわらのひろつぐ。?~740)が、吉備真備・玄昉らの排除を求めて北九州で大規模な反乱をおこしました。これを藤原広嗣の乱といいます。
政府は大野東人(おおのあずまひと。?~742)を大将軍に任じ、1万7千人もの征西軍を派遣して、この乱を鎮圧しました。しかし、うち続く飢饉・疫病・反乱に動揺したのでしょうか、聖武天皇はそれから数年間、山城国恭仁京(くにきょう。現京都府木津川町)・摂津国難波宮(なにわのみや。現大阪市)・近江国紫香楽宮(しがらきのみや。現滋賀県甲賀市)と宮都を転々と移し、政局は混乱しました。

④ 国分寺建立と大仏造立
仏教をあつく信仰した聖武天皇は、仏教の力によって国の平和と安定をはかろうと考えました(鎮護国家思想)。
《 国分寺の建立 》
741(天平13)年、聖武天皇は恭仁京で、国分寺建立の詔を出しました。諸国に国分寺(こくぶんじ)・国分尼寺(こくぶんにじ)をつくらせ、僧侶たちに鎮護国家(護国)を祈らせることにしたのです。
国分寺は正式名称を「金光明四天王護国之寺(こんこうみょうしてんのうごこくのてら)」といい、ここには20人の僧侶を置いて護国経(注)の一つ、金光明最勝王経(こんこうみょうさいしょうおうきょう)を読ませることにしました。
ちなみに国分尼寺は正式名称を「法華滅罪之寺(ほっけめつざいのてら)」といい、10人の尼僧を置いて法華経を読ませました。法華経も護国経の一つです。
(注)金光明(最勝王)経・法華経・仁王経の三つの経典を「護国三部経」といいます。
《 大仏の造立 》
次いで743(天平15)年には、紫香楽宮で大仏造立(だいぶつぞうりゅう)の詔を出しました。聖武天皇は745(天平17)年に平城京にもどりますが、大仏造立事業は奈良の地に移されて続けられました。行基(ぎょうき)(注1)をはじめ、多くの人びとがこの大事業に参加しました。
(注1)国家統制の枠組みに入らず、みだりに民衆に禍福を説くというので、最初のうちは「小僧行基」と罵られ、政府から弾圧されました。しかし、橋をかけたり、ため池を掘ったり、運脚で倒れた農民らを救うために布施屋を作ったりするなどの社会事業に取り組んだので、民衆からは「行基菩薩」と呼ばれて、絶大な信頼を集めました。そうした行基の民衆結集力を、政府は大仏造立に利用しようとしたのです。行基は大僧正になり、大仏造立に協力しました。
大仏は華厳経の本尊で、正式には盧舎那仏(るしゃなぶつ)といいました。この名は「光明遍照(こうみょうへんじょう)」を意味します。つまり、盧舎那仏は太陽神崇拝から考え出された仏であり、大乗仏教において仏法そのもの示す法身仏とされる仏です。
盧舎那仏を安置する東大寺の正式名称は、「金光明四天王護国之寺」です。これは全国に造られた国分寺と同じ名称ですね。すなわち、東大寺は全国に置かれた国分寺を統べる「総国分寺」であり、大仏は、各国分寺に安置された丈六仏(じょうろくぶつ。1丈6尺=約4.8mの釈迦如来像)を統べる役割をも担っているわけです。聖武天皇は、社会不安によって動揺する日本列島を、盧舎那仏と諸国に配置された丈六仏を結ぶ仏法のネットワークによって押さえ込んで、攘災招福をはかろうと考えたのでしょう。
749年に陸奥国で大仏に鍍金(ときん。メッキ)する黄金が発見されると、聖武天皇はこれを瑞祥とし、「天平感宝」と改元して娘の阿倍内親王(あべないしんのう)に譲位します。孝謙天皇(こうけんてんのう)です。さらに聖武太上天皇(注2)は「天平勝宝」と改元し、出家して法名を「勝満(しょうまん)」と称しました。
(注2)天皇は譲位後、「太上天皇」と呼ばれました。初例は、持統太上天皇です。平安中期以降になると、省略して「上皇」と呼ばれるようになりました。
752(天平勝宝4)年4月9日、孝謙天皇によって、大仏の開眼供養(かいげんくよう)の儀式が盛大におこなわれました。聖武太上天皇、光明皇太后、孝謙天皇はじめ、インド僧・中国僧ら1万人以上が参加した盛儀で、バラモン僧菩提僊那(ぼだいせんな)が筆で大仏に目を入れ、仏哲(ぶってつ)が林邑楽(りんゆうがく。ベトナムの音楽)を奏でたと伝えられています。

⑤ 藤原仲麻呂(恵美押勝)
孝謙天皇の時代には、天皇の従兄弟にあたる藤原仲麻呂(ふじわらのなかまろ。南家。706~764)が、叔母の光明皇太后と結託して紫微中台(しびちゅうだい)という役所の長官(紫微令。のちに紫微内相(しびないしょう。内相は内大臣の意)と改称)を足がかりに、政界で勢力を伸ばしました。
紫微は天帝の居所を意味し、紫微中台という名称は、中国の則天武后がおいた中台(尚書省)と、玄宗がおいた紫微省(中書省)に由来するらしいのです。紫微中台は、単なる皇太后のための家政機関ではありませんでした。最高行政機関の太政官とならびたち、皇太后の意志を受けて、国政を執行する機関だったのです(丸山裕美子「政争が繰り返された末に女帝の時代が終わる」-『週刊新発見!日本の歴史12』2013年9月22日号、朝日新聞出版、P.12-)。
《 橘奈良麻呂の変(757) 》
仲麻呂によって引退に追い込まれた橘諸兄の子奈良麻呂(ならまろ。721?~757?)は、仲麻呂の専横を憎んでその排斥を企てますが、密告によって計画が漏れ、検挙されてしまいました。仲麻呂の追及は厳しく、首謀者のほとんどが拷問のために死に、他は流罪に処せられました。757(天平宝字元)年に起こったこの事件を、橘奈良麻呂の変といいます。
《 仲麻呂の政治 》
生涯独身だった孝謙天皇には後継者がいませんでした。仲麻呂は息子の妻の後夫(長男真従(まより)の妻で未亡人になっていた粟田諸姉(あわたのもろね)の婿(むこ))、淳仁天皇(じゅんにんてんのう。在位758~764。)を擁立して即位させました。そして、天皇から「恵美押勝(えみのおしかつ)」(注)の名を賜わるなど破格の待遇を得、太師(たいし。太政大臣のこと)にまでのぼりつめて権力を独占すると、近親者によって政府の要職を独占しました。ちなみに、生前に太政大臣に任命されたのは、恵美押勝が初めてです。
恵美押勝は、祖父不比等が作った養老律令を施行(757年)し、律令国家に対する藤原氏の功績をアピールしました。
また唐の玄宗皇帝や則天武后の治世にならって、官職名を唐風に改めました。たとえば、太政官は乾政官(けんせいかん)、紫微中台は坤宮官(こんぐうかん)、太政大臣は太師、左大臣は太傅(たいふ)、右大臣は太保(たいほ)、大納言は御史大夫(ぎょしたいふ)、中務省は信部省、式部省は文部省、治部省は礼部省などと、それぞれ改名させました。
(注)758(天平宝字2)年、淳仁天皇は、藤原鎌足以来歴代大臣として人民を「汎(ひろ)く恵むの美、これより美なるはなし」とし、また橘奈良麻呂の変に際し「暴を禁じ強に勝ち、戈(か。武器)と止め乱を静」めたと、仲麻呂の功績をたたえる勅をだしました。この勅は、おそらく仲麻呂自身が作ったのでしょう。
《 恵美押勝の乱(764) 》
しかし、光明皇太后が亡くなると、後ろ盾を失った恵美押勝は貴族たちの中で孤立を深めました。
折しも孝謙太上天皇が僧道鏡(?~772)を寵愛するようになり、これが原因で淳仁天皇と対立することになると、天皇から権力を奪うという挙に出ました。危機感をつのらせた恵美押勝は、道鏡を除こうと
764(天平宝字8)年に挙兵します。しかし、孝謙太上天皇側に先制され、近江で敗死させられてしまいました。これを恵美押勝の乱といいます。この乱で亡くなった死者の霊をなぐさめるために作られたのが、百万塔陀羅尼(ひゃくまんとうだらに)です。
淳仁天皇は皇位を廃されて淡路に流されました(淡路廃帝)。代わって、孝謙太上天皇が重祚(ちょうそ)して称徳天皇(しょうとくてんのう。在位764~770)となりました。

⑥ 道鏡の仏教政治と宇佐八幡神託事件
道鏡は称徳天皇の支持を得て、765年に太政大臣禅師(だいじょうだいじんぜんじ。僧侶でありながら太政大臣)、さらに翌766年には法王(ほうおう)になり、権力を掌握して仏教政治をおこないました。尼(称徳天皇)と僧侶(道鏡)が最高権力者として政治を主導した時代というのは、日本歴史上、他に例を見ません。
この時期には造寺・造仏が盛んに行われ、加墾禁止令(765年)でも寺社が除外されるなど、寺社が優遇されました。
《 宇佐八幡神託事件(769) 》
769(神護景雲3)年、九州の宇佐八幡宮が「道鏡が皇位につけば国家安泰となろう」という神託を下しました。当時の大宰府長官は道鏡の弟弓削浄人(ゆげのきよんど)、神託を申し出たのは大宰府の主神(かんづかさ)でした。
後継者がいない称徳天皇は、道鏡に譲位する心積もりがありましたが、貴族たちからの猛烈な反対があることを予想したのでしょう、神託を確認するために九州に使者を派遣することにしました。しかし、派遣された和気清麻呂(わけのきよまろ。733~799)は、先の神託が偽託であり、「天日嗣(あまつひつぎ)には必ず皇儲(こうちょ)をつけよ。无道(むどう)の人は宜(よろ)しく早く掃除(そうじょ)すべし(皇位には皇族をつけ、道鏡を追放せよ)」という神託を復奏したのです。激怒した天皇は、清麻呂の名を奪って「別部穢麻呂(わけべのきたなまろ)」という醜名(しこな)に改名させ、大隅国(おおすみのくに)へ流してしまいました。これを宇佐八幡神託事件といいます。
しかし翌年、称徳天皇が死去すると、天皇の信任以外何も後ろ盾をもたなかった道鏡は、たちまち失脚してしまいました。下野国薬師寺の別当に追放されてその地で死去(政府の命令で庶人として葬られました)。清麻呂は直ちに、平城京に呼び戻されたのでした。

⑦ 光仁天皇の登場
道鏡時代の仏教政治で混乱した律令政治と、破綻した国家財政の再建が課題となりました。そこで、藤原百川(ふじわらのももかわ。式家。732~799)・永手(ながて。北家。714~771)らは、壬申の乱以降長らく続いた天武天皇系の皇統にかわり、天智天皇の孫である白壁王(しらかべおう)の即位を決めました。光仁天皇(709~781。在位770~781)です。62歳というかなりの高齢での即位でしたが、中大兄皇子(天智天皇)らを中心に律令体制の完成を目指した、あの大化改新の出発点に立ち戻ることを人びとに示したのです。
こうして光仁天皇のもとで、律令政治の再建がはかられていくことになりました。

① 百万町歩開墾計画(722)
政府は、人口増加や荒廃田増加による口分田不足に対処するため、722(養老6)年、良田百万町歩の開墾計画を立てました。その内容は、農民に食料や道具を支給し、10日間開墾に従事させることによって、良田を開こうというものでした(対象地域に奥羽地方のみ・全国の2説があります)。
しかし、百万町歩という数字自体、実現不可能な机上の空論でした。そのため、期待された成果はあげられませんでした。

② 三世一身法(723)
そこで、翌723(養老7)年、三世一身法(養老七年の格)を施行することにしました。
この法は、新たに灌漑施設を設けて未開地を開墾した場合は子・孫・曾孫(また本人・子・孫という説もあります)の三世代にわたり、旧来の灌漑施設を利用して開墾した場合は本人一代に限り、田地の私有を認めるというものでした。この時、私有面積に制限はありませんでした。
この法によって耕地面積は拡大しましたが、私有期間が残りわずかになってくると農民たちは耕作を怠けるようになりました。どうせ最後は政府に没収されるなら、真面目に取り組んでも仕方がない、と考えたのです。その結果、政府が回収する頃には、開墾地は荒れ地に戻ってしまったのです。

③ 墾田永年私財法(743)
こうして、三世一身法も効果が薄かったので、743(天平15)年、政府は思い切った法令を出しました。墾田永年私財法(天平十五年の格)です。位階によって所有できる土地面積には制限があったものの、開墾した田地の永久私有を認めることにしたのです。これは、律令制度の根幹である公地公民制の原則を、政府自らが否定したことを意味します。
しかし墾田は輸租田でしたから、租を納入しなければなりません。この法によって、政府は増大する墾田の掌握と、土地に対する支配力の強化をはかったのでした。
その一方、貴族・寺社・地方豪族たちは競って開墾し、私有地が拡大していきました。とりわけ東大寺などの大寺院は、国司や郡司と結託して広大な原野を占有し、班田農民や浮浪人らを駆使して大規模な開墾を行いました。こうして成立した私有地を、初期荘園(しょきしょうえん)といいます。

④ 加墾禁止令(765)
道鏡政権下の765(天平神護元)年、寺社と現地百姓のものを除いて、有力者のみを利する新規の開墾が禁止されました。しかし、道鏡が失脚すると、772(宝亀3)年、この法令は廃止されました。

① 農民の生活
奈良時代の農民生活はどのようなものだったのでしょうか。この頃になると農業技術にも進歩がみられ、鉄製農具が普及しました。人びとの住居も、従来の竪穴住居に代わって、土地を掘り下げない平地式の掘立柱(ほったてばしら)住居が、西日本からしだいに普及してきました。
結婚は、男性が女性の家に通う形をとりました。これを妻問婚(つまどいこん)といいます。そのうち、男女いずれかの親のもとで夫婦生活をし、やがては独立して自分たちの家を持ちました。
女性の発言権が強かったことも特徴の一つです。結婚しても夫婦別姓のままで、女性は自分の財産を持ち、生業分担や子どもの養育などで強い発言権をもっていました。
農民は、口分田を耕作したり、園地(えんち)で桑・漆・野菜類を栽培したりするほか、乗田や寺社・貴族などの土地を借りて耕作しました(賃租)。土地の借用期間は1年が原則で、収穫の2割を地子(じし)として持ち主に納めるのが普通でした。

② 重い税負担から逃げる農民
農民の負担は成年男子(正丁)に課せられる人頭税が中心で、物納や労役が中心でした。雑徭や運脚などの労役、また衛士・防人などの兵役の負担は、彼らにとってとりわけ重いものでした。生産力が低い時代でしたから生活に余裕などなく、天候不順等に影響されて凶作・飢饉もおこりやすい状況でした。こうした農民たちの厳しい生活は、山上憶良が作った長歌「貧窮問答歌」などからもうかがい知ることができます。
そのため、中には生活が破綻して、生活が立ちゆかなくなる農民も多数出現しました。彼らは、口分田を捨てて諸国に浮浪したり、労役に赴いた現場から逃亡したりしました。また、、ある者は貴族や寺社・地方豪族などのもとで資人(しじん、とねり)と呼ばれる従者になったり、ある者は公の許可を得ることなく勝手に出家する私度僧になったりしました。また、税負担の多い男子を少なく虚偽申告する偽籍(ぎせき)も行われました。中には、住民の90%以上が女性、という戸籍もありました。
農民たちはこのようにして、重い税負担から逃れようとしたのです。
その結果、口分田の荒廃、調・庸の滞納、その品質の悪化、兵士の弱体化などが進みました。こうした事態は、国家財政や軍備に大きな影響をもたらすことになりました。


