11.奈良時代の外交
話を聞き終わると、鑑真はすぐに口を開いた。( 中略 )
「( 前略 )いま日本からの要請があったが、これに応えて、この一座の者の中でたれか日本国に渡って戒法を伝える者はいないか」
たれも答える者はなかった。暫くすると祥彦(しょうげん) という僧が進み出て言った。
「日本へ行くにはびょうまんたる滄海をわたらねばならず、百に一度も辿りつかぬと聞いております。人身は得難く、中国には生じ難し。そのように涅槃経(ねはんぎょう)にも説いてあります」
相手が全部言い終わらぬうちに、鑑真は再び口を開いた。
「他にたれか行く者はないか」
たれも答える者はなかった。すると鑑真は三度口を開いた。
「法のためである。たとえびょうまんたる滄海が隔てようと生命を惜しむべきではあるまい。お前たちが行かないなら私が行くことにしよう」
一座は水を打ったようにしんとなっていたが、総てはこの間に決まったようであった。
(井上靖『天平の甍』1964年、新潮文庫、P.63)
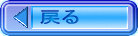


① 唐の繁栄
618年、隋にかわって唐が中国を統一しました。唐は律令制度を基盤とする大帝国でした。貞観の治・開元の治の隆盛期を経て内政を充実させ、アジアに版図を拡大し、周辺諸地域に多大な影響を及ぼしました。また、インドやペルシアなどの国々とも交流して、都の長安(現、西安)はさながら国際都市の様相を呈していました。

② 遣唐使の派遣
日本からも、唐の制度や文物を輸入するため、外交使節団が派遣されました。遣唐使です。630年に第1回の遣唐使として犬上御田鍬(いぬかみのみたすき。?~?)が派遣されてから、894(寛平6)年に菅原道真(845~903)の建議で停止されるまで、10数回にわたって派遣されました(遣唐使の派遣回数については、中止等をどう数えるかによって、12回説から20回説まで諸説あります)。8世紀には、ほぼ20年に1度の割合で派遣されました。
遣唐使には、留学生・学問僧なども加わり、200名から多い時は500名にも及ぶ人びとが、4隻(1隻や2隻の例もあります)の船に乗って海を渡りました。4隻に分船したので、遣唐使船には「四つの船」の別称があります。複数の船で渡海したのは、当時の造船・航海の技術が未熟だったため、海上での遭難が多かったことも理由の一つだったでしょう。極論すれば、4隻で行けば1隻くらいは無事に到達できるだろう、という考えだったのかも知れません。事実、8世紀に新羅との関係が悪化すると、朝鮮半島の西岸沿いを北上して山東半島から入唐する安全な北路(ほくろ)を通ることができなくなり、五島列島から直接東シナ海を突っ切る南路(なんろ)にコース変更されると、遭難が増加しました。
東シナ海は、夏から秋にかけては台風、晩秋から春先にかけては季節風と、1年中荒れる海の難所です。ただでさえ、東シナ海の横断は危険でした。小説ですが、井上靖は『天平の甍(いらか)』の中で祥彦(しょうげん)という僧に、「日本に行くにはびょうまんたる滄海を渡らねばならず、百に一度も辿(たど)りつかぬと聞いております」(井上靖『天平の甍』)と言わせています。おそらく、当時の人びとの認識もこれに近いものだったでしょう。

③ 海を渡った人びと
そうした危険を覚悟の上で、わが国と大陸の間を渡った人びとがいました。
《 鑑 真(がんじん) 》
わが国に戒律を伝え、唐招提寺を創建したことで知られる鑑真和上(がんじんわじょう。688?~763)も、この「びょうまんたる滄海」に幾度も渡航を阻まれました。日本からの伝戒使招請の懇願にこたえてわが国を目指しましたが、その前には鑑真の渡航を阻止しようとする妨害やら弟子の脱落やら難破やら、数多くの苦難が横たわっていました。6度目の渡航で坊津秋目浦(ぼうのつあきめうら。現在の鹿児島県)にたどり着いた時に、失明していた鑑真は日本の風景を見ることができませんでした。鑑真が渡海を決心してから、すでに12年の星霜が過ぎていました。
《 阿倍仲麻呂(あべのなかまろ) 》
また、阿倍仲麻呂(698?~770?)のように、帰国がかなわず、異国の土となった人びともいました。
仲麻呂は、王維・李白らとも親交があった文化人で、玄宗皇帝に仕えて政府高官にのぼりました。『旧唐書(くとうじょ)』は仲麻呂のことを
中国の風を慕(した)い、留(とど)まって去らず、姓名を朝衡(ちょうこう)と改め、左補闕(さほけつ。従七品上)・儀王友(ぎおうゆう。従五品下)を歴任した。衡は、京師(長安)に留まること五十年、書籍を好み、故郷に帰らせようとしたが、逗留して去らなかった。(石原道博編訳『「旧唐書」倭国日本伝・新訂版』岩波文庫)
と書いています。
しかし実際には、753年に日本に戻る遣唐使一行とともに、帰国を試みています。この時、仲麻呂は56歳前後。ところが、途中暴風にあって船は吹き戻され、ベトナムに漂着しました。一命を落とさなかったのは幸いでしたが、これ以後、帰国を断念したようです(この時の遣唐大使藤原清河(ふじわらのきよかわ。?~?)も帰国をあきらめ、「河清」の唐名で唐朝に仕え、彼の地で客死しています)。
『古今和歌集』巻9に収められている
天の原ふりさけ見れば春日(かすが)なる三笠(みかさ)の山にいでし月かも
の和歌は、帰国の途につく送別の宴の席上で、30年前の日本での送別の情景を思い出して仲麻呂が詠んだものと伝えられています。

④ 遣唐使がもたらしたもの
このように、東シナ海を横断するのはたいへん危険だったため、中には遣唐使の任命を拒否する人びとも出てきました。たとえば、小野篁(おののたかむら)は病気と称して渡航しなかったため、流罪に処せられています。しかし、多くの人びとは先進の制度や技術・国際文化などを学ぼうという気概を持ち、航海の危険を冒してまで東シナ海を往来したのです。このようにして、遣唐使たちが、唐からもちかえった先進的な制度・技術・文化等は、わが国に大きな影響をあたえました。
帰国した人びとの中には吉備真備(きびのまきび。693?~775)や玄昉(げんぼう。?~746)のように、聖武天皇(701~756)に重用されて、政界で活躍する者もいました。
◆日本人留学生の墓誌
2004年10月、中国西安市で、日本人留学の墓誌が発見されました。中国で古代日本人の墓誌が発見されたのは、これが初めてです。西安は、かつて唐の都長安があった場所です。
墓誌は、一辺が39cm正方の石で、その表面に171文字が刻まれていました。この墓誌は「井真成」という留学生のもので、日本名を何といったのかはわかりません。「井」は日本の姓を中国風に一文字にしたもので、「真成」は本名だと考えられますが、裏付けとなる史料がないので推測に過ぎません。墓誌の内容は、井真成が日本の留学生で優秀な人物だったこと、734年に36歳で死去したこと、玄宗皇帝がその死を悼んで「尚衣奉御(しょういほうぎょ。皇帝に衣服を捧げる役職の長)」の官職を贈ったこと、などが書かれていました。
皇帝が死後に官職を贈るというのはきわめて異例のことです。よほど優秀な人だったのでしょう。 |

① 新羅との交渉
唐と同盟を結んだ新羅は、660年に百済を、668年には高句麗を滅亡させました。さらに、直接境界を接することで対立していた唐を追い出し、朝鮮半島を統一したのは676年のことでした。
この境界争いが、新羅・唐間に緊張関係を生み出しました。そこで、唐を牽制するために、新羅は日本と結ぼうとしたのです。新羅はやむなく日本に臣従の態度をとり、貢調使(こうちょうし)を派遣してきました。
しかし、733年、唐と新羅の関係が改善したため、もはや日本に臣従する必要がなくなりました。そこで、新羅は日本に対し、対等な国交を要求しました。しかし、日本はこの要求を認めようとせず、新羅に対し非礼な態度をとり続けました。たとえば、新羅が贈り物の名称を「調(みつぎもののこと)」から「土毛(どもう。みやげもののこと)」と変えたことに気を悪くして、その受け取りを拒否したことがありました。また、753年には、唐朝の元旦の儀式で、遣唐使副使の大伴古麻呂(おおとものこまろ)が新羅使と席次争いをして、新羅の席次を下位に引きずりおろすという事件も起こりました。あくまで日本は、新羅の上位に立とうとしたのです。
そのため、新羅との関係は悪化しました。一時は、藤原仲麻呂(ふじわらのなかまろ。706~764)が新羅攻撃の計画を立てるほど、仲が悪くなっていたのでした。
8世紀末になると遣新羅使(けんしらぎし)の派遣はまばらとなりましたが、民間商人たちの往来はさかんでした。正倉院には『買新羅物解(ばいしらぎもののげ)』(この文書は鳥毛立女屏風の下貼りになっていました)という、新羅からもたらされた物品に対する貴族たちの購入希望書が残っています。これによると東南アジアやインド等で産出される物品も含まれており、新羅商人の交易活動が広域にわたっていたことをうかがわせます。

② 渤海(ぼっかい)との交渉
一方、 713年に中国東北部に建国された渤海とは、頻繁な使節の往来がありました。
渤海の起源は、698年にツングース系靺鞨族(まつかつぞく)と高句麗遺民によって建てられた震(振)国にあります。建国者の大祚栄(だいそえい)が、713年に唐の玄宗皇帝から渤海郡王に冊封(さくほう)されてから、渤海を国号とするようになったのです。9世紀には「海東の盛国」と称されるほど繁栄しましたが、926年に契丹(きったん)に滅ぼされました。
渤海は、唐・新羅との対抗関係から 727(神亀4)年にわが国に渤海使を派遣して、通交を求めてきました。日本も新羅と対抗関係にあったので、渤海とは友好的に通交しました。渤海使の来日は、727年から919年の間に34回にも及びました。渤海使を迎える客院は、加賀国(能登客院)と越前国(松原客院)に置かれました。
最初の通交は政治的意味合いが強かったのですが、のちには貿易が主となりました。渤海からは貂(てん)や大虫(おおむし。虎のこと)の毛皮、薬用人参、蜂蜜、宣明暦、仏典などがわが国にもたらされました。一方、日本からは絹、?(あしぎぬ)、金、水銀、漆などが輸出されました。渤海の宮都跡から和同開珎が出土しているのも、こうした両国の交渉の歴史を裏付けるものでしょう。


