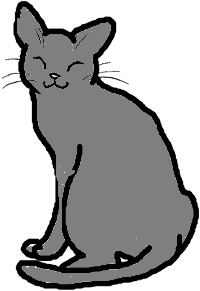はじめに
根岸鎮衛の『耳袋』に次のような話がある。
秋の大雨の夜、男が従者を連れて、江戸の番町馬場にさしかかった。ふと見ると、道端に女(?)がうずくまっている。いったん通り過ぎたものの、不審に思い、とって返すとその姿はすでにない。そこは隠れる場所もない、見通しのいい道だった。いぶかしく思いながら帰宅すると、従者ともども高熱を発して病の床に伏してしまった。あの女は、人の形をした瘴癘(しょうれい。気候・風土等によって起こる伝染性の熱病)の気だったのだ(根岸鎮衛著・鈴木棠三編注『耳袋1』1972年、平凡社、P.262)。
病気の原因や予防法・治療法などの多くが不明だった時代、とりわけ致死率の高かった伝染病に対しては、人々は大きな恐怖心をもっていた。「病の化身」を一目見ただけで、たちどころに感染・発病してしまうという『耳袋』の話なども、そうした恐怖心の裏返しだろう。
時代が下り、「病の化身」の正体が暴露され、それへの対処法が徐々に明らかになって、迷信的治療法は次第に駆逐されてはいった。しかし、医学的知識が豊富になったから、その分われわれが賢明になったかというと、必ずしもそうとは言い切れまい。
そうした事例の一つとして、小稿では、明治期後半から大正期にかけて、小さな「病の化身」に振り回された人々の姿を紹介しよう。
1.「薮入り」の情景
熊さん、おみつさん夫婦は朝から落ち着かない。今日は薮入り。商家に奉公に出した金坊が、初めて宿下がりしてくるのだ。思えば3年前、まだ八つばかりの子供を奉公に出すのは、熊さん夫婦にとっても辛いことだった。しかも、独り息子というのであれば、なおさらである。しかし、子供の将来を考えれば、他人様(ひとさま)の中で揉まれて、その腐った性根を叩き直してもらった方が本人のためになる。だから、夫婦とも、大家さんの奉公の勧めに不承不承従ったのだ。
その金坊が今日帰ってくる。普段は横の物を縦にもしない熊さんが、おちおち寝てもいられず、今朝は夜明け前から家の表を掃除しているあんばいだ。だから、金坊が帰って来たその時なんぞ、嬉し涙で我が子の姿が見えなかったくらいだ。
ところが、である。金坊の留守に、おみつさんが金坊の財布を開けてみると、小僧には分不相応にも5円札が3枚も入っている。初めての宿下がりにあれだけのみやげ物を買って、15円の小遣いは多過ぎる。もしやまた、昔の悪い癖が出て…と思うと、外出から戻った金坊に、熊さんの拳は口から出る言葉より早かった。
それを必死に押しとどめて、おみつさんが金坊に財布の件を問質すと、鼠を捕って交番へ持って行き、懸賞に当たった金だというのだ。(興津要編『古典落語(続々)』1973年、講談社文庫から要約)
2.ペスト菌の発見
明治27(1894)年6月7日、ペスト流行の調査のため、北里柴三郎・青山胤通らが政府派遣として香港へ出発した。教科書的通説に従うなら、この年こそ、北里柴三郎によるペスト菌発見の年となるのである。
しかし、実際には北里は純粋な状態でのペスト菌を発見したのではなく、フランス人エルザン(イェルサン、A.Yersin)が発見したいわゆる「エルザン菌」こそ純粋に単離されたペスト菌であった。その後長らく両学説間で論争が続くのであるが、明治32(1899)年11月20日に至って「ペスト病毒はエルザン菌たることを確定し、北里氏も遂に同意」(「国民新聞」同年11月23日付け)したことにより、この論争に決着がつくのである。
さて、ペストは本来鼠の病気で、鼠に寄生するケオプスネズミノミ(ペスト菌の保菌者)に噛まれることにより発病する。ペストには腺ペストと肺ペストの2種類があるが、特に肺ペストは発病すると高熱を発し、精神が虚脱状態となって譫(たわごと)をいうようになり、血痰や喀血などの肺炎症状を示し、皮膚が乾燥して黒紫色の斑点や膿胞を生じて高い死亡率を呈した。この皮膚がどす黒くなるチアノーゼ症状から、ペストは「黒死病(black death)」の名で恐れられた。
先に紹介した「薮入り」はもとは男色を主題とした艶笑物の落語であったが、明治末期に盲小せんこと3代目柳家小せんが「鼠の懸賞」の題で改作し、前述のような人情噺の形となって現在に至っている。この落語の成立の背景になったのが、明治期後半から大正期にかけてのペストの流行であった。
近代日本においては、ペストの原因は北里らの研究・調査により判明し、その被害も中世ヨーロッパの黒死病の流行と比較すれば遥かに小規模なものであった。そうした中で、前述の「薮入り」のように、交番に鼠を持参すれば金になるという奇妙な制度が生まれたのである。
3.発端
明治27(1894)年6月7日、北里らが香港に出発した2日後、ペスト患者を乗せたアメリカ船のペリュー号が長崎に入港して人々の不安を呼んだ。2年後の明治29(1896)年3月31日、2日前に横浜に上陸した中国人がペストで死亡した。最初のペスト患者である。
明治32(1899)年、神戸でペストの疑似症状で13歳の少年が病死し、新聞は「ペスト、神戸に侵入」の見出しでこれを報じた(「国民新聞」同年11月11日付け)。周辺諸国からの日本へのペスト来襲を懸念した政府は、同年11月18日、官報号外で勅令第434号を公布、内務大臣は伝染病予防のために必要と認めるときは物件の種類を限りその輸入を禁止できることとし、同日これを施行した。勅令公布と同時に内務省は省令第54号を発令、ペスト予防のため、インド・清国諸港・香港・台湾からの襤褸・古綿・古着・古紙・古皮革・古羽毛類の輸入を禁じた(「国民新聞」同年11月19日付け)。この年、大阪株式市場で株価が下落したが、その原因はペストの流行とその検疫励行によって物流や人の移動が阻害されたためと噂された。事実、ペストの侵入地と目された神戸付近とその以西の鉄株は、特に売り方が多かった(「国民新聞」同年11月19日付け)。
明治32(1899)年のペスト患者は「時事新報」(明治33年1月1日付け)によると、総計49名(内死亡40名)で、内訳は神戸市22名(内死亡18名)、大阪市21名(内死亡17名)、姫路で1名、そのほか広島・福岡・和歌山・長崎・静岡で死亡者各1名ずつと発表された。 このままでは、ペストが神戸・大阪・岐阜を経てやがて沼津に至り、鉄路を伝わって東京へ侵入するやも知れぬ。そう危惧した松田東京市長は、一つの奇策を同年12月27日の東京参事会に提案した。それが、鼠20万匹の買い上げ作戦である(「報知新聞」同年12月30日付け)。
4.鼠の買い上げ (1)
明けて明治33(1900)年は奇しくもネズミ年であった。この年の1月15日から東京市では、1匹5銭で鼠を買い上げることにした(柳田国男「鳶の別れ」1926年には、「鼠の価は最初は2銭、後に諸色の騰貴とともに、改めて5銭と定められた」(『野草雑記・野鳥雑記』角川文庫版、P.211)とあるが、この点は未確認)。ペストの媒介者である鼠を駆除することによって、ペストの予防・撲滅をはかろうとしたのである。神戸では既に1匹8銭で買い上げた先例があったので、これに倣い、とりあえず1万円を支出して20万匹の鼠を買い殺すことにした。買い上げの方法は、近辺の交番に鼠を持参して現金引き換え切符を受け取り、それを区役所で換金するという手段が採られた。
尾崎紅葉が「一頭五銭」と題して「霜の手の銭や鼠を売りて来し」の句を詠んだのは、鼠買い上げの始まった直後である。ちなみに、明治33年当時の諸物価を瞥見すると、ジャムパン1個2銭、天丼(並)1杯が7銭 、米1升が16銭、銭湯入浴料(大人)3銭、理髪料(大人)10銭…という具合いである。当時、割合高給取りの部類に入る大工の日当が84銭(普通の人夫は30銭くらい)で、この年から採用がはじまった女子駅員の日当は15銭であった(週刊朝日編『値段の明治大正昭和風俗史』1981年、朝日新聞社および岩崎爾郎『物価の世相100年』読売新聞社、1982年を参考とした)。鼠3匹が女子駅員の1日の賃金に相当したのであるから、5銭というのはなかなかばかにはできない金額である。
そこで、ペスト感染の危惧もあらばこそ、大人も子供も長い尻尾の端をつまんで鼠をぶら下げ、交番の前に立ち並んだ。中には鼠捕りで生計を立てる者もおり、風説では買い上げてもらうことを目的に、鼠を養殖する者さえいたという。だから、猫の食いぶちを横取りするくらいは、当り前であった。その憤懣を「車屋の黒」は「吾輩」に、次のようにぶちまける。
いってえ人間ほどふてえやつは世の中にいねえぜ。ひとのとった鼠をみんな取り上げやがって交番へ持って行きゃあがる。交番じゃだれが捕ったかわからねえからそのたんびに五銭ずつくれるじゃねえか。うちの亭主なんかおれのおかげでもう一円五十銭くらいもうけていやがるくせに、ろくなものを食わせた事もありゃしねえ。おい人間てものあ体のいい泥棒だぜ。(夏目漱石『吾輩は猫である』1965年、旺文社文庫、P.16)
明治33年2月刊の『風俗画報』は神戸での鼠買い上げの様子として、箱にたくさんの鼠を入れた女性や、鼠捕獲器を持ったり棒の先に鼠を挟み込んだりした子供達が、警官に鼠を差し出している姿を描写している。ここに描かれているのは、悪評轟く「オイコラ警官」や、泣く子も黙る「こわい人」のイメージを持った警官ではない。この時代は、警官に庶民が最も親近感を抱いた時代だったのかも知れない。
5.鼠の買い上げ(2)
東京市が買い上げた鼠はおびただしい数に上るが、そのために支出した費用も巨額である。たとえば、明治37(1904)年3月1日から翌38(1905)年2月28日までの1年間に東京市が買い上げた鼠の数を見ると、斃鼠が19,737匹、捕獲が1,207,162匹、合計1,226,899匹で、一日平均3,361匹余に相当する。その鼠買い上げの総費用は41,108円61銭にものぼった(「国民新聞」1905年3月12日付け)。
ただし、この年度の鼠買い上げ金額は、4月末日までは1匹5銭であったが、5月以降は1匹3銭に値下げされている。値下げの理由は不明だが、前年度の鼠駆除関係支出が84,000円余で、当時の東京市予算の約4パーセントを占めていたというから、日露戦争の折り柄、経費節減のためだったかも知れない。なお、オリンピック東京大会の開催年度である昭和39(1964)年度に東京都が鼠を含む全ての虫疫類駆除のために支出した予算は約4億6,000万円で、都全予算の中で0.1パーセントを占めるに過ぎない。
さて、こうして集められた鼠は桐ケ谷その他の火葬場で焼き捨てられたが、これらの鼠の霊の冥福を祈るために、明治35(1902)年、市内の祥雲寺(現東京都渋谷区広尾1丁目)境内に「数知れぬねずみもさぞやうかぶらん、この石塚の重きめぐみに」の歌を刻んだ鼠塚が建立された。
6.跣足禁止令
明治34(1901)年5月29日、警視庁は東京市内に対して、次のような庁令を発した(警視庁令第41号)。
ペスト予防の為め、東京市内に於ては住居内を除く外、跣足にて歩行するを禁ず。
本令に違背したる者は刑法第四廿六条第四号により、拘留又は科料に処す。
前記庁令がペスト予防を主なる目的としていたのは勿論のことであるが、実は風俗取締りの目的をも兼ね持っていた。その注意すべき対象を「車力、人力車夫、馬丁其他職工等の労働者」(「毎日新聞」同年5月31日付け)としていることから見て、これらの人々の多くが、当時はだしで往来を闊歩していたことが窺い知れる。 翌明治35(1902)年10月11日付けの「日本」は、横浜市でのペスト患者の発生にともない、東京市内に限定していた跣足禁止令の適用区域を周辺市街地にまで拡張することを予告している。同月30日、ペスト発生地域の家屋12戸を焼き払ったが、跣足禁止令のかいもなく、12月24日には東京にもペスト患者が発生した。
7.終息
明治34年から翌35年にかけては、日本国外でもペストは猖獗を極めた。明治28(1895)年に締結した下関条約によって日本統治下に置かれていた台湾では、明治34年にペスト患者4,496名、内死亡者3,670名の被害を出した。またインドでの被害の状況は「ポンジャブに於ける黒死病は、頗る猖獗にして、一日の死亡数千を越ゆ」(「時事新報」明治35年3月3日付け)と報道された。
しかし、その後、日本国内では明治40(1907)年の死者320名をピークとして、大正3(1914)年の東京での流行(死者41名)、大正11(1922)年 の最後の流行(死者67名)を経て、さしもの猛威を振るったペストも終息に向かうのである。
8.結びにかえて
昭和52(1977)年6月、和歌山県有田市にコレラが発生した。事件はわずか3週間ほどで終息したが、コレラという伝染病に対する人々の恐怖心をマスコミが増幅し、周辺の人々が次々と罹病者を中心とする内側の人々を差別していった。そのため、この「差別の同心円構造」の中心部にいた有田市民や和歌山県民は、大きな精神的・物質的苦痛を被った(藤竹暁『「勉強しなさい」しか言えぬ親たち』1979年、講談社。岩川隆『コレラ戦記』1978年、潮出版社)。
人間のエゴイズムや情報化社会の抱える様々な問題点を浮き彫りにした事件であったが、こと病気に関する限り、「病の化身」に笑われないまでには現代の我々も未だ賢くはなっていないようである。
(初出1983年。一部加筆・訂正した)
【注】
本文中で引用した新聞資料は全て中山泰昌編著『新聞集成明治編年史』第10〜12巻、1934年によった。また、本文中に一々明記しなかったが、以下の書籍を参考にした。
・立川昭二『病気の社会史』1971年、NHKブックス
・村上陽一郎『ペスト大流行』1983年、岩波新書
・宇田川竜男『ネズミ』1965年、中公新書
・長谷川恩『ネズミと日本文学』1979年、時事通信社
・森銑三『明治東京逸聞史2』1969年、平凡社