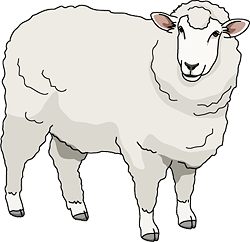| 2015年12月26日(土) |
| ゴロゴロ日本史2 |
○黒曜石の産地(ゴロ合わせ)
「わだしは姫!」とか ウソ こくよう。
和田峠 姫島 十勝岳 阿蘇山 黒曜石
○ひすい(硬玉)の産地(頭文字で覚える)
ひすい
ひめかわ(姫川)
○蘇我氏(知っている言葉に名前をはりつける)
あ い う え いるか
稲目 馬子 蝦夷 入鹿
(仏教受容) (飛鳥寺建立) (乙巳の変で滅亡)
○物部氏(知っている言葉に名前をはりつける)
あ お もり
麁鹿火(あらかび)尾輿(おこし) 守屋(もりや)
(磐井の乱鎮圧) (仏教排斥) (滅亡)
○磐井の墓(頭文字で覚える)
いわいの乱
いわとやまこふん(岩戸山古墳)
○最澄と空海(ゴロ合わせ)
ひえ~ 天 才! 高野 豆腐の 真 空 製法。
比叡山延暦寺 天台宗 最澄/ 高野山金剛峰寺 東寺 真言宗 空海
○山門派
1、 2の3もん派
円仁→ 山門派(延暦寺) ※円珍→寺門派、園城寺
○三筆と三跡(筆跡と縦に書く。筆が最初で、跡があと)
三筆 平安初(弘仁貞観) 唐様(中国風の漢字)
三跡(蹟)平安中(国風) 和様(かな文字)
○三筆(ゴロ合わせ)
「佐賀みかん、食うかい?」と 立ち話。
嵯峨天皇 空海(風信帖) 橘逸勢
○三跡(ゴロ合わせ)
去り 行く 豆腐屋
佐理(離洛帖) 行成 道風
○佐理の『離洛帖』(連続して覚える)
さり
りらくじょう
○院政(白鳥を縦に二つ書く。二つ目の白鳥に後をつける)
白河上皇 1086年に院政開始、北面の武士
鳥羽 保元の乱の原因
(1156年 保元の乱)
後白河 策謀家「日本一の大天狗」、『梁塵秘抄』編纂
後鳥羽 西面の武士、承久の乱
○似絵の名手(連続して覚える)
藤原隆信
信実
○京都五山(ゴロ合わせ)
天 国 軒の 饅頭 豆腐(まんじゅうどうふ)、何膳でも。
天竜寺 相国寺 建仁寺 万寿寺 東福寺/ 南禅寺(別格)
○三大改革の前後(ゴロ合わせ)
ゲ! しょう(そう)来 た か。 王 手!
元禄時代→正徳の政治→享保改革→田沼時代→寛政改革 →大御所時代→天保改革 |
|
|
|
| 2015年12月19日(土) |
| ゴロゴロ日本史 |
日本史用語には紛らわしいものが多い。それを区別するには、ちょっとした工夫が必要だ。そうした工夫の例を、少しあげてみよう。もっとも、受験生なら、いろいろな語呂合わせを頭の中に詰め込んでいるだろうが。
○更新世(氷河時代)に日本にやってきた動物
北からマンモス・ヘラジカ(4文字)
南からナウマンゾウ・オオツノジカ(6文字)
○土偶と埴輪の時代の見分け方
じょうもん→どぐう(濁音同士)
こふん→はにわ (清音同士)
○朝鮮半島の新羅と百済の位置関係
高句麗
ひ み
百済くだら 新羅しらぎ
り
加羅(伽耶)
○私有地・私有民の区別
おおきみ(大王)→みやけ(屯倉)→こしろ・なしろ(子代・名代)(清音同士)
ごうぞく(豪族)→たどころ(田荘)→かきべ(部曲)(濁音同士)
○渡来僧の伝えた文化 (ドングリころころの歌で)
ドングリころころ紙(かみ)・墨(すみ)・絵(の具)、くだらの かんろく こよみだね
曇徴 高句麗 紙・墨・絵の具 / 百済 観勒 暦
(高句麗僧の曇徴は紙・墨・絵の具の製法を、百済僧の観勒は暦をわが国に伝えたといわれる)
○仏教公伝年とそれに関する史料
ここに(552年)仏教伝来、ごさんぱい(538年)
538年説(ごさんぱい)
→『上宮聖徳法王帝説(じょうぐうしょうとくほうおうていせつ)』
『元興寺縁起(がんごうじえんぎ)』(濁音同士)
552年説(ここに)
→『日本書紀(にほんしょき)』(清音同士)
○ 552年に足し算
552年(仏教伝来『日本書紀』)+200年→752年(大仏開眼供養)+300年
→1052年(末法元年)
○「聖」なる仏教関係者
聖明王(百済の王でわが国に仏教を伝えた)
聖徳太子(厩戸王。憲法十七条で仏教重視、法隆寺を建立)
聖武天皇(国分寺・国分尼寺の建立、大仏造立、「鎮護国家」)
○藤原氏の他氏排斥事件の順番(俳句っぽく)
ヤクルトや、ジョワが 横転、 道に あんなに
薬子の変 承和の変 応天門の変 道真左遷 安和の変 |
|
|
|
| 2015年12月13日(日) |
| 鉛の兵隊トテチテタ |
|
今月9日、85歳で亡くなった野坂昭如(のさかあきゆき)氏は、多才な人だった。童謡の『オモチャのチャチャチャ』を作詞したことでも知られている。
ところで、この童謡の中に、「鉛の兵隊トテチテタ」という言葉が出てくる。この「トテチテタ」というのは、いったい何のことだろうか。
江戸時代末期、幕府はフランスの援助を受け、西洋式の軍事訓練を行った。その時、信号ラッパの訓練も行われた。しかし、その頃の日本人は、西洋の音階(ドレミファソラシド)がわからない。そこで、音を出しやすい口の形を示すために、タ行を使って「ド・ト・タ・テ・チ」と吹き方を教えた。これがのち、より言いやすい言葉として「ト・テ・チ・テ・タ」に変化したのだという(NHKクイズ日本人の質問編『NHKクイズ日本人の質問』1996年、河出書房新社、P.234)。
野坂氏というと、破天荒な行動をする人、という印象がある。しかし、最期まで「戦争反対」を言い続け、日本の行く末に警鐘を鳴らしていた。一本、筋を通す昭和人の一人だった。ご冥福をお祈りする。
|
|
|
|
| 2015年11月29日(日) |
| 歴検を受けてきた |
|
1年ほど前、ふと漢字検定1級を受けようと思い立った。その際 「漢字検定1級に合格したら、ポメラ(文字だけしか打てないメモ機。起動が早く乾電池で動く)を買おう」と自分自身にニンジンをぶら下げて、勉強してきた。試験は先月の25日(日)。しかし、合否結果が郵送されて来る数日前に、ポメラを買ってしまった。電気店で値引きしていたのを見つけてしまったからだ。幸い昨日、合格証が送られてきた。自分自身への約束を違えることにならず、とりあえずはよかった。
今日は歴史検定があったので、午後から1級日本史を受験してきた。地元で受けられるので、ここ数年間、ボケ防止のために受験し続けている。年に一度の年中行事だ。例年は、12月初旬の日曜日が検定日だ。だから、歴史検定が終わると「そろそろ今年も終わりか」という感慨をもつ。
検定を終えての帰り道、「来年は古文書の勉強でもしようか」と考えているところだ。
|
|
|
|
| 2015年11月24日(火) |
| 武士の上役は老人ばかり? |
江戸幕府の職制では、現代の総理大臣や国務大臣等に相当する役職を、大老・老中・若年寄などといった。これらの役職には、「老」や「年寄」という文字が入っている。各藩にも藩政を取り仕切った家老といった役職があった。これにも、「老」の文字が入っている。江戸時代の武士のリーダーは、老人ばかりだったのだろうか。
結論を先に言ってしまえば、「老」や「年寄」はリーダーという意味で、年齢とは関係がない。15世紀頃、村や町に自治組織が形成されると、そのリーダーをオトナとかトシヨリなどと呼んだ。当初は、年長者や経験者が組織の代表者に選出されただろうから、かく呼んだのだろう。このオトナ・トシヨリに「老」「年寄」と当て字した。つまり、大老・老中・家老というのもオトナ(すなわちリーダー)という意味なのだ。
武士も本来は、村や町の住人だった。近世になって身分制が分かれることによって武士になったわけだから、かつての自治組織のリーダーの名称の痕跡が、幕制・藩制の職名となって残っているわけだ。
【参考】
・尾藤正英『日本文化の歴史』2000年、岩波新書、P.145
・井上光貞他『日本歴史大系3・近世』1988年、山川出版社、P.241~241
|
|
|
|
| 2015年11月13日(金) |
| てまり上人 |
菅江真澄(すがえますみ。1754~1829)の『高志栞(こしのしおり)』に良寛のことが載っていたので、句読点を適宜付して書き写した。( )の中の片仮名は原文のまま。原史料は大館市立図書館のホームページ(http://lib-odate.jp/sugae.html、2015年11月10日閲覧)にpdfファイル形式で公開されている。
○てまり上人
手鞠上人は出雲崎の橘屋ノ由芝(1)(割注)「三井氏門葉也」がはらから(割注)「弟(2)也」、名を良寛といふ。國上山の五合(3)に住ぬ。くし作り、うたよめり。うたなどはいといとよけく、鵬齋(4)翁も此書(テ)なとはいミしきよしを誉める也。托鉢にありくに、袖にまり二ツ三ツを入れもて、児女手まりつく處あれハ、たもとよりいだして、ともにうちて小児(ワラハ)のごとに遊びける。まことにそのこころ、童(ヲサナキ)もののごとし。よめるうたに、
此里の宮の木下タの小どもらとあそぶ春日ハ暮れずともよし
【注】
(1) (2)「由之(よしゆき)」の誤り。由之は良寛の弟。
(3)五合庵。国上山の中腹にあった庵。良寛は文化元(1804)年から13年住んだ。
(4)亀田鵬斎。折衷学派の儒学者、書家。1752~1826。 |
|
|
|
| 2015年11月11日(水) |
| みんなくねくね |
|
せっかく、會津八一記念博物館を再訪したことだ。「明暗」を見るだけで帰るのはもったいない。再び、八一の書を見て回ることにした。この時しげしげと鑑賞したのは、良寛(1758~1831)の漢詩を八一が書いた作品。
子どもらと鞠つき遊びに興じる良寛の姿を、越後に来ていた亀田鵬斎(かめだぼうさい。儒学者・書家。1752~1826)がスケッチした。鵬斎がその絵に賛を添えるよう求めると、良寛は七言詩を書き付けた。八一の書は、その七言詩を書いたものだ(漢詩の本文・読み下し・大意は『訳注良寛詩集』(大島花束・原田勘平訳注・1933年、岩波文庫)やインターネット等を参照した)。
日々日々又日々 間伴児童送此身 袖裏毬子両三箇 無能飽酔太平春
(読み下し)
日々(にちにち)日々、又(また)日々。間(のどか)に児童を伴って此の身を送る。
袖裏(しゅうり)の毬子(きゅうし)両三箇。無能飽酔(ほうすい)す太平の春。
(大意)
毎日毎日、子どもたちと長閑に遊び暮らしている。袖の中にはいつも二、三個の手まり。
何の取り柄もない私だが、太平の春を満喫している。
八一の書は、くねくねとした草書だった。そういえば、良寛もくねくねとした草書を書く。また、亀田鵬斎もくねくねとした草書を書いた。みみずがのたくったような字だというので、鵬斎の書は蚯蚓流(みみずりゅう)と言われた。
鵬斎がくねくねとした草書を書くようになったのは、「良寛の書風に影響を受けたから」というのが江戸川柳子の解釈。
鵬斎は越後がえりで字がくねり
ただし、ウィキペディアには、鵬斎の書風は中国唐代の書家懐素(かいそ)の影響によるところが大きい、とある(「亀田鵬斎」の項。2015年11月9日参照)。
|
|
|
|
| 2015年11月10日(火) |
| 「明暗」を見に行った |
先週の土曜日(11月7日)、會津八一記念博物館(早稲田大学構内)に行ってきた。横山大観・下村観山の合作「明暗」を見るためだ。今春、当地を訪れた際には、公開されていなかった。貴重資料であるため管理の都合上、公式行事や展覧会等の機会のみ公開しているのだという。
折しも学園祭のさ中。構内は大勢の人でごった返していた。博物館の真正面に学生たちの発表ステージが設けられていたので、喧噪はなおさらだった。人混みを抜け、館内に入ると喧噪からは解放された。
そして、世界最大の手漉き和紙(直径445cm)に描かれた「明暗」と、ついに対面できた。
1925(大正14)年、早稲田大学図書館が竣工すると、ホール正面に飾る絵が求められた。「明暗」は、図書館に飾る目的で制作された作品なのだ。「混沌とした暗闇から知恵の日が昇る」有様が描かれている。「読書をしなければ無知蒙昧のままで暗く、すれば知識を獲得して明るくなる」との趣旨だ。絵の完成は1927(昭和2)年。
館内は写真撮影ができないので、1階受付で「明暗」の絵をあしらったクリアファイルを購入した。
【参考】
・早稲田大学HP(http:www.wul.waseda.ac.jp/collect/other/meian.html)、2015年11月5日閲覧。
|
|
|
|
| 2015年11月8日(日) |
| 安全な水の誕生 |
「水道水は塩素臭い」というので、わざわざお金を出してミネラル・ウォーターを買う人たちがいる。しかし、その「塩素臭い水道水」が、わが国の乳幼児死亡率を押し下げ、平均余命を改善させたという。
乳幼児死亡率が高かった原因はいろいろあっただろう。しかし、水道水が塩素殺菌されるまでの死亡率は、ことのほか高かったという。水道水を通じて運搬された細菌が、抵抗力の弱い多くの乳幼児を死に至らしめたのかも知れない。19世紀のイギリスにおいて、コレラ菌を含んだ不衛生な水道水が、病死者を増加させる原因になっていたという例もある(1)。
それが、水道水が殺菌されるようになると、乳幼児死亡率は次第に低下していった(2)。東京市で水道の塩素殺菌が始まったのが1921(大正10)年。1921年段階で30万人以上の乳幼児が死亡していたが、この年を境にみるみる死亡率は低下していく。だから1921年は、「安全な水」が誕生した年であるとも言える。
しかし、なぜ1921年というこの時期に、水道水へ塩素殺菌が導入されたのか。それはシベリア出兵(1918年開始)に関係があるという。シベリア出兵を機に、軍事用の液体塩素(毒ガス用)が開発された。しかし、出兵が早期に終了してしまったため、民生利用(水道水の殺菌)に転用されたのだという。国土交通省の官僚だった竹村公太郎氏は、「民生利用を推進した立役者は、当時の東京市長後藤新平ではなかったか」と推理するが、真偽の程は不明だ(3)。
いずれにせよ、「塩素臭い水道水」が多くの人命を救う一助を担ったことは間違いない。もっとも、今では水道水もずいぶんと改善されておいしくなった。東京都では、水道水をミネラル・ウォーターのように、容器に入れて売っているという。
【注】
(1)西内啓『統計学が最強の学問である』2013年、ダイヤモンド社、P.10~14
(2)乳幼児死亡率が低下した理由は、水道水の殺菌だけによるのではない。公衆衛生や医療設備の整備等も大きく関わっていた。速水融氏らによれば「出産が自宅ではなく病院、それも産院で行われるようになったこと」、「また、自宅で出産する場合も、産婆が介助することで、産婦・産児ともに死亡率が下がった。粉ミルクが登場し、大正8年には練乳も発売され、哺育が容易になった」(速水融・小嶋美代子『大正デモグラフィ-歴史人口学で見た狭間の時代』2004年、文藝春秋(文春新書)、P.220~221)等のことが乳児死亡率を押し下げた理由だという。
(3)荻原邦男「『大正10年における乳幼児死亡率改善』と『後藤新平』~専門知とは何か~」、
http://www.nli-research.co.jp/report/researchers_eye/2013/eye140219.html。2015年11月6日閲覧) |
|
|
|
| 2015年11月3日(火) |
| ない袖は振れぬ |
|
参勤交代のために、莫大な国費が浪費された。国元が遠方の大名ほど旅費が嵩(かさ)む。江戸在府の費用も馬鹿にならない。在府費用は片道旅費の同額から倍額かかったという。江戸時代の川柳に、
半分は江戸へこぼれる雀の餌
というのがある。米所仙台藩(「竹に雀」紋は仙台藩主伊達氏の家紋)の財政収入の半分が、参勤交代や江戸在府で消費されてしまうという意味だ。
実際、参勤交代にはどれほどの費用がかかったのか。高崎藩8万2,000石の場合、江戸まで26里の片道旅費が900両、佐賀藩35万,7000石の場合が江戸まで260余里の片道旅費が2600両だったという。莫大な支出だ。
だから、たいていの大名は経費節減のために、さまざまな工夫・努力を重ねた。しかし、そうした涙ぐましい倹約ぶりも、庶民の目には「大名のくせに、何ともしみったれた行動だ」くらいにしか映らなかった。
人の悪いは鍋島(なべしま)・薩摩、暮れ六(む)つ泊まりの七(なな)つ立ち
(午後6時頃着、午前4時頃発の強行軍。宿泊数を減らすために、昼間に移動距離をかせごうとした)
お国は大和(やまと)の郡山(こおりやま)、お高は十と五万石、茶代がたった二百文
(大和郡山藩の柳沢甲斐守は15万石の大名のくせに、たった200文の茶代しか使わない)
松本丹波のくそ丹波、くそといわれても銭出さぬ
(信州松本藩6万石の戸田丹波守に至っては、宿場に1文の金も落とさない)
【参考】
・渡邊容子「参勤交代について」
(華頂短期大学博物館が学芸員課程『華頂博物館学研究』第5号、1998年12月所収)
・早川明夫「参勤交代のねらいは?-「参勤交代」の授業における留意点-」
(文教大学『教育研究所紀要』2007年12月所収) など
|
|
|
|
| 2015年11月2日(月) |
| 華美になる大名行列 |
参勤交代制が、将軍との主従関係を確認するための大名の役儀・奉公だったことは、すでに述べた。
参勤交代時に、幕府は弓・槍等の武器類携行を諸大名に義務づけた。参勤交代が、軍役の一つだった証拠だ。つまり、参勤交代の大名行列は一種の軍事パレード、軍事デモンストレーションでもあった。だから、大名の宿泊所を「本陣」といったのだ。
さて、参勤交代の大名行列は、次第に華美を競い合うようになった。何年もそうした競い合いを繰り返していくと、そうした華美な風俗はいつの間にか「伝統」となってしまい、「格(かく)」と呼ばれるようになった(荻生徂徠『政談』)。
「格」の高い大名行列といえば、紀州藩のものがとりわけ有名だった。紀州藩の大名行列がことのほか盛大で見事だったのは、「親藩としてのご威光を張るため」だったという。つまりは、見栄(みえ)だ。
見栄の張り合いから生まれた「格」が、大名行列の編成や人数を甚だしいものにしていった。行列の長さは数キロメートルから数十キロメートル、一つの宿場を通過するのに数日を要する大名行列もあったという。
一茶の俳句に、越後柏原宿(一茶の故郷)を通過する大名行列が、延々と続く有様を詠んだ句がある。
跡共(あとども)は 霞(かす)みひきけり 加賀の守(かみ)
はるか遠方に、行列の供人(ともびと)が霞んで見える、というのだ。ちなみに加賀100万石の5代藩主前田綱紀(つなのり)の頃の行列が4,000人、12代藩主前田斉広(なりひろ)の頃の行列は3,500人だったという。 |
|
|
|
| 2015年10月21日(水) |
| 参勤交代制度化の目的は? |
「参勤交代制度化の目的は、大名の財力を削り、幕府への反乱を防止するため」と、かつてはいわれた。しかし、武家諸法度を読むと
「従者の員数(いんずう)近来(ちかごろ)甚(はなは)だ多し。且(かつ)は国郡の費(ついえ)、且は
人民ノ労也。向後(きょうこう。今後)其(そ)の相応を以(もっ)て之(これ)を減少すべし」
(武家諸法度寛永令)
と、幕府はむしろ大名たちの浪費に対して自制を求めている。これを見ても、参勤交代制度化の本来の目的が、経済的理由になかったことは明らかだ。
大名が江戸の将軍のもとに伺候(しこう)したのは、将軍に対する忠誠を示す自主的・儀礼行為だった。だから、家康は外様大名に対して参勤交代を奨励はしたものの、強制まではしなかった。また秀忠は、将軍自ら大名行列を見送って、遠方からわざわざやって来た大名をねぎらってもいる。
それが家光の時代になると、江戸城大広間に諸大名たちを集めて武家諸法度を読み上げ、役儀・奉公としての参勤交代を一方的に命令しているのだ。
将軍とはいえ、かつて同僚だった大名たちに対して、家康・秀忠には遠慮があった。「生まれながらの将軍」家光には、そうした遠慮がなかった。だから、参勤交代の制度化に踏み切ったのだ。
参勤交代を制度化した目的については、さまざまな意見が出されている。しかし、主なる目的が、将軍権力の安定化にあったことは間違いない。将軍・大名間の主従関係を再確認させ、地方に割拠していた大名たちを将軍権力のもとに統制しようとしたのである。
参勤交代のために往来する大名行列は、将軍権力の強大さを庶民の前に視覚化したものとも言える。この点からも、参勤交代は、将軍権威を大いに高める役割を果たしたはずである。 |
|
|
|
| 2015年10月8日(木) |
| しっぽ |
ある老人、買い物に出て日暮れになった。余りに疲れたので、道で見つけた駕籠を雇って帰ることにした。「稲荷橋までやっておくれ」と声をかけ、駕籠に乗った。
目的地に着いたので代金を払おうとすると、駕籠かきが地べたにひれ伏して変なことを言いだした。
「いかで其(その)賜ものをうくべき、只われらの息災延命を守り給へ」。
老人が強いて代金を渡そうとすると、ふたりとも逃げ去ってしまった。事情が飲み込めないまま、自宅に戻った老人。ふと見ると、羽織の隙間からしっぽが出ている。老人は狐の毛皮を買い求めた。その際、手で持ち帰るのが面倒だったので、腰にまいた上から羽織を着ていたのだ。
駕籠かきは、老人を稲荷明神とでも勘違いしたのだろうか。(続日本随筆大成第6巻、吉川弘文館、1980年、P.42~43参照)
これは、松平定信が書いた『退閑雑記』(巻之二)にある話。定信と言えば、「寛政改革成功のためなら、我が女房・子供の命まで差しあげましょう」などと、とんでもない誓約をする男だ(江戸本所吉祥院の歓喜天に、天明8(1788)年正月2日付けで願文を奉納している)。
そんな定信が落語のような話を、わざわざ書き留めている。妙におかしい。 |
|
|
|
| 2015年9月29日(火) |
| 羊の生(な)る木 |
|
17世紀初め、イギリスはアジア貿易に乗り出していた。ところが1623年、「世界の運搬人」オランダに、モルッカ諸島のアンボン島で痛烈な一撃をくわされた(アンボイナ事件)。この事件をきっかけに、イギリスは香辛料産地であるインドネシア東部から撤退し、平戸にあったイギリス商館まで閉鎖して日本貿易からも手を引いた。
そして、舳先(へさき)を南アジアに方向転換して、インドで「VEGETABLE LAMB(「羊の生る木」の意。木綿を知らなかった中世ヨーロッパ人の言葉)」に行き当たった。
綿製品に出会ったイギリス人は、欣喜雀躍した。綿製品は何回も洗えて衛生的であり、夏は涼しく、冬は暖かい。染色も容易だし、おまけに安い。インドの人件費はイギリスよりはるかに低かったため、イギリス製毛織物製品よりもインドの綿製品の方がはるかに安かったのだ。たちまちイギリスでは綿製品ブームが起こった。
綿製品の需要に応えるため、イギリスでも綿製品の生産が始まった。しかし、インド製綿製品の安さに対抗するためには、大量生産によるコストカットを達成しなければならなかった。そこで機械による大量生産という方式がとられることになる。
イギリスの産業革命が伝統的な毛織物工業からではなく、綿工業から始まったのは、こうした理由によるのだ。
【参考】
・祝田秀全『忘れてしまった高校の世界史を復習する本』2003年、中経出版
|
|
|
|
| 2015年9月19日(土) |
| そんなことまで言わなくていいのに |
|
夏目漱石の紹介で、朝日新聞に長編小説『土』の連載が決まった長塚節(ながつかたかし)。まとまった金額の原稿料が支払われることとなり、その大金を新聞社の某(なにがし)が持ってきた。某が漱石夫人に語ることには、「今日これだけの金を長塚さんに渡すのだが、きつといろいろ厄介になつているから、今晩御馳走をしてくれるに違いない」。
しかし長塚は、原稿料全額を田舎へ送金してくれるように依頼し、某にはバナナ一房だけを礼として贈った。御馳走を食べそこねた某は「節の奴、あの金できつと田地を買ふんだよ」と憎まれ口。こうした長塚節のつつましい生活ぶりに対する漱石夫人の評が次。
長塚さんのつつましいのは評判でしたが、私どものところにもその御禮だとあつて、
五六十銭かと思ふ半分腐(くさ)りかけた果物の籠(かご)を持つて來てくだすったもの
でした。(夏目鏡子『漱石の思ひ出・後篇』1954年、角川文庫、P.92)
いくら思い出話だといっても、「お礼が安物で、おまけに傷んだ果物だった」なんて、長塚の不名誉になるようなエピソードまで披露せずともよかったのに。「長塚さんのつつましいのは評判でした」で止めておけば、夫人自身の品格が疑われることもなかった。
|
|
|
|
| 2015年9月8日(火) |
| あえて誤訳 |
われわれ日本人が「国際連合」と呼んでいる組織は、英語表記では「United Nations」だ。素直に訳せば「連合国」だ。
連合国というのは、第二次世界大戦で日本・ドイツ・イタリアのいわゆる「枢軸陣営」と戦ったアメリカ合衆国やイギリスなどのグループの呼称だ。つまり、「United Nations」というのは、連合国がつくった国際的な枠組みであり、戦争中の呼称をそのまま使っているのだ。
しかし、敗戦国日本が「United Nations」に加盟する時、旧敵国のグループ名「連合国」に加盟するというのでは、どうも具合が悪い。そこで、外務省は意図的に「United Nations」を「国際連合」と誤訳したのだ(池上彰『ニュースの読み方使い方』2004年、新潮文庫、P.204)。
外国語の意図的翻訳ばかりではない。これまでも政府が、敗戦記念日を終戦記念日、占領軍を進駐軍、戦車を特殊車両などといった日本国内向けの意図的な言い換えはいくらでもあった。
これらは、ある種の情報操作と言えなくもない。 |
|
|
|
| 2015年8月29日(土) |
| 尾崎紅葉 |
丸善に、尾崎紅葉(おざきこうよう。1867~1903)が現れた。そこで働く内田魯庵(うちだろあん。1868~1929)は、旧知のやせ細った姿を見て驚いた。紅葉が言うに、「癌(がん)で余命3ヶ月」とのこと。
来店目的は、ブリタニカの予約だった(ただしこの時、ブリタニカは在庫がなかった)。百円以上する高価な辞書だ。紅葉は生前、3円50銭の絵だか骨董だかが買えなかった(魯庵は、これを誤聞と断じている。しかし、そんな話が世間に伝わるほど、紅葉は切りつめた生活をしていたのだ)。経済的にも余裕がなく、余命幾ばくもない病人が、そんな高価な辞書を買ってどうする気か。
「欲しいと思うものは頭のハッキリしている中(うち)に自分の物として、一日でも長く見て
おかないと執念が残る。字引に執念が残ってお化けに出るなんぞは男が廃(すた)ら
アナ!」
と力のない声で呵々(からから)と笑いながら、
「『センチュリー』なら直ぐ届けられるだろう。」
「むむ、『センチュリー』なら直ぐ届ける」
というと、漸(ようや)く安心したような顔をして、
「これで先(ま)ア冥土へ好い土産ができた」
と笑いながら丁度店員が応接室の外を通ったのを呼留めて申込書と共に百何十円の
現金を切れるような紙幣(さつ)で綺麗に支払った。
(内田魯庵「硯友社の勃興と道程-尾崎紅葉-」(底本は「思い出す人びと」1924年)、青空文庫による)
ほどなくして、紅葉は永眠した。魯庵は、死の間際まで知識欲の高かった紅葉を、「決してただの才人ではなかった」と評している。 |
|
|
|
| 2015年8月27日(木) |
| 江戸の人口は2億4千万人? |
「18世紀前半、江戸の人口は100万人で、江戸は世界最大の都市だった」。日本史の教科書にはそう書いてある。果たして、本当だろうか。
何せ、国勢調査がなかった時代のことだ。8代将軍吉宗の時、子年と午年に全国の人口調査を始めたというが、それも悉皆調査ではなかった。
江戸の人口について、300万人説、140万人説など、かつてさまざまな説が飛び交っていた。つまるところ、江戸の人口に関する正確な史料がなかったからだ。
では、現在の通説「江戸の人口100万人」というのは、どこからきたのだろう。
どのように調査されたのかは不明だが、江戸の人口を記載した史料は、あることにはある。たとえば、1724(享保9)年と1815(文化12)の人口データを下に示した。江戸の人口は江戸時代前期に急増し、中期から幕末までほぼ停滞していたことが知られている。停滞していたのなら、①と②の人口データはほぼ一致するはずだが、どうだろう。
① 1724年の江戸人口(出典:『柳烟随筆』)
町方 588.325人
武家 53,865人
合計 642,190人
② 1815年の江戸人口(出典:『甲子夜話』)
町方 532,710人
出家 26,090人
山伏 3,081人
新吉原 8,480人
武家 236,580,390人
合計 237,150,751人
②の史料では、江戸には何と2億4千万人の人々が住んでいたことになっている。①と②が相違する最も大きな原因が、武家人口の差にあることは明白だ。参勤交代で絶えず武家の往来が絶えない江戸では、武家人口の把握が困難だったのだろう。
ちなみに町方の人口は、他の史料でも55万~60万人前後である。だから町方人口は少なくとも50万人はいたはずだ。そして、江戸の市域の規模を考えれば、武家人口も50万人くらいと見るのが妥当という。だから江戸の人口は、50万人+50万人=100万人ということになったのだ。
【参考】
・大石慎三郞『江戸時代』1977年、中公新書、P.113~117 |
|
|
|
| 2015年8月26日(水) |
| 郵便制度の導入 |
イギリスの切手には国名が入っていない。世界最初に切手を作ったからだ。わが国の郵便制度はイギリスから導入された。導入したのは、租税権正(そぜいごんのしょう)だった前島密(まえじまひそか)。現在、1円切手の肖像になっている。
郵便制度は1871(明治4)年3月1日、東京・京都・大阪の三都市間で始まった。東京から京都・大阪までの間に、郵便役所は65カ所しかなかった。初日の全郵便役所の差し立て数は308通のみだったという。
使用された切手は48文、100文、200文、500文の4種類。郵税(郵便料金)は距離別制で、同一市内なら48文、東京から小田原までが200文、大阪まででは1貫500文だった。1貫500文は銭に直すと15銭になる。当時は握り鮨1人前が5銭だったという。かなり高価で、庶民が気軽に利用できるものではなかった。
【参考】
・田辺猛「少女の涙から生まれた切手」-『スタンプマガジン』1996年4月号- |
|
|
|
| 2015年8月25日(火) |
| 電信柱 |
夕空を見上げると、電信柱のてっぺんにカラスがとまっている。電信柱というのは、もともと電信のために敷設したものだ。電信の役割がなくなった今日でも、一般的には電信柱と呼ばれている。
わが国に実用電信が初めて敷設されたのは1869(明治2)年。イギリスから電信技士を招き、横浜市内の官舎と裁判所の間に設けられた。翌1870(明治3)年には、東京・横浜間に敷設された。当初は電信と呼ばれず、「針金通し」と呼ばれた。
当時の多くの日本人は、電信が何をするためのものか、わからなかった。「電線を引く(敷設する)」というのを「伝染病を引っ張ってくる」と誤解して、電線を切ったりした。「物を遠くに運ぶそうだ」と生聞きして、遠方の親戚に荷物を送ろうと、風呂敷包みを電線にぶら下げる人もいた。そのため、馬に乗った警官が、電線を見張っていたという。 |
|
|
|
| 2015年7月27日(月) |
| 銀の国 |
15世紀後半以降、明が銭経済から銀経済へと移行する中で、膨大な銀需要がうまれた。その結果、中国では金の対銀相場が大幅に下落した。1600(慶長5)年頃、日本での金銀比価は1対12だったが、中国では1対5だった。金1gを銀に替えると日本では12gになるのに、中国では5gにしかならなかったのだ。だから、石見銀山などで銀が豊富に産出していた日本では、中国産生糸の支払いには金を使わず、銀で決算したのである。
中国にとって、気前よく銀を支払ってくれる日本は、貿易相手として魅力的だった。一方日本も、高級衣料の原料である中国産生糸の獲得を熱望していた。このような両者の思惑から、中国産生糸と日本銀との取り引きは膨大な量にのぼった。
この貿易で、1年間に日本から流出した銀は200トン。当時の世界全体での銀産出量は年間420トンだったというから、流出した日本銀がいかに巨額だったかがわかる。
この時代、石見銀山をはじめとする日本の銀山は、世界経済に大きな影響を与える存在だった。この意味において、わがジパングは「黄金の国」ではなく、「銀の国」だったのである。
【参考】
・荒木信義『黄金島・ジパング~謎解き・金の日本史』
-『NHK知るを楽しむ 歴史に好奇心2006年8月~9月テキスト』P.150~151- |
|
|
|
| 2015年7月26日(日) |
| 日の目を見た手紙 |
|
何も書かれていない白紙がある。それを光にかざすと、文字がうきでる。手紙なのだ。
1910(明治43)年、社会主義者の管野スガ(かんのすが。1881~1911)ら4人は、明治天皇暗殺を企てた容疑で獄中にいた。取調べが進むなかで管野は、官憲が幸徳秋水(1871~1911)ら社会主義者を事件の首魁に仕立て上げようとしていることを察する。秋水は、事件には無関係だった。
そこで、管野は獄中から幸徳の無実を訴えようと考えた。彼女は看守の目を盗み、半紙に無数の針穴を開けることによって文字を認(したた)めた。手紙はひそかに獄中から持ち出され、新聞記者の杉村楚人冠(すぎむらそじんかん。1872~1945)のもとに届けられた。しかし管野の願いもむなしく、1911(明治44)年、管野らともども幸徳らも刑死(大逆事件)。
光にかざすと文字が見えるこの手紙は、2006(平成18)年に千葉県で発見された。100年の時を経て、日の目を見た手紙だ。
【参考】
・梯久美子『百年の手紙』2013年、岩波新書、P.12~14による。
|
|
|
|
| 2015年7月21日(火) |
| 雁は自然暦の一つ(雁取り5) |
雁には食料、害鳥などの側面のほかに、季節の指標としての役割があった。たとえば、一茶の
斯(こう)しては居られぬ世也雁がきた(1)
という句は、雁の飛来によって、冬支度の準備に大わらわになる信州の農村風景を詠んだものと解せられる。
ところで、ウグイスなどの鳴禽類がもっぱらその鳴き声によって季節の変わり目を知らせるのに対し、雁の場合、その鳴き声ばかりでなく、人々の視覚に訴えて季節の到来を認識させる。棹になり鍵になりして群飛する雁行という習性は、とにかく目立つ。だから、そうした雁の飛行形態を見つけると、
がんがん弥三郎、おびになれたすきになれ(2) (注:濁点は筆者が入れた)
と、子どもたちは囃し立てた。
それでは、雁行はいつごろ見られるのか。中国では社日(しゃにち)、すなわち春分・秋分に最も近い戊(つちのえ)の日に雁が往来すると考えた。
わが国ではどうであったのか。近世初期の『犬子集(えのこしゅう)』には、次のような句がある。
鳥ならで立帰ゆくひがんかな(3)
声きけバ雲にも二季のひがん哉(4) (注:濁点は筆者が入れた)
中国思想の影響もあるかも知れないが、飛雁(ひがん)に彼岸(ひがん)を掛けているので、日本でも雁は秋分頃に飛来し、春分頃帰る渡り鳥と見なされていたのだ。このように雁は年2回の彼岸頃に往来する鳥として認識されていたため、二季鳥(ふたきどり)・候鳥(こうちょう)などの異称を持つ。
そこで、雁の往来する頃の季節的な事物・事象の名称にも、雁の名前が付されることになった。たとえば、旧暦8月を「雁来月(がんらいづき)」、八月に吹く風を「雁わたし」、帰雁の頃降る雪を「雁の目隠し」(東北地方)と唱えるなど。このほかにも、雁金草(かりがねそう)、雁来紅(がんらいこう。葉鶏頭のこと。雁の来る頃、葉が赤くなる)、雁瘡(がんがさ。痒疹の一種)、ガンタケ(シメジ茸の肥前方言)、麦蒔雁(むぎまきがん。隠岐海士郡西海岸の諺)等があり、「雁が来るころ(または帰る頃)○○になる(○○をする)」式の命名法だ。
「雁取爺」の昔話も、我々の祖先に秋を連想させる昔話だったのかも知れない。
【注】
(1)『七番日記』-一茶全集第3巻、P.385-
(2)『弄鳩秘抄』-芸能史研究会編、日本庶民生活史料集成第5巻、1973年、三一書房、P.909-
(3)(4)松井重頼撰『犬子集・上』1967年、古典文庫、P.46、P.161
(5)川口孫治郎『自然暦』1972年、八坂書房
|
|
|
|
| 2015年7月20日(月) |
| 雁は害鳥(雁取り4) |
|
雁取爺が得た幸福は、美味な雁汁を食べることだった。ただし、この昔話に狩猟的モチーフがあるとはいえ、現代的なわれわれの感覚からすると、粗野で残酷な昔話という印象を受けるのは否めない。しかし、雁をはじめとする渡り鳥は、狩猟対象でなければ、長らく排除すべき害鳥だったのであり、農民たちにとっては憎悪の的であった。
江戸時代に民間で行われていた風習に、正月七日の七草粥の前夜に七種の菜を俎板の上にのせ、包丁や擂粉木(すりこぎ)などで叩くというものがあった。その際、たとえば常陸国水戸地方(現、茨城県水戸市)では、次のような唱えごとをしたという。
七くさなつな、とうとの鳥の、いなかの土地へ、渡らぬさきに、ストトトトトトントン(1)
早川孝太郎によれば、「とうとの鳥」は「尊との鳥」であったという(2)が、その語源がどうであれ『諸国風俗問状答(しょこくふうぞくといじょうこたえ)』などにも「唐土の鳥」と当て字しているように、一般には人々は外国から飛来する渡り鳥と理解していた。地方的な異同はあるが、こうした唱えごとは現在でも「鳥追い唄」として日本各地で歌われている。突然群れをなして出現する渡り鳥は、一面では害鳥でもあった。
江戸時代の国学者菅江真澄が記録した仙台領胆沢郡徳岡の鳥追い唄には、害鳥に対する農民の強烈な憎しみが歌い込まれている。
早稲鳥ほいほい、おく鳥もほいほい、ものをくふ鳥は頭割(わ)ッて塩せて、
遠嶋さへ追て遣れ、遠しまが近からば、蝦夷が嶋さへ追てやれ(3)
追われる害鳥の種類は土地ごとに異なっている。たとえば、新潟県西蒲原郡では鴨類がそのおもな対象であり、その被害の甚大さを表現する「ゴッコ八万」の言葉があるという(4)。
それでは、この点について雁はどのように見られていたのだろうか。
上流階級の文学に登場する「頼むの雁(かり)」(『伊勢物語』第10段)は「田の面(も)の雁」の転であるし、陰暦8月の季語「代(しろ)かえる雁(かり)」の「代」も田のことである。田に舞い下りる雁の群れの情景を、彼らは風雅なものととらえるが、農民の思いは別の所にあった。田畑に舞い下りる雁陣による被害の甚大さは、近世の農書の多くが説くところである。加えるに、雁は狩猟の絶好の獲物でもあったため、為政者の鷹狩りによって害鳥の農作物への被害はさらに拡大することになった。
早稲晩稲の穂並出るより、北風に誘はれて雁鴨南に翔り、田に下りて稲を食ふ事
言ふはかりなし。百姓共は迷惑がりて追立てんとすれば、御鷹狩の為とて所所に
鳥見を置かれ、過銭を掛けて取らるる故に、追立つる事もならず。追ねば稲を一夜
の中にも皆喰ひ尽す。さる程に百姓共はこの雁を代官の如く、地頭の如く恐しがりて、
田の畔に佇み、血の涙と共に「いかにお雁様、お立ちなされて給はれ。さやうに稲を
上がりては、我等は水牢に入れらるる歟、妻子を沽却(こきゃく)いたすに」と言へ共、
常喰(ひたぐ)ひに喰ふ程に、一畝(いっせ)二畝(にせ)は今の間に藁ばかりになす。(5)
(早稲・晩稲の稲穂が出る頃になると、北風に誘われて雁鴨類に南に飛来して、田に下りて稲を食うことはひどいものだ。百姓たちは迷惑がって追い払おうとするものの、領主の鷹狩りのためと称してあちこちに見張り番を置き、追い立てようものなら罰金をとられるので追い払うこともできない。追い払わないと一晩のうちに稲が食い尽くされてしまう。そこで、百姓たちは雁のことを代官や領主のように恐ろしがって、田の畔に佇んで血の涙を流して「どうかお雁様、お帰りになって下さい。そんなに稲を召し上がっては、私どもは年貢が払えなくなって水牢に入れられるか、借金のかたに妻子を売らざるを得なくなってしまいます」といっても、雁たちは稲をひた食いに食うので1畝、2畝の田んぼは瞬く間に藁だけになってしまう。)
同様の鷹狩り批判は『可笑記』にも見える(6)。したがって、上の記述に誇張はあるかもしれないが、了意の全くの創作ではないだろう。現実の一端を踏まえたものと考えられる。
【注】
(1)『弄鳩秘抄』-芸能史研究会編『日本庶民文化史料集成第5巻』1973年三一書房、P.909-
(2)早川孝太郎「鳥を追う詞」1937年-全集第4巻、P.306-
(3)菅江真澄『かすむこまかた』天明6年1月16日の条-全集第1巻、P.334-
(4)金沢友之亟『蒲原の民俗』1967年、野島出版、P.276
(5)浅井了意『浮世物語』-日本古典文学大系90、1965年、岩波書店、P.306-
(6)『可笑記』-徳川文藝類聚第二、1970年(1914年初版)、国書刊行会、P.82~83-
|
|
|
|
| 2015年7月19日(日) |
| 雁は食材(雁取り3) |
|
雁は美味な食材として、民間で珍重されてきた。「葱(ねぎ)を背負った鴨」の慣用句がある鴨と同じガンカモ科の水鳥だ。
たとえば、高知県高知市の子守唄には、雁取爺に出てくる雁汁が、鯛の浜焼きと同等のご馳走として歌われている。
朝はとうからおひるなれ、お乳(ちち)の出端(でばな)を進(あ)げましよぞ、
お乳の出端がお嫌なら、鯛の濱焼雁の汁、ねんねんや(1)
ご馳走だからこそ、雁を射落とすことが大きな手柄になったわけであるし(昔話の「三人の婿」)、小判を投げつけてまで雁を獲ろうということにもなったわけだ(昔話の「三人の兄弟」)。「雁は八百、矢は三文」の諺も、雁の価値の高さを表現している。
雁の肉料理に舌鼓を打ったのは、こうした伝承を炉辺(ろへん)で語る人々ばかりではなかった。古典をひもとくと『古今著聞集』には大雁を食べる若侍たちの話が見えるし(2)、『きのふはけふの物語』には生臭坊主が檀家に雁を横取りされた話がのっている(3)。
江戸時代には、将軍放鷹(ほうよう)において、雁は鶴に次ぐべき獲物とされた。江戸で獲らえた初雁は禁裏へ献上され、貴族たちはそれぞれの品階に応じてこれを賜ったのち、宴会となった。これを「雁の披(ひらき)」という(4)。
都会の庶民たちも、旧暦10月に季節の初物として売り出される雁や鴨を食べることを楽しみにしていた。芭蕉の句に、
振賣(ふりうり)の雁(がん)あはれなりゑびす講(5)
がある。
【注】
(1)高野斑山・大竹紫葉編『俚謡集拾遺』1915年-復刻版、1978年、三一書房、P.325~326-
(2)日本古典文学大系84、1966年、岩波書店、P.490
(3)日本古典文学大系100、1966年、岩波書店、P.56
(4)人見必大著・島田勇雄訳注『本朝食鑑2』1977年、平凡社東洋文庫、P.165
(5)中村俊定校注『芭蕉俳句集』1967年、岩波文庫、P.277
|
|
|
|
| 2015年7月18日(土) |
| 昔話の分布とガンモドキ(雁取り2) |
『日本昔話大成』によると、「雁取爺」の昔話は福島以北と南九州にその分布が限られる。しかし、獲物の種類を雁に限定すると、この昔話は東北地方に厚く分布すると解せる(下表)。雁の渡りのコースから考えて、東北地方の人々が季節の変わり目に雁を目にする機会が多かったからだろう。
| 「雁取爺」の採話地 |
灰撒きによって手に入れた獲物 |
鹿児島 喜界島
沖永良部島
下甑島
熊本 某地
天草郡
長崎 北高来郡
岡山 真庭郡
島根 仁田郡
鳥取 (不明)
新潟 (不明)
福島 南会津郡
山形 最上郡
最上郡
最上郡
秋田 鹿角郡
仙北郡
平鹿郡
宮城 (不明)
岩手 二戸市
岩手郡
九戸郡
紫波郡
北上市
胆沢郡
水沢市
江刺市
遠野市
遠野市
上閉伊郡
釜石市
気仙郡
青森 上北郡
上北郡
三戸郡
三戸郡
八戸市
八戸市
八戸市
北津軽郡
南津軽郡
黒石市
西津軽郡 |
(灰撒きの条なし)
猪
(灰撒きの条なし)
(灰撒きの条なし)
(灰撒きの条なし)
(灰撒きの条なし)
(灰撒きの条なし)
(灰撒きの条なし)
(不明)
(不明)
雁
雁
雁
雁
雁
雁
雁
(不明)
雁
雁
雁
雁
雁
雁
雁
雁
雁
雁
(不明)
雁
雁
雁
雁
雁
雁
雁
(灰撒きの条なし)
雁
雁
鷹
雁
雁 |
※同一地名は採話数が複数のものである。『日本昔話大成』から作成(P.157~170)。
かつて雁は、美味な冬の食材としての価値を持っていた。現在、われわれが食しているガンモドキは「雁擬」であって、雁の肉の味に似せたもの、の意である。ガンモドキという言葉は、東北から関東地方において多く使われている。これは、「雁取爺」の昔話の分布が東北地方中心であるのと同じ理由だろう。雁の味を知っている人々がこの地域に多くいたことによる名残りと思われる。その証拠に、同じ食材を関西ではヒリョウズ(飛竜頭)、四国・九州地方ではヒロスと、ガンモドキとは異なる言葉で呼んでいる。これはポルトガル語のfilhosが語源とされる(大野晋『日本語の年輪』1966年、新潮文庫、P.125)。 |
|
|
|
| 2015年7月16日(木) |
| 雁取爺(がんとりじい。雁取り1) |
|
「花咲爺」の昔話は、江戸時代には「枯木(かれき)花さかせ親仁(おやじ)」などと題されて、赤本(子ども向けの絵本)によって民間に流布した。またこの昔話は、曲亭馬琴の『燕石雑志』をはじめとし、近世の随筆等にもしばしばとりあげられている。「花咲爺」は、江戸時代から知識人・一般庶民の別なく、人気のあった昔話の一つだったのだ。
しかも、そのあらすじ・内容ともに、現在のわれわれが知るところのものとほとんど変わっていない。これは、「花咲爺」の話の内容が早い時期に定型化し、明治期以降の教科書などで教材化されたりしたためだろう。そのため、「花咲爺」の昔話は古くから人気があったものの、話の地域性や民衆の生活臭が削ぎ落とされてしまっている。
ところで、「花咲爺」と同系の昔話に、「雁取爺」という話がある。柳田國男は、「雁取爺」を「花咲爺」の古型ではないか、と推測している(1)。両者とも真似そこないの「隣の爺」式の昔話であるが、「花咲爺」とくらべると、「雁取爺」の方が地域に根ざした民衆の生活臭を強く印象づけられる。ただし、その分、結末は粗野かつ残酷であって、現在の幼児絵本で語られるようなものではない。
次に、岩手県岩手郡の伝承例によって、「雁取爺」の内容を確認しておこう(2)。
ある日よい爺が川に梁(やな)をかけたところ、川上から木の株が流れてくる。薪にでもしようと思い、これを割ってみると中から小犬が生まれ、急速な成長を遂げる。成長した犬は爺と山へ行き、鹿を獲る。これを羨んだ隣の爺は、犬を借りて同じことを試みるが失敗する。隣の爺は失敗した腹立ち紛れに犬を叩き殺し、その死体を山に埋めて、目印に米の木(3)を立てて帰ってくる。よい爺は花の咲いたその木を伐って家に持ち帰り、座敷に飾る。すると、その木から金や米が落ちてくる。隣の爺が木を借りて真似てみるが失敗し、怒って火に焚いて灰にしてしまう。よい爺はその灰を貰って帰る。ある時、雁が頭上を連なり飛んでいくのを見たよい爺は、笊(ざる)に入れた灰を抱えて屋根の上にあがり、唱え言をしながら灰を雁に向かって投げつける。
「雁のまなぐ(眼)さ入れ、ぼだぼだ、雁のまなぐさ入れぼつぼつ灰撒(ま)いたとさ。したば鍵(かぎ)になって飛んできた雁のまなぐさ灰あ飛んで入って、ぼたぼた墜(お)ちてきたど。」
そこで、よい爺はよい婆と二人で喜んで、雁汁(がんじる)を煮て食べる。例のごとく、隣の爺は灰を貰ってこれを真似ようとする。しかし、唱え言をまちがえたために自分の目に灰が入り、屋根から転げ落ちる。下で待ち構えていた隣の婆は、てっきり爺を雁だと思い、これを叩き殺して雁汁にして食べてしまったというのである。
【注】
(1)柳田國男「花咲爺」1937年(『定本柳田國男集・第6巻』、P.214~215)
(2)関敬吾『日本昔話大成・第4巻』1978年、角川書店、P.156
(3)「米の木」は植物の方言で、『日本国語大辞典』(小学館)には「①あせび(馬酔木)。青森県南部地方 ②こごめうつぎ(小米空木)。青森県三戸郡・岩手県・秋田県 ③みつばうつぎ(三葉空木)。青森県・岩手県・秋田県 ④むらさきしきぶ(紫式部)。青森県津軽・秋田県・岩手県・宮城県(以下略)」とある。
|
|
|
|
| 2015年7月5日(日) |
| 壁に耳あり(2) |
|
インターネットで「壁に耳あり」を検索すると、国会図書館のHPに行き当たった(「コラム1壁に耳あり・史料にみる日本の近代」http://ndl.go.jp/modern/column/01.html)。そこにあったのは、竹橋事件(日本初の兵士反乱。1878年)発端に関する大木喬任(おおきたかとう)宛ての岩倉具視の書簡(明治11年8月23日付け)だった。写真版が掲載されているので、前半部分を紹介しておこう。なお、読みやすくするため、適宜句読点を付しておいた。
今夕、内務省判任官西村織兵衛退出、掛神田橋外通行之折柄、同所便所ニ立入
候処、近衛兵卒三人、右便所前片隅ニ立寄、及密談候儀、右判任官之者、
厠(かわや)中ニテ窃(ひそか)ニ聞取候大意、左之通。
今晩一時、近衛鎮臺(ちんだい)之者申合(もうしあわせ)、卒然「 」(1字闕字)皇城
近傍ニ火ヲ放チ、諸官員参朝之者、不残可及斬殺(のこらずざんさつにおよぶべし)
云云(うんぬん)。已(すで)ニ協議相整候との大意 -以下、略-
1878(明治11)年8月23日の夕方、内務省判任官(下級官僚)の西村織兵衛は退勤途中、神田橋に差し掛かったところで公衆トイレ(当時「辻便所」といった)に立ち寄った。西村が用を足していると、便所の前の片隅に近衛兵卒3人がやってきて、何やらひそひそ話している。個室の中からそれとなく聞き耳を立てていると、それはとんでもない内容の話だった。今晩、宮城近くに放火して、あわてて参内してくる政府の官僚たちを残らず斬殺する、という反乱の謀議計画だったのだ。3人が立ち去ると、西村はあわてて内務省にとって返し、内務書記官に急を知らせた。
この報は右大臣の岩倉から大木参議兼司法卿に知らされた。それが上掲の書簡である。「虚実如何ハ難測(はかりがたく)候へとも、萬一異変出来候而ハ一大事件ニ付」き、陰々に警備させていた。計画は事前に漏れていたが、結局、事件を阻止することはできなかった。しかし、近衛兵の一部が蜂起したものの、翌朝早々には鎮圧されている。
それにしても、いつどこで誰がどんな話を聞いているのか、わからない。滅多なことは口外できないな。
|
|
|
|
| 2015年7月2日(木) |
| 壁に耳あり(1) |
|
1203(建仁3)年7月、2代将軍源頼家が病に倒れた。翌8月には危篤状態に陥ったので、頼家と若狭局(わかさのつぼね。父は比企能員(ひきよしかず))との間に生まれた長男、6歳の一幡(いちまん)が頼家のあとを継ぐことになった。
頼家の跡を継ぐからには、一幡が全国の総守護・総地頭となるのが当然だ。しかし、実際に一幡が相続するのは、全国総守護と関東28カ国の総地頭だという。総地頭の半分以上(関西38カ国の総地頭)は、頼家の弟にして12歳の千幡(源実朝)に譲る、と発表されたのだ。
一幡の外祖父比企能員は、激怒した。娘婿の頼家が危篤なのをよいことに、北条氏が仕組んだに違いない。権力が比企氏側に移るのを恐れたゆえの企みだろう。
そこで、能員は急遽病床の頼家に面会し、ひそかに北条氏討滅の謀議をめぐらした。
ところが、北条政子(頼家の母)が、二人の密議を障子の陰で立ち聞きしていたのである。政子からの知らせを受けた北条時政は、比企能員を自宅におびきよせると、これを捕らえて部下に刺し殺させた。残された比企一族は一幡を含め、皆殺しにされた。頼家も伊豆修禅寺に幽閉されたのち、これまた北条氏の手の者によって殺されてしまったという。
以上が比企能員の乱のあらましである。話の大部分は『吾妻鏡』を典拠としている。重病の将軍と密議をめぐらしている能員。それを障子の陰で立ち聞きしている政子。あまりにもできすぎた話だ。
偶然残された関連史料や、当時の貴族の日記等から考えると、『吾妻鏡』の話は真実からはほど遠い。現代の歴史家は比企氏の乱を、巧妙に仕組まれたフレームアップではなかったか、と疑っている。
【参考】
・石井進『日本の歴史7・鎌倉幕府』1974年、中公文庫、P.289~296
|
|
|
|
| 2015年7月1日(水) |
| 宋銭 |
宋銭が日本各地から出土する。宋代には銅銭が基本通貨だった。しかし、中国では原料の銅不足に陥っていた。それなのに、なぜ宋は日本に銅銭を輸出したのだろうか?
宋代、銅銭とともに会子(かいし)と称する紙幣が使用されていたのである。
また、日本で出土する宋銭は、宋代のものとは限らない。次の元代には、銅銭は通貨として鋳造されなかった。通貨としては銀が使用され、また交鈔(こうしょう)と称する紙幣が使用された。その結果、宋銭がだぶつき、日本をはじめ海外へ輸出されたのだ。
元代にも、宋銭が大量に日本に輸出されていた証拠となったのが新安沈船(しんあんちんせん)である。1976(昭和51)年に韓国の新安沖で見つかった沈没船で、寧波から博多に向かう途中で沈没したらしい。京都東福寺の造営費用を捻出するために仕立てられた貿易船だった。その沈没船の中から、何と28トンにものぼる大量の宋銭が見つかったのである。
日本では税の銭納がはじまり、銭の需要が高まった。また、銅製品をつくる材料としても宋銭が利用された。鎌倉の大仏も、輸入された宋銭を材料に鋳造されたものだという。 |
|
|
|
| 2015年6月22日(月) |
| 中村勧農衛の人口対策 |
谷田部藩領の人別は、延宝年間(1673~8)には12,533人であったが、天明年間(1781~9)に至って8,465人に減少した。約100年の間に、32.5%の減少を見たのである。この大きな原因の一つが、その間の飢饉・凶作等による農民の死亡・離村等にあったのは言うまでもない。
極端な人口減少の結果、領内には耕作者のいなくなった手余耕地(てあまりこうち)が多く生じ、残った者たちの間からも、困窮のために潰れ・退転が続出した。そのため、谷田部藩の租税収納高は年々減少し、藩財政は逼迫した。さらには、天保5(1834)年の江戸大火によって、谷田部藩上屋敷が焼失するという悪条件が重なった。
谷田部藩が尊徳仕法を採用し、中村勧農衛に藩財政立て直しのために農村復興を命じたのは、こうした背景があったからである。
ところで、当地には次のような歌詞の子守唄が伝わっている。
女のお子ならおっちゃぶせ、男のお子ならとりあげろ、
とりあげ婆さん名はなんだ、八幡太郎とつけました(「高良田の子守唄」)(2)
勧農衛は、農村人口減少の背景の一つに、こうした間引き・堕胎の盛行があると考えた。そこで間引き対策として、出生時に1分、1カ月に400文ずつの養育手当を支給することにした。
また、谷田部藩領でも衰退久しい苅間村(かりまむら)四組に対しては、救助米支給・無利息貸付け・荒地再開発等の手段を講じるとともに、嘉永4(1851)年正月に間引き・堕胎を戒める教諭書『御領内村柄取直永安諭種(ごりょうないむらがらとりなおしえいあんさとしぐさ。通称『諭種(さとしぐさ)』)』を各戸に配付している。
農民相手であるがゆえに『諭種』の全文はほとんど仮名書きである。また、間引きの罪悪を犯す者は地獄に堕ちて閻魔大王の呵責を受ける、とする地獄絵を付し、そこに「子を間引く鬼にも勝る心こそついに我身に報ふなりけれ」という自作の和歌を載せた(3)。他地域でも見られる類型的な地獄絵だが、間引きなど行えば地獄でこのような恐ろしい報いを受けるのだ、と視覚の上からも農民たちを脅したのだ。
【注】
(1)以下の記述は、『茨城県史・市町村編Ⅱ』P.303~307及び『日本人口史之研究』P.512~521による。
(2)『日本残酷物語・第1部貧しき人々のむれ』1975年(第2版第5刷)、平凡社、P.213
(3)『谷田部の歴史』P.110 |
|
|
|
| 2015年6月15日(月) |
| 中村勧農衛(なかむらかのえ。1802~1858) |
|
元順(玄順)は、下野国芳賀郡中里村(元栃木県真岡市)に農民の子として生まれた(1)。
農事を嫌った彼は医者を志し、江戸の下谷御成街道(したやおなりかいどう)に居を定め、黒川元順と名乗って開業した。しかし、元順はいわゆる藪医者で、妻にさえ「あんたの医術の腕前はもとから拙(つたな)かった。下野の片田舎ですら医者としてやっていけなかったのに、良医・名医が大勢いる江戸で一旗揚げようだなんて。最初から無理な話だったのさ」と酷評される有様。患者は一向に集まる気配がなく、貧乏暮らしに嫌気がさした妻は子どもを連れて帰郷してしまった。
その後元順は、縁あって細川氏領谷田部(やたべ)藩(常陸国谷田部・下野国茂木(もてぎ))の藩医中村周圭の居候(いそうろう)となり、周圭の代診などを務めながら日々を送っていた。そのうち周圭が突然の病で急死してしまう。周圭には跡継ぎがいなかったことから、藩主細川侯は周圭と懇意だった元順を中村家の養子とし、同家の存続をはかった(2)。
しかし、元順の生活は相変わらず苦しかった。当時、二宮尊徳が下野国桜町で復興事業(桜町仕法)に当たっていたことを知ると、元順は尊徳のもとを訪れ、借財を申し入れた。尊徳は元順の申し入れを拒絶し、我が身のことしか考えない不心得な態度を戒めた。元順は己を恥じた。
ある時、元順は尊徳のことを藩主に話した。尊徳に興味をもった細川侯は、藩財政立て直しのため尊徳から指導を受けるよう、元順に命じた。当時谷田部藩は、農村の荒廃と借財の積み重ねによる未返済分の累積によって破産状態だった。そこで元順は、天保5(1834)年、下野の尊徳のもとへ赴き指導を受けるのである。そして翌天保6(1835)年、藩主から「勧農衛」と改名するように命ぜられ、改革仕法実施の責任者となった。
御用達商人からの借財帳消し、藩支出の削減、荒廃田畑の再開発、人口増加策等、勧農衛が展開した諸政策は一応の成功を見た。しかし、勧農衛の農村巡回が余りに熱心で頻繁に過ぎたため、「茂木の勧農衛、畑の地しばりなけりゃよい」と囃されるほど農民たちからは嫌われ、その諸政策もことごとく農民たちの反感を買った。勧農衛の諸政策が、藩財政回復に重点を置きすぎた強引なものだったからである。そのため安政4(1857)年には、積穀騒動(つみこくそうどう)(3)が起こっている。
その翌年の安政5(1858)年、勧農衛は没した。57歳だった。
【注】
(1)以下は高橋梵仙『日本人口史之研究』1941年、三友社、P.517~521、及び谷田部の歴史編さん委員会編『谷田部の歴史』
1975年、P.106~108による。
(2)『茨城県史・市町村編Ⅱ』P.304に「玄順、藩医中村周堂の養子」とある。
(3)安政4年は天候不順で凶作だったが、谷田部藩では農民の義倉への積穀をこの年も厳命した。これに反対する農民が
立野原に集まって越訴を計画し、江戸の谷田部藩邸に大挙出訴したのが積穀騒動である(『谷田部の歴史』P.103参照)。
【参考】
・古川与志継「一近江商人の凶作記録『天保七丙申年大凶作書』-近江国野洲郡大篠原小澤七兵衛家文書-」(東京大学日本史学研究室紀要第3号、1999年)
近江商人の小澤家は江戸前期に関東に下り、茂木で本格的な商売を始めた。「釜屋」の屋号を名乗り、谷田部藩茂木領で最も有力な商人に成長したが、10代小澤七兵衛の時に谷田部藩財政立て直しのため、借金の帳消し等を余儀なくされた。
|
|
|
|
| 2015年6月2日(火) |
| 長篠合戦の鉄砲の数 |
|
長篠合戦は、鉄砲の威力を示した戦いとして有名だ。この時、織田信長は「三千挺の鉄砲による三段撃ち」という戦法で、武田勝頼の騎馬武者隊を撃破したとされる。
火縄銃の弾込めには時間がかかるため、次の射撃までに空白時間が生じる。そうした欠点を補うため、足軽鉄砲隊を1,000人ずつ3列に分け、間断なく射撃を繰り返したというのだ。この場面は、ドラマや映画などでの見せ場の一つになっている。
しかし、真相はどうも違うらしい。「三千挺の鉄砲による三段撃ち」の話の出所は、江戸時代初期の儒医小瀬甫庵(おぜほあん。1564~1640)が書いた『信長記(しんちょうき)』。江戸時代に広く流布し、この話を「史実」として定着させていった。しかし、この本は、長篠合戦(1575年)から40年以上も経ってから書かれたものだ(1622年刊行)。また、軍記物として、史実が大胆に改変されていることでも知られる。
最も信頼できる史料とされるのは、信長に仕えた太田牛一(おおたぎゅういち。1527~?)の『信長公記(しんちょうこうき)』(小瀬甫庵の『信長記』と区別するために、太田牛一の書は『信長公記(しんちょうこうき)』と通称される。『信長公記』は江戸時代には出版されなかった)。『信長公記』には「三千挺の鉄砲による三段撃ち」の記述はない。現在、「三千挺の鉄砲による三段撃ち」は、甫庵の創作と考えられている。
そもそも鉄砲「三千挺」という数字自体が怪しい。ちなみに、『信長公記』を古い牛一自筆本から新しい写本へと並べると、鉄砲の数には次のような異同がある。
① 「千挺計(ばかり)」(建勲(たけいさお)神社蔵の太田牛一自筆本)
② 「三千挺計(ばかり)」(岡山大学付属図書館池田文庫蔵の太田牛一自筆本。本文の「千挺計」
の「千」の右肩に、小さな文字で「三」が加筆されている)
③ 「三千挺計」(②を写した内閣文庫蔵の写本。「三」が本文中にしっかりと書き入れられている)
こう見てくると、鉄砲「千挺」が、実態に近い数字といえそうだ。
【参考】
・『新発見! 週間日本の歴史01・戦国時代3』2013年、朝日新聞出版、P.24
|
|
|
|
| 2015年5月26日(火) |
| 明治を下からよむと |
|
慶応4(1868)年が明治元年と改元された。出典は、易経の「聖人は南面して天下を聴き、明に嚮(むか)ひて治む」という。口の悪い庶民たちは、早速この元号をやり玉に挙げて、次のような落首を詠んだ。
上からは明治だなどと言うけれど 治明(おさまるめい)と下からはよむ
(政府の連中は「明るく治まる」などと言っているが、下から読んだら(庶民から見れば)「治まるめい」だ)
さて、明治10年、西南戦争が勃発した。街中では、「賊軍が連戦連勝する」などと、さまざまな流言飛語がとびかった。世情不安の中、7歳の茅原廉太郎(かやはられんたろう。1870~1952)少年は、「平泰下天、年十治明」と書いた旗を押し立てて、大勢の子どもたちを引き連れて町中を練り歩いた。その意味を、茅原は次のように説明している(茅原華山『半生の懺悔』大正5年、実業之日本社、P.34~35
(http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/955149/71参照。2015年5月25日))。
「明治十年、天下泰平」といふ文字を轉倒したので、「平泰下天、年十治明」は
「兵隊勝てん、年中治まるめい」といふのであつた。
7歳児の言葉にしては出来過ぎだ。だが、物事をひっくり返したり下から読んだりして世情を皮肉るのは、庶民が権力者や世情を風刺する際の伝統的なわざの一つだ。
事実、「明治」という元号のめでたい字面と相違して、明治初期は農民一揆、打ちこわし、士族反乱等がうち続き、「年中治まるめい」という日々が続いたのだった。
|
|
|
|
| 2015年5月21日(木) |
| 病院は嫌い |
|
病院が嫌いだ。長く待たされるからだ。早朝から待たされて、夕方5時近くになってやっと診てもらうということが何度かあった。待っているうちに、病状がますます悪くなってしまう。だからそれ以来、具合が悪くなっても、病院には行かないことにしていた。
しかし、ここ数日間、どうにも体調が悪くていたし方ない。年次有給休暇を午後半日分もらい、意を決して病院に行ってきた。病状はさておき、今日は1時間半の待ち時間で済んだのがうれしい。まずまずだ。今月、子どもの日に東京国立博物館(平成館で鳥獣戯画を展示)に行った時は、駐車場に入るだけで1時間、博物館の中で展示にたどり着くまでが2時間だったのだから。
|
|
|
|
| 2015年4月19日(日) |
| 靴を奪え |
|
1863(文久3)年、薩英戦争が起こった。前年、島津久光の行列の前を横切ったイギリス人を、薩摩
藩士が殺傷した生麦事件に対する報復である。結局、激しい砲撃戦の末、薩摩藩は敗北する。
この時、薩摩藩はイギリス軍艦への斬り込み決死隊を編成している。薩摩藩庁は、105名の斬り込み隊員たちに、次のような訓辞を与えたという。
「イギリス人と戦っていよいよ駄目だと知ったら、やつらから靴を奪え」
なぜ、靴を奪うのか。
ヨーロッパ人が靴を履くのを見て、草履や下駄を履いていた日本人は不思議に思った。なぜ、彼らは、わざわざかかとをつけた靴を履くのだろう、と。
そこで次のように考えた。外国人の足にはかかとがないのだ。それなら、靴を奪ってしまえば、外国人たちは歩けなくなるはずだ、と。
開明的な君主島津斉彬(なりあきら)を生んだ薩摩藩にして、一般の武士たちにはこの程度の外国認識しかなかったのだ。
【参考】
・鯉渕謙錠『史談往く人来る人』1987年、文春文庫、P.129
|
|
|
|
| 2015年3月22日(日) |
| 彗星の出現で徳政令を出した |
永仁の徳政令を発令したのは、彗星出現がきっかけという。中世、彗星の出現は飢饉や戦乱などの凶兆と考えられた。科学的知識の乏しい時代である。そう考えたとしても無理はない。では、そうした凶兆にはどう対応したらよいのか。験(げん)直しをはかるか徳政を行えばよいと考えた。
だから、1210(承元4)年に彗星が出現した際には、後鳥羽上皇は土御門天皇から順徳天皇へ譲位させて災厄から逃れようとした。永仁5(1297)年2月に長く尾をひく彗星が出現した折りにも、幕府は災厄を避けるために永仁徳政令を出したというのである。
【参考】
・笠松宏至『徳政』1983年、岩波新書、P.191~P.192
|
|
|
|
| 2015年3月21日(土) |
| 教科書から消えた落首(2) |
折角だから、「泰平の…」の解説をしておこう。
「はい」は容器に入れた液体を数える言葉。また、船を数えるのにも用いる。上喜撰4杯に蒸気船4隻を掛ける。ただし、黒船4隻のうち、蒸気船は2隻(サスケハナ号、ミシシッピ号)のみで残り2隻(プリマス号、サラトガ号)は帆船だった。表向きの意味は、上等なお茶を4杯も飲んだのでカフェインで脳が興奮し夜眠れない、の意味。これに、わずか4隻の蒸気船のために、不安が募って一睡もできない、の意を掛ける。
上喜撰は極上茶の銘柄。「上」が極上を、「喜撰」が茶を意味する。もともと喜撰は六歌仙の一人喜撰法師のこと。喜撰は生没年・その伝ともに不詳。その実作として確からしいのは『古今和歌集』の「我が庵(いお)は都の辰巳(たつみ。東南の方角)しかぞすむ世をうぢ山と人はいふなり」の一首のみ。のち百人一首に採られたことで「宇治は喜撰法師の隠棲地」として著名になり、宇治山は現在喜撰山と呼ばれているという(京都府宇治市、標高416m)。 また宇
治は茶の産地として有名。そこで、喜撰→宇治(山)→茶という連想が働いたのである。
なお、インターネットで検索すると、お茶の銘柄で上喜撰・正喜撰などが出てくる。お茶を1杯飲んで、幕末に思いを馳せようか。 |
|
|
|
| 2015年3月20日(金) |
| 教科書から消えた落首(1) |
ペリー来航による世上の混乱ぶりを伝えた落首「泰平の眠りを覚ます上喜撰たった四はいで夜も寝られず」。昔の高校日本史教科書なら、必ずといっていいほど載っていた。しかし、近年の教科書で、この史料を載せるものはほとんどない。日本史教科書の定番と言われる『詳説日本史B』(山川出版社)にも、それは載っていないのだ。
これは、「泰平の…」の落首が明治時代にまで遡る史料がないという、明海大学教授岩下哲典(いわしたてつのり)氏の説に基づき、教科書からはずされたのだ。氏によれば、上記落首を確認できる確実な史料は『武江年表』のみで、『武江年表』の「泰平の…」に関する記事は明治時代になって書かれたものだという。江戸時代に「泰平の…」に類似する落首はあるが、同じものはない。「泰平の…」の落首はそうした江戸時代の落首を参考に、江戸幕府の慌て振りを明治期の人びとが嘲笑して作ったものだろう、というのである(岩下哲典『予告されていたペリー来航と幕末情報戦争』2006年、洋泉社)。
ところが、2010年に元専修大学講師斎藤純氏によって、この説が覆された。日本橋の書店主山城佐兵衛が常陸国土浦(現茨城県土浦市)の国学者色川三中(いろかわみなか。1801~1855)にあてた書簡(1853年6月30日付け。東京都世田谷区の静嘉堂文庫蔵)の中に、「太平之ねむけをさます上喜撰たった四はいで夜るもねられす」とあったのを、斎藤氏が発見したのである。「ねむけ」と「眠り」のわずかな差異はあるものの、「泰平の…」の落首がまさしく黒船来航騒ぎ(ペリー来航は1853年6月3日)のまっただ中で詠まれた当時の生々しい史料ということが証明されたわけだ。
土浦市立博物館(茨城県土浦市中央1丁目)では、3月21日から特別展「次の世を読みとく-色川三中と幕末の常総-」が始まる。その中で、写真版であるものの、「太平之…」を記した上記書簡も展示されるという(『朝日新聞』地方版・『茨城新聞』、ともに2015年3月1日付け)。
教科書会社には、是非とも「泰平の…」の落首を、日本史教科書に復活させてもらいたいものだ。
|
|
|
|
| 2015年3月5日(木) |
| 音の世界 |
土一揆といい、国一揆・一向一揆などという時の「一揆」は、『孟子』の「揆(みち)を一つにする」というが語源という(新版角川日本史辞典「一揆」の項)。揆は「道・目的」の意だから、一揆は「同じ目的を持った者同士の結合やその行動」ということになる。
中世社会で一揆を形成する際には起請文を書き、誓約した後これを燃やし、神前に供えていた水(神水)にその灰を入れて全員がまわし飲みするという儀式を行った。これを「一味神水(いちみしんすい)」という。
しかし、こうした儀式はのちになってつくり出されたもので、中世社会の一味神水の古い形は少し違っていたらしい。勝俣鎮夫氏の『一揆』(1982年、岩波新書、P.38~9)によれば、文字による一揆結成の時代の前には、大鐘などの金属器を打ち鳴らすことによって神を迎え、全員が口頭で誓言を述べ、、神水を飲むことによって一揆を結んでいたらしい。つまり、すべてが音だけだった。
中世の人びとは、音の世界に住んでいたのだ。
|
|
|
|
| 2015年3月2日(月) |
| 今日は代休 |
代休をもらったので、早稲田大学に行ってきた。會津八一記念館で横山大観・下村観山の合作「明暗」を見ようと思ったのだ。
企業説明会をやっていたので、構内はリクルートスーツを着た学生で溢れかえっていた。
しかし、屋外の賑やかさを忘れさせるほど、記念館の中は静寂だった。残念ながら、世界最大の手漉き和紙に描かれた「明暗」には会えなかった。絵に覆いが掛けられていたのだ。公開は3月下旬以降という。
少々落胆した。しかし、会津八一の「学規」や荻原守衛「女」、第15代沈寿官氏(第14代は司馬遼太郎の『故郷忘じがたく候』の主人公)の焼き物も見られたし、よしとするか。ついでだからと大隈記念講堂で、大隈の演説を録音したレコードを聞き、大隈が遭難した際に着ていた爆弾でちぎれた衣服を見た。
そして、坪内逍遙の演劇資料館の中に入ってみた。ギシギシきしる階段を昇った2階の展示室に、松井須磨子の遺書が展示されていた。島村抱月の墓に一緒に埋めてくれ、という内容だったが、愛人の願いはかなわなかった。
午後、国立新美術館で「ルーヴル展」を見て帰宅。 |
|
|
|
| 2015年2月26日(木) |
| 日本史教科書で変わったこと |
兼好は昔は「吉田兼好」と教わった。しかし、俗人としてなら卜部兼好(うらべのかねよし)、出家後の名前なら兼好法師(けんこうほうし)が正解だ。それが江戸時代に、吉田兼好と誤って伝えられてしまった。だから、近年の高校日本史教科書には、「兼好法師」と書いてある。
宗祇は昔は「飯尾宗祇」と教わった。しかし、宗祇の姓を飯尾(いのお。いいお)とする確証はない(『国史大辞典第1巻』P.764)。現在、教科書には「宗祇」のみ。
宗鑑は昔は「山崎宗鑑」と教わった。宗鑑は出自・伝記とも不明。山崎というのは姓でなく、「単に山崎に住んでいた宗鑑」というに過ぎない(『国史大辞典第14巻』P.142)。だから、現在の教科書には「宗鑑」のみ。
歌川広重は昔は「安藤広重」と教わった。しかし、広重が「安藤広重」を名乗ったことはない。広重は武士安藤源右衛門の長子で、幼名を徳太郎といい、のち重右衛門、徳兵衛と改めた。15歳で浮世絵師を志し、のち「歌川広重」の画号を許された。そもそも広重は、本名を名乗る際には安藤姓でなく、父の生家の田中姓に戻って「田中徳兵衛」と称していた。画号と実名を混同すること自体おかしいが、武家時代の最初の姓の「安藤」に「広重」の画号をくっつけた「安藤広重」という誤りは、大正年間に出版された美術雑誌の中で起こったという(五味文彦他『ちょっとまじめな日本史Q&A・下 近世・近代』2006年、山川出版社、P.94)。その誤りが世間に広まってしまい、いまだに尾を引いているわけだ。現在、教科書には「歌川広重」と正しい表記がされている。
その他にも、おかしな表記はまだたくさんある。しかし、正しい表記にすれば、「それで解決」というわけでもないらしい。表記変更がしっかりと周知されないと、お互い話が通じなくなってしまうからだ。たとえば、「厩戸王(うまやとおう)」といっても、年配の方々にはまるで通じない。現在でも、「聖徳太子」のネームバリューは絶大なのだ。 |
|
|
|
| 2015年2月20日(金) |
| 一条兼良の機知 |
『樵談治要(しょうだんちよう)』や『花鳥余情』(かちょうよせい)・『日本書紀纂疏(にほんしょきさんそ)』など多種多様な著作があり、学問に通じていた一条兼良(いちじょうかねら(かねよし))。自らの学才を誇って「菅原道真より自分の方が上だ」などと豪語していたらしい。だから亡くなった時には「500年に一人の天才」とまで持ち上げられて、その死を惜しまれた。そんな一条兼良の機知にまつわる伝承。
一条兼良は、顔が猿によく似ていた。13歳で元服する時、虚空(こくう)に怪しい声がした。
猿の頭に烏帽子(えぼし)きせけり
すぐさま縁(えん)の方へ走り出た兼良は、次のように付け句した。
元服は未(ひつじ)の時の傾きて
「猿の頭に烏帽子をかぶせている」と怪しい声に揶揄されたのを、即興で「元服の時間が未刻(午後2時頃)から次の申刻(さるのこく。午後4時頃)に傾いて」と、猿に申をかけて応じたのだ。
【参考】
・南方熊楠「猴に関する民俗と伝説」-南方熊楠全集第1巻、1971年、平凡社、P.339-
|
|
|
|
| 2015年2月19日(木) |
| 尊氏が天下取りを目指した動機は? |
足利氏は、源義家の孫義康が下野国足利荘を本拠にしたところから始まる。
足利家には、源義家の置文(おきぶみ)なるものが伝わっていた。それには「私(源義家)は7代目の子孫に生まれ変わって天下を取ろう」と書いてあった。7代目は足利家時である。しかし、天下を取る時機は、いまだ到来していなかった。そこで家時は自らの命と引き替えに、「3代以内に天下を取らせたまえ」と八幡大菩薩に祈り、腹かき切って自殺した。
3代目が足利尊氏である。
鎌倉幕府と後醍醐天皇を裏切り、尊氏が天下を取ろうとしたのは「ただこの先祖の発願によるもの」というのだ。今川貞世の『難太平記』に記されている話である。
|
|
|
|
| 2015年2月18日(水) |
| 伝統的な駄洒落 |
新書を読んでいたら、次のような記述があった。
堺の町の女房16、7人が、それぞれ福の神の姿をして京都に入った。これに対し、京都の町の男5、60人が貧乏神となって、それを象徴する鶯やニワトリの型をしたものを頭にのせて、堺へ向ったのである。この交換は戦火(注:応仁の乱の戦火)で焼かれ荒廃した町を、繁栄を謳歌する堺の福をもらうことにより復興しようとした当時の民衆の意識をしめすものとして興味深い(後 略)
(勝俣鎮夫『一揆』1982年、岩波新書、P.119)
気になったのは貧乏神の姿だ。この文章によると、鶯やニワトリは貧乏神の象徴だそうだ。初耳だったので、インターネットで検索してみたところ、「貧乏神は焼き味噌が好きで、やせた老人の姿をしている」という記述があるばかり。「鶯やニワトリが貧乏神の象徴」という典拠は一体何なのだろう。
ところで、「1月は去(い)ぬ、2月は逃げる、3月は去(さ)る」という言葉がある。1月から3月までの期間が慌ただしくあっという間に過ぎ去ってしまうことを、頭韻を踏んで言ったものだ。ここに「去(い)ぬ」「去(さ)る」がある。犬、猿とくれば、残りは「鳥」だろう。
ウィキペディアの「貧乏神」のところを見ると、最近造られた次のような貧乏神像の記述があった。頭に犬が乗った「貧乏が居ぬ(犬)」像、貧乏神の頭の上に猿が乗る「貧乏が去る(猿)」像、頭にキジが乗った「貧乏を取り(鳥)」像。ゲームの「桃太郎電鉄」に出てくる貧乏神のパロディらしいが、つまるところはすべて駄洒落だ。
勝俣氏は「鶯やニワトリは貧乏神の象徴」と書いておられるが、やっぱりこれは「貧乏を取り(鳥)」という駄洒落じゃないのかな。しかも、応仁の乱後、少なくとも500年以上も脈々と続く伝統的な駄洒落。 |
|
|
|
| 2015年2月9日(月) |
| トウフ |
2月8日と12月8日は「事八日(ことようか)」と呼ばれる民間行事が行われる。地方によっては八日節句とか事始めとか、さまざまな名称で呼ばれている。本来は、この日に神が来訪したところから、物忌みをする日であったらしい。それがいつの間にか本来の趣旨が忘れられ、一つ目小僧や疫病神などの魔物が外からやって来る日ということになってしまった。そこで民間では、魔物を追い払うために、門や家の入り口のところにイワシの頭やヒイラギ、ニンニクなどを飾り付けるようになった。
『中陵漫録(ちゅうりょうまんろく)』には、江戸後期の常陸国水戸(現茨城県水戸市)の風俗として、次のような記述を載せている。
水戸にて都鄙(とひ)の差別なく、十二月八日、二月八日の夕、豆腐を三分四方に切て、葱(ねぎ)を同じく串に貫きて、門戸の両傍に挟(はさん)で邪気を却(しりぞ)くと云(いう)。是(これ)を蒜豆腐(ひるどうふ)と云。昔は蒜許(ばかり)を挟みたりと云。余案ずるに、唐にては鬼門の方に指したる桃の枝を切て符とし、門戸に立て邪気を防ぐ事なり。是を桃符(とうふ)と云。是を聞誤(ききあやまり)て、今豆腐を用ゆ。豆腐にても験(しる)しあるや。俗家大抵如此(かくのごとし)。深くせむる事なかれ。
(佐藤中陵『中陵漫録』-『日本随筆大成第三期3』1976年、吉川弘文館、P.142~143-)
「水戸では豆腐と葱を串に刺して、門戸に立てていた」という記述だ。その由来を中陵は「中国の桃符(とうふ)を聞き誤って、豆腐(とうふ)を刺したのだ」と述べている。水戸の人間は「桃符と豆腐の区別もつかない」と言っているわけだ。随筆という気楽さからか、中陵先生(佐藤中陵は本草学者)もテキトーなことを言っているな。しかも「俗家大抵如此。深くせむる事なかれ(民間の人たちってたいていこんなもんだ。強く責めちゃいけないよ)」なんて失礼なコメントまで付け加えている。こんな言い草を知ったら、水戸の人たちは怒っちゃうだろうな(水戸出身者は「水戸っぽ」といって「怒りっぽい」ので有名)。
|
|
|
|
| 2015年2月1日(日) |
| 重力に逆らっている |
弘法大師こと空海(774~835)は、真言密教を日本に将来し、高野山金剛峰寺・東寺等を拠点として活躍した。そのめざましい活動は宗教界にとどまらず、学問・文学・芸術・社会事業等多方面にわたった。そのいずれもが後世へ多大な影響を及ぼすことになったため、その事績の伝説化が早いうちから進んだ。
空海といえば、「弘法は筆を選ばず」・「弘法も筆の誤り」などの諺があるように、能書家としても知られる。実際、空海は書の達人だった。その書風は王羲之(おうぎし)の書法をわがものとし、それに顔真卿(がんしんけい)の書法を加味したもので、俗に「大師流」と呼ばれた。同じ能書家の嵯峨天皇とともに「二聖」と称せられた。これに橘逸勢(たちばなのはやなり)を加えたのが「三筆」だ。
したがって、空海には、書にまつわるとんでもない伝説も多い。たとえば、『水鏡』には次のような伝説が書きとめられてある。
唐(もろこし)にても、御殿の壁の二間(ふたま)侍(はべ)るなかに、羲之といひし手かきの物を書きたるが、年久しくなりて崩れにければ、又改められて後、大師にかき給へと唐の帝申し給(たま)ひければ、五つの筆を、御口、左、右の御足、手にとりて、壁にとびつきて、一度に五行になん書き給ひける。この國に帰り給ひて、南門の額は書き給ひしぞかし。さて又応天門の額をかかせ給ひしに、上のまろなる点を忘れ給ひて、門にうちて後、見つけ給ひて、驚きて、筆をぬらして投げあげ給ひしかば、その所につきにき。見る人手をうち、あざむこと限(かぎり)なく侍りき。只空を仰ぎて文字を書き給ひしかば、其(その)文字現はれき。
(唐の皇帝から求められ、宮殿の壁に文字を書くことになった。口・両手・両足で五本の筆を持って飛びつき、一挙に五行を書いた。帰国後、応天門の額の字を書いた時、あとになって「応」の字の上の点の書き忘れに気づいた。そこで、筆を投げあげてその点を加えた。空に文字を書く真似をすると、その文字が空に現れた。)
(和田英松校訂『水鏡』1930年、岩波文庫、P.101。旧漢字は現行のものに改めた)
1本の筆を口にくわえて、両手・両足にそれぞれ2本ずつ筆を持ち、壁に飛びついている空海の姿は、想像するだけでおかしい。上記の伝説から空海は「五筆和尚(ごひつおしょう)」とよばれている。
しかし、壁というからには垂直に立っていたのだろう。五行というからには、各行ごとに別々の文字を書いたのだろう。「重力に逆らわない限り、五本の筆で一挙に五行も書くなどという芸当はできるはずがなかろう」などとツッコミを入れる人はいなかったのだろうか。「エライ御大師様の伝説だから」といって、昔の人々は神妙にこの話を聞いていたのだろうか。
それにしても、空に文字を書くほどの超能力を持ちながら、「応」の字の点を書き忘れるなんて、伝説上の空海は、案外うっかり者だ。 |
|
|
|
| 2015年1月23日(金) |
| 今井兼次氏 |
流通経済大学名誉教授の三宅立雄氏(1928~)は、三宅雪嶺の令孫である。立雄氏は生後5カ月の時、突然の事故で父を失った。ゆえに氏には、父親の記憶がまったくない。しかし、父親の人となりは知っている。それは若き日の父親の姿を、大学時代の旧友が息子に伝えたからだ。
その人の名は今井兼次(いまいけんじ。1895~1987)氏。立雄氏が「ただ一人、もっとも印象に残っている」と評する人物だ。
今井氏は、日本にガウディを紹介した草分けとして知られる。建築家であり、早稲田をはじめとする各大学で教鞭を執った教育者でもある。早稲田大学図書館(現会津八一記念博物館。東京)、同坪内博士記念演劇博物館(東京)、碌山美術館(長野)、日本二十六聖人殉教記念館(長崎)、桃華楽堂(香淳皇后生誕60周年を記念して皇居内に造られた音楽堂。現楽部音楽堂)など、著名な建築を数多く手がけた。立雄氏の父親とは大学時代、早稲田大学理工学部建築学科でたまたま同級になったという。
三宅氏は、故今井兼次氏との親交について次のように振り返る。
大学の同級生というのは3年間終わればそれでだんだん疎遠になるのが普通だと思うんですけれども、この今井兼次さんだけはずっと親友でありました。(中 略) 私が結婚したとき、32歳の時ですから、つまり父が死んでから32年たったときですけれども、ちゃんと出席して式辞を述べていただきました。その今井兼次さんは、やはり私としては非常に友情の深かった、しかもそれを絶やさない、しかも今井兼次さんの息子さんまでが今でもお付き合いをしているほど親密な関係にある。これは私としては大変ありがたかった。というのは、今井兼次さんが私の知らないような大学時代の話、大学を卒業してからの父親の話、こういうものをお話になったり、私が出したつたない字の年賀状なども全部保存していて下さった。これは大変ありがたかったと思いますね。
(三宅立雄「三宅家の家庭のこと・三宅家親族のこと」-流通経済大学『三宅雪嶺記念資料館ニュース』第12号、2014年、P.8)
今井氏の手がけた瀟洒な建物は、今でも静かな輝きを放っている。卓越した技術もさることながら、その人柄がにじみ出ているからだろう。
|
|
|
|
| 2015年1月21日(水) |
| 一千万遍 |
摂津国河辺郡の住人、源傳(「みなもとのつたえ」と読むのだろうか)は重代の武士だった。信仰心などまるでなく、仏僧を敬わず、経文の教えも信じなかった。年老いて風痺(ふうひ。風邪のような症状で、関節・筋肉の疼痛がともなう)を煩い、ついに癒えることはなかった。
いよいよ臨終という時に、弘法大師の袈裟を取り出して身に着けた。言うことに、「実はこの30年間、毎日一千遍の念仏を心の中で称(とな)えてきたのだ」と。そして、眠るように亡くなった。念仏の功徳によって極楽往生したのである(『後拾遺往生伝』(注))。
さて、1日に1,000遍、30年間、心の中で念仏してきたわけだから、その総計は次のようになる。
1.000遍×365日×30年=10,950,000遍
つまり、1,000万遍以上、念仏したことになる。この数値は、東京都の人口とほぼ同じだ。
(注)『後拾遺往生伝』は、国立国会図書館のホームページの「近代デジタルライブラリー」に所載されているものを参照した
(Kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/p:d/822297)。 |
|
|
|
| 2015年1月20日(火) |
| 座ってみる |
昨年末に受験した歴検日本史の結果が来た。1級日本史には合格。しかし、今回はうっかりミスがもっとも多く、反省すべき点が多々。
さて、昨年、カキツバタの咲く頃、東京の根津美術館に行った。この時期だけ、光琳の『燕子花図屏風』を公開しているからだ。案の定、ごった返していた。人気の展示会では人が多く、踵(きびす)を挙(あ)げて前列の人の肩越しに鑑賞することが多い。この時もそうだった。しかし、かなわぬ夢だが、誰もいない空間に光琳の屏風を立てて、畳の上で座ってじっくり眺めてみたいものだ。
なぜ座って見るのか。日本の作品の多くが、そういうように作られているからだ。それを強く感じたのは、20年ほど前の小さな体験からだ。
慈照寺で、国宝の東求堂同仁斎が特別公開されていた。そこで、あの有名な明かり障子のある付け書院の前に座る機会を得たのである。正座をすると、書き物をするには低い机が、あぐらをかくとちょうどいい。ああ、義政はあぐらをかいて、ここで書き物をしていたのだ! 明かり障子をあけ、すわって眺めてみる。左右の障子の間に、外の景色が掛け軸に描かれた風景画のように見える。義政はこんな工夫をしていたのか! あれもこれも、座ってみてわかることばかりだった。
庭も座って見るものだ。永六輔氏の『職人』(1996年、岩波新書)には次のようにある。
どこの庭でも座らなきゃだめなんです。
座ると、軒先の高さに応じて借景をどう計算しているか、というのが見えるわけで、
座ってはじめて、軒先と鴨居・敷居に区切られて浮かび上がる構図の見事さがわかる。
廊下を歩いてちゃだめなんです。絶対に座らなきゃいけない。
さて、同書には、我々が座って眺める慈照寺の庭園が、500年以上前に義政が眺めた庭と同じだ、と書いてある。いくらなんでも、そりゃ嘘だろう。500年も経てば、草は生えるだろうし、木ものびるだろうし…。そう思われた方は、同書のP.188~191を参照されたい。その理由に納得されることだろう。 |
|
|
|
| 2015年1月17日(土) |
| 春よ来い |
阪神淡路大震災から今日で20年。マス・メディアは特番を組んで、神戸の現在の様子を連日、テレビ映像で伝えてきた。
どの映像を見ても、街並みはきれいに復興されてはいる。そこには倒壊した高速道路も、崩れ落ちたビルディングも、焼けただれた商店街も、もやはない。しかし、建物は復興できても、罹災した人々の生活や心の傷はなかなか元には戻っていないという。
悠々自適の老後を送るはずだったのが、倒壊した家を建て直すためにローンを組んで、今も働きずくめの毎日を送る人々。収入が乏しく持病もあるのに、仮住まいからの退去を求められる人々。震災で逝った人々の思い出が、心の中に大きな傷となって残っている人々。マスメディアが伝えるどのレポートも、厳しい現実を思い知らされる話ばかりで、聞いていてやるせない。
震災直後、ユーミンの「春よ来い」の歌が流れ、人々に震災から立ち上がる勇気を与えた。あの歌のように、罹災したすべての方々に、いつの日か、本当の春が訪れることを願わずにはいられない。
※今日は大学入試センター試験の初日。56万人が受験する。全力を尽くせ、受験生! そして、みんなのもとにも、春よ来い。
|
|
|
|
| 2015年1月10日(土) |
| 日宋貿易の硫黄 |
日宋貿易の開始とともに、宋への日本産硫黄の輸出が始まった。なぜ、この時期に硫黄の輸出が始まるのか? この疑問を解明したのが、神戸女子大学文学部准教授の山内晋次(やまうちしんじ)氏だ。山内氏によると、その理由は次のようなものだ。
唐末に黒色火薬(木炭粉・硝石・硫黄を主原料とする)が発明されると武器への利用が進み、さまざまな火器が生まれた。それらの火器が大きく発展するのが宋代だ。10世紀、西夏との戦争においても火器は利用されたことだろう。
こうして火薬需要は高まった.。ところが宋には、黒色火薬の主原料の一つである硫黄が国内自給できない、という大問題があった。硫黄を産出する火山が、領域内にほとんど分布しなかったからだ。さらに、金の侵攻で支配領域を大きく南に押し下げられた南宋時代には、硫黄不足は一層深刻な問題になったはずだ。
この問題を解消するために宋は、海上貿易という手段によって硫黄確保に乗り出した。そこで目をつけたのが、火山国の日本だったというわけだ。
日本の硫黄主産地の一つが、薩摩半島南方に浮かぶ硫黄島だ。山内氏は、この小さな火山島から採掘された自然硫黄が博多に持ち込まれ、そこから宋の貿易船によって中国に運ばれたと推測している。
ただし、宋に運びこまれた硫黄は、日本産ばかりではなかった。東南アジアのジャワ島や、はるか西アジアのペルシア湾・紅海周辺などからも硫黄が持ち込まれたという。
硫黄の交易ルートは、日本史の枠を超えて、世界史レベルで理解すべきものだったのだ。
【参考】
・山内晋次『日宋貿易と「硫黄の道」』2009年、山川出版社(山川リブレット) |
|
|
|
| 2015年1月8日(木) |
| 惺窩は中国行きの船に乗ったのか |
前回は「儒学を本場で学ぶため、渡明を試みた藤原惺窩の船は、難破して鬼界島(きかいがしま)に漂着した」という話だったが、どうもこの話は誤りらしい。
一説によると、船に乗る前に渡明を考え直したとも。渡航の前、惺窩は山川の正龍寺(しょうりゅうじ。臨済宗。明治時代に廃寺)に宿泊した。薩摩は桂庵玄樹に始まる薩南学派の根拠地で、儒学研究の盛んな土地柄。当寺でたまたま『大学章句』のテキストを目にして、惺窩は渡明を思いとどまったという(ウィキペディア「正龍寺」の項。2015年1月7日参照)。「日本の儒学のレベルがこんなに高いなら、わざわざ渡明するには及ばない」ということか。
ただし、惺窩が渡明しなかった真相は、船が難破したからでも、『大学章句』を読んだからでもない。惺窩は姜沆に対し、渡明しなかった理由を自ら次のように語っているのだ。
吾れ辛卯の年三月に於て薩摩に下り、海舶に随いて大唐(注:中国)に渡らんと欲するも、瘵疾(注:病気)を患(わずら)いて京に還(かえ)る。病少(や)や愈(い)ゆるを待ちて朝鮮に渡らんと欲するも、継いで師旅有り、相い容(い)れられざらんことを恐る。故(ゆえ)に遂(つい)に敢(あえ)て海を越えず。其(そ)れ上国(注:先進国の中国・朝鮮)を観光するを得ざるも、亦(ま)た命なり。(姜沆『看羊録』)
(吾妻重二「江戸初期における学塾の発展と中国・朝鮮─ 藤原惺窩、姜沆、松永尺五、堀杏庵、林羅山、林鵞峰らをめぐって」-『東アジア文化交渉研究』第2号、P.50-http://www.icis.kansai-u.ac.jp/data/journal02-v1/05_azuma.pdf参照)
姜沆の証言によれば、惺窩が渡明しなかったのは惺窩自身の病気が原因だ。病が少し回復して、今度は朝鮮に渡ろうとしたが、「師旅(文禄・慶長の役)」のためにあきらめた。どちらにせよ、惺窩は海外行きの船に乗ることさえなかったのだ。 |
|
|
|
| 2015年1月7日(水) |
| 藤原惺窩(ふじわらせいか) |
藤原惺窩(1561~1619)はあの『新古今和歌集』を撰した藤原定家の子孫で、和歌を家学とする冷泉(れいぜい)家に生まれた。しかしその後、和歌の道を歩むことはなかった。仏門に入ったのである(のち還俗)。京都相国寺にあった惺窩は、しかし儒学に嵌(は)まりこんだ。
当時、五山僧侶の間で、儒学は教養の一つとして学ばれていた。しかし惺窩は、なぜか仏教よりも儒学に強く惹かれた。来日した朝鮮人や中国人と交流するにつけ、中国の文物に対する憧れが次第に強くなり、中国で儒学を本格的に学びたいという願望を抑えることできなくなった。ついに1596(慶長元)年、薩摩国山川港から明国への渡航を試みた。36歳の時である。しかし、船が難破して鬼界島(きかいがしま)に漂着。留学の望みは叶えられなかった(揖斐高『江戸幕府と儒学者』2014年、中公新書P.34による)。
さて、渡航失敗から2年後の1598(慶長3)年、朗報があった。慶長の役で日本に強制連行された捕虜の中に、高い学識をもつ朱子学者姜沆(きょうこう。カンハン。1567~1618)がいたのだ。大洲(おおず。愛媛県)で捕虜生活を送っていた彼は、当時、京都伏見に移送されていた。惺窩は正装して姜沆のもとを訪れ、熱心にその教えを請うた。そして、姜沆から四書五経などを学ぶ貴重な機会を得たのである。
姜沆の帰国後も惺窩は儒学研究を続け、後世「近世儒学の祖」と評価されるまでになった。惺窩は諸大名からの仕官の誘いを断り、京都に住んで、儒学講究と門人育成にその生涯を捧げた。惺窩を祖とする儒学の門流を「京学派」という。弟子に林羅山がいる。元和5(1619)年死去。59歳だった。 |
|
|
|
| 2015年1月4日(日) |
| 兄弟の名前が覚えられない? |
高校日本史の時間。室町文化のところで、浄土真宗(一向宗)本願寺派の蓮如(兼寿)を扱う。
教師は通常、「蓮如は北陸地方の農村を中心に布教し、御文(おふみ。御文章とも)と講組織という二つの手段によって、信者を獲得していったんだ」というような説明をする。
この時蓮如は、各地の布教拠点となる真宗寺院間の結束を、血縁によって強固なものにしたといわれている。そのため、大勢の子どもをもうけた。有力寺院に自分の息子を送り込み、離間しそうな寺院には娘を送り込んで、がっちりスクラムを組んだというのだ(樋口清之『歴史を見る目』1977年、ごま書房、P.88)。
そこで、蓮如の子どもたちを一覧表にしてみた(小和田哲男『誤伝の日本史』1984年、日本文芸社、P.93から作成)。江戸時代の徳川将軍の子だくさんと異なるところは、将軍が大勢の妻妾を有していたのに対し、蓮如の妻は皆正夫人だったところだ。
下の表を見ると、長男と末っ子が56歳の年齢差だったことがわかる。蓮如の子だくさんについて、兄弟姉妹たちはそれぞれどんな感情を抱いていたのだろうか? そもそも、全員がお互いの顔や名前を知っていたのだろうか?
なお、加賀の一向一揆を知る史料として有名『実悟記拾遺』(「近年ハ百姓ノ持タル国ノヤウニ」のフレーズで有名。日本史教科書にも載っている)は、蓮如の十男実悟(兼俊)の『実悟記』に漏れたものを浄土真宗の僧先啓が編集したものだ。
| |
子どもの名 |
子どもの誕生年 |
蓮如の年齢 |
母の名 |
備 考 |
1男
1女
2男
2女
3男
3女
4男 |
順如
如慶
蓮乗
見玉
蓮綱
寿尊
蓮誓 |
嘉吉 2(1442)
文安 3(1446)
〃
文安 5(1448)
宝徳 2(1450)
享徳 2(1453)
康正 1(1455) |
28
32
32
34
36
39
41 |
如了
〃
〃
〃
〃
〃
〃 |
蓮誓を産後、如了死亡。 |
5男
4女
5女
6女
7女
6男
8女
9女
7男
10女 |
実如
妙宗
妙意
妙空
祐心
蓮淳
了忍
了如
蓮悟
祐心 |
長禄 2(1458)
長禄 3(1459)
寛正 1(1460)
寛正 3(1462)
寛正 4(1463)
寛正 5(1464)
文正 1(1466)
応仁 1(1467)
応仁 2(1468)
文明 1(1469) |
44
45
46
48
49
50
52
53
54
55 |
蓮祐
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃 |
蓮祐は如了の妹。実如は延徳1年(1489)本願寺法主。
|
| 11女 |
妙勝 |
文明 9(1477) |
63 |
如勝 |
如勝、産後の肥立ち悪く死亡。 |
| 12女 8男 |
蓮周
蓮芸 |
文明13(1481)
文明16(1484) |
67
70 |
宗如
〃 |
宗如、蓮芸を産後死亡。 |
13女
9男
10男
11男
12男
14女
13男
|
妙祐
実賢
実悟
実順
実孝
妙宗
実従
|
長享 1(1487)
延徳 2(1490)
明応 1(1492)
明応 3(1494)
明応 4(1495)
明応 6(1497)
明応 7(1498)
|
73
76
78
80
81
83
84
|
蓮能
〃
〃
〃
〃
〃
〃
|
妻は蓮如より50歳年少。
蓮如、延徳1年(1489)に実如に跡を譲り隠居。
|
|
|
|
|
| 2015年1月2日(金) |
| 2015年(平成27年度)が始まりました |
新年を迎えた。初詣に行ってお神籤を引いたら「中吉」。あれ、確か去年も中吉だったような…。今年も、「めでたさも中(ちゅう)くらいなりおらが春」(一茶)というところか。
そこで未年も、去年と似た目標を2つ立てた。一つは、HPの「中世へのとびら」を完成させること。もう一つは歴検日本史1級を今年も受験して合格すること。
何事も継続が大事。もっとも、この「継続」というのが一番難しいことだ。 |
|
|
|