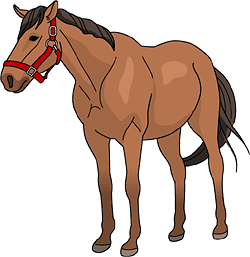| 2014年12月31日(水) |
| たずねてきたのは宇宙人? |
|
江戸時代、都会の文化が地方にまで浸透した。その例として取り上げられるのが、丹後国柏原(かやはら)に住む田氏捨女(でんしすてじょ。1633〜1698)が詠んだという次の一句。
雪の朝 二の字二の字の下駄の跡
捨女は当時6歳だった(竹内玄玄一『俳家奇人伝・続俳家奇人伝』1987年、岩波文庫、P.232〜3)。田舎にも、早熟の才媛が出現したという例。
それはさておき、雪の上の足跡、という同じ題材で、ある人が次のような和歌を詠んだ。
雪の門(かど)足跡付けて出でければ訪(と)はれぬるかと人のあやしむ
..
「雪の上に二の字二の字の下駄の跡があった。『ご免下さい』の客の声に家人が気づかなかったために、留守だと早合点した客を帰してしまったらしい。こんな雪の日にわざわざ訪ねてきてくれたのに、本当に気の毒なことをした」と話し合ったという意味。ところが、いたずら好きの人がいて、この和歌の2カ所に濁点を打ってしまった。
雪の門足跡付けで出でければ飛ばれぬるかと人のあやしむ
(外に出たはずなのに、雪の上に足跡が付いていない。空を飛んで行ったのだろうか、の意)
【参考】
・鈴木棠三『ことば遊び』1975年、中公新書、P.7〜8
|
|
|
|
| 2014年12月26日(金) |
| 鎌倉時代に「北条政子」はいなかった? |
源頼朝の妻で、2代将軍頼家・3代将軍実朝を生んだ母親は、「北条政子」ではなかった。「そんな馬鹿なことがあるか」と思う人がいるかも知れない。しかし、頼朝の妻にして、頼家・実朝の母親である女性は、夫の頼朝や父親の北条時政からさえ、「北条政子」の名前で呼ばれたことは一度もないのだ。
まずは「政子」という名前だ。「○子」という名前は、位を有している特別な女性のみが名乗ることができた。「政子」という名前がつけられたのは、1218(建保6)年、従三位(じゅさんみ)を朝廷から授与されるに際して、位記(いき。位階を授ける時に作成する公文書)などの文書に名前を記す必要があったからだ。しかし、その名前でさえ父時政の一字を便宜的につけて「政子」としたに過ぎない。すでに出家していた彼女は「尼御台所(あまみだいどころ)」と呼ばれており、少なくとも19年前に死んだ夫の頼朝や15年前に死んだ息子の頼家、3年前に死んだ父親の時政から「政子」と呼ばれたことはなかったはずだ。
次に、北条を冠した「北条政子」という名前だ。高橋秀樹氏によると、少なくとも大正時代まで「政子」「平政子」と記す書物はあっても、「北条政子」と記した書物は見あたらないという。つまり、「北条政子」の名前が一般化したのは昭和になってからなのだ。
なぜ、頼朝の妻が「北条政子」と呼ばれるようになったのかは不明だ。ただ、わかっているのは、彼女が「北条政子」の名前で我々に周知されるようになったのは、ここ数十年のことらしい、ということだけなのだ。
【参考】
・高橋秀樹『日本史リブレット20・中世の家と性』2004年、山川出版社、P.1〜5
|
|
|
|
| 2014年12月24日(水) |
| 頼朝の人心収攬術 |
頼朝は、御家人を一人ずつ物陰に呼んで、「お前だけが頼り」と耳元で囁いたという。鎌倉殿直々の言葉に、御家人たちは「俺一人だけが特別扱いされた」と勘違いしただろう。こうして頼朝は、鵜飼いの鵜を操るように、御家人たちを操縦したのだ。
また、こんなエピソードがある。石橋山の戦いで討ち死にした頼朝方の武士に、佐奈田与一(義忠)という者がいた。建久元年(1190年)正月20日、頼朝が三島、箱根、伊豆山に参詣した折りのことである。帰途、頼朝は佐奈田与一とその郎等文三の墓に立ち寄る、と言った。墓に詣でると、与一・文三の奮戦ぶりを偲んで、涙を流したのだった(与一・文三の奮戦ぶりは『平家物語』や『源平盛衰記』に記載されている)。
家来の命がけの忠義を顕彰しつつ、涙まで見せた頼朝の行動に、素朴な東国武士たちはおそらくグッときたに違いない。そして、「命がけで忠義を尽くすなら、この殿以外にない」と、鎌倉殿への忠義の覚悟を新たにしたことだろう。
ただ、これが計算ずくでの演出だったなら、頼朝っていうのはかなり恐ろしい上司ではある。その上、結構ねちねちした執念深い性格だったし…(「あれやこれや 2014」2014年10月9日参照)。
|
|
|
|
| 2014年12月21日(日) |
| 何を「21回」したの? |
|
来年のNHKの大河ドラマは、吉田松陰の妹がヒロインなのだそうだ。
ところで、吉田松陰は天保元(1830)年8月4日、長門国萩の松本村に藩士杉百合之助の次男として生まれた。吉田は養子先の姓である。天保元年が庚寅(かのえとら)年だったので幼名を虎之助といったが、のちには大次郎、松次郎、寅次郎などと称した。名は矩方(のりかた)、松陰は字(あざな)である。
松陰は、「松陰」以外にもいくつかの字を持っている。その一つに「二十一回猛士」というのがある。たとえば、久保清太郎宛て書簡(安政2年2月19日付け)など見ると、「二十一回生」と署名している(広瀬豊編『吉田松陰書簡集』1937年、岩波文庫、P.120)。
ところで、この「二十一回」というのは、何のことなのか?
実は、「吉田」を分解して、組み直したものなのだ。「吉」を分解して「十一口」とし、「田」を分解して「十口」にしたあと、「十十一」で「二十一」、「口口」を組み合わせて「回」としたというわけだ。
教育家としても知られた吉田松陰。案外、松下村塾では生徒たちにクイズを出して、楽しんでいたのかも知れない。
|
|
|
|
| 2014年12月11日(木) |
| ハリーポッターもびっくり! |
その昔、算木(さんぎ)という道具を使って計算をした。ぱたぱたと算木を並べて、いびつな土地の面積を割り出したり、水たまりの周辺の長さと水深から貯水量を算出したりした。義務教育などというものがなかった時代である。一般の人々は、不思議な術を操っている、と感じたらしい。
さて、時は鎌倉、2代将軍源頼家の治世である。頼家のお気に入りの一人に、太夫坊源性(たいふぼうげんしょう)という僧がいた。源性は算術に関して、当今並ぶ者がないという評判だった。
奥州で土地の境界争いが起こった。実地検証をさせるため、頼家は算術に長けた源性を現地に派遣した。務めを終えた源性は、ほどなく鎌倉に帰ってきた。そして頼家に、次のような奇妙な体験を報告した。
源性は、松島で一人の老僧に出会った。その者が言うことに、
「私は天下第一の算術師だ」
と。
算術の第一人者を自負する源性は、老僧の言葉にカチンときた。
「井の中の蛙(かわず)の田舎者め。私(源性)の算術にかなう者など、この世の中にいるはずがない」
と。
老僧に対する軽蔑の気持ちが、ありありと源性の顔に現れていたのだろう。それを察したらしい老僧は、
「私の算術の腕前をご覧に入れましょう」
と言うや、算木を取り出した。そして、源性の周りにぐるりと置いたのである。
たちまち、源性の目の前は真っ暗闇。確か自分は、草庵の中にいたはずだった。しかし、いつの間にか、周りは大海に変わっているではないか。丸い敷物は大きな岩となっている。ヒュウヒュウという風の吹きすさぶ音と、荒れ狂う波音が迫ってくるばかり。源性は、自分が生きているのか死んでいるのかもわからない始末。
源性は慢心を後悔した。すると、たちまち夢から覚めたような気分になり、ふと窓の外を眺めると、太陽がさんさんと降り注いでいるのに気がついた。
源性は老僧に術の伝授を願ったが叶わず、追われるように帰ってきたのだった。
【参考】
・作者不詳・増淵勝一訳『北条九代記(上)』1979年、教育社、P.158〜163 |
|
|
|
| 2014年11月26日(水) |
| ダイナマイトを積んでいた「14カ条」 |
「民主主義を守るため」と称して、第一次世界大戦に連合国側として参戦したアメリカ。しかし大戦途中で、ロシア革命が起こった。革命をリードしたレーニンらは、帝政ロシア時代に英・仏・日ら連合国諸国間で、戦後の植民地再分割などについて密約があったことを暴露した。
「大戦の真の目的が植民地の争奪にあった」というのでは、身も蓋もない。世界の人々が幻滅してしまうだろう。そう考えたアメリカ大統領ウィルソンは、大戦の理想化をはかることにした。1918年に発表した「14カ条」がそれだ。そこでは「勝利なき平和」や「国際連盟の創設」の提言とともに、「民族自決」の原則など、輝かしい美辞が羅列されていた。
ただ、ウィルソンの念頭にあった「民族自決」の想定地域はごく限定された地域(ポーランド、ベルギー、ルーマニア、セルビアなど)であり、植民地は対象外だった。
しかし、ロバート=ランシング国務長官は、ウィルソンの14カ条が「ダイナマイトを積んでいる」ことを看破していた。「民族自決」のスローガンは、植民地の人々の心の中に、「宗主国からの独立」という希望の種子をばらまいたのだから。
【参考】
・加藤陽子『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』2009年、朝日出版社、P.232〜234
|
|
|
|
| 2014年11月18日(火) |
| 一服一銭(いっぷくいっせん) |
室町時代、立ち売りの喫茶業を「一服一銭」といった。「一服一銭」の文書上の初見は1403(応永10)年で、東寺百合文書(とうじひゃくごうもんじょ)にある茶売り人3人が、喫茶の営業許可を求めて京都の東寺に提出した請文(うけぶみ)「南大門前一服一銭茶売人道覚等連署請文」であると言われている。
ところで「一服一銭」の名称の由来だが、おおかたの国語辞典は「抹茶一服を一銭で売っていたから」と書いている。しかし、「一銭」というのは茶代ではなく、実際は抹茶の量を表したものらしい。
インターネットで調べてみたところ、「特別展 京都歴史こぼれ話−京都新聞連載コラム『雑学京都史』より−展示資料 解説集」
(www.pref.kyouto.jp/shiryoukan/resources/kaisetu20.pref)に次のようにあった。
「一服」は粉薬など一包(一回分)を意味する単位で、「一銭」は代金と思われがちですが、当時は喫茶に適した抹茶の量のことを指したと思われます。量を量るのに一文銭大の匙が用いられたことから、こう呼ばれるようになったのかもしれません。日本に茶が伝来したこと、医薬品として喫茶されていたことを考え合わせますと、この名称がなるほどと思われます。(京都府立総合資料館 資料主任池田好信氏による)
「一文銭大の匙」とあるが、一体どのようなものなのだろう。実物を見てみたいものだ。ただ、中国では漢方薬の粉末を量るのに、薬匙ではなく銭を使っていた。銭の上に盛った量で重さを計測していたというのだ。それなら、わが国でも匙ではなく、当時は一文銭の上に抹茶をのせて、一服分の量を決めていたのかも知れない。 |
|
|
|
| 2014年11月16日(日) |
| 目が覚めた? |
イギリス人は、朝から夜中まで酒を飲んで暮らしていた。ほかに飲むものがなかったからだ。
17世紀初めに、イギリスにコーヒー・ハウスができた。18世紀にはティー・ハウスが開店した。酔生夢死の生活を送っていたイギリス人の慣習の中に、コーヒーや紅茶が導入された意義は大きい。人々の日常が、アルコールによる酩酊状態から、カフェインによる覚醒状態へと移行したからだ。
コーヒー・ハウスやティー・ハウスには、様々な知識・経験をもつ人々が集った。男子のみに限られていたものの、そこは一種の社交場だった。コーヒー・紅茶を飲みながら、さまざま情報を交換し、世間のうわさ話や政治・芸術談義に花を咲かせ、世論を形成した。
世の中を動かす思想は、目覚めた頭と多様な人々とのネットワークから生まれたのだ。
【参考】
・角山栄(つのやまさかえ)『茶の世界史』1980年、中公新書 |
|
|
|
| 2014年11月15日(土) |
| 冷水先生(ひやみずせんせい) |
「寛政の三博士」の一人として知られる岡田寒泉(1740〜1816)。名を善里(よしさと)・恕(はかる)、字(あざな)を仁卿(じんけい)・中卿(ちゅうけい)・子強(しきょう)、通称を又次郎・式部・清助、号を泰斎、または寒泉などといった。
日本史教科書に載っている「寒泉」という号は、江戸の居宅(神田小川町)に井戸があり、冷泉が湧き出していたことに由来する。
当地の人々は、それを「ひやみず」と呼んでいた。だから、この界隈には冷水・冷水番所(ひやみずばんしょ)・冷水橋(ひやみずばし)などの地名があった。そんなわけで人々は、岡田のことを「冷水先生(ひやみずせんせい)」と呼んでいた。
ただ、「冷水先生(ひやみずせんせい)」では、「年寄りの冷水」みたいだ。何とも語感が悪い。たぶん、そう思ったのだろう。そこで自ら「寒泉」と号し、住居を「寒泉坊」、家塾を「寒泉精舎(かんせんしょうじゃ)」と名づけた。
現在、「寒泉」のことを「冷水先生」と書いてある日本史教科書は、一冊もない。
【参考】
・重田定一『岡田寒泉』1980年、筑波書林(ふるさと文庫) |
|
|
|
| 2014年11月10日(月) |
| 「隼」から「はやぶさ」へ |
「零戦」の開発に関わった堀越二郎は、ジブリのアニメ映画『風立ちぬ』の主人公のモデルとして、世に知られるようになった。戦時期の飛行機開発に関して言えば、もう一人、名機「隼(はやぶさ)」開発に携わった技術者糸川英夫(1912〜1999)も特筆すべき人物だ。
戦後、糸川は宇宙を目指した。糸川が最初に作ったロケットは、鉛筆に羽根をつけたようなオモチャのようなものだった。このペンシルロケットの水平発射実験を行ったのが、1955年のこと。以後糸川は、ロケット研究の草分けとなって、宇宙開発の道筋を作っていった。しかし、ロケット打ち上げの度重なる失敗や、あらぬ誹謗中傷のため、責任をとって東大を辞職。宇宙開発の表舞台から姿を消すことになる。
1970年、日本は初の人工衛星「おおすみ」の打ち上げに成功した。しかし、そこに糸川の姿はなかった。
そして1999年、糸川永眠。享年86歳。
糸川が亡くなって4年後の2003年、糸川の志を継ぐ技術者たちは、小惑星探査機「はやぶさ」を打ち上げた。「はやぶさ」が目指した小惑星には、糸川に対する敬意から、「イトカワ」という名前が与えられた。「はやぶさ」が「イトカワ」の地表面観察を行い、採取した試料を地球に持ち帰ったことは、我々の記憶に新しい(2010年)。
糸川は今、「日本の宇宙開発の父」と呼ばれている。 |
|
|
|
| 2014年11月9日(日) |
| 「入鉄砲に出女」というのは本当か? |
江戸時代、関所を置いた目的は「入鉄砲に出女」の取り締まりにあった、というのが教科書的常識。
「入鉄砲に出女」とは、武器の江戸持ち込みと、人質である大名妻子の江戸からの逃亡とを監視するという関所の目的を、端的に言った言葉だ。しかし、関所によっては、これをほとんど取り締まらなかったり、本来の目的からはずれた取り扱いをしているところもあった。たとえば、箱根の関所がそれである。
加藤利之著『箱根関所物語』(1985年、神奈川新聞社かなしんブックス)によれば、「箱根の関所は入鉄砲の調べはしなかった」(同書P.82)という。また、鉄砲証文がなくても、鉄砲を通したというのだ。その理由を、同書は、「東海道では西の新居関所で厳しく鉄砲改めをしたので、それから東は、譜代大名との幕府の代官しかおらず、幕府に謀反を起こす心配が、全くなかったからであろう」(同書P.84)と推測している。
このように、箱根関所では入鉄砲の調べはしなかった。しかし、出女の取り締まりは、やたらうるさかった。たとえば、ある一般女性は髪を解かれ、その髪先が切ってあるかないかを調べられた際、「髪切に紛らわしい」という理由で15日間も関所を通ることができなかった。また、女児の赤ん坊は、産着では箱根関所を通れなかった。「小女(0〜15、6歳の少女)」は振袖を着ることになっていたからである。
どちらも、人質になっている大名奥方の逃亡とはまるで関係がない。本来の目的が失われて、煩瑣な手続きばかりになってしまったのだ。 |
|
|
|
| 2014年11月3日(月) |
| お茶壺道中 |
土下座は、将軍への献上品を運ぶ行列に対しても要求された。
有名なのが、将軍に宇治茶を献上する「お茶壺道中」だ。街道筋でお茶壺に出くわすと、大名でも道を譲り、駕籠から降りなければならなかった。将軍の権威を振りかざし、袖の下を要求されるなど無理難題をふっかけられることも多かったという。だから、「お茶壺道中」の行列は、大名ばかりか庶民にとっても鼻つまみだった。その記憶が「ずいずいずっころばし」のわらべ歌に姿を変え、現在に伝わっている。
お茶壺行列が近づいたことを知るや、道筋の人々は家の中に逃げ込んで、戸をピシャンと閉めた。そして、その早い通過をひたすら祈った(「茶壺に追われてトッピンシャン」)。どの家も息をひそめて静かにしているので、ネズミが米を食べる音や、外の井戸あたりで茶碗を割った音まで聞こえてくる(「俵のネズミが米食ってチュウ」、「井戸のまわりでお茶碗欠いたのだあれ」)。そして、行列が宿場や村々を通り抜けると、何もなかったことに「やれやれ」と安堵したのである(「抜けたらドンドコショ」)。
将軍権威の高揚には役だったろうが、何とも迷惑な話である。
【参考】
・安藤優一郎『大名行列の秘密』2010年、NHK出版生活人新書
・ウィッキペディア「ずいずいずっころばし」の項(2014年10月31日参照) |
|
|
|
| 2014年11月2日(日) |
| 土下座 |
大名行列に出くわすと、その長い行列が通り過ぎるまで、庶民は土下座を強いられた、というのが時代劇の常識。しかし、少なくとも江戸府内の場合は事情が違っていた。将軍・御三家(尾張・紀伊・水戸)・御三卿(一橋・田安・清水)の行列を除いて、庶民は大名行列に土下座をしなくてもよかったのである。
4月になると、全国から大名行列が江戸へ、江戸へと集中する。幕府が、1635年から4月参勤(江戸への出仕を「参勤」、領地に就くのを「交代」といった)を制度化したからだ。
江戸にはともかく大名が多い。こんな状況下で、大名行列に出くわすごとに一々土下座をしていたのでは、仕事はままならず、商売もあがったりだ。百万都市江戸の機能が阻害されてしまう。だから、たとえ百万石を領する藩主の行列であっても、江戸庶民に土下座を強いることはできなかった。
ただし、百万石の藩主には土下座しない江戸庶民も、その妻の行列には土下座した。将軍の娘だったからだ。第13代加賀藩主前田斉泰(まえだなりやす。1811〜1884)の妻は、第11代将軍徳川家斉(とくがわいえなり。1773〜1841)の娘溶姫(ようひめ)である(ちなみに家斉には通算40人の側室がおり、55人の子女をもうけた。子だくさんだったので、多くの息子・娘は養子や嫁として、諸大名に縁づけられた)。
このように土下座は、将軍家にゆかりのある人びとに対しても強要された。幕府は、将軍家と他の大名行列との格の違いを「土下座」の有無によって人びとに見せつけ、将軍権威の確立・維持に利用したのだ。
【参考】
・安藤優一郎『大名行列の秘密』2010年、NHK出版生活人新書、P.103〜105 |
|
|
|
| 2014年11月1日(土) |
| 綱吉と大根 |
「江戸煩い」といえば、こんな伝説もある。
生類憐みの令の発令で知られる5代将軍徳川綱吉。まだ上州館林藩主時代に江戸煩いになった。陰陽師に占わせると、綱吉は右馬頭(うまのかみ)だったので、「馬」の名がつく土地に転地療養するがよい、とのこと。そこで「練馬」という地名を見つけると、早速そこに別邸を建てて移り住んだ。この時、綱吉の母親が尾張から大根の種を取り寄せて、練馬の畑で栽培させた(綱吉の母桂昌院は本名を玉といい、八百屋の娘だった)。江戸煩いが快癒した綱吉は練馬の地を去ったが、あとには大根畑が残った。これが「練馬大根」の起源だという。
本当なのか。早速「練馬区」のHPにアクセスした。そこには、「練馬大根誕生伝説」というページがあって「将軍綱吉説」が載っていた。結論から言うと、この話はどうも眉唾らしい。
【参考】
・練馬区公式ホームページ(2014年10月31日参照) http://www.city.nerima.tokyo.jp/annai/fukei/daikon/daikontoha/densetsu.html
|
|
|
|
| 2014年10月31日(金) |
| 江戸煩(わずら)い |
江戸を訪れた地方の侍や商人らが、きまって罹患する奇病があった。「水が合わない」とでもいうのか、体調がともかく悪くなるのである。最初は気が滅入り、だるくなって足下が覚束なくなってくる。顔がむくみ、食欲はなくなり、寝込んでしまう。悪くすると、死んでしまうことすらあった。西国大名の江戸屋敷では、必ず誰もが罹患したという。
ところが、故郷へ帰る段になり、箱根山を越えるころには自然に治癒してしまう。これを当時の人々は「江戸煩い」と呼んだ。
江戸の浅草には蔵屋敷が建ち並び、諸国からの米俵が大量に運び込まれた。平和が続くと米価も安定し、一日三食の食事回数も定着した。とりわけ江戸では、米糠を落とした精白米をたらふく食べるようになった。玄米・稗飯などより、白米の方がうまいからだ。
しかし、米糠にはビタミンB1が含まれていた。地方で玄米・雑穀などを食べていた人々は、自然とビタミンB1をたっぷり摂取していた。それが江戸に出てくることによって、白米中心の食生活にどっぷりつかることになる。たちまちビタミンB1不足になってしまい、「江戸煩い」を発症してしまうことになる。
それが、地方に帰れば玄米や麦・雑穀を常食する食生活に戻るため、「江戸煩い」も自然に治癒したのである。
「江戸煩い」がビタミンB1不足に起因する「脚気」だと判明したのは、明治期以降のことである。
【参考】
・立川昭二『日本人の病歴』1976年、中公新書
|
|
|
|
| 2014年10月25日(土) |
| 「取」るのが「最」高の物って? |
秦代、敵の首を一つあげると、階級を一級上げた。そこで、敵の首を「首級」といった。しかし、秦以前は、首ではなく、左耳を切りとって敵を倒した証拠としたらしい。首を切ることを「馘首(かくしゅ)」(現在は解雇の意味で使う)というが、「馘」の古字は首偏でなく耳偏だった。「取」(「耳」と「又(右手)」から成り立っている)という漢字はここから生まれたと言われる。だから、「取」の字が含まれている「最」には、「敵の耳を多くとった人」の意味がある。耳を取れば取るほど、多大な恩賞に預かれる。それが「最」高ということなのだろう。
日本にも、敵の首を切って戦功の証とした歴史がある。もっとも、身分の高い武士は首級を、身分の低い武士はその耳や鼻をとるのが、当時の日本の習わしだったともいう。
そこで想起されるのは、秀吉の朝鮮出兵だ。明・朝鮮の戦闘員ばかりか非戦闘員からも鼻や耳を削いだという。何とも残酷な話である。それらの鼻や耳は、塩漬け・酢漬けなどの防腐処理を施した上で、日本に送られた。この時作成された鼻受取状は、朝鮮出兵の陰惨な裏面史を今に伝える証拠史料の一つになっている。
これらの鼻や耳を埋めて供養したのが、京都に残る「耳塚」だ。当初は「鼻塚」と言ったらしい。「鼻削ぎ行為は残酷だ」という林羅山の意見によって、「耳塚」と称するようになったという。
【参考】
・加納喜光『見て味わう漢字の満漢全席』1995年、徳間文庫、P.107〜108
・ウィキペディア「耳塚」の項(2014年10月24日参照)。 |
|
|
|
| 2014年10月16日(木) |
| 発電所並みの発熱量 |
清盛が重病に陥った。発病してから高熱を発した。その熱病のすさまじさを、『平家物語』は次のように伝える。
清盛の熱病は、まるで火を焚いているかのような熱さ。清盛の側に近づくと、その熱さは耐えきれないほど。清盛もただ「熱い、熱い」と言うばかり。これは普通の病気ではあるまい(おそらく神仏の祟りに違いない)。そこで、比叡山の千手井という井戸から汲み出した水を、石で造った水槽に湛え、そこに清盛を沈めて冷やそうとした。ところが、あまりの熱さのために水はものすごく沸き立って、ほどなく湯になってしまうという有様。清盛の苦痛を少しでも和らげようと、筧(かけい)を使って水をかければ、焼けた石や鉄にかけたかのように水がほとばしって、全く寄せつけない。たまたま清盛に当たれば炎となって燃えあがる始末。部屋の中は黒煙で充満し、炎がうずまいて燃え上がる…。
ほどなく清盛は、「頼朝が首をはねて、わがはかのまへに懸くべし」(頼朝の首を刎ねて、我が墓前に供えよ)という言葉を遺して死去する。64歳だった(1184年)。
冷水が沸騰して湯になるばかりでなく、発火するほど発熱量を持っているなら、清盛をエネルギー源にした発電所を造れるかも。江戸時代の川柳子は、「清盛の医者ははだかで脈をとり」と、悪のりしすぎた『平家物語』の表現を茶化している。
【参考】
『平家物語』の該当部分(原文)は次の通り。
「身の内のあつき事、火をたくが如し。ふしたまへる所四五間が内へ入(いる)ものは、あつさたへがたし。ただのたまふ事とては、「あた、あた」とばかり也。すこしもたゞ事とは見えざりけり。比叡山より千手井(せんじゅい)の水をくみくだし、石の舟にたたへて、それにおりてひえたまへば、水おびたゝしくわきあがッて、程なく湯にぞなりにける。もしやたすかりたまふと、筧(かけひ)の水をまかせたれば、石やくろがねなンどのやけたるやうに水ほとばしッて、よりつかず。おのづからあたる水は、ほむらとなッてもえければ、くろけぶり殿中にみちみちて、炎うづまいてあがりけり。」(梶原政昭・山下宏明校注『平家物語(二)』1999年、岩波文庫、P.288)
|
|
|
|
| 2014年10月15日(水) |
| 名前は立派じゃない方がいい? |
兆民の話が出たついでに、名前の話をもう一つ。兆民に子どもが生まれた。兆民は「立派すぎる名前は、子どもにとって迷惑だろう」と考えた。そこで、将来、子どもが人力車夫になっても支障がないように、「丑吉(うしきち。1889〜1942))」と命名した(ちなみに、丑吉の妹は体が小さかったので千美(ちび)と命名したという)。
しかし、丑吉は人力車夫にはならなかった。東京帝大法学部政治学科を卒業後、中国思想の研究家となって活躍した。
妻子がなかったため、丑吉の死をもって中江家は断絶したが、もし丑吉に子どもがいたなら、何と命名しただろうか(出典不明)。 |
|
|
|
| 2014年10月14日(火) |
| 明治の知識人はソウジ好き? |
|
我が国にルソーの社会契約論を紹介して、「東洋のルソー」と称された中江篤介(なかえとくすけ。1847〜1901)。自ら、「億兆の民」を意味する兆民(ちょうみん)と号した。しかし、以前は「秋水」と名乗っていた。「秋水」の号は、弟子の幸徳伝次郎(こうとくでんじろう。1871〜
1911)に譲っている。大逆事件で処刑されたあの幸徳秋水に、だ。
「秋水」といえば、『荘子(そうじ)』(外篇)の「秋水篇」が思い浮かぶ。「魚の楽しみがわかるか」について、荘子と恵子(けいし)の問答が載っている(1)。名文だというので、高校時代の漢文の教科書にも載っていた。
そういえば、『小説神髄(しょうせつしんずい)』の評論で知られる坪内逍遙(つぼうちしょうよう。1859〜1935)の「逍遙」も、『荘子』に出ていた。『荘子』(内篇)を開くと、最初のページが「逍遙遊篇」で、北の果ての暗い海に棲んでいた巨大な魚が鳥に化して、南の果ての暗い海を目指すという壮大な寓話が載っている(2)。大事業をなすたとえの故事成語「図南鵬翼(となんのほうよく)」の出典となる話だ。
また、小説『滝口入道』で知られる高山樗牛(たかやまちょぎゅう。1871〜1902)の「樗牛」も、同じ『荘子』の「逍遙遊篇」に出てくる。樗(ちよ。ぬるでの木。無用のものを樗櫟(ちょれき)という)は幹は瘤(こぶ)だらけで、小枝は曲がりくねっている。建築用材にならないので、大工も振り向かない。牛は野牛のことで、図体ばかり大きくて罠にかかる心配はない。しかし、鼠を捕るのには役立たない。役立たずだからこそ、斧(おの)や鉞(まさかり)で切られることもなく、危害を加えられる気遣いもない(3)。
なまじ「できる人間」と見なされると、妬みやそねみから失脚の憂き目にあうやも知れない。むしろ「樗牛」としての穏やかな人生を選びたい、と思う人も多いはずだ。そう考えると、『荘子』に魅了されるのは、明治の知識人に限ったことではない。
【注】
(1)森三樹三郎訳注『荘子(外篇)』1974年、中公文庫、P.229〜230
(2)森三樹三郎訳注『荘子(内篇)』1974年、中公文庫、P.7〜8
(3)森三樹三郎訳注『荘子(内篇)』1974年、中公文庫、P.23〜24
|
|
|
|
| 2014年10月9日(木) |
| 執念深い上司 |
|
軍事政権を打ち立て、「鎌倉殿」として専制的権力を強めていった源頼朝。しかし、頼朝には頭痛の種があった。それは、京都の公家政権から位階官職をもらい、それを誇るという鎌倉武士たちの権威主義。
御家人が官職に就く場合には、頼朝が該当者を推薦し、しかるのちに京都方が任命するというルールがあった。ところが、頼朝の推薦を受けずに多くの関東武士が直接、朝廷の官職に就任したのである。これでは、ほかの御家人たちにしめしがつかない。勝手に任官した御家人らに対する頼朝の怒りはすさまじかった。
1185年4月、頼朝は彼らの本国帰還を禁止した。そして、尾張国の墨俣川(すのまたがわ)以東に足を踏み入れた者は、本領を没収した上斬罪(ざんざい)に処すとまで言い切った。
さらには、該当者のリストに、一々悪口まで書き添えた。
たとえば、「兵衛尉(ひょうえのじょう)義廉(よしかど)」のところを見ると、「(義廉は) 鎌倉殿(頼朝)は悪主である。それに比べ木曽義仲は吉主だと言い、父親をはじめ昵懇の者たちを引き連れ、木曽殿のもとへ馳せ参じようと言った。さらには、鎌倉殿に仕えても、ついには落人(おちうど)になるのが関の山。こんな憎まれ口を言ったことも忘れたのか。この「悪」兵衛尉め!」みたいなことが書いてある。
そのほかの御家人に対しても、「目ハ鼠眼(ねずみまなこ)ニテ只候スベキノ処(ところ)、任官希有(けう)ナリ」とか「色ハ白ラカニシテ、顔ハ不覚気ナルモノノ、只候スベキニ、任官希有(けう)ナリ」、「顔ハフハフハトシテ、希有(けう)ノ任官カナ」などという悪口がずらずら。
九条兼実が「其ノ性強烈」(『玉葉)』)と評した頼朝。その徹底した執念深さって、本当に「お〜こわ;」。こんな人は上司に持ちたくないわあ。頼朝が上司だったら、憂鬱になって会社に行けなくなっちゃうかも。
【参考】
・永原慶二『源頼朝』1958年、岩波新書、P.131〜132
・龍粛訳註『吾妻鏡(一)』1939年、岩波文庫、P.183〜185
|
|
|
|
| 2014年10月8日(水) |
| サネモリ様 |
平家方の武将斎藤実盛(?〜1183)は、武蔵国長井荘の別当職にあったので、斎藤別当実盛と呼ばれた。寿永2(1183)年、加賀国篠原で源義仲軍と戦い討死。享年は50余歳とも、60余とも、70余とも言われる。老武者だからといって敵兵から侮られぬよう、白髪を黒髪に染めて出陣したという(『平家物語』)。最初から討死覚悟の出陣だった。
実盛の最期については、西日本一帯に広く分布する民間伝承がある。実盛は、稲株につまずいて倒れたために討ち死にした。その遺恨によって、実盛の霊は、稲を食う害虫となった。そこで、虫害に悩まされた農民たちは、大きな藁人形を作り、「御陣立(ごじんだ)て、御陣立て、実盛虫(さねもりむし)の御陣立て」と囃しながら鉦や・鼓等を打ち鳴らし、害虫を村外に追い払う「虫送り」をするのだという。(注)
なぜ、実盛と虫送りが結びついたのか。
『平凡社大百科事典』を引いてみると、そこには二つの説が紹介されていた。一つは、古語の「いなむし」はイナゴ・バッタ・ウンカ・メイチュウなどイネの害虫を総称したもので、イナゴを別当と呼んだことから、斎藤別当に付会されたのではないか、いう説(「イナゴ」民俗の項、千葉徳爾氏による)。もう一つは、田の虫を意味するサノムシが実盛に転訛したとする説(「虫送り」の項、大島暁雄氏による)。
不勉強で、「イナゴを別当と呼んだ」なんて事実を初めて知った。一体、どこの地方で使われた方言なのだろう(バッタならベットーへの訛伝は想像されるが)。だから、上の二説のどちらが妥当か、私には判断できない。ただ、西日本に実盛に関する伝承が分布しているのは、平氏の勢力圏が西日本だったことと関係があるのだろうか。
(注)「西国の農家にてハ斉藤別当実盛、手塚太郎光盛と戦し時、実盛が馬稲株につまづきて落馬しけるを手塚取て押へ首をかきたりしゆゑ、其霊魂蝗となり稲に害をなすよしの俗説をまうけ、大きなる藁人形を二ツ拵へ、紙にて鎧を着たる躰に絵どり、其人形を竹にさし高くさしあげ、大勢声をそろへ御陣立御陣立実盛虫の御陣立、手塚どのにうたれて後富貴栄た、えいえいわあと鯨波をあげ鉦・太鼓・螺貝を吹て田の大畔道を往て、其人形と松明を野辺あるひハ川の辺などに捨かへる也」(大蔵永常『除蝗録』)
【参考】
・谷川健一「魂虫譚」(同氏『魔の系譜』1984年、講談社(学術文庫)所収)
・乾克己他編『日本伝奇伝説大事典』1986年、角川書店、「斎藤実盛」の項
・『除蝗録』(国会図書館デジタルコレクション、http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1089422)
その他 |
|
|
|
| 2014年10月4日(土) |
| 文字が読めたのは、たったの0.02%? |
武家政権として成立した鎌倉幕府。しかし、頼朝は、侍所別当に和田義盛を任命したものの、公文所・問注所両長官には鎌倉武士ではなく、貴族出身の大江広元や三善康信を登用した。それは、当時の武士の教養が低くて、自分の名前すら書けない者たちがいたからだ。
そんな説明を補強するのによく引用される例がある。それは次のようなものだ。
「承久の乱で、鎌倉軍に敗れた上皇方が、降伏の院宣を出した。ところが、鎌倉武士たちの中で読める者がいない。そこで、その場にいた鎌倉武士5,000人の中から読解できる者を探し求めたところ、藤田三郎(能国、よしくに)という御家人だけが院宣を読解できた」。
念のため、インターネット上で引用されている史料文を検索してみると、なるほど、院宣を読み得た者は「五千」人にわずかに一人だけ、となっている。ところが、手元にあった岩波文庫版『吾妻鏡』を開いてみると、こちらでは数字が違っていた。
(承久3年6月15日)國宗院宣を捧げ、樋口河原に於て、武州に相逢ひて子細を述ぶ、武州院宣を拜す可しと稱して、馬より下り訖(おわ)んぬ、共(とも)の勇士、五十餘輩有り、此中(このなか)に院宣を讀む可きの者候かの由、岡村(異本では「崎」)次郎兵衛尉を以て相尋ねるの處、勅使河原小三郎云、武藏國の住人藤田三郎は、文博士の者なりと、之を召し出す、藤田院宣を讀む。(龍肅訳注『吾妻鏡(四)』1941年、岩波文庫、P.205)
「五千」と「五十」。文書のコピーを手書きでしていた時代だから、こんな相違も珍しくはないのだろう。それにしても、どちらが正しいのだろうか(もちろん、どちらも誤りの場合だってある)。
たとえば、仮に「五十」が、『吾妻鏡』に書かれてあった元々の正しい数値だったしよう。「十」の二画目に筆を入れる際、力を入れて書いたら「千」の字に見える。また、誰かが訂正等の目的で、「十」の二画目の上に「ノ」の字を書き加えて「千」にしたのかも知れない。写本を作成する段階で、単純に誤写したとも考えられる。
それにしても、「50余人に1人が院宣を読めた」と、「5千人に1人しか院宣が読めなかった」では、鎌倉武士に対する印象がまるで違ってくる。
いくら院宣の文章が難解だからといっても、幕府の諸機関には多くの貴族が寄人(よりうど)として参加していたのだから、武士との文化的交流もあっただろう。また、好学の武士も藤田三郎一人に限ったことではなかったろう。
「5千人に1人しか院宣が読めなかった」というのは、ちょっと言い過ぎのような気がするな。 |
|
|
|
| 2014年10月3日(金) |
| 百分の三 |
藤原定家が撰んだ小倉百人一首。この中に一家から三人採用された人びとがいる。清原深養父(ふかやぶ。?〜?)、清原元輔(もとすけ。908〜990)、清少納言(?〜?)だ。心覚えに、三人の和歌を次に書き留めておこう。なお、和歌の引用や深養父・元輔の経歴は、島津忠夫訳注『百人一首』1969年、角川文庫、によった。
清原深養父は豊前介房則(ぶぜんのすけふさのり)の子で、元輔の祖父、清少納言の曾祖父にあたる。内匠允(たくみのじょう)、内匠大允(たくみのだいじょう)を歴任、延長8(930)年に従5位下。晩年京都洛北に補陀落寺(ふだらくじ)を建立したという。『古今和歌集』には17首入集している有力歌人。
夏の夜はまだ宵(よひ)ながら明(あけ)ぬるを 雲のいづくに月やどるらむ
(短い夏の夜は、まだ宵の口だと思っているうちに明けてしまった。これでは月も西の山まで行き着く
暇がない。雲のどこにあの月は宿っているのだろうか。)
清原元輔は下総守春光(または下野守顕忠)の子。深養父の孫。清少納言の父。河内権少掾(かわちのごんのしょうじょう)より諸官を歴任。天元3(980)年に従5位上。「梨壺(なしつぼ)の五人」(梨壺に置かれた和歌所の寄人(よりゅうど))の一人として『後撰和歌集』の撰集と『万葉集』の付訓の事業に当たった。三十六歌仙の一人で勅撰和歌集に約百首が入集。
契(ちぎり)きなかたみに袖をしぼりつつ 末の松山なみこさじとは
(かたく約束したはずだったのに。お互い幾度も涙に袖を絞りながら、あの末の松山を浪の越すことが
ないように、二人の間も決して末永く変わらないようにと。それなのにあなたは心変わりなんかして…。)
清少納言はご存じ『枕草子』の作者。
よをこめて鳥の空音(そらね)ははかる共 よにあふさかの関(せき)はゆるさじ
(夜の明けないうちに、鶏の鳴き真似をして函谷関の番人をだました孟嘗君の手を使おうとしても、あなたと私
との間の逢坂の関(男女が相逢ういう名がある関所)はそうはいきませんよ。わたしは決して会いませんから。)
|
|
|
|
| 2014年10月2日(木) |
| 首が落ちても死なないって?(3、終) |
新田義貞と並んで、『葉隠』が称揚したのが大野道賢の行動。
大野道賢の最期は、同じ『葉隠』に出ている(和辻哲郎・古川哲史校訂『葉隠・下』1941年、岩波文庫、P.119〜121)。
大野道賢は、豊臣秀頼の家臣大野治長(はるなが)の弟。大坂冬の陣の和睦後、家康が約束を破って再度大坂城に攻めてくることを予見していた道賢は、伏勢を置かせないため、先手を打って堺の町を焼き払った。これを知った家康は道賢を深く憎み、夏の陣では道賢の生け捕りを命じた。戦後、生け捕りにされた道賢の下げ渡しを、堺の町人が願い出た。こやつの放火で住人たちはこの上もない難儀をした、町の焼け跡で火あぶりにしてくれよう、というのだ。
かくして道賢は火あぶりにされた。
やがて検使罷(まか)り越し、遠あぶりにて苦しみ候様にこしらへ候ども、すこしも動き申さず焼け死に候に付て、火を取り直し候へば真黒にからだばかりが見え候が、その儘(まま)検使に飛びかかり、検使の脇差(わきざし)を抜き取り、唯(ただ) 一突きに突き殺し、からだは忽(たちま)ち灰になり候由。
火あぶりになって真っ黒にされた道賢。そのまま検使に飛びかかり、その帯びていた脇差を抜き取ると、一突きに検使を殺してしまった。すると、たちまち道賢のからだは灰になって崩れ去った、というのだ。
山本常朝には悪いが、義貞・道賢のエピソードとも「講釈師、見てきたような○○を言い」の見本のようなエピソードだ。 |
|
|
|
| 2014年10月1日(水) |
| 首が落ちても死なないって?(2) |
『葉隠』が「出し抜けに首を打ち落とされても、ひとはたらきは十分にできるものだ」という例としてあげているのが、新田義貞の行動。
義貞は、越前藤島の戦いにおいて、流れ矢に当たって死んだ。その最期を、『太平記』は次のように伝える。
義貞を乗せた馬は、5筋の矢をその身に受け負傷していた。そのため脚力が弱っていたのであろうか、平生ならたやすく跳び越えられるような小溝に脚をとられ、どっと倒れてしまった。馬の下敷きとなった義貞が体を起こそうとしたその瞬間、義貞めがけて白羽の矢が一筋飛んできて、眉間の真ん中に命中してしまった。急所を射抜かれ、「もはやこれまで」と覚悟を決めた義貞は、太刀をすらりと抜きはなつと左の手に取り渡し、自らの首をかき切った…。
実はこの後、とんでもないことが『太平記』には書いてある。
名もない雑兵(ぞうひょう)に首を取られることを恐れたのか、首のない義貞は、自ら刎(は)ね落とした首を深泥(じんでい)の中にかくし、その上に身を横たえたというのだ。 |
|
|
|
| 2014年9月30日(火) |
| 首が落ちても死なないって?(1) |
佐賀出身の大隈重信が、「奇異なる書」「奇妙なる経典」と呼んだ書物がある。佐賀に伝わる『葉隠(はがくれ)』だ。元佐賀藩の武士で、出家・隠棲していた山本常朝(やまもとつねもと)の口述を、田代陣基(たしろつらもと)という青年が宝永7(1710)年から7年間にわたり筆記したもの。「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり。二つ二つの場にて、早く死ぬかたに片づくばかりなり」の強烈な言葉で知られる。
常朝はこの本の中で、結構、無茶苦茶なことを言っている。
たとえば、「出し抜けに首を打ち落とされても、ひとはたらきは十分にできるものだ。(中略)心がふがいないからなすところなく倒れてしまうのだ。(中略)これは、何かをしてやろうという考えで一筋に思いこむことである。武勇のためには、怨霊にも悪鬼にもなってやるぞと、人なみはずれたふてぶてしさを心に持てば、首が落ちても、死ぬはずはない」(奈良本辰也訳編『葉隠』1973年、角川文庫、P.130)なんて言っているのだ。
「首が落ちても、死ぬはずはない」なんて言っているが、首が落ちても生きていた人間なんていたのだろうか?
常朝に言わせれば、「いた」のである。それは、新田義貞(にったよしさだ)と大野道賢(おおのどうけん)の二人だという。
【参考】
上記現代語訳に相当する原文(全文)は以下の通り。
「出し抜きに首打ち落されても、一働きはしかと成る筈に候。義貞の最後證據なり。心かひなく候て、その儘打ち倒ると相見え候。大野道賢の働きなどは近き事なり。これは何かする事と思ふぞ只一念なり。武勇の爲、怨霊悪鬼とならんと大悪念起したらば、首の落ちたるとて、死ぬ筈にてはなし。」(和辻哲郎・古川哲史校訂『葉隠・上』1940年、岩波文庫、P.109) |
|
|
|
| 2014年9月29日(月) |
| 栄西の慈悲 |
日本臨済宗の開祖栄西(えいさい、ようさい。1141〜1215)が、まだ建仁寺にいた頃の話。
一人の貧人が寺にやってきて言うことに、「私の家は貧しくて、竈の煙が絶えること数日間に及び、夫婦子ども2、3人が餓死しようとしています。お慈悲をもって、お救いください」と。しかしその時、建仁寺の僧坊中には、まったく衣食財物等がなく、どうしてよいかわからなかった。ただ、薬師如来像を造立するのに、後背の材料として打ちのばした銅が少々あった。栄西はこれを取り、自分で打ち折って束ねて丸め、「これを食物と代えて飢えをふさぎなさい」と言って、貧人にやってしまった。貧人は喜んで寺から退出した。
弟子たちは栄西の行動を非難した。
「あの銅は仏像の光背を造るためのものです。それを俗人に与えてしまうのは、仏のために使用するものを勝手に使用した罪になると思いますが、いかがですか」
栄西は言われた。
誠に然(しか)り。但(ただ)し佛意(ぶっち)を思ふに佛(ほとけ)は身肉手足
(しんにくしゅそく)を割(さ)きて衆生(しゅじょう)に施こせり。現に餓死すべき
衆生には設(たと)ひ佛の全體を以て與(あた)ふるとも佛意に合(かな)ふべし。
(誠にその通りである。ただ仏の意志を思うと、仏は身肉手足を切って施しをされたのであり、現に餓死に瀕する
人びとがいれば、たとい仏の全体をもってその人たちに与えても、仏意にかなうことになろう。)
また、次のようにも言われた。
我れは此(こ)の罪に依(より)て悪趣(あくしゅ。地獄、餓鬼、畜生、修羅の悪道)に
墮(だ)すべくとも、只(ただ)衆生の飢へを救ふべし。
(自分は仏の物を私用に使った罪で悪趣に堕ちても、ただ人の飢えを救うであろう。)
【参考】
・古田紹欽(ふるたしょうきん)訳註『正法眼蔵随聞記』1960年、角川文庫、P.74〜75
|
|
|
|
| 2014年9月28日(日) |
| こんなことなら書くんじゃなかった |
|
坪内逍遙(つぼうちしょうよう。1859〜1935)の日記は、一部英語で書かれてある。英語がわからなかった妻に、日記を読ませないためだ。その部分には妻への悪口や不満が書いてあるそうだ。おしどり夫婦で知られた坪内夫妻。それでも、妻に対する憤懣があったらしい。
「妻には日記を見せたくない」と考えたのは、逍遙ばかりではない。石川啄木(1886〜1912)もそうだった。妻に読まれたくなかったので、日記をローマ字で書いた。次は、日記の1909年4月7日(水)の部分。
「なぜこの日記をローマ字で書くことにしたか? なぜだ? 予は妻を愛してる。愛してるからこそこの日記を読ませたくないのだ、―しかしこれはうそだ! 愛してるのも事実、読ませたくないのも事実だが、この二つは必ずしも関係していない。そんなら予は弱者か? 否、つまりこれは夫婦関係という間違った制度があるために起こるのだ。夫婦! 何という馬鹿な制度だろう! そんならどうすればよいか? 悲しいことだ!」
こうして啄木は、妻には見せられないようなろくでもないことを、ローマ字でさんざん日記に書き綴った。しかし1912年、肺結核に罹患した啄木は、26歳の若さで病没する。妻の節子には、日記を燃やすようにと言い遺した。しかし妻は、愛着のため、処分することができない。日記は啄木の親友に託され、この世に残ることになった。
のちに日記は、啄木研究の重要資料として活字化された。こうして、故人の意思に反して、その内容は広く公開されるはめになってしまった。
啄木はあの世で悔いているに違いない。「こんなことになるなら、書くんじゃなかった」と。
|
|
|
|
| 2014年9月14日(日) |
| 将軍の虫歯 |
|
徳川14代将軍家茂(いえもち)が、第2次長州征討の途上、大坂城で病死する。20歳の若さだった。将軍の遺体は後年、掘り出され、現代科学によって分析された。そこで興味深いことが判明した。家茂の歯のほとんどが虫歯だったのだ。
残存していた歯31本のうち、虫歯でなかったのは下顎(したあご)の右、第三大臼歯(きゅうし)1本だけだった。どのような食生活習慣を送ってきたかも問題だが、20歳でここまでひどい虫歯とは、よほど歯が弱かったのだろう。ちなみに、家茂夫人の静寛院宮(公武合体で将軍と結婚したあの「和宮(かずのみや)」のこと)の虫歯は7本だった。江戸時代、庶民の虫歯の平均本数は4.5本だったというから、将軍家の人々は、庶民より甘いものを多く摂取していたとみえる。
ところで、12代将軍だった徳川家慶(いえよし)は60歳で没した。その歯の噛み合わせ部には、磨耗がまったく見当たらず、まるで子どもの歯のようだったという。きわめてやわらかい食物しかとっていなかったことの証拠だ。
【参考】
・進士慶幹「公方様の普段着」-文化出版局編集部編『江戸意外史』1978年、文化出版局 所収-
|
|
|
|
| 2014年9月13日(土) |
| 馬を背負って逆落とし |
|
軍略の天才、源義経。平氏の陣営を断崖下に臨み、その背後を急襲しようとの無謀な作戦。「鹿でさえ谷を下ることができる、馬にできない道理はない」という無茶な論法。「御大将に遅れるな!」とばかりに、真っ逆さまに斜面を駆け下りる源氏の騎兵たち。不意を突かれた平氏の兵らは、右往左往の大混乱。おなじみ一ノ谷合戦の名場面!
ところでこの時、畠山重忠は考えた。谷を駆け下ることで、馬がケガでもしたら一大事。そこで重忠、ヒョイと馬をおんぶして、そのまま岩場を下っていった(『源平盛衰記』)。このエピソードをもとに、埼玉県深谷市畠山には、愛馬「三日月」を背負った畠山重忠の銅像まで建っている(「畠山重忠公史跡公園」で検索すると、銅像の写真が見られる)。
『源平盛衰記』には、重忠が馬を背負って谷を下る有様を
手綱腹帯より合せて、七寸(しちすん)に余て大に太き馬を十文字に引からげて、鎧の上に掻負(かきおい)て、椎の木のすたち一本ねぢ切杖につき、岩の迫(さこ)をしづしづとこそ下けれ。
と描写し、こうした重忠の大力ぶりを「人間業(にんげんわざ)ではない」と、次のように評している。
東八箇国に大力とは云けれ共、只今(ただいま)かゝる振舞(ふるまい)、人倫には非ず、誠に鬼神の所為(しょい)とぞ上下舌を振(ふるい)ける。
しかし、いくら大力で知られた畠山重忠であっても、本当に馬を背負うなんてことができたのだろうか?
たとえば、重忠の馬「秩父鹿毛(ちちぶかげ)」は「7寸8分」の馬だったされる。中世、馬の体高を表す場合、基準を4尺(約121cm。これを「小馬(こうま)」といった)とし、これを超える場合には、1寸とか2寸とか表記した。つまり、7寸8分というのは、4尺に7寸8分(約24cm)を足して、4尺7寸8分(約145cm)の体高の馬ということなる。
5尺(約152cm)を「大馬(おおうま)」と言ったから、それに少し足りないくらいの大きさだったわけだ。これは現在でいうと、ポニーと同じだ。しかし、それでも体重は300kg前後はあるだろう。
20kgほどの鎧・甲冑を着て、300kgの馬を背負い、谷を下りたというのである。そんな芸当が、いくら力自慢の畠山重忠だったとしても、到底できたとは考えにくい。見てきたような嘘をつく、軍記物のなせる「ハナシ」だろう。
同じ軍記物の『平家物語』には、重忠が馬を背負う「ハナシ」は出てこない。また当時、畠山重忠が属していたのは、源範頼の軍勢だったという。そもそも義経の別働隊の中に、重忠はいなかったのだ。
【参考】
・村田重幸「中世の馬について」1957年(2014年9月12日、インターネットで検索)
・『源平盛衰記』の引用は「http://www.j-texts.com/sheet/seisuik.html」を参照。
|
|
|
|
| 2014年8月30日(土) |
| ピローブック |
|
当時は貴重品だった紙。一条天皇と中宮定子に料紙を献上する人がいて、中宮からその料紙が清少納言に下賜された。
「主上(一条天皇)は『史記』を書くつもり。少納言は何を書くの?」 清少納言の答えが「枕にこそはべらめ」。「主上が『史記』をお書きになるなら、私は「枕」にしましょう」程度の意味。では、この「枕」とは、一体何のことだろう。
凡人の私には、「昼寝をする際、枕にするのに丁度よい厚さの本」くらいのことしか思い浮かばない。
遠い昔に何かで読んだ記憶では、「各段の文頭(枕)が、『花は』『鳥は』『うつくしきもの』『にくきもの』という「ものはづけ」で文章が始まる、だからこの名称になったのだ」とか…。しかし、これには諸説ある。
その中の一つで、五味文彦氏が『枕草子の歴史学』(2014年、朝日選書、P.16〜20)で披露した説が次。
一条天皇は、中国の歴史書『史記』を書きつけるという。天皇が漢文の『しき』を書くのなら、私は和文で『しき』を書きましょう。だから、清少納言の文章は、四季を枕(文頭)にして書き始めたので、「春はあけぼの」から始まる。「史記→しき→四季」という連想と、中国風に対する和風という対比で、全文通して季節や身辺の事柄を書き付けたのが『枕草子』だというのが五味氏の説。
機知に富む清少納言らしい受け答えだ。でもこれって、結局はダジャレ?
|
|
|
|
| 2014年2月6日(木) |
| こんなところで大田さん |
狂歌・洒落本・黄表紙・随筆等に多彩な才能を発揮した大田直次郎(1749〜1823)。四方赤良(よものあから)、寝惚(ねぼけ)先生、蜀山人(しょくさんじん)等これまた多様な戯号を使用した。
本名は何というのか。本名は覃(「たん」、または「ふかし」)といい、字(あざな)は子耜(しし)、通称を直次郎、南畝(なんぽ)と号した。子耜の「耜」は農耕に使うスキの意だし、南畝は南に面した日当たりのよい土地のことだ。苗字の「大田」の縁語でつけたものだろうと思っていた。
たまたま岩波文庫の『千字文』(安本健吉註解、1937年)の「俶載南畝…」(注)のところを見ていたら、ここの部分は『詩経』に依拠していると説明されており、次の一文が参考として掲げられていた。
○詩ノ小雅ノ大田ニ、我ガ覃(たん)耜(し)ヲ以テ、俶(はじ)メテ
南畝ニ載(こと)シ、厥(そ)ノ百穀ヲ播(う)ウ。(原漢文)
ひょんなところで「大田直次郎」に出会い、意外な発見に得した気分になった。それと同時に、江戸人の教養の高さに改めて感心させられた次第だ。
(注)「俶(はじ)めて南畝に載(こと)あり」と訓ずる。「春になると、農民がはじめて日当たりのよい南方の田に出て、耕作に取りかかる」の意味。 |
|
|
|
| 2014年1月12日(日) |
| 祝!成人 |
|
明日1月13日は成人式。前倒しして、日曜日である今日、式を行ってしまう地方自治体も多いようだ。
現在は20歳になると、成人と見なされる。ただ、世界の多くの国々では18歳を成人としているため、日本でも法律改正の動きがある。しかし、平安時代、貴族の子どもたちは12歳前後で成人式を行った。
成人式を迎える前の少年少女たちは、みんな振り分け髪というヘアースタイルだった。頭の真ん中で両側に髪を垂らし、伸ばしていたのである。少年は、髪をみずらに結う場合があった。
男子の場合、成人式を元服といった。元服を現在は「げんぷく」と読むが、当時は「げんぶく」と読んだようだ。元服の時に髪を結って、冠を初めてかぶる。そこで、男子の元服を冠(こうぶり)といったり、初冠(ういこうぶり。初め冠をかぶる、の意)ともいった。以後、男子は宮中に出仕するのである。
女子の場合、髪の毛を後方で束ね(髪上げ)、着物の上に裳(も)を着けるので、女子の成人式を裳着(もぎ)といった。裳は、成人した女性の証明である。
女性の正装を女房装束(にょうぼうしょうぞく)という。何枚もの着物を重ね着したので、別名、「十二単(じゅうにひとえ)」ともいうが、重ね着の枚数は12枚に限っていたわけではない。これより少ない場合の方が多かったが、反対に15枚、20枚と多く着ることもあった。それにしても、相当な重量だったことは、間違いない。正装の際、着物の一番上に、豪華な唐衣(からぎぬ)を着た(唐衣を脱ぐと略装になる)。唐衣を着る時には、腰から後方に装飾用の布を垂らした。これが、「裳」だ。
成人した女性は、化粧をすることになる。当時の寝殿造の建物は広く暗かったため、コントラストがはっきりした顔が好まれた。そこで、白粉(おしろい)で顔を白く塗りたくり、毛抜きで眉を引き抜いて、黛(まゆずみ)で眉を描き直した(引き眉)。唇には紅をつけ、歯を黒く染めた(お歯黒)。
こう見てくると、成人式は圧倒的に女性の方が大変だった。
現在の成人式だって、男性はスーツ姿でOKだが、女性の方は化粧やら、美容院やら、着物のレンタルやらで、その費やす労力・時間・費用は莫大だ。
|
|
|
|
| 2014年1月7日(火) |
| 座布団1枚! |
関東で反乱を起こした平将門。新皇を自称し、一時期関東を制覇した。しかし、940(天慶3)年2月14日、追討軍の平貞盛・藤原秀郷(俵藤太)らの軍勢と合戦に及び、石井(いわい。現在の茨城県坂東市)の北山で討たれた。向かい風の中、矢に貫かれて死んだという。
死後、将門の行状は、さまざまに伝説化され。『太平記』には次のような伝説が語られている。
朱雀天皇の時代。平将門は東国に下って都をたて、都の天皇のように百官を任命して、自ら「平親王(モトノママ)」と称した。官軍はこぞって将門を討とうとしたが、将門のからだは鉄でできていたため、弓矢や剣によって殺すことができない。そこで都の公卿たちが相談することに、鉄の四天王像を鋳造し、比叡山で「四天合行の法」を行おうということに話が決まった。その呪法によって、天から一筋の白羽の矢が飛び降って、将門の眉間に突き刺さった。
将門の首は藤原秀郷によって刎ねられた。そして、都に運ばれ獄門にかけられた。しかし、3カ月たっても顔色が変わらず、眼(まなこ)を見開いたままだった。おまけに、「斬られし我が五体、何(いず)れの処(ところ)にか有るらん。此に来れ、頭ついで今一軍(ひといくさ)せん」と、夜な夜な呼ばわる。これを聞いて恐れない人は誰もいなかった。
ある時、道行く人が将門の声を聞いて、次のような落首を詠んだ。
将門は米かみよりぞ斬られける 俵藤太が謀(はかりごと)にて
これを聞くと、将門の首はカラカラと笑い、眼はたちどころに塞がって、その屍はついに枯れてしまったという。
上の落首は、鉄身であった将門の唯一の弱点がこめかみだったことを指摘し、米と俵の縁語を用いて一首にまとめ上げている。この落首を創作した者は、よほどその出来に自信にあったのだろう。
そうでなければ、死んだ後まで怒り狂っていた将門が、こんな落首に大笑いして、その怨念がおさまるなどという話はできなかったはずだ。これでは伝説というより、まるで落語。
【参考】
・福田豊彦『平将門の乱』1981年、岩波新書の「6 伝承の世界」参照
|
|
|
|
| 2014年1月5日(日) |
| 今年の目標 |
|
初詣に行ってお神籤を引いた。中吉だった。今年は新規なことには手を出さず、「継続することが大事」とのご託宣。継続することがいかに難しいことか。そこで2つの目標を立てた。
昨年は仕事が忙しくなって、ホームページの更新が思うようにいかなかった。今年はとりあえず、「原始・古代」にケリをつけて、「中世」に突入することが1つ目の目標。2つ目の目標は、今年も歴史検定1級を受験し、合格すること。
そういえば、そろそろ昨年受験した検定結果が返ってくる頃。論述問題は別にしても、鉄剣銘文の穴埋め問題と「下知状」を答えさせる問題は、ともに難問だった。
|
|
|
|