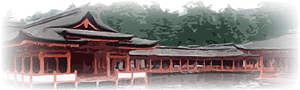| 2013�N12��26���i�j |
| �u�����v�̗R�� |
�@����(1716�`1783)�͐ےÍ������i�Ђ����Ȃ�j�S�єn�i���܁j���i���s�s����єn���j�̔_�Ƃɐ��܂ꂽ�B�̂��A�߂��̓V�������ֈڏZ�����B�V��������т͌Â����畓�̎Y�n�Ƃ��ėL���������B���̎�q�͑S���ɍL����A�u�V�������i�Ă�̂������Ԃ�j�v�̖��Œm��ꂽ�B���̎Y�n�䂦�A�����ƍ������i���������w�{����l�B�E����x1976�N�A�������ɁAP.162�j�i���j�B
�@�u�^�Ӂv���́A�ꎞ�i�����Ƃ��j�؍݂����O��{�Â̒n������Ƃ����B�����͍]�˂ɏo�Ĕo�~���w�сA��������������A�ŏI�I�ɋ��s���Z�̒n�Ƃ����̂ł���B
�i���j����ɁA�������́w�A�������i������炢�̂��j�x�i�u�A�����a�i������Ȃ��j�A�c�����i�܂��j�ɕ��i���j��Ȃ�Ƃ� �Ӂi�Ȃ�j���A�炴��v�j�ɗR������̂ł́A�Ƃ���i�E�C�b�L�y�f�B�A�u�����v�̍��B2013�N12��25���{���j�B |
|
|
|
| 2013�N12��22���i���j |
| �t�O |
|
�@�j�̒ʏ̂������ÉE�q��i�܂ނ炩������j�Ƃ������B���̋����̕������������A�G�t�Őg�𗧂Ă悤�ƍl�����B��Ƃɍ���חサ�����̂́A����ɊG�����ꂸ�A�於��������Ȃ������B���͂�A���E�ȊO�ɓ��͂Ȃ��A�Ƃ܂Ŏv���l�߂��B
�@�������A�ł�����Ŏ��ʂ̂͋C���i�܂Ȃ��B���������A�t�O��H�������Ƃ��A��x���Ȃ��B�ǂ������ʂȂ�A�t�O�̖ғłɓ������Ď���ł�낤�B�����l���āA�����̃t�O���Ă����B�����̕ʂ�Ƃ���ɁA���̍�ɂ���ӂ��ƃt�O��H���A�����ς���ĐQ�Ă��܂����B
�@�ڂ��o�߂�ƁA���łɓ��͍��������Ă���B�̂͏�ƕς��Ȃ��B���炭䩑R�Ƃ��Ă������A�����܂����Ƃ��낪����A�Ăщ�Ƃɍ���חサ���B���̌�A�ǁX�於������ɒm����悤�ɂȂ����B
�@�̂��A�j�͐ےÂ̌����i����́j�̗��ɉB��āA�V���ɏt���}�����B�����ŁA�������i���j�A�����t�i�����j�Ƃ����B�l��h���J�������t�i�������B1752�`1811�j�̈�b�ł���B
�y�Q�l�z
�E���������w�{����l�B�E����x1976�N�A�������ɁAP.235
|
|
|
|
| 2013�N12��21���i�y�j |
| ���c�e |
�@���������A���R�ɔz������Ă����e�͊O�����ł���A���������푽�l�ɂ킽���Ă����B�K�i�����ꂳ��Ă��Ȃ��������߁A�e�������P���ɍۂ��Ă��e���[����ɂ������Ă��A��ɕs�ւ������܂Ƃ��Ă����B����K�i�̏��e�������Ő��Y�ł��Ȃ����̂��B���R�̒��ł́A���Y�e�J����]�ސ����������Ă����B���������̂��ƁA���H�̖�������̂��A���R�R�l���c�o�F�i�ނ炽�˂悵�B1838�`1921�j�������B
�@���c�͂��ƎF���˂̖C�p�t�͖��Ƃ��ĕ�C�푈�ɏ]�R�����o��������A�ˌ��̖���Ƃ��Ă��m���Ă����B�Ί�ɂ��Ă̖L�x�Ȓm���Ǝˌ��̘r�O�������܂ꂽ�̂ł���B����8(1875)�N�A���c�͎ˌ��Z�p�ƕ��팤���̂��ߓn������B�A����A�O�����̏e�ɉ��ǂ��������P�����e���J�������B���̏��e�́u���c�e�v�ƌĂꂽ�B����13�i1880�j�N�A���c�e�i13�N���j�͗��R�ō̗p���ꂽ�ŏ��̍��Y�e�ƂȂ�B
�@����ɑ��c�́A���{�l�̑̊i�ɂ��킹�ďe�����ǂ��i18�N���j�A����22(1889)�N�ɂ͖����Ζ��p�����A�����e�i�e�q�ɂW����[�߂�j��v�����i22�N���j�B�������đ��c�e�́A���R�̎�͏��e�ƂȂ�A�����푈�i1894�`95�j�Ŏg�p���ꂽ�̂ł���B�������A�A�����͌̏Ⴊ���������Ƃ����B
�@�̂��A�C���H�����略��������ꂽ���c�e�͉��ǂ��������A���Ԃɂ͗e�Ƃ��čL�܂��Ă������B
|
|
|
|
| 2013�N12��19���i�j |
| �ӓ������ |
�@��������A���i���C���ɕ��C����ہA�C���̐l�X�ƍŏ��ɐڐG����ꂪ�u���}�i�����ނ��j���v�ł���B���}���Ƃ́A�����ŔC���̖�l�������V�C���i���o�}����V�����B�@�V���̓��e�͒n���ɂ���č����������B�P�Ȃ鎩�ȏЉ�Ƃ����ȒP�Ȃ��̂���A�����q�̌��̎n���i�Ƃ��ɂ��̍��̎x�z�����ے�������́j������Ɏ�����̂܂ŗl�X�������B
�@���}���́A�V�C���i�ƔC���̖�l�����Ƃ̍ŏ��̕��̒T�荇���̏�Ƃ����Ӗ��������������B�w���̕���W�x�ɂ͎��̂悤�Ȑ��b���`�����Ă���B
�@���}���̋����ɁA�����ƌӓ��������肪����ł���B���̗��������āA�V�C�̐M�Z��͂Ȃ������̕\����ׂĂ���B�����������l���A�u�����̋��}���ł͌ӓ��������ނ̂�����v�Ƃ����āA���i�Ɍӓ��������������B�����܂��A���i�͐��ƂȂ��ė��ꎸ���Ă��܂����Ƃ����B�M�Z��̓T�i�_���V�i���j�̐��܂�ς��ŁA�ӓ��͒������Ɍ��ʂ���Ƃ���Ă����H���������̂��B
�y�Q�l�z
�E���X�،b��w���{�j���u���b�g12�E��̂ƒn���Љ�x2004�N�A�R��o�ŎЁAP.76�`78�ɂ��
|
|
|
|
| 2013�N12��18���i���j |
| �^�b�`���H�g�L���l���H |
�@�K���a��������_�C�v�B���������O�����A���Ƃ��Ƃ͉��R�h��Ƃ������B
�@�h��́A1842�i�V��13�j�N�A�M�B���ܖ�̏��c����i���������j���ɁA���ܒ�≮���c�މ��R�V�\�Y�E�Ȃ݂̎��j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B1861�i���v���j�N�A20�ŗב��̈��y���ɒ�q�ɏo���ꂽ�h��́A6�N���1867(�c��3)�N�A���y���߂��̉�_�R�Ǖ�@�̏Z���ɂȂ����B�������A�p���ʎ߂̂���1871(����4)�N�A�Ǖ�@�͔p���ƂȂ�A�ґ����邱�ƂɂȂ����B�ґ��ɍۂ��A�R���́u��_�v�𐩂Ƃ��A�ďo����}�����̂��Ƃ����B
�@���������āA�u��_�C�v�v�Ƃ������O�́A�e�������������̂ł͂Ȃ��B�����Ŗ�������̂��B�ł́A�u�C�v�v�͉��Ɠǂނ̂��낤�B
�@�]���A�u�������v�Ɠǂނ��Ƃ����������B�������A�����́u�Ƃ��ނˁv�B��1��������Ɣ�����̉p���o�i�ژ^�ɁuGAUN�@TOKIMUNE�v�ƋL����Ă���B
�y�Q�l�z
�E�����F�Y�u�r���|���j���ʂ������y�̐l�X�|�@13.��_�C�v�v�@�@�@�@
�@http://www.shimintimes.co.jp/yomi/kyakko13.html
|
|
|
|
| 2013�N12��16���i���j |
| �K���{�[���ĉ��H |
�@����10(1877)�N8���A�����������ŁA��1��������Ɣ�����J���ꂽ�B�������{�̐B�Y���Ɛ���̉��A�Y�Ə����ړI�Ƃ����B��3�J���Ԃ̉�����ɁA����Ґ���45���l�B���ɂ�84,000�_�]�̓W���i���W�����ꂽ�B�����̏o�i���̒�����A�P��܁i�ق����傤�B�ŗD�G�܁j����܂����̂��u�K���a�v�������B
�@�u�K���a�v�͉�_�C�v�i������Ƃ��ނˁB1842�`1900�j�����������Ȏ��a�ы@�B�ł���B�@�B���^�]����ƁA�u�K���K���v�Ƃ��������o�����Ƃ���u�K���a�v�Ƒ��̂��ꂽ�B����̃n���h�����ƁA�_��ɂ��������ȁi�����ȁE�{���Ȃǂ������Ƃ����j���l�߂��u���L�����Ɩؐ������������ɉ�]���A�u���L�����̖Ȃ���Q������������������o�����(��1)�B������������Ɋ������A�Ƃ����d�g�݂������B�a���i�ڂ������j�E�����i���j�̗���Ƃ��@�B�ŘA���������͉̂���I�������B
�@����ɁA������ɏo�i���ꂽ�K���a�ɂ�40���i�����j���̃u���L������������Ă����B�ꋓ��40�{���̎����������̂ł���B���ɁA�u���L��1�����A�]���̎��Ԃ��g�������1�l���ɑ��������Ƃ���ƁA�K���a�͂��̐��Y������C��40�{�Ɉ����グ���v�Z�ɂȂ�B���Ɣ�������w�����Ă������O�l�����A�u�{����m�D�����v�Ɛ�^�����̂������悤�B
�@�������A�K���a�͍\�����ȒP���������ߖ͑��i����ʂɍ���Ă��܂����B�܂��A�������x���s�\�����������Ƃ�����(��2)�A���������̕ی�����Ȃ�������_�́A�����̍����Ɋׂ����B
�@���̂��߁A����14�N���̃K���a�̍L���i�u�Ȏ��@�B�L���v�j�ɂ́A���~�̒��Ɂu�i���ܔv(��3)�^�Ȏ��@�B�^��_�C�v�v�Əc�ɎO�s�����ɂ����Ĉ�̐}���ڂ��Ă���B�L���̒��ŁA��_�́u����X�i��낵�j�N��m�Ĉg�V�e�َ��X�w�V�v�Əq�ׁA�͑��i�Ƌ�ʂ���悤���ӂ𑣂��Ă���B
�@���̌�A�K���a�͐l�͎����琅�Ԏ��ɉ��ǂ���A�ȍ�n�т̎O�͒n���𒆐S�ɕ��y���Ă������B�������A�K���a�Ŗa�т������͑����ĔQ�肪�キ�A���x�Ƒ@�x���s�����������B���̂��߁A�m���a�ы@�������@�B����a�эH�ꂪ��������ƁA����ɂ��̎p�������Ă������ƂɂȂ����B
���P�F��_���q�ǂ��̍��A�ΐ����|�̓��ɖȂ��l�ߍ���ň�������o���Ă͗V��ł����B���̎��A���藎�Ƃ�������
�@�@�@�@���邭�����čג������������Ɏ��R�ɔQ�肪���������B���ꂪ�����̃q���g�ɂȂ����Ƃ����B
�@�@�@�@�i�����F�Y�u�r���|���j���ʂ������y�̐l�X�|�@13.��_�C�v�vhttp://www.shimintimes.co.jp/yomi/kyakko13.html�j
���Q�F����4�i1871�j�N�Ɂu�ꔄ���K���v����t�������̂́A�R�����̕s�����̏�����ɂ��A���N�{�s�����~����
�@�@�@�@���B�{�i�I�ȓ������x�̊J�n�́A�u���W���v�i1884�N�j�A�u�ꔄ�������v�i1885�N�j�A�u�ӏ����v�i1888�N�j
�@�@�@�@���̌��z�ɂ���Ăł���B�@
���R�F��2��������Ɣ�����i1881�N�j�Ŏ�܁B��2��̔�����ł́A���_�E�i���E���Z�E�L���E���^�̊e�܂ƖJ���
�@�@�@�@�U�܂��������B��܂���Ə�Əܔv�i���_���j�����^���ꂽ�B
�y�Q�l�z
�E�����������فw�������ɂ݂锭���̃`�J���|�������̎Y�ƋZ�p�Ɣ����Ƃ����|�x
�@����22�N�H�̓��ʓW�p���t���b�g
�E���m��w�����n���Y�ƌ������w���{���ւ�Y�ƈ�Y�E�O�̓K���a�x2005�N
�@�i�C���^�[�l�b�g��pdf�t�@�C����2013�N12��16���{���j |
|
|
|
| 2013�N12��15���i���j |
| �f�i�܂�j�̐� |
�@�����M���̗V�т̈�������R�f�i���܂�A���イ�����j�B���݂̃T�b�J�[�i�R���B���イ���イ�j�Ƃ͎��Ĕ�Ȃ鋣�Z���B
�@�����܂�Ō����ƁA���v�ł���ꂽ�f���A���ȏ�̍����ɏR��グ�A�n�ʂɗ��Ƃ��Ȃ��悤�ɂ���V�тł���B�P�`�[���͂S�l�A�U�l�܂��͂W�l���琬��A���̃��t�e�B���O�������c�̐�ƁA�f�𗎂Ƃ����҂��Ƃ���l�킪�������B
�@�u�V�сv�Ƃ͂������̂́A�R�f�̓��ɔM�����Ă��̋Z���_��ɓ��B���A�㐢�u�R���i���イ�����j�v�ƌĂꂽ�l��������B�������ʁi�ӂ����̂Ȃ�݂��j���B
�@���ʂ̏q���ɂ��A�R�f�̓��Ɏu���Ă���A����7000���Ԃ͗��K�����Ƃ����B�P���Ɍv�Z����19�N�]�B���̂����A����̋x�݂Ȃ����K�𑱂������X��2000���]��B�Ԃ��ʂ���5�N���Ƃ������Ƃ��B
�@�ɂ�����Ύ���̒�ŋf���R�����B�����o�Ă���A��������̉��A����R�����B�J�̓��ɂ́A��ɓa�i���������ł�j�ŏR�点�Ă�������i��ɓa�͌����s���Ŏg�p����ȊO�́A���i�͎g���Ȃ������������j�B�a�C�̎��ł��A�Q�Ȃ���f���R�����B�������āA�Ў����f���痣��邱�Ƃ͂Ȃ������B
�@���鎞�A������i�R�f�̋��Z��̎l���ɂ́A���E���E���E���̖����ꂼ��A�����B���̂S�{�̖��u������v�Ƃ����j�̖��̎}�ɁA�݂��甯�������A�F�̓������𒅂�12,3����̏��N���o�������B���N�́A�u�f�̐��v�������Ƃ����i�w�\�P���x�j�B
�@�D���Ȃ��Ƃ��Ƃ��Ƃ�˂��l�߂āA���̋Z�����݂ɓ��B����A����ɏo�����Ƃ�����Ղ��N���邾�낤�B�������ʂ������炳������Ȃ�A�Ƃ����b���B
�@�Ȃ��A���s�s�̔����_�{�Ȃǂł́A�f�̐���͏��N�̎p�ł͂Ȃ��A�R�C�̉��̎p�����Ă���Ɠ`���Ă���i�E�B�L�y�f�B�A�u�R�f�v�̍��j�B�@ |
|
|
|
| 2013�N10��21���i���j |
| �����Ǒ��i�ӂ����̂悵�݁j |
�@�����Ǒ��i813�`867�j�͓~�k�̌ܒj�ŁA���a�V�c�̐ې��ƂȂ����ǖ[�̒�ł���B
�@�Ǒ��͕��w�ɑ��w���[���A�M�S�̌����l���ƕ]������Ă����B�x�ʂ��傫���A�l�]����������p�i�ЂƂ��ǁj�̐l���������炵���B�E��b�ɂ܂Ői���A�ӔN�͉^���Ȃ������B
�@���V��̕ρi866�j�̍ۂɂ́A��[���̔��P�j�i�Ƃ��̂悵���j�ɗ^�i���݁j���č���b���M�i�݂Ȃ��Ƃ̂܂��Ɓj�̑ߕߖ��߂��A�Z�ǖ[�ƑΗ������B�������A�P�j���������ΔƂƒf�߂���A�ǖ[���ې��ɐ����A�C����ƁA���̐����I�e���͂��}���Ɏ��Ȃ����B���N�i867�j�A�ɂ킩�ɕa�Ď����i55�j�B��l�̖��������E���a���V�c�̏���ł��������A��������c�q�܂Ȃ������B����ɂ́A�Ռp���̏�s�i�Ƃ���B836�`875�j�܂ł���875�N�ɑ����i40�j�B���̌�A���̎q������́A������y�o���邱�Ƃ��Ȃ������B
�@�������āA�Z�ǖ[�̉A�ɉB��āA�Ǒ��̖��͖Y�ꋎ��ꂽ�B
�@�Ƃ��낪2011�N�H�A�������E���O����V�Z������A�Ǒ��̓@��u���O���i�ɂ����傤�Ă��j�v�̈�\���������ꂽ�̂ł���B
�@���ڂ��ׂ��́A��ʂ̖n���y��̏o�y�������B���̂����A�������������n���y��́A�����_�ŁA�������ŌÂ̏o�y��ƂȂ����B�����ɂ́A�X���I�㔼�܂Ŋm���ɂ����̂ڂ鑐�����i�������ȁj��������������Ă����̂ł���B�������Ƃ����̂́A���t���������������������������̏��̂������B�X���I�̉��������͋H���Ȃ̂��B
�@1000�N�ȏ�̎����o�āA�����l�����Ǒ��ɁA�������Ă��邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�y�Q�l�z
�E�ې�`�L�u�������E���O����V�Z��(�����Ǒ��@�A���O���A�S�Ԓ�)�̒����v2012�N12��15���i��240�s�s�l�Î����ٕ������u���j�|�C���^�[�l�b�g�ɂ��A2013�N10��21���{���| |
|
|
|
| 2013�N10��12���i�y�j |
| �ʃR�[�q�[ |
|
�@�ʃR�[�q�[�Ɋi���̂悤�Ȍ��t�������Ă���B���ł��A�u�S�ɉ����錾�t�v���A���\�����̖���{�̒�����E���o���āA�P�ʂɂ��P��ނ�������Ă���̂��������B�ʂɈ������Ă���QR�R�[�h�X�}�[�g�t�H�����������ƁA�o�T�̖���{���P���̂ݖ����œǂ߂���T�܂ł��Ă���B
�@�Ƃ���ŁA���܂��G�L�����J������A�Q�[�e�̌��t���������Ă������B
�@�@���傤�ł��Ȃ��悤�Ȃ�A�B���������߂ł��B
�@�@��������āA�ނ��ɉ߂����Ă͂����܂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��������Җ�w�Q�[�e�i���W�x1952�N�A�V�����ɁAp.81�j
�@�Q�[�e�̗�܂��́A�ʃR�[�q�[�́u�����v���A����������Ƌꂢ�B
|
|
|
|
| 2013�N9��14���i�y�j |
| �w���������i�͂���������j�x |
�@�w���������x�́A�O�ւ̈�l�����s���i972�`1027�j�̑�\��B�����M���ɐl�C�������������Ղ̎�8�҂��A�s����47�̎��A�w�������W�x���珑���ʂ������̂��B���݁A�������������قɏ�������Ă���B������B
�@���̍�i�ɂ́A���̗����ɂ��āA������Ƃ����G�s�\�[�h������B
�@��c�̏��������̊����́A���R�ɂ���Ďq���̎�ɓn�����B�����ɏ����ꂽ�s���̎q��������M�i�ӂ����̂����̂ԁB1088�`1156�j���땶�ɂ��ƁA�ۉ�6(1140)�N10��22���A�H��i�ق�����B�������̖�j�����l�̕����菗�����~�ɓ����Ă����B���͓̊�����ɗ����̂��Ƃ����B�ꊪ�͍s�������̏������������쓹���i��͂�O�ւ̈�l�j�́w�����y��i�т傤�Ԃǂ����j�x�A�����ꊪ�����́w���������x�������B�o�t�i���傤���j�̍ȂƂ��������菗���A�ǂ̂悤�Ȍo�܂ł����M�d������肵���̂��͕s�������A�w���������x�͂������Ďq���̎茳�ɖ߂����̂ł���B
�@���̑��A�w���������x�ɂ́u���m2�i1018�j�N8��21���ɏ������v�Ƃ����s�����M�̉�����A���w�̌p���ڂɂ́w���������x���������������V�c�̉ԉ�������B
�@�ǂ̃G�s�\�[�h��Ƃ��Ă����ꋉ�i�̍�i���B
�y�Q�l�z
�E�������������ّ��ҁw���ʓW�@�a�l�̏��x2013�N�A�ʐ^P.100�`101�A�ߕ�P.306�A
�@���P.270�|2013�N7/13�`9/8�J�Â̓������������ٓ��ʓW�̐}�^�|
�E�������������كz�[���y�[�W�u������v
|
|
|
|
| 2013�N8��14���i���j |
| �V�i�S�����ĉ��b�̖��O�H |
|
�@�����������������q�����V�c�̌�{�ɓ����������b�́A���̊ԏ������B���̍ہA�œ��蓹��̈�����������ɁA����ꗬ�̍ːl�ł���̐l�ł������������A���ɁA�a�̂̌�����˗��������Ƃ��������B
�@���̎��A�a�̂����悵�������ĐM�i�Ȃ�̂ԁB967�`1035�j�E�������C�i����Ƃ��B966�`1041�j�E���r���i�݂Ȃ��Ƃ̂Ƃ������B960�`1027�j�ƁA�����̘a�̂������������s���i966�`1041�j�ɂ͋��ʓ_������B���V�c�̌��ɁA�ĐM�͌����[���A���C�͌���[���A�r���͌����[���A�����čs���͌����[���������̂��B
�@�w�˂��ӂ�邱�̌����A���A�����̐l�тƂ́u�l�[���i���Ȃ���j�v�ƌĂB
|
|
|
|
| 2013�N8��12���i���j |
| ���i�ނ炳���j�̐l�X |
�@���͍��M�ȐF���B���̂��߁A�V�c�ȂLjꕔ�̍��M�Ȑl�тƂ����A�g�ɂ܂Ƃ����Ƃ�������Ȃ������B���������F���A�F�i�����j�Ƃ����B
�@���ɂ䂩��̂����v�l�����o�ꂷ�镨����A1000�N���O�ɏ����������Ƃ�����B���������B�������̕��e�ł���˚��́u�ˁv�A���̌�ȂƂȂ铡��́u���v�A�����Č������̐��Ȏ��̏�́u���v�B���ׂāA���F�̐A�����B��҂̖��O���A���̍�i�ɗR������j�b�N�l�[�����B
�@�������́A���_�Ɍ��܂����u���̉ԁv�ƌ`�e���ꂽ���q�̂��ƂɁA�w��������x�����������ċ{�d�������B����́A���O2�i1005�j�N��3�N�̂��Ƃ������Ƃ����B���ɍʂ�ꂽ����́A�����Ƃ����M�Ȑl�i���V�c�j���A���q�̂��ƂɎ䂫����������ʂ������ɈႢ�Ȃ��B���ꂱ�����A�����̎v���ڂ������̂��낤�B���O5�i1008�j�N�ɒ��{���q�͔D�P���A�Җ]�̍c�q���i���Ђ�j�e���B
�@���q�̎��͂ɂ͎������ȊO�ɂ��A�a���A�ɐ����i�����Ӂj�A�Ԑ��q���A�B�X����˕Q�������ߎ����Ă����B�ޏ������ɂ���āA�u���������v�̈ꗃ��S��ꂽ�̂ł���B |
|
|
|
| 2013�N8��10���i�y�j |
| �a�̂��˂��� |
�@���V�c�i980�`1011�j�ɂ́A��q�i976�`1000�j�Ƃ���4�ΔN��̎o���[�������B���v�������������A�o�Y�̂��ߗ��A�肵�Ă����B�c�@��q���{���𗯎�ɂ������̌���_�����̂悤�A�����i966�`1927�j�͒������q�i988�`1074�j�����V�c�̂��ƂɁA����Ƃ��ē����������B���ی�(999)�N11��1���̂��Ƃł���B
�@�����͓�������b�B�����A���ɁA���̉œ��蓹��Ƃ��ėp�ӂ��������S�ڂ���̛����ɁA�a�̂̊��|�𗊂݂܂�����B���q�̂��܂�������ɗ\�肳��Ă����̂ŁA����ɂ��Ȃ��̛����������Ƃ����B����ɖ��H���푥�i�������ׂ̂˂̂�j�̑�a�G��\��A������������W�߂��a�̂��A�O�ւ̈�l�����s���i�ӂ����̂��������j�ɏ������悤�Ƃ���������B
�@�j������������������낤�B���͎҂̈˗��ɁA���������i�ӂ����̂����Ƃ��j�E�����ĐM�i�ӂ����̂����̂ԁj�E���r���i�݂Ȃ��Ƃ̂Ƃ������j��A�����ꗬ�̉̐l�ł��������������������X�Əj��̘a�̂��钆�A�u�ǂݐl�m�炸�v�Ƃ��������̌`�ŁA�ԎR�i������j�@�c�܂ł��a�̂��Ă����B�����A�������̓������������͓����̗v�����̂�肭���Ɠ����āA�Ƃ��Ƃ��a�̂������Ȃ������B
�@�u�O�M�i���イ�j�̍ˁv�Œm���铡�����C�i�ӂ����̂���Ƃ��j�������Ɍ��悵���a�̂́A���̂悤�Ȃ��̂������B
�@�@�@ ����b�ނ��߂̒��{�̗��ɒ�(���傤)�����i�ׁ͂j�肯�雠���Ɂ@ �E�q��i������̂��݁j���C
�@ �@ ���̉_�Ƃ�����铡�̉ԁ@�����Ȃ�h�i��ǁj�̒��i���邵�j�Ȃ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w�E��W�x�E�G�t�E1069�j
�@�u���v�����o�g�̏��q�̔��������u���v�̉ԂɌ����Ă��킯���B�u���_�v�͐����i�������傤�j�ŁA���Ȃ킿�u�߂ł������i�������j�v�̈Ӂi�u���v�͍��M�ȐF�ōc���̈Úg������A�u���_�v�͍c�@�������̂��낤�j�B�����Ƃ����Ȃ炱�̎���A�c�q�ނ��Ƃɂ������Ȃ��B�����V�c�ƂȂ�c�q�ނ��Ƃ����q�̎g���ł���A���̍c�q�͂܂������̑��ł�����̂��B
�@�������ď��q�́A���������x������L�͎҂������A�����������������ċ{���ɏ�荞��ł������B
�@�������A�֒��i�����j�̋V���i�����̐��l���j���ς܂����Ƃ͂����A���̎����q��12�B���݂Ȃ�A���w�Z6�N���̔N��B |
|
|
|
| 2013�N8��8���i�j |
| ���i�����イ�ꂫ�j |
�@�����̓��L�́A���i�����イ�ꂫ�j�̗]���ɏ������܂�Ă���B���Ƃ����̂́A�N���s������̏o�E���̓���̎����A�g���Ȃǂ��L������̂��Ƃ��B�����̋L�ڎ������u��i�ꂫ���イ�j�v�Ƃ����B�u��v���u��i�ԁj���i�ڍׁj�v�ɋL������Ă��邩��A���Ə̂����킯���B
�@���́A�����ȁi�Ȃ��������傤�j�ɑ�����A�z���i����݂傤��傤�j�̗�m�i�ꂫ�͂����j���쐬�����B�쐬�����Ƃ����Ă��A�V���ϑ���������A���G�Ȍv�Z���J��Ԃ����肵�āA�Ǝ��̗��������킯�ł͂Ȃ��B��������`��������i�閾��j�ɏ]���č쐬�����܂łȂ̂��B
�y�Q�l�z
�E��������}���كz�[���y�[�W�u��̗��j�v
�@http://www.ndl.go.jp/koyomi/rekishi/03_index_01.html |
|
|
|
| 2013�N8��7���i���j |
| �w�䓰�֔��L�i�݂ǂ�����ς����j�x�����ɍs���� |
�@����A�������������قɁw�䓰�֔��L�x�����ɍs�����B�������M�̓��L�ł���B�w�䓰�֔��L�x�Ƃ͂������̂́A�������g�A�֔��ɂȂ������Ƃ͂Ȃ��B�㐢�̖����҂��~�X��Ƃ��A��������ʂ܂܁A���̖��O���蒅�����̂��B
�@�w�䓰�֔��L�x�͍��N�i�Q�O�P�R�N�U���P�W���j�A���l�X�R�́u���E�̋L���i���Ɂu���E�L����Y�v�j�v�Ɏw�肳�ꂽ�B�����̓��L�́A�뎚�E�E���╶�@�̊ԈႢ�����������ƂŒm���Ă���B����ȓ��L���A����l�ނ̈�Y�Ƃ́B�����́A���̐��ŋ���Ă���ɈႢ�Ȃ��B
�@�w�䓰�֔��L�x�́A�����߂Ă̓W�����J�������B����ł܂��܂��ώ@���悤�Ǝv�������A��傫�Ȏ��s�������B�I�y���O���X�����Q���Ȃ��������Ƃ��B�K���X�z���̓W��������A�����ȕ������Ƃɂ��������Ȃ��B
�@���ǂ͐}�^���w�����āA�ʐ^�ōēx�̊ӏ܂Ƃ������ƂɂȂ����B |
|
|
|
| 2013�N7��15���i���j |
| �����ɂ܂��s�m���Ȃ��� |
�@���̒��́A�܂��Ƃ��₩�Ɍ��`�����Ă��鎖���̒��ɂ́A�u�{���ɂ����Ȃ́H�v�Ƌ^��Ɏv�����̂����Ȃ��Ȃ��B
�@����A����n�����珑�̒��Ɂu�r�X�P�[�p�Œ��v�����D�̐ςׂ݉̏������C���ł��߂ɂȂ����B�̂Ă�̂͂��������Ȃ��B�����ŁA�C���ɂ��������������˂ďĂ����Ƃ���A�E�}�C���َq���ł����������B�r�X�P�[�p�ɂ��Ȃ�Ńr�X�P�b�g�Ɩ��Â���ꂽ�v�Ƃ�����|�̂��Ƃ������Ă������B�������A���̃r�X�P�b�g�N�����͖��炩�Ɍ�肾�B����́A���}�Ђ̕S�Ȏ��T�Ȃǂ������Ă݂�����ɂ킩�邱�Ƃ��B
�@�������A���������ԈႢ�E�v���Ⴂ�́A�N�������X�ɂ��ĔƂ��������B���ׂ������肾�Ƃ킩�邱�Ƃ����邪�A�o�����킩�炸�A���f�ɖ������Ƃ����Ȃ��Ȃ��B���̂�������ނ�ɂȂ��āA�s�m���Ȓm�����]�݂������Ɏc�邱�ƂɂȂ�B
�@���珑�Ƃ����^�ʖڂȖ{�Ȃ�A���߂Ă��̏o�T�Ȃ�A�T���Ȃ���A�����Ă����ė~�������̂��B
�@�Ƃ���ŁA�ŋ߁A�����u�[���炵���A�e���r������ƁA�����W�E�����W���]�~�����^�����g�������B
�@���Ƃ��A
�@�������ŏ��m���]��œ����X�ɂ��Ă��܂����A���������Ȃ��̂ŏ`�̒��ɂ��ꂽ�̂��u�������`�v�B���ꂪ�u�P���`���`�v�ɂȂ����B
�@����́A�N�����m���Ă��鎖���N�����b�̈�B�������A�w���{����厫�T�x�Ȃǂɂ͈Ⴄ���������Ă���B
�@�ǂ����A���l����悤�Ȗʔ����b�ɂ́A�����������̂������B�^�U�̒��͂��Ă����A�����ɂ܂�邱�̎�̃n�i�V���A���������Ă݂悤�B
�@�@�S�^�S�^
�@�����l�̍��m�u��������i��������ӂ˂��B�Y�����J�j�v�����q�������ɏZ�����B�������A�b�����t�������ꂾ�����̂ŁA���������Ă���̂����{�l�ɂ͂킩��Ȃ��B�������̙Y���a���̌������Ƃ͂킩��Ȃ��A�Ƃ����̂ŁA������u�������S�^�S�^�v�ƌ����̂��������i����12�`�����l���w�A�h�X�b�N�x2013�N6��22�������A�u�k���q�v�j�B
�A�@�K�����h�E
�@�̂̂����͍L��ȕ~�n��L������̂������A���̒��ɋ���Ȏ����������ۂ�ۂ�z�u����Ă����B������A�ՎU�Ƃ��Ă���L�l���u�K�����h�E�i�����E���j�v�ƌ����̂��Ɓi�����}�j�A�����C���閟�ˎt�̃����C���V�̘b�B�ԑg���͎��O�j�B
�B�@�_�C�i�V
�@�����̑�����Ȃ��ƁA���肪�����������݂��ڂ炵��������B���ꂪ�u�䖳���v�̌ꌹ�Ƃ����i�o���s���j�B
�C�@�����ׂ͖���
�@���ł������͏@���@�l�ŁA�Ő���D������Ă���B�M�҂����������͂܂��܂����������Ă���B������A�u�M�ҁv�Ƃ�����������������ƁA�u�ׁi�����j�v����Ƃ��������ɂȂ�̂��i�o���s���j�B |
|
|
|
| 2013�N7��6���i�y�j |
| �����͒�R�̃V���{�� |
�@�����̒����V���i�����j��ǂ�ł���ƁA���挴��҂̏�A���L�����u�t�����`�V�T�v�Ƃ����J�N�e���ɂ��ď����Ă���R�������ڂɂƂ܂����i�u���ނɂ͗��R�i�킯�j������v�j�B
�@���̃J�N�e���́A�h�C�c���S�������̃t�����X�̃����b�R��ɂ����f��u�J�T�u�����J�v�ɏo�Ă���B�J�N�e���̖��O�́A��ꎟ���E���Ŋ����t�����X�̂V�T�~���C�ɗR������B�h�C�c���ł��ӂꂩ����J�t�F�̒��ŁA�h�C�c�ɑ����R�̏�����Ƃ��Đ�������Ă���̂��B�����g�͉��˂Ȃ̂ŁA���̕��ʂɂ͑S���s�ē������A�J�N�e�����͎̂��݂̂��̂��B�鎁�ɂ��u�����̓W���t�B�Y�Ɏg���Y�_���V�����p�[�j���ɑウ�Ė������B�A�����̉₩���ɃR�N�ƊÂ݂������A�Ă炵�����Ȉ�t�ƂȂ�v�������B
�@
�@���������A���̉f��ɂ̓h�C�c�ɑ����Ӎ��g�̎d�|�����l�X�Ɏ{����Ă����B�f��̃��X�g�߂��ŁA�x�@��������r���S�~���Ɏ̂Ă�V�[�����������B���̎��̖��O�́u�r�V�[�v�B�h�C�c��̉��̃t�����X���S�����i�r�V�[�����j�̖��O���B |
|
|
|
| 2013�N6��22���i�y�j |
| �U���Q�Q���͊I�̓� |
�@���̊I���y���U���Q�Q�����u�I�̓��v�ƌ��߂��Ƃ����B����ɂ͓�̗��R������B���̈�́A�I�����U���Q�Q������n�܂邩��Ƃ������ƁB������́A�u�����������v�̌\���\�ŁA�u���v���u���v���琔���ĂU�ԖځA�u�Ɂv���Q�Q�Ԗڂ����炾�������B
�@�Ƃ���ŊI�Ƃ����A�v�������Ԃ̂̓t�����V�X�R���U�r�G�����B���鎞�A�U�r�G�����\���˂��C�ɗ��Ƃ������Ƃ������āA������I���E���ē͂����Ƃ�����b������B��������A�I�ƃU�r�G�������т����B
�@���Ȃ݂ɁA���{�j�̋��ȏ��ɍڂ��Ă���L���ȃU�r�G���̏ё�������Ă݂悤�B���̑O�Ō������Ă��闼����݂�ƁA�܂������I�̎p��\�����Ă���ł͂Ȃ����B
|
|
|
|
| 2013�N6��16���i���j |
| �������̂��݂Ă���̂Ɂi���̂R�j |
�@���߂������������A�ޗǂ̓��厛�啧�a�̒��A�啧�̂����߂��ɁA�W�{���i�����j�̃A�Q�n�`���E�̍�蕨�������Ă���B�����Ȃ̂�����A���R�E�ɂ���`���E�͂U�{�����ӂ����B�Ȃ��A�W�{���Ȃ̂��낤�H
�@�l�������Ƃ͂�����ł�����B�P�ɐ���҂��ԈႦ���B���ۂɂW�{���̃`���E�����āA��������f���ɂ����B���̐��E�ł����y�ɂ���`���E�͂W�{���ƍl����ꂽ�c�ȂǂȂǁB�C���^�[�l�b�g�������ƁA���낢��Ȃ��Ƃ������Ă���B���߂͑��l���B
�@�Ƃ���ŁA���̂W�{���̃A�Q�n�`���E�����āA���锭���̃q���g���O���l�������B�X�C�X�̐����w�҃Q�[�����O���m���B�ʏ���Q�{�����������`���E���������m�́A�u�����̑̂̃p�^�[�������肷���`�q�����݂���̂ł́H�v�ƍl�����B�̂��ɂ��̈�`�q�����A�u�z���I�{�b�N�X��`�q�v�Ƃ������O�������B
�@�W�{���̃A�Q�n�`���E�́A����܂ŋC�̉����Ȃ�قǑ吨�̐l�����Ă����͂����B�����W�{���̃`���E�����Ă����l�тƂ͐��̐��قǂ����̂ɁA�Q�[�����O���m�̂悤�ȓƑn�I�ȍl���������l�́A����܂ň�l�����Ȃ������B����͖{���ɕs�v�c�Ȃ��Ƃ��B
�@���ӎ�����Ɏ����Ă��Ȃ���A�u����ǂ��������v�Ƃ������ƂȂ̂��낤�B
|
|
|
|
| 2013�N6��9���i���j |
| �������̂��݂Ă���̂Ɂi���̂Q�j |
�@���ꂪ�Ⴆ�A�Ƃ炦�����قȂ�B����́A���i�Ɍ���Ȃ��B
�@�w�����q�x��226�i�́A�z�g�g�M�X�̖����ɂ��ď�����Ă��邪�A�����[���Ƒ����������Ƃł́A���̐��̂Ƃ炦�����܂�ň���Ă����B
�@��֍s����������A�c�A�������鏗�������̎p��ڂɂ��������[���B���̎��A�ޏ��������̂��Ă����c�A���̂��u�����ɂ��S�J���v�Ə����Ă���B
�@����́A�_�����������̂悤�ɁA�u�قƂƂ��������ƂȂ߂������v���Ă������炾�B
�u�قƂƂ����A����A�����B������Ă����A��͓c�A�����i�قƂƂ����̂��������A�c�A�������Ȃ��Ă͂Ȃ�ʁj�v
�@�����[����M���w�ɂƂ��ẮA�z�g�g�M�X�̐��́A�Ă̓�������������̂Ƃ��Ęa�̂Ȃǂœ���݂̂�����̂������B�������A�_�������ɂƂ��ẮA��������ȓc�A���J���̊J�n�𑣂��������������̂��B
|
|
|
|
| 2013�N6��8���i�y�j |
| �������̂��݂Ă���̂Ɂi���̂P�j |
�@�������i�����Ă��A�j���Ŋ��������Ⴄ�ꍇ�����邻�����B
�@���Ƃ��A�����^���[�����i�߂Ă��A�j���͂����ɖO���Ă��܂��Ƃ����B����ɑ��A�����͂P���Ԃł����C�Œ��߂Ă�����Ƃ����B������A�j�����A��i�ɖO���ēy�Y�����ł����F���Ă悤���̂Ȃ�A�u�{���ɂ��Ȃ�������A���}���`�b�N�̌��Ђ��Ȃ��l�I�v�ƌ��߂���ꂩ�˂Ȃ��B�̕������b�Ȃ̂ŁA�ו��͖Y��Ă��܂������A������������́A�j���Ō�����F�̎�ނ��Ⴄ���ƂɋN������炵���B
�@�j���ɂ�鍷�ق���ł͂Ȃ��B���̐l�̒u���ꂽ�����ɂ���āA�������i�ł����������Ⴄ�ꍇ������B
�@����ƂɂȂ��̂ŏ������m�F�ł��Ȃ����A�w������ɓǂO�q�i�݂��킩���j�̖{�i�w�V�n������_�x�������낤���H�j���炻�̂��Ƃ���������B�O��͐M�B����ɂ��̖����c���A�n������̑��l�҂��B
�@�O���{�A���v�X��w�i�Ƃ����_�����i���A�u�������Ȃ��v�Ɗ��������߂Č��ɂ���ƁA���ɂ����j�Ɂu����ȕ��i�A���������ƂȂ�����̂��I�v�ƌ����ɔے肳�ꂽ�A�Ƃ����̂��B
�@���̕ӂ̋L���͒肩�łȂ��̂ŁA���̎�|�Ȃ�Ȃ����x�ł̂��Ƃ��b�����悤�B
�@���Ƃ��A���n�x�ɗ��s�ɍs�����Ƃ��悤�B�t���}���A�c����������������n�x���������s�҂́A�����炭���̐�i�Ɋ������邱�Ƃ��낤�B
�@���n�͌��݁A�u�n�N�o�v�Ɣ�������B�������A���Ƃ́u�V���E�}�v�������B�t�A�R�̐Ⴊ�Z���n�߂�ƁA��R�ɔn�̎p�������n��������Ă���B�����Ȃ�ƁA�c�ނ̑�~�i���납�j����Ƃ��n�܂�B�����ŁA���̎R�́A�u��~����Ƃ��n�܂鎞����m�点��n�v�Ƃ����Ӗ��ŁA�u��n�v�x�Ɩ��Â���ꂽ�B�̂��ɔ����́u�V���E�}�v�Ɉ��������āA�u���n�v�Ə�������Ă��܂������܂ł����u�n�N�o�v�ƂȂ����B
�@�_��Ƃ��ߍ�����������ɂ́A�n���_���ɂƂ��āA���N���܂��d�J�����n�܂鎞�����}�������Ƃ��������i�Ƃ��āA���W����C�����ɂ����镗�i�������킯���B�_��Ƃ��n�܂鍠�̔��n�x��������Ǝv�����̂́A�n���_���̘J��Ɋւ��������Ȃ������ҁi�悻���́j�̖ڂ��������炾�B
�@�Z�p�̐i���ŏd�J��������A�H����H�킸�̂����ꂪ�Ȃ��قǂɐ������������サ�Ȃ���A���i���y���ނƂ����S�̂�Ƃ�����܂�Ȃ��̂��B
|
|
|
|
| 2013�N6��1���i�y�j |
| ��������̓V�c�̓}�U�R���H |
�@�e���r�����Ă݂�ƁA�u���ł���I�v�̗��s��ō��ꐢ���r���Ă��铌�i�\���Z�̗яC�����A�o���G�e�B�[�ԑg�ɏo�Ă����B�ю��̞H���A�u�j�q���吶�̂قƂ�ǂ̓}�U�R���ł���v�B
�@�l�I�����Ȃ̂��낤����A���吶�Ƀ}�U�R�����������ǂ����A���ۂ̂Ƃ���͂킩��Ȃ��B�������A���Ȃ��Ƃ��A��������̓V�c�̓}�U�R�������������悤���B
�@���͐ۊ������B�ې��E�֔��ƂȂ铡�����́A������������čc�q�܂��A�����̓V�c�̊O�c���ƂȂ��ĉe���͂��s�g�����B�������A�V�c�̕�e�̉e���͂��A����܂��傫�������B
�@�V�c�̕��e�ł����c�́A���ʌ�A��������{��O�ɏo�邱�ƂɂȂ��Ă����B����V�c�ȗ��̊���ł���B���鑾��V�c�̕ςɂ�����u����v�̂悤�ȍ���������邽�߂̑[�u�������B������A���ʂ���Ə�c�́A���q�ł���V�c�ƕʋ������̂ł���B
�@�������A�V�c�̕�e�́A�q�̓V�c�����ʂ���ƓV�c�ƂƂ��ɓ����ɏZ�B���ʂ̋V�ɍۂ��Ă͓V�c�ƂƂ��ɍ�����i�����݂���j�ɂ̂ڂ�A�V�c���c�����ɂ͌㌩���A�����͕�e�̌�O�ɂ����čs��ꂽ�B
�@����ȗL�l����������A�ۊւ̔C���ɍۂ��Ă��A�V�c�̔��f�͕�e�̈ӌ��ɂ���č��E���ꂽ�B�~�Z�V�c���������ʂ��֔��ɔC�����͕̂�e���q�i���ʂ̖��j�̈▽�ɂ����̂��������A���V�c����������������ɔC�������͕̂�e�F�q�i�����̎o�j�̖��߂ɋt�炦�Ȃ��������炾�B
�@��e�̎����������������邱�Ƃ́A�����̓V�c�ɂƂ��āA����̃}�U�R�����吶�i�H�j�̔�ł͂Ȃ����������m��Ȃ��B
�y�Q�l�z
�E�Ð��ޒÎq�w�ۊ����@�V���[�Y���{�Ñ�j�E�x2011�N�A��g�V���AP.25�`26
|
|
|
|
| 2013�N5��30���i�j |
| �w���X�s�[�`�W�x�̃���������Ă݂��i���a�̐��A���̂S�j |
�@�w��㑍����b�̖��X�s�[�`�W�x�́A���̂܂܂ł͗��p���Â炢�B�Ȃ��Ȃ�A���̓��e�\�����u������d�Y�w��W�X�Վ��鍑�c��{�����j�����x�i���a�Q�O�N�j�v�Ƃ������x�����炾�B����ł́A��̓I�ȓ��e�͂킩��Ȃ��B�����ŁA�w���X�s�[�`�W�x�̓��e�̊ȒP�ȃ������쐬���Ă݂��B
�@�������A���̃J�Z�b�g�e�[�v���̂������Ă���l�͏��Ȃ����낤���i���łɐ�Łj�A�킪�Ƃ̃J�Z�b�g�e�[�v���R�[�_�[����ꂽ��A�e�[�v���ꂽ��ł�������A���̃��������p�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�@���������������N���A�ɂ����w���X�s�[�`�W�x���A�b�c���l�o�R�ɂ��čĔ̂��ė~�������̂��B�ł���A����������āB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y���z��1�`17���㊪�A��18�`37�������ɏ����B�\���́u�N�v�͂��ׂď��a�B
| �� |
�� |
���@�@�@�@�� |
�N |
���@�@�@�@�� |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
�c���`��
�l���Y�K
����X���Y
���{�@�B
�֓��@��
���c�[��
�L�c�O�B
�ёL�\�Y
�߉q����
�߉q����
�����u��Y
�����M�s
�ē�����
�߉q����
�����p�@
���鍑��
��؊ё��Y
|
�����ɍ���
�o�ϓ�ǂ̑ŊJ�ɂ���
�͂邩�ɓ��{�����ɍ���
�V���t�̐Ӗ�
��펞�̊o��
���I���ɍۂ���
��70�鍑�c��{�����j����
�������N�ɍ���
��71���ʒ鍑�c��{�����j����
��73�ʏ�鍑�c��{�����j����
�喽��q����
�喽��q����
��75�ʏ�鍑�c��{�����j����
�I��2600�N�L�O���T�j��
��ق�q������
�ނ݂đ�قɉ������
�喽��q���āi�k�b�j |
3
4
5
7
7
11
12
12
12
13
14
14
15
15
16
19
20
|
���ʑI���@�ɂ��ŏ��̑��I���ɗՂ��
�����ւ̕K�v��i����
�����h���C�R�R�k���ɂ��ĕ�
���B�������ƌo�ϕs���̔҉}��
�u������v�v�Ō��݂̓�ǂɂ�����
�I���ɂ��u���E�̏v������
�c���𒆐S�ɍ����̈�v�c���A�s�ޓ]�̌���
���}�����ɂ��4�J���őސw
���E���a��i����A����ɓ����푈�u��
�u�������{��Ύ�Ƃ����v�i�߉q�����j
���Ƒ������̐����������ē��O�e�ʂ̍������s
�u�V�������݂̌��Ɓv�u�鍑�����̐i�W�v
�������̉�����簐i
�鍑�b���ɑ���u�V�c�É����v
�����V�����̌��݁A���h��F�A�s����
�V�ƍc��_�̎q���ł���V�c�͉F����̐_
�u���̎r�݉z���č��^�̑ŊJ��簐i�c�v |
18
19
20
21
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
|
���v�����F
������d�Y
�g�c�@��
�ЎR�@�N
���c�@��
�g�c�@��
���R��Y
���X�R
�݁@�M��
�݁@�M��
�r�c�E�l
�r�c�E�l
�����h��
�c���p�h
�O�ؕ��v
���c���v
�啽���F
��ؑP�K
���]���N�O
���]���N�O
�|���@�o
|
��88�Վ��鍑�c��{�����j����
��89�Վ��鍑�c��{�����j����
��90�Վ��鍑�c��{�����j����
��1���ʍ���{�����j����
��2�ʏ퍑��{�����j����
��20�Վ�����M�\������
��21�ʏ퍑��{�����j����
�g�t��̋L�҉
��27�Վ�����{�����j����
�V���ۏ���̈��A
�����{���v��ɂ��āi�k�b�j
��40�ʏ퍑��{�����j����
��49�Վ�����M�\������
��70�Վ�����M�\������
��74�Վ�����M�\������
��84�ʏ퍑��E�O�c�@�{��c��\����ւ̓���
��88�Վ�����M�\������
��93�Վ�����M�\������
��108�ʏ퍑��{�����j����
�����T�~�b�g�����L�҉
��111�Վ�����M�\������ |
20
20
21
22
23
29
30
31
32
35
35
37
40
47
49
53
54
55
62
61
62
|
�I��Ɏ���o�߁A���ǂɓ������Ă̌���
�O�c�@�c���I���@�̉����A�����I�����x�̔p�~
���@�����A����I�����v�̎��s
�V���@�̏���A���x�����`�̐��̊m��
���ǂƖ����̈���ɓw��
����7�J���K�₩��A���A���ێЉ�ւ̕��A
���{�̎����̒B���A���啽�a�O���A���@����
����O���ƐϋɌo�ϐ���A����
���ĊW�̉��P�i���Ĉ��ۂ̉���j
�u���ĊW�̑�2���I�ɓ������v
�u10�N��������i�����́j2�{�ȏ�Ɓc�v
�u�^�̕����͊z�Ɋ����Č��݂��ׂ����́v
�u�����������c����������̔��W�̊�Ձv
���{�����_
�����ϗ��̊m���A�Љ�I�s�����̐���
���ł����������̕����o�ϔg�y���ʂ���
�����̌��ˑ��̐��̉��P
�����ŋ��̂�����Ȃ��I�����x
��㐭���̑����Z�A��A�̉��v
�A�W�A�E�����m�n��̈���Ɛi���ɍv��
�ӂ邳�Ƒn���_ |
|
|
|
|
| 2013�N5��29���i���j |
| ������b�̃X�s�[�`���i���a�̐��A���̂R�j |
�@ ���āA�킪���̗��j�ł���B�����푈����A�W�A�E�����m�푈�ւƁA�푈���D��������ɂ�A���̌�����͐_������I�ŁA�ߑs���Y�����ӔC�Ȍ��t�����X�Ɣ�яo���悤�ɂȂ�B���������o���Ă݂悤�B
�u�����Q�U�O�O�N�A���͂��܂����Đ킢�ɔs�ꂽ���Ƃ�m��܂���c�L����������������āA���ɕ��ɏ}����̎��͍��ł���܂��B�v�i�����p�@�A���a�P�U�N�j
�u�V�c�É��͉F����̐_�ł��邱�ƍ�����\���܂ł��Ȃ��c�v�i���鍑���A���a�P�X�N�j
�u�������ɑ喽���~�����܂����ȏ�A���͎��̍Ō�̂�����ƍl���܂��Ɠ����ɁA�܂������ꉭ���N�̐^����ɗ����Ď��ɉԂ��炩���A�������N�͎��̎r�i�����ˁj�݉z���č��^�̑ŊJ��簐i����邱�Ƃ��m�M���܂��āA�ނ�Ŕq��v�����̂ł���܂��B�v�i��؊ё��Y�̑喽��q���Ă̒k�b�A���a�Q�O�N�j
�@�����̌��t���A�Ƃ������{�̍ō��ӔC�҂̌�����o�Ă������ƂɁA�낵����������B����Ȍ��t�������ɕ��������悤�Ȏ���ɁA��x�Ƃ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
|
|
|
|
| 2013�N5��28���i�j |
| �푈���n�߂����R�i���a�̐��A���̂Q�j |
�@�J�Z�b�g�e�[�v���Ă݂�ƁA�������悭�Ȃ��B�J�Z�b�g�e�[�v�Ƃ����}�̂̂�������łȂ��A�Â�����ɘ^�����ꂽ�����ɖ�肪����̂��낤�B
�@�������A�������ɂ����Ƃ��A�u�I���K�叫�v�c���`�����h���R�k���S���̎�Η玟�Y�A�u�j�q�̖{���v�̖��䎌�ŗL���ȕl���Y�K��܁E������ŝ˂�錢�{�B�ȂǁA���ȏ��̎��ʂ̏�ł������ڂɂ�����Ȃ��ނ炪�A�m���ɂ��̐��ɑ��݂����Ƃ������Ƃ�������������B
�@�ނ�̐����ɂ��A��肫��Ȃ��Ȃ�̂́A�����̍��̎w���҂������A���ł́u���ە��a�v��W�Ԃ��Ȃ�����A�푈�ɓ˓����Ă����Ƃ����������B���������̐l������邽�߂ɁA�����̐l�тƂ̐l����j��u�푈�v�Ƃ������Ɏ�i�ɑi���邱�Ƃ��A�ނ�͂ǂ̂悤�ɗ������Ă����̂��낤�B
�@�l�ނ̗��j���ӂ肩�����Ă݂�ƁA�e�����푈���n�߂鎞�̌����́A���܂��āu���ە��a�̂��߁v�Ƃ��u���q�̂��߁v�Ƃ��ł���B�ǂ̍����A���`�̃q�[���[�ʁi�Â�j���Đ푈���n�߂Ă���B�푈�ɂ́A�V���b�J�[��f�X�g������i�Â����Ă킩��Ȃ����ȁH�j�̂悤�ɁA�u���������n���E�����m�^���j�����V�e�C���m�_�v�ȂǂƓ��X�Ƃ����Ă̂���A�킩��₷�������͑��݂��Ȃ��B���ꂼ�ꂪ�A�푈�Ɏ��炴��Ȃ��u�����ȗ��R�v�Ƃ������̂�U�肩�����Ă���̂��B |
|
|
|
| 2013�N5��27���i���j |
| �J�Z�b�g�e�[�v�����o�����i���a�̐��A���̂P�j |
�@���N�͕����Q�T�N�B���������E�����ɂ��A�u���a�͉����Ȃ�ɂ���v�Ƃ��������������Ƃ������B�v���Ԃ�ɁA�u���a�̐��v���Ă݂��B
�@���o�����̂́A�u���a���N�E����X���Y���畽�����N�E�|���o�܂ŁA���j�������j�����̓����v�Ɩ��ł����w��㑍����b�̖��X�s�[�`�W�x�i�m�g�j�T�[�r�X�Z���^�[�ҏW�E����A�ɓ����ďC�A�i���[�^�[���c�K�q�B�������́i���j���o�o�ŁB���ݐ�Łj�B���݂ł͂قځu���v�ƌĂ��ł��낤�u�J�Z�b�g�e�[�v�v�Q�{�ł���B�������A�ʓI�ɂ��R���p�N�g�ɂ܂Ƃ܂��Ă���A���ꂾ���ŗ�㑍����b�̃X�s�[�`�ɂ���́u���̏��a�j�v�ɂȂ��Ă���B
�@���̂ق��A�킪�Ƃɂ́w���a�̋L�^�|�����̂T�T�N�|�x�i�m�g�j�ďC�A�P�X�W�O�N�A���������傤�����j�Ƃ����J�Z�b�g�e�[�v�P�O���́u�^���W�v�Ɓu�ʐ^�W�v����Ȃ鍋�ؔł�����B�������A�B��쓮���Ă��鏬�^�J�Z�b�g�e�[�v���R�[�_�[�����悤���̂Ȃ�A�e��S�~�ƂȂ��Ă��܂����낤�B |
|
|
|
| 2013�N5��20���i���j |
| �H�@�ł��H |
�@���q���{�̂R�㏫�R�������̘a�̏W���w���Řa�̏W�i�����킩���イ�j�x�Ƃ����B�悭�ԈႦ�āu���Łv���u����v�Ə����Ă��܂��B�u����v�ł́A���̃J�^�}�����B
�@�w���Řa�̏W�x�́u���v��GOLD�ł͂Ȃ��A���q�̂��ƁB���̋����Ƃ����B
�@�u�Łv�͂���̖̂��ƁB��������A���t�i�������j�E�����i�����Ӂj�E���ہi�����فj���b���̍ō��ʂŁA������O���i�����j�Ƃ������B�O���̍����߂�̂ɁA����ɂR�{�̂����A�����Ƃ��납��A�O���̉ƕ����u�Ŗ�v�ƌĂB�킪���ł́A�O���ɑ�����b�E����b�E�E��b�����āA�u�Ŗ�v�����̓����Ƃ����B
�@�����͉E��b�������̂ŁA�u���q�̞Ŗ�̘a�̏W�v���Ȃ킿�w���Řa�̏W�x�Ɩ��Â����킯���B
�@���Ȃ݂Ɏ��ł́A�����i���������j�̍��i����j��A���Ē�߂��B�����͋㋨�������̂ŁA������㞙�i���イ���傭�j�܂��͞��H�i���傭��j�Ƃ������B�u�Ŗ垙�H(�������傭��)�v�Ƃ����ΎO���E�����ُ̈̂ł���A���E�ł̍ō������̂��Ƃ��ƂȂ��Ă���B |
|
|
|
| 2013�N5��13���i���j |
| �Y�f�P�S���āA����Ȃɏ��Ȃ��́H�i���ː��Y�f�P�S�A���̂R�j |
�@�q�ǂ������̉Ȋw�G���Ɂu�T�������S�ȁE�T�Ԃ�������v���X�v16���i2006�N7��23�����s�A�����V���Ёj������B�q�ǂ������̍ŋ߂̐}�ӗނ����������A���ꂪ�ӊO�ƍ����x���ŁA�������킩��₷���B�{���̓��W���u���̂̌Â��𑪂邱�Ƃ��ł���́H�v�B
�@���������ƁA�u���R�E�ɑ��݂���Y�f�P�S���āA����Ȃɏ��Ȃ��́I�v�ƁA�C���X�g�őN�₩�ɐ�������Ă���B���̎G���ɂ��ƁA���R�E�ɂ���Y�f�̗ʂ�10�g���g���b�N���ύڂ��鍻�̗ʂɂ��Ƃ���ƁA10�g���g���b�N100��̂���99�䕪�̍����Y�f�P�Q�A�P�䕪�̍��̂قƂ�ǂ��Y�f�P�R�B���̎c��P�䕪�̂�����100�����̂P���Y�f�P�S�Ȃ̂��Ƃ����B���̂��Ƃ͂Ȃ��B10�g���g���b�N100�䕪�̍��̒���1���������Y�f�P�S�Ȃ̂��B���̑傫���͂킸����1mm�I
�@���ː��Y�f�P�S�N�㑪��@�Ƃ����̂́A������ۂ��������Ȃ��Y�f�P�S�𑪒肷��̂��B�Ȋw�Z�p�̔��W�̂������Ɋ��S����ƂƂ��ɁA���̑���@�̐M�ߐ��ɉ��^�I�ɂȂ�͎̂������H |
|
|
|
| 2013�N5��12���i���j |
| �{���ɐ����������́H�i���ː��Y�f�P�S�A���̂Q�j |
�@���������ʂƁA��_���Y�f�̌`�ő̓��Ɏ�荞�܂ꂽ�Y�f�P�S�́A����ȏォ�炾�̒��ɓ����Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��̂�����A�̓��̒Y�f�P�S�̗ʂ͑����Ȃ��B������A��Ղ���o�y�����Y�f���܂╨�i���Ƃ��A�Y���āj������A���̒��Ɋ܂܂��Y�f�P�S���ǂ̂��炢�c���Ă��邩�ʼn��N�O�̂��̂��킩��̂��B
�@������@�́A�╨��R�₵�ē�_���Y�f�ɂ��A����ɍ��d���������ĒY�f�P�S��������ۂɏo�����ː��𑪒肷��B���̗ʂ��A���݂̂��̂̔��������Ȃ���A5730�N�O�̂��̂Ɣ���ł���B
�@�������A���̕��@�ɂ͂��낢��Ǝ�_������B
�@���R�̂��ƂȂ���A�Ί��K���X�ȂǁA���Ƃ��ƒY�f���܂܂Ȃ����̂͑���ł��Ȃ��B�@�N�オ�Â��Ȃ�Ȃ�قǁA�╨�ɂӂ��܂��Y�f�P�S�̗ʂ����Ȃ��Ȃ�킯������A���܂�ɂ��Â��N��̂��̂��A�Y�f�P�S�����ʉ߂��đ���Ȃ��B
�@�܂��A�Y�f�P�S���܂�ł��Ă��A�╨�̂ǂ̕������c�邩�ɂ���Ă͑傫�Ȍ덷����\��������B���Ƃ��A��N���ő������╨���o�y�����Ƃ��悤�B���̈╨���؍ނ̐c�t�߂̂��̂��A�N�ւ̊O���t�߂̂��̂��A�ǂ��炩���c��̂͋��R�ł���B���̏ꍇ�A1000�N���̌덷��������\�������낤�B
�@����ɂ́A5000�N�O�A1���N�O�ƁA��Ɏ��R�E���ǂ̔N��ɂ����ʂ̒Y�f�P�S�Ŗ�������Ă����Ƃ����ۏ͂ǂ��ɂ��Ȃ��B
�@���������āA����ɂ́A��Ɍ덷�����܂Ƃ��Ă���͂����B |
|
|
|
| 2013�N5��11���i�y�j |
| �P�Q�C�P�R�A�P�S�͂����ĂP�T�͂Ȃ��i���ː��Y�f�P�S�A���̂P�j |
�@�l�Êw�̔N�㑪��@�̈�Ƃ��ďo�Ă�����ː��Y�f�P�S�N�㑪��@�B���́u�Y�f�P�S�v�́u�P�S�v�Ƃ����͉̂����낤�B
�@����́A���q�j���\������z�q�ƒ����q�����킹�������B
�@�����������R�E�ɂ͂R��ނ̒Y�f���q�����݂���B�Y�f�P�Q�C�Y�f�P�R�A�Y�f�P�S���B���̂R�̒Y�f�́A���q�j�������Ă���z�q�̐����ǂ���U����B�z�q�̐��������Ȃ̂ŁA���ׂĂ������Y�f���B
�@�Ⴂ�͒����q�̐��ł���B�Y�f�P�Q�͒����q�U�A�Y�f�P�R�͒����q�V�A�Y�f�P�S�͒����q���W�Ȃ̂��B
�@�P�Q�Ƃ��P�R�Ƃ��P�S�Ƃ��������́A�z�q�ƒ����q�̘a�������Ă���B���Ȃ킿�A�Y�f�P�Q�͗z�q�U�{�����q�U���P�Q�A�Y�f�P�R�͗z�q�U�{�����q�V���P�R�A���Ȃ����Y�f�P�S�͗z�q�U�{�����q�W���P�S�Ƃ����킯���B
�@���̂����A�z�q�ƒ����q�����킹�ĂP�S���Y�f�P�S�ɂ́A�ʔ�������������B���ː����o���Ȃ���A���̊����ł����Ă����A�z�q�V�E�����q�V�̒��f���q�ɕς���Ă��܂��̂��B5730�N�ł��Ƃ̗ʂ̔����ɂȂ�A�P��1460�N��ɂ͂���ɔ����i���Ƃ̗ʂ�1/4�j�ɂȂ�B�Y�f�P�S�́A����Ύ��R�E�̎��v�Ȃ̂��B
�@���ː��͋@�B�ő��肷�邱�Ƃ��ł���B�Y�f�P�S�̂��̐����𗘗p����A�l�Êw���ΏۂƂ���悤�ȌÂ��N��̈╨�����̂��̂��A���肷�邱�Ƃ��ł���͂����B���ꂪ�A���ː��Y�f�P�S�N�㑪��@�̍l�������B
|
|
|
|
| 2013�N5��9���i�j |
| �v���Ή����ɗ������� |
|
�@���֏��ŁA����������{�֏��n���ꂽ�ɓ������ł��������A�O�����Œ����Ԋ҂�]�V�Ȃ����ꂽ�B�Ԋ҂����₢�Ȃ�A�ɓ������̓�[�i������u�֓��B�v�B�����̒���̊C���̏I�_�ł���R�C�ցi��������j�̓��ɂ���y�n�̈Ӂj���A��������̑d�Ƃ����`�ŁA���V�A������肵�Ă��܂����B���ꂪ���I�푈�������N���������̈�ɂȂ����B
�@���āA���̎����V�A�������ƂƂ��ɑd������A�i�������j�́A���V�A��̂c���������i�_���j�[�j�ɗR�����Ă���B
�@�쉺����i��ցA�C�ցj���Ƃ郍�V�A�́A���̎��A�����S���암�x���i�n���r���E�����ԁj�̕~��������ɓ���Ă���B����́A���[���b�p�����V�A���牄�X�Ɓu������n�i�V�x���A�j�v�𓌂Ɍ������A�V�x���A�S�����瓌���S����쉺���A���ɒg�C�i���C�j�ւ̏o�����m�ۂ������Ƃ��Ӗ�����B�����Ƀ��V�A�́A�������m�̂͂���ɁA���ɔߊ肾�����s���`���䂪���̂Ƃ����̂ł���B
�@�c��j�R���C�Q���͂��̒n���c���������Ɩ�������ƁA�������ɏ��`���݂ɏ��o�����B�c���������́A�u�����v�̈ӁB���Ȃ킿�A���V�A���y�������Ɋm�ۂ����s���`�A�Ƃ����킯���B���V�A��1902�N�܂łɁA1000�g�����̑D����25�ǂ��W���ł���u���������������B�c���������͋���ȍ`�p�{�݂������R�f�Ս`�Ƃ��Ĕ��W�����B���V�A�����z������A�ˁA�s�X�n�𑽂��̃��V�A�l�B��舕����Ă����B
�@���̌�A���I�푈�œ��{�R���c�����������̂���ƁA1905�N2���A�ɗz����R�ߒB��R���ɂ���āA���̒n���u��A�v�Ɖ��́B�_���j�[�̉����A�����Ɏʂ����̂ł���B
�@�|�[�c�}�X���ŁA�ɓ������y�ђ��t�ȓ�̓S���d�،������{�ɈϏ������ƁA��A�ɂ͑����̓��{�l���n�q�����B���c�h�ꎁ�́w�����E���I�푈�x�i2007�N�A��g�V���AP.224�`5�j�ɂ��ƁA��A�ݗ��M�l�͓��I�푈���O��1904�N1���ɂ�307�l���������̂��A1911�N���ɂ�8798��2��9775�l�ɋ}�����Ă���B
|
|
|
|
| 2013�N5��5���i���j |
| �����Ɠd�C�̊W |
|
�@�I���O�V���I���A���݂̃g���R�����Ɉʒu���Ă������f�B�A�Ƃ������ŁA���E�ŌÂ̒����ݕ������s���ꂽ�B
�@���f�B�A�̋��݂́A�o�N�g���X��̉͏����瓾��ꂽ�嗱�̎��R���i���Ƌ�Ƃ̎��R�����j�������ɂ��Ă����B���̎��R���̐F���A�Ñ�M���V�A�����߁i�G���N�g�����j��A�z�������̂ŁA�ݕ��̓G���N�g�����i�G���N�g�����݁B���ߋ��j�ƌĂꂽ�B
�@�Ƃ���ŁA���߂ɂ͕z�Ȃǂł�����ƐÓd�C��тсA�����Ȏ��ЂȂǂ��������鐫��������B16���I�A�Ód�C���������Ă����C�M���X�̃E�B���A�����M���o�[�g�́A�������߁i�G���N�g�����j�̐����ɂ��Ȃ݁A�d�C���G���N�g���j�N�X�Ɩ��������B
�@���E�ŏ��̒����ݕ��G���N�g�����A���߂̃G���N�g�����A�d�C�̃G���N�g���j�N�X�́A�����ꌹ�Ȃ̂��B
�y�Q�l�z
�E���{��s���Z�������ݕ������قg�o�u�ݕ��̎U�����E��54�b�@�G���N�g�����Ɠd�q�}�l�[�v�Ȃ�
|
|
|
|
| 2013�N4��29���i���j |
| ���~�D�͏����̋��� |
�@2000�N�ɉ���T�~�b�g���L�O���Ĕ��s���ꂽ���~�D�����B���݂́A����������A�قƂ�Ǘ��ʂ����邱�Ƃ͂Ȃ��B���s���������Ȃ���A��������Ă��邩�炾�B
�@�v���Ԃ�ɓ��~�D�����o���Č���ƁA�v��ʔ���������B�ꖇ�̎����̒��ɁA���܂��܂ȏ��̂��������Ă���̂��B
�@�ۂ���ɗp�����Ă���̂́A�����`��̏��́u⽏��i�Ă�j�v���B������Ȃǂɒ���ꂽ�����Ȃ̂ŁA���������̐����ŏ�����Ă���B
�@�u���~�v�Ƃ��������͊���Ɏg��ꂽ�u�ꏑ�i�ꂢ����j�v���B����ɂ͎������ǂ���A�����Ȏ������y�������߁A�����͂����ς玆�ɕM�ŏ������悤�ɂȂ����B�����ɍׂ��E������������悤�ɂȂ����̂́A�M�Ŏ��ɏ������悤�ɂȂ����䂦���B�Ƃ�킯�A�͂炢�̕����̎O�p�`�������I�ȏ��̂��B���̐`�E��������̏��̂̈Ⴂ���u�`⽊���i����Ă�ꂢ�j�v�Ƃ����Ă���B
�@�ꏑ�͞����i��������j�̂��ƂɂȂ����B���݁A����ꂪ���ʂɎg���Ă��鏑�̂��B���~�D������ƁA����̎��̖傪�`����Ă���A��z�Ɂu���V�M�i����ꂢ�̂��Ɂj�v�Ƃ���������������B���̕����́A�������B
�@���ɏ������悤�ɂȂ��������́A���p�̏�Ŏ���ɑ����������Ƃ���v���ɂ��A���̂��s���i���傤����j�E�����i��������j�ւƔ��W���Ă������B
�@�킪���̂������Ȃ͊����̈ꕔ�����o�������̂����A�Ђ炪�Ȃ͑������琶�܂ꂽ�B���~�D�ɂ́A�A�ȁi���߂�j�ŏ����ꂽ�������Ђ炪��(�w��������G���x�i�钎�̊��j�̎����i���Ƃ����j)���A�������Ă���B
�@���~�D�ꖇ�ɂ́A���̕������Ïk����Ă���B
|
|
|
|
| 2013�N4��25���i�j |
| �H�ꐧ�@�B�H�� |
�@�Y�Ɗv���ɂ���āA�H�ꐧ��H�Ƃ́u��v�̕������u�@�B�v�ɒu��������āA�H�ꐧ�@�B�H�Ƃ����������B
�@�@�B���g���悤�ɂȂ��āA���Y�������サ���̂�����A�����l�тƂ͂����Ԃ�Ɗy�ɂȂ����͂����B�������A�����͋t�������B�ǂ����ĂȂ̂��낤�B
�@���{�Ƃ͎��̂悤�ɍl����B�@�B�ɂ�����������̂ŁA�ł��邾�������g�������B���̈���ŁA��ɍŐV�̋@�B�ɍX�V���Ă����Ȃ��ƁA���ЂƂ̋����ɕ����Ă��܂��A�ƁB
�@�����ŁA�����Ԃŋ@�B��O�ꂵ�Ďg���ׂ��ƂƂ��ɁA���X�ƍŐV�̋@�B�Ɠ���ւ��Ă������ƂɂȂ�B����́u���ԂƂ̐킢�v�ł���B���̌��ʁA�J�����Ԃ̉�����J�������������炳���B
�@�܂�A�ŐV�@�B����������Ċy�ɂȂ�͂��������̂��A�\�z�ɔ����āA�܂��܂��d���ɖZ�E�����Ƃ���������������̂��B���̖������J���^���i�J�����Ԃ̒Z�k��J�������̉��P�v���j�̌����𑣂����ƂɂȂ�B
�y�Q�l�z
�E�����w���܂����u���{�_�v�x2008�N�A�����V��
|
|
|
|
| 2013�N4��24���i���j |
| �u�}���Y�̉F���N���_ |
�@�u�}���Y�́w��ېV���x�̕t�^�ɂ����u���ו����}���v�̒��ŁA���̉F���N���_���q�ׂ��B
�@�u�}�ɂ��ƁA�F���͓������ׂƂ��Ė������ł���A������C�݂̂��������B���̃o�����X������A�C�͎���ɋÏk�E�W�����ĔZ���ƂȂ�A���͂������ĉ�ƂȂ��Ă����B�������đ��z�n���������ꂽ�̂��Ƃ����B
�@����́A�������[���b�p�Œm��ꂽ���_�N�����Ƃقړ������z�ł���B�u�}�͓Ɨ����āA�����l���ɓ��B�����̂������B�������A�����̓��{�̓V���w�҂́A��@�����̂��߂ɓV�̂��ϑ������̂ł����āA�V�����̂��̂�F���_�ɊS�����҂͂قƂ�ǂ��Ȃ������B���������ʂł��A�u�}�͓��قȐl���������B
�@�������A�u�}�̗]���́A�ނɌ����̌p���������Ȃ������B49�Ŗv�����̂ł���B
�y�Q�l�z
�E�g�c���M�w�]�˂̉Ȋw�҂����x1969�N�A�Љ�v�z�Ёi���㋳�{���Ɂj�AP.156�`157 |
|
|
|
| 2013�N4��23���i�j |
| ���C�� |
�@���ߎЂ́A���˂炢�Ă��B��1911�i����44�j�N�ɐݗ������B���̖����́A�P�W���I�̃C�M���X�ŁA�ꕔ�̃C���e���Ԃ��������������₩�����u���[�X�g�b�L���O�ɗR������B���X�͕̏̂������̂��B
�@�Ȃ��A�u���C���v�Ȃ̂��B���}�Ђ̕S�Ȏ��T�́u�u���[�X�g�b�L���O�v�Ɓu�����^�M���[�v�̍��ڂɂ��ƁA���̗R���͎��̂悤�Ȃ��̂������B
�@�G���U�x�X���r�[�W�[�Ȃ鏗���̃T�����ł́A���w��|�p�ȂǂɊւ��鍂���ȋc�_���s��ꂽ�B���̗[�ׂ̉�ɏ����ꂽ�a�m�̈�l�ɁA�x���W���~�����X�e�B�����O�t���[�g�Ƃ����l���������B�ނ́A������ʓI�ȍ������̌C���ł͂Ȃ��A���ю��̌C�����͂��Ă��āA�l�тƂ̒��ڂ��W�߂��B�������A���̎�̉�����C���e�����������́A�u���C���v�Ɗ֘A�Â��ČĂ��悤�ɂȂ����Ƃ����B
�@�������A�����V���Еҁw���j�G�w���T�i���E�ҁj�x�i1975�N�A�����V���Ёj�ł́A���ю��̌C�����͂����j�́A�r�[�W�[�v�l�̃T�����ł͂Ȃ��A�G���U�x�X�������^�M���[�i1720�`1800�j�̃T�����ɂ���Ă������ƂɂȂ��Ă���B��Ƃł������������^�M���[�v�l�́u�u���[�X�g�b�L���O�E�\�T�G�e�B�[�̏����v�ƌĂ�A���̃T�����̓u���[�X�g�b�L���O�̃j�b�N�l�[���ŌĂꂽ�Ƃ����B |
|
|
|
| 2013�N4��16���i�j |
| �u�L���ŕ��v���āA���Ȃ�̔��H |
�@�������́A��X�w�҂̉ƕ��ł���B��������̑O���ɂ́A�����E���P�E���^��3��ɂ킽��A���͔��m�i���傤�͂����j��y�o�����B���̊w���̐[���䂦�A�������ɋI�`���Ȃǂɂ��āA�����𐿂��҂����Ƃ�₽�Ȃ������B�����ŁA����̏��ցi�R�A���Ƃ������j�ŁA���������҂����������邱�Ƃɂ����B���݂ł����Ȃ�A���m�Ƃ����Ƃ��납�B
�@�Ƃ��낪�A��l�̐�������ɑ����āA���ւɎ��܂肫��Ȃ��Ȃ����B�����������ԂɑΏ����邽�߁A�ꏊ�����ւ���L���Ɉڂ��A�����ōu�`���邱�Ƃɂ����B
�@�䂦�ɁA�������̎��m���u���ƘL���i���낤���j�v�Ə̂���B |
|
|
|
| 2013�N4��15���i���j |
| ��������ڂ��ꂭ�ǂ��i���c����39�B����ŏI���j |
101�@�F��������ق��ꂭ�Ƃ�
�����B�݂Ȃ���B����ǂ̂������B�䑶�Ȃ�ǂ��B�����Ă�����ȂցB�����ǂ���������B��ԑ�L�����̏��ɍ��ł��n�肾�B���l�͂��ꂼ��B���ʂ��Ƃ�́B�N�͎l�\��Ō����a������B�����͐ߋ傶��B�厖�̓o�邶��B�ߏւ�������B�召�����݁B��������肵�ЁB�o���n���h����B�������̖�o����B����̂�������B��͂��炿��ڐ悩���ւʂ��B���čs�g����B�������n����Ђ��B����Ȃ��B�͂ꒅ�i���A�e�Ɂu�߁v�Ƃ���j�𒅂�����B�˖����܂킵�B������ނ���ŁB���������@�ǂ�B�ޏo������B�������Ȃ܂�����B���������Ȃ��B������ʃn�B���m�����Ă�B�����ʂꂶ��B���̎d������B�I�̖�����B�[�ւ�҂ȂցB�i�̗��H����B�\�����y����B�G�͂���Ƃ��B�ڐ�ɂ〈���Ȃ��B���}�̈됺�B�ǂǂ�Ƒł����B�����▔�Ȃ₢�B�U�߂̂��Ȃ炩�B�����͂���������B�����ő�L���B�����������ւ��B�Ў��ꂽ�B�����܂���ρB���Ă���Ȃ�B���؍��݂�B��k��獏o���B���킮�Ƃ���ɁB���Ęe���ĉ�̓��ł́B�n�k�̎q���₼���B�o��ӂ����ӂ��B������̏��ցB�E�ƍ����B������B������āB��͂���肶��B�����Ƃ��@���h����B�M�ɔ������āB�s�q�͒m��ʂƁB����B�����B�������邶���B������������B�S�n���悢����B�����ƃn�ɂ���B������Ȃ��ŁB���߂�ŁB�₽��ɂ܂���āB�d������B�����Â̂�������ƁB��͗��h����B��͐Ԃ��āB���~��������B�����̐��B�����ł��炷���B�ƒ�����B�߂��߂���B�����ʂȂ��肶��B���Ȃ�������B�����̏K�Ђ���B�����a������B���܂ւ͂Ȃ��B�O�\�ܖ��̍�����̂����B�Ɨ�����R����Ńn�Ȃւ����B��l�������Č��Ă̂Ȃ��̃n�B�_�̌䔱���\�����邾��B����������n�B����Ăǂӂ���B��Ԃ͌����āB�o�����@�Ȃ����ցB�e�̂�Â�́B�厖�̕����₼�B�v�Ƃ��ӂ̂��B�c���̐܂���B���ɔw�ЂāB�o�Ƃ�����̂��B����܂���N�Ō��̂��B��������ꐶ����̂��B�e���c�ցB�s�F����Ȃ����ցB��m���x���B�䒃�j�Ď��Q����B���܂ւ͖�������̃n��������B�l�����ɂ���B�ƒ������ɂ���B�������̉ʂɂ́B�V�������ɂ���B�ǂ�Ȍ䒃�ł��B���ɂĂ̂߂邼�B��������Ȃւ����֒Ǎ��B���Ƃ͐����ŁB���肪�肩�ނ��ցB�d�钉�b�B���ɂ��āB�d���āB�����t�����R�B�����֒ǂ��B�͂���₠���B�ɂ�������B�e�ɗ��ʌZ�L�̏����B�嗧��Ɖ]�����B�{������ɖ����Ɉ���B�����B�����������Ђ�ŁB���ƏO�����܂����B�����������B�֗��ɔw���B�����v�����B�̕��Ȃn�B�劭�s���̂Ȃ�ƁB�䔱������ʂ��̂��ցB���Ƃ̑啿��j���ɂ́B��a�������B������v�āB�_�c�̈�P���B�ꐡ�͎�炸�ɂ�B���E�ɑ��䂹�ʂł͂Ȃ����ցB�|�n�����B�����Ȃn�B���܂��ׂ͈��Ƃ��B�ƒ��ׂ͈�����B�����n���ɂ��B���Ă͂��낤�ɁB�w�c�J�Ȃ́B�V�����ъB�悾������炵�āB���@���Ă��B�܂����̎��ɂ́B���ɂ��Ȃ�Ȃ��B���ƈҐ��@�B�����̔��͂��B�O�����ɂ��ŁB獂Ă��B�ア�Ƃ��ӂ��ł͂Ȃ����ցB�Ȃ₨�܂��́B���̎����B�C�L���X����́B�Z���������ƁB�����ꌾ�B�����ɋ���āB�厖�̒���B�����Ďd�����B�Ȃ�ƊF����B���܂��������B���˂�B������B�z�O�Ȃ��B���ċ����B�V���̑�ρB�ᒺ�ᒺ�Ɖ]��āB���Ēm��ʒm��ʂƁB���Ă��ɋ���B���ꂪ�����B���̎n���B��ӂ���������B�₽��ɉB�����B�ꂺ��߂��Ȃ�B���̂����悯��ƁB����̂�邢���B�n�����ł������B���̗���ɂ�B�������Ȃ����ցB�Ƃ�Ȓn�̗����B�l�a�ɂ������ƁB�Ўq�@�����B�]��������Ȃ������B�����}�ӂāB�a�e���厖����B�v���̏��ʂ��B���c�̌܃����B����ł����߂��B�ٌ������Ȃ��B�q���X���B�挩���h�āB������v���B�V���̑嗐�B�悵���B��߂����B���\���₠��ƁB���x�]�Ă��ꐡ�����Ȃ��B���̓n���́B��i�}�}�A�u�́v���j�ƈ�ӂāB�����n�����āB�J���X�͔����ƈׂ˃n�B�V���́B����Ȃ��ƂāB�����B���傳�炵�āB�ǁV�̂āB�]�����ȂցB����̉]���B���Ȃ��B���́B��V����n�B�͂˂�Ɖ]�����B���i���̂ɂ�ׂ�Ȃ��j�@���Ƃ�����B���{�ɂ�Ȃ����ցB����܂肠����āB�����։]��ʁB���܂��ɁB�ׂ�ڂɁB�ЂЂ����悢���B�����e�i�́B���������邼�ցB�l����邢�ɂ�B���������܂�ʁB���̉]���B�Ȃ�ł������ցB�Ћ˂Ȃ́B�n���Ȃ�B�b�{������߂ŁB�x�z����������B�Ă�s�����́B��������Ȃ����ցB�z�Ӑl�Ƀn�B�����������邼�B�e�މ��҂́B�o�������邼�ցB���l�͑a���āB���͂ނ���Y�n�B���Ђ悭�āB�{�Ƃ֏捞�B����d�����āB��\�ܐl�ɁB��l�̂������B�⊾���炵���B�l���v���āB�Q�V������B獂ꂽ�Ȃ�ǂ��B���ƃn�i�V���K���B���䂭�āB���{�キ�āB�|���l�肾�B�����Y���ǂ���B��ς肻������B����ŁB�l���̑��ЁB��̉^��B�ǂ��ɂ��Ȃ����ցB�i���Ă����B���肪�Ȃ����ցB���ɂ��܂ꂸ�B��������ނ��B�U�߂̈Ό��n�B��V�߂��āB�Ⴂ�g��Ђ����B�܃n���āB�R�V���炯�ŁB�떜���c����B����ł��B��ς�B���������B�ЂЂ����B�������Ӑl�@�B�����ւ̂��邼�B�e���`���������Ȃ��̂ɁB�ŊQ�Ȃn�B�Ƃӂ�������B���t���������B�d��������̂ƁB�l�ɉ]���āB�₽��ɁB�ӂꂳ���B���܂փn�����ŁB�����̌����B���̎������B�͂�����獂邼�B�l����傩���B���ɂ������ցB�B�����r�Ƀn�B��L�ɍ��āB�w�����ւāB���܂Ĉ������B���P�����B����������āB���������ւ�獂����B��������B�ߕ���������߂��B�Ȃ������Ȃ�ǂƁB�ЂƂ�����Ȃ������B�Ԃ���Ȃǂӂ肻�Ȃ���B��N�����B���߂����Ȃ����ցB�ٌ`�̑启�B����o�������B��J�啗�B���߂����Ȃ����ցB�֓���r�B�Ƃӂ�������B����w�����B���Ďd�����B���������B���߂����Ȃ����ցB�����Ȃ��B�Ƃӂ�������B�V�n�J���Ďn������B�C�̐����B�ŋC������āB�܂���E���сE���������́B�����Ђ��B����肱��蕂�o���B�����Ȃ��B��Ă��܂���ʁB�l���B�����ŁB�e�ʂȂ��B�����łȂ������B�]�˂�����肶��B�c�ɂ�����肵��B�S���]�l���B��x�ɂ���肶��B���܂ւ̎�܂āB�����ŁB�������@�B�����炱���́B�����₵���낤���B�����F����B���Ă�����Ȃ�B�����a���́B�ւ��B�a������B�ڂ̂��炾�́B�Ȃ܂������R�B�܂Ȃ��n���Ă��B���ڂ������Ȃ��B�������Ă��B�����炰���R�B�S�����Ă��B�悢������ȂցB�������Ă��B���s���o���ȂցB���肪���Ă��B�������Ȃ��B��a���Ȃ��̂́B�܂������B�A�����J�S���B�\�����邤���B��ག̎��Ȃ�B�Ȃ�ł��B�����ցB���ʂ���Ȃ�B����ɂ��Ȃ��ցB���n���B���߂��o�B�ǂ��ł��悢���ցB���{�̕��Ȃ�B�Ȃ�ł���邼�ցB�_�ИŊt�B������Ă������āB�ΐl�̉��n�́B���s���̂����B������H�n�B�q�������āB�������ǂ��āB���l�̂�����n�B���Ƃ��B�\�n���B���c���悢�ƂāB�ɂ��ɂ��ӂāB�Ƃ�ŏo��B�Ȃ́B�����ꂽ���l�B����ɗ����Ȑ���������փI���V���̈����B���䂩�\���B�t�˂��B��āB�䂳������������B���m�����B��߂��́B�悯��ǁB���Ւv���B�����ȂƁB�a�e�V�V�ƁB�Ă������B�������ɂ�B���V���g�����B�g�߂𗧂����B�����������ȃn�g�߂̐l�����B�͕S�����s�Ȃ������Ƀn�B�ڂ̋ʂ��肮��B�܃n�肫���ƂāB�ւǂ�f���B�����ꂽ�B�܂܂ɂāB���l���R�B�����߂Ȃ���B����B�؋����B���Ă��݂Ȃ��ցB��������B���M�ɂ�B��x���B��Ȃ��l���B�����̉ʖ��B�s��牂������́B�ւ�ڂӂ���܂���B�Ȃ����ցB����n�܂������B���Ԃ��⍢��ʁB���鎖�ɂ́B���F�̍����B�͔��N�B���Ȃ������ɁB�����i�V��āB������B�v�Ɉ���āB���܂ŏ�āB��ག̃h���ɂāB�ʘH�������āB�V���悭�Ă��B���邩��Ȃ����ցB�₪����B�g������āB��l���ʁB�i�V���āB���m�̗E�����B�ǁV�ւ邼�ցB���ɂ����܂փn�B���ڂ��āB���炷���B���܂���B����āB���d�ɁB�Ȃ����B��َq���B��āB�˂ނ����B�܂����ցB���喼�ɂ́B�؋��ӂ��邼�B����{�ɂ́B�y�Y���Ȃ����ցB��Ɛl�Ȃɂ�B���c���Ȃ����ցB�Ă̒��i���B�����Ȃ�ǂ��B�����Ȃn�B�ւ�ڂɈ��B���B���܂��ɁB��Ă͏����n�����B���{�̑�s�́B��]�s���Ȃ����ցB���n�V���́B��������Ȃ����ցB���Ђ�Ȃ́B����������ɁB���X�ȂɁB���K�����Ƃ́B���ꂳ�a������B�{������B����܂��B����Ȃӂ���́B�������Ȃ����ցB���܂փn�B�䒃�����B���������B�F����B�삹��ɁB�悤���ŁB����ӂ����B���ɂ�ӂ��n�B�܂������B�悯��ǁB�䒃�ɂ�ӂ��́B�n���ɂ₨�ւȂ��B�E�l�Ȃɂ�B��i������ƂāB���o���c�B�l���������ȂցB�����Ȃn�B���������܂ŁB�������炵�āB�ǂȂ��l��ŁB����ŁB�ӂ���n�B�ł��邶��B����܂��B�ӂ���ł����́B���ł��悢�Ƃ́B������āB�����o�Ȃ�����@�B�Ȃ����ցB�₯���n�B���߂���B�d�����Ȃ���ǁB�O�ɂ́B�܃����B�ɂ��ŁB���邼���B���ɂ́B�嗐�������āB���邼�ցB����厖���B���������ɂ́B���܂��n���B�F���̌��ցB�n�̒��B�����Đl���^��B���K�肪���邭�āB獂�ł��낤���B�Ղ̎n���n�B�ǂӂ�������B�\���ɂ����́B���ė����B��ӂ����ག͒n�̗����B�\���m�����B���܂ւ̎ア���B�S�܂ď��m����B�v�ł��i�ڂɁB����̂���ག���B��������n�B�{�����邻���B�\���Ȃ��āB�����������邼���B���Ո�N�B�Â������Ȃ�B�i�V���F���V�܂ŏ�b�āB�l�C�����B���ė����₤����B�q�����낵�āB���[����˂B���������́B���̂����B�o���ȂցB�Ȃ�Ƌː��́B�������B�������B������i�B��b���l��ŁB�����炱����́B�Ƌ������킵�āB�Ă�D�āB�Q�V���̂����B���ɓV���́B������������B���{���n�B�ᖙ�o���ȂցB���҂��o�鎞�@�B�������܂�ʁB�q�E�����́B�����˂���ŁB���������Ȃ��B�d���n�B�ǂ����₢�B�I�Ȃ��B�������ɁB���āB���s�����킪���B���������n���B�P�{����āB�֓��։������B��䏊�ɒv���́B�Ȃ�ǁT�B���ΐ�j�́B���܂��ɁB�悽���B�֗��n�ǂ��ЁB�v�Ńn�����ʂ��B��ག˃n�B���n���Ȃ��B�]��Č��n�B���������B����ǂ��B�����։�āB�{�������߂āB�d���ɕ��l�v���Ȃ�ǁB�����S�B�Ȃ������S�B�e���ۉƂ���u�B������Y���B�k�����ǂ��ŁB���H�̗��{���̌䏊��B����Ȃ�ǁT�]����B�t�b������āB�����������āB���炾���B�����āBᚕa�B��ނƃn�B�V�q�̌䔱���B��������Ȃ����ցB���ɂ��푺�ӂ�ӂ�B��Y������c�ğ��ŁB�o�����d��ƂāB�����炱������B��������B�܃n�āB�l�̂��炨�B�₽��ɁB�������āB�j���e�����B�_�ɂ��v���āB���݂̂蕨�ɂāB�������悯��ǁB�A�b�Č�����o�B�傫�ȊԈ�ЁB�Ⴂ�N��B���ς�͂���āB������������B�S�n���悢����B��ς�䔱����B�O���ɂ���肶��B�l�̂����n�B�܂������悯��ǁB�Ȃ⏨�́B���Q��E�Q�B�������Ȃ����ցB���T�߂��o�邶��B�����̂₯�����B�䔱����ӂ�������B���ꂳ�a������B�����肵�Ȃ���B���̒��������B������Ȃ����ցB���߂���B����n�h�ЁB���Ƃɂ͕������B�Ў����Y��ȁB
�֗�����삵�āB��ག�ƁB�_�c�̈�P�ŁB���̔@������B�����֎��o�B�V���n�₭�B�A�����J�B�C�L���X�B�I���V���B�͎艺�̍ߐl�B��̕�����悾�B���������]����B�|���x���B�����`���B�Ă��ʂ��킹�āB���ӂ��Ӊ]���āB�������āB�l�̔@������B���܂��ׂ̈邱�Ƃ́B��b�������Ȃ��B�_�c�̝|�ɂ�B���������ȂցB����܂̌��q����B�ނ����ɂ���B���܂��B��������B�������v���āB���G�ގU�ގU�B�ǂ��납�B�܃����������B�������b�āB�ǁV���邼���B��������B�֗��n�Z�\�]�B�́B���Ȃ��B�����������܂��o�B�悳���āB���܂��́B�ՂĂ����Ă��B���{�́B�_������̂��ցB���{�̌䍑�́B��ɐ��ɂ��邼�ցB�_�c�̌�ʃn�B�����ɂ��邼�ցB�R�̂����́B�ӂ����ŁB�Ȃ����ցB�o�_�̑�Ђ́B�䍐�������B�V�̎g�ɁB��������B���V�����B�_�����āB�����S�̑א�a�����B�[���������B�������ꂽ���B�_�c���`�������B�����ɗ���B��N�����āB�o���Ȃ��B���ɁB����ẮB�̂��ɂ��B���Ђ���ƃn�B��ς莫���́B�̂Ńn�Ȃ����ցB�J���̗w�́B������āB�����n��Ƃ��B���ɂ���ƃn�B��g�̎����o�B�]������Ȃ����ցB�Γ��|���āB��c�̒m�点����B�v���B�����Ƃ��B�m��Ȃ��B�j�Ƃ��́B�Ȃ�ƊF����B���킢����B�Ȃ����ցB�ɐ��ƁB�o�_�ƁB�����̑�_�B�O�Ђ̌䔱����B�O���O������B�V�q�̓{��ƁB���l�̍��ƁB�܃b���ƃn�B�����B�Ȃ����ցB��������B�ڂ݂���B�Ȃ����ցB�U�Ďd���ӂ́B�Ύ~�Ȃ���B��Ə�����B�s�ւȂ���B������Ƃӂ���B���܂��̎��Ȃ�B�܂�B�߂����́B����������āB�O�r����B�����n�āB���o�̎R���B��ق�ٓo�āB�Z���҂ɂāB�߂��̂��B�͂���āB��̍~�̂ɁB�͂����ŁB����ڂ���ځB���܂ɑ�L�ȁB�����Ď����B�߉ނ𗊂��B���ӂ�҂ӂ��B�߉ރn�O��N���߂����B���Ӄ@�\�Z�����N���B�҃n��`����B���ł̐��E����B���ꂳ�a������B���ď�ӂ��B�߉ނ��B���ӂ��B������B��߂Ȃ�B��b����₢�B�d�������邻�ցB�������b�āB�|��j�b���B��l��\�V�āB��ɐ����b�āB�_���q�����B��l��\�āB�o�_���āB�_����j�b���B��l��\�āB��S���łɁB�O�l���������Ȃ�B�䋖�����邼�ցB���܂֒f��B�n���𗣂�āB���L�n���B�߂��n�S���B�v����l�Ԑ��E���B�o�����āB�q�����H��l���B�֏��B�i�V�����������B���Ȃ�Ƃǂ̎d���n�B���V�喼�B������x�n�B�F�����āB����ȃj�āB�x�M�ɐ���邼�B�v�͝M�u�B���Ղ͂ǂӂ���B�����́B�B���̐T���āB���R���琭�������āB���n�e������B��U���ՁB�䍂�͎c�炸�B�V�q�֎w��P�B���{��b�āB�喼�����āB�_���h�ЁB�������~�B���҂���ŁB�������^���B���͊ۂ����B��གྷn����B�����_���B����n�Ȃ����ցB�܃����ގU�B�����n�Ȃ����ցB�_�������B�߁V�ɂ��邼�ցB�Ȃ�ł�����ł��B�䒼���䒼���䒼���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�C�m�����Аl�T�q
|
|
|
|
| 2013�N4��14���i���j |
| ��ՒÂ������v���`�i���c����38�j |
00�@��ՒÕ������v���B
�߂ɂ����̉Ԍ����A�o�邨�����ƑҎ�āA���ƌ������ĂƊ�A�i��炵�����₳�肽�āA�l�̌���߂��Ȃ�̂��́A������ł��Ă����Ƃ��ʁA�ڐ�ɖ��f�A�����̏O������т₹�܂����Ԃ�ɁA�ʂ�Ă����ւƂӂ�Ƃ���A�˂������킯�ɂȂ��̂��A�������Ă������ɁA���˂ƍ��c�r����ׁA���̐ߋ�̒��ڂ炯�A���o�̂����߂Ƒł͂����A�s�ӓS�C�̓���ɁA����Ăɂ��Ƃ������߃n�A���䂭�Ƃ��ӂ��̏��Ă����A���̓a���͘I���炸�A�v�Ђ������킽������́A�Ȃ�̖������������낼�A���Ȃ���łăn�{�]�ƁA�݂���~�����A�������Ɏ��������镗��Ȃ�
�y�����z
�@��֒Õ������v�͏�֒Ð߂̑��v�B����i1709�`1781�j�͍ŏ��{�ØH�L�㝁�̖�l���������A�L��߂��]�˂ŋ֎~���ꂽ�̂ŁA��֒Ð߂�n�n�B���ڕ������v�i1731�`1799�j�͖���̗_�ꍂ���A�O��ځi1792�`1820�j�͑����������ߎ��Ղ͑����Ȃ��B�u������v�́u������v�̈ӁB
�E���̍��ځA���Z���B
|
|
|
|
| 2013�N4��13���i�y�j |
| �������i���c����37�j |
99 ������
a �i���[�j���ߊn�v�Ќ��@�@�@�@�@�@���{�̌�Ɨ�
�y�����z
�@�Q�m�B�͑�V�P���̍ہA�X�ܘZ�Y����U�i�̑̂ōs��ɋ߂Â��A�拟�Ɏa�荞�ނ̂����̍��}�ɂ����B��U�i���čs��ɋ߂Â����͎̂v���t���������A�̈ӁB
b �����ɂĂ肫�̂͌�̌��@�@�@�@ �O�N�c�̜A�ԁ�
c ���ւ̏�łӂ���@�@�@�@�@�@�@�@�@ �C�̌��̔Ԏm
d ���̍s�q������ʐ_���� �@�@�@�@ ������
e �䂩�炾�l�ɂȂ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�䏢�d
f �n��獏o���������댎 �@�@�@�@�@�@�@�@�@���R��
g �ԂЌ��Ő��������� �@�@�@�@�@�@ ��ɂ̖��
h �e���͉ɂł���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �㐙�̒ҔԐl
i ��͂Ԃ�ł͑傻�ӂȂ����� �@�@�@�@����J�n��旼���
�y�����z
�@����J���ԕЋːΌ���Ɣn�����Ԍ˓c���V��́A������Q�m��̌��ʍs�������~�߂Ȃ������߂ɂ��A�Ƃ��ɍ����T���𖽂���ꂽ�B
j ����Ă̒��ŋ��ʂ����Ȃь��@�@�@�@ �a��
k ���x�͊����ЂƂ��猎�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B��
l ���m���o�����ė͌��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ɂ̉ƒ�
m ��ƕ����r�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���x
n 獂����Ăɔ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c�̌�
o �܂��Ƃӂ��ӂȕ@�̂Ђ��� �@�@�@�@�@ �䎛
p �����Ȃ������͉��Ă��t�Č��c��ꂵ���Ԍ�
q ���V�Ɍ����ʌ��͂Ȃ���ǂ�����̌������[�̂�
�y�����z
�@�O���O���ɈÎE���ꂽ�̂ŁA�O������Ɍ����������[�߂̌��ɂȂ����A�̈ӁB
�E���̍��ځi����j�A���Z���B
|
|
|
|
| 2013�N4��12���i���j |
| ���c�̌��s�����i���c����36�j |
98 ���c�̌�����
a �^�̌�
�Ⴉ���闈������Ԃ������鉽�̋���Ȃ����^�̌�
�y�����z
�E�u�Ⴉ���������Ԃ������鉽�̉_�Ȃ����^�̌��v�Ɂu�s�������闈������[�֓˂������鉽�̋���Ȃ����^�̐s���v��������B
b�@���猎
���邩�����Ȃ����N�̎p���Ƃ͂��݂��Ȃ���܂Ȃ����猎
c�@�Ƃ茎
�͂��Ȃ������₵�Ȃ݂��̂���ւ��ˍȂ̂���݂̍��ɂƂ茎
d�@�Ƃь�
�T�S�Ƃ��ӂ܂����炷�ԍ��H�ʂ����͂₭�k�m�ւƂЌ�
�y���z�w�������ځx�O���y�[�W�́u�k�m�v���u���āv�Ƃ���B
e�@�����⌎
����ɂ��ɐ�ɒ��ƃn�܂̂�邫���ǂ舫�����͂����⌎
f �܂���
���t�Ă����͂����ԂȂ��Ԃ�Ԃ�Ƃɂ���o��ł₽��܂���
g�@�V�̌�
��~���݂Ƃ����͂ʐl���Ȃ����n�������V���̂�
h�@�ǂ���
����ƕ��Ă��肱��艺�n��ɂ��鋟�̂ǂ���
i�@������
���₵���ɂ͂肳���ނ˂�������ݘH�ɂ̂������Ɨ�������
j�@�˂���
���Ђ��Ђɍ����͂�����Ɨ��������̍ς��łǂ����˂���
k�@���猎
���ς����֒��x���̍��̉��Ă̂����݂�Ⴋ�猎�i�}�}�j
�y�����z
�E��������ɒ��x�����A�ƌ��������āA�I�̍��̉��ĂƑ������B�������O�ɔ����˂̍s�o�邵�A������ɋI�B�˂̍s��V�P�������ʂ�߂����B����͑�V�����̌�����A�I�B�ˎ傪��U�̒�����`��������i�܂Ȃ��j�������Ă����A�̈ӁB
l�@�ւ���
���܋}����������̔䋻���̖ڕt����ꂶ�Ƃɂ���ւ���
�y�����z
�E�u���܁v�͋�i�n�j�ɋ��R��璩���i�Ƃ����j���|����B�u�ڕt����ꂶ�v�́u���t�����܂��v�̈ӂɁA���̖�E�i�ڕt�j�̈ӂ����Ԃ��Ă���B
m�@�ނ���
��Ύ肠���Ђ���@�����Ă݂�l�V�̂ނ˂͂ނ���
n�@�ǂ���
���������������獂�����Ƃ��Ђɂ����n�ǂ���
o�@������
�؍������������̎蕉�l�F���ꂻ��ɂ���͂�����
p�@�Ђ⌎
��ӂ�ӂƂɂ�������n���ΐ삨�����ނ˂̂܂����Ђ⌎
q�@�Ԃ猎
�ʂ��o���邢���Ƃ����ɂ����ꂢ�Đl�߂����̂ѓ�x�̂ӂ猎
r�@������
���͂������̂��|���̎I�]�ȂǂƂ��܂��Ă����Ƃ�����
s�@�܌�
���ւ̂Ȃ��V�E�������ĂЂ����Ƃ��炭�Ђ��Ȃ܌�
t�@������
�������݂����̂�Ӊ\���Ă��炴�鎖�����ɂ�����
u�@���̕ʂ��̂�
��O�N�g�̗{������邢��֎�̂����ƂȂ肵���c |
|
|
|
| 2013�N4��11���i�j |
| �܌����i���c����35�j |
97 �s�m�I��i�}�}�A�u�܁v�j�����@����ߏ����
a�@���Ɏ��ʏ�
��l�s�B�c�����ߕӁB�Ք��D�ǓG�B�V�����L�F�B
b �鑗��g �@�P�c
��g�l�Q���B�Ɨ����a�B�B���N�ҋ���B�����n��O�B
c�@�ᐅ����
��n�����O�B�s�m�F���B�����G�ߖv�B�������P���B
d�@���}�g��
���틟���B�^��������B���w�n�g�B����גN�Y�B
e�@���u�דG
�������V���B�ߔޓ������B���S���f��B�N���ߓ��m�B
f�@��H�T �@����
�����R�쉓�B�o�{�ݗ��t�B���S�����q�B�s���ӓ��l�B
g�@�ߏ�����
�k��������B���З��͟��B�ߏ��������B�����s���B
h�@����
�`�l���B�[���������B�A���⍦�~�B�s�m�S�N���B
i�@�t��
�Ԑl�s�o�߁B���X�o����B�������퐺�B�m�����B
j�@���铚����V �@�ҏ�A
���ݍs�痢�B���늸�ꌾ�B���ב��v�B�s���M�`���B
k�@�����ҁ@�@�@�@�@�ϟ�
�����o�d�r�B�������Ҍ��B���S���sᶁB�O�����B
l�@���ˋɁ@�@�@�@�@�D���
���X�J��B䩁X�������B�����ߗp�ԁB�ݗ��s�h���B
m�@���H�V�@�@�@�@�s�^
�n�|���ᐰ�B�ݖ��|���B��h�����ہB�풆��p�j�B
n�@��ʗ��@�@�@�@�@�\��
�~�����N�߁B�N���������B�s�V�A���x�B�����ՏI���B
o �q���s���@�@�@�ƒ�
���@����B��t�̖B���ݍ��풆�B��[�i�}�}�j
p ���l ���B��
������鉺�B����Γ����B�ƒ�����i�u���v�j�m�B�G獕s�m�ǁB
�@�s�m�I�V�V�ɏI
�y�����z���̍��ځA���Z���B |
|
|
|
| 2013�N4��10���i���j |
| �别�i���c����34�j |
95 �别
�@�@�@��S�D��
�d�Ԏq�H�别���ӎ�e�p���~�V��牗�N�c���l�l���������ϔV������]���V�]�ҕK��V���ԕ��ב������ށ�
�别�V���ҍݖ����J�ݕ���ݖŎ��R���]�۔ޓ���\�X�~�L�z�ώ��@�ؔ@���@�h�@����a���a��a獙a�L���ˎm���s���@�ؔ@���ғ�����@�h�@���Ҏ������a���a�Җ��ʖږ��a獙a�҈ً`��L�������I�s�Y�ғ��B�����R�ߔV�s�\����
���������N�c�O��ᢖC���敨�T�T��獋A�Z�ڋ����͓��o��{���i���͋��ւ�ɑq�j�Ԗ偙���@�g�F���ၙ���������s�q��m�叫����@��D��
�@�@�ڋ��@�@�@�@�@���Γ^
�۔ޓ������ڈ�ɗL���Q�O�@��@���@�Ԕ@�@�ؙa�˙a�řa��a�L����m�I�s�h
�۔ޓ��l�����|�X���L�����c�����͑�ϔ������a���h�a���a�L�����m�I�s�s�i���������j��
�۔ޓ��j焈Ք@�y�L����@���@�h�@���@���a���a�l�a�c�f�P��p�a�s����a
�@�@�S��ɋ�O�͏Ύ~��
96 �别 �i�别���w�����@���j
�@�@�@��S�D��
�d�Ԏq�H�别���ӎ�e�p���~�V��牗�N�c���l�l�V���������ϔV������]���V�]�ҕK����ԕ����������ށ�
�别�V���ݖ����J�ݕ���ݖŎ��R���]�[�ޓ���\�\�~�L���ώ��@�ؔ@���@�h�@�����a��a��a���a�L���ˎm�I�s���a�@�ؔ@���ғ�����@�h�@�����|�甇�a��a�Җ��ʖږ��a���a�җL�ًV�猌�L�����I�s�Y�ғ��B�����R���V�J������i���ґ�����B���a��a�Ҕ������a���a�ҏ�����������x�x���ҋ��|�r�����ځj
�E�ϔV�ꓝ�ҊW���m�����ˎm��V���a�V�D���ґ����O���i�u�V�v�j�ӎ����l�Q�V���p�����L��R�����ώ����ɍX�s�l���ʈ��ՐJ�@���i�}�O�E�ܖ��Δy�p���ҔN�������ՐJ�i�������c�Ӊ����V�j
�]��H���������H���x�V�ږ������H�����c�}�F���[�ז�
�E�Y�V�Җ�������
䢕��ݓ��{������B�L�\���l�B�s�h������B�����\���l�B�T�W�����q�V�]�l�������q�B�s��O���l�ݓ��{�f�՚��i�u���v�j��N���{�����o�O�����a��B���e���t�i���{�e�`�f�ՁB���Ȕ����q�B�L�d���V�ӁB���l�d�h����B�K���������g���E�B�ۉ�~�E�B�������ŏ����߁B���{���鑍�B�����e�O�����g��b�B�e�X�ސT�h��B�[�O���Z�����`�㈲�J���B
�y�����z���̍��ځA���Z���B
|
|
|
|
| 2013�N4��9���i�j |
| �ʊӍj�ځi���c����33�j |
94 �ʊӍj�ځ@���閠�����N�@�㔕�
�t�O�����h�Ԝ����]��N��O
�Ԝ������C�S�ߚ��ˎm����֘`�����R���ց��O�،��X�s���Ӕ������A�ˏ��A�،��ѓc�d���q���ːV�O�ؔɊC�@�`��糎Q�������H���}�N���V���V���s�ٚ@�ڏ]�k�����i�h�����`�n�����T���o�a�������s�Ӑ��w�t�V�⒆���@����H�Ԝ��뚠�V��@�b���ލs�V�n�R���L��Y�b���ϖ��i�s�`�ގ��ɓ��@���@���P���������U�S�s�m���V
�i�����u�ԋS����o�Ԝ��P��鰌����L����v�u�\���l�דV�����Q�v�u�E�g���m�v�u�����E�n�V�v�j
���@�@�����\���l��Ԝ��\�N�뚠�F��������b���q�l�l�������\���l�ҕs�����������W�\���l�҈ȑ��N�אԜ����J���w�ȎE�Ȕ������Ґ��̕s�Ȏ{�S�j�\���V��\�V��j�ڌ���薼�\�D�V�|����
�A�` �Ԝ��O�\�ݐg�ז��{��V���\���l�ҎE�����˕s���@�Ǔe毕s�������E�o�\��j�č����ȋ����́����ĈΗv���a�M罉p�ŏ��Ε��V�����ݎs���{�L�i���]���_������咣�p���K�~���V���˒����L������Ιԏ��i�F�k�]�V�s���������c���������Ȗ��{�@���g�L�p���V������˗��ו�ߔV�H�����Ώ٘����{�X����ʘ��������������叫�R�����t�Ԝ����c�������ݑ����w�V�Ș���������P�O�V�u�����َ|����嘪�R���߁����l�y�����a�ɐl���ы��r�ȗ��D���ߐ��H������������������ȉ����V���֍|�i�u���v�j���C�E�����x�Ҏ��\�P�l���c�Ҋ������Ԝ����������ڌ��R��ݎs�ݓڔ��n�m��s���������˕��J�]���������O�{�G���l���s�������D��V�����X��嫎��������F�m�ݎs�Q�R�������Ɣ@�`�l���z�l�V��ዐ�c�����ȉݘG���s�����F�偙�V�l�����߈��щm�V�n�s�q�_�l�������\���l�ȁ��V��j�ڕϕ����\���l�������������틎���݈Ȍ����ߕs�ᐥ�뚠�V��@�L�����ߎ����@�V��m�Ֆֈ����������n���b���q�V�S�����y�d�葴����������̈��������ڈהV���]
�y�����z
�E�u�ʊӍj�ځv�@�w�����ʊӍj�ځx�ɂȂ��炦�ď����ꂽ�����B�w�����ʊӍj�ځx�́A�v�̎i�n��������w�����ʊӁx�ɂ���čj�ڂ���������́B�������j�i��v�j�������A�ځi�זځj����t�����������B�@
�E�u���閠�����N�v �u����v�͍F���V�c�B�u�������N�v�͖������N�B
�E�u���v�@���͑��̈ӂŁA���@��j��ҁB���˘Q�m17�l���w���A�F���Q�m�L���͐l���ɓ����Ă��Ȃ��B
�E�u�Ԝ��v�@��ɂ̟Ӗ��u�ԋS�v�ɂ������ׂ�������A�Ԓp�������̈ӂ��|�����B�����Ɂu�ԋS����o�Ԝ��B�P��鰌����L����i�ԋS�̌���ɐԜ��o�ÁB�P�ي�鰌��̑��Ɋ���L�邪���Ƃ��j�v�Ƃ���A�Ԝ��i��ɒ��J�j��ԋS�̕s�т̎q���Ƃ����B��鰌��͖k�v�̌��b���g�i���B1008�`1075�j�̂��ƁB�͓���z�̐l�ŁA�p�@�̎�鰍����i�����������j�ɕ�����ꂽ�B�_�@�̎��A�����̐c�@�ɋ��������A�܂��v�E���Ă̐킢�ɏ悶�Č_�O�����n�����߁A�����������^���悤�Ƃ���Ɣ������B�w��鰌��W�x�w���z�W�x�̒�������i���哌�m�j���T�Ҏ[��ҁw�V�ғ��m�j���T�x1980�N�A�����n���Ёj�B
�@�s�т̎q���Ԝ��i��ɒ��J�j�̈��������ɏo���ꂽ����i�������イ�A�H�`1207�j�͊��g�̑\���B�����ɁA��������g�̑��Ƃ���̂͌��B����͓�v�̌��b�ŁA���@�̍c�@�Ɖ������Ƃ��ĔJ�@�i���Ɋ���B���G�����r�����A��q�w�h���������A�����������ς�ɂ����B�������A���Ɛ���Ď��s���A�ӔC�����ĎE���ꂽ�i�w�V�ғ��m�j���T�x�j�B
�E�u���ˎm�v ���i����j�͈Ձi�����j�̔��T�i�͂����j�̈�ŁA���E�B���E�Ȃ�ށE�k���E���F�Ȃǂ�\���B����Ě��˂͐��ˁi���˔ˁj�̈ӁB
�E�u���v ����|�V��B�͒|�̈ӁB
�E�u��֘`�v�@��֘a���Y�B�`�͘a�ɓ����B
�E�u�����v ���O�Y�B���͍��̈ӁB
�E�u�R���v ���R���Y�B���͜\�i��j�̕��Ƃ������́B
�E�u�ց��v �֓S�V��B
�E�u�O�،ށv�@�X�ܘZ�Y�B�O�͐X�i���O�����j�̈ӁB�ނ͌܂ɓ����B
�E�u�X�s�v �@�c�s�ܘY�B�X�i�����E���j�͘@�i�܂��͘@���j�̂��ƁB
�E�u���i���̂�������ނ�Ȃ��j�Ӂv �֓��ĕ��B�ӂ̕��Ƃ�ΊĂ̎��ɂȂ�B
�E�u�������v ��v�l�B�����͍E�q�̒��j�E��̎��i�����ȁj�B���������Ĕ����͌�̈ӁB
�E�u�A�ˏ��v�@�˂͑傫�ȉ��̈ӁB���̈ӕs���B�L���q�V���Y�B�@
�E�u�A�،��v�@�L�؏��V��B�،��͏��̎����������́B
�E�u�ѓc�d�v�@��c�d���B�т͈�̈ӁB
�E�u���q���v ���q�����B���́u���悢��A�܂��܂��v�̈ӂ��瑝���������B
�E�u�ːV�v �R���C�V��B�˂͑傫�ȉ��ŎR�B�V�i����j�͒C�i����j�Ɖ��������B
�E�u�O�ؔɁv�@�X�R�ɔV��B�O�͐X�̈ӁB
�E�u�C�@�`�v�@�C�㍵��V��B�@�͌�ɓ����B�`�͈�ɒʂ���B
�E�u��糎Q�v �����O�\�Y�B���͑傫�ȉ��̈ӁB���������ĕ�糂́u�����ׁv�Ɠǂ߂�B�Q�͎O�ɓ����B
�E�u�V���s�ٚ@�ځv�@���̂��߁A�킸���̋����ł������������Ȃ��B�@�͎��ڂ�8���i��18�Z���`���[�g���j�A�ڂ�1�ځi��22.5�Z���`���[�g���j�B�@�ځi�������j�ł���߂ċ߂������B
�E�u�t�V�⒆���@�v�@�V���e�⒆��������i�₷����j�@�B�����͂��̏ꍇ�A�����ȁi�������E�v�Ȃǂŏْ��E�����Ȃǂ��i�������������B���{�̗ߐ��ł͒����ȁj�̖�l�����āi���イ���傩��j�̂��ƁB�����Ă̘a���𒆖����i�Ȃ�����������j�Ƃ����A�������͒����ȂŎl�����i���A���E����A���E����A��^�E���^�j�̎����ɂ�����B
�E�u�@���@�v�@�א�@�i���F�{�ˁj�̂��ƁB�@�ׂ͍��̈ӁB
�E���̍��ځi����j�A���Z���B |
|
|
|
| 2013�N4��8���i���j |
| �p�̖i���c����32�j |
92 �p�̖�
���T�ӂ���Ⴉ�ȁA�v��͑|���ɂāA��ĎU����
�y�����z
�E�薼�́u�p�̖v�͗w�ȁu���̖v�̂�����B���̕����́u���̖v�̍���퐢�̏o�́u���T�ӂ���Ⴉ���B�����ɐ��ɂ���l�̖ʔ��������B�������A�сi�������j�Ɏ��Ĕ��ŎU�����A�l�͒߂��傤�i�u���傤�v�́u�Ɓv�̉��Ɂu�сv�j�𒅂ė��Ĝp�j���Ƃ��ւ�v�̂�����B�u�߂��傤�v�͔�z�i�ЂӁj�̂悤�Ȏd���ĂŁA���n�ɍ��̉����Ƃ������B�B�҂Ȃǂ������B
93 ��ɉԂ��U�Ĕ��˂̘H���ӂ�
�y�����z
�E�\�ʂ́u�f���炵���Ԃ��U���Ă��܂����̂ŁA���ɎU�������Ԃт��ⴂő|�������v�̈ӂ����A�uⴁv�ɁA���Е�s�������ˎ�i�O��{�Ôˎ�j�́u���ˁv��������B
|
|
|
|
| 2013�N4��7���i���j |
| 0407�@�������i���c����31�j |
91 �͂���
�@�@�@�@�@�@(�����ȗ�)
�y�����z
�@���ꂼ��̒P��̎���̈ꕔ���������Ă���B�u���ԁv�́u���v�̑���Ɓu�ԁv�̑����������Ă���B���ԁi�k�j�͈�ɉƂ̖䏊�ł��邩��A���J�́u�Ȃ��v�Ƃ������Ƃ����������́B���́u��V�v�́u��v�́u��v����u�l�v���E���������́B���������āu��V�ɐl�Ȃ��v�Ɠǂ߂�B�����悤�Ɂu�e�ʁv�́u�e�v����u�ځv���A�u�Ԏm�v�́u�ԁv����u�l�v���A�u�]�c�v�̊e��������u���v���A�u�V���v�́u���v���璆���̕��������ꂼ�ꌇ�����Ă���B����āA���̔������͎��̂悤�ɓǂނ��Ƃ��ł��悤�B
�u���ԁi�k�j�Ɏ�Ȃ�
�@��V�ɐl�Ȃ�
�@�e�ʂɖڂȂ�
�@�Ԏm�ɐl�Ȃ�
�@�]�c�Ɍ��Ȃ�
�@�V���ɕ��Ȃ��v
�i��ɂɂ͎Ȃ��B��V�ɂ͓K�C�҂����Ȃ��B���R�ɂ͐l�ނ�����ڂ��Ȃ��B���c���������ē����o���Ԏm�ɂ͐l�ނ��Ȃ��B�t���̕]�c�ɂ͈ӌ����Ȃ��B�V���ɂ͓x�ʂ��Ȃ��B�j
|
|
|
|
| 2013�N4��6���i�y�j |
| ���Ƃ��b�i���c����30�j |
88 �|�����l�䖳���Ɍ�A�Ɛ\�����ЁA�����l��o���Д퐬�A�������U��������j�t�A��ˑO���A�|�����l���n�A����@����
�y�����z
�E�u����@�����v�@���ۂ͎��D���Ă����ɂ�������炸�A��V�����Ɣ��\�������Ƃ𝈝��������Ƃ��b�͑����B��U�̌˂��J���āA�u����͂ǂ��������Ƃ��v�Ƃ��������̌��t�ɁA��U�̒��͓������ŎȂ��A�̈ӂ��|����B
89 ���̐ߋ�ɉ�U�̒��A��Ȃ������ʂ��͂������Ȃ��A��ɉƂ͂��߂ƂȂ肩�T��
�y�����z
�E�u��ɉƂ͂��߂v�@��ɉƂ͎��ŁA�̈ӁB
90 �Ȃ����s��
�}���̒��Ȃ����s���̂Ȃ����ɁA���̂Ȃ����̂���ƂȂ��B�㖤�̑��߂��ɂȂ��B���c�����Ƃقӂ��Ȃ��B����łǂ�����Ȃ��B��ł��Ƃ��ǂЂĂ��Ȃ��B��l���l�����d�����Ȃ��B���n�ǂ��ւ������ĂȂ��B���U���L�Ă������Ă��Ȃ��B�㐙�ҔԂ��������Ȃ��B��ԏ��ǂ��ł����Ă��Ȃ��B�Q�l�����㟆���Ȃ��B�e��掟�A�o�Ă��Ȃ��B������Ă����Ă��Ȃ��B�����ŋ��͍s�Ă��Ȃ��B���l��͊ۂłȂ��B�����Ŕq���Ȃ��B�]��̂��킬�͒m��l�Ȃ��B���[�e���n�l�łȂ��B�F���̉���킩��Ȃ��B�镪�n���ς�ʂ肪�Ȃ��B���l�����������łȂ��B�V���������Ƃ��Ȃ��B�S�[��l�O���Ȃ��B���ł͐��̒������܂�ȁi�}�}�A�u�Ȃ��v�j�B�v�ł���j�A�R�͂Ȃ��B�ǂӂ����������n�����Ȃ��B�߂��Ȏ��n���Ă��Ȃ��B�����Ȃ����烏����Ȃ��B����Ȃ��i������u�ȏ��t���ɂ��Ȃ��B�v�j���̂̂Ȃ��͂Ƃ����ꚽ���Ȃ��B�߂��i�}�}�A�u�ȁv�E���j�������ӂ��̂Ȃ��B |
|
|
|
| 2013�N4��5���i���j |
| �A�́i���c����29�j |
87 �A��
���͍���͍~��ǂ��퐶���ȁ@����
�@����n�ԉ̂�����c�̊O�@�X
�l�S�Ė�̌��̐��˂Ȃ�ā@�@�֓�
�@������ق��Ɉ��Ԕ��ց@�@�@�c
�E���̒q�b�\������Ƃ���@�@����
�@�����H�̕��������ʂ��@�@�@�A��
�א�����ق̍g�t����s�@�@���
�@���c��V�������̌��@�@�@�@�
���n�̑���葁���\����@�@�@�A��
���͎���̎���ʂ��́@��c
�b����Ȃ����҈������r�J�@�@���c�i�}�}�j
�����݂ɂ��ق鍑�̂����� �C��
��Ɉ䂯�����܂ʐ�̒��@�R��
�@���ʎԂ̂��j��Ȃ�@�@�@���R
�ʔ��������̎R�����n���@�@��
�@���h�召���V��Ȃ�@�@�@�@�X
�E�ꏄ�������
�ߌ��̓���o�@���Ȃ�
�E�V�O�ϒ��ʏV
�ۗ{����j�����B�V
�y�����z
�E�u���͍��c�v�@���q���G���{�\���̕ς��N�����ɂ�����A������b��ƘA�̂̉���Â����B���̍ۂɌ��G���r���傪�u���͍����߂���������܌����ȁv�ł���A��̒��ɖd���̈Ӑ}����߂��Ă����Ƃ����B�j���̗����́A��������~���ɂ��Ă���B
�E�u�l�S�Ė�̌��̐��˂Ȃ�ā@������ق��Ɉ��Ԕ��ցv�@�u�Ė�v�Ɂu�����i�₯�j�v���A�u�g�ƂȂ�āv�Ɂu���ˁv��������B�u�Ė�v�Ɓu������ق��v��賂̉���B�u�Ė��賎q�i�������j�v�͐e�q�̈���̐[��栂��B�q�������賂́A�g�ӂɉ������Ă��q�����̂Ă��ɏĂ����ʂƂ����B�w�L�����i��O�Łj�x�ɂ́u����v���u�ق��v��賂̖����Ƃ��邪�A�u����v��賂̖����ŁA�u�ق��v�͉H�ł��̉��Ƃ����i�R�������w����璹�̖����́x�j�B�u������ق��v�͜��Ái����ǂ�j�Ɋ|���āA�Ƃ�����ׂ��Ȃ��l��\������B�u賂Ȃ�ΏĖ�ł����Ă��q�����ʂ����Ƃ������낤�ɁA��ɉƂ̎��B�i�Ԕ����͈�ɉƂ̐��ł̕����B����Ĉ�ɉƂ��w���j�͎����ɂł��Ȃ����̂��A�Ƃ�������Ȃ��悤�Ɉ�������ł��܂����v�B
�E�u�E���̒q�b�\������Ƃ���v�@�����E�����\���������Ƃ����`�����ӂ܂�����B�w�O���u���`�x�̑�91��ɁA�\���N���̕��ꂪ����B����ɂ��ƁA�E�����_��̖Њl�𐧈����A冂ɋA��r���m���Ƃ�����Ɏ������B�ˑR�É_�����ꍞ�߁A���������������r�ꂽ�B�����A�m���ɂ͍r�Ԃ�_�����āA�M�������邽�߂ɂ�49�l�̐l�Ԃ̎�ƍ����E���r������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����B�����ōE�����m���̐_�̓{�����߂邽�߁A�l���̑���ɔ��������˂Đl���������ǂ点�A���̒��ɋ���r�̓����߂����Ă�����u�\���v�Ɩ��t���A�_�ɕ������Ƃ����B�������A���݂̒������\���i�}���g�E�j�́A���ɉ����l�ߕ������Ȃ��B
�E�u���c��V�������̌��v�@��@��h��ł����Ă��J�c�̂��Ƃ�c�t�Ƃ����A�����̑c�t�����c�Ƃ����B�����ł������c�́A���@�@�J�c���@���w���B���@���@������ꏊ�����q�̗����i���̂����j�Y��ł������̂ŁA�n���̗ގ����w�E����B
�@���@�͕��i8�i1271�j�N9��12���A�����i���_�ސ쌧����s�А��j�Ŏa��悤�Ƃ����B�����A�ÏP���̕s���ɂ��т��閯�O�ɖ@�ؐM�����߁A���@���������������@��h�́A���q���{�ɂ���āA�������I�Ȉ��}�I�������Ȃ��҂����Ƃ��Ēe�����ꂽ�B���@�͂��̒��S�l���Ƃ��āA�a��̊��ɂ������̂ł���B���@�����̂�����u�����@��i���i���N�̖@��j�v��Ƃꂽ�̂́A����ɂ��������������A���@���~�������ƂɂȂ��Ă���B�����́A�k�����@�̍Ȃ����B�א��̖��ŁA�厞�����D�����������߂Ƃ����B�܂��א��ɏ���ʂ��ċ߂��������@�̒h�z��w�O�Y�́A�א��ւ̓�������������������Ƃ��i�w���j�厫�T��9���x1988�N�A�g��O���فA�u�����@��v�̍��i���ؖL�����M�j�ɂ��j�B
�@�܂��A���@�@�ł͈�ɉƂƓ����k����g�p�����̂ŁA���J������@�ւ̘A�z���������̂ł��낤�B���@�͒剞���i1222�j�N�Ɉ��[�������S�����������̋��t�̎q�Ƃ��ďo�������Ƃ����邪�A���̉ƌn�ɂ��Ă͎O�����A�܂��͊і����̏o�ł���Ɠ`���Ă���i�{��p�C�ҁw���@���T�x1978�N�A�������o�ŁAP.7�j�B�і����͈�Ɏ����番���ꂽ�Ƃ����A���@�@�ł͋k���Ƃ����B�������A��ɉƂ̕���c�J�̍������͑����@�B
�@�����䏊��������@�Ɠ��l�ȓ�ɑ������Ƃ��闎��ɁA���̂悤�Ȃ��̂�����B
�u�k�Ɉ䌅�͑c�t�̖䏊���@�@�،o�̍Г�v�i�w�������ڒ����xP.396�j
�u�k�̌���ς藳�̌��v�i��P.404�j
�E�u�ߌ��̓���o�@���Ȃ��@�E�V�O�ϒ��ʏV�v�@�u�ߌ��̓��v�͑|�����B�|�������o�邵�����Ȃ��B�Ȃ��ȊO�͉���ʏ����Ȃ��A�Ɣ�����Ă���B
�E�u�ۗ{����j�����B�V�v�@��p�������|���Ă���B
�E���̍��ځi����j�A���Z���B |
|
|
|
| 2013�N4��4���i�j |
| ��Ɋ��ƌ������ĉB���A�l���o���i���c����28�j |
77 ��ɂ����ƌ������ĉB���l���o��
�y�����z
�E�u�������v�Ɂu��ɑ|���v��������B�h�q��������������A���˂́u�B���v���Ȃ킿����ď��ł���Ƃ������������������Ƃ�闎��B
78 ���{�Q�i�X�C�t���j�͈�ɂ��납�����b��
79 ��B������ɋk������
80 �����o�č��c�O�̑�ʂ߂�
�y�����z
�E�u�ʂ߂�v�͓D�܂݂�ɂȂ邱�ƁB�u�����o�āv�͐��˘Q�m��̏P���B
81 �����̒B�҂���đ|���i�J���j�Y��
�y�����z
�E�u�����̒B�ҁv�͐����i���j�j�̏n���҂̂��ƁB�u���v���琅�˂�A�z�����A�u�����̒B�ҁv�ɐ��˘Q�m�̈Ӗ������Ԃ���B���˂͐��{�����p�i���́u�̂��v�i���j���j�B����E�����g�ɂ��Ẳj�@�j�ŗL���ł������B�u�����i�ߎE���v�Ɂu�|�����Ƃ����߂�E�ł��̂߂��v�̈ӂ��|����B
82 �헤�V�قӂ��ł��ǂ��S�̂���
�y�����z
�E�헤�V�͕��������̓`���I�l���헤�V�C���i��������j�̂��ƁB���`�o�̉Ɛb�����ߐ�̐킢�ɎQ�킹���A���H�B��l�������͐l���̓���H���ĕs�V�����ɂȂ����Ƃ����B
83 ��ɂЂȂ̂����܂Ȃ���n�݂Ƃ��Ȃ�
84 �ԋS���Ĕޗ��̂���
85 ���̂Ȃ������̓o��͔�����
86 ���o�������ɈɁi�}�}�j�����n���ꂯ��
|
|
|
|
| 2013�N4��3���i���j |
| ���`�ŋߍ]�̕Ă̂͂����i���c����27�j |
68 ���`�ŋߍ]�̕Ă̂͂����A�V���Ƃ������A�Ђ˂��Ƃ�����
�y�����z
�E�u���`�i�܂������j�v�͊O���c��ƁA���ނȂǂ̌v�ʊ�ł���e�Ƃ��|���Ă���B��ق̏o������i�Ռ��i�������j�j�ɂ́A�G�̒��i��h�����߁A�݂��Ⴂ�ɂ����H��i�����������j�A��̑O�ʂ�x�E�y�ۂŖh�������n�o�i���܂����j�Ȃǂ̖h��p�{�݂��݂���ꂽ�B�e�i���j�`�����̈�ŁA�x�ɂ��������̓����ɁA��E�y�ہE�x�E�E�Ȃǂ��͂�ŕ��`�̋n��݂������̂������B���̗̂R���́A���̕������e�̌`�Ɏ��Ă���Ƃ��납��A�܂����̏ꏊ�ɓG�����߂�Ƃ��납�炫���Ƃ����B�]�ˏ�O���c��́A��������������e�`��\�̈�Ƃ��Ēm����B���̑��e�`�̈�\�ɂ́A�]�ˏ鐴����E���c����A�����ΐ��A�ۋT�����Ȃǂ�����i�w���j�厫�T13���x1992�N�A�g��O���فA�u�e�`�v�̍��A���䐹���j�B
�E�ߍ]�͕F���˂̘A�z�����ɂ��w���B
�E�u�ʂ�v�Ɂu�d��v�A�u�V�i�V�āj���v�Ɂu���v��������B�u�i�Ђˁj�v�͌ÕĂ̈ӁB
�u�ߍ]�Y�Ă�e�Ōv�ʂ��������A����l�͐V�Ă��Ƃ����A����l�͌ÕĂ��Ƃ����v�̈ӂɁA�u�e�`�i�O���c��j������ň�ɑ�V���͂��育�Ƃɂ���Ďa��ꂽ�Ƃ����B��������������A���̐����̒��͔��R�Ƃ��Ȃ��v�̈ӂ��|����B
�y�Q�l�z
�E�u���`�ŋߍ]�̕Ă̌v�肫�ꂵ�����ӂЂ˂��Ƃ����Ӂv�i�w����N�^�x�j
�E�u�݂ƑC�ł͂���肽��ߍ]�Ă��Ƃ����ЂЂ˂��Ƃ����Ӂv�i�w�������ڒ����x�j�B�Ȃ��A�u�݂ƑC�v�́u�݂Ɓv�ɂ́A�u���Ɓv�E�u���ˁv�E�u�O�l�v�̎O�̈Ӗ����|���Ă���Ƃ����i��؞��O�Ғ��w���T�x�������o�Łj�B�܂��u���v�E�u���v�E�u�͂���v�͕Ẳ���B
69 ��Ɏ����v�Ђ̊O�̑|�����Ƃ��Ă݂Ƃ��Ȃ�����
70 �t�Ȃ�o�O���c�ň�Ɍ��ܐ��˂��Ȃ��قǎU�肤���ɂ���
�y�����z
�E�u���܁v�Ɂu���ԁv���|����B
71 ���c�Ĉ�Ɋ�����ɓ���Đ��ĕԂ������
�y�����z
�E�u�������v�Ɂu��ɑ|���v���A�u��v�i���̎�j�Ɉ�ɂ̎�̈ӂ��|����B
72 ��ɑ|�������荞�~�ɂ������ĉ�c�ւЂ��ǂЂ��ʓV��
73 ���c�֖���̕��̗U�З��Ă��炷�퐶�̂����͈�ɉ�
74 ��܂Ă̒��݂�Ȑ��˂̖A�����ނ��r���t�������ʂ�
�y�����z
�E�u���̖A�v�ɐ��˂̈ӂ��܂܂���B�u�����ށv�͑|���ɉƖ���|�����B
75 ����Ƃ��ɂ����Ǝv�ЊO���c���˂��O�ɐ�l�͂Ȃ�
76 ��ɉԂ��炳����c�Ƃ����Ђ��ɏ㖤�̐�ɂ��ق�͂��Ȃ� |
|
|
|
| 2013�N4��2���i�j |
| ������Łi���c����26�j |
61 ������ʼnΓ�ş�������Ŗ�����ň�ɋ�J����
62 �t�Ȃ�ΊO�̍�����ɉԌ����˂��Ȃ��قǎU��ɂ���
63 ��Ɏ������f�����̂�����܂肩���Ƃ̎n���͐��˂��Ȃ����
64 ��Ɉ�ɂƐ��˂��Ȃ��قǂ������ł����Č�����o�������Ȃ�
65 ���˂��Ȃ����̂Ƃ͂��ւǍ��x�͐l�͕��m�Ԃ͂�����c
66 ��ɂ����ƌ��Ƃ߂Ă�����T�S�ɐ��Đ���Ԕ��ւȂ�
�y�����z�u�Ԕ��ցv��NO.9���Q�ƁB
67 ���o�ēn�肠�ӂׂ��l���Ȃ��O������c�̐�̏�
|
|
|
|
| 2013�N4��1���i���j |
| ��̒���߂��i���c����25�j |
59 ��̒���߂��A�����ǂ��͂��܂鐅�ˑ|���A���s�n�т��肬�悤�ĂA�܂ǂԂ������炳�킬���āA�����߂��o���������A���狏�̎蔲�łւ�����ƃn���������˂ցB��l�����ăn�����������A����܂�Ȃ��낽�ւ��̂ƃ���Ђ܂��B�ЂƂ���������ʂƃn�A�M�������т₤�Ȃ����ނ炢�B
�y�����z
�E�u���s�v�@�����s���i�����̂��݁j
60 ��B�̂炤�l���A��̍~�̂ɂ������������܂đ��k���A���悢�悠���Â��ƂƂ̂ւāA���O�ɐނ��ӁA�悤���̒������܌䂩����ڂ����đō��n�A�����ނ��炵����ʂƈ��o���A�Ȃ�̂����Ȃ��{�]�Ƃ�����A�C�̌��̘e�≮�~�������Ă����B
�y�����z
�E��50�̗����ɓ����B |
|
|
|
| 2013�N3��31���i���j |
| ���c�s�i���c����24�j |
58�@�N�c�s
�O���O���V���B�N�c��O�l�ח�B��V��`�~�o��B�����ފԑM���S�B�q�����N�N���x�B�����f��瞑N���B�{�X�V�����B���k�����B�������X�����T�B���������s�����B�����ƕS�N�B�B�̕��Xᶋ���B�꒩�|�{�����Q�B���^���\�`�s���B�N�s���J�ԏ��ЁB�R���v�s�Ր痢�O���J�B
�y�����z
�E�w�������ڒ����x�ɗޕ�����B����P.441�Ƃ̈ٓ��͎��̒ʂ�B
�@�@�u��V��`�~�o��v���u��������~�o��v
�@�@�u�M���S�v�@�@�@�@���u�M���S�v
�@�@�u�q�����N�N���x�v���u�������N�N�\�x�v
�@�@�u�{�X�V�����v���u�{����o�V�����v
�@�@�u�����ƕS�N�v�@�@���u��S�L�]�N�v
�E���̍��ځi����j�A���Z���B
|
|
|
|
| 2013�N3��30���i�y�j |
| �������������䗤�ځi���c����23�j |
57 �������������䗤�ځA�����Ă����ւ����悱���A�䋟���т��肤�낽���āA���ւ��ւ�����ăn������܂���A�ނ��̂����Ȃ�n��ӂ��Ɏ�܂���A������������܂��A����ꂨ���т₤�Ȑl���Ƃʂ��͂Ȃ��A�Ȃ�̂����Ȃ���c�ʁB
�y�����z
�E�u���ځv�@�Z�ڂƂ������B�]�ˎ���͎G��l�̑��̂����A�����ł͉����l(������)���̂��ƁB
�E�u��c�ʁv�@�Γ�e��10��i��37.5�O�����j�ʂ�����Ĕ��˂��邱�ƁB�܂��͂��̒e�ۂ������B
|
|
|
|
| 2013�N3��29���i���j |
| �V����ڂ���Ԃ��i���c����22�j |
56�@�V����ڂ���Ԃ�
��X�����Ԃ��ɂ�
���������F���ЂĂ��N���˂ցA��������x��Ɏ�������A���c���̑�����O�A�ꏊ�͂����炩�A�܂Îs�V���\���̑��܂�O�ŁA�l�\���l�O�\�̂��āA�����藧������\���l�ŁA�c�����̏o�̎t��������A�`���g���悫�ƙ�˂ցB�N�͈������c�̐\�ŁA���͎O���㖤�̐ߋ�A�����喼�̓o��̐܂���A�ނ˂ɑ��}�̔��q�ؑłāA���̘L���̈⍦����Ȃ���ǁA�t���������Ǝ肮���ˈ��āA�҂Ƃ��m�炸�Ɍ��ӂ̕����A�Ղ̈Ђ�����l���Ȃ�ǂ��قӂ��قӂ��Ɣ��͔��̎��A�����͂փm���B���̌҈��A�̏o���ŁA���킸�ƒm�ꂽ�����̎����t���ƁA�����葁���A�ʂ��ӂ炸�A�ؓ��N��A�����ɂ�����ĂӂƂ������ӂ�A���o�X���a�A���Ɉ�l�t������́A���Ă̒��ɂĎv�Ă��Ր�A�l�ɂ���ĎO�r�̗��H�B��͓��ɁA���炾�n���ɁB�͂Ȃ�͂Ȃ�̐l���Ȃ��n�A�\�R�j��l�A�������ɓ�l�B�r���Ȃ��Ƃ��V�����Ȃ��Ƃ��A���낤�낤�낽�֎�l�̊�����Ȃ��瓦���ĉ��~�j�A��́A�{���Ď�̕��ƃn���ւǂ��A�]�肽�킯���n������˂ւ����ցB�\���n�M�u�\���l�n��𓁂ɋT�q�̗l�ɂ��܂��������ƈ����ォ��A�O�ɂ���ڂ��������Ɏ����ʁA���炢�����ă\�m��R�`���j�n���ĉ������B�悭�����ꂽ�������Ȃ����ցA�T�z�h�ق����͐��Ȃ�Ƃ��A����o���Ԃɂ������n����A���N���Ȃ���Ǘ��Ă����₵��A�v�ɂ������������q�䐭���n���X�̉��~�֗��W����Ȃ�S�{�����Ă��ꂵ�ӂȂ��Ȃ��A���킯������c�A�P�P�����������a��l�A�\�m���̎����狟�𑝂���l�����o������A�T�z�h�������������Ȃ�A�܂�Ō����f�\�āA�V�����܂�߂ĖV��ɂ��邩�A�Ђ��̂͂��ĉB��������̂��A��c�O�c�����g�̂������A�T���h�C�̂���h�F�����n�A���ʂ炪�~�ӂȏ����Ȃǃn�A�ڂɂ����Ȃ��A���S���Ȃ����A�T�A���h�������m���Ȃ��Ȃ�A�����c��̈Վ҂𗊂�ŁA�˂ցA�����L���ƌ�߉ނ���ł�����ꂽ���t���A�R���n��O�Ɉ�ɉ��߂ŁA�����̑������S������ցA�ȃ��ЂƂ肪��Ȃ�����ŁA���Ԃ̎J�������R�ɂ����ցA�l�̂���݂��~�����Ȃ�āA�x�m�̎R�������ƍ����A�ɐ��̊C��胂�`�c�g�[���A���n���Ƃ��炭����̐Չ��Ă��y�ʂ悭�����Ԃɂ���ꂽ�ׂ�{�E�A�Ђ��ӂȎ��ɂĎ������ƌ��ӂĂ��A�e�n���炷�Ƃɂ풹�Â炩�A�����̎��߃n����������Ȃ����ցA������F����A����t���Ă����Ăȏ��ň��̂�����A�T���o�V�����䕐�^���v�A��q���ɐ��A���X�N���A�ۂ�����A��߂Ă���
�y�����z
�E�u�V���v�@�Ă��B���̂��ƁB
�E�u�����L���v�@�����L���i������傤�䂤�����j�̌��B
��U����߂Ă��܂������͂���ȏ㏸�邱�Ƃ��ł����A���͉������Ȃ̂ʼn���������Ƃ����ӁB�]���āA�x�M��h�B�����ߐs�������҂́A�K��������Ƃ������Ƃ̔�g�B |
|
|
|
| 2013�N3��28���i�j |
| ���ׂ��ׂ�����ڂ���i���c����21�j |
55 ���ׂ��ׂ�����ڂ���
�������������A�݂�Ȃ����Ă邱��ǂ̑����A���ׂ̂�ڂ��A���{�ɐ���āA���{�̂߂������āA����舫�S�܂ʂ��ŁA�ӂʂ��ŁA���a�݂��ŁA�|�炩��ЂāA�|��j�āA��т��ɂ�邵�āA�������́A�J蓈ȗ��̒p�Ńn�˂ւ����A���㞊�̔s�����̂����点��Ȃn�A���̂ꂪ�p�J�𐢊Ԃւ��点�邠�ق��̌��肾�A�_�Ђ����ɒ��������߂ċ���Ƃ肽�āA���ׂ����Ӑl�����炩���Ă��A���̂ꂪ�s���ɂȂ�Ȃ��l���o�ނ�݂Ɏ��āA�厖�̐������Ђ�ł���ƃn�A�ǂ���������A���������݂���Ȉΐl�������߂āA�]�˒����邩���A�_�ИŊt�A�Ԃ���r�̂ւǂɂ��q�����A�ւ�ڂɑ傫�ȓ���Ȃ��������Ă݂���ǁA�ΐl�Ɏ����A�˂��݂���ɂ������Ă����ƃn�A����܂�p����A�܂��܂����邼�ցA����Ȃ̂��Ƃ����i���A��т��̂��̐}���Ɠ��l�A����������߂����A��Ќ����Ƃ��āA�Ȃ炱����A��ꂷ�܂˂ցA���s�����܂��āA���l�l���ᒺ�ɂ���Ƃ͕s���̈��A����܂肷�܂˂ցA���Վn��A���F���s���ŁA�Ȃ�ł������A���Ă��܍��ŁA���������S���A���ނЂ͍����āA�����Ƃ������āA���Y�������āA�����ƒҐނ�݂ɂ͂�āA���ɂ��@�ɂȂ邩������˂��A�厖�Ȃ����������ւĂ��Ȃ���A���̓��≎�y�A��ۂÂ݂ŗV��ł���ƃn�A�������������A�Ȃ�ł����܂փn�l�ł͂Ȃ������A�ǁX�������̂Ă��邩��A�V�n�̐_�X�A���������Ă����A����ɂ�Ԃ�����Ƃ��Ƃ��ꂽ���A�����܂̋F������Ƃ������Ȃ��A�������̊O�����{�ŋ������A������Ƃ��Ă݂ɂ���ɂ��܁A�@�̈ΐl��M���邩��A��Ђ����Ă͂�����̖{���݂��悾�A�؎��ł�m�〈�Ȃ����A���킸�Ƃ���Ă�V���Ȃ邼�ցA�������Ɉ�̐�X�@�̊Q���i�}�}�j�̂���āA�V���̏��l������ǂ̂����ЂŁA�����瑾���A����̂��l���o���Ȃ�A�܂��܂����ԂȂ��A�悭�悭�C��t�A�˜��Ɖ��a��߂Ă��܂āA���m���݂����āA�N�ɂƔᔻ�̂����ʐ����A�����肤��A���₭�ɂ�
�y�����z
�E�u���ׂ��ׂ�����ڂ���v�@�u���v�́u������i�|���j�v���Ђ�����Ԃ������́B��ɑ|�����̂�������Ƃ͑S�Ă����ׂ��ׂ������Ɣ���������́B
�E�u�|��j�Ă�т��ɂ�邵�Ē������v�@�����̑c�@��j��A�A�����J���̎��^�E���[���g���n���X�ɓ��ďC�D�ʏ�������������̈ӁB����5�N6��19���i1858�N7��29���j�A�A�����J�R�̓|�[�n�^������Œ���B���{���S����㐴���E�␣���k�B�������i1860�j�N�A���V���g���Ŕ�y�������B���O�@����F�߁A�Ŏ��匠�̌��@�����s������������߁A�������ɏ����������܂ŁA���{�l�͂��̕s�������ɂ���đ傫�ȕs���v�������B
�E�u�͂�����̖{���݂��悾�v �\���˂̃L���X�g�݂������A�̈ӁB
�E�u�؎��ł�m��v�@�m��ɍ�����Ă���ё����A�܂�Ő��̂悤���Ƃ��������́B
|
|
|
|
| 2013�N3��27���i���j |
| ����ڂ���i���c����20�j |
54 ����ق���
�����F���Ă�����˂ցA�㖤�̐ߋ�œo�������ƂāA�o�������Ƃ��낪�A���˂̘Q�l�A�}�⍇�H�ő��g������āA���������ɑ҂ӂ����ċ��āA�拟������A���đi�̐^�����A����̂��̂ɂāA�����܂����߂��Ɛ�����������A���Ԃ����Ȃ��A���肿����A�l����獏o���A�k�}�̒��ł��A�蕉�̂��̂ǂ��A�V�����~�����i����҂��A�א��ւ������ނ��̂��A�������ɂĕ������A�O�㖢���̑呛�����ƁA�̑�����m�ċ��Ȃ���A����܂����f�A�͂��ŕ��Ă��c�O���ɂ��A�v���痂���l�Q�q�́A�����ƒ��䗘������ӁA���肪�����ƃn�v�ċ����ƂāA���P�Ă���Ă����t�܂ց���A���Ƃ֓V��ƕ]�������ƂāA���^�ԂƂ�̂��Ԃ�҂ǂ��A�_�̂��������ɂ�������ӁA�����ߗ��̖��Ƃ̎���ցA�����l�ƂČ䕠�����܂���A��l�O�ƂĕK���̑F�c�ŁA�����牽�܂œs������낵���ςނł����炤���A�����l��Ă��͂܂��܂��A�ǂ��Ȃ鎖��炿�Ƃ��킩�炸�A���t�k�}�A�c��̎҂ǂ��A�ЂƂ���c�炸�E���Ďd���āA�����t��������A�Z�\�]�B�̏��l�����S�A������ӂ܂Ŏ�����A�x��͂₵�ĉԌ��ɏo����A���~�ɏo����A����͔ɐ��A�V���ו��A�ق����ق���
�y�����z���̍��ځA�e��{�̕��������ʂł����i����j�A���Z���B
|
|
|
|
| 2013�N3��26���i�j |
| ���s�����Ԃ��i���c����19�j |
53�@���s�����Ԃ�
���������F����A���x�̑�ւ�A�����Ȃǂƃn�[��̂��炲�ƁA�O���O���j�ӂ�o���s��A�Ђ�Ȃ����т̂������Ə����A�O�㖢���̙�̎n�����A����Ђ�܂�ŕ��Ă�����˂ցA���炪�ƂȂ�̖����ƂȂ�́A�����炪�V���̐^������Ƃ́A���邤��݂̎R�����Ђ��A�����������{�̏��R�n���ɁA�����������̋F�����������A���������낵�j��������s���A���c������ŋт̌���̂����ȂǂƂ́A���炴��B���̂Ђ␅����܂��A�����т����A��Ƃ�A�ҔԐe���̂����܂łƂԂƃn�A�̗t�V��̏��ׂ�������Ȃ��A�ǂӂ������A�A���ӂ������ƍ����ʂ����āA���c���]�c���A�Ȃ������قł܂��ɂʂ���A���̒p�J�n���コ�߂܂��A�F���ւĂ��܂��̖�l�A�ǂӂ�����Ȃ����܂߂̎�������A����łӂ��߂邨���₯�����ɂ��A���������̂ɂ͂ӂ��߂����킬�ŁA�O�\�܁��̏��ʗl�q�ɂƁA�͂����o�����邻��͂ǂ���ŁA�o�����铹�y�ނ����n�O������Ё��˂̍��Y������A�U���đ厖�n�䂽������̂Ȃ�ܖ{���ĂӐ�́����́A�����Ȃ߂�������Y����V���ו����y�����A���T��ř�����ꂿ���
�y�����z���̍��ځA�e��{�̕��������ʂł����i����j�A���Z���B |
|
|
|
| 2013�N3��25���i���j |
| ���w�i���c����18�j |
52�@�B�����펪�|�����ق�����O�x�Ɉ�x�͎E���S�Ȃ�܂��قӂ��قӂ�
�y�����z
���w�u�����q���펪����A�G���ق�����A�O�x�Ɉ�x�͒ǂ킸�͂Ȃ�܂��A�̂ق�ق̂ق�فv�̂�����B�����q�͓c�Ɏ҂ُ̈́B���̉S�ɍ��킹�Ċ��m�ȗx���x�����B�B���́A���˂̉B���i����ď��j�B |
|
|
|
| 2013�N3��24���i���j |
| ���Â�������ڂ���i���c����17�j |
51 ���Â�������ق���
�e�ʂ܂ʂ��ň�ɂȂ�قӂ����A��l�ӂʂ��ňٍ��ɂ���܂�A��ɂ��щ�U�ʂ��A���܂��Ɏ�ʂ��A���Q�ł��]�˂�獂ʂ��A����J�͎蔲�ŕ傭��āA�����a�V���n�g�ʂ��̎x�x�Ō�������A�א삩���ʂ����Ƃ̂߂��킭�A�����̉B���͎�݂ĉx�сA�����������炸�ɕF���̍����Ɠ���u����A���낻���ʂ��Ƃ���ǂ̂����܂���ʂ�����V���o�����o�Ȃ�܂��A���̓Ő疜�A��l���ʂ��Ńw�h���h�w�h���h�}�S�}�S�}�S
�y�Q�l�z�w������ڒ����xP.408�ɓ�������B |
|
|
|
| 2013�N3��23���i�y�j |
| ���Ƃ��b�i���c����16�j |
48�@���͂Ȃ�
�����Q�l�A�O���c����䉮�~�䌺�֍]��o�A�����͉��r����s���V�`�L�V�A����A���V���f��փn�������V�R�A�䑊������V��ƂƁA�䌩���\�q�́A��掟�i�C�i�C�Ɠ���
�y�����z
�E�u���X�i�����ɁB���ւɁj�v�Ǝu���������v�B
49�@�ܑ��
�@���˂Ƃ̋��ɂ��܂ł��A�Ȃܒ��܂ăo�������ЁA���Ƃւ�����Ē��ӂ�ƂĂ��A�B�����߂̖����܂A�A�V�Ȃ�Ƃ���ӁA������ɂ̎��łƂāA���炽�͂Ƃ�ʌܑ�V�A���킳��Ȃ���|���q�b�Ȃ�����ӂ����A�ڂČ����悼�֏ӂ��ցA��(�Ϥ��٣��)������Ƃ��A������
�y�����z
�E�w������ڒ����xP.425�ɓ�������B
50 ��B�̘Q�l����̂ӂ�̂ɂ��T�������W�đ��k���A���悢�捇���Ė���ނ���ɐނ��ԁA�p�ӂ̎킩�����U��ڂ����đō��n�A�����ނ����ނ����A�e�ʂ����o���Ȃ�̋���Ȃ��ق�]�Ƃ�����A�C�̌��̘e�≮�݂������čs
�y�����z
�E�u�C�̌��̘e�≮�݂������Ă����v�@�֓��E����E����E�@�c���4���́A���˂Ă̎蔤�ʂ莩�i���邽�߁A�C�̌��ɂ������V���e�⒆��������̉��~���������B
�y�Q�l�z
�E�u��B�̘Q�l����̍~�̂ɂ��R���������܂đ��k�����悢�悠���Â��ƁR�̂ւĂނɂނ���ɐނ��Ԃ�ӂ��̎킩�������Ă�ڌ����đō��߃n�����ނ������e�ʂ����o�����̂����Ȃ��ق�܂ӂ𐋂����ĒC�̌��̘e��₵���������čs�v�i�w����N�^�xp.395�j
|
|
|
|
| 2013�N3��22���i���j |
| ���c�̕ώ��i���c����15�j |
42�@���c�̕ώ�
��ォ���ď��̂˒���̂Ђ����܂Ő��͍s�͂Ȃɐ�Ȃ�
43 ��ɂ�ӂɂ��܂��ł��ΐ��˂��Ȃ��A���Â�|���Ɍ���捹��
�y�����z
�u��ɂ��A�Q�m��̎v������x���������ꂽ�݂̂͂��Ƃ��Ȃ��B����ȕs���_�ȗL�l�ł́A���Âꖋ�{�����ɉƂɑ��A�Ɩ�Ɋւ���荹�����Ȃ����悤�v�B
44 ���̐ߋ�����������Ⴊ�ӂ�
�y�����z
�@���͍��c����|����B�������������Ԃ��B
45 ��ɒj���߂Ė��r�֏헤��
�y�����z
�@�ł��̂߂��̈ӂ́u���߂�v�̌ꂩ��A����̑т������Ă����B���y�ցu�����v�ƌ��������āu�Ђ����v�Ƒ������B�헤���͐��˂�A�z�B�헤�т͎����_�{�̐_���B����14���̍�̓��A�j�������̂��̈Ӓ��̎҂̖���z�тɏ����Đ_�O�ɋ����A�_�������������ʼn����߂����̐肢�B
46 ���c�������邭�Ȃ�n��ɂ����
47�@��ɔn��������h�ď����
|
|
|
|
| 2013�N3��21���i�j |
| ��Ƃ������������Ă݂�Ɓi���c����14�j |
39�@��
���Ă���������猩�Ă���{�_�܂ނ��Ƀ~��͈�ɂ̂ւ�ڂ�
�y�����z
�@�u��v�́A�k�ƕ��Ԉ�ɉƂ̖䏊�ň䌅�i�䓛�j�B��̎��͏c�E����{�_�̑g�ݍ��킹����ł��Ă���B�^�����i���ʁj���猩�Ă݂�ƁA����͈�ɉƂ̖䏊�䌅�������̈ӁB��{�_�́u�ڂ��v����u�ׂ�ڂ��v���A�u��ɂׂ̂�ڂ��߁v�Ƒ�����B
�@�ׂ�ڂ��͐l��l��}��Ƃ��ɂ�����B�n���E�����̗ށB�֗��V�E�V�Ƃ��������A�{�����_�ŁA�����̂��ƁB���ɂ��Ă������ĝ��蔫�ɓ���A�_�Œׂ�����i���Ƃ��B�Ă��璼�ڍ�����c�q�̂��Ɓj��������Ƃ��납��A�_���u���ׂ��v�Ƃ��������B��������A������H�ׂ����Ŗ��ɗ����Ȃ��l�Ԃ�l��̂Ɂu�ׂ�ڂ��v�Ƃ������̂��Ƃ����i������V�w�H�ׂ���{�j�x1996�N�A�������ɁAP.170�`172�j�B�������A�O�c�E�ҁw�]�ˌ�̎��T�x�i1979�N�A�u�k�Њw�p���Ɂj���̑��̎��T�ނ́u�����N���A�S�g�^���œ��s�����A�ڂ͐Ԃ��~���A��͉��̂��Ƃ��b�l�̌������ɏo������n�܂�v�i�u�ׂ�V�v�̍��j�Ƃ̌ꌹ�����ڂ���B�������A���́u�b�l�v���Ȃ��u�ׂ�V�v�Ƃ������̂��͖��ځB
40 ���͔��A��͉��F�Ėʂ͐A��n�܂Ԃœ��͐^��
�y�����z
�F�s�����ł܂Ƃ߂��B
�E�u���͔��v�@�����܂̐F�B
�E�u��͉��F�v�@��ɉƂ̎����̌I�F�Ȃ߂��̏���A���F�ƌ댩�������i�w�������ڒ����xP.398�j�B
�E�u�ʂ͐v�@���|�Ŋ炪���߂��̈ӁB
�E�u��n�܂ԁv�@���c�@�̕\��͎�F�B
�E�u���͐^���v�@���̒��͐^�����B
41 �����͐��m���̓S�{���Ȃ����łȂ��A�|��������������
�y�����z
�@�u�ŋ߁A���[���b�p���̓S�C��ł��Ȃ��̂͂ǂ����Ă��v�̓�|���B�����́u�Ζ傪�������i��ꂽ�j����v�B����ɁA�|�����̕����̈Ӗ����|����B
|
|
|
|
| 2013�N3��20���i���j |
| ���c�̐��i���c����13�j |
38�@���c�̐��@�@�@�@�@�@����J�̗܊�@ �@
�@�@ ��ɂ̔��������@�@�@�@����̋A�� �@
�@ �@�㖤�V���̐�@�@�@�@�@�|���T�^�̐s
�@ �@�Ɠ��T��̉J�@�@�@�@�@���Ԃ̉i��
�y�����z
�E�n�Ái���傤���傤�j���i�̂�����B�n�Â͒����Γ�ȓ���̓���ɂ����n���ƏÐ����w���B���n�t�߂͉��i�Ɍb�܂�A�R�s�����E��������E�����[�ƁE���Y�A���E�]�V���E����H���E�n�Ö�J�E�����ӏ����n�Ô��i�ƌĂB����ɂȂ炢�A�ߍ]���i�E���˔��i�ȂǏ̂�����̂����{�e�n�ɑ�����B
�E�u����J�̗܊�v�@�Q�m�����͈�ɓ@�̔��Α��̓���J�����A����F�݂͊ɂ����ĒC�̌����ʂɌ��������B
|
|
|
|
| 2013�N3��19���i�j |
| ���c�֖���̕��̗U�����āi���c����12�j |
28 ���c�֖���̕��̗U�З��Ă��炷�퐶�̂����n��ɉ�
29 ��܂Ă̒��݂�Ȑ��˂̖A��������r���t�������ʂ�
�y�����z
�@�u���˂̖A�v�͐��̖A�ɁA�u������i�Ɩ�j�v�͑|�����Ɋ|���Ă���B
30 ���T�����ƂĂ����ĉB���ጩ����
�y�����z
�@�u���T�����v�͈�ɂɊ|���Ă���B�u�Ă����āv�́u�}���āi���傤���āj�v�B�u�}���v�͕����ǂ���u��������B���炩���B���ɂ���B��M����v�i�w�]�ˌ�̎��T�x�u�}���v�̍��j�̈ӁB��ɂ̉������A���˂̉B���i�ď��j�������C���ƚ}���Ȃ���ጩ�����Ă���A�̈ӁB
31�@�O���c�̑�����
���͂˂̕��̂��炵�̂���З��ĉԍ�~�����u��̂ӂ邳��
�y�����z
�@�}�g��i���ˁj�͈�錧�̒}�g�E�V���E�^�ǎO�S�ɂ܂�����W��876���[�g���̒}�g�R�̂��ƂŁA���˔˂������B�u�u��v�͔��i�Γ쐼�݈�т̌ď̂ŁA�F���˂������B�}�g�E�u��Ƃ��×��̖̉��B
32�@�F����̌���l��
�N�����ߎ̂閽�͂������炵��ǂ̍����ɖ������Ƃ߂Ȃ�
�y�����z
�E�u��ǂ̍����v ���i�ΐ��݂̔�ǎR�̂��ƁB���`�ɂ͖H���R�݂̂������A�L�`�ɂ͂���ɑŌ��R�A���ރP�x����������ǎR�n���w���B�ߍ]���i�̈�u��ǂ̕��v�ŗL���B
33�@�T�S�l��
���́T�ӂ̓����͂킯��������ɂ����������̖�������������
34�@���Ƃ��ɂ����Ƃ����ЊO�����琅�˂��O�ɐ�l���Ȃ�
35 ��ɉԂ��炽�ƌ���Η��ԔT��������Ȃ��ł��˂��Ƃ�ꂽ
36 ��ɉԂƂ��ӕF���̂��������o���Ď����琅�˂��Ȃ����
�y�����z
�u�����iጁj�v�͔~�ł̑��́B�Ԃ̂悤�Ȕ��]���o���B�~�łȂ�@������������B��ɂ͕@�Ȃ�ʎ��������݂��Ƃ��Ȃ��i���˂��|����j�A�̈ӁB
37 ��͔���c�������̒��ɉ��Ƃċ��͂����Ȃ�����
�y�����z
�@��V�̎�сA���c��O�ő���N����悤�Ȃ��̎����Ȃ̂ɁA�ǂ����ċ���肪���Ȃ������̂ł��낤���B
|
|
|
|
| 2013�N3��18���i���j |
| �����i���c����11�j |
25 ���c�������g�ԁA�H�T�������̍��A����F�O�l�[�A�ԋS�ߐ��@�V�L
�y�����z
�w����N�^�xP.395�ɓ�����������B
�u���c������A�g�ԂɎ�����B�H�T�A�������������̂�̍��B����A�F�ׂ��O�l���[�i�����j�B�ԋS�߂ɐ��ӂ��ƁA�V�L�̔@���B�v
26 ������s��A�����]�ˊJ�ȗ��A���I���O�Ύ��A�ǎ��V���痢�@
�y�����z
�w����N�^�xP.395�ɓ�����������B
�u�����̎�сA��炸�B�����������A�]�ˊJ�����ȗ��B�ւɋ���A�I�ɊO�̎��ɓ���Ƃ��B�ǂɎ�����A�V�Ɍ�����A�痢�̊@�i���������j�B�v
�i��V�̎��ꂽ�܂܂ŕԂ��Ă��Ȃ��B����Ȃ��Ƃ͍]�ˊJ���ȗ����������Ƃ��Ȃ��B���̂悤�ȑ̂��炭���O���l�̎��ɂł���������ǂ�����B�j
27 �`���l�\���l�ӁA�u��v(����)���u���v(����)�ᒆ�S�N�v�A�C�v�����s�D�A��D�]���O�R�t
�y�����z
�E�u�`���l�\���l�Ӂv�@��ɂ��P�������˘Q�m������ԕ䎖���̎l�\���m�Əd�ˍ��킹�A�u�`�͎l�\���m�̈ӂƓ������v�Ƃ����Ă���B
|
|
|
|
| 2013�N3��17���i���j |
| �ς��鍦�ݐ�̍��c�i���c����10�j |
24�@�ς鍦��̍��c
�����T�鎡���̌�㒆�ɁA�������H�Ȃ�ɁA�������ɕt�Ă��A���˓a���v�ЉΌ��~����߁A��̌�ɋq�Ɛ���A�Ђ��ӂ̂���Ȃ�ނ��₩�ɁA��l�蛇����̏Z���ƃn�A�j�����낷�������t�A���͕v�Ɉ��ւāA������̛�q�����܂��A�p���������݂̊}��A�A���͂ɂ��낻��ƁA���c�߂����s���āA�َq��̌����ɗ��x��ЁA���ӂ����ӂ����ƌ�p�S�퐬�܂��A�킽����S�{�ł܂����́A���֒ʂ��ĉ������i�A�A���������ǂ�������u�A������炠�₵�����̂��������ցA�u�����₵���ƃn���҂���A�Ɖ�U�T�˂���ɗ��ӂ�����A���T��M�l�n�T�S����i�A�A�����ɎP�������T���A�����c�։����ɗ����̂���A�u�A�C�A�킽�����ɓa�֍�����ҁA���ł��ĉ������i�A�A�u�Ȃ�قǁA���ɓx�͎E���Ă����ӂ��A���r���L���A�u�C���R�R���̂�ӂɁA�[��n�䂴��킢�i�A�A�u�肵��ł��Ȃ��n�A獍s���n�Ȃ��Ȃ��
�u���A���̂�ӂɂ��͂��Ƃ��A�������n���G�ł���ӁA�u�n���]�ʂ��Ă�肽���̂ӁA�u����Ȃ�o�A����J�]�ʂ��Ă����܂�ӂ��A���T�S�A����Ȃ炨�ꂩ�q�鎖�����邪�A�v����V���邩�A�u�����A��炪�o�ւċ��鎖�Ȃ�A�Ȃ�Ȃ�Ƃ��\�ĕ����ӁA�n�C�i�A�A�u��A��ꍇ�_���䂩�ʁA�u�����}�A�A�����ցA�u�T�A�A����n���������l�̕����n�A���߂�̔������ӂ��āA�g�ɂ��܂��錌�܂Ԃ���A���̓��S�䉮�~���Ȑl�����t����A���͒ʂ��ʂ�Ȃ�ǁA�����𑴖��ǂЂ��͂������a�A���Ȃ���Ȃ�������l�ɁA�����ӂ�����[�s�G�̂��ӂ���́A�ǂ����ӂ肭����������ʁA�u����Ƃ�A��n�헤�o�́A��̐�����ʂڂ����₭���l�A�Q�l�̐g�ɂĎ��ӂ���A���R����n������ǁA�o��̓���m�Ȃ���A�Ȃ������Ђʂ��ʂ̂���A�����g�������Ƃ́U�����A�S�������߂Ă���킢�i�A�A�V�e�{�]�ƃn���Ȃ�A�u���̈������Ԑl�̂��ЁA�������������ɂ͂����ʒq�b���H�v���捹�����A�����ЂȂ��܂ł���Ƃ��ɏo�čs���̒u�n�A���Ў��Ńn�Ȃ������ȁA��ڂɂ��T����͂Â������A�����̌��̊�����ƁA�������ނ˂��������Â߁A�O�֊O�ւ�獂�����
�y�����z���̍��ځA�e��{�̕��������ʂł����A���Z���B
|
|
|
|
| 2013�N3��16���i�y�j |
| ����i���c�����X�j |
23 ��c
�����A����Ђǂ�Ȏ�Ђǂ�ȁA�����㖤�̌�o��́A�t�͉ԍ���c�ɁA���˂̘T�S���\�l�A�閾��ғ����o���n�A������K���ƌ�������A���₨�����Ƒҏ��A�܃c�̑��ۂǂ�ǂ�Ƒ����V�Ђ炫���ɁA�قǂȂ��o����k�́A�ڂČ��߂��A���{�̘T�S�ē��A���̍s��i�}�}�A��j���G�Ȃ��A���肵���t�̂����ɁA�������ӂ���L�l�́A���ɂȂ����Ȃ����f�Ȃ�A�k獂�Ƃ��鏈�A�����͂Ȃ炶�ƘT�S���A�|��������������݁A���̊ۂƃn�v�ւǂ�����������̎��Ȃ�o�A����J����ʼnz�ւđ�א�ւ���肳���A�����゠����܂���
�y�����z
�E����́A��A���܂��͐ߕ��̖�ɁA��N�ɓ�����l�̉Ƃ̖�ȂǂōЖ�����t�������đK�邱�ƁB�܂��͂��̐l�B
�E�u��א�ւ���肳���v�@����̕���̖����̌��t�́u���̊C�ւ���肳���v�B��N���̍Ж�⏔���𐼂̊C�֗����Ă��܂��̈ӁB
|
|
|
|
| 2013�N3��15���i���j |
| �����i���c�����W�j |
22 ��H��g�N�c�p�����E�m�\���l�A�Z�����������d�A�l���щ�A���Ր��A�Ԗ�搶�@�X�l������U�A�u�����A萐����A�݉����A�����@�֑i�C���A��X���X�y�G�{�A�L���g�����ҔԒޑ�s��F�䕨�A�A�ؕ����c�}�ށA���ԕ]�����ȗցA������������A�n�}���a�������A���Ύl���~�s�L�i������x�ŋR�n�o��獒�(�Ϥ���)�ꌎ�ԍ��G�Y�Q�H�A���X������Ϗt�B
�y�����z
�E����ɂ͑薼�����Ă��Ȃ����A�w�������ڒ����x�́u���䎍�i��ڂ������j�v�A�w����N�^�x�́u�ה��ޔV���i��������̂��j�v�̑�ŁA�����������ڂ���B�O�҂̑薼�ɂ���u��邽���v�͖����̈ӁB���薼�Ƃ��u��n�䎍�i��������j�v�̂�����B
�@�u��n�䎍�v�́w�g����b�����G���x�w�]�k���x�ȂǂɗR������g���^�����b�ɓo�ꂷ���ǎ��̂��ƁB���b�ɂ��A���������g���^���͏������|�ɏ���Ă������ߓ��l�̎��i���A����_���A�S�̏Z�ޘO��ɕ����߂���B�������A���̋S�͈��{�����C�̗�ł���A�������Đ^������������B�O����E�o�����^���́A�S�̏����āA���l���o���������X�Ƃ��Ȃ��Ă����B���̓��̈���u��n�䎍�v�̉�ǁB�ǂݕ����킩��Ȃ��^���́A�Z�g�喾�_�E���J�ω��ɋF��ƈ�C�̒w偂�����A���̏�����������Ȃ���ړ�����B����ɏ]���āA���Ɂu��n�䎍�v��ǂ݉ʂ������Ƃ����i���q���F���ҁw�_�b�`�����T�x1963�N�A�������o�ŁA�u�g���^���v�̍��j�B
�E�u�����E�m�\���l�v�@���˘Q�m�݂̂̐l���ŁA�F���Q�m�L�������q��͐��ɓ����Ă��Ȃ��B
�E�u�A萐����A�݉����v�@�@���˘Q�m�̍L�؏��V���E�֓S�V�������̏ꂩ�瓦�S���A�s�����m��Ȃ��Ȃ������Ƃ��w���B
�E�u�����@�֑i�C���v�@�@����|�V���E���O�Y�E�@�c�s�ܘY�E�֓��ĕ���4�����C�m���̘e��@�i�e�⒆��������i�₷����j�A�V���A�d�B����ˁj�Ɏ��i�������Ƃ��w���B
�E�u��X���X�y�G�{�v�@��֘a���Y�E�X�ܘZ�Y�E���R���Y�E�X�R�ɔV����4�����A�א�@�i�א�z����Č�i�Ȃ����j�A���F�{�ˁj�Ɏ��i�������Ƃ��w���B�א�@�ł͗��狏�g�c���V�����Q�m��ɉ����A���ς{��ڕt�v�L���T�E�ڕt��䒩���i�Ƃ����j�A���ΐ�̐��˓@�ɋ}���B
�E�u�A�ؕ����c�}�ށv�@�L�͍L���̌�肩�B�L���q�V���Y�͏d�����A����@�i�����y�������A�P�H�ˁj�O�Ŏ��������B
|
|
|
|
| 2013�N3��14���i�j |
| �������i���c�����V�j |
13 ��ɂ�������̊����Ɏ������
14 ��Ɏd�������̍՟b���܂肩�Ԃ������邳����c�̂䂫
15 �t�Ȃ�ΊO�̍��͈�Ɍ��ԁi�P���J�j
16 �����̓��͐��˂Ɏ��ꂯ��
17 ��͔炾�͕��鐢�̒��ɉ��ƂĉƂ͗��������ʂ�
18 ��ɐߋ�т����Âɐ��Ղ肵��Ⴛ�ނ���c�̉�
�y�����z
�@���̐ߋ�̐�����ɂ͔�џ���~���̂��K�������A�ÎE���ꂽ��ɂ̌����Ŕ��Ⴊ��џ��̂悤�ɐԂ����܂����A�̈ӁB
19 �ԋS�̂��т��R�����ɂ��Ӎ]�R�ނ����n�O�g���܃n������c
�y�����z
�u�ԋS�v�͒��J�̟Ӗ��B�́A�������炪�ގ������ԋS�i��ۓ��q�B�����̋S�Ȃ̂Ŋ�͐^���Ԃƍl�����j�͒O�g����]�R�ɏZ��ł������A���̐ԋS�i��ɒ��J�j�͍��c��O�őގ����ꂽ�A�̈ӁB�R�����ɑO�X�N�i1858�j���s�̃R�����i�����R�����ƌĂj�̈ӂ��|���Ă��邩�H
20 �A�����J����肵�ނ��Ђ̂���݂��̂����̕\��O
�y�����z
�@��V�ÎE�̌������A���ďC�D�ʏ����̒���ɂ���Ƃ����B
21 �ԋS�̗_��n��ɂ����c�œ����̂ӂĐ��˂��L��܂�
�y�����z
�@�ԋS�i��Ɂj���O���c�Ŏ���͂˂��A�����Ȃ��Ȃ��Ă݂��Ƃ��Ȃ��낤�A�̈ӁB�u�����v�Ɂu��Ɂv�A�u�݂��Ƃ��Ȃ��v�Ɂu���ˁv�����ꂼ��|���Ă���B |
|
|
|
| 2013�N3��13���i���j |
| �����ǂ��֍s���i���c�����U�j |
12 ���܂�ǂ��֍s
������ǂ��֍s�A���c�V�O�ŁA���U�ŏo�����āA�Q�l�ɏo���āA���Ƃ�Ƃ���ĐԂ���Ƃ�ꂽ�A����ǂӂ����A���˓a�Q�l�ƎF���a�̘Q�l�Ǝ���獂Ă��܂�
�y�����z
�E�u���܂�c�v�@�F�����ܕ��q�Ƃ����̐S���������ނɂ����̗w�B�������͏�ڗ��A�̕���Ȃǂɂ��Ȃ����i��ڗ��u�F���́i���܂����j�v�A�̕���r�{�u�ܑ�͗��g�i�������肫�����̂ӂ����߁j�v�Ȃǁj�B
|
|
|
|
| 2013�N3��12���i�j |
| �َq�����D�i�Ђ��ӂ��j�i���c�����T�j |
11 �َq�����D
��S�{�ā@�@�@�@�@�@�@���i�ꐶ����
�ꂩ����G�ρ@�@�@�@�@��݂₰�U������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�\�ܕ�
���ː���X
��Q�l�͂�ԂƖ� ���i�䏟�莟��
�ꕐ�m�r���� ��s��
��]�肱��߂��@�@�@�@�䂫�肤��ς��ɂČ䒼�i�s��
��䂾����Ȃ��c�q�@�@�T�C�L������j��
���t��
��Ԏm�Ԃ�Ԃ�݁@�@�@�䒼�i�Ȃ�
�@���O����獂������m�ł��������ؗ�����D����
�O���O���̏��@�O���c�������Y
�@�c���e���Ȃ�Ђт�Ђ��œ����Z�ϔV�㍷��\��
�y�����z
�E�u���D�v�@���D�́A�]�ˎ���Ȍ�A���X���J�X�┄�o�����`���邽�߂ɔz�����L���̎D�B�]�˂ł͈��D�A����ł͂��炵�ƌĂi��c����w�ߐ������u�i���攍e�j�x�j�B
�E�u�S�{�āv�́A�����̓��ɓ��h�q���X�����ďĂ������́B��V�ÎE�ɓS�C���g��ꂽ�B
�E�u���i�ꐶ���v�@�l�i�͂��肬��܂ň������Ă���B
�E�u������G�ρv�͊�������̎G�ςɁA�|�������|���Ă���B
�E�u��݂₰�U������ �O�\�ܕ��v�@�y�Y�p���Ăɓ������������Ė݁B��ɂ̉��Ăɓ���˂����Ă�ꂽ�̈ӂ�������B�l�i�́u�O�\�ܕ��v�́A�F����35���i���ۂ̐���30���B���a2�N�ɖ��{�̂̏�t��2����a�����A�����m�s���Ɋ��Z�����5���ɑ��������̂ŁA���킹��35���̊i���Ə̂��ꂽ�B�j�̈ӂ��|�����B�@
�E�u�Q�l�͂�ԂƖ݁v�@�͂�ԂƖ݁i�啟�݂̑O�g�Ƃ������ׂ��a�َq�ŁA���݂̂Œ������������Q����ꂽ����̑�`�̖݁j�ɁA��V�ÎE�̘S�l�����͂͂�ԂƁi�_�́E�x�ʂ��傫���B�������j�ł���̈ӂ��|���Ă���B
�E�u���m�r����v�@�����r㻁i�����Đ�����r㻁B�����Q�ɏ������A�����A���ʂ̉��������ė���ł߁A�����グ�č��j�ɕ��m���|���Ă���B
�E�u���t���v�@���t�i�����j�͞e�`��̂�����ŁA������̔Ԏm���ʍs�l���Ď������ꏊ�B�]�ˏ�ɂ͓��s�E�O�s���킹��36�̌������������Ƃ����A�ԍ〈���E�l�J�����Ȃǂ̒n�����c���Ă���B�����ł͊O���c��̌������w���B
�E�u�]�肱��߂��v�@����߂��i���сj�����Ă����Ăŏ��������́B |
|
|
|
| 2013�N3��11���i���j |
| ��ɂ̐Ԕ����i���c�����S�j |
9 �Ԕ��ւ���݂Č�����̒�
�y�����z
�E�u�Ԕ��ցv�@��ɉƂ̐��ł̏o�ŗ����́A�Z�E���E���E�w���ȂǑS�ĐԂ����߂������B������u��ɂ̐Ԕ����v�Ƃ����A�V���ɂ��̗E�������������B
�E�u����݂āc�v�@�u�邪�����Ė��邭�Ȃ�v�ɁA�u�F������A��������������v�̈ӂ�������
�y�Q�l�z
�E�u�����������̕��̋�̐F�Ȃ�Ō����قɐ��݂��Ԓp�̋S�v�i�w�������ڒ����xP.436�j
10�@��ނ�ɂɂ���n�Ɉ�(��)�Ɨ�
�y�����z
�E�u�ނ�v�͓��̂��ƁB�����ł͑�V�̎�B��ɉƂł͒D��ꂽ��V�̎�����߂ĉƗ��ꓯ����ɂ߂��B |
|
|
|
| 2013�N3��10���i���j |
| �A�́i���c�����R�j |
8 �A��
�@�ӂ�N�̉����Ƃ��Ă͂�̉J�@�@�@�@������
�@�l�͕��m�Ԃ͍��c�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@���ӂ����͔u�Ȑ��Ɂ@�@�@�@�@�@�\���l
�@���������̂͂Ƃ�����@ �@�@ �@�]��
�@���[�̈��ɂ��ɂ����܂�́@�@�@�@����
�@�|�̏t�ƂĒ��̉��ɖ@�@�@�@�@�@�@�@�ƒ�
�@���̗F�I�ŝc��(��)���͂�Ё@�@�@ ����
�@���肿��ɉ��H�֏M�͕��s�@�@�@�@�@�@�ٍ��l
�y�����z
�E�u�ӂ�N�v�͔N���̈ӁB�ӂ�A�Ƃ���A�͂�̉J�A�͉���B
�E�u�l�͕��m�Ԃ͍��c�v�@�u�Ԃ͍��A�l�͕��m�v�̂�����B
�E�u�u�Ȑ��Ɂv�@�Ȑ��i���������j�͔u�𐅂ɕ����ׁA���ꂪ�����̑O�ɗ��ꒅ���܂łɘa�̂��r�݁A�ł��Ȃ���Δ��Ƃ��Ă��̔u�Ŏ������ޗV�сB�㖤�̐ߋ�i3���̍ŏ��̖��̓��B���߂�3��3���ƌ��߂�ꂽ�j�̗V�сB�Ȑ��Ɏg�p����u�͒��̌`�����Ă����̂ʼnH�[�i�����傤�j�Ƃ����A�u�����Ƃ肷�邱�Ƃ��u�H�[�����v�ƌ������B�u�Ȑ��v�Ǝ���́u�����v�E�u�����v�͐��̉���B
�E�u�\���l�v�@17�l�͈�ɂ��P���������˘Q�m17�l�B�F���Q�m1�l�i�L�������q��j�͓����Ă��Ȃ��B
�E�u�|�̏t�v�@�u�|�̏H�v�̌�肩�B�|�̗��t���͉A��3���ɓ�����̂ŁA�|�̏H�͉A��3���̋G��ƂȂ��Ă���B
�y�Q�l�z
�@�u�ӂ�N�̂���݃n�Ƃ��ďt�̍��@�@�L���瑽��
�@�@�l�n���m�ԃn������c �@�@�@�@�@�@�@����
�@�@���������n�u�Ƃ��Ȑ��Ɂ@�@�@�@�\���l
�@�@���������̂ςƗ��Ă�@�@�@�@�@ �]��
�@�@���[�̈��Ƃ��ɂ����̂܂ꂷ �@����
�@�@���Ƃ̏t�Ƃ�峂����ɖ@�@�@�@�@�@�ƒ�
�@�@���̗F�I�����c���͂�Ё@�@�@�@�@�@����
�@�@���肿�艓�H�ɑD�n���s�@�@�@�@�@�@�ّ��@�@�@�@�@�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w����N�^�xP.367�j
|
|
|
|
| 2013�N3��9���i�y�j |
| �B���d���Ɋ���߂�i���c�����Q�j |
2 ��~�肢�����Ƃɂ������Ƃ�
�y�����z
�@�B���d���́A�����Ɋւ��Ȃ��Ў�Ԏd���̂��ƁB�B���͐��˔˂̓���ď����Î��B���ɑ|�������|����B��ɈÎE�̍�����ď��ƌ��Ȃ������́B��������̗����ɁA���̂悤�Ȃ��̂�����B
�@�u��̒��B���d���ɂ������Ƃ�v�i�w�������ڒ����xP.404�j
�@�u�O���͓��̐ߋ�ɐႪ�ӂ�B���d���ɑ|���̌䗿���v�i�w�������ڒ����xP.398�j
3 ���������������ق��ĉɂ�����
�y�����z
�@�u�����v�͈�ɂ��A�u���v�͐��˂��Î��B�u�ɂ�����v�͕s���B�������A���̍��A�Ύ������������B����5�i1858�j�N2��10���y��11��15���]�ˑ�A��6�i1859�j�N2��22���]�ˎR�̎��A��10��17���]�ˏ�{�ۉ���ȂǁB
4 �����Ȃ͓��̐ߋ�ɐԂ��Ȃ�
�y�����z
�@�k�́A�䌅�ƂƂ��Ɉ�ɉƂ̖䏊�B�k�̉Ԃ͔����B�����ŋk�i����Ɂj���Ԃ����܂����A�̈ӁB����̗����Ɂu�k�����̐ߋ�ɐԂ��Ȃ�v�i�w�������ڒ����xP.404�j�B
5 �݂Ƃ��Ȃ��A����������Ԃ�(��)����
�y�����z
�@�u�݂Ƃ��Ȃ��v�i�݂��Ƃ��Ȃ��j�ɐ��˂��A�u���������v�Ɉ�ɂ�������B�ߋ�̔������A���ŐԂ��Ȃ����B����̗����Ɂu���˂��Ȃ���ɔ�����Ԃ����āv�i�w�������ڒ����xP.404�j�A�u�������̂ނ͈̂�ɂ��Ԃ��Ȃ�v�i��P.437�j�B
6 �����ӂ�ɂ���������Ɏ�
�y�����z
�@�u�����ӂ�v�͐����C�ŁA���D�ɂ��镗�C�̂��ƁB�������C�̓]�Ƃ��A�i�������C�łȂ��j��ː����p�ɂ�閼�̂Ƃ������B�����C�ɂ͐��{�S�i���˂̘S�l�j�̈ӂ���������B�u���C�����傤�ǂ悢�������ŁA��܂ł����Ă���v�̈ӂɁA�u���˂̘S�l�����Ɉ�ɂ�����ꂽ�v�̈ӂ�������B����̂��̂Ɏ��̂悤�Ȃ��̂�����B
�@�u���{�Q(����)�͈�ɂ��납�����c��v�i�w�����G�L�x��15���A��78�̗����j
�@�u�����Q�Ɉ�ɂ����Ǝ�c����v�i�w�������ڒ����xP.404�j
�@�u���{�Q����ɂ����Ǝ�c����v�i�w����N�^�xP.368�j
7 ��͔���͂���鐢�̒��ɉ��ƂĒ��͗҂�������
|
|
|
|
| 2013�N3��8���i���j |
| ��ɉƉƐb�̊菑�ɑ����������i���c�����P�j |
1 �[��ɉƐb�V�蕶��
��Ɉ����y���@�z�Ɨ��ޒN���l�ꓯ��V���B��ɉƔV�V�Ґ�c�����E�����i�{���N�j�y���A�z�ȗ���V�������E���ȂēV���j�֒��d�A���V���V�E��@�t�y���B�z���ΕA��|�����y���C�z�V�������V�E��J���@��l�y���D�z���N�j�����j�t�A�ʎ��S�z�d�g����e�A���𑊗���A�������^(�Ϥ��\�)�V�Ƃɐ����d�́A���הV�����͕s�s�͔V�V�L�V�A�E���V���َ͐ҋ����l�j���D���y���E�z�v�A���^�d�ւ����V���A�َҋ��Z�ˌ̃j�s�s�͔V�����L�V��]�������V���L�V��R�A���S���|�����V�߃j�͖��V�A���َҋ��V�s���ƛ��V����B�E���V���莖�N��A�c�O���O�����O���c�A�����˓a�Ɨ����ߕ��Q�l�b���ƏE���l�k�}�v�A�E���V���s���فA��r�j�|���������~�A�T�S��V�Ɛ��@�d��B�|�����a���A�����\����j�́A�ގҋ��s�@�\���̏��u�j���ăn�A����ɐ₵���A����Ƃ͗E���V���C���j�B��Ȃ��A���ɏ��A�ԁE���Җ�������u��j�A�͓��l���j���e�Ճj�����d���A�Ɨ��j�����E�蕉���L�V�A��䓙�j������A��V�����w���v�Ȃ��瓾�ƌ����j�A���Y���ƛ��ɖڂ�������B�����Ɖ��ăn��߁A�����E�ɉ��ăn�މ��B�䓙�����y���F�z�V���j�́A���Ȃ炷�S���������o�ΔV��A�ގ҂����g�j����\���A���S��Ȃ�o�A���V�����̋��Ď��߂�\�G�ƁA���~�֍��\�t�A�݈�O���j���L��߃n�A�l���j���������Ȃč߂��w���ׂ�����ԁA�Ɨ����V�e�l���S���A���V�����̂Č�����r�j�p�J�𑊔E��l�A���@�v�ւ��|�\����j�t�A�ꓯ���d�A�֎��S�������͂��܂��A���Ζ���V�S������d��B�v�ɏA�ėP�X�����s���j���f�`�V���y���G�z獂���Μ��d��B�R�����A���r����(�Ϥ����)�v���A�s�K�ɂ��P�a�����A�����d��ԁA�E���V�ӎ���s���B�A���]������A�B�V�c�O�V�V�ƉƗ����ꓯ�ߒV�d��B�����o�i���e�V��m�b���ȁA�ޓ������߂���G�Ɣ�݁A����j�n�����ꓯ�ؕ��d�A�㗃�s�s�͔V�߉Ȃ��n�R�A�|�����V�֖����S�A��������V�S��������j���ق�A�����ɉ��Ă����y���H�z�j��z�A�����ȗ�����V��l�j�\桔V���j��������Ƃƕ�B�|�������������ꓯ�ޓ��������⍦���V�j�͌���B�R�䓙�����E�l�����n�A�r�c�P���a�y���I�z�i�䎁�V���\��V���v��ӎ�ƕ́A�S���j�䌫�@�퉺�@��V��ב��ƒ��𑊙���|���������S��ח��A�@��m�b�V�����ݖ��q��䌫�f�j����B�����V�͑O��\���߉Ȏ����V�S�훔���Μ��V���A���V�|�������Ӑ\����́A�}���d��o��j�����B��i�X�����B�����B�ȏ�B
�@�O���V���߈ꓯ�S�_�f���d�A�O��s�����V�A���͗��s�s�V���i���莧�L�V�V�ƕ�B�E���V���A�X�䋂��䐄�@�V�����B
�y���@�z��Ɉ���
�@���ۂ͒��J���������a�Ƃ̊Ԃɂ������������C�i�悵�܂�j�A�̂��̒����̂��ƁB�Éi���i1848�j�N���A����35�i1902�j�N�v�B
�y���A�z�����E����
�@�������͒����E���F�B�����͓���l�V���i���Ɏ��䒉���E�{�������E�匴�N���j�̈�l�ɐ������A�փ����̖��ł͓��R�̌R��s�Ƃ��Ċ����B���̌��ɂ��ߍ]��15���A����3���A�v18����^����ꂽ�B�������A���̒����p�i�����j�͕a�ゾ�������߁A�Ɠ�풼�F�ɏ���A���p�����3���������ď�썑�����Ɉڂ����B���F�͑��Ă̐w�ŗ��N�E�G�����͂��Ď��E�ɒǂ����ނƂ������Q�̕����𗧂āA�Ȍ�3�x�ɂ킽��v15�����������ꂽ�B����ŕF���˂͍��킹��30���ƂȂ������A����ɖ��̂̏�t��2����a�����i�����m�s���Ɋ��Z�����5���ɑ����j�A�u�F��35���v�����̂����B
�y���B�z���V���V�E��@�t�c
�@��ɉƂ̐Ȏ��͗�㗭�ԋl�ł���B����ɏ헭�i�܂��͖{�ȁj�Ƃ����A��ɉƂ͏헭�̉Ɗi�ł͂��̕M���ł������B���ԋl�喼�͖��{����D������A�]�ˏ钆�̐Ȏ��͘V��������Ƃ��ꂽ�B�ݕ{�̍ۂ͖���10���E24���̗����o�邵�č����@�̗��Ԃɋl�߁A����������ꍇ�ɂ͘V���Ɠ��c���A�܂����ڏ��R�ֈӌ�����\�ł����B�܂��A���喼�ɑ厖��`�B����ۂ́A�V���Ɨ�������i�g�c��g�w��ɒ��J�x1963�N�A�g��O���فAP.93�`94�j�B�����Ɉ�ɉƂ̉Ɗi�������������킩�낤�B
�@��V�́A��10���Έȏ��̂��镈��喼�����C������A���ʂ͎l�ʏ����E�l�ʒ����ȂǂɔC����ꂽ�i��ɒ��J�͐��l�ʏ㍶�߉q�����ɂ܂ŏ��i�j�B���{�E�����ō��̐E�ŁA���R��⍲���A�����S�ʂ������B��V�̒���͈ꖼ�ŁA�K�C�҂����Ȃ���ΔC�����Ȃ������B��u�̐E�łȂ��������߁A��V�E�ɔC�����ꂽ�̂́A�]�ˎ���ʂ��Ă킸���Ɏ���10���i���אl���B����9���j�ɉ߂��Ȃ��i�l���ɂ��Ăِ͈�������B�w���j�厫�T��8���x�́u��V�v���̋L�q�ɏ]���j�B
| |
���@�� |
���@�� |
��@�n |
�@�� |
�ݐE���� |
| 1 |
�y�䗘�� |
�吆�� |
������ |
16���Η] |
���i15�`���ی� |
| 2 |
���䒉�� |
�]��� |
�ዷ���l |
11��3500�� |
���i15�`����3 |
| 3 |
���䒉�� |
��y�� |
���X�� |
13���� |
����6�`����8 |
| 4 |
�x�c���r |
�}�O�� |
������ |
9���� |
�V�a���`�勝�� |
| 5 |
��ɒ��� |
�|���� |
�ߍ]�F�� |
30���� |
���\10�`���\13 |
| 6 |
��ɒ��Y (�����̍ĔC) |
�|���� |
�ߍ]�F�� |
30���� |
�������`����5 |
| 7 |
��ɒ��K |
�|���� |
�ߍ]�F�� |
30���� |
�V��4�`�V��7 |
| 8 |
��ɒ��� |
�|���� |
�ߍ]�F�� |
30���� |
�V��6�`�V��12 |
| 9 |
��ɒ��J |
�|���� |
�ߍ]�F�� |
30���� |
����5�`������ |
| 10 |
���䒉�� |
��y�� |
�d���P�H |
15���� |
�c�����`�c���� |
�i�w���j�厫�T��8���xP.920�B�������b�q���쐬�́u��V�ꗗ�v���甲�������j
�@����10���̑�V�̓�5���܂ł���ɉƂŐ�߁A�������̔�C���҂ɔ�ׂĊi�i�ɑ����B�y��E����E�x�c�e���͘V���E�ɂ��A�C�������A��ɉƂ͑�V�E�ɂ����A�C���Ȃ������B
�@��V�̌��Ђ͐��ł���A��V���o�d����ƁA����E����̔Ԏm�͎c�炸�������̗���Ƃ����B��p�����ł͍ł�������߁A��V����������ƘV���͈ꓯ�����ċ����сA���R�ɑ���̂Ɠ��l�A�������Ĉ��A�����B��V���V�����ĂԎ��́A���R�Ɠ������A�V���̊��E���Ăю̂Ăɂ����i���Ƃ��Ίԕ�������F���i�����N�ԁj�ł������Ȃ�A�u��v�̕������āu�����v�Ɗ������Ăю̂Ăɂ����j�B����ɑ��A�V������V���ĂԎ��́A�u��O�l�v�ƌh�̂����B�܂��A��V�Ɠ�������ꍇ�ɂ́A�V���͐������̌�������ĕ��s��������B
�@��V�̌��Ђ́A���ɂ͏��R���z�����B��V�̌��ς͏��R�Ƃ����ǂ�����������Ƃ͂ł��Ȃ������Ƃ����A��V���������ő喼�ɖ��߂���ꍇ�͏��R�Ɠ����ł������B��V�ɍs����Ə��喼�͏钆�ł��H��ł���������A��O�ƁE��O���Ƃ����ǂ���V�ɂ͉�߂����B
�@���R����͖��N�_��50�H�A��1�H�i�w�����x�i���X�Q���ޏ]��܊��j�B�ߔq�̂̏d�v���ɂ��ẮA��t�������w���{�j�̂Ȃ��̓������T�x1992�N�A�������o�ł́u�߁v�̍��A�܂��́w����x�Q�Ɓj������A���̑�����L�i�̎f���A�q��A���M���͂��ׂĘV���ɔ�ׂĈꓙ��ł������Ƃ����B
�@���̂悤�ɓ��ʂȑҋ��A���Ȍ��Ђ���������V�E�ł��������A���ۂɖ��������E���錠�͂��s�g�����̂́A����V�̒��ł��A�u���n���R�v�i�]�ˏ�̉��n�D�̑O�ɓ@��������̂Łj�ٖ̈����Ƃ������䒉���ƁA��ɒ��J�̓�l�ł������Ƃ����B
�i�ȏ�A�Q�l�����F���ԗǕF�w�]�˖��{��E�W���i����Łj�x1965�N�A�Y�R�t�AP.101�`104�B�w���j�厫�T�攪���x1978�N�A�g��O���ق́u��V�v�i���a�M�v�����M�j�̍��B�������Y���E�i�m�c���Z���w�Z���]�ˎ��㐧�x�̌����x1971�N�A�����[�AP.361�`365�j
�y���C�z�|����
�@���ߐ����A�{���Ȃɑ����ċ{���̐��|��V���̍ۂ̎���ݔ��Ȃǂ��i��������|�����Ƃ����A�����̒������|�����B�����A�{���Ȃ̓��|���i�i�����̂�����̂����j�Ƒ呠�Ȃ̑|���i�i������Â����j�����������A�O�m11�i820�j�N�ɂ��̓���������đ|�����Ƃ����Ƃ����B
�y���D�z��l
�@ 14�㏫�R����ƖB
�y���E�z�D��i�����͎��ւ�ɖ�j
�@�������́u��D�v�Łu�тق��v�B�Ƃ���낤�̈ӁB
�y���F�z����
�@�y���B
�y���G�z�f�`�V��
�@�f�`�͛��ʑf�`�i����������B�E�����ʂ������A�\�̂ݐH��ł��邱�ƁB�\���l�j�̂��ƁB
�y���H�z�� ����̍��B
�y���I�z�r�c�P��
�@ 1564�`1613�B�P�H53���̔ˎ�B�q�̒��p�E���Y�����O�W�H��̂��A���Ɂu�P�H�ɑ��S���v�ƌĂꂽ�B
|
|
|
|
| 2013�N3��7���i�j |
| �w�����G�L�x�̂��Ɓi�����X�j |
�@�w�����G�L�x�i���{�͓��t���ɑ��j�Ƃ����{������B�M�҂́A���p�w����ƂƂ��������Ɛ��肳���B������恁i���݂ȁj���A�ʏ̂�펟�Y�q��A���𐮍ւȂǂƏ̂��A���v2�i1862�j�N��72�Ŗv�����Ƃ����B�w�����G�L�x�́A���삪�������Ɛ��������T��̎G�L�i�����E�V�ہE�O���E�Éi�E�{���j�̈�ł���A�S16�����琬��B��ɉÉi������������ɂ����Ă̐���̋L�����A�قڔN�㏇�ɔz�Ă���i�w�����G�L�x�i���Ï��@�j���y�сw�j�Љ�莫�T�i�ߐ��ҁj�x�i�������o�Łj�ɂ��j�B
�@���̂����A��15���͍��c��O�̕ςɊւ��闎��݂̂��琬��B�����āA�{���݂̂ɂ������ڂ���Ă��Ȃ��M�d�ȗ��������̒��ɂ͊܂܂�Ă���B�w�����G�L�x�͉e��{�݂̂ŁA�����ɖ|�����ꂽ���̂��Ȃ��̂ŁA�������̂��Љ�������ł��Ӗ������낤�B
�@����A�{���ɋL�ڂ��ꂽ�������A�����Љ�Ă������Ƃɂ��悤�B |
|
|
|
| 2013�N3��6���i���j |
| �j���Ƃ��Ă̗����i�����W�j |
�@���{�j�����҂��j���Ƃ��ė����𗘗p����ꍇ�A���j�̑��ʂ����G�s�\�[�h�̈�Ƃ��āA�܂ݐH���I�ɗ��p����邭�炢�������B���ł����������X���͂��邾�낤�B
�@�����������ŁA�n���ɗ������E���W�߂���A������ϋɓI�Ɋ��p���Ă��̎j���Ƃ��Ă̗L�����𐢊Ԃ̐l�тƂɍĔF���������肵���A���Ƃ��Ύ��̂悤�Ȓ���͏d�v�ł���Ǝv���B
�E�I�c����Y�w�������{�j�x1967�N�A�O�E�ꏑ�[
�@�@�i��������g���ē��{�l�̔ᔻ���_�̓�����ՂÂ����j
�E��؞��O�ҁw���T�x1982�N�A�������o��
�@�@�i���L������ɂ킽���Ă����ȗ���݂̂���肠���A������������j
�E������ҁw�]�ˎ��㗎�����ځx��E���E�����A1984�`85�N �������o��
�@�@�i�]�ˎ���̗������܂Ƃ߂����̂Ƃ��Ă͑啔�̂��́j
|
|
|
|
| 2013�N3��5���i�j |
| �u�ތ^�I�v�Ƃ͉���(�����V�j |
�@���Ԃ������������悤�ȁA�����傫�Ȏ������N���邽�тɁA��ʂɗ����������B����̗����͎U�킵�Ă��܂������A����ł����݂ɂ܂Ŏc���Ă闎���̗ʂ͖c�傾�B
�@�������A�Z���Ԃɑ�ʐ��Y����邽�߁A��Ɏ����ɑ��č��ꂽ�����̓��e�́A�ތ^�I�œ�����̂��̂���B������������̂��̂������̂��B�������A�㐢�̂����̖ڂ��炷��A�����͕K���������������j�I�]���������Ă���Ƃ͌������������̂�����������B
�@�������������Â炳�������Ă̂��Ƃ��A�����̎j���I���l�́A�����L�^�ȂǂƔ�ׂď]���͌y�������X���ɂ������B
�@�������A�t���I�ł͂��邪�A���������ތ^�I�Ȏj������ʂɎc����Ă���A�Ƃ������Ƃ������d�v�Ȃ̂��A�ƌ����܂����B�ތ^�I�Ƃ������Ƃ́A������ς���A���̎���ɐ�������ʂ̐l�X�����Y�����ɑ��ĕ��������ʂ̈�ہE�ӌ��E���z�ł���A��́u���_�v�Ƃ������ׂ����̂����炾�B
�@���������l�S�̓����E����I���͋C�Ȃǂ́A�����L�^�Ȃǂ���́A�܂��͉M���m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���������_������A�����̎j���I�d�v�����咣���邱�Ƃ��ł���B
�@�Ȃ��A���c��O�̕ςɊւ��闎��������ƁA���˘Q�m����`�m�A��ɒ��J�����l�A��ɉƒ��̎m�E���喼���������A�Ƃ���ތ^���������̂������B
|
|
|
|
| 2013�N3��4���i���j |
| �����i�����U�j |
�@����肳��Ă�����ł́A�l�X�ȋ�������ь����B��V�ÎE�͕�����Ȃ��������������A���̎ǂ��Ȃ������ɂ��ẮA�������X�������B
�@�����������A����r�ɕ������҂��A��ɒ��J�̎��Ђ����ɐ��˂ɉ^�Ƃ������������ꂽ�B��������ł͂Ȃ��B
�@�Ƃ��낪�A���������̊Ԃɂ��^���̒��ɕ��ꂱ��ł����B������ʔ�����l�����������̂��낤�B�������A���ꂪ������G�Ȃǂ̌`�ɂȂ��ČŒ艻����Ă����ƁA�������������u�����v�ƂȂ��Ă����B
�@�������N�̋ъG�u�ߐ��`�E�`�v�i���ڈ�Ѝ֖F���M�j�ł́A��V�̎�𐅌˂Ɏ����������l�����A��V�P���Q�m�̈�l�����O�\�Y�Ƃ��ĕ`���Ă���A�܂����݉����Ƃɂ͂���������ƔF�߂���肪�`���Ƃ����B
�@�u�ߐ��`�E�`�v�́w���j�厫�T��11���x�i1990�N�A�g��O���فA�u�]�ˎ���̔�r�v���ڂ̌��G25�j�ɍڂ��Ă���B�Q�l�܂łɂ��̐��������f�ڂ��悤�B
�u�@�@�����O�\�Y�@�s�N�l�\�܍�
�����ˉƂ̔˂ɂ��Ē��E����̉p���Ȃ�B�����𑖂鎖�ލ��i�}�}�j�@���\���B��l�O���[���a�߂Ȃ����Ě�孋����Ȃ肵��莞�̖\����A���u�̎҂Ɩ��Q�l���āA��V���M�ӁB���Ȃ�ƁB�����M�\�O���O���A�ꓯ�v�����߂ğN�c�ɖ{�ӂ�B���B�����艪���n����r�Ɍ`�e���A�C�V���̏M���ɐ��~�A�w�̎����A���Ɏ��Đ��{�ɕ���B��A�g���f���ɂď��߂ƂȂ�A����C����v�֗a�ƂȂ肽��B�@�@�@�@�@�@���@���q�v
|
|
|
|
| 2013�N3��3���i���j |
| �����̐��Y�i�����T�j |
�@�����̏��`�B��i�̈�Ƃ��āA�������傫�Ȕ�d���߂Ă��������́A�����ƒ��ӂ���Ă悢�i��������f�B�A�Ƃ��Ă̈�Ƃ��đ��������̂ɁA�g������Y�w�����Ƃ������f�B�A�|�]�˖��O�̓{��ƃ��[���A�|�x1999�N�A����o�ŁA������j�B
�@���Ƃ��A���c�����Ɋւ��闎���̖c�傳������A�u�l�̌��Ɍ˂͗��Ă��ʁv�������������悤�i���Ȃ݂ɁA1860�N�̍����A���c��O�̕ς��N�������j�B
�@��V�͂��łɉ������Ă������̂́A���{�E�F���˂͂��̌��Ђ�ۂƂƂ��Ɉ�ɉƂ̉Ɠ�����}�邽�߁A�W�҂�⭌��߁i�����ꂢ�j���������B�����āA�����̂ق�1�J����Ɂu��V�a���v�\�����B
�@�Ƃ��낪�A�n���̏����ł���قǂȂ��u��V�ÎE�v�Ƃ��������̐^����m��̂ł���B������荬�������ł͂��������̂́A���̍ō����͎҂������ÎE���ꂽ�Ƃ��������̏Ռ����E�d�含���琔�����̗���������A�M�ʁE���Âē��ɂ���āA�e�n�֓`�d���Ă��������߂ł���B |
|
|
|
| 2013�N3��2���i�y�j |
| ����Ƌ��̂͂ǂ����Ⴄ���i�����S�j |
�@�����ƈ���ɂ����Ă��A���̌`�Ԃ͕��́E���́E�ŋ��̑�{�E���Ƃ��b���l�X�ł���B�Ƃ�킯57577�̒Z�̌`�Ԃ��Ƃ���̂���ʂɎc���Ă���B����𗎎�i�炭����j�Ƃ����B
�@����͍�邱�Ƃ���r�I�e�Ղ��B�������A�Z�����Y�~�J���Ȃ��߁A��r�I�l�̋L���ɂƂǂ߂₷���B������A�l�����Y�t�i��������j��������́A�l����l�ւƋ}���Ɋg�U�`�d���Ă������̂��낤���A�����Ȃ�����Ƃ��܂�������Ђ˂�o�����Ƃ��ł���A�Ƃ����l�X�̎v��������̑e�������ɂȂ������̂��낤�B
�@�Ƃ���ŁA����Ƌ��̂́A�ǂ��������57577�̒Z���`�Ԃ��Ƃ邪�A���҂ɈႢ�͂���̂��낤���B
�@�����ĈႢ�������Ȃ�A����͕��h�������邩�Ȃ����̈�_�ɍi����B�����A�f�l�ڂɂ́A����Ƌ��̂̋��E�͋ɂ߂ĞB���ł���A��ʂ����邱�Ƃ͎��ۂɂ͍���B
�@�������Ȃ���A�]�ˎ���̋��̎t�ɂ́A�����ɕ���킵���������h�̋��͍̂��Ȃ��Ƃ����������������Ƃ����B���{�̒e��������Ă̂��Ƃ������̂����m��Ȃ����A������u翗�i�Ђ�j�v�ȉ̂Ƃ��Ĕr�����A�u����́i�炭����Ă��B����ɕ���킵���A�̈Ӂj�v�̋��̂͊��{���炱�Ƃ��Ƃ��폜���Ă����Ƃ����̂��i���c�C�u���_�̉����v�|�l�c�`��Y�E�X�쏺�ҁw�ӏܓ��{�ÓT���w�A��31���A����E���́x1977�N�A�p�쏑�X�����|�j�B
|
|
|
|
| 2013�N3��1���i���j |
| �����̗�Q�i�����R�j |
�@�ʍs�l�̑����ꏊ�ɗ�����\�t������Ƃ��āA�w����N�^�x�Ɏ��̂悤�Șb���ڂ���B�]�˖��{�����O���ƒʏ�����������A�f�Ղ��J�n���ꂽ�B�����ᔻ�����������A����7�i���������j�N3���A�u���{�����D��։��j�F�i�������j�ߓB�i�����j�j���i�āj�ŕt�i�������j�v���Ă������Ƃ����i���{�R����w����N�^�x�|��錧�j���E�����҇U�AP.396�|�j�B���̗����Ƃ́A���̂悤�Ȃ��̂ł������B
�@ �@�u���Ղ����o�]�˂�����ɂȂ��i���A���Ղ������]�˂���ɂȂ��j�v
�@�����l���]�˖≮��ʂ����A�J�`��̉��l�ɕ����ĊO���l�ƒ��ڎ�������Ă��܂����߁A�]�ˎs���ɂ����Đ����K���i�����ꂵ�Ă��܂��A�������������Ă��錻����ᔻ�����̂ł���B
�@�܂��A�]�˂̈���i�����������j�ɂ��A�悭����������o���ꂽ�B�����ɂ͖��q��T������ח�������A�e�����q��T����i�Ƃ��āA�q�ǂ��̖��O�����������������ɒ���o���Ă����B���c��O�̕ς̍ۂɂ��A��ɑ�V�̉��������闎���������ɓ\�t����A�O�ڂɎN���ꂽ�Ƃ����i�w�]�ˎ��㗎�����ڒ����xP.437�j�B
|
|
|
|
| 2013�N2��28���i�j |
| �����̗�P�i�����Q�j |
�@�U���Ώېl���̉��~�ɒ��ړ\�t���������̗�Ƃ��āA�w�����M�i�肳�������Ђj�x�ɂ͎��̂悤�Șb���ڂ���B
�@���˂̐g���炨�����ēV������𐬂������A�ʐl�b���ɂ߂��G�g�́A���s�ɑs����ڊy��i����炭�����A����炭�Ă��j�c�����B������A�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���i�����j����̋v�����炸�v
�Ə��������������Ă������Ƃ����i�u�ꗝ�ցw�����M�x���{���M�听��3����1���A1976�N�A�g��O���فAP.301�j�B
�@���̘b�ɂ̓I�`������B�����̌������G�g�́A����������F�i�������j�߂āA���̎����ɒ��点���B���̒��莆�ɞH���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���炸�ƂĂ��v�����炸�v |
|
|
|
| 2013�N2��27���i���j |
| �����Ƃ́i�����P�j |
�@�����Ŏ��グ��̂́A�ߐ��Ɍ��肵�Ă̗����i�炭����j�̘b���B
�@�����Ƃ́A�����i�Ƃ��߂��j�̎Љ�慎h�E�l�U���̎�i�̈���B�U���Ώېl���̉��~�̖����ǁA�ʍs�l�̑������Ȃǂɓ\�t���Ă��̓��e���O�ڂɎN�i����j������A�܂����H�ɗ��Ƃ��Ȃǂ��Đ��Ԃɕ]�����Ă悤�Ɗ�Ă��B������A�u�炭����v�u���Ƃ��Ԃ݁v�ȂǂƌĂꂽ�B�w���������x�ɂ��uRacuxo�i�炭����j�v�̈Ӗ����ucaqivotosu�i�������Ƃ��j�v�Ƃ��Ă���B
�@�������A�Ȃ��A���Ƃ��̂��낤�B
�@���̗��R�ɂ��āA�����j�Ƃ̏������v�i���܂��������j�����ʔ������Ƃ������Ă���B�����Ƃ�������ɂ́A�u���Ƃ��v�s�ׂɂ���āA�����̓��e��������̈ӎv���痣���ƍl�����B�����āA�����Ă����������E�����Ƃ́A�_�̈ӎv���Ɖ��߂���Ă����i�w���Ƃ̕����j�i�����P�j�x���}�ЁA1988�N�j�B
�@�l�������ė��Ƃ����������_�ӂɉ����Ȃ�A���̎҂�������E���B�E��ꂽ�����ɂ͐_�ӂ��h���Ă���킯������A���̓��e�̐^�������ۏ���邱�ƂɂȂ�A�Ƃł��������Ƃ��B
�@������A�����u�����v�Ƃ��������ł����Ă��A������u�炭�����v�Ɠǂ�ł��܂��ƁA�Ӗ����܂�ň���Ă��܂��B����C�܂܂̎�V�тƂ����Ӗ������������Ȃ�A���h���������Ă��܂����Ƃɂ��Ȃ�i��؞��O�ҁw���T�x1982�N�A�������o�ŁA����Q�Ɓj�B
�@���߂Č������A�����Řb��ɂ���̂́A������ߐ��Ɍ���ɂ����u�炭����v�ł���B |
|
|
|
| 2013�N2��26���i�j |
| �Ђǂ��������ɍs��������E��Z |
�@1936�i���a11�j�N�̍����A��E��Z�������N�������B���R�c���h�i�����ǂ��́j�̐N���Z���A�u���a�ېV�v��f�s���ׂ��A���m���E����P�S�O�O���𗦂��ĉ��c�[��A�֓����i�����Ƃ��܂��Ɓj����b�E���������i�����͂����ꂫ��j������d�b����P���A�S���Ԃɂ킽���ē����̒�������苒�����B���̓��͂Ђǂ��������������B
�@�����ŁA���́A���̂悤�Ȍ�C���킹�ł��̎������o����B
�@�@�@�@�@�@�@�Ђǂ����i�P�X�R�U�j�����ɍs���i�c���j������E��Z�B
|
|
|
|
| 2013�N2��25���i���j |
| ���сi����ڂ��B�H�`746�j |
�@729�N�A�ז��҂̒����������E�ɒǂ�����ŁA�����q���V�c�̍c�@�ɂ����邱�Ƃɐ������������l�Z��B��т����̊ԁA���鋞���P�����V�R���̗��s�ɂ���āA�������ŕa�v���Ă��܂����B
�@�����Đ������������̂��k���Z�������B���Z�͓��A��̋g���^���ƌ��т𐭎��ږ�ɂ��A���������[�h�����B
�@�ʔ����Ȃ��̂́A��ɕ{�̖�l�Ƃ��ċ�B�ŕs������i�����j���Ă��������L�k�������B���員�����Əo�g�̎����������u���āA�������E�ł́A�ǂ��̔n�̍����킩��Ȃ��m����c�Ɋw�҂����͂��ӂ���Ă���̂��B�����A���т������V�c�̐M�������������́A���炭�T�a�������{�q�i�����̐���j�����̖@�͂ɂ���ĉ������������Ƃɂ��B�ǂ��ɂ��ӎU�L���z���B
�@�T�����Ă����L�k�́A740�N�A���тƋg���^���𐭎��ږ₩�珜�����Ƃ����߂ċ��������B�����L�k�̗��ł���B�������A���͒�������A�L�k�͎a��ꂽ�B
�@���̌�A���т́A�m���Ƃ��Ă̍s���ɔw���s�ׂ����������߁A�}���ϐ������ɗ�����āA�����Ŗv�����B�䓪���Ă������������C�ɂ���Ĕr�˂��ꂽ�Ƃ��A�����V�c�̌�p�ґI��Ɍ����͂��s���s�ׂ����܂ꂽ�Ƃ��A���т������ꂽ���R�Ɋւ��Ă͂��낢��Ɖ���������B
�@�����A�����̐l�тƂ́A���ю����̗��R�����R���Ƃ͔F�߂Ȃ������B�L�k�̉���ɂ���ĊQ����ꂽ�̂��A�Ɖ\���������̂ł���B�Ȃ��A�ޗǎs�ɂ��铪���i���Ƃ��j�����т̎�˂Ƃ��鑭��������B
|
|
|
|
| 2013�N2��24���i���j |
| �t�ɕ�����ł����̂�������������i�k�O���Q�j |
�@�{�q����c�q�i���тƂ݂̂��B��̐����V�c�j�ނƁA�O�����܂��s�䓙�Ƃ̊ԂɈ��h�Q (�������ׂЂ�) �B���h�Q�͂̂��ɐ����V�c�̕v�l�i�̂��ɍc�@�j�ƂȂ�����q�ł���B
�@�O���́A�Ăѓ���ɂȂ��āA���̏����̕v�ƂȂ��c�q��{�炵���B�O���͂���ŁA�����E�������q���̓�����Ƃ߂����ƂɂȂ�B
�@708(�a����)�N11��25���A�����V�c�i�����V�c�̕�j�͑H�N�另�Ձi���������傤�����j�ɍۂ��A�O���̒��N�̌��тɕ邽�߁A�t�ɕ����ԋk�ƂƂ��ɋk�h�H�i�����Ȃ̂����ˁj�̎��������������B�����V�c�́u�E�߂̋k�v�����Ă����B�䂦�ɁA�k�̉����͓V�c�̎O���ɑ���M���̌�����낤�B
�@716(��T2)�N�A�s�䓙�ƎO���́A���̈��h�Q����c���q�̕v�l�Ƃ��邱�Ƃɐ���������̂́A4�N���720 (�{�V4)�N�A�s�䓙�͕s�A�̋q�ƂȂ��Ă��܂��B
�@721(�{�V5)�N�A��������V�c���d�ĂɂȂ�ƁA�O���͂������o�Ƃ����̉��F�����B733�i�V��5�j�N�v�B����ʂƑ�v�l��Ǒ����ꂽ�B
�@��v�̎q�A���鉤�E�����̌Z��́A�O���̎��ɂ���ċk�����₦�邱�Ƃ����ꂽ�B�����ŕꐩ���p�����Ƃ��肢�A�����ꂽ�B��l�͐b�Ѝ~�����āA���ꂼ��k���Z�E�k���ׂƖ��̂����B
|
|
|
|
| 2013�N2��23���i�y�j |
| �k���̂���c�i�k�O���P�j |
�@�������k�i������Ƃ����j���l���i�������j�Ƃ����B���Ȃ킿�����A�����A�������A�k�����B���̂����k���́A�ޗǎ���̋k�O���i�����Ȃ݂̂���B�H�`733)�Ƃ�����l�̏����ɂ͂��܂�B
�@�O���͌����{���l (���������ʂ����̂����܂Ђ�) �̖��ŁA�ŏ��A�����{�O���Ƃ������B
�@�����{���́A�ԑq�i�݂₯�j�̑q�ɂ��x�����錢�{���i���ʂ����ׁB�Ԍ��p�Ɍ������{���Ă����̂��낤�j���Ǘ����������i�Ƃ��݂̂���j�����B���i���ˁj�͘A�i�ނ炶�j���������A684�i�V���V�c13�j�N�A�V�����������ɍĕҐ��i���F���i�₭���̂��ˁj�j�����ہA�h�H�i�����ˁj���ƂȂ����B
�@�O���́A�V���E�����E�����E�����E�����̗��V�c�ɁA��{�i�������イ�j�����Ƃ��Ďd�����B���w�i�݂傤�ԁj�������Ƃ����ȊO�͂悭�킩��Ȃ��B
�@���̂����A�O���͍c���̔��w (�݂�) ���ƌ��������B���w ���͕q�B�i�т��j�V�c�l���̎q���ɂ�����Ƃ����B�����āA���鉤 (���炬�����B�k���Z)
�E���� ��(����) ���E���R (�ނ�)���� (�����[�O�i�ӂ������j�̍�)�̎O�q�ށB
�@���鉤��A�y�c�q�i����݂̂��j�̓���ƂȂ����B���̍c�q���A�̂��̕����V�c�ł���B
�@�����V�c�����ʂ���ƁA�����s�䓙�͖��̋{�q�i�݂₱�j�����̕v�l�i�Ԃɂ�j�Ƃ��ē����i���ゾ���j�������B���̎��A��{�̎��͎҂������O��オ�A�{�q�̓����ɋ��͂����Ƃ����B������@�ɁA�O���ƕs�䓙�͋}���ɐڋ߂����B���傤�ǔ��w���͑�ɐ��i�������̂��j�Ƃ��ċ�B�ɕ��C���ł���A�s�䓙�͐܂������Ȃ�S�����Ă��������������B
�@�O���͔��w���Ɨ�������ƁA�s�䓙�ƍč������B
|
|
|
|
| 2013�N2��22���i���j |
| �����͐������q�̖��� |
�@622�i���ÓV�c30�j�N�̍����i2��22���j�A�������q�i�X�ˉ��j�������{�i�����邪�݂̂�j�ŖS���Ȃ����B49�������Ƃ����B�w���{���I�x�ɂ��ƁA���q�̓ˑR�̎��ɁA�����E���b���͂��߁A�����̐l�тƂ��Q���߂��Ƃ����B
�@�ߔN�́A���̎��݂����^�⎋����Ă��鐹�����q�B�ނ����݂̐l���������ƌ���ꍇ�ɂ́A�ÎE���E�a�����E���E�����A���܂��܂ɂ��̎��̌�������荹������Ă���B����͎j���i���{���I�A�������q�`��Ȃǁj�ɁA�������q�́u�������ɓˑR�̂��ƂŁA���̂��߁A�l�X�̃V���b�N�������ւ�傫�������Ƃ����ӂ��ɏ����āv�i�p�쏑�X�ҁw���{�j�T�K�R�x1984�N�A�p�앶�ɁAP.77�j���邩�炾�B�ǂ����A���R���Ƃ͍l�����Ȃ��B�������A�^���͕s���ł���B
�@���̎��A���q�̕����̎t�������m�d���i�����j�́A���łɖ{���̍����ɋA���Ă����B���q���]��ɐڂ��A�u���q���S���Ȃ��Ď����ЂƂ肪�����Ȃ��炦�Ă��Ă����̉v�����낤�v�Ƃ����A���N�̑��q�̖����ɁA���̌��t�ʂ葾�q�̂��Ƃ�ǂ����Ƃ����B
�@2��22���͂܂��u�|���̓��v�A�u�L�̓��v�B |
|
|
|
| 2013�N2��21���i�j |
| ���������N�@�ɂ͋C�����悤 |
�@�g���C�A��Ղ̔��@�ŗL���ȃV�����[�}���i1822�`1890�j�B�ӔN��10�N�ԁA�ނ��Z���~�̓M���V�A�̃A�e�l�s���Ɍ����Ă���B�V�����[�}���͂��̉��~���u�C���[�E�E���[���g�����v�Ɩ��Â����B����u�C���I���̏����v�Ƃ����Ӗ��ŁA�e���ȏ�����A�z������B���ۂɂ̓z�����X�̒��Ńg���C�A�̐_�́u�{�a�v���Ӗ������ł���A���̖��Ɉ��ʍ��@���Ƃ����B
�@�u�C���[�E�E���[���g�����v�̈�Ԃ̓����́A�e�����̃h�A�̏�̕ǖʂɁA�Ñ�M���V�A�̌��l�����̌��t���f�����Ă������Ƃ������B�����ɂ́u���������f�i���イ�悤�j���̐S�ł���v�Ƃ��u���i�Ȃj���g��m��v�Ƃ������x�傪��������Ă������B
�@�Ƃ���ŁA���f������V�����[�}�����g�A����̂��Ƃ��悭�m���Ă������낤���B
�@�ނ́A���������N���ɂ��Ă����B���N�ێ��̗B��̕��@���C�������ƐM���A�Ă͑����S������A�~�ł��T������̐������������Ȃ������Ƃ����B���̉��������N�@�̌��ʁA�������i��������j�������点�Ă��܂��A���ꂪ���ƂŖ��𗎂Ƃ��͂߂ɂȂ����B
�@1890�N�A�V�����[�}���́A�N���X�}�X���Ƒ��Ɖ߂������߂ɋA���r���A�i�|���̘H��œ|�ꂽ�B�N���X�}�X�̗����i12��26���j�A�}���B68�������B
�i�g�D�V�����[�}�����A�Έ�a�q��w�V�����[�}�����s�L�@�����E���{�x1998�N�A�u�k�Њw�p���ɔŁAP.198�`199�EP.209�`211�j
|
|
|
|
| 2013�N2��20���i���j |
| �T�C�����~�����Q |
�@�Ƃ���ŁA�Ȃ��A�֓��̕��m�����́A�����Ǝ�]�W�����̂��낤���B����́A���������̉Ƃ�y�n�ȂǁA���Y�̑��������������ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�����S�����A�ނ�̓y�n�́A�������̕��m�����̐N���ɂ��炳��Ă����B�֓����m�����́A���������̓y�n��ۏ�i�{�̈��g�j���Ă����A�����ȊO�̌��Ў҂����߂Ă����̂��B���̓_�ɂ����āA�����̓������闊���́A�����œ|�Ɋ֓����m���������W�����鋁�S�͂������Ă����B
�@�����A�֓��݂̂Ȃ炢���m�炸�A���q���{�̎x�z�����S���Ɋg�債�Ă����ƁA���܂ł������Ƃ����l�̃J���X�}���ɗ����Ă͂����Ȃ��Ȃ�B�S���I�Ȑ������ێ����邽�߂ɂ́A�ǂ����Ă��吨�̖�l�ŁA�����S���邱�Ƃ��K�v���B�����ŁA�����l���������Ă��������i�������������j���A�������������镶���i���R�Ɛ��������j�Ɉڍs����悤�ɃV�X�e�����ς���ꂽ�B
�@�������A���̃V�X�e���ύX�ɑ��āA���������̍�����]���Ă�����t����i���˂��ˁB1118�`1201�j�炩��٘_�̐������������B��������l�Ƌ����̂͊��q�a�i�����j�ł����āA�����ȂǂƂ��������ł͂Ȃ��A���q�a�̒����̓������������~�����Ƃ����̂��B
�@���ǁA���{�n�Ƃɑ傫�ȗ͂̂������L�͌�Ɛl����Ȃ��߂邽�߂ɁA�����͏]���̑��������s������Ȃ������B |
|
|
|
| 2013�N2��19���i�j |
| �T�C�����~�����P |
�@�������i1147�`99�j�̃T�C�����������������A�u�������������i���ł͂����Ԃ݁j�v�Ƃ����B�E�M�i�䂤�Ђj�������������̓��e���A�����̈ӎv�Ɋ�Â����̂ł��邱�Ƃ��ؖ����邽�߂ɁA�����̉E�[�i���j�̕����ɃT�C���i���j�����̂ł���B���̃T�C���̂��Ƃ������i�����͂�j�Ƃ��ԉ��i�������j�ȂǂƂ������B�����́A�����̖��O�u���v�̍������Ɓu���v�̉E�����A���Ȃ킿�u���v�Ɓu���v�����̂��������̂��A����̉ԉ��Ƃ��ėp�����B�����i�������Ԃ݁j�Ƃ����̂́A��ʂ̎҂��牺�ʂ̎҂ɑ��Ĕ������镶���ŁA�����̍ŏ����u���i�������j�v�Ƃ������t�Ŏn�܂�̂ł��̖�������B
�@�����̑�������������ƁA�ŏ��ɗ����̋���ȉԉ����ڂɔ�э���ł���B���q�a�̌��Ђ��A�s�[������̂ɁA�\���Ȍ��ʂ������Ă���B���q�a�ƌ�Ɛl�́u�l�Όl�v�̎�]�W���A�ڂɌ�����`�ŕ\�����Ă���̂��A���̉ԉ����B |
|
|
|
| 2013�N2��18���i���j |
| ��̐����g���������ꑰ�S |
�@�����������ɂ��ӂꂽ���ʁA�����̓������Ƌ�ʂ��邽�߂ɁA�n���ɎU���ēy�������������́A�y������������c���Ɏ����ꂽ�B���Ƃ��A���݂́u�����v�Ƃ����c���́A�u���v��ɓy�������u���v�����̖��Ⴞ�Ƃ����B�u���v�̎����܂ޕc�������ׂē������̎q�����Ƃ͌����Ȃ����낤���A�n���ɓy�������������̖����������c���ɂ́A���̂悤�Ȃ��̂�����B
�@�@ �@ �@�����{����������
�@�@�@�@�@���]�{�������]��
�@�@�@�@�@�ɐ��{�������ɓ�
�@�@�@�@�@�����{�����������@�Ȃ�
�@�܂��A�����ƊW�̂Ȃ�������������B���{���ƍ����W���������u�����v�A�d�����{���i�����݂̂�̂��݁j�������u�֓��v�A���ɐl�i���ǂ˂�j�������u�����v�ȂǁB |
|
|
|
| 2013�N2��17���i���j |
| ��̐����g���������ꑰ�R |
�@�����ߕҎ[�̒��S�l���Ƃ��āA�������Ɛ_�_�����咸�_�Ƃ�����{�Ǝ��̊����@�\�����グ���s�䓙�B���̓�̒��_��Ɛ肵���̂��������i�������j�ƒ��b���i�_�_���j�������B
�@�������ĕs�䓙�́A�Â��������x�̂��Ƃō��J��E���Ƃ��Ă������b���ꑰ���A���b���Ɠ������ɕ������邱�ƂŁA���ߑ̐��Ƃ����V���ȑ̐��ɑΉ������邱�Ƃɐ��������̂ł���B
�@�Ȍ�A�����̐��E�͓������ɂ���ċ������Ă����B���������ɉh�������ʁA�������̎q���͐��ɂ��ӂꂽ�B
|
|
|
|
| 2013�N2��16���i�y�j |
| ��̐����g���������ꑰ�Q |
�@701�i��j�N�A�����s�䓙�����S�ɂȂ��ĕҎ[���ꂽ��߂����ɏo��B��߂́A���̉i�J���߁i���������傤�j����{�ɍ��ꂽ�Ƃ����邪�A�������A���̂܂܂ł͂Ȃ��B���ߊ����̕s�䓙�ɂ���āA�s�䓙���ɏĂ���������Ă���̂��B
�@���Ƃ��A���̊����@�\�͎O�ȘZ���i���傤�肭�ԁj�Ƒ��̂���邪�A�����ȁE�剺�ȁE�����ȎO�Ȃ́A�c�邪�������s���ۂ̕⏕�@�ւɉ߂��Ȃ��B�����ł͍c��̓ƍٌ��������̂��B���̂��߁A�����ɑ���ӔC�́A�P���E�����̗��]���Ђ�����߂āA���ׂčc�邪�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����������ƁA�u�V�����v�i���炽�j�܂�v�ƂƂȂ��āA������D�����Ƃ���y�i�₩��j���o�Ă����i������j��������B�v���i�Ր��v���j���B
�@�Ƃ��낪�A���{�̏ꍇ�A���Ȉ��܉q�{�̒��_�ɂ���̂́A�������Ɛ_�_���ł���B�ǂ�������{�Ǝ��̂��̂ŁA�����ɂ͂Ȃ��B
�@�������́A�قƂ�ǓV�c�̐������s�ł���@�ւł���B�V�c�́u���l�_�i����ЂƂ��݁j�v�Ƃ��āA�����̐����ɐӔC�������Ȃ��B�䂦�ɁA�킪���̎d�g�݂́A�����̂悤�Ȋv���v�z�Ƃ͖������B
�@�܂��A�V�c���u���l�_�v�ł��邪�䂦�A�V�_�n�_�i�Ă��B�V�n�̐_�X�j���܂�_�_���̐ݒu���A�K�R�I�ɏo�Ă���B
�y�Q�l�z�E�p�쏑�X�ҁw���{�j�T�K�R�x1984�N�A�p�앶�ɁAP.300�`301�A��R�t�����ɂ�� |
|
|
|
| 2013�N2��15���i���j |
| ��̐����g���������ꑰ�P |
�@�V�q�V�c�́A��Ă̏��ɂ��������b�����̒��N�̌��т��������A��D���i�������傭����j�̊��ƁA�u�����v�̐��i���ˁj��^�����B
�@�u�����v���́A���Ƃ��Ɗ����l�ɗ^����ꂽ���̂��������A����Ȍ�A���b���ꑰ�́A���b���Ɠ�������K�X�A�g���������ėp����悤�ɂȂ����B���b����p���鎞�͐_�_�W�̎d���A��������p���鎞�͍s���W�̎d���ɂ��ꂼ��g����Ă����ꍇ�������B
�@698�i�����V�c2�j�N�A�����V�c�͒��b���ꑰ�ɑ��āA�����̋@�\����������悤�A�ق����B����ȍ~�A���b�ꑰ�͈Ӕ����C�i���݂܂�j�̎q���𒆐b���A�s�䓙�̎q�������Ƃ��邱�ƂƂȂ����B
�y�Q�l�z�E����N�F�w���{�̕����x2002�N�A��g�W���j�A�V���AP.52�`53
|
|
|
|
| 2013�N2��14���i�j |
| �u���v�̋�s�� |
�@1899(����32)�N�͈�N�������B�䂦�ɁA���̔N���s�̓��{��s���i10�~�D�j�͗��ɒ����`����A�u���v�̈��̂ŌĂꂽ�B
�@�Ƃ���ŁA����10�~�D�̕\���ɂ́A�a�C�����C�ƌ쉤�_�Ђ��`����Ă���B�Ȃ��A�a�C�����C���B����́A���̂悤�ȓ`���ɗR������B
�@�����̍c�ʂւ̖�S���������a�C�����C�������i�F�������_�������j���A������ɔz�����ꂽ�ۂ̍���ȗ��̂������A�����ށi�ȁj���ė����Ƃ�����Ȃ����B�������r��A�������������C�����猾��̂��߉F�������{�������ƁA�ˑR300������̒������ꂽ�B�����āA�����{�܂ł̓��̗������x�삵���̂��Ƃ����B
�@���s�̌쉤�_�Ђ́A�a�C�����C���쉤�喾�_�Ƃ����J��_�Ђ��i���Ɏo�̍L���i�Ђ�ނ��B�@�ϓ�j�Ǝt�̘H�L�i�i�݂��̂Ƃ�Ȃ��j�����J�j�B��ʂ̐_�Ђ͎Г��ɍ�����u�����A��L�̓`���ɂ���āA�쉤�_�Ђ͒���u���Ă���̂ł���B
�y�Q�l�z�E��C�ѐ��wfinal�@���{�j���ڂ�b�@�Ñ�E�����x2007�N�A�R��o�ŎЁAP.63�`66 |
|
|
|
| 2013�N2��13���i���j |
| �ŏ��̓��{��s���͂������������H |
�@�ŏ��̓��{��s���́A1885�N�ɔ��s���ꂽ10�~�̙[���⌔�������B�[���Ƃ͖{�ʉݕ��i���̏ꍇ�͋�݁j�ƌ����ł���Ƃ������́B�}�č쐬�҂̓C�^���A�l�̃L���\�[�l�B�����F�ŁA2�U�̕ĕU�̏�ɂ����单�V��`�����B�����ŁA�u�单�D�i�����������j�v�Ƃ��Ăꂽ�B
�@�单�V�͕����̎��_�i�V���j�̈�B�����_�̈�l�ŁA�����ɐ��̐_�Ƃ��ėL�����B�������A�{���̓C���h�̃}�[�n�J�[���i�单�̈ӁB�V���@�_�̜|�{���j�ŁA���E�퓬�E�L�`�E���Y�̐_�������B���ꂪ�����ɓ`���Ƒ܂�w�����A���{�ł͂���ɕU��������ꂽ�B�킪���ł́A�u�����̔��e�i���Ȃ̂��낤�����j�v�̐_�b�ŗL���ȑ卑�喽�i�������ɂʂ��݂̂��Ɓj�ƏK�����āA�M����Ă����B1886�N�܂łɔ��s���ꂽ1�~�E5�~�E100�~���́A���ׂđ单�V��`���Ă���B
�@�������A���̍ŏ��̋�s���́A�����ƃg���u�������������B
�@�����F�ɂ����̂́A�ʐ^�Ɏʂ�ɂ������āA�U����h�~���邽�߂̍H�v�������B�������A�F�̊痿�ɉ����i����ς��B�g���͉���Y�_���Ō×����甒�F�痿�Ƃ��Ďg�p����Ă����j���܂�ł������߁A����n�ł͗������f�Ɖ��w�������N�����č�����ł��܂����Ƃ��������B�܂��A�p������v�ɂ��邽�߂����蕲����ꂽ���Ƃ������ɂȂ��āA�l�Y�~�⒎�ɂ�������Ƃ����H�Q�����������B |
|
|
|
| 2013�N2��12���i�j |
| ���{��s�{�X |
�@��s���̔��s��P���s�ɏW��������������A������s���x�Ƃ����B������s���x�́A�X�E�F�[�f���Ɏn�܂�Ƃ����B
�@�킪���Œ�����s�̖����́A���{��s���S�����B���̐ݗ���1882�i����15�j�N�B�呠���������`�̎��ł���B
�@����������{��s�{�X��v�E�{�H�����̂͒C�����i1854�`1919�j�B���[���b�p�e�n�̋�s�������̂��A�]�˂̋����ՂɌ����B1890�N�ɒ��H���A1896�N�ɏv�H�����B�u�C�쌘�Łi���̂��j�v�Ƃ��������ꂽ���������āA�����E�Α��A���l�T���X�l���̏d�����łȍ앗�ƂȂ��Ă���B���R���낤���A�����̊O�ς�^�ォ�猩��ƁA�u�~�v�̎��`�ɂȂ��Ă���B
�@�捠�A2�K���Ă���{����3�K���Ăɕ������ꂽ�����w���A�C��̐v�B������̓A���X�e���_��������ԏ��͂����A���_���Ȑԗ������̌������B |
|
|
|
| 2013�N2��11���i���j |
| �y������ |
�@���E��E���Ȃǂō���������ݕ��́A�n�����̂ɉ��l������������M�p���ꂽ�B�������A���z�ɂȂ�ƁA�����^�Ԃ̂ɏd���A�g�p����̂ɉ����ƕs�ւ������B
�@���Ƃ��A���K�P���̏d���͂P��i����߁j�A���Ȃ킿3.75���ɉ߂��Ȃ��������A1000�����Ȃ킿�P�ѕ��ɂȂ��3.75�����ɂ��Ȃ����B�����ŁA���i�͏d���Ă���������ݕ��������������A�����ƈ��S�Ōy�����������g�p���邱�Ƃ��l���o���ꂽ�B
�@���E�ŏ��߂Ă��������������i���Ȃ킿�����j��������̂́A�����l�������Ƃ����B�k�v����́u���q�i�������j�v�����ꂾ�B
�@�킪���̎������s�̍ŏ��́A�]�ˎ��㏉���A�ɐ��Ŕ��s���ꂽ�R�c�H���i��܂��͂����j�Ƃ����B |
|
|
|
| 2013�N2��10���i���j |
| �K�̕a |
�@���ߐ��{���~�K���ʗ߂��͂��߁A���܂��܂Ȏ��ł��ĉݕ��̗��ʂ𑣂������A���̎g�p�͋E���₻�̎��ӂɌ��肳��Ă����B�܂��܂����X�������嗬�ŁA�S���I�K�͂ʼnݕ���K�v�Ƃ���قǁA�o�ς����W���Ă��Ȃ������̂ł���B
�@���̂����A10���I�ɂȂ�ƁA���{�̉ݕ��������Ɓi�{���\��K�j�͏I�����Ă��܂��B����́A�ݕ��s�ł��Ȃ��قǁA���ߐ��{�����ނ��Ă��܂������Ƃ��Ӗ�����B�������A�ݕ������s����Ȃ��Ȃ��Ă��A�����̐l�тƂ̌o�ϐ������x������������Ƃ����b�͕����Ȃ��B����͂܂�Ƃ���A10���I���_�̌o�Ϗł��A�ݕ���K�{�̂��̂Ƃ��ĎЉ�v�����Ă͂��Ȃ������Ƃ������ƂȂ̂��B
�@�Ƃ��낪12���I�㔼�A���Ƃ����v�f�Ղ��s���āA��ʂ̑v�K����{�ɂ����炷�悤�ɂȂ�ƁA�ݕ��o�ς����������`���a�̂悤�ɓ��{�S���ɍL�����Ă������B
�@���ƑS���̍��A�`���a�����s����ƁA�l�тƂ͂�����u�K�̕a�v�ƌĂ�ŋ��ꂽ�B���퐶���̒��ɑK�����킶��Z�������������ƂɁA�l�тƂ͓`���a�Ɨގ��̔��C�������������āA���悤�Ȍ��t�œ`���a��\�������̂��낤�B
�@�����āA�����ȍ~���݂Ɏ���܂ŁA�ݕ��o�ς͂��Ɍ�߂肷�邱�Ƃ͂Ȃ������B
�y�Q�l�z�E�r�ؐM�`�u�������E�W�p���O�`������E���̓��{�j�v
�@�@�@�@�@�|�wNHK�m����y���ށ@���j�ɍD��S�x2006�N�x8���9���e�L�X�g�AP.126�`128�| |
|
|
|
| 2013�N2��9���i�y�j |
| �����i�����g���T�j |
�@���̉��l��l���̗͗ʂȂǂ肷�镨�����u�����i�������j�v�Ƃ����B����́A���Ƃ��Ƌ����Ŏg���Ă����������ꌹ���B
�@�����́A�����ɏ����Ȃǂ���������āA�����ɂ����ꂽ�����F�i���傤���傭�j���A�����_�i�W�������j�̐F�Ɣ�r���āA���̔Z�x�肷�铹��ł���B���̒n����Â����݁A�܂������r���̋��݂̕i�ʂׂ邽�߂ɗp����ꂽ�B
�@�����̌����ƂȂ鍕�ɂ́A�����ς�ߒq���i�Ȃ����낢���j���p����ꂽ�B���݂̎O�d���F��s�_�쒬����Y�o�����S��i�˂��j�̈��ł���B���F���k���i���݂j�Ȃ̂ŁA������������������A�����F�����ʂ��₷���̂��B���݁A�ߒq���͌��i������j���i�������j�̍��Ȃǂɗ��p����Ă���B�@
�y�Q�l�z�E�V���w�u�]�ˎ���̋����Ə����̐����H���v�|NICHIGIN�@2008�N�A��14�|
�@�@�@�@�@�@�@�i�C���^�[�l�b�g�ʼn{���\�j |
|
|
|
| 2013�N2��8���i���j |
| �������낦��i�����g���S�j |
�@�M�����ł�����́A�_�낤���A�u���b�N�낤���A�܂�������ł��낤���A���̌`��ɊW�Ȃ��A���Ƃ��Ď�������B���Ȃ̂͌`��ł͂Ȃ��A�i�ʂƏd�ʂȂ̂��B
�@�����Ȃ�ƁA���m�b������₩�炪�o�Ă���B�����̉��i�ւ�j�����X���⏬���łق�̏��������A��������ďW�ߒ��߂����������Ă������悤�Ɗ�B�����āA���ꂽ�����̕��́A�f�m��ʊ炵�Ďg���Ă��܂��̂��B
�@���̕s�������j��ɂ́A�������������d�˂Ă݂�悢�B�s�������鏬���͍��ꂽ���̕�������ւ���ł���̂ŁA�������d�˂邱�Ƃɂ���Č������邱�Ƃ��ł���̂��B�����ŁA�������ł��ڂ��Ȃ����ꂢ�ɏd�Ȃ����ꍇ���A�����̍��E���[�����Ɍ����ĂāA�u�����̎������낤�v�Ƃ����B�؋�����x�Ɋ��ς��邱�Ƃ��u�������낦�ĕԂ��v�Ƃ����̂́A�������炫�Ă���B |
|
|
|
| 2013�N2��7���i�j |
| �����͎���ō���Ă����i�����g���R�j |
�@�u�]�ˎ���A�����Ȃǂ̋��݂́A�]�˂̋����ō��ꂽ�v�B�m���A���Z�̓��{�j�̎��ԂɁA������������B
�@�������A���Ȃ��Ƃ����\����ȑO�́A�吨�̐E�l����̍H�[�ɏW�܂��ċ��ݐ����ɏ]�����Ă����̂ł͂Ȃ������B�E�l���ꂼ�ꂪ�A����ō���Ă����̂ł���B�܂蓖���́A�E�l�̎��Ɖc�Ƃ������̂��B
�@���\�ȑO�́A�����t�Ə̂���E�l�������A�e���̉Ƃŏ����𒒑����Ă����B������u��O���i�Ă܂��Ԃ��j�v�Ƃ����B�����͌��������㓡���O�Y�̉ƂɏW�߂��Č������A���i�������̂ɂ͋Ɉ�i��������j���ō����ꂽ�B
�@�������A�����������U�^�̐��Y�����͊Ǘ���D�܂������Ƃł͂Ȃ������̂ŁA���\����̉ݕ��������@�ɁA�]�ˋ������ł̏W�����Y�̐��ɉ��߂�ꂽ�̂ł���B
�@
�@�Ȃ��A�]�ˏ����ɂ́A�����͍]�ˁE���s�E�x�́E���n�ɂ������B�]�˂̋����̐Ւn�ɂ́A���ݓ��{��s�{�X�������Ă���B |
|
|
|
| 2013�N2��6���i���j |
| ���̂����܂�i�����g���Q�j |
�@����ɂ���ƁA���x�͕ʂ̍�������肪�o�Ă����B�����܂�ɂ���ƁA�K�v�ȕ������蕪���邱�Ƃ�����̂��B�����A����͏����ȋψ�̏d�ʂɕ����邱�Ƃ��ł���Ή����ł���B������A�]�ˎ���̋��݂́A�����d�ʂɕ�����ꂽ�v���ݕ��Ȃ̂��B���݂𐔂���P���E�Q���́u���v�Ƃ����P�ʂ́A���Ƃ��Ƃ͏d���̒P�ʁi�P���͖�16.5���j�ł���B
�@�������A�������肪�������B�u���b�N��̋���̌`���ƁA���̒��g�܂ŋώ��Ȃ̂��ǂ����킩��Ȃ��B������������A�\�ʂ����������b�L�ŁA���g�͕������i�܂������́j���Ƃ������Ƃ������蓾��B�����̋����i�̍����ŁA���̉��ז_���Ǝ҂̂��Ƃ֔���ɍs������A���̉��ז_�Ɏ������������i�O���������b�L�Œ��g�͓S�j�ȂǂƂ������b���������B
�@���̖����������邽�߂ɂ́A�Ȃ�ׂ����g���Ȃ��i�����݂��Ȃ��j�����悢�B�唻�⏬���Ȃǂ̋��݂���ɔ����@���̂���Ă���̂́A�����������̉�����_�������̂ƍl�����Ă���B |
|
|
|
| 2013�N2��5���i�j |
| �����i�����g���P�j |
�@�a���J�݂��͂��߁A�Ñ�E�����܂ł̓��K�͂P���P���̂��̂����Ȃ������B�s�v�c�Ȃ��ƂɁA�P��100�����Ƃ�1000�����Ƃ��������z�ݕ������Ȃ������̂ł���B�������݁A�P���P�~�̉ݕ������Ȃ���ԂŁA���Ƃ���200���~�̎����Ԃ������w�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���ƁA�����̎�����l���������ł��C�������Ȃ�B�́A���z���i���ꍇ�ɂ́A�ǂ����Ă����̂��낤�B
�@���́A���K��艿�l�̍����A�������g�p���Ă����̂��B
�@�������A���͉ݕ��ł͂Ȃ��A���Ȃǂ��玩�R���Ƃ��č̏W���ꂽ�����̌`�Ŏg�p���ꂽ�B�����A�����̓o���o���ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA��������������B�ŏ��̂����͎��ɕ��A�|���ɓ��ꂽ�肵�ďd�ʂŎ�������Ă����B�������A�s�ւ������̂ŁA���̂����n�����ĉ�i�����܂�j�ɂ���悤�ɂȂ����̂��B |
|
|
|
| 2013�N2��4���i���j |
| �U�����̔����i�a���J�݂T�j |
�@���ߐ����A�U�����̔������u�a�i����j�v�ł��������Ƃ͑O�ɏ������B�w�����{�I�x�a��4(711)�N10��23���̏��i���}�Г��m���ɔŁAP.128�`129�j�ɂ́A�U�����Ɋւ��邻�̑��̔����������Ă���B���e����悤�B
�@�@�@�@��Ɓ@�@�@�F�a�Y
�@�@�@�@�]������ �F���ɖv���i���ˁE���z�X�Ƃ���j
�@�@�@�@�Ƒ��@�@�@�F���Y
�@�@�@�@�ܕ� �@�@ �F�m��Ȃ��疳�͓��߁A�m��Ȃ������ꍇ�͍ߌܓ�����������
�@�@�@�@�U�����g�p����������@�F�߈ꓙ��������
�@�@�@�@�U���𖢎g�p�Ŏ���@�@�F�ƍ�
�@�@�@�@�Ɛl���B�����͂��@�@�@�@�F�Ɛl�Ɠ���
�@�ܕہi���فj�Ƃ����̂́A�]�ˎ���̔_���ɂ������ܐl�g�̂悤�Ȃ��́B�A�ѐӔC�����ߏ��̂��Ƃ��B�����A�ƍs��m��Ȃ��Ă����������Ȃ�āA�������Ɨ��s�s�������Ǝv����B |
|
|
|
| 2013�N2��3���i���j |
| �{���\��K�̓��Z�b�g�{�^���i�a���J�݂S�j |
�@�a���J�݂ɂ͋�K�����������A�����ɗ��ʂ��֎~����A�����ς瓺�K�����ʂ����B���ʂ����Ƃ����Ă��A�����̓��{�͂܂��܂��ݕ��o�ς̒i�K�ɓ����Ă��炸�A�Ă�z�Ȃǂ�������X���������S�������B���{���K�̗��ʑ��i�ɖ�N�ɂȂ��Ă��A����͐��Y�Ɋ֗^�����A�s�Ő��������B���Ȃ���Ȃ�Ȃ��������ߊ��l��s�s����҂������W�܂镽�鋞�₻�̎��ӂ������ẮA�K�̗��ʂ͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ��Ƃ������B
�@�܂��A���K�ɂ́A���l�̎ړx�Ƃ��Ă̖����������B���ߐ��{�́A���K���̂����n���̉��l�ɂ���ׁA�����啝�ɒ����鉿�l�K�ɕt�^���Ă����B���{�́A���K���s�ɂ���đ��������ژ_�킯���B���̂������́A���鋞�̑��c�ɂ��g��ꂽ�͂��ł���B
�@�������A���K�����{���������ł���Ƃ������Ƃ́A�U���i�ɂ����ˁj�����o�������錜�O���������B�܂��A���K���̂ɏ\���Ȓn�����l���Ȃ���A���{�����߂���������ݕ����l��l�тƂ��M�p�����A�ݕ����l�̉������Ƃ��Ȃ��댯�����������B
�@�O�҂ɂ��ẮA���{�́A��������U���̉��s��\�z���Ă����B�����ŁA�U�����ɑ��ẮA���Ɓu�a�i����j�v�Ƃ����A�܌Y��\���̒��ł��ō��Y�i���Y�j�ŗՂނƂ������d�p����ł��o���Ă����B
�@��҂̉ݕ����l�ɂ��ẮA���Ƃ��Βn������10�~�̉��l�����Ȃ����̂����100�~�ƌ��������ċ������ʂ����Ă���킯������A���X���������K�I����������ɁA����ł͉ݕ����l���͈ێ��ł��܂��B�ݕ����l���������A�������㏸����͓̂�����O�ł���B
�@���̎��Ԃɑ��ẮA���{�͕�����������x�܂ŏ㏸����ƁA���̓s�x�V�ݕ��s����Ƃ�����i�őΏ������B���̍ہA�V�K1�������K10���Ɠ����ł���Ɛ錾�����B�܂�A10�{�ɂȂ����������A�V�K�ɂ���Ĉꋓ��1/10�ɂ��Ă��܂����ƍl�����킯�ł���B
�@�������ė��ߐ��{�͕������㏸����ƁA�Q�[���@�̃��Z�b�g�{�^���������悤�ɁA���X�ƐV�K�s���Ă������B���ꂪ�A�a���J�݈ȍ~�A�{���\��K�s�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��������R�ł���B
�@���ߐ��{�����ނ���ɂƂ��Ȃ��A�K�̎��͒ቺ�A�`���������Ȃ��Ă������B���ɂ́A10���I�̊������̔��s���Ō�ɁA���ߐ��{�̉ݕ������͏I����Ă��܂��̂ł���B |
|
|
|
| 2013�N2��2���i�y�j |
| �u����v���u�ق��v���i�a���J�݂R�j |
�@708�N�A�����������S�Ŏ��R�����Y�o�����B���ߐ��{�͂���𐐏ˁi�������傤�B�߂��ł������Ƃ��N���邫�����j�Ƃ��āA������a���Ɖ��߁A�a���J�݂�������B
�@�Ƃ���ŁA�Ȃ��a�u���v�J�݂ł͂Ȃ��̂��B
�@����ɂ́A�����̋Z�p�����n�ōׂ��������𒒑��ł��Ȃ������̂ŁA���̂��˂ւ���ȉ�i���傤�����j�����Ƃ�����B�a���͋g�ˋ�i�������傤���B�߂ł������t�j�䂦�̗p���ꂽ�̂ł���A�����̘a���Ƃ͒��ڊW�͂Ȃ��A�Ƃ�����Ȃǂ�����B
�@�v���ɁA�a�����̗p���ꂽ�̂́A�����̘a���ƒʉ����邩��ł͂Ȃ������낤���B
�@���ɁA�Ȃ��J�u�݁v�Ȃ̂��B
�@�݂͒��ّ̈̎��Łu����v�ƓǂށB���̊J���ʕ����{�ɂ����̂Ȃ�A�J�u��v�̂͂����B�����̉ݕ��̍Ō�̕����́u��v�ɂȂ��Ă��邵�A�킪���̖{���\��K���A�a���J�݂������āA�Ō�̕����͂��ׂāu��v�ɂȂ��Ă���B
�@�����ŁA�a���J�݂̓ǂݕ��ɂ��āA���̂悤�ȓ�����o�Ă���B
�@�݂͖{�����ّ̈̎��ł���A���Ƃ������t���̂��̂Ɂu������v�̈Ӗ�������B�a���J�݂͂��̂܂܁u��ǂ���������v�Ɠǂނׂ����Ƃ�����B
�@�a���J�݂����A�Ō�̕������u��v�łȂ��̂͂��������B�����Z�p�����n���������߁A�����̛̂��i������j���炤����ނ�ƊL���ȉ悵���̂��낤�B���������āA�u�݁v�͒��łȂ���ł����āA�a���J�݂́u��ǂ������ق��v�Ɠǂނׂ����Ƃ�����B
�@���݂́u��ǂ���������v�Ɠǂސ��̕����L�͂ł���B
|
|
|
|
| 2013�N2��1���i���j |
| �Ñ�̉ݕ��͎��v����i�a���J�݂Q�j |
�@�a���J�݁i��ǂ���������j�́A���v��0���̈ʒu�Ɂu�a�v�A3���Ɂu���v�A6���Ɂu�J�v�A9���Ɂu�݁v�̕��������ꂼ��z����Ă���B����́A�{���\��K���ׂĂɌ�����B�a���J�݂̂悤�ɏォ�玞�v���ɓǂނ̂��A�z�ǁi�����ǂ��j�Ƃ����B
�@�a���J�݂́A���̊J���ʕ�i����������ق��j���Q�l�ɂ��č��ꂽ�ƌ����Ă���B�Ƃ��낪�A�J���ʕ�́A0���Ɂu�J�v�A3���Ɂu�ʁv�A6���Ɂu���v�A9���Ɂu��v�̕��������ꂼ��z����Ă���B�ǂݕ��́A0����6����3����9���i�㉺�E���j�̏����B���̓ǂݕ���Γǁi�����ǂ��j�Ƃ����B
�@�Ȃ��A�a���J�݂Ǝ�{�ɂ����J���ʕ�̓ǂݏ����قȂ�̂��B�P���Ɏ��v���ɕ�����z���̂����m��Ȃ����A�킪���̑K�ݒ����ɂ��������l�тƂ��A�J���ʕ���u�J�ʌ���v�Ɠǂ݊ԈႦ�Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���Ȃ݂ɁA�]�ˎ���ɍ��ꂽ���i�ʕ�̕����z��́A�����K�Ƃ��Ȃ����ΓǂɂȂ��Ă���B
|
|
|
|
| 2013�N1��31���i�j |
| �܂邭�Ă������i�a���J�݂P�j |
�@�́A�q�ǂ��̂Ȃ��Ȃ��Ɂu�܂邭�Ă������B�ȁ[�v�Ƃ����̂��������B�����́u�i�ޗǂ́j�����݁v�B���̏o�����́u�ۂ��Ďl�p�v�ł͂Ȃ��A�u�܂邭�Ă��������i�ۂ��Ď��H���j�v�Əo���̂��B
�@�Ƃ���ŁA�x�{�K�i�ӂق�j��a���J�݁i��ǂ���������j�ȂǁA�����K��͂����ݕ��͂Ȃ��ۂ��A�����Ɏl�p�����������Ă���̂��낤�B����͒����̉A�z�v�z�ɂ���Ă���B�~�͓V��\���A�l�p�͒n��\���Ă���B������A�����c�邪�V�n���Ղ����V�d�͉~�`�ŁA�n�d�͕��`�������B
�@�������ݕ����~�`���E�̌`���Ƃ��āA���ꎩ�̂œV�n�A���Ȃ킿���̐��̈��\�����Ă���̂��Ƃ����B�v��|��ɏI����Ă͂��܂������A����V�c����������Ă��ݕ��̖��O�́u�����ʕ�i������ق��j�v�Ƃ������B�����͓V�n�̈ӂł���B����Ȃ�A�֊s���l�p�ŁA�����ۂ��ݕ��������Ă��悳�����Ȃ��̂��i�����̂Ƃ���͒��ׂĂ��Ȃ��̂ŁA�{���̂Ƃ���͂킩��Ȃ��j�B
�@�����Ƃ��A�ݕ������̎d�グ��Ƃ������ŁA���S�̌����~�`���Ɠs���͈����B�Ō�ɁA�������K�i���Ȃ�����j�̊O���ɂ͂ݏo���o���������̂����A���̂����͒������K���d�˂Ē��S�̌��Ɏl�p���_���������݁A���̗��[�������ă��X����u�i�Ƃ����j�ŃS�V�S�V����Đ��`�����B
�@���S�̌����~�`���Ɖݕ����_�ɂ�������Œ�ł��Ȃ��̂��B |
|
|
|
| 2013�N1��30���i���j |
| Moods�@cashey�i�ނ��������j |
|
�@����̂Â��B
�@�s�a���E�C���O���b�V���Ƃ��s�a���E�W���p�j�[�Y�Ƃ������ꍇ�́A�u�s�a���ipidgin�j�v�Ƃ������t�́A��̂ǂ������Ӗ��Ȃ̂��낤���B
�@�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂĂ݂�ƁA����́u�r�W�l�X�v���Ȃ܂������̂��Ƃ����Ă���A�Ə����Ă������i�w�L�ׁx��389���A1999�N6��10���A�uhttp://www.yurindo.co.jp/static/yurin/back/379_2.htl�v���Q�Ɓj�B��͂�A�r�W�l�X�̕K�v��A���܂ꂽ���t�̍H�v�Ȃ̂��B
�@����ł́A�s�a���E�W���p�j�[�Y����̏o��B���̉p�ꕗ�����̓��{��́A��̉���\���������̂��낤���B
�@�@�@�@�@�@�i��j��@Oh�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���O�@�i�I�[�A�}�C�����܂��j
�@�@�@�@��P�@Eel�@oh�@�@�@�@
�@�@�@�@��Q�@Oh�@terror�@
�@�@�@�@��R�@Am�@buy�@worry
�@�@�@�@��S�@She�@buyer
�@�@�@�@��T�@Sigh�@oh�@narrow
�@
�@�Ȃ��A�����Ɨp���m�肽����A���̘_�����Q�Ƃ��ꂽ���B
�@���{�L�v���u�����ېV�̓��p����ڐG�|���l�̉p��n�s�W�����{��i�P�j�|�v
�@�@�@�@�@�@�@�ihttp://www.seijo.ac.jp/graduate/gslit/orig/english/pdf/seng-42-18.pdf�j
�@�@�@�@���P�@�F�i�C�[���I�[������j
�@�@�@�@�@���Q�@�����i�I�[�e���[������j
�@�@�@�@�@���R�@���~�i���j�����i�A���o�C�E�H�[���[���������邢�A���q�������̈Ӂj
�@�@�@�@�@���S�@�ŋ����i�V�[�o�C���[��������j
�@�@�@�@�@���T�@���悤�Ȃ�i�T�C�I�[�i���[�j
|
|
|
|
| 2013�N1��29���i�j |
| �Í��̂悤�ȊO���� |
|
�@�������疾�����A�����n�ŊO���l�ƐڐG����悤�ɂȂ������{�̖��O�́A�p����g�킴��Ȃ��Ȃ����B���Ƃ��A���{�l���l���A�hHow much dollar?"�Ƃ������t�̈Ӗ��𗝉��ł��Ȃ���A����������O���l�q��ɏ����Ȃǂł��悤�͂����Ȃ��������炾�B
�@�Ȃ��p�ꂾ�����̂��B����͓��{�j�̋��ȏ����J���킩��B���ȏ��ɂ́A���̍��̖f�Ղ̂قƂ�ǂ͉��l�ōs���Ă������ƁA���������̖f�Ց��荑�̓C�M���X�����S���������ƁA����ɂ̓C�M���X�Ƃ̗A�o�����f�Պz�S�̂̒��łW�����߂Ă������ƁA�Ȃǂ�������Ă���B
�@�ł́A�ނ�͂ǂ�����āA�p����o�����̂��낤�B���́A�p��̔�������{��̗ގ����ɕ����Ȃ��Ƃ������@���Ƃ����̂��B���Ƃ��A��L�́hHow�@much dollar?�h(�l�i�͂�����H)�B���Ȃ킿�u�n�D�}�b�`�_���[�v���u�n�E�}�E�`�E�h�E���i�l�璹�j�v�ƕ����Ȃ��Ċo�����̂ł���B����ŁA�O���l���u�l�璹�v�ƌ������Ȃ�A�����������˂Ă���̂��Ƃ������Ƃ��킩��B���������ł������������p�p����A�s�a���E�C���O���b�V���Ƃ����B
�@����A���{�̋����n�ɏZ�ފO���l���A���{����o���Ȃ���ΐ����ł��Ȃ������B�p�ꂪ�킩����{�l�ȂǁA���݂����͂邩�ɏ��Ȃ��������炾�B�����ŁA�ނ�����{��̔������A�ގ�����p��̒P���Ԃ�ɒu�������Ċo���悤�Ɠw�͂����B������͂������߁A�s�a���E�W���p�j�[�Y�ł���B
�@���Ƃ��A���{�̂���E�Ƃ��A�hStart�@here�h�Ɗo�����B������Tailor�B���Ȃ킿�A�u�X�^�[�g�q�A���V�^�[�e���i�d�����j�v�Ȃ̂ł���B
�y�Q�l�z
�E�����V���w���D�O��E�u�m�ƌo�ρx1981�N�A��g���ɁAP.179�`185
|
|
|
|
| 2013�N1��28���i���j |
| �Í��̂悤�ȕ��� |
�@�Í��Ƃ����A�c�Ɂu�ꐶ�v�Ə������ꕶ���Łu�l�v�Ɠǂ�A�c�Ɂu�R���y�v�Ə������ꕶ���Łu�n�v�ƓǂނȂǁA�Ȃ��Ȃ��̂悤�ȕ��������A�����S�y�ɂ��̎g�p�������������l��������B���𒆒f�����Ď��𗧂Ă������j��B��̏���A���V���@�i�����Ă�Ԃ����B624�`705�j���B
�@�ޏ�����点�A�g�p������������17�����̊����𑥓V�����i�����Ă�����j�Ƃ����B689�N�ɂ܂�12���������z�E���肵�A690�N�A694�N�A697�N�ɂ�����A704�N�܂Ŏg�p�������B���V�����������Ɏg�p���ꂽ���Ԃ́A�قڂ���15�N�Ԃ������B
�@���V�����́A�����ł̎g�p���Ԃ����肳��邽�߁A�j�����ɑ��V�������g�p����Ă��邱�Ƃ������ɁA�j���̔N�オ����ł���Ǝ咣�������������B���V�����̎g�p�������ɁA�؍��c�B�̕������ň�����ꂽ�w���C�����ɗ���o�i�ނ����傤������������ɂ��傤�j�x�i�N��̋L�q�Ȃ��j�������A�����ŌÂ̈�������Ǝ咣���邱�ƂȂǂ����ꂾ�B
�@���V�����������̌������ȂǂŎg�p����Ă���ꍇ�A��L�̎咣�͂�����x�̑Ó������������m��Ȃ��B�������A����ȊO�̏ꍇ�͂ǂ����낤�B���Ƃ��A�؍��́w���C�����ɗ���o�x��������Ƃ��āu�����ŌÁv�ł���\���͂��낤�B�����A�N�����肷�邻�̑��̎j�����Ȃ��܂܁A���V�����̎g�p�����������Ɂu�����ŌÂ̈�����v�ƒf�肷�邱�Ƃ͂ł��܂��B
�@�Ȃ��Ȃ�A���V�����́A�������肩���̎��ӂ̊��������������ɂ��}���ɍL�܂�A��������ȍ~���g�p����Ă������炾�B�킪���ł��A8�`9���I�̏��j���ɑ��V������������B�܂��A�]�ˎ���Ɂw����{�j�x�̕Ҏ[�ɒ��肵�����˔ˎ哿������́u���v�Ƃ����������A���͑��V�����̈���B�����́A���V���@����1000�N����̐l���ł���B
�@���������āA�j�����ɑ��V������������Ƃ��������̗��R�������āA���̎j�������V���@����i��8���I�O���j�̂��̂ł���Ƃ́A�ȒP�ɂ͒f��ł��Ȃ��̂��B
�y�Q�l�z
�E�w�b�w���̓��x1997�N�A�W�p�Е��ɁAP.186�`187 |
|
|
|
| 2013�N1��27���i���j |
| ���t�����͈Í� |
�@�w���t�W�x�͖��t�����ŏ�����Ă���B���t�����͓���ŁA�N�����ǂނ��Ƃ��ł����킯�ł͂Ȃ������B���̂��߁A�\�������̂Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�����������ƁA���t�����͂����܂��ɔp��Ă��܂����B���t�����́A�������ǂ߂�҂��N��l�Ƃ��Ă��Ȃ��Í��ɂȂ��Ă��܂����̂��B
�@���̎���́A�w���t�W�x�̐��ƂɂƂ��Ă��������B���������āA�u����ɏ\�l�̖��t�w�҂ɑS�l��ܕS�]��̓ǂ݉�������点��A�\�l�̊Ԃɂ����炭���S�ӏ��Ƃ������Ⴊ�o�Ă��邱�ƕK��ł���B�|�����|�Ӓn���������Ȃ�A���ǂǂ̖{�ɋ����Ă݂��Ƃ���őS�ʓI�ȐM�p�͂����Ȃ��v�i���|���L�w�Ì�G�k�x1986�N�A��g�V���AP.186�j�̂��B
�@���Ƃ��A����̋��ȏ��ɕK���ڂ��Ă���`�{�l���C�̎��̘a�̂́A���̂悤�ɓǂނƂ����ۏ͂ǂ��ɂ��Ȃ��B
�@�@���i�Ђނ����j�̖�ɂ�����Ђ̗������Ă��ւ茩����Ό��X�i�����ԁj����
�@�����͂킸���P�S�����ł���B
�i�����j���쉊�������������Ҍ����n
�@���̌������A��L�̂悤�ɓǂ݉������͍̂]�ˎ���̍��w�҉�ΐ^���i�����̂܂Ԃ��j���B���܂�ɂ������ȓǂ݉����Ȃ̂ŁA�Ȍ㐔�S�N�Ԃɓn���Đl���C�̘a�̂͂��̂悤�ɓǂނ̂��A�Ƃ����͎v������ł����B�������A�^���ȑO�́A
�@�@�@�@���Âܖ�̂��Ԃ�̗��Ă鏊���Ă��ւ茩����Ό��X����
�Ɠǂ݉����Ă����B���݂ł��A���Ƃ��u�����n�v�́u�����n��v�Ƃ��̂܂ܓǂ݉����������A���̓��̏o�Ɛ��̌������ΏƂ����ĉ̈ӂ���������ʂ�A�Ȃǂƈ٘_�͑����B
�@�܂�Ƃ���A�^�C���}�V���ł���������āA��҂ɒ��ډ���Ď����Ă݂Ȃ����Ƃɂ́A�������ǂ݉����͂킩��Ȃ��̂��B |
|
|
|
| 2013�N1��26���i�y�j |
| �������ی�f�[ |
�@64�N�O�̍����A1949�i���a24�j�N1��26���ɁA�@�����������Ă����B
�@�����@�����́A�����E�d���̉�̍H�����������B�ЂɋC�Â����H���������̎����E�����A�����̖h�ΐ����Ƀz�[�X�����t���A�����̏��ɂ��������B�z�[�X�͂R�l������łȂ���Ύ��ĂȂ��قǐ������������̂������B�����̒��ɂ͖����������A�����̏��̍ۂɂ̓z�[�X�̃R���g���[�����������A�lj�ɑ�ʂ̐����������Ă��܂����B���̂��߁A�lj�̍ʐF���܂����������Ă��܂������肩�A�lj�ɑ匊�܂ł����Ă��܂����i�v�쌒�u�������̎��v�|�w�ʐ^�L�^���a�̗��j�C�x1984�N�A���w�ُ����|�j�B�������āA�@���������lj�͏đ������̂ł���B
�@���̌����͕s�������A�lj�̖͎ʍ�ƂŎg�p�����d�C�A���J�̓d���̐�Y��A�܂��͘R�d�ł͂Ȃ����Ƃ����Ă���B
�@���̕s�K�Ȏ��������������ƂȂ��ĕ������ی�@�����肳��A�������������B1��26�������ی�f�[�Ƃ����B |
|
|
|
| 2013�N1��25���i���j |
| �͑��� |
�@�����Ɍf�����Ă��鎞�Ԋ��\�B�傫�Ȗ͑����Ƀ}�W�b�N�E�C���N�ŏ����Ă��邱�Ƃ������B���āA���̖͑��������A��̉����u�͑��v���Ă���̂��낤�B
�@
�@1879(����12)�N�A�p���ŊJ���ꂽ����������ɁA�W�����F�Ō���̂��錘�S�E����̎荗���a�����o�i���ꂽ�B�呠�Ȉ���ǂŐ������ꂽ���߁u�ǎ��i���傭���j�v�̖��ŌĂꂽ���̎��́A�O���i�݂܂��j���匴���ɂ��Ă������ߔ��ɏ�v�������i���̏�v�ȓ����䂦�A�O���͌��݂ł������̌����Ƃ��Ďg�p����Ă���j�B�����ŗD�G����F�߂�ꂽ�ǎ��́A���܂̉h�_���B
�@����ȍ~�A���[���b�p�e�n�ł́A�ǎ��̖͑��i������ɍ����悤�ɂȂ����B�������A���̖͑��i�͖؍ރp���v�������������B���F���T�C�����̍ۂɂ��g��ꂽ���̖͑��i�́A�C�~�e�[�V�����E�W���p�j�[�Y�E�x�����iImitation Japanese vellum�B���Ȃ킿���{�̗r�玆�̖͑��i�j�ƌĂ�A���x�͓��{�ɋt�A������邱�ƂɂȂ����B
�@�܂�A���̘a���̖͑��i���A���{�ł���ɖ͑������̂����݂́u�͑����v�Ȃ̂ł���B |
|
|
|
| 2013�N1��24���i�j |
| ���~�� |
�@�]�ˎ���̑����B�헤���i�Ђ����̂��Ɂj�̎����喾�_���O���̋S�i���j�Ɛ�����B�����_�R�i���݂������j�Ƃ����B�܂��A�o�H���̔ѐ��ˁi��������Â��j�A���������C�i�Ƃ�̂��݁j�Ƃ����Ƃ���ɂ��_�R�Ƃ������Ƃ��������B���̏؋��ɁA�u�_���i��j�v�Ƃ����āA�V�i�₶��j�̂悤�Ȑ��~��Ƃ����B
�@�����Ȃ��ꏊ�ɁA�˔@�Ƃ����V�̂悤�Ȍ`���������A�����o�����邱�Ƃ͂��т��т������B�w�����{��I�x�A�w���{�O����^�x���ɂ��L�^����Ă���B
�@�������A�]�ˎ���̍����I���_�́A���������̓ˑR�̏o����,�u�_�R�v�ɋA�����Ƃ��悵�Ƃ��Ȃ������B
�@�w�L�v�����فi���������������ׂ�j�x�́A�u�_���i��j�v���u�V���ӂ�Ƃ͔�Ȃ�B�����ɂ���Ƃ���̐A��J�̂Ƃ�����Џo��������̂Ȃ�ׂ��v�Əq�ׂĂ���i���崗��w�L�v�����فx1989�N�A���}�Г��m���ɁAP.31�`32�j�B |
|
|
|
| 2013�N1��23���i���j |
| ����i�u�������Ē핐���v�R�j |
|
�@�`�������쒩�̑v�Ɏg�҂�h�������̂́A478�N�������B����̏����Q�N�ɂ�����B����͑O�N�̂V���A�c��̈ʂɂ����B�`�������A���N�A�������g�����̂́A�c��̑�ւ��ɍۂ��āA���N�����암�̌R�����̏��L�ƈ����叫�R�̏̍��̊l����v�����邽�߂ł���B
�@�]�̏ꍇ�͕s�������A�u�`�̌܉��v�̒N�����A���X�Ȃ܂łɏ�L�̎咣���J��Ԃ��J��Ԃ��s���Ă����B������M�݂́A���ۂɂ͌`���ȏ�̂��̂ł͂Ȃ������ɂ�������炸�ł���B���̂悤�Ɏ��X�Ɏ咣���J��Ԃ��Ă�������́A�`���ȊO�ɂ͂Ȃ��B���̂悤�ȁu�`�̌܉��v�����̍s�����A���Ԑ���i�Ƃ��܂������j���́u�߂��炵�����O�ł���A�v���̖�l�����ǂ납���ɑ������̂��������낤�v�i�����w�`�̌܉��x1968�N�A��g�V���AP.94�j�ƕ]���Ă���B
�@���̎��O������A���̎��`�����́A���邩��u�g���ߓs�`�E�V���E�C�߁E�����E�`�E��ؘZ�����R�������叫�R�`���v�̏̍���^�����Ă���B
�@�������A���ɏ̍���^��������͗�479�N�A�Ē����͂��߂��J�Д��i���傤���傤�͂��j�ɂ���Ĉʂ�ӒD�i���j����A�E����Ă��܂����B����13�������B�@
|
|
|
|
| 2013�N1��22���i�j |
| �}�����̕ρi�u�������Ē핐���v�Q�j |
�@�`�����͈��N�V�c�ɔ�肳��Ă���B���N�V�c�����o�܁i�������j�ɂ��āA�w�Î��L�x�͎��̂悤�ɓ`����B
�@�b����槌��i����j��M�����A�i�z�i�`�����B���N�V�c�j�̓I�I�N�T�J�̉����E���A���̍Ȃ̃i�K�^�̑�Y���i��������߁j��D���Ď����̍ȂƂ����B
�@���鎞�A�A�i�z�͍Ȃ̃i�K�^�Ɂu�}�����i�I�I�N�T�J�ƃi�K�^�̊Ԃɐ��܂ꂽ�j�q�j�������������ɁA�����}�����̕����E�������Ƃ�m������c�c�v�ƐQ����Ō�����B��a�̏����ŗV��ł����}�����́A�A�i�z�̂��̌��t�����R�����Ă��܂����B���ɂ�����āA��e�̌��݂̂ꂠ�����A���e�̂������Ƃ́c�B�}�����͂܂��V���������A�A�i�z���Q�Ă���Ƃ�������������āA���ɂ������品���Ƃ�ƃA�i�z�̎��藎�Ƃ����B���ꂪ�u�������āv�̐^�����B
�@���̌�ǂ��Ȃ������B
�@���̂����������}�����́A�b���̃c�u���I�z�~�̉Ƃɓ������B����A�Z�A�i�z���E���ꂽ�I�I�n�c�Z�i�`�����B�Y���V�c�j�͌��{���A�c�u���I�z�~�̉Ƃ��͂�Ő퓬�ɋy�B�I�I�n�c�Z���Ăт�����ƃc�u���I�z�~���o�Ă��āA���̂悤�Ɍ������B
�u���ƌ܃J���̑q�͂��Ȃ��Ɍ��サ�܂��傤�B�������}�������q�͎��𗊂��Ă���Ă��܂����B���Ȃ��l�ɏ����Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤���A���q�����̂Ă邱�Ƃ͂ł��܂���v
�@�������Đ퓬���ĊJ���ꂽ���A�c�u���I�z�~���͖�s���A�������A�������܂����B�}�������������Ƃɂ́u�����v�������Ȃ��B�킽�����E���Ă��������v�B�����ŁA�c�u���I�z�~�̓}�������h���E���āA����������Ď��Ƃ����B
�@�w�Î��L�x�́A�܂�Ō��Ă����݂����ɏ����Ă���B�����L����ǂނɂ��Ă��A�w���{���I�x���ʔ����B��N�́A�w�Î��L�x��������Ă��炿�傤��1300�N�̋L�O�̔N�������B��w�����ł��I�������A�w�Î��L�x���Ђ��Ƃ��Ă݂���H
�y�Q�l�z
�E�ɂɁw�Î��L�x������i���c�S�g��j������B |
|
|
|
| 2013�N1��21���i���j |
| �Z���^�[�������I���i�u�������Ē핐���v�P�j |
�@��w�����Z���^�[�������I������B�͍��m�E�x�l�b�Z�E��[�~�ȂǑ��\���Z�̕��ϓ_���������ƁA�O�N���͂�����A�S�̓I�ɕ��ϓ_�͉����邾�낤�Ƃ̌����݂��B
�@���{�j�̕��ϓ_��������炵�����A��N�̖��Ɣ�r���Ă݂Ă��A����قǓ���Ȃ����Ƃ͎v���Ȃ��B���������Ƃ��Ă��A������������P�╪���炢�i�R�_���炢�j�ŁA�W���I�ȃ��x���̖��ł͂Ȃ����ȁH
�@���̓��{�j�̑�Q��ɁA�`�����̏�\���i�w�v���x�`���`�j���j���Ƃ��ďo���B�S�V�W�N�ɘ`�����i�Y���V�c�j���v�̏���ɁA�����叫�R�Ȃǂ̏̍���v�������L���Ȏj�����B�u�������Ē핐���v�̃t���[�Y�ł͂��܂�B
�@�Ƃ���ŁA�����ǂ����Ď��̂��A���̌o�܁i�������j�����������낤���B |
|
|
|
| 2013�N1��20���i���j |
| �w�Í��a�̏W�x�Q |
�@ �w�Í��a�̏W�x�̂Ȃ��ɁA�ǂ̒������H���邩�A�Ƃ������Ƃɋ��������l�͗]�肢�܂��B�Ƃ肠�����A�G�N�Z���ɂ��܂��f�[�^���ڂ����̂ŁA�Ƃ肠�����͒��ł͂Ȃ��A�l�̕��ׂĂ݂��B�ǂ̎��i�����j�̉̂������̂��A�Z�̐�̍�̐��͂ǂ̂��炢���A�ׂ��B�i�@�j���́��́A�S��1,111���100%�Ƃ��Čv�Z�������̂��B
�@�w�Í��a�̏W�x�̌����҂ɂƂ��Ă͎����Ȃ��ƂȂ̂��낤���A�����[���v���l�����邾�낤�Ǝv���Љ�悤�B
�@�@�@�@�@�@�ǂݐl�m�炸 �@434��i39.1%�j
�@�@�@�@�A�@���ʂő�������
�@�@�@�@�@�@�@�@�P�ʁ@ �I���@�@ 163��i14.7%�j �����I�҂̋I�єV��102��i9.2%�j�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�ʁ@ �������@�@69��i 6.2%�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�R�ʁ@ �����@�@56��i 5.0%�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�S�ʁ@ ���쎁�@�@33��i 3.0%�j
�@�@�@�@�B�@�Z�̐�
�@�@�@�@�@�@�@�@�P�ʁ@ ���ƕ��@30��i 2.7%�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�ʁ@ ���쏬���@18��i 1.6%�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m���Տ��@18��i 1.6%�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�R�ʁ@ �����N�G�@ 5��i 0.5%�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�S�ʁ@ ��F����@ 2��i 0.2%�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�T�ʁ@ ���@�t�@ 1��i 0.1%�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Z�̐�v 74��i 6.7%�j
�@�w�Í��a�̏W�x��4���͓ǂݐl�m�炸�̉̂ł���B
�@���ʂŌ���ƁA�������ɖ����͂ł��Ȃ��̂��낤�A����������ʂɂ���B�������A�P�ʂ̋I���̔����ɂ��y�Ȃ��B���̋I���̒��ōő��Ȃ̂��A�I�єV���B�I�҂̓��������āA�w�Í��a�̏W�x�̖�P���������̉̂Ő�߂Ă���B�����I�ɂ͕s���ł������I���ƍ������A����������������Ƃ�͂ނ悤�Ȍ`�ɂȂ��Ă���B
�@�Z�̐�ł݂�ƁA�l�C�҂͂�͂��ʂR�ʂ܂łɏW���B�̐���������ƁA�c��R�l�͕t������A�̊�������B |
|
|
|
| 2013�N1��19���i�y�j |
| �w�Í��a�̏W�x�P |
�@�́A�ɂ��������������ɁA�ӂƁw���t�W�x��w�Í��a�̏W�x�Ȃǂ̒��ɂǂ�Ȓ������H�̂��Ă���̂��A�^��Ɏv�������Ƃ��������B�����ŁA���ɖ{��1�y�[�W���߂���Ȃ���A�J�[�h�ɘa�̂������ʂ��Ē��ׂ����Ƃ��������B
�@����ǂ��A�w���t�W�x���I����āA���낻��w�Í��a�̏W�x�ɂƂ肩���������A�Ñ㕶�w�̒��ɓo�ꂷ��E�O�C�X���A����W���g���Ē��ׂ��l�����邱�Ƃ�m�����B�t�ďH�~���ꂼ��̋G�߂��ƂɁA�ǂ̒�����ԑ��������o�ꂷ�邩�ׂ����̐l�̘_���������āA�}�ɋ����������Ē��ׂ�̂���߂Ă��܂����B���ׂ��J�[�h�ނ��A���̌�̉��̈����z���̒��ŁA�������Ă��܂��Ă����i�Ȃ��A���̘b�͕ʂ̋@��Ɂj�B
�@�Ƃ���ŁA�ŋ߁A�p�\�R���̒��̃t�@�C�������Ă�����A�́A���[�^�X123�ɓ��͂����w�Í��a�̏W�x�̃f�[�^���o�Ă����B���N��ɁA���̎��̋^����A���x�̓p�\�R�����g���Ē��ׂĂ݂悤�Ǝv�������āA���J���������ď�������1,111�����͂����̂����A���̌������ςȂ��ɂ����܂܂ɂȂ��Ă����B�d�����Z�����Ȃ��āA�w�Í��a�̏W�x�̒��ɂǂ�Ȓ������H���邩�A�ȂǗI���Ȃ��ƂׂĂ��鎞�ԂȂǂȂ��Ȃ��Ă�������ł���B
�@������A���\�N���O�ɑł����f�[�^�ł���B���������͂ł��Ă��邩�ǂ����`�F�b�N���Ă͂��Ȃ����A���݂̃p�\�R���ɂ���\�t�g�̓G�N�Z���Ȃ̂ŁA�Ƃ肠�����G�N�Z���Ƀf�[�^���ڂ��Ă݂��B |
|
|
|
| 2013�N1��18���i���j |
| �����J�����āA�{���͂ǂ�Ȑl�H |
�@��N�̓A�����J�ő哝�̑I���������B���������ˌ�����Ӗ��������炩�A�A�����J�ł̓����J���i�����J�[���j�Ɋւ���f�悪���{�����ꂽ�i�����J���͋��a�}�o�g�̑哝�́j�B
�@�����J���́A�u�̐l�`�v���̐l���̈�l���B����ꂪ�m��Ƃ���̔ނƂ����A�u�ۑ������o�g�̑哝�́v�A�u�Q�e�B�X�o�[�O�ł̖����`�i��̉����v�A�u�z�����̕��v�ł���A���݂����������u�̐l�`�v�ɂ����郊���J���̃C���[�W����A�����͎��R�ɂȂ��Ă͂��Ȃ��B
�@�����ŁA�{�I����A �{�Ԓ������w�����J�[���|�A�����J���吭���̐_�b�|�x�i�����V���A1968�N�j���A�v���Ԃ�Ɉ�������o���Ă݂��B���s�N�͂��������Â����A���e�͂��܂��ɐF�����Ă��Ȃ��B
�@���҂�1929�i���a�S�j�N�����ɐ��܂�A1949�i���a24�j�N�ɓ��勳�{�w�����{�w�Ȃ𑲋ƌ�A��w�����Ƃ��ăA�����J�j�E�A�����J�v�z�j����Ƃ��Ă����o�������B
�@���āA�����J���ɂ��ẮA�Q��ނ̑�������_�b�����݂���B��́A�����̖��b�I�p�Y�Ƃ��Ĕނ�`����������́B�A�����J���O�������l�Ԃ̗��z����\�����Ă���B������́A�{���̕���u�A�����J�����`�̐_�b�v�Ɏ������A�����`���ƂƂ��ẴA�����J���O���̗��z���ے�������̂Ƃ��Ă̐_�b�����ꂽ�ނ̓`�L�B
�@�{���́A��҂̐_�b����A�_�b���̃��F�[��������āu�^�̃����J���v����`���o�����Ƃ������̂��B���������Ė{���ɕ`����郊���J���́A�ۑ���������z���C�g�n�E�X�܂��Ă��̂ڂ������u�`���̐l���ł��A�t�����e�B�A���_�̌����ł��A�܂��z�����ɗ����オ�������z��`�҂ł�����Ȃ��B�{���ɂ����āA�����J���͓O���O���A�����I�Ȑl�ԂƂ��ĕ`����Ă���̂��B
�@�{����ǂ߂A�����J���ɑ���Љ��ʂ̃C���[�W�͕�����邱�Ƃ��낤�B�������A�������Ƃ��Ă��A��͂胊���J���͈̑傾�����A�Ƃ��킴��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�ނ́A�哝�̂Ƃ��ăA�����J���O���̖����`�Ɠ������邽�߂ɓ�k�푈��킢�����A�A�����J�j�ő�̂��̓���ɐ����ȈӖ���^�����̂�����B
�@�������{�l�́A�킪���y�э��ێЉ�ɑ傫�ȉe���͂����A�����J�̐��������ɁA��ɐ[���S���Ă����B�A�����J�̐�����^�ɗ������邽�߂ɂ́A�A�����J�����`�Ƃ��̒��ɂ����鐭���Ƃ̂�����𗝉����邱�Ƃ��K�v���B���̓_�ŁA�A�����J�哝�̒��ł��̑�ȑ哝�̂Ɩڂ���Ă��郊���J���̎�����m�邱�Ƃ́A�����ɉ��炩�̎�����^���Ă���邾�낤�B |
|
|
|
| 2013�N1��17���i�j |
| �����`�̐��_ |
�@���N�̂m�g�j��̓h���}�w���d�̍��x�́A�V�����d�̕��ꂾ�B���˂ɃA�����J��k�푈����n�܂�B���{�����E�j�̗���Ƃ͖����ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ����������炵���B��k�푈�Ŏg��ꂽ���킪�A�����̓��{�ɗ��������Ƃ����B
�@��k�푈�̏�ʂł́A�����J���̃Q�e�B�X�o�[�O�����i1863�N11��19���j�́hThe�@government�@of�@the�@people�Cby�@the�@people�Cfor�@the�@people�Cshall�@not�@perish�@from�@the�@earth.�i�l���́A�l���ɂ��A�l���̂��߂̐��������̐�������ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��j�h�Ƃ����A���̗L���ȉ����̈�߂����ꂽ�B���̎��A������v�ҕ�n�ōs��ꂽ�k�R��v�ҒǓ����T�ł̃����J���̉����́A�킸����3���Ԏ�B���܂�ɂ��Z���Ԃ��������߁A�J�����}�����ʐ^���B�낤�Ƃ������A���łɉ����͏I����Ă����B�䂦�ɁA���̗��j�I�������s���Ă��郊���J���̎ʐ^�͑��݂��Ȃ��B
�@�Ƃ���ŁA���̃����J���̉����̈�߂��A�����̌��@�̒��ɁA�p�Y���̂悤�ɖ��ߍ��܂�Ă��邱�Ƃ����������낤���B���{�����@�O���́u�������������́A�����̌��l�ȐM���ɂ����̂ł��āA���̌��Ђ͍����ɗR�����iof�@the�@people�j�A���̌��͍͂����̑�\�҂�������s�g���iby�@the�@people�j�A���̕����͍��������������ifor�@the�@people�j�v������ł���B
�@GHQ�ō��i�ߊ��̃_�O���X�E�}�b�J�[�T�[�̓A�����J�l�B�ނ́A���{�����@���Ă̑O���ɁA�����J�����q�ׂ��A�����J�����`�̐��_��D�荞�̂��B
�@���������A��N���ɖS���Ȃ����x�A�e�E�V���^�E�S�[�h������i1923�`2012�B���{�����@���č쐬�ɂ���������Ō�̐����ؐl�B�l��������S���j���A�Ǔ��j���[�X�̒��Ŏ��̂悤�Ɍ����Ă����̂���ۓI�������B�u���{�����@�́A�A�����J�̌��@�����͂邩�ɑf���炵�����@�ł��v�ƁB
�@�����`�̖{��̌��@�����f���炵���A�ƕ]���������{�����@�B����ȑf���炵�����@���A���ꂩ����������{�l�͎���Ă�����̂��낤���B |
|
|
|
| 2013�N1��16���i���j |
| ���͐�̖� |
�@���̍����́A��̖��O�ɗR������B�����̂قƂ肩��N����������ł���B�����Ɠ����悤�Ȑ삪�V��ɂ������Ă���B�䂦�Ɂu�V���v�Ƃ������B�V�̐�̂��Ƃ��B
�@�����Ԃ��������������߂ē��ꂵ���̂͐`�ł���B�������`���C�i�iChina�j�Ƃ��V�i�i�x�߁j�Ƃ��̂���̂́A�`�iChin�j�ɗR������B�������A�`�Ɗ��̂��āu�`���鍑�i����Ă������j�v�Ƃ������̂́A�`�������ꂵ�Ă������Ԃ͂��܂�ɂ��Z�������B
�@����ɑ��A���͋I���O����͂���ŁA�O��200�N�A�㊿200�N�̍��킹��400�N�ԁA�����ɌN�Ղ��������B���̂��߁A�����l���u�`�����v�Ƃ͂��킸�u�������v�Ƃ������A�����̕������u�`���v�ł͂Ȃ��u�����v�ł���i�����Ƃ��`�̕�����⽏��Ȃ̂ŁA���̗ꏑ�̕������݂̎��̂ɋ߂��j�B�܂���O���A�����ȂǁA�u���v�ꕶ���Ől�i�j�j��\���悤�ɂȂ����B |
|
|
|
| 2013�N1��15���i�j |
| �ǎ��ꑰ |
|
�@���ǕV���N�e�����w�����x���A�q�̔njł������p���������B�����njł̖��Ǐ����������������Ƃ͑O�q�����B
�@�Ǐ��͂܂���������ƂƂ��Ă��m����B�a��̐M�C�āA�c�@�ȉ����������̋���ɂ�����A����Ɓi�����������B���搶�̈Ӂj�ƌĂꂽ�B���͌�����̐��ŁA�v�̑����f(�����������キ)�̑�����A�{�d�������̂ł���B���̒��w���r�i���傩���j�x���т́A�킪���́w����w�x�ɑ�������B
�@�njł̒킪�ǒ��ł���B�ǒ��͐���s��̔C�ɂ���A�����̊Ép�i�����j���`���i���������B���[�}�̂��Ɓj�ɔh���������ƂŁA���Z���E�j�̋��ȏ��ɂ��̖����ڂ��Ă���B�܂��A�u�Ռ��ɓ��炸��ΌՎq���v�̖�����f�����l���Ƃ��Ă��m����B
�@�ǎ��ꑰ�́A�ȏ�̂悤�ɑ��ʂł���B
�y�Q�l�z
�E�K��諑��u�����̔ǒ��v1917�N�i�ɂɂ��j
|
|
|
|
| 2013�N1��14���i���j |
| �w�����x |
|
�@����A�b��ɂ����u���_�V�u�v�́w�����x���o�T���B�w�����x�ƌ����A�u�`�v���o�ꂷ��ŌÂ̎j���Ƃ��ėL�����B�u�v��y�Q�C���ɘ`�l�L��B����ĕS�]���ƂȂ�v�Ƃ������̎j���ł���B
�@�w�����x�͑O���̍��c���M�i��イ�ق��j����V�̉��́i���������j�܂ŁA12��230�N�ԁi�O206�`��23�N�j�܂ŏ��q�������j�����B�鉤�̓`�L�ł���{�I12���A�b����̓`�L�ł����`70���A���x�Ȃǂ̎u10���A����E�����Ȃǂ̈ꗗ�ł���\8���̌v100�����琬��B�̂��A�ו�����120���ɂȂ����B
�@�w�����x�͈�ʓI�ɂ͔njł̕҂Ƃ���Ă���B�������A���ۂɂ͕��q�E�Z���R�l�̎���o�Ċ��������B���ǕV�i�͂�҂傤�j���N�e���A�q�̔njł����̎��Ƃ��p�������B�����A���Ƃ̊����ڑO�ɁA���z�i���傤�ǁj�����s��̍߂ɘA�����č����B���̔Ǐ��i�͂傤�j���Z�njł̈�u���p���A���\����ѓV���u��₢���������̂��w�����x�Ȃ̂ł���B
|
|
|
|
| 2013�N1��13���i���j |
| �u�͉_��荂�� |
|
�@���̊ԁA�e���r�ŃW�u���̃A�j���w�R�N���R�₩��x����������Ă����B������ڂ��茩�Ă�����A���a30�N��Ǝv�������Z�̕������������̓�����ɁA�u�u�͉_��荂���v�Ə�����Ă����B�����炭�̓W�u�����x�������ԏ��X�̎В�������ɊW���錾�t�Ȃ̂��낤�i�������̎���j�~���悤�Ƃ��鍂�Z���ɗ������������������A�A�j���̒��Łu���ۗ������v�Ƃ��Ă���A���ԏ��X�W�҂Ƀ��f�������邱�Ƃ���������F�߂Ă���B���Ȃ݂ɁA������������Ă����Ԃ̃i���o�[���u�P�O�X�O�v�i�g�N�}���j�������j�B
�@���Ƃ��Ƃ��̌��t�́w�����i����j�x�g�Y�`�i�悤�䂤�ł�j�ɂ���u���_�V�u�i��傤����̂����내���j�v�����T���B�����ʂ�A�_���������̂��ł̂ڂ낤�Ƃ��鍂���u�������B�ӋC����ŁA�傢�ɔ�悤�Ƃ���u���������̌��t�́A�������̂悤�Ȏ�҂��W����ɂ����Ăӂ��킵�����t���낤�B
�@�Ƃ���ŁA���������ɍ��ꂽ��������W�Ɂw���_�W�x������B���̏ꍇ�́u���_�V�u�v�́A�]���đ����Ԃz���������Ȏu���Ӗ����Ă���B
|
|
|
|
| 2013�N1��12���i�y�j |
| �Q�T�Ԃ̂��x�݂����Ă��������܂��� |
|
�@������ƖZ�����āA�z�[���y�[�W�̍X�V���肪���B�N���E�N�n�̋x�ݒ��ɁA���̃z�[���y�[�W�����j���[�A�����悤�Ǝv���܂������A�Z�p�����킸�A���ǂ��܂������܂���ł����B���̃y�[�W���\�����d���Ȃ��Ă����̂ŁA�ǂ��ɂ����悤�Ǝv���Ă����̂ł����c�B
�@����͂����ƁA�{���A�����̌��ʂ��͂��܂����B���{�j�P���ɂ͍��i�������̂́A������Ō��̌����������Ă��܂�����A�L�q���ł͗��j�p�ꂪ�܂������v���o���Ȃ�������ŁA���Ȃ��邱�Ƃ�����ł��B
�@���͂�L���͂̐�����������ɂ��Ȃ��悤���r��ς݁A���N��12���ɂ��܂������Ƀ`�������W�������ł��B
|
|
|
|